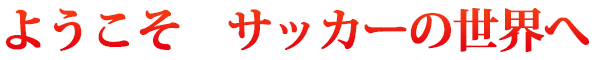現在につながる世界のサッカー、日本のサッカーの伝説の年は、まず1986年、そして1992年、1993年、1994年、1996年、1997年、1998年、1999年、2000年、2002年、2004年、さらに2010年、2011年、2012年、2018年、2022年、
実に多くの伝説に満ちた年があったのです。
それらは「伝説のあの年」として長く長く語り継がれることでしょう。
さぁ、順次、ひもといてみましょう。
伝説のあの年 1997年
1997年は、翌1998年にフランスで開催されるFIFAワールドカップのアジア予選が行なわれる年です。前回1994年アメリカ大会の出場権を、最後の最後に逃してしまった痛恨の経験を持つ日本、そして2002年ワールドカップ日韓大会の一つ前の大会であるフランス大会には何としても参加を果たしておきたい日本が、このアジア予選をどのように戦ったかを中心にこの年をひもといていきます。
天皇杯決勝はヴ川崎が9シーズンぶり、全国高校サッカーは市立船橋が2度目の優勝
元日の第76回天皇杯サッカー決勝、今回の大会は地域代表の出場権をこれまでの全国9代表から各都道府県代表に拡大、ユース世代代表にも出場権を拡大、合計80チームが参加して開催された初めての大会でした。そのため1回戦から決勝まで合計7試合、Jリーグ組はシードされて3回戦からの登場となりましたが、アジアカップサッカーが12月に開催されたため、その間を避けた日程となり、決勝進出チームは10日間で4試合をこなす大会となりました。
元旦の決勝に勝ち進んだのは準決勝で浦和を破ったヴ川崎と、準決勝でG大阪を破った広島でした。試合は前半3分に北澤豪選手のゴールで先制したヴ川崎が終始主導権を握り結局3-0で優勝、前年12月に開催されたポストシーズンの「サントリーカップ・チャンピオン・ファイナル1996」にも出場したヴ川崎でしたが、タイトルを逃してしまい、Jリーグ4年目にして初めて無冠に終わるかという最後の大会で、ようやくタイトルを手中に収めました。
ヴ川崎は、エメルソン・レオン監督が前年シーズン後半戦から指揮をとって、栗原圭介選手や菅原智選手などの若手を起用して、チームの若返りを図りながら天皇杯制覇という結果も出したのですが、クラブが当初から契約更新しない前提だったため既定路線どおりの退任となりました。
ヴ川崎はこれでJリーグ三大タイトル6冠目(リーグ戦2、ナビスコ3、天皇杯1)となり、Jリーグ最強チームの面目を保ったタイトルでした。
一方の広島は、前年に続いて天皇杯決勝に進みましたが、またも涙を飲みました。しかもJリーグがスタートしてから国立競技場での試合に弱い(4連敗)というジンクスもついてしまった試合でした。
第75回全国高校サッカー選手権は「キミ達を、2002年に見たい。」の大会キャッチフレーズのもと、全国4119校、本大会出場48校の頂点を目指して1月8日決勝が行なわれ、千葉・市立船橋と神奈川・桐光学園という首都圏同士の対戦となりました。
市立船橋には1年時に優勝メンバーとなっているFW北嶋秀朗、桐光学園には前年のアジアユース選手権で一躍司令塔として脚光を浴びたMF中村俊輔という超高校級の選手を擁するチーム同士の戦いでしたが、市立船橋が北嶋の今大会6得点目、1年からの通算16得点目となるゴールなど2点をリード、桐光学園の反撃を1点に抑え一昨年以来2度目の全国制覇を果たしました。
北嶋選手の通算16ゴールは、それまでの11ゴールを大幅に更新する大会記録となりました。
一方の中村俊輔選手、この大会では主役の座を北嶋選手に譲りましたが、そのあとのJリーグでの活躍そして海外での活躍により日本サッカー界を代表する選手に成長していきます。
この大会の主な出場選手と進路
FW 北嶋秀朗(市立船橋→柏)、坂本紘司(静岡学園→磐田) MF 佐藤陽彦(市立船橋→京都)、中村俊輔(桐光学園→横浜M)
DF 佐原秀樹(桐光学園→川崎F) GK 南雄太(静岡学園→柏)、都築龍太(国見→G大阪)
2年生以下
小笠原満男(大船渡)、遠藤保仁(鹿児島実)
Jリーグ移籍市場、活発化の兆し、前園選手・横浜F⇒ヴ川崎、城彰二選手・市原⇒横浜M、ビスマルク選手・ヴ川崎⇒鹿島 .etc
この年の特徴としてJリーグ移籍市場、特にこれまでの年と異なり日本人選手の移籍が賑わったことがあげられます。
その筆頭格が前園真聖選手でした。
前園選手は、前年夏、日本五輪代表キャプテンとしての活躍に関心を持った、スベインリーグ・セビリアの関係者が選手視察に訪れてから移籍交渉を横浜Fを介して進めていましたが、最終的には成立しなかったことから、横浜Fへの信頼をなくし、退団ありきで1997年を迎えていました。
ちょうどその頃、新シーズン、ヴ川崎の監督に就任することが決まった加藤久氏がメディアからの取材に対して「前園加入歓迎」の意思を示したことで両クラブ間の交渉がスタート、移籍交渉締切日の1月31日ギリギリに成立した移籍でした。
けれども前園選手自身の心の底には「ホントは海外に行きたかったんだよなぁ」という思いが澱(おり)のように横たわっていて、心底からヴ川崎の一員になりきっていなかったようです。
前期のスタートダッシュに失敗したヴ川崎は加藤監督の解任に踏み切りましたが後任のエスピノーザ監督になっても好転せず、前園選手は監督交替によりスタメンから外れてしまいました。
そこから悪循環に陥り日本代表にも招集されなくなり、次第に負のスパイラルに入っていったようです。日本代表に招集されても、加茂監督から「守備をしないヤツは使わん」とばかりに外されてしまいます。前園選手に代わって招集されたのが、前園選手を兄貴分と慕う中田英寿選手だったのですから、世の中つくづく皮肉なものです。
フランスワールドカップ出場に向けて自分を奮い立たせるという目標があるはずなのに、力が入らないというジレンマ。サッカー選手にとって「あの時チャンスだったのになぁ」という大きなものを失うと、なかなか気持ちを立て直せない、立て直すのは至難の技だということを前園選手の1997年が示しているようです。
同じく海外移籍の可能性を探りながらも果たせず、一度所属クラブから離れた気持ちをなかなか元にもどすことができず、環境を変えなければと移籍を選んだのが市原の城彰二選手でした。
城選手は、市原に入団した1994年のJリーグでいきなり開幕から4試合連続ゴールという衝撃的なデビューを飾っています。ですから当然5試合連続ゴールというルーキーにして前代未聞の記録に期待がかかったのですが、ちょうど正月の全国高校サッカー選手権の優秀選手で編成された「日本高校選抜欧州遠征」のスケジュールと重なり5試合目から3試合欠場して渡欧したのでした。
その「欧州遠征」であるベリンツォーナ国際ユースサッカー大会で、城彰二選手は日本高校選抜があげた3得点のうち2点をあげ、大会を見にきた欧州各クラブの関係者の目にとまっています。
その中の、イタリア・セリエAのユベントスとASローマの関係者からは、その後も連絡が続き、1996年のアトランタ五輪の際には「もしアトランタ五輪サッカーで日本代表が決勝トーナメントに進出したら、キミの獲得を本格的に考えましょう」ということになっていたそうです。
しかし結果はグループリーグ敗退に終り城選手の海外挑戦の夢は一旦ご破算になってしまったのです。
そのため、アトランタ五輪後、市原に戻った城選手ですが、自身の著書「エースのJo 城彰二」(リヨン社1998年2月刊)によると「俺の心の中は隙間風ばっかり吹いていた」そうです。
そこから城選手は考えます。自身の著書にはこう綴られています。「このままずっとジェフにいて、21歳という若さでチームの顔にもなり、居心地はいい。でも、そこに胡坐をかいて黙っていてもいいものか」
「五輪に出て、世界に触れたこともあり、俺はもっとうまくなりたい。そのためには、うまい奴の中で揉まれて、もっと競争の激しいチームでプレーしていかないといけない。五輪で結果を出せなかったのは、そういう環境に慣れてしまって、ガムシャラさに欠けたせいかもしれない。」
そこで12月に入ると、チームに退団の意思を伝えクラブと話し合いを重ね始めたのです。
そんな時、横浜Mが日本人FWを探しているという情報を耳にした城選手は日本代表で一緒になった井原正巳選手と連絡をとり、自分の意思を伝えました。
そこから市原と横浜Mの交渉が始まり1月末、横浜Mへの移籍が決まりました。城選手も前園選手同様、日本代表にも召集され始め、心機一転の気持ちから「もっとうまくなりたい」気持ちを前面に出してプレー、W杯アジア最終予選にも召集されて成長していきます。
一方、ヴ川崎・ビスマルクの鹿島移籍は、リーグの盟主を争っているヴ川崎から鹿島への移籍でしたので、これも大きな話題となりました。鹿島は、平塚から名良橋選手を補強したことと合わせて「欲しい選手であればライバルチームであっても獲りにいく」という戦略的補強が注目を浴びたのです。特にビスマルク選手の獲得は、抜けたヴ川崎にとっても痛手ですからライバルを蹴落とす効果もありました。
そのほかG大阪の10番・磯貝洋光選手が浦和に、JFL本田技研からロペス選手が平塚に加入しました。
ロペス選手はこの時28歳、20歳でブラジルから日産自動車に加入して以来8年目にしてJリーガーの仲間入りを果たしました。ロペス選手は、かねてから日本への帰化を考えていて、平塚での活躍とともに帰化申請が認められれば、日本人選手として代表への道が開けることになり、本人にとっても日産時代の恩師でもある日本代表・加茂監督にとっても期待の高まる移籍となりました。
外国人選手の加入で話題となったのは、G大阪にエムボマ選手(パリSG)、横浜Mにフリオ・サリナス選手(スペイン・ヒホン)、C大阪に高正云選手(韓国・一和天安)などです。
高校の新加入選手では、お正月の全国高校サッカー選手権の項目でもご紹介しましたが、優勝した市立船橋のエース、北嶋秀朗選手が柏、決勝を争った桐光学園の中村俊輔選手が横浜Mに加入、そのほか磐田には静岡学園から坂本紘司選手、倉貫一毅選手、名古屋に東福岡から古賀正紘選手、奈良育英から中谷勇介選手、G大阪に国見高から都築龍太選手、が加入したほか、変わり種としてはブラジルから高知・明徳義塾にサッカー留学の形で来日していたアレックス選手(のちに帰化して日本名・三都主アレサンドロに)が清水に入団しています。
また、G大阪ユースに所属する高校2年の稲本潤一選手が、年明けからトップチームに合流しています。前年のU-17世界選手権出場メンバーではクラブチーム所属のメリットでJリーグトップチーム所属の一番乗りになりますが、公式戦への出場がいつになるかも楽しみです。
大学卒業組では、柏に早稲田から渡辺光輝選手、筑波大から萩村滋則選手、ヴ川崎に駒沢大から山田卓選手、横浜Mに早稲田から丸山良明選手、横浜Fに国士館から佐藤尽選手、筑波大から佐藤一樹選手、平塚に早稲田から外池大亮選手、清水に筑波大から興津大三選手ら多彩な顔ぶれが加入しています。
フランスW杯アジア予選、アジア3.5枠をめざしていよいよスタート、まずは一次予選をオマーンラウンド、日本ラウンドを無敗で通過も課題を残す
この年の日本代表の挑戦が、まず2月のタイ・キングスカップから始まりました。すべてはフランスW杯アジア予選に向けての調整の位置づけとなりました。
キングスカップでは、初戦のタイ戦、城彰二の代表初ゴールで先制しましたが追いつかれてドロー、次のルーマニア選抜は若手中心のチームということで、日本もタイ戦からメンバー8人を入れ替えて戦い先制されたものの、残り9分で追いつき、またもドロー、最終戦のスウェーデン戦は0-1で敗れ3位決定戦に回ることとなりました。
3位決定戦の相手は一度引き分けたルーマニア選抜、今度は2-0で制し3位で大会を終えました。
98フランスW杯は、前回94年アメリカW杯の出場国24から8枠増えて32ケ国が出場できます。
その理由は、当時のFIFA・ジョアン・アベランジェ会長がアジア諸国とアフリカ諸国からの支持を取り付けるため、1982年大会から出場国を従来の16から24へ、1998年に24から32へ増やしたことによります。
これによりアジアには3.5枠与えられ、「ドーハの悲劇」で涙を飲んだ94年アメリカW杯アジア予選の2枠から条件が大幅に緩和されたことになります。
この理由として、サッカー後進地域のアジア・アフリカ諸国でのサッカー振興という大義名分もありましたが、アジア、特に日本が経済大国としての地位を築きつつありFIFAのスポンサーとしての期待を持っていたためという打算的な指摘もありました。
この3.5枠という与えられ方が果たして適正な枠なのかどうかについては後世の検証を待たなければなりませんが、日本代表は、2002年日韓共催W杯が初めての出場という恥ずかしい状況にならないためには、何としても98フランスW杯に出場を果たしておきたい、そういう意味では大変なアドバンテージをもらってアジア予選に臨むことになりました。
フランスW杯アジア一次予選は、オマーン、マカオ、ネパールと4ケ国で1位を争う戦い、まず3月のオマーンラウンドでは初戦のオマーン、この組は事実上、日本とオマーンの一騎打ちと見られていることから、決して侮れない試合、引き分け以下ではあとの戦いが苦しくなるため、何としても勝利が欲しい戦いでした。
そのことが日本代表をかなりの緊張に追い込み、開始10分にDF小村徳男選手のゴールで先制したものの、なかなか追加点が奪えず、逆に終盤にはあわや同点というピンチを招くシーンもありました。最後は薄氷を踏む思いで1-0の勝利、安堵のスタートを切った形となりました。その後2試合は順当勝ちで3連勝でオマーンラウンドを終えました。
その後、日本代表は5月に日韓W杯記念の韓国戦を行ない、前年アトランタ五輪で活躍した中田英寿選手を初招集してスタメンに起用しました。中田選手は期待に応えて好プレーを披露、ゲームは引き分けに終わりましたが、鮮烈なデビューを果たしました。
中田選手は続く6月のキリンカップにも出場、クロアチア戦、トルコ戦の連勝に貢献しました。
6月後半には、アジア一次予選の日本ラウンドが行なわれました。初戦マカオを、2戦目ネパールを下し、最終戦のオマーンは得失点差の関係で、10点差以上で敗れなければ1位確保できる状態でしたがホームということで確実に勝利したい試合でした。開始4分、すっかりレギュラーに定着した中田英寿選手のゴールで先制しました。
ここで加茂監督は、最終予選で守備の要の井原正巳を欠いた時を想定して、後半、井原選手を下げると、守りのリズムが狂い、63分に同点に追いつかれ引き分けて試合を終えました。無敗で一次予選を突破したとはいえ、いろいろな課題を抱えたまま9月からのアジア最終予選に臨むことになりました。
Jリーグは17チームによる前期、後期1回戦総当たりの変則方式で実施、日程もW杯アジア最終予選日程の変更に翻弄されるシーズンに
この年のJリーグは前年の16チームから昇格が神戸1チームだけということで、17チームという奇数になり、1シーズン制をやめ2ステージ制、前後期とも1回戦総当たり方式にしました。
そのため一例として、前期、あるチームは鹿島とホームで対戦するが、あるチームは鹿島とアウェーで対戦するという不公平が生じるやり方で、前期あるいは後期それぞれのステージできちんとホーム&アウェーの試合にはならなくなるという苦肉の策でした。
17チームという奇数でありながら2ステージ制にするのは、2つステージで、終盤の優勝争いで観客増が見込めること、そしてチャンピオンシップという頂上決戦で満員の集客が見込めるためですが、かと言って前期、後期それぞれをホーム&アウェーの2回戦総当たりにしてしまうと試合数が多すぎて不可能という理由から1回戦総当たり方式にしたものです。
各クラブの収入増を図りたいという希望と、試合数をあまり多くして負担になってはいけないという制約を、リーグ戦、カップ戦の試合方式や、日本代表の試合期間などを避けたスケジュール調整など連立方程式を解くような作業の結果として生み出されてきた試合方式でした。
その結果、この年のリーグ戦は、前期が4月12日開幕・7月12日閉幕、後期が7月30日開幕・10月4日閉幕という日程となり、この後期最終節が10月4日というのは、レギュラーシーズンの日程において最も早い最終節として記録的な日程となりました。
これは、ご存じのように、フランスW杯アジア最終予選の日程が、当初11月の中立地における集中開催と予定されていたためのものですが、のちにW杯アジア最終予選の日程が、ホーム&アウェー方式に変更されたため、そのスタートが9月上旬に前倒しとなり、Jリーグは9月上旬から10月4日の最終節まで、日本代表に選手をとられているチームが主力選手抜きで戦わなければならないという不公平な状況を生んでしまいました。アジアサッカー連盟(AFC)の気まぐれのような日程変更に翻弄されてしまったシーズンとなりました。
ちなみに、J1リーグ、すなわちトップリーグでの、奇数クラブ数による2シーズン制は、この年が最初にして最後の試みでした。
リーグ戦の試合方式は従来どおり、完全決着方式(前後半90分で決着が付かない場合、前後半15分ずつのVゴール方式による延長戦を行い、それでも決着が付かない場合はPK戦)を採用しましたが、前年の鹿島が「PK戦負け」の数の差で優勝したこともあり、勝ち点配分の見直しが行われました。見直しにより、90分勝ちが3、Vゴール勝ち2、PK勝ち1に改められ、負けはいずれの場合も勝ち点0になりました。
また、このシーズンから各選手が付ける背番号が固定制となったのも意外ですが、前年までの4シーズンはスタメン選手が1~11までを、サブの選手が12以降の番号にしていたものを固定制にしたのです。
Jリーグチームの中で、新監督は、浦和・ケッペル監督、ヴ川崎・加藤久監督、横浜M・アスカルゴルタ監督、磐田がルイス・フェリペ・スコラーリ監督、C大阪がレヴィー・クルピ監督、福岡がカルロス・パチャメ監督、17チーム中6チームが新監督に変わりました。ちなみに日本人監督は、ヴ川崎・加藤久監督と平塚・植木繁晴監督の2人だけ、Jリーグ5年の中でもっとも少ない状況でのスタートとなりました。
ところで、この年のJリーグ放送は、CS放送でのテレビ中継放映権をジュピタープログラミング(現・ジュピターテレコム)が取得しましたが、当時ジュピターにはスポーツ専門放送が無かったため、代替処置として生中継はCSN1ムービーチャンネルの枠内番組「CSN1 J SPORTS」として毎節1試合のみ放送、残りの試合はGAORA、スカイ・Aにサブライセンスする形での録画放送となりました。
一方、NHK-BSでは午後2時キックオフの試合、午後7時キックオフの試合をなるべく複数放送したり、場合によっては深夜枠で録画放送するなどの形で放送、そのほか首都圏UHF局(チバTV、埼玉TV、神奈川TV)も積極的に地元チームのカードを放送するなどの対応も見られました。
Jリーグ開幕に先だって4月5日行なわれた恒例のゼロックススーパーカップ’97は、前年のリーグ覇者鹿島と今年元旦の天皇杯決勝覇者ヴ川崎、奇しくもJリーグ元年のチャンピオンシップを争ったチームの戦いとなりました。
試合は、あいにくの雨にもかかわらず、一歩も譲らぬ攻防となりました。ヴ川崎が先手を取りましたが、鹿島は、2年目のシーズンを迎える柳沢敦選手が72分にはヘディング、79分にはこぼれ球を確実に決め、チームを2-1の逆転勝利に導びく活躍、初タイトルで開幕に弾みをつけました。
前期は鹿島制覇、前年年間王者に続き黄金時代到来かと思わせる強さ、横浜F健闘空しくまたも優勝逃す
4月12日に開幕した前期の戦い、序盤の話題をさらったのはG大阪にフランスリーグ・パリサンジェルマンから加入したカメルーン代表のエムボマ選手でした。
浪速の黒豹・エムボマ選手、開幕戦でスーパーゴール、日本のファンに鮮烈なあいさつ、3節には稲本潤一選手が史上最年少ゴールを記録、G大阪が序盤の話題をさらう
エムボマ選手は平塚との開幕戦、3-0でリードした後半27分、スーパーゴールを決めてみせます。ペナルティエリアの左角付近で、ゴール正面付近からのミドルパスを受けたエムボマ選手は相手DF2人のマークをかわすため一旦下がると見せかけてから、2人の間をすり抜けにかかりました。
その時、ボールが相手DFに当たり浮いてしまったのですが、自分の長い足で1度リフティング、そして2度目のリフティングは意図的だったのかコントロールをミスしたためか、自分の頭を大きく越えてペナルティエリア内にフワリと上がりました。エムボマ選手は素早く身体の向きをかえてボールを見上げながら追いつくと、タイミングを計るようにして左足を思い切り振り抜きました。
ただでさえ日本人選手より頭一つ背の高いエムボマ選手が、その長い手足を活かしてバランスを取りながら思い切りシュートを打ちましたから、平塚DFも身体を寄せるなどという守備ができず、味方選手もサポートに動くなどという気の利いたことができず、エムボマ選手の後ろから、唖然とボールの行方を見送るだけでした。
するとドンピシャのボレーがGKの頭上を越えてゴール右サイドネットに突き刺さったのです。さっそく付けられた「浪速の黒豹」のニックネームにふさわしい衝撃のゴールで日本のサッカーファンにあいさつしました。
G大阪は、3節に高校生のままトップチームでプレーしている稲本潤一選手が初ゴールを記録、これはJリーグ最年少ゴール記録(17歳7ケ月)となる快挙でした。G大阪は開幕3連勝でダッシュ、序盤の話題をさらいました。
稲本選手は3月8日にスタートしたナビスコカップグループリーグ開幕戦にスタメン出場を果たしており、これはJリーグ公式戦最年少記録となる17歳6ケ月(3月時点では、まだ高校2年)での出場となりました。ちなみに、その前までは96年シーズン2節(3月)に市原の山口智選手が記録した17歳11ケ月での出場でした。
このほか開幕戦は昇格した神戸が前年王者の鹿島と対戦、神戸の大物外国人選手、ミカエル・ラウドルップ選手がJリーグに初お目見えで奮闘しましたが、王者鹿島の前に2-5で屈しました。神戸は2節に名古屋を永島昭浩選手のVゴールで破りJリーグ初勝利をあげました。
4月19日の3節、磐田・スキラッチ選手今季初ゴールも、腰痛が悪化、以後欠場、そのまま引退、日本での3シーズンのキャリアを終えました。
4月23日の4節、横浜M・中村俊輔選手が京都戦で横浜Mの全ゴールに絡む3アシスト、すっかり司令塔の風格を漂わせる活躍でした。
5月3日の6節、横浜Mvs平塚戦、この試合ではまださほど注目を浴びませんでしたが、後々、日本サッカーを代表する2人となる中田英寿選手と中村俊輔選手の初対戦となった試合という意味でメモリアルゲームでした。試合は平塚のロペス選手、中田選手の活躍で平塚が大量リードしましたが、中村俊輔選手が後半、得意のFKで待望のJリーグ初ゴール、中村俊輔選手にとっても、まさにメモリアルゲームとなりました。
5月7日の7節、序盤ダッシュしたG大阪に代わりエジウソン選手の活躍で柏が名古屋を下し首位に。名古屋はこれで開幕7連敗、名古屋の初勝利は8節。
5月17日の9節、浦和vs横浜F戦、雷雨のため史上初の延期(7/2)に
5月31日の12節、鹿島が平塚を破り首位浮上、このあと日本代表戦(アジア一次予選日本ラウンドのため7/2まで中断)
6月4日磐田フェリペ監督突然の辞任、ブラジル・パルメイラス監督就任のため帰国、磐田は桑原隆氏が監督代行として指揮をとることに。
6月25日ヴ川崎加藤久監督辞任、エスピノーザ監督就任を発表
ヴ川崎は加藤久監督を迎えて期待されましたが、好守が噛み合わず低調に推移、たまらずクラブはブラジルから当時50歳のエスピノーザ氏を招聘、再建を託しました。
7月2日の13節、平塚に新加入の洪明甫選手、名古屋戦からスタメン出場
7月9日の14節、横浜Fが平塚を破り首位に浮上、平塚・洪明甫選手は2試合目にして退場処分
7月12日の15節、鹿島が敵地広島で勝利、首位奪回
7月19日前期最終17節 鹿島、敵地でC大阪を0-1で前期優勝決定
鹿島はヴ川崎から加入したビスマルクとジョルジーニョ選手が試合の主導権を握る活躍で、秋田豊選手、相馬直樹選手、本田泰人選手の日本代表選手を中心としたMF・DF陣と、柳沢敦選手、マジーニョ選手のFW陣がしっかりと結果を出し、最終節ではあったものの前期を制覇、黄金時代到来かと思わせる強さを見せました。
この前期も終始優勝争いに加わった横浜F、最終節に勝ち、鹿島の結果如何では逆転優勝の可能性があったことから、スタジアムに残り結果を待ちましたが、またも惜しくも2位に終わりました。前期終了後、チームの顔だったブラジル代表・ジーニョ選手が惜しまれながら2年半にわたって在籍した横浜Fを退団しました。
オールスターゲームも主役はG大阪・エムボマ選手
7月27日 神戸ユニバー記念競技場で、第5回目となるコダックオールスターサッカー97が行われました。
過去2年採用された前年度の総合順位が奇数順位「Jヴェガ(織女星)」、偶数順位「Jアルタイル(牽牛星)」に分ける方式を取りやめ、東西に分ける方式に戻されて、ファン投票結果をベースに、他の大会参加のためや、ケガによる欠場などを理由に監督推薦により選手入れ替えで選ばれた合わせて30人の選手が選ばれました。
J-EASTの井原正巳選手と、J-WEATの沢登正朗選手が最多の5連続選出、J-EASTの中田英寿選手、中村俊輔選手、J-WEATの宮本恒靖選手ら15人が初選出というメンバーとなりました。
ちなみに、この年はチーム数が17と奇数だったため、以下の9チームと8チーム分けになりました。主な選手とともに紹介しておきます。
J-EAST 鹿島、柏、浦和、市原、ヴ川崎、横浜M、横浜F、平塚
エジウソン選手、カズ・三浦知良選手、中田英寿選手、ジョルジーニョ選手、井原正巳選手、ブッフバルト選手、川口能活選手、(交代出場)ビスマルク選手、中村俊輔選手
J-WEST 清水、磐田、名古屋、京都、G大阪、C大阪、神戸、広島、福岡
エムボマ選手、ストイコビッチ選手、ドゥンガ選手、ラモス瑠偉選手、名波浩選手、宮本恒靖選手、(交代出場)永島昭浩選手、沢登正朗選手
試合は開始直後、1分もたたないうちに動きました。J-EASTブッフバルト選手が、ファーストタッチのために井原正巳選手に出したバックパスが少し優しすぎたため、いきなりJ-WEST・エムボマ選手にカットされました。エムボマ選手は、そのまま川口能活選手と1対1になりゴールをあげると、その後も前半38分、後半5分にもゴールをあげてハットトリック達成、森島寛晃選手のゴールと合わせて4得点、神戸ユニバー競技場に詰めかけた関西ファンを大喜びさせる勝利でした。
J-WESTはストイコビッチ選手がチャンスメイクに徹し、ドゥンガ選手と京都・ラモス瑠偉選手がボランチを組み、J-EASTのエジウソン選手の突破を阻むという役割がうまく機能しました。
J-EASTは後半からビスマルク選手、中村俊輔選手を投入して挽回を図りますが前半にあげたジョルジーニョ選手の1点にとどまりました。MVPは文句なしにエムボマ選手が選ばれました。
ワールドユース日本代表、惜しくもガーナに敗れるも2大会連続のベスト8進出達成
6月19日からマレーシアで開催された第11回FIFAワールドユース選手権に、日本ユース代表(山本昌邦監督)が2大会連続の出場を果たし、2大会連続のベスト8進出を達成しました。
この大会、前年のアジアユース選手権で彗星の如く現れ活躍したMF中村俊輔選手が、横浜Mでも活躍を始めたことから自信をつけ、すっかり司令塔に成長したのをはじめ、FW柳沢敦選手、FW永井雄一郎選手、MF大野敏隆選手、DF宮本恒靖、GK南雄太の各選手らの活躍で、スペイン、コスタリカ、パラグアイと同組のグループリーグを2位で通過、決勝T1回戦の豪州戦も主導権を握られながらも柳沢選手のゴールによる1点を守り切ってベスト8に進出しました。
準々決勝ガーナ戦も優勝候補ガーナと互角の戦いを演じましたが、惜しくも1-2延長Vゴール負けを喫して大会を終えました。。
それでも、のちに95年大会組の中田英寿選手、松田直樹選手らを加えて2000年シドニー五輪組の中核となる世代の躍動が始まった大会でした。
この大会、決勝はアルゼンチンvsウルグアイという南米勢のカードとなり、アルゼンチンが2大会連続3度目の優勝を果たしました。主な選手としてはアルゼンチンのリケルメ、アイマール、フランスのアンリなどが出場しています。
6月 Jリーグ特別指定選手制度(現JFA・Jリーグ特別指定選手制度)がスタート。第1回指定選手に・・・。
日本初のナショナルトレーニングセンター「Jヴィレッジ」が福島県にオープン
7月20日、福島県沿岸の楢葉町と広野町にまたがる総面積49haに及ぶ広大な敷地を持つ、日本初のナショナルトレーニングセンター「Jヴィレッジ」がオープンしました。
「Jヴィレッジ」は、福島県沿岸地域に原子力発電施設を立地している東京電力㈱が、地域振興事業の一つとして総工費130億円を投じて建設し福島県に寄付した施設です。
それを、日本サッカー協会 (JFA) 、日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)、福島県、東京電力などの出資で設立された株式会社Jヴィレッジ(旧社名・株式会社日本フットボールヴィレッジ)が運営管理する施設としてオープンしたものです。
東京電力㈱は、福島県内に原子力発電所を含む多くの施設を所有していたことから、1994年 (平成6年)に地元への貢献として地域振興施設の造営・寄贈を行うという提案を行ったことから動き出したプロジェクトでした。
この時、ちょうど地域密着を掲げて人気を博していた「サッカー」と結びつけた整備が適当と判断され、日本サッカー協会が協力する形でナショナルトレーニングセンターを設立する合意がなされたのです。
その後、東京電力㈱は1995年(平成7年)から、楢葉町と広野町町有地に建設を決定して整備を進めていたものでした。
「Jヴィレッジ」という名称は元イングランド代表のボビー・チャールトンによって命名されたといいます。
敷地には、全部で8面もの天然芝サッカーコート(観客席付きのJヴィレッジスタジアム含む)をはじめ、人工芝を加えると11面となる施設を備え、サッカー日本代表の合宿はもとより、各カテゴリーのチームのトレーニングなどに利用できる夢のようなトレーニングセンターが出現しました。
日本サッカー協会・長沼会長は、かねてから自らの4つの夢をあげていて、これで「プロリーグ創設」「W杯招致」「ナショナルトレーニングセンターの建設」の3つが実現したと述べました。残る一つは「W杯アジア予選突破⇒本大会出場」ということで、この年秋が深まる頃にその答えが出ることになります。
この施設は、2002年W杯共催を決めた日本にとって、代表強化の拠点となる心強い施設というだけでなく、他のさまざまなスポーツのトレーニング拠点としても活用が期待される、まさに日本のスポーツ振興の一大拠点が誕生したのでした。
これまで日本サッカー協会は、各カテゴリーの選手育成事業や指導者育成事業を、千葉県幕張近くにある東京大学検見川総合運動場や、静岡県掛川市の「ヤマハリゾートつま恋」などを確保しながら行ってきましたが、さっそく8月、W杯アジア最終予選を控えた日本代表の合宿から使用が始まったのを皮切りに、ユース代表候補の選抜研修会や、全日本選抜中学生大会なども、ナショナルトレセンU-17、ナショナルトレセンU-14という形で、トレーニングと研修に重点をおいた腰を据えた育成事業が始まりました。
しかし、後年「東日本大震災」という未曽有の大災害により原子力発電所の事故が発生したため、この「Jヴィレッジ」もスポーツ施設としては全面閉鎖し、長らく国が管理する原発事故の対応拠点となりました。その経緯については別の機会にご紹介したいと思います。
日本サッカー協会「将来構想プロジェクト」による「JFA行動宣言」と「アクションプラン」を発表
9月10日、日本サッカー協会は、JFA100周年(2021年)を見据えた「将来構想プロジェクトチーム」がまとめた「JFA行動宣言」と「アクションプラン」を理事会で承認、発表しました。
これは、前年、日本サッカー協会が創立75周年を迎えたことを記念して行われた記念事業の一つで、浅見俊雄日本サッカー協会理事を座長に設置された「将来構想プロジェクトチーム」において、前年11月から議論と検討が続けられていたものです。
「JFA行動宣言」は日本サッカー協会が創立100周年を迎える2021年に向けた行動指針です。
ここで全文を紹介、記録して長く記憶に留めたいと思います。
JFA行動宣言(1997年9月10日)
①フェアプレーこそ、人とひとをつなぐ、最も大切なもの。試合や練習やスタンドだけでなく、世のなか全体に広げていくように活動します。
②性別や、年齢や、障害のあるなしに関係なく、サッカーをはじめ、からだを動かす楽しみを味わえる環境を提供するよう、努めます。
③サッカーを楽しく観戦できるスタジアムが、全国各地にさらに増えるように働きかけて、素晴らしい国内・国際試合を開催していきます。
④各年代の日本代表が、つねにアジアの代表になって、世界のトップと競い合えるよう、力を高めます。
⑤日本のサッカー界がたくわえた、人的・知的・物的なもののすべてを活用して、アジアと世界のサッカーに貢献します。
以上の行動宣言を具体化するための「アクションプラン」には、
・フェアプレーを順守すること
・2002年ワールドカップを成功させること
・ワールドカップ開催で得られる人的・知的・物的財産を日本スポーツの発展に活用すること
などを掲げました。
その上で、10月には「アクションプラン」の具体策を検討するプロジェクトチームが、浅見俊雄氏を座長として設置され、議論と検討が続けられ、翌年「JFAサッカー行動規範」という形でまとめられ発表されることになっています。
W杯アジア最終予選の試合方式が変更になり、日本にも有形無形の影響が
フランスW杯アジア最終予選を翌月に控えて日本代表は、8月から最終予選直前まで、3つのテストマッチに臨みました。これは、7月22日に行なわれた最終予選組み合わせ抽選会の際、FIFAが最終予選の試合方式をセントラル方式からホーム&アウェー方式に切り替えたため日程が大幅に前倒しになり、テストマッチがその3つで終わりになってしまったのでした。
最初の試合は8月13日、大阪・長居スタジアムでブラジルとの親善試合でした。日本は世界王者相手ということで、前半守りを固める戦術でスタートしたものの1失点で折り返し、後半は攻勢に出たものの逆襲を浴びて、さらに2失点、結局3-0で敗れました。対戦相手のブラジルからは「先に対戦した韓国のほうがズル賢く激しかった。日本はそういった点が足りなかったと思う」と指摘を受けました。
次に8月27日、浦和・駒場スタジアムでJOMO CUP’97 、Jリーグ外国人選抜チームとの試合でした。結果は0-0 。対戦相手のJリーグ外国人選抜の選手たちからは「ボールを持ったら、もっと前を向いて仕掛ける気持ちが必要」「ミスを恐れずチャレンジしなければ・・・」「シュートかが打てそうなのに他の選手に回そうとしている」「GKにとって一番いやなのはペナルティエリアの中でプレーされることだけど、日本代表は・・・・」と、盛んに「W杯アジア最終予選」が間近に迫ってきた日本代表の攻撃に関する指摘が相次ぎました。
最後の試合が、9月2日、磐田スタジアムでのジュビロ磐田との35分ハーフマッチでした。結果は0-1で敗戦、ドゥンガと名波選手が不在、藤田俊哉選手も前半だけで退き、若手中心の磐田相手に無得点だったのです。
これには取材陣も呆れた様子で「このままでは最終予選、かなり危うし、今からでも遅くない、監督を代えるべし」と毒づく人もいたほどの出来の悪さのまま、最終予選に突入することになりました。
いよいよアジア最終予選がスタート、73日間の長い波瀾万丈の過酷な戦いに
9月、いよいよフランスW杯アジア最終予選スタートです。2組に分かれてのホーム&アウェー方式、各組首位は出場権獲得、各組2位同士で第3代表決定戦、その試合に敗れたチームがオセアニア代表との大陸間決定戦に臨んで最後の枠を争う方式です。
実は、当初は中立国でのセントラル方式で行なうことになっていた最終予選ですが、7月22日に行なわれたFIFAの組み合わせ抽選会に先立ち、ホーム&アウェー方式で約2ケ月半にわたる日程設定に覆されたのでした。
これはセントラル方式で行なう場合の開催地が、シンガポール&マレーシア案とバーレーン案で折り合いが付かなかったための変更という説明でした。
この時、アジアサッカー連盟(AFC)理事として開催地決定の交渉に参加していた日本サッカー協会の小倉純二専務理事は変更の経緯を次のように語っています。
「最終決定はFIFA(国際サッカー連盟)が行なうが、その会議の直前に中東選出のFIFA理事がバーレーン開催を画策してFIFAに対してロビー活動をしているという情報が入り、急遽、アジア最終予選進出の韓国、中国さらには中央アジアのウズベキスタン、カザフスタンにも「バーレーンのような、あんな暑い国で試合をさせられたら、おたくらの選手も死んでしまうぞ」と呼びかけ『開催地はAFC本部があるマレーシアで』という案をまとめ、FIFAでの開催地決定の会議に臨んだ。議長だったレナード・ヨハンソン副会長が会議の冒頭に「日本のオグラからマレーシア開催の提案をもらっている。異議はありますか?」と呼びかけると、即座に中東勢が猛反発、会議は紛糾して、中東勢も我々も一歩も引かず平行線のままだった。するとヨハンソン副会長が頭にきたとばかりに、『君らアジアは他の連盟と違い仲がいいといつも言ってるけれど、違うじゃないか、もうこの議論は終わり。FIFAのルール通りホーム&アウェー方式でやってもらう』と発言、そのまま最終決定となった。ある意味、瓢箪から駒のように実現したホーム&アウェー方式だったが・・・。」(小倉純二著「平成日本サッカー秘史」2019年4月講談社刊)
この変更が日本にとって吉となるか凶となるかは、まさに日本の戦い方次第ということになりました。
日本の入った組は、第1戦は9/7ホームでウズベキスタン戦、第2戦は9/19アウェーでUAE戦、第3戦が9/28ホームで韓国戦、第4戦が10/4アウェーでカザフスタン戦、第5戦は10/11アウェーでウズベキスタン戦、第6戦は10/26ホームでUAE戦、第7戦は11/1アウェーで韓国戦、最終第8戦が11/8ホームでカザフスタン戦という日程となりました。
各組とも1位の国は文句なしに出場権獲得です。各組2位になったチームは第3代表決定戦に臨むことになりますが、この段階では、第3代表決定戦の場所も日程も未定です。2位の国が東アジアなのか中東なのかによって、場所の設定も変わるためでした。
9月7日、初戦ホームのウズベキスタン戦、日本代表の初陣を国立競技場の54,328人の大観衆が青いビニル袋をふくらませた風船と日の丸の小旗を持ち寄り、スタジアムを青と日の丸に染めて後押ししました。
選手が入場して整列すると、この日を待ち焦がれていたサポーターたちが用意した膨大な量の紙吹雪が舞い、スタジアムがまるで夢の空間になったような光景を描き出しました。ところが紙吹雪は風に流されてスタジアムの外に大量に飛散してしまったため、これが最初で最後の紙吹雪となってしまいました。スタジアムを一瞬だけ夢空間にしてくれた紙吹雪、しかし、そのあと風の中、漂流し始めた紙吹雪の姿は、まるで、その後の日本代表が味わう壮大なドラマの行く末を暗示するかのようでした。
試合は、カズ・三浦知良選手の4ゴールなど6-3で圧勝、まさにお祭りムードの船出となりましたが、専門家からは3失点を食らった日本の守りに対する不安が実は指摘されていましたし、加茂監督も「この状況も一回負けたら、ひっくり返るんや」と浮かれることはありませんでした。
続く第2戦は灼熱のUAEでのフウェー戦、日本代表は直前に実施した気候順化の対策も役に立たないほどの猛烈な暑さに苦しみ、攻撃陣はウズベキスタン戦での爆発が噓のように鳴りを潜めてしまいましたが、GK川口能活選手の活躍もありスコアレスドロー。翌日の新聞各紙は「ガッチリ勝ち点1」などと好意的に報じましたが、選手の中には「勝てる試合を勝ちにいかなかった結果」と感じていた選手も多く、少しチーム内がギクシャクし始めていました。
最終予選、前半のヤマ場、ホーム韓国戦で痛恨の敗戦
第3戦は9月28日、この組最大のライバル・韓国をホームに迎えました。
日本は、新兵器・呂比須ワグナー選手の帰化申請が認められたことから、さっそく韓国戦メンバー入り、スタメン出場しました。
国立競技場には日本の勝利を信じて56,704人のサポーターが集結、宿命の日韓戦を見守りました。
日本は後半22分、山口素弘選手がゴール正面15mのところから絶妙のループシュートを放つと相手GKの頭上を超えてゴール、待望の先制点をあげました。
そこから6分後、加茂監督は呂比須ワグナー選手をさげてDF秋田豊選手を投入、DF陣が5枚となり、逆にマークが曖昧になるという混乱を招いてしまいました。日本はずるずると自陣に張り付くようになったため、韓国に押し込むスペースを与えてしまい、後半39分、後半42分と立て続けに2失点、痛恨の逆転負けを喫してしまいました。
この戦い方について、のちにサッカーダイジェスト誌98.1.7/14合併号は「あくまで推測だが、過去の『歴史』が多分に影響のではないだろうか」と振り返っていました。つまり、加茂監督が、嵩にかかって攻勢に転じる采配ではなく、とにかく逃げ切る策を選択したのは、過去、韓国戦は敗北だらけの歴史であるということが、脳裏から離れなかったためではないだろうか、というのです。
この結果を受けて、日本サッカー協会強化委員会は大仁委員長が委員を招集して「このままではまずい」という話し合いをしています。そして強化委員会の総意として川淵副会長のもとを訪れ「加茂監督は代えるべきです」と直談判を行ないました。しかし川淵副会長は「いま、そんな話は聞きたくない」と拒否します。川淵副会長も心の中では「どこかで代えなければならないかも知れない」とは思っていましたが、逡巡していたのです。
強化委員会のメンバーは、ずいぶん前から心配していたことが現実になったという認識に固まっていたのです。というのは、加茂監督が強化委員会のサポートを一顧だにしていなかったことが分かったからです。
実は強化委員会は、最終予選の各試合毎に相手チームのスカウティング活動を実施していて、毎試合レポートを提出していたのですが、加茂監督はスカウティング担当との打ち合わせ会議に出席せず、レポートにさえ目を通していなかったというのです。
そのため韓国戦でも、強化委員会のスカウティングでは「FWの高正云を先発させ変則3トップで来る」と読み切っていたのですが、加茂監督は「高正云は体調不良で出られない」というマスコミ報道を安易に信じてスタメンを完全に読み違えるというミスを犯してしまったのです。
このミス自体が直接の敗因には繋がらなかったものの、ここで強化委員会は「これではまずい」と危機感を強めたのです。
加茂監督が強化委員会のサポートを毛嫌いしたのには訳があって、2年前の1995年11月、当時の加藤久強化委員長のもとで出されたレポート、いわゆるネルシーニョ事件の発端となったレポートに対する強烈な拒否反応があったからです。
強化委員会と代表監督の相互信頼関係がないというのは、オフト監督がせっかくレガシーとして確立した「スカウティング活動によるサポート」という日本代表としての大きな武器を自ら手放すようなものです。このことからも加茂監督が批判を受けることが多い理由の一端が窺えます。
ここから加茂ジャパンの歯車が狂い始めます。第4戦は10月4日、アウェーのカザフスタン戦、日本は呂比須ワグナー選手のゴールで1点をリードしたままロスタイムに入りましたが失点、同点とされてしまいました。
この同点劇、カズ・三浦知良選手が相手ペナルティエリア近くでドリブル突破を試みたボールを奪われ、そのまま逆襲されて同点にされたもの。同僚たちから「何やってんだ、全く」「バッカじゃないの」「時間稼ぎすべきところでできていない。監督に言われなくてもわかることなのに」といった声が出る有り様で試合終了、日本はこの組3位、出場権獲得の望みがない順位に沈みました。
この失点に関与したと言われても仕方のないカズ・三浦知良選手のプレーは、ベンチで見ていた岡田コーチの目にも同様に映ったのではないでしょうか。この最終予選に入って初戦こそ4ゴールの大暴れでしたが、その後ノーゴール、焦っていたとは思いますが、リードしている展開でのロスタイムに入ってのドリブル仕掛け、およそチームリーダー格のベテランとは思えないプレーを岡田コーチは脳裏に刻んだかもしれません。
加茂監督も「カズはチャンスを外していて点が欲しい焦りからだろう。こっちは『サイドでキープや』と声がかれるぐらい叫んだんだが・・・」と信じられない様子で振り返っていました。
ただ、すでにベンチに退いていた名波浩選手は、のちに、このプレーについて聞かれ、こう答えています。
「もちろんあと数分守りきれば勝てるというのは頭では理解できるんですけど、もし僕がフィールドに立っていても、同じように2点目を取りにいっちゃっていたと思います。それくらい相手のディフェンスが ”ザル”だったから・・・」(「名波浩 泥まみれのナンバー10」(平山譲著1998年6月TOKYO FM出版刊)より)
実はカズ・三浦知良選手、前の韓国戦で相手GKの激しいチャージを受けて尾てい骨を強打していたのでした。韓国戦終了後、加茂監督・コーチ陣がカズ・三浦知良選手の尾てい骨の状態について、カザフスタン戦起用は難しいだろうと見ていたのですが、フラビオ・フィジカルコーチが「試合までには間違いなく回復させると思うので別メニューで調整させましょう」と提案、そのように準備させたのですが、実際には痛みはひいていなかったのでした。
カザフスタン戦直前練習、明らかに動きがよくないカズ・三浦知良選手でしたが加茂監督はスタメン起用を決め、結果、相手にカウンターを許す無理なドリブル突破につながったのでした。
試合後、現地に応援に行っていた数少ないサポーターの一人が車に乗り込もうとする加茂監督の顔にツバを吐きかける狼藉を働きました。加茂監督も一瞬ジロリと睨みつけたものの、黙って車に乗り込みましたが、左頬にはベットリとツバが残りました。
カザフスタン戦のあと、突然の監督交代劇、岡田コーチが昇格
その夜、カザフスタンに同行していた日本サッカー協会・長沼会長以下幹部が緊急に善後策を協議、「流れを変えなければダメだ」という意見に長沼会長も決断するしかありませんでした。加茂監督を更迭することは決まりました。では誰が指揮するのかについて長沼会長以下協会幹部に腹案があったわけではありませんから、大仁強化委員長に話を振ると「岡田コーチで行きましょう」と提案しました。
そもそも誰かを日本からカザフスタンなりウズベキスタンに呼ぶにしても、入国ビザの問題があり手続き的に不可能でした。
長沼会長以下幹部も、他に選択肢がないことはわかっていますから、岡田武史コーチを監督に昇格させる策が決まりました。すぐ加茂監督と岡田コーチが呼ばれ、ことの経緯が伝えられました。
岡田コーチは「監督を引き受けてくれ」と迫られましたが、そう簡単に「わかりました」と言えるはずもありません。「少し考えさせてください」と青ざめた顔で答えます。
すると協会幹部は「ダメだ。ここで監督を引き受けると言ってくれ。それ以外は受け付けない。」
なおも岡田コーチは「監督が更迭されたのは、コーチの自分にも責任があります」
すると、大仁強化委員長が「日本から誰かを呼ぶといっても手続き的に不可能だし、監督不在のまま試合に臨むわけにはいかない」と説得します。それでも岡田コーチは押し黙ったままです。
すると加茂監督が「お前がやるしかないんだ」と口を開きました。
仕えていたボスからそう言われてしまえば、もう受諾するしか選択肢しかない状況だったのです。岡田コーチは「わかりました。ウズベキスタンだけはやります。」と答えたのです。
長沼会長と大仁強化委員長に伴われて岡田コーチが記者団の前に現れました。その顔は青ざめて憔悴しきった表情でした。
長沼会長が口を開きました。「結論から申し上げます。加茂監督を更迭して、岡田コーチに昇格してもらって、ウズベキスタン戦以降の戦いに臨むという方針を決定いたしました。」
その理由について長沼会長は「特に第3戦(韓国戦)、第4戦(カザフスタン戦)、どうも流れがよくない、流れを何とかして変えなければならない。そのためには、いわば棟梁を変えるという思い切った手を打つしかないというのが私どもの結論です。どうかご理解いただきたいと思います。」
次いで岡田新監督が挨拶しました。
「(加茂監督が辞任され)私たちは大黒柱を持たない、いわば2×4(ツーバイフォー)の家のようなものです。お互いを支え合って強固な家にしていきたいと思います。」
「ともかくウズベキスタン戦に全力を尽くして頑張りたいと思います。これまでの戦いについてはメンタルとか戦術を含めて全て修正可能な問題だと思っています。メンバーなどの大きな変更がなくても十分修正できると思っています。」
記者団から「自信と不安、どちらが大きいですか?」と問われると「いや、そのどちらもないです。」と短く答えました。
加茂監督のことがまだ選手たちに伝えられる前、協会幹部たちの慌ただしい動きにただならぬ気配を感じた選手たちは「加茂監督が解任になるらしい」と知ったそうですが、笑えない逸話が伝えられています。
井原正巳選手と秋田豊選手が、加茂監督が解任らしいという話を聞いて、岡田コーチに「次の監督、誰なんですか」と尋ねたそうです。黙りこくる岡田コーチの顔色がとても悪かったので、どうなっているのか心配になったというのです。
さらに「後任は岡田コーチ」の名前を聞かされた選手たちは、一様に「エーーッ」とのけ反ったというのです。その時まで岡田さんという人は、監督というイメージから一番程遠い感じの人だったことを物語っています。
夜、各自がそれぞれ部屋にいると、宿泊先のホテルの一室に選手たち全員が集められ長沼会長から監督交代が告げられました。
選手たちは、一旦、それぞれの部屋に戻ろうとエレベーターに乗り、各部屋のフロアに着きますが、そう簡単には解散できそうにない出来事を聞かされましたから、誰からともなく「リラックスルーム」や「マッサージルーム」という名目でキープされていた部屋の前で立ち話を始めました。
誰も部屋に戻ろうという気になれないのです。その空気を察した井原選手が「一度、皆んなで集まろう」と声をかけ、あらためて三々五々、今度は酒やソフトドリングなど思い思いのものを片手に集まり始め、語り合い始めました。
気がつけば、ほとんどの選手・スタッフが集まったそうです。
その場は、井原キャプテンを中心とした自主的ミーティングの場と化し、残りの選手たちにも来てもらい、お互いの胸の内をぶつけ合う場となり3時間ほどの率直な話し合いを通じて「あきらめるのはまだ早い、これまでの反省を活かせば、必ず何かが起きる」という気持ちを共有して「2試合続けて守り切ることができなかった、それはなぜだったか」を議論し合い、各自のやるべきことをあらためて確認し合ったといいます。
何人かの選手は、夜が白々と明け始めるまで部屋に残り続けました。眠れない夜だったのです。
これまでは、加茂監督が、ある意味放任主義的なチームマネジメント方針だったこともありますが、日本代表チームとは言いながら、数人づつに分かれたグループの寄せ集めのようだというのが多くの記者たちの印象でした。
つまりカズ・三浦知良選手、井原正巳選手、中山雅史選手らの「ドーハ組」、相馬直樹選手、小村徳男選手、名波浩選手らの「バルセロナ五輪組」、川口能活選手、城彰二選手、中田英寿選手らの「アトランタ五輪組」、その他の選手たちのグループ、といった具合です。
それぞれの仲間同士ではコミュニケーションを取り合っていたものの、それ以外のグループ間の交流が少なかったためチーム全体が結束する機会がなかったというのが実情だったというのです。
このミーティングは、自然発生的な集まりだったことで、かえって結束を深める絶大な効果がありました。カズ・三浦知良選手も部屋に来ましたが、まもなく出ていきました。この深夜のことについてカズ・三浦知良選手は「たったひとりのワールドカップ」(一志治夫著)の中で、このように述べています。
「昨日(注・加茂監督更迭が発表された日)の夜、グラウンドに立っている加茂さんの夢を見た。どこかで自分(注・カズ自身)の心にひっかかっているんだろうね。」
加茂監督が更迭された原因の半分が選手たちの責任であることを痛いほど理解しているカズ・三浦知良選手です。また、自分に全幅の信頼をおいていてくれた加茂監督がいなくなってしまうことによって、自分の立場がどうなるのだろうか、そんな思いも頭をよぎったかもしれません。
このあとに待ち受けるカズ・三浦知良選手の「ワールドカップ」に絡む運命の流れは、もしかしたら、この夜が源流になったのかも知れません。
長い一夜が明けました。翌日、次のウズベキスタン戦に臨むため選手・スタッフ全員が移動してしまい、一人だけになったホテルで加茂監督が記者団に口を開きました。
「韓国戦の逆転ゴールがすべてだったと思う。昨夜、長沼会長と大仁強化委員長に呼ばれ『降りろ』と言われた。辞めるつもりはなかったので悔しいが長沼会長に言われては仕方がない。その時、岡ちゃんが引き継ぐ話を聞いたが、岡ちゃんもびっくりしていた。2人で夜中の2時ぐらいまで飲んだよ」と悔しさをにじませながらも、岡田後任監督を励ました昨夜のことをサバサバした様子で語りました。
このタイミングでの監督交代、加茂監督が「負け越しているわけではないので悔しい気持ちだ」と語ったことの裏返しで「いまなら、まだ遅きに失したタイミングではない」というタイミングだと言えます。1位で文句なしの出場権獲得はなくなったものの、2位を確保しして第3代表決定戦の権利を確保することは十分可能なタイミングということになります。
岡田監督初采配、ウズベキスタン戦、ロスタイムに同点に追いつく。「ひょっとしたら」と感じさせる奇跡のゴール
岡田監督は当初1試合限定という条件で第5戦、10月11日、アウェーのウズベキスタン戦の指揮を採りました。この試合、日本は1点をリードされてしまい、もし、そのまま敗戦となればW杯出場権獲得はほぼ絶望的となる状況でしたが、ちょうど後半ロスタイムに入ったかという時です。自陣最後尾でボールをキープした井原選手は、明らかに意を決したプレーを選択しました。
放送していたNHK-BSのTVカメラも、まるで「君が主役になるんだ」と訴えかけるように、画面の中心に井原選手を捉えました。
井原選手は、2,3歩助走すると、力みのないきれいなフォームから超ロングキックを繰り出しました。
自陣からおよそ60m先まで飛んだボールは、最前線に張っていた呂比須ワグナー選手に見事に合い、ヘディング、するとボール2バウンドして、飛び出したGKの股間を抜けゴールに吸い込まれたのです。起死回生の同点ゴールの瞬間でした。
呂比須選手がヘディングした場所はペナルティエリアのすぐ外の位置でした。落ちたボールをカズ・三浦知良選手が追いかけたものの、追いつかずワンバウンド、2バウンド目にGKのところに届き、楽々キャッチするものと思われました。
ところがボールはGKの手に届く直前にバウンドしたため、ちょうどGKの股間をすり抜けてしまったのです。カズ・三浦知良選手の動きに惑わされた相手GKがボールを合わせ損なった結果でした。
岡田監督は、そのゴールを見て「これはひょっとすると、ひょっとするかも知れない」と思い、思わず、そう呟いたそうです。それを耳にした年配の記者からは「お前、バカか」と嘲笑されたといいます。記者たちはもう半分以上、投げていたのです。
サッカージャナリストの杉山茂樹氏は、後にネットコラム「webスポルディーバ・平成サッカー史を変えた怒涛の1週間」の中で、この同点ゴールのことを次のように振り返っています。杉山氏は、このゴールが日本サッカー史を語る上で、絶対に外せないゴールと強調していますので、しっかりと記録に留めておきたいと思います。
「ウズベキスタンのGKがなぜ後逸することになったのか。井原が最後尾から蹴ったボールが、なぜ、ほぼ直接ゴールに吸い込まれることになったのか。
GKがカズの動きに幻惑され、ボールから目を離したとしか言いようがないが、数ある観戦歴のなかでも、このゴールほど、不可解でミステリアスなものは珍しい。日本サッカー史に重大な影響を与えたゴールがこの有様では、大真面目にサッカーを論じることがバカバカしくなるほどだ。だが、それがサッカーの持つ恐ろしい魅力でもある。”事実は小説よりも奇なり”を地で行くゴールとはこのことだ。
タラレバ話をしたくなる。あのゴールが決まっていなければ。普通にGKがキャッチしていれば……。
岡田さんのその後の人生は、この運によって支えられているといっても言い過ぎではない。日本サッカーもしかり。サッカーは結果に対して運の占める割合が3割あると言われるが、平成サッカー30年史を語ろうとしたとき、これは外せない珍事と言えよう。だが、なぜか皆、この件にはあまり触れたがらない。いまだキチンと向き合えずにいる。」
杉山氏はこのように回顧しています。あのゴールがどうにも不可解で仕方がないのに、そのゴールが日本サッカー史に重大な影響を与えたのですから、複雑な気持ちになるのは無理ありません。
井原選手は、この試合イエローカードを1枚受けたため累積2枚で次の試合出場停止、しかし土壇場で執念が乗り移ったかのようなロングフィードをゴールに結び付けました。前述の杉山茂樹氏も、これまでの試合とは全く違う鬼気迫る動きで存在感を示していた井原選手について「大きな収穫だった」と評価しました。
試合後、殊勲の呂比須ワグナー選手が「このゴールは90%カズさんのおかげ」とコメントしたように、カズ・三浦知良選手の動きは、カザフスタン戦での状況を考えないドリブル仕掛けによる失点を帳消しにできる価値があったと評価した専門家もいましたが、ウズベキスタン戦後の日本代表の修正点について専門家の多くが「加茂監督が退任した今、次に手をつけるべきはカズ・三浦知良選手を外すことだ」と指摘しました。
すでに第2戦のUAE戦以降、カズ・三浦知良選手はFWの選手として決定的な仕事ができない状況が続いており、そうなると高さもないスピードもないカズ・三浦知良選手は並みの選手ということになり、こだわって使う理由は何一つないというのが専門家の指摘でした。
ウズベキスタン戦で勝利できなかったため、自力での2位確保がなくなったものの、まだ首の皮1枚繋がった状態で帰国した日本代表。
実は、試合を終えた選手たちはロッカールームでほとんどの選手が涙を浮かべて絶望感に打ちのめされていたそうです。冷静に考えれば、まだ全てが終わったわけではないのでしたが「オレたちはもう無理だ」といった雰囲気だったといいます。
それを見て岡田監督は「こいつらも大変な重圧の中で戦ってるんだ、こいつらを置き去りにして逃げるわけにはいかない。最後までこいつらとやる。」と思い直したといいます。
1試合限定でウズベキスタン戦を引き受け「あとのことは日本に戻って加茂前監督と会ってから」と話していたとおり、帰国後すぐ加茂前監督に面会「このまま選手を置き去りにして自分だけ辞めれば済むという問題ではないという気持ちです」と率直な気持ちを伝えると、加茂前監督からも「辛いだろうけれど頑張ってくれ、時々電話するから」と背中を押され腹を括って指揮を続けることにしました。
日本サッカー協会も、岡田監督が続投してくれる意思を固めたことで、あらためて「最終予選終了まで岡田監督続投、コーチ役には小野剛強化委員がベンチ入り」を発表、第6戦、10月26日、ホーム国立競技場にUAEを迎えることになりました。この時UAEは2位、実はウズベキスタン戦のあと帰国して国内合宿に入っていた日本代表のもとに「UAE、カザフスタンに0-3で敗れる」の報が入ったのです。勝ち点差7のUAEに対して、日本は勝ち点6、これで日本は、残り試合次第で、自力で2位に入る芽が出たのです。
岡田監督は小野剛強化委員のベンチ入りについて、1997.12.17サッカーマガジン誌に寄せた「独占手記-その2」の中で「強化委員会から推薦されたのではなく、ぼくが決めさせてもらいました。コーチの肩書にしなかったのは、コーチという立場にしてしまうと選手から『なぜ、それをやらなければならないんだ』と言われた時、きちんと説明しなければならない義務を負ってしまう。そこまで求めては酷だ。けれども身近に融通が効く形でいてもらえるのはありがたい、そう考えて強化委員のままベンチに入ってもらったんです。」と語っています。
このタイミングでNHKは総合テレビの「土曜特集」の枠で「緊急特番」を組みました。日本代表を応援してくれている全国のサッカーファンに、W杯出場権獲得のカギについて一緒に考えてみましょうという趣旨でした。NHKは、加茂監督が更迭された翌日の10月5日にもBS放送で「緊急特集・加茂監督更迭・・W杯をめざして『ジーコ』の提言」という2時間番組を放送しましたが、もっと後押しが必要と考えたのでしょうか。
特番のタイトルはズバリ「どうすればフランスに行けるのか」
番組はNHKの堀尾正明キャスターが司会を務め、W杯アジア予選の経験者である元日本代表・加藤久氏、木村和司氏に加え、タレントの清水圭さん、高見恭子さん、そしてコラムニストで漫画家の山藤章二さんという顔ぶれ、番組の後半には日本が生んだ最高のストライカー・釜本邦茂さんも加わり1時間15分にわたって、過去の日本代表の戦いをひも解きながら、W杯出場権獲得のカギを話し合いました。
ホームUAE戦に勝てず、怒ったサポーター暴動を起こす
そして10月26日、国立競技場には56,089人の観衆が詰めかけました。
日本代表サポーター「ウルトラス」は、選手入場の時にこの唄に思いを託しました。国立競技場には、サポーターたちの大きな歌声が響き渡りました。
「翼をください」という曲です。作詞・山上路夫、作曲・村井邦彦、唄・赤い鳥
「♫いまぁ~~、私の~~、ねがいごとが~~、叶うならば~~、♫つばさをください~~ この~~~、背中に~~、♫鳥のように~~~、白い翼~~、つけて下さぁぁ~い、♫この大空に、翼をひろげ、飛んでいきたいよ~~~、」
この曲は1971年に作られたといいますから、すでにこの時で25年以上経っている曲です。もともとは歌っているフォークグループ・赤い鳥のシングルレコードのB面に、自分たちのグループの「テーマ曲」のような意味合いの曲(鳥というグループ名なので翼に関する曲がいいだろうと)として収められましたが、時を経て「サッカー日本代表」のテーマ曲のようにして、こうして大観衆の国立競技場に響き渡ったのですから、不思議なつながりです。
この歌声に後押しされるように、日本は前半3分、この日井原選手に代わってゲームキャプテンを務めたカズ・三浦知良選手からのパスに反応した呂比須ワグナー選手のゴールで先制しました。ところが前半36分にFKからヘディングで同点ゴールを許してしまいました。
その後は、UAEの引き分けで良しとする徹底したアウェー戦術に攻め手を欠き、またしても引き分けで終わりました。
またしても日本代表は、自力で2位を確保する芽がなくなり、絶望の淵にたってしまいました。心底日本代表を応援しているサポーターたちの気持ちは、まさに「翼をください・・・、翼をひろげ、飛んでいきたい・・・・」そんな心境でした。
もはや崖っぷちのところに来た日本、国立競技場を埋め尽くした満員のサポーターたちは、素直に帰宅の途につく気になれず、一部の観客の鬱積した気持ちが怒りとなって爆発、スタジアムを出てきた選手たちに詰め寄る事態に発展しました。その数3000人とも5000人とも言われる数にのぼり、駐車場を隔てるフェンス越しに出てくる選手たちに罵声を浴びせ始めたのです。
そしてカズ・三浦知良選手が姿を表した時にも、罵声を浴びせペットボトルやゴミ袋などを投げつけましたが、カズ選手はサポーターに向って「次だ、次 !!」と言って車に乗り込みました。
しかしサポーターたちの怒りは収まらずカズ・三浦知良選手の乗った乗用車めがけてペットボトルや生卵などを投げつけ「やめろ!! !!」コール。今度はカズ・三浦知良選手のほうが車から飛び出すと「おい!! 出て来い。この野郎!! ふざけんなぁ、話してやる」と、普段のカズ・三浦知良選手とは思えない表情で怒鳴り返したのです。
多くの報道陣やサポーターがぎっしり見守る中でのカズ・三浦知良選手の怒りに驚いた関係者がカズ・三浦知良選手を羽交い絞めにして引き留めようとしますが「余計なことをすんじゃねぇ、呼んで来い。」
これに対して一部のサポーターが柵を乗り越えてカズ・三浦知良選手に飛びかかろうとしますが警察官に取り押さえられ、報道陣も巻き込まれて一時は大混乱となりました。
カズ・三浦知良選手は、あわてて飛び出した小野剛強化委員に抱えられるようにして車に戻りました。
しかし、車は3000人とも5000人とも言われる大勢のサポーターのため通用門を封鎖された形になり、しばらく立ち往生、その車で競技場を出ることを断念せざるを得なくなり一旦ロッカー室に戻り30分ほど待機、他の選手たちも、別の門からワゴン車やタクシーに分乗して競技場を後にしました。
暴徒化したサポーターは、約200人ほどの機動隊員と警察官の制止も聞かず、記者会見場となっていた通用門横の体育館屋上から約10㎝ほどの石を駐車していた報道陣の車のボンネットめがけて落としました。
警察はさら30人増員して辛抱強く対応にあたりましたが、深夜まで騒ぎは収まらず、最終的に逮捕者や検挙者までは出なかったものの、日本サッカー史に汚点を残すサポーターの暴挙となりました。
それもそのはずです。第3戦の韓国戦以降、いらいらする試合運び、もどかしいチャンスつぶしなど、日本全国のサポーターのフラストレーションは溜まりに溜まっていて、その理由がカズ・三浦知良選手の不振にあることも痛感していましたし、この日も5分ぐらいはあると思われていたロスタイムが1分そこそこでホイッスルが鳴ってしまい、怒りがMAXに達していたのですから。
この時のサポーターの暴挙とカズ・三浦知良選手の行動について、カズ・三浦知良選手は97.12.18Number433号でジャーナリスト・一志治夫氏のインタビューに答えてこう述べています。
「僕らはグラウンドで何を言われてもいいけど、やっぱり自分を応援に来た家族が傷つけられそうになったら、それは行くしかないでしょ。一部の心ないファンがそういう行動に出たわけだけど、それは間違いでしょ。『彼らにはその権利がある』なんて言っている評論家もいたけど、それは絶対に違うよね。」
ちなみに、このUAE戦、負傷者の治療などのためロスタイムはどう考えても5分ぐらいはあるだろうと思われていましたが1分そこそこでホイッスルが鳴ってしまいました。日本は勝ち越しのゴールを狙って猛攻を仕掛けていましたからベンチも選手もサポーターもこぞってレフェリーに対して猛抗議の意思を示しました。
これが一説には、翌年のフランスワールドカップにおけるロスタイム表示の明確化という競技規則の改訂につながったとも言われています。それを裏付ける資料はありませんが、もし事実であれば、歴史を動かした試合になったのかも知れません。
奇しくも、この日は10月26日、日本サッカー界にとって「因縁の10.26」の日でした。
1985年のこの日、W杯メキシコ大会アジア最終予選・韓国戦で敗戦、1987年のこの日、ソウル五輪アジア東地区最終予選・中国戦で敗戦した日でした。
もはや、これ以上の崖っぷちはもうない、というところでアウェーの韓国戦を迎えることになりましたが、少し様子が変でした。
日本がUAEと引き分けたことによって、ここまで6試合を消化していた首位韓国が、残り試合に関係なく、この組の首位通過、W杯出場権を確定したのです。
その状況で第7戦のアウェー韓国戦を迎えたのです。韓国は、ホームにも拘わらずモチベーションが幾分弛んでいたことは明らかでした。もし韓国にとっても負けられない順位・勝ち点状況だったとしたら・・・。「たられば」は禁物なのですが、どうしても、そう考えざるを得ません。こうした巡り合わせも、この最終予選を一層劇的なものにしたと言えます。
アウェー韓国戦、いろいろな意味で流れが変わった1戦、会心の勝利
韓国がすでにW杯出場権を決めていたという状況は、日本にとって、天の恵み、神のおぼし召しと思わざるを得ません。
11月1日、韓国・チャムシルスタジアムには約7万5000人(公式発表は80,000人)の観衆が入ったそうですが、このうち日本から約1万5000人と見られるサポーターが海を渡りました。9月28日国立競技場で行なわれた韓国戦を応援した韓国サポーターは約6000人ほどと言われており、それを大幅に上回る数となりました。
日本代表はといえば、もう失うものは何もない、吹っ切れた気持ちで試合に望みました。それぞれの選手が、それぞれの理由で吹っ切れていたのです。
韓国代表はリベロの洪明甫選手が累積警告による出場停止のため守備ラインが少し不安になっていたことも幸いしました。
試合は、早々と前半2分に動きました。これまでの試合、守備意識にこだわり過ぎてか、本来の持ち味を出せていなかった、日本の左サイドのコンビネーション、相馬直樹選手と名波浩選手の崩しから生まれました。
センターサークル付近から中田英寿選手が出したパスを受けた名波選手が、相手DF2人をかわすように外側を向き、駆け上がってきた相馬選手のスピードに合わせた丁寧なパスを送ります。パスを出した名波選手は、そのままゴール前のスペースに上がりました。
相馬選手は来たボールと味方選手の位置関係を測りながらタテに動き、ダイレクトで中に折り返しました。ボールはペナルティエリアの中、ほぼゴール正面にいた呂比須ワグナー選手に届きます。呂比須選手は相手DFを背負って、左足で触りましたが、無理にひっかけようとせず流すようにタッチしました。ボールは、ものの見事に上がってきた名波選手の足元に届いたのです。
相手DFを引き連れた呂比須選手と、その後ろのカズ・三浦知良選手もDFを引き連れて、後ろ側にスペースを作る動きをしてくれたため、名波選手はGKと1対1の状態でシュートを打てる場面ができました。
ボールはちょうどペナルティスポットのあたりです。名波選手はほとんど助走なしで左足で、狙いすましてゴール右隅にボールを蹴り込みました。ボールは狙い通りに右ポストの内側からゴールインして行きました。
これで好守のリズムを取り戻した日本は、その後も左サイドからの攻撃をたびたび仕掛け、前半37分には、またもオーバーラップしていた相馬選手が中田選手からの浮き球のパスを受けると相手DFを一人かわしながらゴールポストのすぐ近くのゴールライン際まで進みマイナスの折り返し、呂比須ワグナー選手めがけてグラウンダーのパスを出すと、呂比須ワグナー選手はこれをきっちりと合わせて追加点をあげました。呂比須ワグナー選手は、カザフ戦の先制ゴール、ウズベキ戦の起死回生の同点ゴールに続く3試合連続ゴールでした。
前半39分には相手の攻撃をDF秋田豊選手が渾身の守備で防ぐと、韓国FW崔竜洙選手がしたたか顔面を打って昏倒、鼻から出血しているのを見た川口選手は、一旦ボールをキープした井原選手に大声で「出せ~~~!!」と指示、プレーを止めさせました。
日本イレブンは気力・集中力ともにMAXの状態で戦っていました。
ハーフタイム、岡田監督は「もう1点取るんだ、怖がるな!」とゲキ。選手交代でも北澤選手に代えて平野孝選手を入れ、攻める姿勢を貫きました。
韓国はFW高正云選手も足に痙攣を起こして前半だけで交代、後半29分にはMF柳相鉄選手も左ひざを痛めてしまいましたが、すでに3人の交代枠を使い切っていたため、痛めたままプレー。後半35分にはDFでキャプテンの崔英一選手が、この日2枚目の警告で退場、ここからは10人での戦いとなりました。
前回のホームでの韓国戦以降、試合終了まで残り時間が少なくなってからの失点を繰り返してきた日本、この日も最後は韓国の猛攻を受けましたが、身体を張った守りで凌ぎ終了ホイッスルを迎えました。
アウェーにも拘わらず2-0の勝利です。キャプテン・井原正巳選手は、試合でのマッチアップを通じて「韓国にいつもの、何が何でも日本には負けられないという気持ちが感じられなかった」と感じていたそうです。
その結果、韓国は、ケガ人や退場者を次々と出してしまうことになってしまいました。
この試合について、岡田監督は1997.12.17サッカーマガジン誌に寄せた「独占手記-その2」の中で「カギになったのは北澤でした。北澤の動きは予想以上だった。正直言って、あそこまでポイントになれるとは思っていなかった。スペースへの飛び出しだけではなく、スペースメーキング、カバーリング、ディフェンスができる。すごい収穫だった。」と称賛しました。
試合後、韓国応援団「レッド・デビルズ」のスタンドには英語で「Let’s go to France together(一緒にフランスへ行こう)」の横断幕が掲げられました。また電光掲示板には「日本代表 おめでとう」の日本語が光っていました。
スタジアムでその横断幕を目にした日本協会の長沼会長にとっても、それは思いがけない光景でした。「それまでの韓国は、日本が溺れているなら蹴落とせ、という感じだったんだからね。いくら韓国が出場権を決めていて余裕があるといっても・・・。しかもハングルでなく英語の横断幕だからね、これはパートナーになれるなって思ったよ。」
日本は明らかに韓国に助けられました。日本代表が韓国から帰国した2日深夜、ホームにウズベキスタンを迎えたUAEがスコアレスドローの引き分けに終わり勝ち点は9、韓国に勝って勝ち点を10に伸ばした日本が再び自力で3位決定戦に出場できるB組2位に浮上したのです。
そして11月8日、最終第8戦、ホームにカザフスタンを迎えました。
日本は韓国戦でカズ・三浦知良選手と呂比須ワグナー選手が累積警告による出場停止、代役にドーハ組の中山雅史選手と高木琢也選手が招集されました。
国立競技場のサポーターは、2週間前のUAE戦での積りに積もった不満を爆発させた暴挙の表情はもはやなく、日本代表を何としても第3代表決定戦に送り込むんだという意思の塊のような集団に変わっていました。
そして、その気持ちを、初戦の紙吹雪にかわる小道具として、白と青の2色の紙テープ、各1万本をバックスタンドを埋め尽くしたサポーターたちが外周トラックに向かって投げ入れるパフォーマンスで表しました。まるで豪華客船の船上から埠頭に立つ人々を繋ぐ、あの無数のテープのような夢空間が再び現出しました。
今度はもう、紙吹雪のように漂流してしまって日本代表の行く末を暗示してしまうような風景にはなりませんでした。
国立競技場の周りには試合2日前の6日からすでに1周するほどの徹夜テント組が集結、11月の夜はかなり冷え込む中をモノともせずに試合当日を待ちました。試合当日の朝には徹夜組が5000人に達したようです。しかし、試合は水もの、不測の事態に備えるため、警備体制は2週間前のUAE戦の二の舞を繰り返さないため、機動隊員を大幅に増やして対応にあたることになりました。
テレビ中継は、韓国戦の勝利を伝えて「不敗神話」を続けるフジテレビでした。
9月28日のホーム・韓国戦以来、山道に例えれば、絶望と希望に分かれた狭い尾根道を、1戦毎に絶望の崖に足を踏み外そうになったり、希望の花園側に戻ったり、行ったり来たりの1ケ月余り、やっと選手たちは「韓国戦の勝利」という何よりの自信回復薬が絶大な効き目を発揮し始めてきました。もともと、実力的にはB組で韓国と2強といわれていた日本だったのですが、その韓国との第3戦でいやな負け方をしてから、なぜか好守のバランスが悪くなりチームの歯車が狂い始めたのです。
そして、監督更迭という荒療治が施されたわけです。その結果、3戦かかってしまったものの、日本代表は「韓国戦の勝利」という自信回復薬によって、本来の自信を取り戻し、自力2位確保が可能な状態で、最終・カザフスタン戦を迎えることができたのです。
韓国の出場権獲得、UAEの自滅という他力要因もあってのことですが、それも含めて日本代表は、挑戦権を自力で得られる星のもとにあったと言っていいでしょう。
あとは、そのチャンスを活かしきれるかどうかという問題だけでした。
11月8日、最終第8戦、ホーム・カザフスタン戦、日本代表の布陣は、城彰二選手と中山雅史選手の2トップ、中盤に北澤豪選手、名波浩選手、中田英寿選手、山口素弘選手、4バックが名良橋選手、井原正巳選手、秋田豊選手、相馬直樹選手、GK川口能活選手。
日本はカザフカタンが守りを固めてくる戦術と睨み、セットプレーから活路を見出すことにして、相当練習に時間を割きました。
その効果が前半12分の先制点に表れました。中田選手からのFKに秋田豊選手がヘッドで合わせて1点、4分後の前半16分には、名波選手から左サイドの相馬選手に展開したボールを相手陣内深くまで持ち上がり、マイナスのグラウンダーを送ると、これを中田英寿選手が左足で合わせてシュート、GKの手に当たりながらもゴール、早くも2点をリードしました。
こうなると、サポーターの期待は2トップのゴールです。特に、スタンドからは日本代表応援団・ウルトラス自慢の応援チャント「オー! ナカヤマ! ナカヤマ、ナカヤマ、ナカヤマー!」いわゆる「中山コール」が響き渡ります。
前半44分、その中山雅史選手が監督の狙い通り、前線からのプレスで相手DFのファウルを誘い、ペナルティエリア右外側でFKのチャンスを得ると、キッカーの名波選手から中山選手にドンピシャのボールが渡り豪快にヘッドで叩き込むゴンゴール。リードを3点に広げました。
そして中山雅史選手、ゴールを決めると、スタンドに向かって走りながら追加招集のためもらった背番号32のついている自分のユニフォームを1枚めくって見せました。そこには背番号11のユニフォームがありました。この日出場停止のカズ・三浦知良選手から託されたユニフォームを着てプレーしていたのでした。スタジアムのボルテージがまた一段あがった瞬間でした。
中山雅史選手、1995年6月のブラジル戦以来、2年5ケ月も代表に招集されていなかったこと自体、信じられないほどのブランクでしたが、戻ってきて、いきなりスタメンで、しかもきっちりと結果を出す中山雅史選手、このあとの日本代表に再び欠かせない選手となったのです。
日本は後半に入っても攻めの手を緩めず、後半22分にはまたもセットプレーから追加点をあげました。ゴール右側から名波選手のコーナーキック、ボールはゴール前に密集していたところではなく、ペナルティエリアの外に張っていたノーマークの井原正巳選手のもとへ、これを本人は照明が目に入ったため、やたら慎重に蹴ったという右足のボレーが見事に決まり4点目です。
後半28分に相手のFKで1点返されたものの、後半34分には、やはり追加招集で後半19分から投入されていた高木琢也選手が、この日、再三左サイドゴールライン際までオーバーラップを繰り返していた相馬直樹選手からの低く速いクロスを、半身になって相手DFの前に出した右足アウトサイドでヒット、見事に5点目を叩き出しました。
追加招集でありながら中山選手と高木選手、そして井原選手「ドーハの悲劇」を知る3人の意地の一発で、試合は5-1の圧勝、同じく追加招集のドーハ組・北澤豪選手とともに、胸を張って第3代表決定戦に乗り込むことになりました。
この日の国立競技場は、第1戦目のウズベキスタン戦で「夢の劇場」を演出した紙吹雪が使えなくなったことから、サポーターたちが智恵をひねり紙テープという奥の手を考えだしました。大型客船が埠頭を離れる時に見られる紙テープの、あの光景です。新たな「夢の劇場」の演出でした。
いよいよ、運命の第3代表決定戦、ジョホールバルの長い夜
第3代表決定戦の会場は中立地ということで、マレーシアのジョホールバル・ラルキンスタジアム。決戦の相手はイラン。仮に敗れてもオセアニア代表との大陸間プレーオフの道が残されているとはいえ、勝って文句なしに決めることしか考えていない日本代表でした。
そして、いよいよ運命の11月16日夜、約20000人収容のスタジアムの大半を日本サポーターが埋め尽くして、日本サッカーの歴史が変わる試合を目撃しました。開門待ちのサポーターの一番乗りは前日23時頃、テントを張った2人組の日本人サポーターでした。
日本国内でも多くのファンがテレビにくぎ付けになり試合を見守りました。
テレビ実況はフジテレビ・長坂哲夫アナウンサー、解説・清水秀彦さんのコンビ。フジデレビは、アエー韓国戦、そして最終8戦目のカザフスタン戦に続き不敗神話を誇るテレビ局でした。(写真・スタンドのフジテレビ放送ブース)
NHK-BSも山本浩アナウンサー、解説・松木安太郎さんのコンビで生放送、番組では午後7時から4時間にわたる直前特番を放送した流れで現地からの放送に切り替える熱の入れ方でした。
イランには、アリ・ダエイ、アジジというアジアNo.1クラスの強力2トップがいて、中盤のバゲリとマハダビキアからのパス供給が脅威のチームですが、今回は、バゲリが出場停止、加えて最終戦にカタールに敗れたため解任され、五輪代表監督が昇格という事態になっていました。
そのため16日の第3代表決定戦に回るかどうか決まったのがサウジアラビアの1位が決まった12日、そこから40時間近くかけて移動したため、マレーシアに入ったのは試合前日の15日、イランのコンディションには、そうしたハンディが生じていました。
そうしたハンディの裏返しだったのでしょうか、試合前日あたりから神経戦とも情報戦ともいえるイランからの怪情報が飛び交いました。
主なものはイラン選手による「カズ? もう終わってる選手だよ」発言、「アジジ選手負傷か?」などです。アジジ選手負傷は事実かそれとも演技か、あまり一喜一憂せずに臨むしかありませんでした。
対戦相手がサウジアラビアなのかイランなのか決まるまでの間、日本側も両チーム分のスカウティングをしなければならないという隠れた苦労がありました。ですから相手チームの試合をビデオ分析して個々の選手の特徴や戦術的な傾向を掴む役割を担った小野剛強化委員は、チームが一旦オフをとった間も返上、昼夜を分かたずホテルに籠りきりで作業にあたったのでした。
岡田監督はイラン戦に臨むにあたって、メンバー選定、戦い方について97.12.19サッカーマガジンNo636に独占手記を寄せ次のように語っています。
「イラン戦のスタメンを決めたのは(3日前の)11月13日で、(ベンチ入り)18人を決めたのは前日(15日)、マレーシアに入ってからの2日間のトレーニングを見て(スタメンを最終的に)決めました。イランだからというわけではなく、選手のコンディション、調子、戦い方を考えて決めたことです。(中略)」
「2トップはカズと中山。デイフェンスのときに、プレッシャーを連続してかけられること、相手のプレッシャーが激しいので、マイボールになったときにファイトできること、引いてボールを受けたときに、あっさりと取られないこと。フィジカル面で持ちこたえられること。そういった理由で2人に決めた。」
「まず攻めに行った時に簡単にボールを奪われて、カウンターを食らうことを避けたかった。イランは技術とパワーがあるチーム。ボールを受けて、少なくとも相手DFと一緒につぶれてくれる選手が欲しい。答えは自ずと決まった。」
岡田監督はカザフスタン戦からFW城彰二選手をカズ・三浦知良選手に戻しただけでした。
最前線の選手をチョイスする理由として、これだけあげられれば、まさに、これは戦術的な理由そのもので、それまで得点がしばらくないとか、城のほうがいいのでは? とか呂比須をなぜ使わない? といったマスコミの意見は「監督が決めたこと」という事実の前では無力でしかありません。
マスコミはカズ・三浦知良選手の尾てい骨痛やコンディションがどれほどなのかを懸念していましたが、カズ・三浦知良選手は、のちに総合スポーツ誌Number433号で、ジャーナリストの一志治夫氏のインタビューに答えてこう答えています「イラン戦に入る前の体は絶好調だった。体自体は、ケツの痛いカザフカタン戦の1週間以外は、ずっとこの3ケ月間よかった。」
岡田監督は、そうした戦い方と布陣を決めた一方で、マスコミに対して「ちょっとディフェンシブにやる」と言って、3バックでやるようなニュアンスが対戦相手に伝わるよう、神経戦とも情報戦とも言える話を流しています。これはソウルでの韓国戦を前にして似たような話をマスコミに対して流しておき、まんまと立ち上がりに先制点をもぎとれた経験が岡田監督を大胆にさせたのです。
日本代表のスタメン布陣は、カズ・三浦知良選手と中山雅史選手の2トップ、中盤に北澤豪選手、名波浩選手、中田英寿選手、山口素弘選手、4バックが名良橋選手、井原正巳選手、秋田豊選手、相馬直樹選手、GK川口能活選手でした。
第3代表決定戦、世紀の大一番、いよいよキックオフ
11月16日、日本時間22時、現地時間21時キックオフ。
日本全国のサッカーファンが固唾を飲んで見守る中、試合が始まりました。
開始1分もたたないうち、最後尾から左サイドの相馬直樹選手に出たボールを、内側に切れ込んで右大外にクロスをあげると相手DFがクリア、これがゴールに吸い込まれ一瞬ゴールかと思われましたが、大外のカズ・三浦知良選手がオフサイド、すぐにゲームは再開されました。
今度は前半9分、イランが波状攻撃をかけ日本を揺さぶりました。右から中央に流れたボールが今度は左サイドのダエイへ、それをヘッドで中央に折り返すとアジジの前に、アジジがボールコントロールしようとするところに川口が突っ込みますが取り損ねてアジジをフリーしてしまいます。アジジがスライディングしてシュートを放つところに名良橋選手もスライディングしながら身体を寄せると、アジジのシュートはゴールポスト僅かに左にそれていきました。
日本、ヒヤッとしましたが事なきを得ます。
試合は、その後一進一退の状況が続きますが前半37分、またもイランの攻撃を受けます。GKからのロングフィードを受けたダエイが落すとマハダビキアへ、それをダエイとワンツーで受けてゴール前、振り向きざまにシュートを放つとボールは左ポストを直撃、戻ってきたボールを井原選手が辛うじて蹴りだし、ここも、事なきを得ました。
その直後、前半39分、日本がGK川口からのロングフィード、相手DFが跳ね返したボールを山口素弘選手が拾って名波選手にパス、名波選手はすぐ前方の中田英寿選手にパス、中田選手は相手DFに詰められながらも一瞬速くスルーパス、そこに中山雅史選手が待ち受けていました。中山選手はゴールキーパーと1対1になると左足でGKの左側を抜きにかかるシュート、ボールはGKの手の下をはじいてネットに突き刺さりました。
日本、待望の先制点です。
そして前半終了、後半開始前のスタンドからは「ニッポン!!、ニッポン!!、ニッポン!!」の大歓声、まるで日本国内での試合のような雰囲気です。
いよいよ後半開始のホイッスル、イランは最後尾からロングボール、それを押し戻してもまたロングボール、それを拾ったマハダビキアが突進、シュートコースがないと見るや後ろのダエイにパス、受けたダエイは左足でダイレクトにシュート、味方DFの陰から急に出てきたシュートに川口横っ飛びではじくも、そこにアジジが詰めてきてゴールを決められてしまいます。
後半開始1分もたたない出来事でした。
その後日本は、シュートを2本放ちましたがゴールに至らず、後半13分、イランに右サイドでキープされたボールが中で待っていた選手に渡り、そこからゴール前を横切るような山なりのクロスが入りました。そこにダエイ選手がいて打点の高いヘディングシュート、決められてしまい、日本は逆転を許しました。ダエイ選手には秋田選手と名良橋選手がついていましたが、身体を寄せられずヘディングシュートを許してしまいました。
日本は先制したものの後半逆転を許す展開、ここで岡田監督が動きました。後半18分、すでにアップを命じて準備ができていた城彰二選手と呂比須ワグナー選手を、カズ選手と中山雅史選手に代えて投入、一気に2枚替えの作戦に出たのです。
岡田監督は前述の97.12.19サッカーマガジンNo636に独占手記で、この交代を次のように振り返っています。
「あの暑さで、あのレベルの相手の競り合ったゲームをしたら、おそらく1試合もたないだろうと考えていた。1-0、あるいは1-1のままで(後半)15分、20分ぐらいまで行ったら、代えようと思っていました。後半に入って呂比須と城にアップするよう指示しましたが、その時点では1人代えるか、2人代えるかは決めていなかった。」
「(後半)14分に1点とられた。1-2になって、フィールドを見ると選手たちの目がうつろだった。これはまずい、刺激が必要だ。下がった士気をあげるために、また点を取りにいくんだという姿勢をみせなくてはいけない。2人いっぺんに行こう、と。いずれにしろ両方代えなくてはいけないと思っていたし、一度に代えたほうがインパクトが強い。すぐ交代を決めました。」
このうち、カズ・三浦知良選手は、最終予選第2戦以降、7試合連続ノーゴールとはいえ、故障以外で途中交代を命じられたことのない日本のエースです。交代指令に思わず自分を指さし「オレなの?」と確認してしまいましたが、もはや手を打たなければ負けてしまう状況、一つの時代が終わったシーンでした。
実はカズ・三浦知良選手、「オレもなの?」と確認したのは、「えっ! 俺を代えるの? 」という意味ではなく、イランのほうでも交代準備していたし、こっちは1人づつ少し間をおいて代えるのかもしれないので「どうなの? 2人いっぺんに代えるの? オレの11のこと?」と確認しただけだと語っています。
しかし、マスコミの多くは、岡田監督が「ダメだ、カズは交代させる」と決意させた規律違反の行為があったからだと、穿った見方をしています。それは後半7分のことです。相手ペナルティエリアの左角のすぐそばで日本がFKをチャンスを得たのです。
チームの約束事としてFKとCKは名波選手か中田選手、PKの場合はカズ・三浦知良選手が蹴ることになっていました。
カズ・三浦知良選手は、その約束事を破ってそのFKを蹴ったのです。ボールはバーの上を大きく越えて外れました。もしカズ・三浦知良選手が蹴っていなければ交代がどう行なわれたか、岡田監督は、そのことをおくびにも出しませんでしたが、この約束違反が「カズ・三浦知良選手途中交代」の引き金になったと多くのマスコミが指摘しました。
この選手交代のあと、イランも守備固めの交代を行なったことから日本が押し込む展開に代わり、後半31分、采配が的中しました。
中央でダエイ選手のスルーパスをカットした山口素弘選手のボールを、受けた名波選手が素早く左サイドの中田英寿選手に展開、中田選手はゴール前に走り込んでいた城選手をめがけて、まさにピンポイントのクロス、これを城選手はヘッドで鮮やかに流し込み同点にしました。
ドーハ組の2人が交代で去ったあと、その次の世代(山口素弘と名波浩選手)がお膳立てしてくれたボールを、アトランタ組の2人が決めた同点ゴールでした。新たな時代が幕を明けたシーンでした。
岡田監督は、この城選手の同点ゴールは、それまでのカズ・三浦知良選手と中山雅史選手の貢献によるものだと、次のように語っています。
「前半からカズと中山が猛烈にプレッシャーをかけて、相手のディフェンダーの足が吊るぐらいに動き回っていた。それがボディブローのように効いているわけです。カズと中山があれだけやってくれていなかったら、城があそこまでフリーになることはなかった。」
このあと、両チーム一進一退、お互い惜しいシーンを作りながらも2-2のまま90分を終了しました。
2-2のままVゴール方式の延長戦に突入、そして延長後半13分、歴史が作られました
試合はVゴール方式の延長戦に突入しました。日本ベンチ前ではスタッフを含めた全員が肩を組んでファイトコール、ベンチ外となった選手たちもスタンドからピッチレベルに降りてきて応援に加わりました。
ここでまた岡田監督が動きました。これまで最終予選、一度も出場機会のなかった岡野雅行選手を北澤豪選手に代えて投入したのです。
この時、岡田監督は先に小野コーチに岡野を呼びに行かせて、少し時間があったこともあり、腕組みをしながら座り込んでリフレッシュしている選手たちの周りをぐるぐる回るようにして考え込んでいる姿がNHK-BSのテレビカメラにも捉えられています。
この時の思案について岡田監督は、97.12.19サッカーマガジンNo636に独占手記で、次のように振り返っています。
「みんながピッチで休んでいる時に、腕を組んで歩きながら考えたんです。これは慎重に考えました。相手は相当バテている。PK戦までいったら、押しに押している日本の方が精神的に不利になる。こうした展開だと、押されているほうが、もうけものだという感じになるんです。(中略)」
「なんとかPKにだけは持ち込みたくない。歩いて1周した時には、『ここで岡野で勝負だ』と決めていた。もしキーパーがケガしたら(注・交代枠を使い切るとキーパー同士の交代ができない)、とかリスクがあった。でもリスク覚悟で勝負しようと、相手もすでに3人代えていましたから。」
岡田監督は選手たちに「ここで勝負に行くぞ。岡野を入れるから、スペースに走らせろ」と指示を出しました。
さっそく延長前半1分、岡野雅行選手にチャンスが訪れました。ピッチ中央付近で中田英寿選手から岡野選手にスルーパス、岡野選手が俊足を飛ばしてGKと1対1となったところでシュート。これはGK正面でしたが、とりあえずシュートの感触をつかみました。
対するイランのほうは疲れからか日本に対するファウルが増え、日本はたびたびFKのチャンスを得ました。しかも中盤が間延びし始めたため日本は中田英寿選手、名波浩選手が自由にボールを散らすことができ延長前半5分以降は日本の一方的な展開となってきました。
延長前半12分には相手FKのこぼれ球を拾った中田英寿選手がドリブルしながら岡野選手にスルーパス、岡野選手は30mほど走ってまたしてもGKと1対1の場面を作りました。今度は岡野選手、左後方からフォローしてきた中田英寿選手に横パスを送ってしまい相手DFにクリアされてしまいました。
なぜ打たないんだという中田英寿選手、なぜ打たないんだと頭を抱える岡田監督、なぜ打たないんだとスタジアム全体を埋め尽くしたサポーターのため息が大きなどよめきとなりました。
続く延長前半13分には相手GKが時間稼ぎなのか、ボールを持ちすぎてオーバータイムによる間接FKが日本に与えられました。場所はゴールからわずか5mのペナルティエリア内、中田選手がチョンと出したボールを名波選手が蹴り込むサインプレーでしたが、名波選手が足を滑らせてしまいました。
さらに延長前半ロスタイム、日本が左サイドのボールキープから中田英寿選手がゴール前に突進、ゴールライン際からマイナスに折り返すと、ボールは呂比須ワグナー選手とGKの奪い合いから後ろに転がります。そこに岡野選手が猛然と走り込んできてシュートを放ちますが相手DFが詰めてきたこともあって、大きくふかしてしまいました。このあと延長前半終了のホイッスル。
さぁ、延長後半の開始、運命の残り15分が始まりました。相変わらず日本の攻撃は続き防戦一方のイラン、イランGKは接触プレーの時、左腕を痛めた様子でしたが時間を稼ぎたいという意識もあったのか、たびたび試合が止まりました。
延長後半9分にはこんな光景がありました。イランGKがメディカルチームに診てもらっている間、その3分ほど前にGKと接触して頭を打った様子の城彰二選手に中田英寿選手が近づき、まるで城選手の頭部を診察でもするように、両手を城選手の耳の上あたりにあてがい城選手の目が泳いではいないか確かめたあと、下げていた頭を抱き寄せるように顔のあたりに近づけて何か語りかけたように見えました。
97.12.18Number433号で、この場面のことを聞いた金子達仁氏に対して中田選手は次のように答えています。
金子氏「城の頭を抱えて一生懸命何かを言ってたみたいだけど。」
中田選手「一生懸命じゃないですけどね。痛いか? って聞いたら痛いって言うから、大丈夫か? って聞いただけ。普通のことですよ。あと残り時間少ないから、がんばって1点取ってください。そんなかんじ。あれは、城も相当ハードにぶつかってるんです。」
中田選手は、そうして、しばし城選手のもとにいたあと、次に呂比須ワグナー選手のもとに歩みより何かを確認するような言葉をかけました。フジテレビの中継アナウンサーは、この光景については何もコメントせず、日本のここまでの戦いぶりを振り返る話をしていましたが、映像は、いま日本イレブンの中で誰がリーダーシップを発揮しているのかをはっきりと映し出していました。
こうして、瞬く間に12分が経過した時、相手ボールが右サイドに出て、受けたマハダビキアがここぞとばかりに40mほど疾走、ペナルティエリア手前からゴールを横切るクロスをあげると左サイトで待ち受けていたダエイに届きました。ついていた秋田選手が必死に食らいつくように身体を寄せようとしましたが間に合わず、ダエイの足が先にボールをとらえました。やられたっ!!! と思った瞬間でしたが、ボールはわずかにクロスバーの左上を越えて外れてくれました。秋田選手の陰からボールが来た形になり、ほんの僅かだけダエイ選手の反応が遅れたためでした。命拾いでした。
岡田監督も「もうダメだ」と思ったそうです。それが入らなかったことで「まだツキは残っている。攻め方も間違っていないはずだ」と確信を取り戻しました。
ピッチの中の中田英寿選手、これはまずいと思ったのでしょう。決まれば終わりの延長戦に入ってチャンスらしいチャンスのなかったイラン、一方の日本は再三チャンスを作りながらモノに出来ずにいたところで、たった1本のダエイのシュート、あれが入ってしまったらと思うと、背筋がぞっとするようなシーンでしたから、中田選手は「あぶない、もはや自分が決めに行かなくてはダメだ」と思ったに違いありません。
それがプレーにすぐ表れました。延長後半13分過ぎ、中盤で呂比須ワグナー選手がカットしたボールのすぐそばにいた中田選手、オレが持っていくとばかりにボールをキープしたのです。呂比須ワグナー選手からパスを受けたのではなく、明らかに自分でボールキープに行ったのです。そして、すぐ1回転しながらドリブルでキープすると、今度は前に持ち出すドリブルを始めました。さらに相手DF 2人に前を遮られると少し左側に持ち出し、ペナルティエリアの直前、相手ゴール正面まで運んで、コースが空いたと見るや左足でシュートを放ったのです。
(これが、その時のシュートの写真です)
この時、相手DF陣は6人、中田選手の右前方向に固まっていましたが、その中に岡野選手が一人、中田選手のドリブルを見ながらコースを空ける動きをしてDFをひきつけています。そして、オフサイドのない位置にいて、中田選手の放ったシュートに対応する姿勢もできていました。
中田選手の放ったボールはGKの右側、ちょうど岡野選手がフォローできる方向に飛びました。GKは横っ飛びでボールをはじきましたが、すでに走り始めていた岡野選手の目の前に転がったのです。
岡野選手は右足で狙いを定めるように小さくスライディングしてボールをヒットさせました。ボールはグラウンダーで見事にゴールネットに突き刺さりました。
この場面は日本サッカー史を変えた場面ですから、その後も幾度となリプレイされました。ここでは通常流れているフジテレビ・長坂哲夫アナウンサー、清水秀彦解説者コンビの実況を再現して記録に留めておきたいと思います。(動画をみながらお読みください)
【フジテレビの実況】
「おっと、呂比須が奪ったぁ、中田がキープ、まだ持っている、ドリブルであがる!! ドリブルであがる!! ひだり足しぃ~~!! どうかぁ~~!! こぼれているぅ~~!! (清水さんの絶叫)やったぁ~~~、 (長坂アナ)岡野ぉ~~~~!! 最後は岡野ぉ~~~~!! ニッポン勝ったぁ~~~!! ニッポン勝ったぁ~~~!! ワールドカップぅ~~~!! やったぁ~~~~!!(長坂アナ、声が裏返り気味) (清水さんあらためて言い聞かせるように絶叫)やったぁ~~~~!!、 勝ったぁ~~~!! ニッポン!! 1997年11月16日ぃ、マレーシア時間の11時35分、ついにワールドカップ出場を決めたぁ!! 」(動画をつけておきます)
中田選手はシュートを打った後、尻もちをつく姿勢のまま岡野選手のシュートを見守り、決まった瞬間を見届けました。
岡野選手はネットが揺れたと同時に立ち上がり、全力で走り出しました。しかし、向かった先はイランベンチの方向でした。走り出した瞬間は無我夢中といった表情でしたが、途中から気づいて、全力で駆け寄って来る日本ベンチの仲間たちに両手を広げ「やりましたぁ~~~」という表情に変わりました。ピッチにいたイレプンも我先に岡野選手めがけて走り出し、我先にと岡野選手に飛びつき、もみくちゃの輪ができました。
センターサークルのあたりで岡野選手のゴールを見届けた名波選手は歓喜の輪に加わろうと歩き出しました。そこに中田選手が歩み寄ってきました。中田選手は名波選手に抱きつくように喜びを表しました。
「コイツも喜ぶんだな」そう思いながら名波選手は祝福の輪に遅れまいと岡野選手めがけて走り出しました。中田選手は「やれやれ」といった表情を見せながら、岡野選手に群がる選手たちの輪に背を向けて歩き出していきました。
日本時間11月17日0時34分、現地時間の11月16日23時34分、ついに歴史が動きました。これはもうPK戦になるのか、日本中のサッカーファンがそう思い始めた延長後半13分の出来事でした。3-2延長Vゴール、日本が第3代表としてフランスW杯の出場権を獲得した瞬間でした。
試合は終了です。そこからテレビカメラは誰彼となく祝福し合う選手たちの表情と、スタンドを埋め尽くしたサポーター席を「ゴーッ」という地響きのような音とともに、交互に映し出しました。
試合後の取材は混乱を避けるため3段階(1.テレビ中継班、2.新聞・雑誌記者班、3.ニュース番組班)に分割して対応、翌日も選手宿舎での取材時間を設定、帰国後も記者会見を設定するなど万全の体制を敷きました。
岡田監督のインタビューが始まりました。インタビュアーはNHKの栗田晴行アナウンサーです。
岡田監督は開口一番、お辞儀をしながら「ありがとうございました。ボクら、皆さんの応援があって、初めてワールドカップに出れるようになりました。ありがとうございました。」
そして次の言葉も「何かボクら、感謝の気持ちしかありません。ボクらだけでこんなことはできなかったと思います。本当にありがとうございました。」と言って、また頭を下げました。
さらに「よく頑張ってくれた選手、3年間この基礎を作ってくださった加茂さん、ほんとにいろんな人に感謝の気持ちで一杯です。」
栗田アナが少し間を空けて「いま何か、ようやく実感が湧いてきたんじゃないですか?」と水を向けても「えぇ、でも、まだほんとにありがたいというだけです。」
Q.こんなに日本はワールドカップに行くのに苦しまなければいけないんでしょうか?
A.「えぇ、それだけのことはあると思います。そんなにワールドカップのハードルは低くないと思います。」
Q.岡田監督も急遽、就任することになって1ケ月半、この1ケ月半は岡田監督にとってどんな1ケ月半でしたか?
A.「ほんとに孤独な1ケ月半でしたけれども、まぁ、辛い時も、いつもボクを信じて励ましてくれた家族がいたのが、ホントに支えでした。」
Q.一時はフランスの道が遠ざかった時期もありました。それを立て直すことができた。一番の要因はどんなところにあると思いますか?
A.「それは、やはり選手が、最後まで頑張ろう、チャンスが残っている限り頑張ろうという気持ちで頑張ってくれたこと、そして、それをサポートしてくれたスタッフ、みんなのおかげだと思っています。」
Q.岡田監督のお話しを伺っている中で「気力」だとか「前へ行こう」だとか、精神面のお話しをよくされていましたね。
A.「いゃ~ぁ、ボクはそんな精神主義者じゃないんですけどぉ。でも、最後、必要なのは戦う気持ちがないと勝てないと思ったもんですから。」
Q.最後にあらためてワールドカップ出場を決めたお気持ちお聞かせください。
A.「いゃ~ぁ、ホント、感謝の二文字です。ありがとうございました。」
続いてすぐ岡野雅行選手のインタビューが始まりました。
Q見事なゴールでした。
A.「いゃ、もう外しまくってたんで、絶対1点入れてやろうと思って。(一呼吸して) よかったです。」
Q.最後の最後に決めてくれましたね。
A.「なかなか出番もなかったし、一番疲れてなかったんで、ボクがみんなの分動いてあげようと思ってね。」
Q.疲れていなかったとはいえね、逆にストレスも一杯あったと思うんです。
A.「結構ありましたけど、皆んな頑張ってたんで、一つになって、これで結果が出たんで。」
Q.これでワールドカップですよ。
A.「そうですね、まだ信じられないっすけど」
Q.大勢のサポーターそして日本でテレビの前の大勢のサポーターが期待していたと思います。皆さんに一言。
A.「そうですね、皆さん、いつも応援ありがとうございました。皆んなの力でフランスに行けたと思います。これからもフランスに向けて皆んなで頑張りましょう。」
中田英寿選手がフジテレビピッチサイドレポーターのインタビューに応じました。
Q.どうですか?、ワールドカップ行きを決めて。
A.「いやぁ、もう練習したくないんで、よかったです。」
Q.今日の試合、苦しかったんじゃないですか?
A.「決めるところ決めないとね。きついんで。また、そこを練習して頑張りたいと思います」
Q.あなたは、これで世界の檜舞台に一歩一歩、完璧にステップアップしてますよね?
A.「まぁ、偶然」
Q.新しいワールドカップ出場という日本サッカー界の歴史、あなたの力で開いたという気もするんですが?
A.「ボク一人でやったわけじゃないんで、でも点とれてよかったです。」
Q. Vゴール決まった瞬間、見ててどんな感じだったですか?
A.「まぁ、やっと決めてくれたか、って思いました。」
Q. その前に、岡野クンに決めて欲しかったかな?。
A.「まぁオカだけじゃないし、みんな決めるチャンスありましたからね。・・・(リプレー映像の大歓声の音で聞き取れず)」
Q.日本で見てくれてるサポーターの皆さんに一言お願いします。
A.「まぁ、代表はうまく盛り上がったんで、あとはJリーグをどうにか、盛り上げてくださぁい。よろしくお願いしまぁ~す。」
この日マレーシアに入った報道陣は294人、ラルキン・スタジアムには記者席がなかったため急遽・仮設のテーブルを設置、それでも100人以上は記者席に座れませんでしだか、試合後は、その報道陣もピッチに降り立ち選手たちを取り囲みました。
そして試合終了から20分ほど過ぎた頃、大勢のカメラの放列の前で選手・スタッフが全員で勝利の雄たけびをあげました。
そして選手たちがサポーター席のほうに向かうと、スタンドのニッポンコールは、いつまでもジョホールバルの夜に響き渡りました。まさに「ジョホールバルの歓喜」の夜となりました。
W杯アジア予選という長い道のり、「ドーハの悲劇」を乗り越えたとはいえ、選手たちにとって過酷な苦しみの連続でした。
何度も崖っぷちに立たされて襲ってくる絶望感、メディアやサポーターからの狂気のような期待という重圧、チーム内の意思疎通の不足からくる不信感、相手チーム選手との激突で生ずる身体的苦痛と疲労。
ですから、ロッカールームに戻ったイレブンは、歓喜に湧くスタンドの声をよそに、まるで負けたチームのように皆んな頭からタオルをかぶったままシーンとしていたそうです。疲労困憊、やっと戦争が終わった、やっと重圧から解放された。もうたくさん。出てくるのはため息ばかり、そんな空気が支配していたロッカールームだったそうです。
日本代表としてワールドカップ予選を戦い勝ち抜くことの難しさ、大変さ、過酷さを極限まで思い知らされた選手たちが、苦難の果てに辿り着き解放された夜のロッカールームでした。
ホテルに戻った選手たちを、同じようにスタジアムから移動してきた大勢のサポーターたちが出迎えてくれて、選手たちの顔にもやっと明るさが戻ってきました。
バスを降りてホテルに入ろうとした選手の列に、一人の女性が名波浩選手を見つけて手を差し伸べながら「ごめんね、うちの子が迷惑かけちゃって」と声をかけました。
岡野雅行選手のお母さんでした。岡野選手のお母さんは、最終予選のすべての行程を、中東から中央アジア、韓国、そしてマレーシアと、まるで帯同スタッフのように応援を続けていて、選手たちにも「岡野ママ」として知られていましたし、名波選手とは岡野選手が特に仲の良い間柄でしたから、家族に声をかけるような気安さだったのです。
勝手知ったるお母さんからの言葉でしたから、名波選手も笑い顔で「本当だよ、もう・・・」と忖度なしに返すと、周囲が小さく湧きました。誰しもが味わった苦難と感動をあらためて共有する一コマでした。
ホテルに入ってからも生気は戻らない選手たちを労おうと岡田監督が「崖っぷちの状況から諦めず戦った君たちは本当に凄い、今日は大いに飲もう」とシャンパンを威勢よく空けたまではよかったのですが、精も魂も尽き果てた選手たちは、とても夜通し飲み明かそうという力が残っておらず、早々にお開きになってしまいました。
部屋に戻った岡田監督は、まず自分に後を託してくれた加茂さんに電話を入れました。受話器の向こうからは「良かった。帰ってきたら、ゆっくりメシでも食おう」。短い言葉でしたが、加茂前監督らしいの心からの労いでした。
岡田監督が試合直後にNHKのインタビューに答えた内容はすでに紹介しましたが、その後あらためて開かれた会見では次のように語っています。いい話ですので、これも記録に留めたいと思います。
「加茂さんが土を耕し、種を蒔き、大切に育ててきたチームです。でも収穫の秋の前に、二つの台風が来て加茂さんは吹き飛ばされてしまいました。韓国台風と、カザフスタン台風です。私は実った収穫を刈り取るだけでした。選手たちはしっかりと根を生やしていました。」
ここで、幾つかの点について、もう少し踏み込んだ記録を残したいと思います。
一つは、突然の加茂監督更迭、岡田コーチ昇格という日本サッカー協会の対応に対して、サッカージャーナリスト等専門家は、どういう見解を示していたのか、拾い出しておきます。
最終的には「ワールドカップ出場権」というミッションを果たした訳ですから「終わりよければ全てよし」と考えれば、突然の監督交代の直後にいろいろ出た見解をあげてみたところで「もう終わったことだから、いいじゃないか」という指摘も出そうですが、それでは日本サッカーの発展のためにはならないわけで、しっかりと後世に伝えたいと思います。
検証.1 最終予選は「加茂監督で十分戦える」という評価だったのか、そうではなかったのか? あのタイミングで交代することになった理由は何だったのか?
最初の検証事項は、そもそも加茂監督にアジア最終予選の指揮を託すこと自体、間違いではなかったのでしょうか、それとも、更迭に踏み切ったあの段階での交代がベストの選択だったのでしょうか。加茂監督の何が問題だったのでしょうか、結局、サッカー協会がカブフスタン戦まで加茂監督を引っ張った理由はなんだったのでしょうか。日本サッカー協会は何を教訓とすべきなのでしょうか、という視点で検証してみます。
まず、1997年を迎えた時点での加茂ジャパンには、どのような評価と課題が指摘されていたのでしょうか?
この年の始めは、ちょうど前年12月に行なわれたアジアカップで日本が準々決勝で敗退した直後であり、その総括の時期となりました。
そこで加茂ジャパンに指摘された課題は二つありました。一つは、アジア勢との戦いを勝ち抜く好守両面の戦術的課題でした。具体的には引いて守りを固めカウンターアタックを仕掛けてくるアジア勢の戦いに対処できず敗れたことに対してどう解決策を見出していくかという課題でした。
もう一つは、加茂監督がレギュラーとして決めた選手にこだわり過ぎ、バックアップ選手のテスト機会が少ないため選手層がまったく厚くなっていないという課題でした。加茂監督はよく「代表チームは選手を育てる場ではない」というが、選手層を厚くするためには真剣勝負の実戦で使っていくしかなく、それによるチームの底上げなくして過酷な最終予選のような長丁場は乗り切れないという課題でした。
特に「サッカーダイジェスト」誌はアジアカップ後、2週にわたって特集を組み、2週目の97.1.22号では戸塚啓氏による緊急提言「日本代表は大丈夫か?」で「このままでは予選突破は危ない」と警鐘を鳴らしていました。
こうした課題を直接加茂監督にぶつけたのが97.2.13Number411号でした。サッカージャーナリストの永井洋一氏の質問に対して加茂監督が次のように答えています。
永井 昨年暮れのアジアカップで、初戦のシリアに失点して、その後引いて戦われました。中国もそうでした。「こうなったらどうするのか」と言われていたことばかり突き付けられたような状況でしたが。
加茂 う~ん、そんなに深刻ではなくて、プレスをノーマルな形でやれる自信はチームとしては付いているわけで、そこからのバリエーションということだから。相手がすごく攻撃的に出てきたらどうするかとか、極端に守備的になったらどうするかとか、まあ、シリアは1点取った途端に守備的になったからね。そういうバリエーションを試せたという意味では、いい経験ができたと思っている。(中略)
相手に自陣深く引かれた時は、片方のサイドにボールを持って行って相手を引きつけ、サイドチェンジで逆サイドに持っていって素早くスピードを上げる。そうしないと、すぐにまた同じ形で守備を整えられてしまう。アジアカップではその繰り返しになってしまった。
だから全体的には「こういう格好になったら、効率のいいサイドチェンジをしないと崩れないぞ」という意識が足りなかったともいえる。決定力のなさでやられてしまったけれど、ジャーナリストが書いているようなショックはこっちは受けていない。
永井 巷で言われているように、日本のゾーンプレスが研究されて、それを打ち破る戦法としてロングボールを使ってきたのとは違いますよね。
加茂 違う。向こうも深いところへボールを入れておいて、全体にギュッと押し上げといて、こっちがつなぎ始めたらパッと突っかかって取ろうと思っている。日本の場合、つないでくるチームには100%ぐらいの確率で勝てる。だけどゾーンを嫌がって蹴ってくる相手に対しては、ちょっとしたミスが5~6回のうち一つは致命的なピンチになる。逆にそれを守り切れば勝てるわけで、大きなミスは必ず起こってくるわけだけれど、それを直せばさほど致命的にやられはしないよ。
永井 さてこれから限られた時間でチームをピークに近づけていくわけですが、これまでのように戦術理解に時間を割かれるのですか。
加茂 それほど時間を割いてないよ。コンディションを整えるほうが先。コンディションが良くなかったら何もできないからね。代表は集まってコンディションを整えることに八割方の力使っている。だから、すごく単純な戦術、覚えやすい戦術でやっているわけ。逆に一人違うことをやられると崩れてしまう。
実は、今でもすごく魅力がある(選手で)、時間があったらこいつは絶対に欲しいという選手が3人はいる。(中略)だけと、今の代表では難しい。
永井 与えられた時間が限られていますからね。
加茂 うん。勝手なことをやられると、バランスが崩れてしまう。11人の人間が同じ考えで、それぞれの役割を100%やろうとすることでチームがまとまって力が出てくる。けれど、たった1人でも違う考え方でグラウンドに立っていると、チーム力はすぐ70%とか80%になってしまう。
これが単独チームだと、選手と話す時間も山ほどある。練習もできるんだけれど、代表では非常に難しい。多分どこの国もそうなんだろうけれど、よっぽど飛び抜けた選手がいれば、例えばマラドーナがいれば簡単。マラドーナがやりやすいようにチームを作ればいい。(中略)
永井 残念ながら日本にはそういう能力を持った選手はいない。
加茂 だから日本はチームが大事。一つのやり方の中で自分の役割をはっきり認識してプレーする。与えられた仕事を、難しいけれど100%やろうとすることで、チームのパワーが上がってくるということだと思う。
以上が97.2.13Number411号での永井洋一氏との一問一答の抜粋です。これを読むと、加茂監督がレギュラーとして決めた選手にこだわり過ぎているのは、自分の考え方を十分にわかっていない選手は使えないし、教えている暇もないから、自然と使う選手が限られてくるという考えかよくわかります。だからバックアップ選手が育たないのも仕方がないという理屈になっていたのでしょうか。
また、引いて守りを固めカウンターアタックを仕掛けてくるアジア勢の戦いに対処できず敗れたことに対する解決策についても、サイドチェンジのスピードをあげ、効率のいいサイドチェンジを繰り返せば大丈夫だとわかっているから、ジャーナリストが書いているようなショックはこっちは受けていない、ということのようでした。
韓国はアジアカップで日本と同様に準々決勝で敗退したため監督が更迭されましたが、日本は一次予選が迫っている中での監督交代は、チーム作りの面でリスクが大きく得策ではないと見る向きがありました。
しかし、どちらかと言うと「日本サッカー協会はアジアカップの成績に関係なく加茂監督でアジア予選を戦うことに決めている」というのが専門家の一致した見方でした。
実は加茂監督、12月のアジアカップの際、倒れるという出来事がありました。すわ体調不安か? と取り沙汰されましたが、その部分が大きくクローズアップされることはありませんでした。
そして3月、アジア一次予選オマーンラウンドの3試合に臨んだわけですが、最大の敵オマーンに1-0で勝ち3連勝という結果は出したものの、引いて守りを固めてくる相手の攻略法や、さまざまな能力を持つ選手たちを組み合わせて攻めに厚みを持たせるといった監督の工夫がなく、常連の選手たちも新しく入った選手たちも、臨機応変の動きや個性の発揮といったアクションが乏しいとの指摘が出されました。
特にオマーンラウンドに招集された前園真聖選手に至っては一度もピッチに立つことなく、能力の見せどころすらありませんでした。
6月に行なわれた日本ラウンドでは、そのオマーンと引き分けに終わってしまい、最終予選への進出は決めたものの、国立競技場のサポーターからはブーイングを浴び、年初来指摘されていた課題が何一つ解決されていないことを示してしまったのです。
アジア一次予選終了から最終予選の初戦ウズベキスタン戦までの間の行なわれた日本代表の試合は2試合、8月13日のブラジル戦と、8月27日のJOMO CUP97 Jリーグ外国籍選抜戦の2試合で、いずれも日本代表は無得点のまま終わっており、攻撃の工夫のなさに対する批判は高まるばかりになっていたのです。
ですから、そのことは選手たち自身も承知していて、守備陣、中盤、攻撃陣とも何か引っ掛かるものを感じつつ、チーム全体として決して自信に溢れた一体感に満ちた状態ではなかったのです。
この加茂監督のチーム作りについては、日本サッカー協会の中で、少なくとも強化委員会レベルでは口には出さずとも満足していなかったであろうことは疑いの余地がありません。
マスコミ等の表には出ていませんでしたが、強化委員会レベルでは5月21日の日韓W杯記念・韓国戦にもし負けた場合は長沼会長に監督交代を進言する意思を固めていました。しかし、この試合、代表デビューの中田英寿選手の活躍もあり引き分けで終わったことから進言に至らなかった経緯があります。
すでに最終予選を前にして、強化委員会としては、一旦緩急あれば対応策が必要だろうというところまで煮詰まっていたのです。だからこそ、3戦目の韓国戦に敗れた時点で強化委員会が集まって川淵副会長のところに談判に行くという対応に繋がったのです。
いよいよ最終予選を迎える段階になると、日頃舌鋒鋭いサッカージャーナリストたちも、もはや筆を投げた状態になっています。
97.9.25Number誌427号には、初戦のウズベキスタン戦をレポートした金子達仁氏が、冒頭に面白いことを書いています。
「実は先日、セルジオ越後氏とこんな話をしたばかりだったのだ。『なぁ、カネコ、最終予選が始まったら、オレはもう代表について辛口するの、よすよ。こっちがよかれと思って言ったことでも、向こうは単なる悪口としか受け取ってないみたいだしな。それに加茂サンは、ちょっとつつかれるとすぐナーバスになっちゃうみたいだし』
私は深くうなずき、同時に決心した。加茂監督の批判はもうすまい。そもそも、こっちは日本のタレントをもってすれば、加茂体制でもフランスに行ける可能性は十分にある、ただ、もっと可能性を高くすることもできる、と言っているだけなのに、やれ誹謗中傷だの非国民だのご都合主義だのと罵られるのも馬鹿らしいではないですか。すごいのになると、加茂体制でフランスに行ったらお前はどうやって責任をとるんだ、なんてご意見までありましたからね。
もう疲れました。・・・」
最終予選初戦ウズベキスタン戦での6ゴールという爆発は、日本代表が超満員のサポーターの暖かい応援という後押しさえあれば、十分持てるものを発揮できることを証明してみせたものの、それが逆に「加茂ジャパンは大丈夫だ」という根拠のない期待を一時的に抱かせた、幻惑にも似た試合だったと言えるのです。
結局、加茂監督では最終予選は厳しいのではないかという意見がサッカージャーナリストたちを中心に相当大きかったにも拘わらず、日本サッカー協会はそうして外部の意見を黙殺したまま最終予選に突入したわけですが、それもこれも最終的な決定権者である長沼会長が加茂監督でいいと考えているうちは、手が出せなかったというのが実態なのでしょう。
それでも第3戦の韓国戦に敗れた時、強化委員会メンバーが集まり「このままではまずい」という認識を強めたことで、次何かあれば、いよいよもって長沼会長に決断を迫るところまで来たのです。
「政治は結果責任」とよく言いますが4戦目のカザフスタン戦の引き分けの時点で加茂監督更迭に踏み切ったという措置は、遅きに失することがなかったという結果となりました。
それにしても長沼会長は1994年のファルカン更迭以降、約3年間、加茂監督の後ろ盾になり続けました。結局、この時まで日本代表監督というのは、時のボスの恣意的な選択で据えられ続けたわけです。
このファルカン時代も含めた日本サッカー協会の対応について「ドーハ以来、実に4年もの時間を無駄遣いした」と鋭く批判するジャーナリストもいたほどです。
サッカーダイジェスト誌は98.1.7/14合併号の中で「この歴史的な監督交代は、大げさに聞こえるかもしれないが世論の力によって生まれたといっていい。かつてないほど注目を集めたワールドカップ予選で、日本代表は間違いなく国民のチームになっていた。(中略)『戦いの最中に棟梁を代えるのは・・・』と加茂体制に固執していた長沼会長が、更迭の断を下したのは、こうした強い働きかけ(注・メディアを通じてなされた強い世論の声)があったからである。サッカー界における”歴史的な”前進と言っていいだろう。(以下略)」
今回のような事態を招いてしまった恣意的な選択や決定が、その後の日本サッカー協会では繰り返されなくなったかと言えば、それは「否」であることは歴史が証明していますから、この1997年秋の教訓がちっとも活かされていないわけです。
このように、歴史の分岐点になるような出来事の時、いつも日本サッカー協会は、幹部の認識の甘さや個人商店的体質が顔を出してしまうところがあり、この1997年になっても、それは少しも改善されていないことがわかったと書き残しておきたいと思います。
前述のサッカーダイジェスト誌は98.1.7/14合併号は、こうも指摘しています。「周囲の劇的な変化にも関わらず、(協会)トップは相変わらず不動、不変である。重要な懸案が密室で決まっているのだ。日本社会そのままである。すべてが変わったというには、やはりまだ早いし、物足りない。」
加茂監督は岡田コーチをなぜコーチに選んだのか? 何年か後に自分の後任になることを予感して選んだのか? まったく予感などしていなかったのか
こうして加茂監督更迭のカウントダウンが始まるわけですが、そのあと後任として、突如表舞台に登場するのが岡田コーチです。
では、そもそも岡田コーチという人は、どういういきさつで加茂監督のコーチになったのでしょうか? 加茂監督は岡田コーチのどういう能力に期待してコーチにしたのでしょうか? 何年か後に自分の後任になることを予感して選んでいたのでしょうか? それとも、まったく予感などしていなかったのでしょうか?
加茂監督は、岡田武史氏をコーチに選任した時のことについて、加茂氏が自身の著書「モダンサッカーへの挑戦」(1997年3月講談社文庫版)の著者あとがきの中でこう書いています。
「日本代表の仕事で忘れてならないのが、スタッフの優秀さとチームワークだ。(中略)私がまず選任したのは岡田武史コーチだった。若く、単独チームを率いてJリーグなどのクラブで監督をした経験はないが、非常にクレバーで、人間的にも素晴らしい。ある時期まで、私は選手と個人的に深く関わらないようにしてきた。次々と選手を入れ替えなければならない時期に、情が移ってはいけないからだ。その分、岡田コーチには、細かくフォローしてもらわなければならなかった」
また1998.3.15サンデー毎日に掲載された「解任直後、岡田君と約束したこと」で加茂前監督はインタビューにこう答えています。
「(岡田君は)非常によく勉強している人で、(中略)現役引退後も、すぐに家族を連れて1年間、ドイツに勉強に行っています。個人的にはそんなに付き合いはなかったんですが、彼が中学生の頃、私の弟がやっていた店(注・加茂サッカーショップ)にしょっちゅう来ていたそうで、弟からよく聞いていたんです。いろんな人の評判も聞いて、最終的に(岡田氏をコーチに)決めたんです。」
「(コーチ時代の岡田氏は)これだという活躍は特にないんですが、彼の持ち味は意思が強く、物事から絶対に逃げないこと。はじめの頃は彼も若いですから、非常にホットで熱くなりやすい性格でしたが、いろいろ経験して、次第に抑えられるようになりました。」
これらを読むと、まさに岡田さんは加茂監督に「選手との間に立って役割を果たしてもらうコーチとしての適性」を評価して選任したことがわかります。
決して、監督としての決断力や戦略家の適性を見て選任したのではないようです。その人が、よもや3年後に、自分の後任として日本代表を、しかも、これまで、どのカテゴリーの監督経験もない岡田コーチに託すことになろうとは、夢だに思っていなかったということだと思います。
検証.2 カザフスタン戦後の加茂更迭・岡田昇格に、日本サッカー協会は、どれほどの成算があったのか?
次の検証事項ですが、3戦目のホーム韓国戦に敗れた加茂ジャパンについて、日本サッカー協会強化委員会メンバーが急遽集まり協議、そして第4戦目のアウェー・カザフスタン戦に勝てず引き分けたことから、急遽、加茂監督更迭、岡田コーチ昇格という荒療治に踏み切った日本サッカー協会には、どれほどの成算があってのことだったのかについてです。
結果よければすべてよしで済まされる話なのか、そうではないはず、という視点で検証してみます。
このカザフスタン戦までの間に、サッカージャーナリストを中心に専門家は「加茂監督ではとても最終予選を乗り切れない」という指摘を続けていたにも関らず、日本サッカー協会強化委員会は、まったく動いていませんでした。
それもこれもボスである長沼会長が「加茂のままでいい」と考えていることが明白でしたから動くに動けないということだったと言えます。
ただ、強化委員会は、アジア最終予選が始まる前(9/7以前)に「最終予選のさなかに監督交代の緊急事態が起きた場合には岡田コーチを昇格させる」ことを決めていたとする資料があります。このことが、事前に公表されていた資料は見当たりませんでしたが、後年、サッカーマガジン誌が「特別編集」企画で出版した「サッカー日本代表・世界への挑戦1991~2010」(ベースボールマガジン社2010年8月2011年1月、10分冊刊)の1997年の項での「エピソード」欄に、そのように記述されています。
この資料が伝える「岡田コーチ昇格案」が、どの程度の可能性を想定したものだったのか、気になるところですが、強化委員会レベルでは5月21日の日韓W杯記念・韓国戦にもし負けた場合は長沼会長に監督交代を進言する意思を固めていたことからすると、結構、加茂監督では厳しいというのが現実味を帯びた判断から「岡田コーチ昇格案」を腹案として持ち続けていたということになります。
つまり、強化委員会はトータルに考えて「加茂監督では厳しい」と見切っていたけれど、正面切って、それは言えない、なぜなら、それは会長専権事項だから。
したがって、他の候補者にも接触できないし、そういう気持ちをおくびにも出せない。けれども、もし、その時が来たらスムーズに交代を完了させなければならない。そうするには「岡田コーチ昇格案」しかない、ということになります。
強化委員会が、なぜ、どのカテゴリーの監督経験もない岡田コーチの昇格案を腹案として持ったのか、そこがよくわかりません。水面下で他の候補者に接触することなく、いざという時の「岡田コーチ昇格」案が、かなりの確信を持った腹案だったとすると「なぜ、岡田コーチなのか」という疑問は残ります。
そうして始まったアジア最終予選、さすがの強化委員会も第3戦のホーム韓国戦の逆転負けを見て「このままではまずい」という危機感を持ちます。結局「加茂監督ではダメです」と進言するタイミングを得たということであり「じぁあ、次誰に・・・」となった場合に、言える名前は「岡田コーチ」だったのです。
そして、カザフスタン戦の引き分けで、長沼会長に「加茂監督ではダメです」と進言するタイミングを得て、それを長沼会長も受け入れるしかない状況になり「加茂は更迭」は決まりました。では次は? となった場合、選択肢は岡田コーチ昇格しかないことは誰の目にも明らかです。成算があったとか、なかったというレベルの話ではなく、そうするしか手がない対応だったというこどなります。
協会は、自分たちが「岡田にする」という決断を下さずに、大仁強化委員長に「あとは誰にする?」と聞いています。大仁強化委員長とて「岡田コーチでいきましょう」と答えるしか選択肢がありません。そもそも誰かを日本からカザフスタンなりウズベキスタンに呼ぶにしても入国ビザの問題があり手続き的に不可能でしたし、監督不在のまま試合に臨むわけにはいきませんが、大仁強化委員長としては岡田コーチ昇格が既定路線ということになります。
岡田コーチの昇格が決まります。
これで、日本サッカー協会は、仮に岡田コーチ昇格でW杯出場を逃しても「強化委員会が岡田コーチを推薦したので従ったまで」と逃げ道を作った形です。
突然「監督をやれ」と言われた岡田氏は、これまで大仁強化委員長から「岡田昇格案」を露ほども聞かされていなかったと見えて「いきなりそんなことを言われても・・・。少し考えさせてください。」と留保します。
しかし「日本からは手続き的に呼べない、監督不在にはできない」と言われれば、押し黙るしかなくなります。
そして最後に、加茂監督から「お前がやるしかないんだ」と言われ「わかりました。ウズベキスタン戦はやらせていただきます。」と答えたのです。その時、岡田コーチはこうも付け加えています。
「ウズベキスタン戦に負けたら、次は引き受け手がいないと思うので、続けて最後までやります。でも勝ったら、この1試合で終わります。協会が次の人を見つけてください。」
この1試合云々の話について、聞いていた加茂前監督は、前述のサンデー毎日のインタビューでこう解説しています。
「結局、彼も私と一緒に責任をとりたいという考えだったんですよ。」
日本サッカー協会にしても強化委員会にしても「監督を交代させるにあたって、どんな成算があったのか」。強いてあげるとすれば、それは「トップの交代による戦い方の変化、そして危機感を持った選手の奮起、つまりは流れが変わること」を期待したというしかないのです。
この日本サッカー協会の荒療治に一つ評価すべき点があるとすれば、あくまで「結果論」ですが「遅きに失した対応ではなかった。ことと次第によってはうまく乗り切れる可能性を残した対応だった」という点です。繰り返しますが、あくまで「結果論」です
それでも、大方のサッカージャーナリストたちの舌鋒は「遅きに失した対応」「ドーハ以後のムダな3年間」と鋭く辛辣なものでした。
そして「加茂がダメなら自分が責任をとる」と言っていた長沼会長の責任はどうなるんだ、と付け加えることも忘れませんでした。
ここで究極の疑問が一つ残ります。さきほど、後年の資料には「最終予選のさなかに監督交代の緊急事態が起きた場合には岡田コーチを昇格させることを決めていた」とありましたが、大仁強化委員長は、その腹案を岡田コーチには伝えてはいなかったのでしょうか。これも、最終的には大仁強化委員長と岡田氏に語っていただく必要がありそうです。
検証.3 岡田監督が成功した要因は何か、論理的に説明のつく要因はあったのか
岡田監督になって最初の試合であるアウェー・ウズベキスタン戦は、1-0とリードされたまま試合が終わろうかという間際、最後尾から放った井原選手のロングフィードが呂比須ワグナー選手の頭に合い、そばにいたカズ・三浦知良選手の動きに幻惑された相手GKの判断ミスを誘って同点に追いつくという、まさに崖っぷちに踏みとどまる試合だったわけです。
そして、続くホームのUAE戦こそは、と期待されたものの、ここでも勝ち切れず引き分けで、試合後のサポーターの大暴走を引き起こしてしまったわけです。
しかし、カザフスタン戦のあと就任した岡田監督のウズベキスタン戦までの6日間は、実は理にかなった6日間だったと言えます。
この期間、岡田監督が行なったことと、その狙いを列挙してみます。
・「今日からは自分が監督である。自分が指揮を執ることに不満がある者がいれば、この場を去ってほしい」と話し、これまでコーチとしてオカちゃんと呼ばれ兄貴分の立場だった自分だが、それをそのまま持ち込むことは許さない。選手が意識を変えるよう、練習中の私語を禁止するなど、何人かの選手にはカミナリも落し震え上がらせたこと。
これについて岡田監督は、1997.12.17サッカーマガジン誌に寄せた「独占手記-その2」の中で「ぼくが常々思っているのは『サッカーに正解はない』ということで、それぞれが次の場面について選択することは間違いではない。だからと言って全員がてんでバラバラなことをやりり出したらサッカーにならない。だから監督であるおれがそれを決める。それに不満があるというなら出ていってくれという意味で言った。規律については、監督が代わっても何も変わらないということだと気持ちを切り替えられない。加茂さんが辞めさせられたというショックから気持ちを切り替えてもらうために規律の徹底という方法をとった。」と語っています。
・一方で、選手の意識をポジティブに戻すことに心を砕いたといいます。これまでの戦いだって選手に大きな問題はない、要は攻めの気持ち、自分たちはやれるんだというポジティブな気持ちを取り戻させ、得点を取りにいかなければならない時は、決定機を多く作ることが大事だと、その点を重視した練習と選手起用を行なった。
これについても前述の1997.12.17サッカーマガジン誌の中で「ぼくが確信を持っていたのは、日本はアジアのベスト5の力を持っている、ということでした。サウジ、カタール、韓国、イラクそして日本です。同じ組には韓国しかいない。他の国より日本は絶対上だ。あれもダメ、これもダメと不安になるな、修正すべてところを修正すれば問題ないんだ。これはアジア一次予選の時にもぼくが全選手に対して言い聞かせたことで、それを思い出してもらって自信を取り戻してもらいたかった。」と語っています。
・「ファイトしないヤツは使わない」という考えの具体的姿勢としてウズベキスタン戦で中田英寿選手をスタメンから外した。これは、中田英寿選手にそういう態度が見られたため外したのではなく、ある意味、一番若いヤツならチームの士気の面でも影響が少ないと思ってのことだと思います。
岡田監督にしてみれば、中田選手が攻撃のキーマンだということは十分すぎるほどわかっていましたし、現に日本がリードを許した後半8分には中田選手をピッチに送り込んでいます。
むしろ「ファイトしないヤツは使わない」という話が本気なんだと選手に自覚させる意味では、もはや中心人物になりつつある中田選手も例外ではないんだと見せたことの効果を狙ったのだと思います。
カザフスタン戦後の加茂監督更迭・岡田コーチ昇格が、サッカージャーナリストをはじめとした専門家たちに、そのまま受け入れられたわけではありませんでした。
次のウズベキスタン戦の指揮を岡田監督が引き受けたものの、1戦限定、そのあとは白紙とメディアに語っていたこともありますが、それ以上に、これまで、どのカテゴリーの監督も経験していない人を、いきなり代表監督に据えるのは考えられない対応でありウズベキスタン戦が終わって日本に戻ってきた段階で、あらためてどういう指導体制にするか当然検討されるはず、という見方が大方の専門家の考えでした。
ところが、加茂監督を支え続けた長沼会長という重しが外れたにも関らず、大仁強化委員長のほうは「加茂監督を代えることが最重要なので、後任としての岡田監督がベストの人材だと思っています。」と岡田監督の経験のなさなど何の問題もないという見解を示したのでした。
唯々諾々と引き受けることを潔しとせず、筋を通しながら全権委任を取り付けた、岡田監督渾身の10日間
この1戦限定、その後は白紙と伝えられた岡田監督の胸のうちについて、鋭く指摘したサッカージャーナリストがいます。増島みどり氏がその人で、増島氏は97.10.29サッカーダイジャスト誌に次のようなレポートを寄稿しています。
「岡田監督は、午前練習が休みとなった10月10日、タシケントにいた日本サッカー協会幹部、長沼会長、川淵副会長、大仁強化委員長、今西委員と宿泊していたホテルで、ウズベキスタン戦以降のことについて、最終的な話し合いの場を持った。」
「話し合いの席で岡田監督は『加茂監督を選んだのは、日本協会で、協会が加茂監督に更迭を言い渡すのは仕方がない。しかし、私を選んだのは協会ではなく加茂監督です。協会からの続投要請を受ける前に、加茂さんの了解なしに引き受けることは絶対にできない』と、強い口調で切り出したという。」
「10月4日に加茂監督の後を引き継いだ岡田監督は、報道陣に対して再三『(11日の試合・ウズベキスタン戦が)終わったら、けじめをつける』と繰り返し、その言葉のみが『辞める』という意味に転じて一人歩きした感があった。」
「しかし、岡田監督の言う『けじめ』とは4日以来、終始一貫、加茂前監督へのけじめ、ただ1点だけを指していた。」
「あくまでも筋を通そうとする岡田監督の態度は、予選4試合を経過し、しかも遠征途中で監督を更迭するという協会の判断の矛盾をつくものであり、さらに言えばささやかな抵抗ともとれる。」
「4日以来、強化委員会、幹部会ともに中央アジアから動かず、練習に通い続けた。これは、岡田監督の説得と体制づくりに全力を尽くすという気持ちを示すもので、同時に、外国人の大物監督の招聘や、日本人監督という新しい交渉は行なわれていない、ということも示していたはずである。」
「(加茂監督更迭以降の)この10日間、すべての主導権を握り続けていたのは、幹部会でも強化委員会でもなく、岡田監督であった。」
「協会の判断を安易に受け入れずに、いわば『仁義を切る』的な筋論にこだわった態度は、すべてが中途半端だった中央アジア遠征の中では、唯一、説得力を持つ行動だった。」
(中略)
「岡田監督は(タシケントから)帰国する12日の朝、『こんなに厳しく大変だった1週間はこれまでなかった。と、同時に、これほど充実した1週間もなかった。選手には本当に感謝したい』と話していた。」
(中略)
「12日朝、川淵副会長の部屋を数人の選手が訪れた。副会長によれば『岡田監督を1試合だけで解任しないで欲しい』と、直訴に来たという。」
この増島氏のレポートが教えてくれているのは、
・協会側が加茂監督更迭・岡田コーチ昇格を決めた時点で「このあとは岡田でいくしかない」と、他の選択肢は用意しようとしなかったこと。そして毎日練習場に足を運び「協会はウズベキ以降もキミに任せるつもりだ」という意思を態度で示していたということ。
・岡田監督は、10月10日のタシケントでの協会幹部との打ち合わせで「協会がウズベキのあとも『自分に』と考えているとしても、自分は加茂監督から指名されて1試合だけ指揮をとる条件で引き受けている身だから、帰国したら、あらためて加茂監督に報告してけじめをつける」と語っているが、これは、帰国後に続投できる状況(加茂氏からの後押しがある)なら続けるが、最終結論はあくまで帰国後のこととして、加茂氏との面会後という条件付きではあるものの『続投の意向を伝えた』ということ。
・そして、ウズベキスタン戦(10月11日)後、ロッカールームで絶望に打ちひしがれている選手たちを見て「このまま見捨てて辞めるわけにはいかない」と、続投の意思は揺るぎないものになったものの、協会から続投要請を唯々諾々として受けるつもりは毛頭なく、加茂前監督へのけじめという筋論を前面に出しながら、全権委任という主体性をもった監督として続投要請されるよう、時間をかけたということ。
以上の3点だと思います。
こうした経緯を知ると、岡田武史氏という人物の深謀遠慮ぶりがよく出ていて、なかなかの人物だなぁ、と思います。この部分は、試合をどう勝ち抜くかという監督=指揮官としての資質とはまた別の人間的資質を見る思いです。
ちなみに岡田監督は、引き継いだあともジャージーを着たままというスタイルを変えませんでしたが、これは仕えていた監督を解任した日本サッカー協会への抗議の意思の表れだとするメディアもありました。
一方、専門家たちの間では、ウズベキスタン戦で1点先制されたあと、パワープレーに頼るだけの手しか打てない岡田監督の采配を見て「やっぱり監督経験のない人のやり方だ」という意見が多く、仮に岡田監督を続投させるにしても誰か経験豊富な人をサポートにつけるといった手当を最低でもするだろうと踏んでいましたが、その点については逆に岡田監督自身が断固拒否したのでした。
岡田監督はウズベキスタン戦を終えて帰国し、そのまま加茂前監督のもとへ直行します。増島氏のいう「筋を通して仁義を切りに行った」わけですが、カザフスタンでの更迭後に引き受ける条件として話した内容には「引き分けたらこうする」という約束事はありませんでした。
「ウズベキに負けたら、引き受け手がなくなるので最後までやります。しかし、勝ったら、もともと加茂さんとともに責任をとるつもりでしたから辞めます」という内容だけでした。
しかし岡田監督は、ウズベキ戦のあとのロッカールームの選手たちの姿を見て「このまま選手たちを置き去りにして自分だけ辞めれば済む問題ではない。自分も選手たちと一緒に運命を共にすべきだ」という考えになり、その気持ちを率直に加茂前監督に伝えました。
加茂氏から「辛いだろうけれど頑張ってくれ」と背中を押され、ふっきれて、10月14日、協会から正式に、残り試合の監督続投要請を受け受諾しています。
その後の記者会見で、記者たちから「誰か経験豊富な人のサポートは受けないのか」と問われて「私は絶対に要請しない。指導者はいったん現場を引き受けたら、現時点の自分を信じてやるしかない。指導者が不安を感じて指揮をとったら、選手も絶対に不安に思う。今の自分を100%信じ、それを出し切れば大丈夫だと思っている。」と答えています。
そう答えたあと記者から「個人の心意気としてはあっぱれだが、客観的に考えれば・・・」と突っ込まれましたが、次のように返しました。
「客観的にどうなのか、といったことは、私が答えなければならない質問ではありません。それは協会が判断することです。」
どのカテゴリーの監督も経験していない人であることは事実でしたが、監督=指揮官が持つべき気構えを見事に持っている人だということがよくわかる会見です。
岡田監督としては「自分がどのカテゴリーの監督も経験していないことを考えれば、日本代表監督としてベストの人材でないことなど、言われなくてもわかる。しかし何の因果か監督の座に就いている以上、自信のない素振りなどを見せて、もし自分の意図と違う考えを持つサポート役などを押し付けられるようなことがあったらチームは完全に崩壊してしまう。そんな中途半端なことはやめて欲しい。任せられないなら代えて欲しい、任せるなら完全に任せて欲しい。」という覚悟の上でのことなのでした。
そこが岡田監督が求めていた「全権委任監督」の意味だったのです。
岡田監督がこれらの手を打ったことで、選手たちが短期間のうちに気持ちを切り替え、チームとしてまとまらなければダメだという気持ちにさせたのは確かですし、ウズベキスタン戦での終了間際の同点劇や、第7戦アウェーの韓国戦に勝ったあとに飛び込んできたUAEの敗戦ニュースなど、日本に幸運が向いてきたと思える幾つかの状況も、こうした岡田監督の覚悟に基づく愚直な姿勢がもたらしたといってもいいように思います。
ウズベキスタン戦、UAE戦と続けて勝てなかったことを見れば、岡田監督の成功が、戦術家としての卓抜な手腕によって成されたとは言えませんが、明らかなのは、監督=指揮官が持つべき気構えと揺るぎない覚悟を持っていた人物が監督に就いたことでした。
岡田監督は「どうやって相手に勝つか、ということに関しては、とにかく考えた」と、98.1.1Number434号の中で、金子達仁氏のインタビューに答えて、次のように語っています。
金子 岡田監督にとってはおよそ1ケ月半の最終予選が終わったわけですが、あの時の感想は?
岡田 いろんなことを教えられた期間ではありました。僕自身、僕という人間があれほどの重圧に耐えられるとは思わなかったし、あそこまで感情をコントロールできるとも知らなかった。(中略)コーチ時代はただ感情に任せるだけだった男に、最終予選は自分の知らなかった自分を見せてくれました。
金子 最終予選は岡田監督をコーチとして大きくさせてくれたということですか?
岡田 それはもう。僕はまだ監督論について語ることのできる人間ではないけれど、いろんなことを教えられたのは間違いない。
金子 たとえば?
岡田 監督は主役じゃないってこと。(中略)監督は選手を育てるのが仕事。そのことを自覚するのがまず第一で、同時に、矛盾するようではあるけれど、精神的な強さもなきゃいけない。僕は世界最高の監督ではないけれど、どうやって相手に勝つか、いかにサッカーをロジカルにとらえるかという点に関してだけは、世界で一番考えたと思います。まあ、世界最高の監督であれば、考えるまでもなく、すぐ答が出てくるのかもしれませんけどね」
このインタビューから窺えるのは、岡田監督が「自分がいかに考え抜いたかについては自信を持って言える」と強い自負をもっていることで、それが「確固たる気構えと揺るぎない覚悟」のもとに考え抜かれたものであることに相違ないと思います。
成功者の要素として「確固たる気構えと揺るぎない覚悟」を持って事にあたるかどうかということに加え、「運」を引き寄せられるかどうかも大きな要素だとよく言われます、それに照らせば、岡田監督は明らかにその星の下に生まれたと言っていいと思いますし、その後の岡田監督のサッカー人生がそれを裏付けていると言っていいと思います。
アウェーのウズベキスタン戦で井原選手が放った超ロングフィードが呂比須選手の頭を経て、最後はGKの股間を潜り抜けてゴールインした様子を見たサッカージャーナリストの杉山茂樹氏が「数ある観戦歴のなかでも、このゴールほど、不可解でミステリアスなものは珍しい。(中略)岡田さんのその後の人生は、この運によって支えられているといっても言い過ぎではない。」と書いていましたが、どちらかというと、岡田監督という人が、こういう「運」を引き寄せられる成功者の星の下に生まれた人と言えるのではないかと思うのです。
やはり「流れを変える方策としてボスを変える」という究極の変化がもたらす効果は「運」も呼び込むことを含めた効果だと今更ながら思います。
73日間の「アジア最終予選」中で、選手たちがどのような心理状態に置かれ、どのように揺れていたのか、主な選手たちの「アジア最終予選」
今回の「アジア最終予選」を語る上でもう一つ重要な要素は、2ケ月半にわたって続いた過酷な道のりの中で、日本代表の選手たちが、想像を絶する心理的重圧を感じながら戦わなければならなかったという点です。
その理由と意義についてサッカーダイジェスト誌98.1.7/14合併号の中で次のように書いています。
「日本のサッカーにとって(注・2002年W杯の共催決定という新たな状況が生まれたことによって)、フランスW杯への挑戦は、これまでのW杯予選とは、根本的に重みが違ったものになった。4年前は『夢』だった本大会出場は、『義務』へと姿を変えた。それが重圧となって代表にのしかかった。(中略)何度崖っぷちに立たされたことか。しかし、代表はやり遂げた。岡野のシュートが決まった瞬間、『義務』は果たされ、日本サッカーは新たな領域に足を踏み入れた。偉大なるステップを踏んだのである。」
では、一人ひとりの選手たちは、どのような心理状態に置かれて、重圧の中、どのように揺れていたのでしょうか。この点についても特にキーマンとなった選手たちの様子を克明に記録に留め、しっかりと後世に伝えたいと思います。
一躍ヒーローの座に駆けのぼった岡野雅行選手、それまで全くチャンスを与えられなかった選手が突然、修羅場に放り込まれた岡野選手の「最終予選」
岡野雅行選手ほど胸のうちにわだかまりを持ったまま、第3代表決定戦・イラン戦を迎えていた選手はいないと思われます。
3月から始まったアジア一次予選、そして9月からのアジア最終予選は合計15試合ですが、岡野雅行選手は全試合に招集されています。
けれども、どれぐらいピッチに立てたかといえば、一次予選で途中出場が3回、合計78分だけです。最終予選も、もし途中出場中心の起用が続けば岡野選手のモチベーションの維持は、それほど難しくはなかったかも知れませんがイラン戦までは、その機会が与えられなかったのです。
岡野選手は、はじめのうちは、自分が無名の選手だったという意識を持っていたことから、日本代表の一員としてワールドカップ予選という真剣勝負の試合に選ばれているだけでも凄いことと感じていて、最終予選第1戦のウズベキスタン戦もベンチ外だったものの、スタジアムの大観衆の中でワクワク感を感じながら観戦していたといいます。
それでも、相変わらず出番はなく、最終予選では、第8戦カザフスタン戦までの8試合でベンチ入りが4試合、残り4試合はベンチ外、つまり半分はスタンドから見守るしかない立場だったのです。
こういう立場の中で、仮にベンチ入りメンバーとなった場合、いつ出番が来るかわからないとはいえ、常に準備を怠らないでいるという気持ちの維持は、かなり難しいものがあることがわかります。
第3戦のホーム韓国戦に敗れた試合もベンチ外でしたが、この時あたりから岡野選手は「俺が出たらこういうふうにするのにな」というイメージを強く持つようになりました。もちろんメンバーに入れているだけでもすごいとは思いつつ「なんで出してくれないんだよと。いろんな感情が湧いてきた」と気持ちが変化してきたそうです。
監督が岡田氏に代わってから、岡野選手は監督室を訪ねて聞いたそうです。「なんでボクを使ってくれないんすか?」
すると岡田監督は「お前は秘密兵器だからとっておく。相手に悟られないように隠しておくんだ。お前が必要な時が絶対来るから」と答えたそうです。
岡野選手は「そうか、とにかく出番が来るまで準備しておくしかないんだな」と気持ちを立て直して自室に戻りました。
それでも、なかなか出番は来ません。第8戦のホームカザフスタン戦では、追加招集された中山雅史選手や高木琢也選手が起用された関係で、岡野選手は、またしてもベンチ外となりました。
第3代表決定戦を前に岡野選手の気持ちはほとんど切れた状態になっていましたが、それでもベンチ入りメンバーとなりイラン戦を迎えたのです。
岡野選手にしてみれば「ついに、秘密兵器の出番が来たなと」という気持ちです。「もう、試合前までの期間は興奮しっぱなしで、なかなか寝られなかったです。試合前日も、寝ようと思って目をつむればゴールのイメージしか出てこない。気づいたら朝になっていました」と振り返っています。
岡野選手はほとんど睡眠をとらないまま、イランとの第3代表決定戦に臨むことになったのです。
試合当日、マレーシア・ジョホールバルのラルキン・スタジアムに到着した時、岡野選手は、「バスを降りた瞬間に、ただごとではないなと。日本人のサポーターがたくさんいて、試合前なのにテンションがすごく高かった。でも、僕はそういう雰囲気が好きなんで、もうやってやるぞという気持ちだけ」だったそうです。
スタメンは前日に発表されており、自分はベンチスタートであることをすでに知っていましたが、出番は絶対に来ると信じて疑わず、岡田武史監督から指名された「秘密兵器」は、その時に備え、心を研ぎ澄まさせていました。
試合は日本が先制しましたが後半イランに逆転されてしまいます。岡野選手は思いました。
「ついに出番が来た」「秘密兵器の出番が来た」
岡野選手はもうアップのスピードをあげ、アピールのために岡田監督の視界に入る場所で、びゅんびゅんと走りまくりました。
「意味もなく、スライディングまでしてましたから(笑)」それほどまでに、岡野選手は試合に出たくて、仕方がなかったといいます。その時までは。
ついに秘密兵器、出番か?
そして後半18分、岡田監督が動きました。どうやら交代選手は2人、カズ・三浦知良選手と中山雅史選手を下げるようだ。「そうか、2枚替えか、よぉ~~~し、やってやるぞぉ!!」
そう思ってユニホームに着替えようとした岡野選手でしたが、なんと、声がかかったのは城選手と呂比須選手だったのです。
岡野選手はヘナヘナとなってしまいました。「おいおい、と。俺、秘密兵器じゃないのかよ」「もうFWをこれ以上代えることはないだろうから、もうオレの出番はないのか」と思ったそうです。
後半31分、城彰二選手が同点ゴールを決めました。その時岡野選手は、
「いや、待てよと。この試合は勝たなければいけないわけだから、攻めに行く必要がある。ということは、まだ出番が来るかもしれない」と思い直したまではよかったのですが、時間が経つにつれ、両チームともに無理をしなくなった様子を感じたそうです。
つまり1点取られたら終わり。そんな緊迫した雰囲気がピッチを包み込み、あれだけ盛り上がっていた観客席も、固唾をのんで戦況を見守るようになって、国立競技場でUAEと引き分けた、あの試合の時のような、いゃ~な雰囲気を感じたそうです。
「あっ、この雰囲気、絶対無理だな。あれだけ出せって思っていたのに、この状況では出たくない。へたすると「戦犯」になってしまう。よし、もうこの試合にはかかわるのはやめよう、そう思ってベンチの隅のほうに隠れましたよ(笑)」
結局、試合は2-2のまま後半終了の笛を聞き延長戦です。岡野選手は隣にいた本田泰人選手に「これって15分ハーフの延長ですよね?」と聞くと「オマエ、何言ってんだよ、Vゴール方式で、どっちか入れたら終わりだよ!!」と言われ「エーーーッそれって最悪じゃないっすかぁ」というやりとりをしたそうです。
その間、岡田監督は腕組みをしながら考え込むようにしてグルグル回っていました。そんな時、中田英寿選手か誰かが「スピードしかないっしょ」「ウラ突くしかないっしょ」とブツブツ声を出していたようで、岡田監督は意を決したように「オカノ~~~!!」と叫んだのです。
こう書くと、いかにも中田選手のブツブツが聞こえた岡田監督が意を決して「オカノ~~~!!」と叫んだように聞こえますが、岡田監督は、すでに述べたように「どこで勝負に出るか、どこで切り札・岡野のカードを切るか慎重に考えて」いたのです。
岡野選手は「まじかよ、やめてくれよ。ここじゃないだろ」。心が折れそうになりながら、ユニホームに着替えると、岡田監督から声をかけられました。「入れてこい!!」
岡野選手は、あとあとになってもこの時の「やめてくれよ」という気持ちを思い出すそうで、これから先も二度とああいう場面はゴメンだと振り返っています。
「入れてこい!! なんて、無理難題もいいとこ」。ピッチに立っても、なかなか気持ちが乗ってこない。早々にチャンスが訪れたものの、シュートは力なく、GKにキャッチされました。延長前半1分のシュートです。
「アドレナリンが出てこないんっすよ、腰が引けてたし、身体も思うように動かないし・・」
ところが不思議なことに、練習ですっかり息が合うようになっていた中田英寿選手からのパスが出ると、岡野選手は条件反射のように本能的に走り出したそうです。
延長前半12分にまた絶好のチャンスが訪れます。
岡野選手は、その時のことを「実際の時間はわずか4~5秒のことだったと思うけど、自分の中では、まるでスローモーションのように、いろんなことが頭に思い浮かんだ」と振り返っています。(以下、浦和の元チームメート・鈴木啓太氏のYouTubeチャンネルに出演した時の対談から抜粋)
「ヒデから、いいパスが出てきて、また独走状態、これはもう絶対入れなきゃなんない」
「これ外したらヤバイ」とか
「でも、これ入れたらヒーローだな」とか
「自分の視界が白っぽいボヤーッとして感じで・・・」
「そうしたら、まるでスポットライトに照らされたかのように左側にDFの選手が視界に入って」
「あっ、まずいっ と思ったんではなく、よかったぁ と思って」
「まったくのドフリーでシュートしなきゃならないより、DFがいたほうがかえって開き直って打てるし」
「ところがDFがコケてしまって」
「そんなとこでコケんなよぉ!! と思いながら前を向くと、GKが目の前、ヤバイ、シュートコースなくなってる」
「そう思いながらチラッと横を見ると、ヒデがいて」
「わぁ~~、いいとこにいるじゃん、渡してポンで終わりだぁ」
「そう思って横に出したら、相手DFがスライディングでカットされて・・・」
その時、岡野選手のスローモーションが終わり現実に戻ると、目の前には日本のサポーターが金網越しに大勢が「おまえ!! 何で打たねんだよぉ~~~」と罵声を浴びせて来るし、日本ベンチのほうを見ると、岡田監督は明らかに岡野選手を怒鳴りつけんばかりに怒っているし、みんなは天を仰いでいました。
前半終了間際にもこぼれ球に反応し、シュートを放ちましたが、ボールはバーの上を越えていきました。3度に渡る決定機をモノにできなかったのです。
サッカーなんか、やらなきゃよかったよ
岡野選手は自分が地獄の苦しみを味わわされている思いがしたといいます。
「これは人生終わったな。もし負けたら日本に帰れないし、サッカーは辞めよう」
「なんでオレはこんなことにならなきゃなんないんだ」「なんでサッカーなんかやっちゃったんだろ」「サッカーなんかやらなきゃよかったよ」
まもなく延長前半が終わり、チームが円陣を組みます。岡野選手は「もう皆んなに見捨てられてんだろなぁ」「ひどいこと言われるだろうな」と思いながら恐る恐る円陣に近づくと、意外や意外、誰からともなく寄ってきてくれ、背中さすったりしてくれながら、名波選手とか中田英寿選手からは「しょうがねえょ、こんな場面で出されちゃってさ」「緊張すんに決まってけどさ」「お前しかいない。頼むから点を取ってくれ」「点とったら、いままでのは全部チャラにすっからさ」とか言われて、それまでの地獄のような気持ちが「す~~~っ」と抜けていくのを感じたそうです。
そして「自分に出来ることは・・・、皆んなはチョー疲れてんだ、よ~~し、オレが追いかけ回すよ、バンバン相手を追いかけ回す。」そう思って延長後半のピッチに飛び出していったのです。ようやくアドレナリン全開になりました。
延長後半、日本はずっと押し気味に試合を進めていて、岡野選手もすっかり落ち着きを取り戻した12分過ぎ、一瞬岡野選手も頭が真っ白になる出来事が起きました。まったくチャンスのなかったイランがカウンター一発、ダエイ選手にクロスが入り合わせられたかに見えたからです。ボールは枠に入らず事なきを得ました。
その直後です。延長後半13分、岡野選手同様、まずいと思った中田英寿選手が自分でドリブルで持ち込みゴール前に迫ったのです。この時のことを岡野選手は鈴木啓太氏との対談でこう振り返っています。
「オレは、絶対またパスが出てくると思ってたから、今度は狙ってたのね。」
「ヒデがドリブルで仕掛けてくるから、相手DFがオレからヒデのほうに引き寄せられるよね」
「だから、パス来るかなと思って構えてたの」
「ところがヒデは頭いいね、自分で打ったのよ」
「そっか、入るかな?、入らなきゃ、こぼれ球のところに構えてりゃいいか」
「そっからがまたスローモーションみたいな感覚になってねぇ」
「GKがはじいたところにオレが詰めてたから、よっしゃ、と思ったのね、そしたらGKがパッとオレの顔見て『なんで、なんでここにいんの?』って顔してたよ」
「あとはもう、絶対にフカしちゃダメだと思ってさ、本能的にスライディングしたんだよね、身体ごとボールを押し込もうって感じで。オレにとってはあれが一番確実な方法だったからね。」
岡野選手は、一躍ヒーローの座に駆け登りましたが、実は試合ビデオは何年もまともに見れなかったと後年告白しています。
あの最終予選の時の自分の揺れ動いていた感情、イラン戦では乱高下したかのような起伏の激しい感情の中で戦ったことが思い出され、身体が震えて見れなかったのだそうです。
日本代表としてワールドカップ予選を勝ち抜くという歴史上初めての体験を、極めて過酷な戦いの末に終えた選手たち、その中でも岡野雅行選手の最終予選、そしてイランとの決定戦は、永遠に語り継ぐ価値のあるものだと、あらためて感じつつ記録に留めたいと思います。
守護神として全試合ゴールマウスを守った川口能活選手、五輪代表からの昇格組が百戦錬磨の守備陣を統率する心の葛藤、最後の砦にかかる重圧の「最終予選」
川口能活選手がアトランタ五輪での活躍が認められてフル代表に招集されたのは、アトランタ五輪が終わってすぐでした。
96.8.25国際親善マッチ・ウルグアイ戦。この試合を含めて2試合ベンチ入りしましたが、その後Jリーグの試合中、右手甲の骨を3本骨折してしまい、このあとのシーズンを欠場することとなりました。
初スタメンで、そのまま正GKの座を獲得
年が明けて97年に入り右手の負傷も全快した川口選手は、2月にタイで開催されたキングスカップに招集され、3試合目のスウェーデン代表との試合に起用されました。
欧州の強豪相手に0-1で敗れたものの、川口選手は高い評価を得て、続く第4戦ルーマニア選抜戦にもスタメン出場、2-0の完封勝利に貢献、以来、日本代表GKのポジションに完全に定着したのです。
したがって3月のW杯アジア一次予選から、11月のイランとの第3代表決定戦まで全15試合、合計1378分、文字通り日本の守護神としてゴールマウスを守り続けました。
GKのポジションは1つしかないレギュラーポジションですから、どのチームも一旦レギュラーポジションを獲得した選手は、大きなケガでもない限り長く守護神として君臨することが多く、いきおい年齢的にも高い選手が多いポジションですが、川口能活選手はチーム内でも最も若い年代に属する極めて稀なGKということになります。
けれども、川口能活選手は、年代が若いことから来る遠慮や、余計な気を使うといった弱さとは無縁の働きぶりで、加茂監督も、さぞ頼もしく映ったことと思います。
また映画俳優を思わせる端正な顔立ちとスラリとした体型から、多くのファンに囲まれる人気選手ですが、若い人気選手にありがちな甘さとは縁遠い、ストイックで自分にも周りにも厳しい選手像が、アトランタ五輪などの大きな舞台を踏む中で次第に輪郭を表してきました。
それにしても、日本代表として初めてゴールマウスを守ったキングスカップのスウェーデン戦は、長身揃いの選手、ゴール前にハイクロスを放り込んでくる空中戦の多い相手であり、初陣のGKにとっては難しい相手でした。しかも、早い時間帯での失点で並みのGKなら大崩れしてもおかしくない試合でした。
しかし、川口選手は、アトランタ五輪代表時代から指導を受けているマリオコーチに「仮にミスすることがあっても、GKは絶対に弱みを見せてはいけない」という教えを思い起こし「とにかく切り替えるぞ、切り替えるぞ」と自分に言い聞かせて乗り切ったそうです。
しかも、そのあとは、事あるごとにチームメイトを大きな声で怒ることが多くなり、とても初陣のGKとは思えないプレーぶりを見せました。川口選手は「あの試合、とにかく自分はアピールしてレギュラーの座をモノにしたいという気持ちで必死でした。守りから攻めに移る起点としてボクはフィードの速さをセールスポイントにしてましたから、すぐフィードしたいのに、ちっとも動いてくれないから大きな声を出したんです。皆んなにとってはフレンドリーマッチに過ぎないかも知れませんが、自分にとってはW杯予選に選ばれるかどうかが掛かっていましたからね」
こうした姿勢が評価されてW杯アジア予選のメンバーに選ばれ、順当に正GKの座を勝ち取った川口選手、一次予選を戦ってみて代表チームに危機感を感じていたようです。
「ワールドカップ予選っていうのはすごく厳しいものだと思うし、はっきり言ってこのままの雰囲気じゃダメだと思うから、僕が生意気なことを言って、昔からいる人がカチンときて、僕に対する目が厳しくなって、それで僕が頑張れれば、チームにとっても僕にとってもいいはずだと思います。アトランタ五輪の経験で、チームメイトにも要求して、自分を追い込んで、そうすれば勝てるっていうのがわかったんです。だから今回も同じようにやっていくつもりです。」
かなり暑苦しい男(ヤツ)、浮いてる男(ヤツ)
しかし、川口選手のそういうストイックなところは代表チームの中でも、かなり「暑苦しい男(やつ)」と見られることが多く、やや浮いている感じのところもあります。しかし、川口選手は毅然として「ワールドカップ最終予選ってのは、キレイごとじゃ勝てないと思うんですよね。相手は死に物狂いでくる。それに勝つには、こっちも負けないぐらい死に物狂いでやらないと。確かに僕は代表で一番若いかも知れない。でも、死に物狂いでやって、それでやっと勝ち抜くという経験はしてるんですよ。だから今度も、勝つためにとことん自分を追い込んでいくつもりです。」
【川口選手のコメントは97.3.27Number414号「川口能活・泥の心」by金子達仁 より引用】
こうして川口能活選手は、9月からのアジア最終予選に臨みました。案の定、最終予選の日本代表の戦いぶりは、川口選手が繰り返していたように「ワールドカップ最終予選ってのは、キレイごとじゃ勝てない」ものでした。
初戦の国立競技場ウズベキスタン戦は6点とったものの3点を返され、3戦目のホーム韓国戦では1点先行しながら後半も終近くに立て続けに2点を返されて逆転負け、そして4戦目のアウェー・カザフスタン戦も1点先行しながら後半終了間際に同点ゴールを許してしまい引き分け、自力での2位確保がなくなりW杯出場権獲得が風前の灯となりました。
カザフスタン戦の後、川口選手はホテルに帰るバスの中で一触即発の出来事を起こしてしまいました。
「(注カザフスタンの)同点ゴールが決まった瞬間から頭の中が真っ白になっちゃって、ずっと独り言をつぶやいてたらしいんですよ。ロッカールームからバスの中までずっとね。で、バスがホテルの前に着いたのに、僕は気づかなかった。そうしたら誰かが肩をポンポンって叩いてきたんです。僕、それをガッて払いのけちゃって・・・。気づいてみたら井原さんでした。」
当然、井原選手は怒りました。自分ひとりでW杯予選を戦ってるような態度を、井原選手は厳しく叱り飛ばしました。
「それに対して、俺、言い返しちゃったんですよ、うるせえって・・・・。」
井原選手は激怒しました。あわやつかみ合いが始まろうとした時、周囲の人たちが止めに入り致命的な衝突は免れました。
部屋に戻った川口選手は、すこし頭を冷やしてから井原選手の部屋に向かいました。
「謝りました。謝って、なぜ自分があんな行動をとっちゃったのかを説明しました。井原さんはすぐにわかってくれて、こっちの話に耳を傾けてくれました。今シーズン、マリノスで失点が多かったこともあって、正直、俺の中には井原さんに対するわだかまりみたいなものがあったんですけれど、あれできれいに消えました。俺は言いたいことを全部言って、井原さんにも俺に対する見方を言ってもらった。今年初めて、本音をぶつけあえたんです。」
この夜、監督更迭が告げられて選手たちが「はい、わかりました」と言ってすぐに部屋に戻るような気分になれない中、自然発生的なミーティングの場がもたれ、そこでもお互いの胸の内をぶつけ合う場となり3時間ほどの率直な話し合いが行われました。
川口選手は、その場で同じGKでありながら控えに甘んじている小島伸幸選手の、場を和ませるというか雰囲気を和らげるふるまいを見て、あらためて存在感の大きさを目の当たりにしました。
そうしたおかげもあって、壊れかけた井原選手やDF陣との信頼関係はギリギリのところで修復されましたが、その一方、川口選手は「自分は代表GK失格なのではないか」という強烈な不安が頭をもたげてきたそうです。川口選手が代表に招集されて不在となった横浜Mは失点がずいぶん減っていて、自分はこの最終予選、初戦3失点、韓国戦2失点、そしてカザフ戦も完封を逃してしまった。新聞・雑誌にも「川口の守り不安」とか「川口不調」と書かれている。そんな時に井原選手と衝突している自分は、代表GK失格どころか人間としても失格なのでは・・・。
そう落ち込んでいた川口選手に追い打ちをかける出来事が起きました。ホテルに国際電話がかかってきて写真週刊誌が「あなたの記事を載せる予定です」と告げられたのでした。写真週刊誌ですから、いい話であろうはずがありません。
これで川口選手は自己嫌悪と人間不信の奈落の底に落ち込んでいくようでした。
この写真週刊誌の記事、かなりショッキングな記事です。1ページ目が車を降りようとした川口選手に突撃風にカメラフラッシュを浴びせ、川口選手は運転席から片足を外に出そうとした姿勢で「誰? 何?」という表情で撮られた写真です。
2ページ目は、ホテルの1室のベットに腰をおろした川口選手が柔和な顔で写っている写真、3ページ目はパンティ1枚の若い女性がベッドに横たわって写っている写真(顔半分は白抜き目隠し処理されている)
本文を読むと、明らかに川口選手は、このオンナと写真週刊誌によって仕組まれたワナにまんとはめられたことがわかります。
こんな記事をバラまかれたら、並みの人間はもたないと思います。1990年代後半、写真週刊誌の世界ではこういうことが平気でまかり通っていましたから、知名度のある人は、よほどガードを固くしないと、まんまと引っ掛かってしまう時代でした。
川口選手はまだ21歳、こういったことに対する防衛策を身につける前に標的にされたのです。
絶望の淵にいた川口選手を救った1枚のFAX
アジア最終予選を戦っている日本代表GKとしてのプライドも自信もズタズタにされ、どうしていいかわからなくなってしまったそうです。
そんな時でした。川口選手のもとに1枚のFAXが届いたのです。写真週刊誌のことを知ったのでしょうか、差出人は高校時代の恩師でした。清水商・大滝雅良監督からのFAXにはこう綴られていました。
「人生最高の時、苦しい時、厳しい時・・・・。力を発揮できるのが日本男児、逃げるな。正面から戦え。正々堂々と。そして自分を信じて、仲間を信じて・・・。」
「お節介かと思いましたが、送ってしまいました。読後、捨ててください。」
川口選手は、そのFAX用紙を自室のドアに貼り付けました。後にこう語っています。
「俺、あのFAXにすがって、何とか1週間乗り切れたんです。あれがなかったら、俺、どうなっていたかわかんないっすよ。」
この大滝雅良監督からのFAXは、同じ清水商で指導を受けた名波浩選手、平野孝選手にも届いていました。もちろん3人とも「読後、捨てて」という恩師の指示には従いませんでした。
川口選手は1週間、折に触れドアの用紙を見ながら、いろいろなことを考えたそうです。
「守備の選手たちを怒るのはやめなきぁ。その前の試合のビデオとか見返してみると、自分でも驚くほどヒステリックに怒ってて、仲間を信じてないってことですよね、これじゃ守備が安定するわけない。怒るのやめないとダメだ」
「そして味方が点を取ったら、一緒に喜ぶようにしよう。それまでの俺って、点が入るとスタンドに向かってガッツポーズしてたんです。全然仲間のこと考えてない。点を取られれば味方のせいにするくせに、点が入ると一人で喜んでる。こういうこと止めて信頼してもらえるGKにならなきゃ」
「せっかくそういう気持ちになっても次の試合負けたらW杯出場は叶わなくなる。もしそうなったら自分にサッカーを続ける資格はないってことだ。」
そう思って臨んだアウェーのウズベキスタン戦、リードを奪われてしまいました。川口選手は、これまでのサッカー人生、22年のサッカー人生で最大の重圧を感じたといいます。
「もう、これで終わりか、こんな形でサッカー人生が終わってしまうのかって考えたら、涙が止まらなくなっちゃって。試合自体、守備陣の出来は最高だったのに、何の意味もなさずに終わってしまうのか・・・って」
ところがサッカーの神様は日本代表を、そして川口選手を見捨ててはいなかったのです。試合終了間際、最高の守備を見せていた井原選手から、まるで祈りを込めたかのような超ロングフィードが最前線に送られました。送られたロングフィードは、呂比須ワグナー選手が競り勝ったボールが、2バウンドして、なぜかGKの股間をすり抜けて同点ゴールとなったのです。
試合は同点のまま終わり、日本が崖っぷちに追い込まれたままの状況は変わらなかったのですが、川口選手の気持ちに変化が生まれました。
「一瞬、神様の存在を感じた気がしました。俺たちはまだ死んじゃいないんだって」
味方を信じ、励まし続けたこの試合で日本の守備陣は最高のパフォーマンスを発揮していました。そのため川口選手は、それまで味わったことのない、GKとしての未知の楽しさを感じたのです。まだ終わっていないという安堵と勝てなかった悔しさが入り交じった複雑な気持ちとともにではありましたが・・・。
川口能活という選手という人は、なんと幸せな男なのでしょう。大切なチームメイトに失礼なブチ切れ方をしてしまい、日本代表GKとしての自信がガラガラを音を立てて崩れ、そこにプライベートなことでまた追い打ちをかけられ、自暴自棄に陥る寸前の、絶望の淵にいた選手のもとに、「神様のお告げ」を思わせるメッセージが届く。
川口能活という選手は、やはり、この時の日本代表GKとしてサッカーの神様から遣わされた選手なのではないかと感じさせる出来事です。
【川口選手のコメントは97.12.4Number432号「密着ドキュメント中田英寿と川口能活の63日」by金子達仁 より引用】
中央アジア遠征の起伏の大きい精神状態から日本に戻り、国立競技場でUAEと引き分けて、日本代表が置かれた状況は相変わらず崖っぷちだったのですが、ソウルに乗り込んだ時は、なぜか無心の状態、高ぶるでもなく、追い詰められた感もない淡々とした心境になっていました。
戻ってきたポジティブなメンタルとは裏腹に身体の疲労は極限まで蓄積
アウェーの韓国戦を2-0でモノにして、第8戦のカザフスタン戦も国立競技場のサポーターとの一体感の中で圧勝すると、川口選手は一気にポジティブなメンタルになっている自分を感じたといいます。
「仮にソウルで韓国と1位争いをして負けて第3代表決定戦に臨むより、3位から2位になって決定戦に行けたんで波に乗れたし、結果的にチームのピークが最後に来たからね。(中略)追い込まれたわけではないから気持ち的にはラクだった。」
その一方でイラン戦を前に川口選手の身体が疲労の蓄積で限界に達しつつあり、思うように動いてくれない身体を抱えていました。
第3代表決定戦、ジョホールバルでのイラン戦、川口選手の動いてくれない身体が試合を難しくしました。
中山雅史選手の先制点で折り返した後半1分、ダエイ選手のシュートをキャッチできずパンチングで逃れたところをアジジ選手に詰められ同点、続いて後半13分、川口選手は目の前にあがったセンタリングに反応するかどうか一瞬迷いました。その瞬間、ダエイ選手が頭でとらえ、ボールはフワリと川口選手の指先をかすめてゴールに吸い込まれてしまいました。
「ただ、ひっくり返されて、いつもならそのまま3,4点続けて失点してしまうか、あとに引きずってどんどん萎縮したと思うけど、あのあと崩れなかった。あそこで皆んな崩れなかったのは、この3ケ月を経験してきたからだと思うんです。」
確かに川口選手は以前とは違って、仲間に対して終始穏やかな表情で接し、時には笑みさえ浮かべて激励していました。
それは、数々の地獄を経験した仲間との間に生まれた信頼感の賜物でした。ここまでの中で、DF陣一人ひとりのプレースタイルに応じたコーチングの仕方を会得した上に、仲間を信頼して楽しくやろうぜ、という気持ちに徹したからでした。
逆転した後のイランの様子を見て川口選手は、第3戦国立で韓国に負けてしまった日本と同じ状況になっていることを感じたといいます。イランが引いて守り運動量もガクンと落ちたのを見て、これはチャンスだと感じたのです。
そして日本は後半31分、中田英寿選手のクロスを城彰二選手が頭で合わせて同点に追いつきます。このゴールについて川口選手は独自の見方をしていました。
「ヒデと城が絶賛されてたけど、あのゴールは半分モトさん(山口素弘選手)のゴールだよ、ヒデに渡る前にモトさんがダエイのスルーパスをインタセプトしたでしょ、あのインタセプトがなかったら絶対スルーパスでやられてたからね。」
(注・この場面、ダエイ選手のスルーパスが通ると、明らかにGK川口選手が相手選手と1対1になってしまう場面でしたが、オフサイドの可能性もあり微妙なシーンでした)
そして川口選手が「この選手に出て来てもらって点を取って欲しい」と考えていた岡野雅行選手が、そのとおり延長後半13分、Vゴールを決めてドラマは完結しました。
川口選手は喜びを爆発させるには、あまりにも疲れすぎていました。
そこには、アジア最終予選という過酷な戦いの中で、怒り、ショック、絶望、放心といった感情を自分勝手に露わにする選手から、仲間を信じ、喜びと苦しみを共に分かち合うGKに成長した川口能活選手がいました。
【川口選手のコメントは98.1.1Number434号「川口能活・まだ夢は終わらない」by佐藤俊 より引用】
キャプテンでありドーハ組でもある井原正巳選手、闘将・柱谷前キャプテンと比較される中で自分なりのキャプテンシーをどう発揮するか試行錯誤の「最終予選」
井原正巳選手は、筑波大学時代の1988年、20歳の時、日本代表監督に横山兼三氏が就任した時から招集され、その後も日本代表監督の交代があっても不動のDFとして10年目を迎えた1997年、3度目のW杯アジア予選に臨むことになりました。
最初の1989年イタリアW杯アジア予選は屈辱の一次予選敗退、2度目の1993年アメリカW杯アジア予選は、あの「ドーハの悲劇」を経験しての今回となりました。好むと好まざると「三度目の正直」を意識せざるを得ない、代表選手の中では唯一の立場でした。。
最終予選を前にして井原選手はサッカーダイジェスト誌のインタビューに答えて次のように話しています。
「前回の時は『ひょっとしたら出れるんじゃないか』とか『頑張ってくれよ』という声が多かったと思いますが、今回は『大丈夫かよ、出なきゃいけないんだぞ』と言われることが多いですよね。周囲の見方、声が厳しくなってると感じます。」
「そういう声を発奮材料にしてます。周りからいろいろ言われてますから、選手は『やってやるんだ』という気持ちですね。最終的には結果が出ればいい話なので、内容が悪いなら悪いなりにどう勝つか、勝てればいいわけです。」
とかく周囲が試合内容について、やれ引かれた時の攻め方に工夫がない、カウンターを浴びた時の守りが不安だ、と並べ立てていることに対しては、冷静に受け止めてしました。
「いいサッカーをして勝てれば、それに越したことはないし、いいサッカーをしなければ、そうそう勝てないことも分かってます。ただ、いい試合をいつもできるかといえば難しい。」
「前回のチームと比べられたりして、いろいろ言われますけど、ボクは前回のチームと比べることはできないと思っています。前回は核になる選手もいて、チームもまとまっていましたけれど、それでもW杯に行けなかったわけですよ。逆に今回、このチームで(W杯に)行ければ、こっちのチームが良かったということになるはずですから。」
【井原選手のコメントは97.5.7/14サッカーダイジェストNo364 集中インタビューより引用】
さすがに、この時すでにA代表試合出場歴3ケタをはるかに越えている井原選手らしい、いわば泰然自若といった心境だったようです。キャプテンとしてチームを牽引するスタイルについても、自分なりのやり方で、と強調しています。
「ドゥンガやテツさん(柱谷哲二選手)のように叱咤激励するタイプではありません。僕なりのやり方で・・・・」
「このチームはお互い仲が良いですからね。仲良しムードを引きずらないためにも、時には厳しくしないと・・・」
「もっとも僕が厳しい台詞を吐いても、どうも優しく聞こえちゃうらしいんですけど」
【井原選手のコメントは97.9.25Number427号 クローズアップby杉山茂樹より引用】
この時期、つまりアジア最終予選の前段階では「このチームはお互い仲が良いですからね」といういうことで、チーム内にまだ目立った軋轢は生じていないという認識と「僕が厳しい台詞を吐いても、どうも優しく聞こえちゃう」という、キャプテンの役割に対する余裕が感じられます。
中央アジア遠征の苦しい時期も「諦め」の気持ちはまったく持たなかった
ところが、最終予選に入ると懐の深い井原正巳選手にもじわじわと重圧がのしかかってきました。
井原選手は、97.12.10サッカーダイジェスト「井原正巳独占手記」の中で、その時期のことを次のように振り返っています。
「最終予選を振り返ると、途方もなく長かったと感じる。ただでさえ長ければ集中力やコンディションの維持が難しいのに加え、加茂監督が更迭された中央アジア遠征の時は心身ともに最も苦しい時期でした。」
「加茂さんが辞めたという事実には選手も動揺しました。なにしろボクたちは加茂さんが選んだメンバーだし、責任の半分がボクたちにあることは間違いありませんから。そこで、加茂さんの更迭が決まった夜、みんなで話をする機会を持ちました。」
「ただW杯出場権獲得に関しては、常に諦めとは無縁でした。確かに結果は出てませんでしたが最悪のサッカーをしていたわけではありませんでしたから。その点は全員が同じ気持ちだったと思います。」
「マスコミを通して聞こえてくる『絶望的』といった声を、ボクたちはよく耳にしていましたが、戦っているボクらにとっては『まだ可能性があるんだから』という思いのほうがずっと強く、聞こえてくる悲観的な声は、むしろ発奮材料としての効果のほうが大きかったと思います。ハングリーさに変えたと言ってもいい。加茂さんが解任されてからは『自分たちで何とかする』という気持ちが強くなり、同じ方向へとベクトルが向かうようになったと感じました。」
「W杯予選を戦う経験が3度目ですが、今回、代表チームが置かれた立場は、過去2度と比べて全く異質でした。今回は、過去2回と違い『絶対に行かなければならないシチュエーション』がありました。周囲もそれを当然とし、ボクらも絶対という気持ちでした。その強い意思があったからこそ、最後まで集中力を維持できたのだと思います。」
「DFとしての仕事で言えば、周囲のボクに対する評価は常に『組織を機能させる上での井原』、つまり守備組織の良し悪しがすべて自分の統率にかかっている。今回のアジア予選を通じて、そう見られていることを痛感しました。これについては多少の波はありましたが終盤になるほど良くなったと思います。」
「主将としての役割についても『強い期待』をずっと感じ続けていました。だからと言って、特別なアクションを起こそうとは思っていませんでした。中央アジア遠征の時もそうでした。あくまでマイペースを貫き通そうと考えてました。もちろん、いろいろな選手と話し合う機会はありましたし、ヨシカツとはケンカさえしましたけれど、このチームには所属クラブでキャプテンを務めている選手が数人いましたから、その選手たちと盛り上げていこうという思いでやっていました。」
「こうしてW杯出場権をとれたということで、そのやり方が間違っていたとは思っていません。素晴らしいキャプテンシーを発揮したと言われているドゥンガやテツさん(柱谷哲二選手)だって批判されたこともありますから、ボクは極力、周囲の声を気にせず、自分の思う通りに、と自分に言い聞かせながら最終予選を戦っていました。」
「最後に書き加えたいことは、チームの裏方の人たちに感謝したいということです。監督や選手たちの影に隠れてしまいましたが、彼らの苦労こそ計り知れないものがあります。マッサー、ドクター、シェフ、栄養士、さらにはポペイロなど帯同してくれた人たち、もちろん限られたベンチ入りメンバーのためベンチ外となってしまった選手も含めて、スタッフすべてが評価されて欲しい。選手が頑張るのは当然で、その選手たちのわがままを聞いてくれた人たちの苦労には、この機会を借りて感謝したいし、そのことが多くのファンの人たちに伝わって欲しいと思います。」
最後は、人格者として評価が高い井原正巳選手らしい、気配り、目配りに溢れたコメントで締めくくられています。
不退転の気持ちで臨んだアウェー・ウズベキスタン戦、最後に「サッカーの神様」が井原選手の超ロングフィードをゴールに導きました
井原選手は、最終予選の中で特にターニングポイントになった試合をあげてはいませんでしたが専門家の中には、井原選手のターニングポイントとなった試合として、岡田監督になって初めての采配となった第5戦のアウェー・ウズベキスタン戦をあげる人がいます。
97.11.6Number430号の「W杯最終予選緊急レポート」の中でウズベキスタン戦をレポートした杉山茂樹氏は、この試合での守備陣の出来を「完璧」と評価して次のように書いています。
「1点こそ奪われたが守備は完璧だった。秋田は相変わらず絶好調で、累積警告の小村に代わって起用された斉藤も、持ち前の冷静さを随所で披露した。驚かされたのは井原だ。キャプテンらしからぬ緩慢な動きを見せていたこのシリーズのプレーとは打って変わり、鬼気迫る立ち回りで存在感を見せつけた。早々のイエローカード(次戦出場停止)が特効薬になったのだろうか。緒戦(第1戦のウズベキスタン戦)のカズにも似た突如の変身ぶりである。
(中略)井原の変身は大きな収穫だった。・・・・」
杉山氏をして、そう言わしめた井原選手のプレーぶり。鬼気迫るプレーに井原選手を突き動かした出来事が、その前のカザフスタン戦のあとに起きたからに違いありません。
その出来事とは、言うまでもなく加茂監督更迭、岡田監督への交代です。井原選手自身が「責任の半分はボクたちにある」と発奮しなければならない出来事だったと同時に、その夜、川口能活選手の振舞いに端を発した2人の議論、そして深夜の自発的ミーティングと続く皆んなとのコミュニケーションの中で、細かい部分もクリアになり「やってやる、何としても」という気持ちになったに違いありません。
感情の起伏を表に出すことを潔しとしない井原正巳選手です。前述のサッカーダイジェスト誌「独占告白」の中でも「中央アジア遠征の時は心身ともに最も苦しい時期でした。」と述べるに留めていますが、ウスベキスタンとの試合は、不退転の気持ちで臨んだターニングポイントとなった試合と言っていいでしょう。
そして、1点リードされた後半ロスタイムに入ったかどうかぐらいの時間に、あの超ロングフィードが生まれ、それが起死回生の同点ゴールを生んだのでした。
感情の起伏を表に出さない井原選手が、心の中では燃えたぎるような気持ちで臨んだ試合で、最後の最後にサッカーの神様が井原正巳選手の鬼気迫る一蹴りを「潔し」としてゴールに結び付けてくれたと言って間違いないと思います。
ジョホールバル・イラン戦、途中交代を命ぜられたカズ・三浦知良選手、常に結果を求められ続けてきたスーパースターの「最終予選」
カズ・三浦知良選手は、このサイトでも一貫して「カズ・三浦知良選手」と表記しているように、愛称と名前をセットにして呼ぶことが許される1990年代の日本サッカー最大の功労者、日本が誇るスーパースターとしての実績があります。
それゆえ、加茂監督も、そのあとを引き継いだ岡田監督も一貫して「カズと井原は外せない選手」としてアジア最終予選を戦い続けてきました。
しかしマスコミの多くは、すでに最終予選前からカズ・三浦知良選手を軸にしたチーム作りには懐疑的な眼差しを向け続けていました。なぜなら、カズ・三浦知良選手は4月に右足首の靭帯を痛めて以来、あまりいいパフォーマンスを見せていなかったのです。
8月13日のブラジル戦で、カズ・三浦知良選手は1トップで先発、次に後半開始すぐに城選手が加わり2トップの一角でプレー、そして後半途中からは、中盤の選手に代えて高木琢也選手を入れた際、カズ・三浦知良選手を2列目に下げて使い続けるといった起用法があったため「それはないだろう」と言われました。
ブラジルが相手ということで、まるで、ブラジルでプレー経験があるカズ・三浦知良選手は最後まで代えるわけにはいかないと決めてかかっているような起用方法でした。
その後、カズ・三浦知良選手は8月22日の代表合宿紅白戦で膝を痛めてしまい、JOMO CUP’97は欠場しています。
さらに9月2日のジュビロ磐田との35分ハーフのテストマッチでも、やはり膝のケガの大事をとって前半だけで退いています。
これらのことからカズ・三浦知良選手を軸にした戦い方は最終予選を勝ち抜くにはリスクが大きいという指摘だったのです。
ところが、そうした懸念を一蹴する出来事が、9月7日からスタートしたアジア最終予選の初戦・大観衆で埋め尽くされた国立競技場でのウズベキスタン戦で起こったのです。
ここ一番という試合、観客の期待がMAXに達するような試合で必ず主役の座を勝ち取ってきたこれまでと同様、この試合でもカズ・三浦知良選手は4ゴールの固め打ちで圧勝劇を演出し、W杯アジア最終予選の最高の船出を飾ってみせたのです。
この活躍の影には、痛めた膝をケアして何としても万全の身体にしてスタートを迎えるんだというカズ・三浦知良選手の強烈な意思と、それを可能にしたドクターとトレーナーの昼夜を分かたぬ献身があったのです。
その結果、ウズベキスタン戦の2日前には痛みが完全にひいて、あとは大事な試合に気持ちをピークに持っていく、いつものカズ・三浦知良選手のメンタルコントロールが功を奏した結果の活躍だったのです。
このカズ・三浦知良選手の強い意思にドクターもトレーナーも、あらためて舌を巻き、このあと、また尾てい骨を痛めた際に、カズ・三浦知良選手をプレーさせるかどうか話し合った首脳陣たちの会議で「カズなら絶対間に合わせる、カズはそういう男だ」と意見を出すことに繋がったのです。
第2戦アウェーのUAE戦は、猛烈な暑さの中の試合で、とてもリスクを負って攻撃重視になれない中、カズ・三浦知良選手も見せ場がなく、後半途中からはワントップ、ひたすら相手を追い回す役割のまま試合を終えました。
そして第3戦の韓国戦、韓国の車範根監督は、DFの一人に対してカズ・三浦知良選手への密着マークを命じました。単なるマークではなく徹底したマーク、まるでスッポンと蛭(ひる)が身体を吸い尽くすようなマークでした。
その上、相手GKからチャージを受け尾てい骨をしたたか打ってしまったのです。
韓国戦で痛めた尾てい骨の痛みが収まらないまま出場したカザフスタン戦、加茂監督更迭の一因に
次のカザフスタン戦を前に、カズ・三浦知良選手が尾てい骨の痛み少しでも抑えるためにとった行動について「たった一人のワールドカップ・三浦知良1700日の闘い」(一志治夫著)には次のように書かれています。
「9月30日、カザフスタンでの練習に入ったカズは、他の選手たちとは別メニューをこなしていた。(中略)カズは早めに練習を切り上げると、トレーナーの並木麿去光とともに控え室に入り、パンツを下げた。尻に氷を当て、ラップをぐるぐると巻きつけていく。患部を冷やしているのだ。果たして4日後の試合に間に合うかどうか、だった。(中略)」
「10月4日、対カザフスタン戦の先発メンバーの中に、カズの名前はあった。しかし、90分を終わってみれば、やはり、カズはでるべきではなったということになるのかもしれない。尻の痛みは明らかに走力とシュートの精度を落していたからである。(中略)」
「カズは痛くないといって出場しようとしたことは非難されるべきことではないだろう。(中略)外すと判断すべきだったのは首脳陣だった。」
この試合のあと、加茂監督の更迭が発表されています。更迭の理由として、さまざまな采配面の拙さが指摘されていますが、その最も大きな原因が、誰の目にも不調が明らかなカズ・三浦知良選手を最後までピッチに残したことにあることは疑いの余地がありませんでした。
最終予選前からカズ・三浦知良選手を軸にした戦い方のリスクが指摘されながら、膝の痛みを初戦のウズベキスタン戦までに完治させて4得点の爆発を見せ、トレーナーたちにも「カズは必ず治す男」と再認識させ、その流れで首脳陣たちも、その言葉を信じてカザフスタン戦のスタメンに送った結果の監督更迭でした。
これは明らかに加茂監督がカズ・三浦知良選手と心中した結果ですが、加茂監督の更迭について、前述の「たった一人のワールドカップ・三浦知良1700日の闘い」(一志治夫著)の中でカズ・三浦知良選手は次のように語っています。
「僕は、加茂さんは辞めないたろうな、最後まで行くんだろうなと思っていた。当然。
(中略)加茂さんが辞めたことに関してはすごく責任を感じていたよ。全員かどうかはわらないけど、少なくとも井原と僕はそういうような話をした。」
「『ずっと僕たち最初から最後まで一緒にいて、責任感じるよな。僕らこれだけ信頼されていて』って感じだった。」
加茂監督更迭が告げられたこの夜、選手たちは、とても眠れる心境になく、一人また一人とホテルのロビーに降りてきます。そして、いつの間にか議論になり、その議論が伯仲して心を一つにする決起集会の場になりましたが、カズ・三浦知良選手も一度は集会に顔を出しますが部屋に戻るとすぐに眠りに入り、そこで加茂監督の夢をみます。スタジアムに一人佇む加茂監督の夢を。
カズ・三浦知良選手は、これまでもそうであったように、チームを背負って立つ強烈な責任感と選手としての本能的なプレー意欲のまま、この最終予選を戦ってきたわけですが、加茂監督の退任によって強力な後ろ盾を失ってしまいました。
岡田監督の下では、カズ・三浦知良選手といえどもFWの一選手でしかなく、働きぶり次第では自分の立場が保証されたものでなくなっていたのですが、その後もカズ・三浦知良選手は、少なくともゴールという結果を出すことができないままイラン戦を迎えました。
そして後半18分、その時がやってきました。1990年9月に日本代表に招集されて以来、7年間にわたって、スタメン出場を果たした試合で、ケガ以外の理由で途交代した経験がないカズ・三浦知良選手が初めて途中交代を命ぜられました。
しかし、カズ・三浦知良選手はショックな様子を微塵も見せずベンチからチームメイトを鼓舞します。とにかく念願のW杯出場権を獲得するためにできることをしていました。
延長後半13分、岡野雅行選手のVゴールが決まると、カズ・三浦知良選手は真っ先に岡野選手のもとに駆け出し、チームメイトとともに歓喜の渦に溶け込みました。
これで念願のW杯の舞台に立てる。その喜びで一杯でした。日の丸を背負って場内を回るカズ・三浦知良選手には、その喜びが溢れていました。
最終予選を通じて押しも押されぬ日本代表の中心選手となった中田英寿選手、はた目からは淡々として見えた「最終予選」の胸の内は
中田英寿選手は、5月21日に国立競技場で行なわれたW杯日韓共催記念試合に代表初招集されると、さっそくスタメン出場、日韓戦という独特の雰囲気にまったく臆することなく司令塔としてフル出場でデビューを飾りました。
次いで、6月22日に行なわれたW杯アジア一次予選の日本ラウンド・マカオ戦もスタメン出場、前半17分には日本猛攻の口火となる先制ゴールをあげ、この試合2得点2アシスト、すっかりフル代表のレギュラーメンバーに定着しました。
日韓戦の前に行なわれたアジア一次予選オマーンラウンドで、アトランタ五輪代表の先輩格である前園真聖選手が一度もピッチに立たせてもらえず、加茂監督から「守らない選手は使わん」と日本ラウンドメンバーから外され、入れ代わるように招集されたのが中田英寿選手でした。
中田英寿選手は、アトランタ五輪代表の時も、当時の中心選手だった小倉隆史選手の大ケガにより、急拠招集され五輪代表に定着しています。通常の選考パターンとは違った事情のため、年齢的に少し早い招集チャンスをもらった形ですが、そのチャンスを一発でモノにする実力を持った選手でした。
このマカオ戦のあとのインタビューも、インタビュアー泣かせのそっけないもので、この頃から「クールな中田選手」のイメージは定着しつつありました。
このクールさは、決して外向けに取り繕ったものではなく、常に冷静に物事を見ている中田英寿選手そのものだということを、まだ多くの人たちは気づいていないのでした。
すでにアトランタ五輪代表時代から中田英寿選手に密着していたジャーナリストの金子達仁氏も97.12.4Number432号「密着ドキュメント 中田英寿と川口能活の63日」の中で、次のように書いています。
「私は、予想していなかった。最終予選が目前に迫っても、そして9月7日のウズベキスタン戦が終わっても、その戦いがあれほど苦しいものになるとは。正直、まったく予想していなかった。」
「6-3という派手な試合が終わった直後、中田英寿の口から意外な言葉が漏れるのを聞いても、ただの取り越し苦労だと思っていた。」
「『フランス、行けないかもしれないよ』彼はそう言ったのだ。(中略)」
「『だって、勝ったとはいっても内容はひどかったじゃないですか。攻撃に関する約束事がなにもないっていう問題は依然として残っていたわけだし、あれで喜べっていうのは無理な話でしょ。もっと気になったのは、まるでワールドップ出場が決まったみたいにはしゃいでいる人たちがいたことかな。選手はもちろん、スタッフの中にもそういう人はいたし、大体、メディアが凄かったでしょ。実体が伴ってないのに空騒ぎしてるって感じがして、それで”行けないかもしれない”って。(中略)でも、俺だって、あの時点では何とかなるって気持ちのほうが強かったんですよ。本当にまずいぞって思ったのは、第2戦が終わった時ですね。』」
実は中田選手、第2戦のUAE戦でスタメン出場したものの、途中交代で退いています。この時、いかにチームの戦い方に不満があっても監督批判ば絶対にできないと心に決めていました。それは前年のアトランタ五輪本大会での第2戦・ナイジェリア戦で起こした、いわゆる「ハーフタイム事件」の経験があったからです。
もし、自分に見えているチームの問題点を率直に話してしまえば、それは監督批判、チーム批判になってしまう、いきおい中田選手の口は重くなり、外向けにはそっけない内容になっていきます。
しかし中田選手の胸の内にしまわれていたUAE戦についての本音はこうだったのです。
「俺、UAEは”勝ちにいかなきゃいけない相手”だったと思うんです。それを、チームが自ら望んで引き分けにもっていって、しかも、それで喜んでる人たちがいる。もし勝ちにいって、結果的に勝てないのは仕方がない。でも、勝てる試合を自分で捨てちゃったのが信じられなかった・・・。」
第3戦の韓国戦を前にした公式会見には中田英寿選手が指名されましたが、記者とのやりとりは、まさしく記者泣かせのそっけないものになってしまいました。
試合当日朝のスポーツ紙「日刊スポーツ」には「のらりくらりの中田節を連発、懸命に質問を浴びせる韓国報道陣をけむに巻き、一触即発ムードを漂わせた」のリード文とともに、会見内容が載っています。
【中田と韓国報道陣のやりとり】
━ 韓国戦についてどのように思ってますか。
【中田】 どのようにと言われましても・・。幅が広すぎるんで。もうちょっと(質問を)絞ってくれませんか。
━ 試合に臨む姿勢は
【中田】 普段どおりです。
━ 韓国の印象は
【中田】 よく走るチームですね。
━ 自分の役割は何か、また、勝利の可能性を選手たちはどう思っているのか。
【中田】 役割は得点に絡むこと。可能性はやってみないと分からないし、だれがどう考えているかも知らない。
━ UAE戦で途中交代したのはケガなのか。
【中田】 (隣に座った広報が耳打ちいた後) 交代のことは監督に聞いてください。
━ 現在のコンディションは
【中田】 やってみないとわからない。
━ 韓国の選手の特徴はわかっているか
【中田】 特徴とかは、やってみないとわからない。速さとかは自分がやってみてわかるものですから。
━ 過去の韓国戦で印象に残った選手は
【中田】 (苦笑いをしながら) 名前を見てやっているわけじゃないので分からない。
実は、その前に行なわれた韓国の公式会見には崔竜洙(チェ・ヨンス)選手が指名され出席したのですが、崔選手は「私から話すことは何もありません」と宿敵を意識したムードの対応だったために、中田選手の会見はその意趣返しではと勘繰る向きもありましたが、決してそうではありませんでした。
中田選手の受け答えは決して舌足らずなものではなく、ある意味、そのとおりだよね、そうしか答えようないよね、と思わせるものですが、記者側からすれば「のらりくらりとはぐらかされた」ようにしか聞こえないことも確かです。
この先も日本国内での会見では常にそうですが、中田選手の会見は、相手チームに対するリスペクトの意味を込めるとか、記者団にリップサービスするとか、謙遜するとか、自信を示すといった、余計なものを決して混ぜ合わせたりしない話し方を徹底しています。
まだ20歳の青年が、百戦錬磨の記者団を相手にしても、なんら動ずることなく過不足のない会見をこなしてしまう事実には驚くばかりです。
その韓国戦に敗れたあとからの中田選手の心の軌跡について、前述の金子達仁氏のレポートを続けます。
「『韓国に負けた段階で、これはよほどの運がないとフランスには行けないぞって覚悟はしたんですよ。そしたら、運どころか、カザフで引き分け、ウズベクではスタメン落ちでしょ。あそこで一度、俺の中では完全に糸がきれちゃいましたね』」
ここにある「あそこで一度、俺の中では完全に糸がきれちゃいましたね」という心理状態は、興味深いことです。これについて、のちにテレビのニュースステーション(12月8日・テレビ朝日)に出演した中田英寿選手が、番組の小宮悦子キャスターからの質問に、こう答えています。
小宮 やっぱり一番の「谷」はアウェーのカザフ戦あたりですか?
中田 う~ん、アウェーのカザフ、ウズベキ戦あたりでは、自分の力ではどうしようもないという感じて、ある程度、運に任せてやるしかないかなとは思いましたけど。
小宮 ちょっと、きれたことがあったって聞いたんですけど・・。
中田 そんなことないですよ、全然きれてないですけど、まぁ、自分の力だけではどうしようもないところもあるんで。
小宮 あとは運を天に任せるしかないと・・・。
つまり中田選手の言う「きれた」というのは「自分の力だけではどうしようもない、運に任せてやるしかない。そう思ったから張りつめていた糸が切れた」という心理状態を説明した言葉のようです。
何という自信でしょうか。「自分の力だけダメな場合は、あとは運に任せるしかない」言い換えれば、自分一人ではできないことだからチームメイトの力を頼るとか、チームメイトを信じるといった思考ではないのです。
おそらく中田選手のこうした思考スタイルは、このあと引退するまで変わらないスタイルだったのではないでしょうか。
中田選手のそういう心理的な変化は、張りつめた糸が切れたことからすれば、練習にも少し影響が出たのではないでしょうか。岡田監督は、そのあたりを鋭く見てとったのかも知れません。ウズベキスタン戦ではスタメンを外されています。
再び、前述の金子達仁氏のレポートを続けます。
(注・ウズベキ戦の) 後半8分、中田はフィールドにたった。『前半から出場できてたらなぁ・・・。1点を取るまで、ウズベキスタンは完全にビビッてたから、中盤はスカスカだったでしょ。ハイクロスなんか使わなくても、十分に崩せた相手だったと思うんだけど・・・・』」
金子氏はウズベク戦でスタメンを外された時の中田選手のベンチでの様子について、こう例えています。
「勝たなければいけない試合のベンチで能天気な笑いを浮かべることがどれほど周囲に違和感を与えるかは、彼も十分にわかっていたはずである。いや、むしろ彼は違和感を持って欲しかったのかも知れない。(中略) ちょうど、教師の寵愛を失った生徒が、反抗的な態度を取ることで、注目を取り戻そうとするように・・・・。」
UAE戦について胸のうちにしまっておいた本音もそうですし、ウズベク戦の戦い方についても言えるのは、中田英寿選手という人は、自分の見立てのほうが正しいはずだという強烈な自負心を持つ人だということです。並みの人ならば、仮にそう思っていても、結果としてどうなるかわからないことを考えれば、そう断定的なことは言えないものですし、そういう言い方はしませんが、中田選手は、自分の見立てのほうが絶対正しいから、そうしなかったチームのやり方が信じられないとまで言い切るのです。
こういう思考スタイルが、まさにアトランタ五輪の第2戦・ナイジェリア戦のハーフタイムのような事態を引き起こすわけで、こういう並外れた感覚の持ち主が1人チームにいるということはチーム自体が穏やかでは済まないことを意味しています。
さきほどご紹介した、ニュースステーション(12月8日・テレビ朝日)の中で、カザフスタン戦の後の監督交代を受けて、選手たちだけで行われたと言われるミーティングについて、小宮悦子キャスターと中田英寿選手が、こんなやりとりを交わしています。
小宮 カザフスタン戦のあと、選手だけでミーティングしたっていうのはホントなんですか?
中田 うそです。
小宮 うそ? 大量のお酒を飲んで朝までミーティングやったって・・・。
中田 たまたまリラックスルームみたいなところにチョボチョボ集まって飲んでたっていうことはホントですけど、ミーティングしたとか、そういうことではないですね。
小宮 フーン、サッカーの話したってわけじゃないんですか?
中田 そうですね、他愛もない話したり、サッカーの話している人もいたとは思いますけれど・・。
小宮 決起集会っていう感じではなかった?
中田 ただとりあえず発散したという・・・。
小宮 あぁ、伝えられていることとはずいぶん違いますね?
中田 ま、よくあることです。
と答えています。他のイレブンが聞いたらどう思うのでしょう。「そのとおり、他愛もない話だったんだよ」と思っているのでしょうか?
選手たちの結束を深める絶大な効果があったとされるこのミーティング、自然発生的な集まりだったとはいえ、多くの選手たちが「あれで気持ちが一つになった」と伝えられているこの集まりは、針小棒大に誇張されて伝わっただけなのでしょうか。
もし「チョボチョボ集まって飲んでた、なんてもんじゃない。」「自然発生的ではあったけれど、濃密なサッカーの話ができた夜だった。」「決起集会とまでは言わないにしても、意義あるミーティングだった」ということが真実に近いのであれば、中田選手の受け止め方はとてもノーマルとは言えません。
逆に中田英寿選手の受け止めのほうが真実に近いのであれば、ただ発散した程度の集まりを、大げさに美化して伝えた側の、歪んだ意図を感じてしまいます。
果たして、どちらが実相なのか「歴史の法廷」での裁きに委ねたいと思います。
このように、並外れた感覚の持ち主である中田英寿選手ですが、だからと言って弱いところなど何もないのかと言えば、決してチーム内の仲間には見せない弱みを、金子達仁氏には打ち明けています。金子氏のレポートを続けます。
「『体質、これはホントにコンプレックスです。(中略)俺みたいな職業についていながら、野菜が食べられない、疲れるとアレルギーが出てくるっていうのは、正直、結構なコンプレックスになってますね。』」
中田選手は、食事上のハンディキャップからくる疲労の問題を言い訳にしないため、人知れず苦労していることは確かでした。
ジョホールバルでの第3代表決定戦の頃も、相当身体がこたえていた時期でしたが、イラン戦の延長後半13分に見せた「俺がきめなきゃ」という確固たる意思を持って始めたドリブルとその先に起きた岡野選手のVゴールは、これまで語ってきた中田英寿選手の見立てが間違っていないことを自ら証明するプレーだったのです。
金子達仁氏は、イラン戦のあと97.12.12Number433号「独占インタビュー・中田英寿」を行なって、最終予選全体を中田選手に振り返ってもらっています。
【金子】オリンピック代表の時は、はっきり言って君の態度にカチンと来てる選手はいたわけだし、人間関係でのトラブルもあったと思う。それが今回、外から見てると非常にスムーズに行ってるなって気がしたんだけど。
【中田】向こうが気をつかってくれたっていうのが大きかったですね。(中略)オリンピックの時と違ったのは、俺がキレかけた時になだめに入ってくれる選手がいたってこと。たとえばナナ(名波)とかね。
【金子】(注・イラン戦では)試合の途中から不思議なぐらいに怒らなくなったよね。前半は岡田さんとも怒鳴り合う場面もあったのに、後半に入ると状況は悪化してたにもかかわらず、怒る場面がなくなった。それどころか、リーダーの風格さえ漂うようになった。特に後半18分、カズが交代してからはね。あの時から、自分がやらなきゃという思いが強くなったんだろうか。
【中田】いえいえ別に、そんなことはありません。
【金子】でも怒らなくなったのは事実だし、延長が始まる時なんかは守備陣に向けて手まで叩いていた。頑張れ、頑張れって。こっちは一瞬、ヨハン・クライフの姿がダブったよ。傲慢でエゴイストと言われてて、でもリーダーシップがあってっていう。
【中田】僕は傲慢でもエゴイストでもないと思いますけどねぇ・・・・。ただね、あの試合に関しては、途中からサッカーがすごく楽しくなってきたっていうのはある。イメージ通りのサッカーができるようになって、感情が高ぶってきたってのはね。ほら、岡野と城ってのは、俺がずっと前からコンビを組みたかった選手なわけだし。ま、リーダーシップっていう点に関しては、ずいぶんとみんなビビッてて異常なぐらい静かだったんで、俺が声でも出して盛り上げるかな、と。」
【金子】延長に入ってから、岡野にズバズバとラストパス通してたよね。でも、一向に決まらない。苛立ちはなかったんだろうか。
【中田】なかったですね。全然。ずっこけたのはあったけど。
【金子】GKと1対1になった岡野がシュートを打たずに折り返してきたシーン?
【中田】そう。いやね、岡野はシュートを打たないだろうなってのは予感してたんですよ。彼は最終予選初出場だし、ビビってるのはわかってたから。(注・岡野に)パスを出した瞬間、あ、これは打たないでDFにクリアされるんじゃないかなって思ってたら、ドンピシャリでしょ。あのとき俺はのけぞったんじゃなくて、ずっこけてたんです。腹はたたなかったなぉ。面白いと思うぐらいの余裕がありましたもん。あの試合は9試合の中で一番楽しかったです。
【金子】決勝ゴールの話をする前にもう一つ、あの場面の直前、ダエイの決定的なシュートがあったけど覚えてる?
【中田】あれはね・・・・。完全にやられたと思いましたよ。ただ、ダエイもだいぶ疲れてたようで、シュートのポジションに入るのがちょっと遅れたのと、軸足がよれてたのが見えたんです。それで、あ、もしかしたら大丈夫かな、と。
【金子】さて、それじゃ最後の場面について聞こうか。試合直後は「俺が自分で決めるしかないって思った」って言ったけど。
【中田】ホントにそう思ってましたよ。地面は濡れてたし、GKはケガしてる。サイドネットに一直線って絵が見えたような気はしたんですけどねぇ。
【金子】シュートがGKのケガしている手の方に飛んだ。あれは狙ったの?
【中田】当然
【金子】GKからしたら最悪の奴だなあ。
【中田】俺にも”爆発的なシューター”とか”俊敏なゴールゲッター”とか呼ばれてた時代がありましたからね。いまは状況がパッサーであることしか許してくれないけど。
【金子】岡野が決めた瞬間は?
【中田】やっと終わったって感じ。ああ、これで練習しなくいいんだなぁって
【金子】昔のビデオとか見てみると、ゴールを決めるたびにガッツポーズを連発してるし、もっと素直に喜んでたけど、どうして喜ばなくなったの?
【中田】どこでゆがんじゃったんですかね。いやいや・・・。ま、慣れですよ、慣れ。(中略) 世界大会も4度目になると、出場を決めたぐらいじゃ感情が爆発するなんて感じはなくなるもんなんですって。
【金子】そう言えば、大会前は”出場が決まったらたぶん泣くと思う”って言ってた川口もまるで泣いてなかった。挙げ句 ”今になって、なんでヒデがオリンピックの時に泣かなかったのがよくわかった”なんて言ってた。
【中田】でしょ。そういうもんなんですよ。
最終予選の前半のほうは、加茂監督の采配やカズ・三浦知良選手を軸とした攻撃陣の不振がクローズアップされて、中田英寿選手のことがクローズアップされる機会が少なかったこともあり、中田英寿選手が最終予選前半の時期、どういう心境だったのか、わかりにくかったのですが、今回つぶさに文献を拾っていくと、チームの戦い方に多いに不満を抱きつつ、中央アジア遠征の頃は、もはや「糸が切れてしまった」状態に陥っていたことがわかります。
それでも、中田選手自身が述懐しているように、年代がほとんど同じのアトランタ五輪メンバーとは異なり、いわゆる「大人」が多い今回のメンバーの中で、中田選手が周囲に支えられながら(言い換えれば上手に持ち上げられながら)、チーム内に決定的な亀裂を作ることなくイラン戦を迎え、最後は「あの試合は本当に楽しかった」と振り返るほど、思い通りのプレーができたということもわかります。
後の項で山口素弘選手の「最終予選」を紹介していますが、山口選手は、最終予選に入ると、ことあるごとに中田英寿選手に「お前が中心になってやるんだ、遠慮なく攻めろ」と背中を押しています。
その言葉を中田英寿選手が、どのように受け止めていたのか、本人の言葉が見つからないのでわかりませんが、第3代表決定戦のイラン戦の時だけは、山口選手にそう言われて中田選手が「本当にいいの? 好きなようにやるよ」と嬉しそうに答えたそうです。
それまでは、遠慮なくやろうとしても相手のマークや守りにエネルギーが割かれて、やりたくてもできない試合が続いたのかも知れません。そしてイラン戦は、自分が自由に動ける状況だったことから「あの試合は本当に楽しかった」と振り返るほど、思い通りのプレーができたのかも知れません。
そうだとしても、山口素弘選手や名波浩選手をはじめとした先輩たちの気遣いが、中田選手にとって居心地のいい環境だったことは疑いようがありません。
中田英寿選手は「(注・第3戦の)韓国に負けたあと、これはよほどの『運』がないとフランスには行けないぞ」と思ったそうです。やや意外な気がしますが、その論に従えば、中田選手は「よほどの運をもっていた」ということになります。それは中田選手のみならず、今回の日本代表全体に当てはまることですし、そして、最後まで絶対あきらめない気持ちの強さとか、講じた手立てとセットになって引き寄せられた「運」だと思います。
果たして中田英寿選手は「最後まで絶対あきらめない気持ちの強さとか、講じた手立てとセットになって引き寄せられた『運』だ」という見立てに同調してくれるでしょうか。
おそらく、こう答えるのではないかと思います。「よほどの運をもっていたのは日本代表も同じだとか、そういうことは考えたこともないです。あきらめない気持ちが「運」を引き寄せたとかについても、そう思う人はそれでいいと思います。」
ジョホールバル・イラン戦、起死回生の同点ゴール、そのあと、頭部激突で一時的に記憶が飛んでしまったあとに見た岡野選手の歓喜の激走、城彰二選手の「最終予選」
城彰二選手は、第3代表決定戦、マレーシアのジョホールバル・イラン戦、起死回生の同点ゴールを決めました。そのあと、イランGKの選手と激突、頭部を強打したため、一時的に記憶が飛んでしまったそうです。そのあとパッと意識が戻った時、中田英寿選手のドリブルからのシュート、そして、こぼれ球に反応した岡野選手のVゴールを目にしたといいます。
城選手は、のちにこの最終予選全体を振り返って、自身の著書「エースのJ0・炎のストライカー城彰二の素顔」(城彰二著1998年2月リヨン社刊)の中でこう述べています。
「(注・岡田さんが最初の指揮をとったウズベキスタン戦) 俺が、この試合で感じたのは、何ごとも最後まで絶対あきらめちゃいけないってことだった。(中略)これで負けたら最後という状況では人間の心理はネガティブになりがちだ。もうダメだ。俺だってロスタイムに入った時はそう思いかけた。でも、岡田監督は最後の最後まであきらめなかった。」
「あきらめずに今考えうる最善の策を自信をもって実行した。執念とも言える勝利へのあくなき渇望がロペ(注・呂比須ワグナー選手)の同点弾を生んだ。俺は今でもそう思っているし、その姿勢には本当に感動した。」
「(注・ホームのUAE戦に引き分けて) ロッカー内は大荒れだった。アイスボックスを蹴り上げる者、ロッカーをブッ叩く者、選手のイライラは頂点に達していた。」
「その時、岡田監督がみんなに注目するように言った。」
「『みんな、まだ終わったわけじゃないぞ。まだ、フランスに行ける可能性があるんだから、引き分けぐらいで下を向いてもらったら困る。俺たちは1%の確率がある限り最後まで戦う。望みを捨てないで、最後まで戦うんだ』 岡田監督のその言葉に感動したね。みんなも『そうだ! そうだ! まだ、あるんだ!!』って盛り上がった。それで暗かった重苦しい空気が一気に霧散した。」
「(注・アウェー韓国戦のため)ソウルに行く前に、俺は岡田監督と話をした。『彰二、次はロペで行くけど、あきらめるな。必ずチャンスを与えるから、その時は頼むぞ。おまえを出す時は最後の最後かもしれない。でも、その土壇場になったら、もうおまえしかいないんだから期待している。それまでコンディションを崩さず我慢してくれ』 そう言われたら、俺は黙ってうなずくしかなかったよ。」
「でもさ、監督にそういうふうに言われるとうれしいよね。自分の気持ちも盛り上がるし、じゃあ出番が来るまでがんばろって思うじゃない。岡田監督は絶対うそはつかないって、ジェフのコーチ時代から知っていたからさ。だから、俺は監督の構想に入っているんだ。俺を使うっていう構想はあるんだってことがわかってホッとした。」
「韓国戦、勝ったはいいけど、カズさん、ロペが累積警告で次のカザフスタン戦に出場できなくなったんだ。その代わりに高木(琢也)さん、ゴン(中山雅史)さんが招集されることになった。」
「俺は、2人のFWが欠けるわけだから仕方ないと思っていた。でも、だれが入ってきても負ける気はしなかったし、ポジションを譲る気持ちはなかった。『このポジションだけは絶対に渡せない』 そういう対抗意識丸出しで合宿に参加した。」
「11月8日(注・ホーム・カザフスタン戦) あの試合、中山さんがゴールした時に、自分のユニフォームの下にカズさんのユニフォームを着てたのを見せたでしょ。実は、俺もカズさんのユニフォーム着てたんだよね。きっと、だれも知らないと思うけど、試合前、カズさんが『この試合、がんばってくれ』って、声をかけてくれたので、その気持ちをユニフォームに託したいって思ってね。(中略)ゴールしたら、俺もハデなパフォーマンスしようかなって思ってたけど、それは見せられなくてちょっとだけ残念だった。でも勝ててよかった。」
「(注・第3代表決定戦・イラン戦) 後半14分。1-2ついにイランがリードしてしまった。『ヤバい』俺はこのまま終わってしまう恐怖にかられていた。同時に出番が近づいているのを実感した。(中略)俺は、頭の中で、最初にロペが呼ばれて、残り10分ぐらいでくるかなと読んでいた。そして後半21分、最初にロペが呼ばれた。予想どおり最初はロペか。俺は『頼むぜ』とロペを送り出した。するとすぐに、『城、おまえもこい』 えっ、て一瞬耳を疑ったよ。本当かよ、と思っていると小野コーチが手招きしている。どういうことだって思ったね。まさかカズさんとゴンさんの2トップをいっぺんに代えるなんて思いもしなかったから、すぐに出られるように傍にいろってことなのかなって思った。」
「行くと岡田監督が『ふたり一気に交代する』と厳しい口調で言った。俺はびっくりしたよ。最初はロペが行くもんだって、自分の中で決めていたから、心の準備がまだできていなかったんだ。でも、出れると思ったらワクワクしてきた。やっとチャンスが来たよ。今までの鬱憤を晴らしたるって思ったね。」
「しかし、状況は一進一退を繰り返すのみ。このまま終わるのはイヤだと心の中で叫んでいた時だった。ヒデの視線が俺に飛び込んできたんだ。(中略)俺は、ヒデと目が合った瞬間、まずGKの位置を確認した。GKは中央やや左寄りにいたので、俺は右スミを狙ってやろうと思っていた。ヒデの視線は、行くぞと合図していた。俺は、その合図に合わせて、ボールがくるだろうという地点へと動き出した。」
「俺にはDFがひとりピッタリとはりついてたんだ。しかも、裏に入りすぎたので、このままボールをもらえばオフサイドになってしまう。そう思って1回外へ逃げた。結果的に、その動きがDFの判断を一瞬惑わすことになった。」
「ヒデの左足で蹴られたボールは外側に巻くように飛んできた。自分の視野の中に、シュートポイントとボールの軌道がバッチリ見えていた。」
『よーっしゃ!! 』
「そのまま再び内側に飛び込んでヘディングした。」
「後半31分、同点ゴール。その瞬間、俺の頭は真っ白になっていた。ロペが両手を広げて抱きついてきた。そして、俺は、そのまま無我夢中になってコーナーに走り、1回転した。」
「ようやく仕事ができたぁ! (中略)」
「あのヘディングシュートは基本どおりで完璧だった。」
「90分が終わると、予想以上に疲れている自分にびっくりした。後半から出場したのに、この疲労はなんだって思ったね。(中略)岡野クンとは、俺がサブで出れない時とか一緒にいて『必ずチャンスがあるから、がんばろうな』って言い合っていたからね。(中略)そんな岡野クンがこの最後の舞台で立てたことは、俺は自分のことのようにうれしかったんだ。でも、岡野クンの顔を見ると、なんか引きつっているんだよね。(中略)」
「延長後半も残り5分ほどになっていた。(中略)ヒデが入れたクロスは、ボールの勢いがなく、微妙な感じで入ってきた。その飛び込む瞬間にGKの位置を確認したんだ。でも微妙なボールだったから触れたらどうにかなるだろうって頭から飛び込んだんだ。」
『ガツーン』
「頭に何かがぶつかって、半分意識を失った。」
「俺はゴールマウス脇に倒れて、『だいじょうぶ』ってしきりに言っていたらしい。でも、その後すぐにヒデが俺の顔に手を合わせて何か言ったことも全然覚えていないし、自分がどこにいるのかもわからなかった。音も何も聞こえない。自分だけ別の世界にいるようだった。それでも俺は、何かしないといけない。なんとかしないといけないって考えていた。そういうのしか覚えていないんだ。(中略)」
「数分間、意識を失っていた俺は、いきなり蘇生した。ワーっていう歓声に意識が戻り、その時、ヒデが中央からドリブルしていく姿が見えた。」
『そのまま決めろ! 』
「その声が聞こえたのか、ヒデは渾身の力を込めてシュートした。それをGKが弾き、岡野クンがそのボールに走り込んできたのが見えた。時間的にもそれがラストチャンスだった。岡野クンはいつも決めるようにスライディングで、確実にボールをとらえた。(中略)」
「ゴールデンゴールを決めた岡野クンが激走している時、俺はグラウンドに平伏して号泣した。とにかくうれしかったし、ホッとした。」
「その夜、俺は最高に幸せな夜になるはずだった。しかし、ホテルに帰ると、GKと激突した時にぶつけた頭が痛くて気持ち悪くなってきた。グルングルン回る感じで、意識はしっかりしていたけど、頭は異常に重く、フラフラしていた。みんなが祝杯をあげている間、ベッドの中にいた俺の頭の中に浮かんできたのは、早く家に帰って眠りたい。ただ、それだけだった。」
城彰二選手の最終予選は、特に岡田監督が指揮をとるようになってから、生き生きとしてきたことがよくわかります。
城選手自身が岡田監督の指示やゲキに感銘を受け、それを信じて起用に応えようとする気持ちを高め、それがイラン戦での起死回生の同点ゴールにつながっています。
最後は頭部を痛めてしまい祝杯の夜をベッドの中で過ごすはめになりましたが「戦士よ、あとは、ひたすらお休み」と声をかけたくなるエンディングです。
サッカーを楽しむ気持ちが戻った時、幾つもの「ひらめき」が生まれ先制ゴールを突き刺したアウェー韓国戦、名波浩選手の「最終予選」
名波浩選手がフル代表入りしたのは、順天堂大学から磐田に加入して迎えた1995年8月6日、京都・西京極競技場で行なわれたコスタリカとの国際親善試合でした。この試合、スタメン出場を果たした名波選手は、いきなり前半44分、先制ゴールをあげ上々のデビューを飾っています。
1995年はこの試合を含めて2試合だけの出場でしたが、1996年に入るとコンスタントにスタメン出場するようになり、1996年5月26日に行なわれたキリンカップ・ユーゴスラビア戦からは背番号10を背負って出場、以降、長く日本代表の10番といえば名波浩選手という時代を築きました。
ところが当の本人は「背番号10」の選手に求められる世間のイメージのまま見られることを、ことのほか嫌っており、最後まで「背番号なんてただの番号でしかない。10番以外なら何番でもいい」と言い続けていました。
本人の意に反して背番号10を背負い続けたため、名波選手は日本代表に逆風が吹くたびに矢面に立たされ、時にはマスコミに叩かれ、時には心ないサポーターから直接罵倒される役回りに立たされ続けたのです。
名波選手にとって今回のW杯アジア予選は特別な意味をもっていたと言います。ここからは名波選手の幼少からフランスW杯出場権獲得までの軌跡を描いた「名波浩 泥まみれのナンバー10」(平山譲著1998年6月TOKYO FM出版刊)から抜粋してみます。
「僕にとっては、アジア予選そのものも凄く重要な戦いなんです。例えば中田がデカいこといえるのは、各年代でアジア予選を突破しているからでしょう? だけど僕は一度も突破していないんです。だからこそ、ワールドカップ予選でアジアを突き抜けたい」
いよいよ最終予選、緒戦のウズベキスタン戦を前に、名波選手はこう語っています。
「ほどよい緊張感をもって試合に臨みたいですね。そんな中でも”楽しさ”だけは忘れたくない。でも今回ばかりはそうもいっていられないかな。勝つという使命もあるわけで、楽しむってことは当てはまらないかもしれない。」
初戦を6-3で勝利した日本代表は第2戦をアウェーでUAEと戦います。
「どうせ僕が一番最初に交代されられると思いましたから、全力で飛ばしました。」
ところが猛暑の中でこれまでに経験したことのない奇妙な感覚に襲われたのは前半35分のことでした。
「寒いんですよ。冷えるって感じで。冬の寒さではなくて、冷や汗をかくような変な感覚なんです。しかもその汗も、ビッショリかいた後すぐにサラッと乾いてしまって。なんか体の循環の悪さが一気にそのまま出た感じでしたね。あんなのは初めて。まじめに、もうこのまま死ぬんじゃないかと思いましたよ。あれは言葉では形容しようがない気持ち悪さ。経験した人じゃないと分からないでしょうね。」
最初に交代させてもらえると思って、好守にわたり動き回っていた名波選手ですが、負傷交代で枠を1人使ってしまったこともあり、結局最後までプレーすることになり、まさに疲労困憊、歩くのもやっとという状態で、ゲームは引き分けに終わりました。
名波選手にとって、この第2戦は「分岐点」となったそうです。
「2ケ月半もの戦いの中で、好不調の波が絶対あるんです。(中略)だから個人的にもチームとしても、いかにそれを少なくして常に調子を上向きにできるかというのがポイントだと思うんです。僕の場合はUAE戦が分岐点でした。あそこまでは上向きだったけど、そこから調子は落ちていきましたから」
韓国戦、これまで相手選手にマークされた経験が数えるほどしかない自分にマンマーク、下り坂のコンディションに追い打ち
そんな名波選手に次戦の韓国・車範根監督の報道陣を通じたコメントが耳に入ってきました。「(韓国が)勝つためには、名波と中田にマンマークをつける」という内容でした。これを聞いた名波選手は「まさか」と思ったそうです。しかし、いざ試合が始まってみると、車範根監督の言葉通り、名波選手には柳相鉄選手が密着マークにきました。
「なんで、コイツがこんなについてくるんだ!! 本来ゲームメーカーであるヤツ(柳相鉄選手)が、大きな舞台であれだけ警戒心を持ってべったりマークしてきたんですからショックでしたよ。それで自分のイメージしていたプレーが全然できなくなりました。マークされたこと自体、生まれてこの方数えるほどしかないんですよ。プロに入ってからはまったくないし、戸惑いました」
とはいえ、名波選手はマークへの対応策を試合中にとっています。
「マークがつくんだったら、どんどん動いてやろう。激しく動いてマークを外そう。そして自分が動くことによって、三列目のボランチの選手にスペースを与えよう。サイドに張ったりもしたんですけど、それでもアイツ(柳相鉄選手)がついてきたんです。もうどうしようかと思いましたよ」
それでも名波選手の思惑どおり、ボランチの山口素弘選手が空いたスペースを活かして攻め上がり、見事なループシュートを決め日本が先制します。
しかし試合は韓国に逆転を許し、日本はホームで痛恨の敗戦を喫してしまいます。
名波選手もこの逆転劇のダメージをしばらく引きずっています。
「生涯でいちばん大事なゲームを落しちゃったんですからね。うつ病になるほどまでではなかったですけど、精神的にかなりショックでした。(中略)予選を突破するためには韓国が最大の敵といえるわけでしょう、その韓国に敗れてしまったんですから、ショックは大きかったですよ。」
しかし日本代表は休息なしで、敗戦の翌日、中央アジアに向けて出発しました。14時間半をかけて、ようやく到着したカザフスタン・アルトマイのホテルに着いて、一息ついた名波選手は知人にかけた電話の会話中、聞き捨てならないマスコミ報道を耳にします。
「━━━新聞やテレビでオマエが「体力面不足」と指摘されてるぞ。」
「マスコミの評価なんてどうでもいいけど、このことだけは凄く残念でした。たしかに韓国戦の後半はバテた部分もあったげと、別に何もしないでバテたわけじゃなくて、あの韓国戦は間違いなく最終予選の中でも、僕が一番動いた試合でもあったから・・・。」
「本当に僕のプレーを追いかけてくれている記者だったら、絶対に『体力不足云々』とは書きませんよ。別にマスコミに対して弁解しようとも思わないけど、またマスコミへの不信感が増したことは事実でしたね。こんなものかよ、って」
名波選手はUAE戦を境に下り坂になっていったコンディションに加え精神的にも閉塞状況の中にいましたが、チーム自体も中央アジアのホテル暮らしというリフレッシュの難しい環境の中で、長いトンネルに入り込んでしまったような状況でした。
迎えた10月4日のカザフスタン戦、名波選手は秋田選手のヘディングシュートによるゴールにつながるCKを蹴っています。その後、後半も残り6分となったところで本田泰人選手と交代でベンチに退きました。
ところがロスタイム、ベンチから痛恨の同点劇を目撃します。
その夜、加茂監督更迭・岡田コーチ昇格が選手たちに伝えられました。名波選手の受け止めはこうでした。
「事実を受け入れるのは難しいことでした。この日本代表は3年近くも加茂さんが作ってきたチームだし、加茂さんは僕を代表に呼んでくれた人だし・・・。みんなも同じ気持ちだったと思います。すぐに受け入れられた人なんていなかったはずですよ」
そして、井原選手を中心に行なわれた深夜のミーティングで侃侃諤諤やり合い「いろんな枝葉がたくさんついていたものを、みんなへし折って、一本の幹にした感じです。あの話し合いでチームが一つにまとまったことは間違いなかったですね」
次のウズベキスタン戦に向けて、気持ちを切り替えようとはするものの、この時期、日本代表の誰もがそうであったように、名波選手も精神的な面を立て直すことが難しく、ホテルのベッドに一人横たわると悶々とした気持ちが襲ったきました。
そんな時、名波選手のもとにも、あのFAXが届いたのです。川口能活選手、平野孝選手にも届けられた清水商の恩師・大瀧雅良監督からのメッセージです。文面の一字一字が心に沁みたそうです。
「見ている人は見ているなと感じました。大瀧先生は、精神面が悪いとはダイレクトには書かずに、励ましてくれたんです。(中略)精神的に弱くなっていた部分があったのは確かだったから。でも、逆に考えれば、メンタルさえしっかり戻りさえすればやれるんだっていう気持ちになれました。そして、後悔したくないなって。これを読んだことでそう思えるようになったんです。」
「名波浩 泥まみれのナンバー10」著者の平山護氏は、大瀧監督に「何を思い、教え子に筆をとったのであろうか」と聞いています。
大瀧監督は「精神的バックボーン(気概)を持っていない子は、精神状態が満杯で緊張の極致にいったときに ”戦い”ができない子になるなと。どこの国の選手でも、きちっと背中にバックボーンを背負いながら戦っている。なのに日本の選手は、格下を相手にしても弾き返されていたのが現状じゃないですか。『せっかくワールドカップ最終予選という大きな舞台に立っているんじゃないか』って。『苦しければ苦しいほど、そんなに楽しいことないじゃないか』って。『男として生まれてきたからには、やることはやろうぜ』って。『日本男児は逃げねえぞ』って、そういいたくてね」
この大瀧監督の真意をかみしめながら、もう一度、川口能活選手のところでも紹介したFAXの文面を書き写してみます。
「人生最高の時、苦しい時、厳しい時・・・・。力を発揮できるのが日本男児、逃げるな。正面から戦え。正々堂々と。そして自分を信じて、仲間を信じて・・・。」
戦いは続きます。10月11日アウェー・ウズベキスタン戦、この試合、名波選手は初采配となる岡田監督からこう指示を受けました。「オマエ、いままでの4試合でボールにたくさん触っていたのは1試合目だけだぞ。もっとボールを触りに行け」
そのとおり名波選手は格段にパスの数を増やしチャンスを演出しましたが結果には結びつかず、逆に後半31分、ウズベキスタンに先制を許します。
日本は流れを変えなければと後半36分名波選手を下げます。名波選手はユニフォーム姿のまま戦況を見つめ続けました。
「何も考えずに、試合を見ていたんですよ。もう駄目だとは一度も思いませんでした」
試合がロスタイムに入ったかという時、自陣から井原選手が大きくボールを前方にフィードしました。
名波選手は、ボールを呂比須選手が相手ディフェンダーと競り合いながらヘディングしたのを目で追いかけると、GKの横をすり抜けてゴールの外へ転がっていきそうに見ました。そして、ため息を漏らしました。「ああ、外れたか・・・」
「終わったとは思わなかったけど、外れたなって・・・」
ところが、カズ・三浦知良選手がボールを拾って、センターサークルへと走り出したので、名波選手は驚いて主審に目をやると「ゴール」のジェスチャー。日本は土壇場で追いついたのです。
試合後、ロッカールームから出てきた名波選手は、取り囲む報道陣に一言だけ発しました。
「まだ、諦めません。」
清水商・大瀧監督が代表練習場に、フェンス越しにかけられた「もう好き放題に、もっと遊び心を入れて」の言葉に自分を取り戻して
中央アジア遠征から戻った日本代表は、また静岡で次戦に向けた合宿に入りますが、そこに清水商・大瀧監督が見に来ました。大瀧監督の目には「まだ名波選手は精神的に疲れているように見えました。他の選手ではなく名波一人だけが疲れているように見えたんです。」
大瀧監督は練習を終えてロッカールームに戻ろうとする名波選手にフェンス越しに、意を決して声をかけました。
名波選手は、その時かけられた言葉が、またもや暗いトンネルから抜け出す「キーワード」になったそうです。
「もっと好き放題プレーしてもいいんじゃないか? もっと遊び心を入れてもいいんじゃないか?」
「大瀧先生がそう言ってくれたことで、もっと遊び心をプレーの中でも出してみようと、楽に考えられるようになったんです。(中略)普通はダイレクトに出さないような場面でも、その場の思いつきでダイレクトに出してみたり。組織の中で動く上で必要な決まり事は抹消できないですけど、それ以外はすべて排除して、思いどおりにやってみよう、と。子供が純粋にサッカーを楽しむようにね! 」
10月26日、国立競技場でのUAE戦、日本は先制したものの、依然として”勝ち方”を思い出せずにいました。名波選手はリスクを恐れずにイマジネーションの趣くままにパスを出し続けましたが精度を欠くパスが多くなってしまいました。
「気合いが入りすぎていたのが原因だと思うんです。僕自身がやってやろうと思いすぎていましたし、チーム全体も気負い過ぎていました。」
日本は最後までUAEの壁を崩すことができず1-1のまま試合終了。
日本は自力2位の可能性が消滅する引き分けでしたが、名波選手は「僕自身、長いトンネルの出口はもう見えていたし、この引き分けも僕らにとっては全然OKかなと思っていましたから。当然まだ諦めていなかったですよ」
しかし、一般の観客は名波選手のような前向きな考え方ができず、怒りの矛先を結果を出せない選手たちに向けてきました。
国立競技場の駐車場で暴動が発生しました。
しかし、名波選手には、この暴動以上にショックを受けた出来事がありました。それは、これまで何百試合も観戦に来てくれたおふくろさんからの言葉でした。
「次の韓国戦、(注・放送の時間帯が)家で一人で見る時間帯なのよ。お父さんも兄ちゃんも家にいないから。韓国戦に負けたら終わりだし、それじゃ(注・一人じゃ)怖くて見れない。家にいるより仕事に行ったほうが気が紛れるから、そうするね。」
「そうか、最終予選の俺は、おふくろが見れないって思うような試合をしてたんだ。それで大事な韓国戦を見ないでパートに行くって聞いて、ショックでしたよ」
そう思った名波選手は開き直りました。
「もう、自分の好きにやって、自分で楽しかったと思えればそれでいい。誰のためでもなく、自分のためにやろう。その結果、例えワールドカップに行けなくて周りががっかりしても別にいい。韓国戦は、自分のためにサッカーを楽しもう。最終予選が終わってみて、楽しい2ケ月半だったと思えるような試合をしよう。後悔だけはしないように」
10月1日、韓国・蚕室スタジアム、フィールドに立った名波選手があらためて自分にこう言い聞かせました。「自分のためにサッカーを楽しもう。」
すると、これまで背番号10とともに背負ってきた重荷がすっと降りていくのを感じたのです。
午後3時ちょうど、キックオフ。名波選手は笛と同時に猛然とボールに向かって走り出しました。開始わずか25秒、名波選手はセンターラインの左端付近で、相手選手をマークすると、そのパスを確実にインターセブト。普通なら近くの味方選手にすぐ渡す名波選手でしたが、この日は何と、前を向くとドリブルを開始したのです。ほとんど見せたことのない行動でした。
「一瞬のひらめきです。キックオフ直後に試してみたかったんです。」
ドリブルで10mほど進んだ名波選手の前に相手選手が近づいてきました。さぁ、名波選手はどうしたか。名波選手は相手選手を股抜きでかわして突破にかかったのでした。
「これもひらめきです。普段は相手に面と向かって突っ込んでいくようなことはあまりしないんですけどね。」
すると股抜きという屈辱的なプレーを許した相手選手はたまらず、自分の脇をすり抜けようとする名波選手の腕を掴んで倒してしまいました。
名波選手の「自分のために楽しむサッカー」はいきなりエンジン全開となりました。その1分後、センターサークルあたりで北澤豪選手とパス交換した中田英寿選手が、身体を開いたまま、自分の左横にいた相手選手の油断を見透かすように、左90度の方向にパスを繰り出しました。ボールはその選手の足元を抜け15mほど先にいたフリーの名波選手の足元にピタリと収まりました。
受けた名波選手は、相手DF2人をかわすように外側を向き、駆け上がってきた相馬選手のスピードに合わせた丁寧なパスを送ります。相馬選手は流れるようにボールをタテに運びダイレクトで中に折り返しました。
ボールはペナルティエリアの中、ほぼゴール正面にいた呂比須ワグナー選手に届きます。呂比須選手は相手DFを背負って、左足で触りましたが、無理にひっかけようとせず流すようにして、自分はつぶれる形になりました。
その後ろには、カズ・三浦知良選手がやはりDFを引き連れて、自分の後ろ側にスペースを作る形になりました。そこに上がっていたのが、さきほど相馬選手にパスを出した名波選手でした。
ボールはちょうどペナルティスポットのあたりです。GKと1対1になった名波選手はほとんど助走なしで左足で、狙いすましてゴール右隅にボールを蹴り込みました。ボールは狙い通りに右ポストの内側からゴールインして行きました。
前半開始2分、あっという間の先制点でした。
実はこの試合前、名波選手は岡田監督から「開始15分間はあまり上がるな」と指示を受けていたそうです。名波選手はこう振り返りました。
「韓国のリベロは、この時、洪明甫ではなく19番の選手だったんです。そいつが僕のパスで完全にナオキ(相馬選手)のほうに振られて、真ん中が2対2の状況(呂比須選手とカズ選手のマークのみ)だったんで、思い切ってゴール前に走り込んだんです。」
監督の指示より「ひらめき」を信じたプレーでした。
前半18分にはNHK-BSで解説を務めていた木村和司さんが思わず「私もウラをつかれました」と唸ったトリックプレーが飛び出します。
ペナルティエリアから10mほど下がったゴールやや左寄りのところで北澤選手がファウルを受け、日本がフリーキックを得ます。ボールサイドにカズ・三浦知良選手と名波選手、やや離れて中田選手の3人が立ちました。
そこで名波選手が「あれ、やろう」と提案したのです。カズ・三浦知良選手が「いいな、やろう」と言って、ボールをチョンと浮かせました。浮いたボールを名波選手がポヨンと前方に出すと、ちょうどDFの壁を越えて、そのウラで待っていた北澤選手のところにピタリと落ちました。北澤選手は、あまりの絶好球だったのか、見事なほど空振りしてしまい、ゴールとは行きませんでしたが、まさに名波選手の遊び心全開のトリックプレー、解説の木村和司さんが「完全にウラをつかれました」と唸ったプレーでした。
このトリックプレーは練習で見ていた岡野雅行選手が「ポヨン」と名付けていたことから、これをやる時の合言葉は「ポヨン」ということになっていました。
「練習でもあんなに上手くいったことないんですよ。パーフェクトでしたね。あの場面でポヨンができたっていうのも、きっと気持ちに余裕があったからでしょうね。」
韓国にアウェーで2-0の勝利を収めた日本に、翌日、朗報が届きました。UAEがホームでウズベキスタンに勝てず引き分け、これで各7試合を終え日本が2位、最終戦カザフスタン戦に勝てば、第3代表決定戦に進出できます。
第7戦・韓国戦以上に思い通りにサッカーができた第8戦・カザフスタン戦
もう名波選手は完全に「サッカーを楽しみながら勝ちに行く」モードに切り替わっていましたから、カザフスタン戦もポジティブ全開でした。
名波選手は、のちに、前の試合韓国戦をベストゲームにあげず、このカザフスタン戦をベストゲームにあげています。
「名波浩 泥まみれのナンバー10」著者の平山護氏は、それを裏付けるカザフスタン戦のデータを著書の中で紹介しています。
「この試合で名波が放った縦パスは、実に37本、そのうち受け手に通ったのは、得点につながったものも含めて32本、オフサイドを取られたスルーパス3本を除くと、パスミスはわずかに2本である。この試合は、左サイドで攻撃の起点となった名波を中心に回っていたといっても過言ではない。」
それだけではありません。日本の5ゴールのうち3点がセットプレーでした。1本は先制点となった中田英寿選手から秋田豊選手へのFKですが、あとの2本は名波選手のセットプレーです。
特に前半は、名波選手が左足で巻いて蹴るセットプレーのほとんどを中山雅史選手に合わせたといいます。中山選手は前半44分、名波選手が蹴ったFKに身体ごと飛び込むようにしてヘディングシュートを決めました。
「中山さんはあのゴールまで、多くのチャンスを活かせていなかったでしょう。だから交代させられちゃう前に、どうしても中山選手に決めて欲しかったんで、セットプレーは全部中山さんに合わせようと決めていました。」
なんという大胆さでしょう。大事な試合だというのに、セットプレーのシチュエーションがどれも中山選手に合わせるのがベストというわけではないはずなのに、何でもかんでも中山さんに、というわけです。
同じチームメイトということもあり、コンビネーションは、まさに以心伝心の間柄だと思いますから、それが、むしろ自然な成り行きだったかも知れません。中山選手が決めたゴールなどを仔細に見ると、まさしく中山選手が中央の密集から外れて大外から入り込んでいます。
大外からの走り込みは、残りもう1本のセットプレー、後半22分の井原選手のボレーシュートもそうでした。2人の完全なサインプレーです。
なるほど、この試合は、名波選手にとっては思い通りに運べた試合ということが、よくわかります。
韓国戦とカザフスタン戦での名波選手のブレーぶりを見ていると、サッカーというスポーツが、イマジネーションを働かせれば働かせるほど、いかに、いい結果につながるかを余すところなく示しています。
名波選手は、このあとも、おそらく最後まで「背番号10」を背負わされていることを、心の中では受け入れることなくプレーし続けたことと思いますが、実は、この2試合のようなイマジネーションに溢れた、遊び心満載と言えるようなプレーこそが「10番」に相応しいプレーだと思うのでです。もし名波選手が、そのことを言われたら、さぞ複雑な気持ちになることでしょう。
「チームの司令塔として責任を持って」とか「10番にふさわしい働きをめざして」といった考えはまったくなく、むしろ純粋にサッカーを楽しむことに集中した結果、紡ぎ出されたプレーが「10番のプレーだ」と言われて、困ったような顔をする名波選手の顔が目に浮かぶようです。それがサッカーの奥深さなのかも知れません。
さぁ、最終予選は最後の第3代表決定戦、マレーシア・ジョホールバルでのイラン戦で決着をつけることになりました。
試合は2-2のまま延長に入り、先にゴールを決めたら試合終了という手に汗握る展開の中、延長後半13分、中田英寿選手のドリブルからのシュートを相手ゴールキーパーが弾いたところに岡野雅行選手がつめてVゴール、とうとう日本サッカーが重い世界の扉を開けた歴史的結末となりましたが、実は、日本の1点目(中山の先制ゴール)も2点目(城の同点ゴール)も名波⇒中田のホットラインから生まれています。
名波選手が「サッカーを楽しむ」と気持ちを切り替えてから3試合目、名波選手と中田選手の出し手と受け手の関係がしっかりと出来上がったことを感じさせる2点でした。
韓国戦こそ先制点をあげた関係でメディアも名波選手にスポットライトを当てましたが、カザフスタン戦、イラン戦とも、これだけ勝利への貢献度が高かった割には注目されていません。
ですから、ともすれば埋没しかねない名波選手の働きぶりを、ここでしっかりと記録に残し記憶に留めることに大きな意義を感じます。名波選手自身が「勝利の立役者」などと持ち上げられることなどに、まったく頓着しない選手ですから、なおのことです。
最後に「名波浩 泥まみれのナンバー10」(平山護著)をしめくくるように語った名波選手の言葉を紹介して締めたいと思います。
「僕自身は目立たなくてもいいんです。自分のことを人を輝かせるために働くプレーヤーだと思ってますから。自分より、仲間が働いてくれたほうがいいんです。点がとれない中盤とかいわれることもあるけど、自分が取らなくても、誰かに取らせることができればいいだろって思っていますよ」
加茂サッカーの申し子として、ベテランと若手を繋ぐ役割、守備陣と攻撃陣を繋ぐ役割を愚直に果たし続けた山口素弘選手の「最終予選」
山口素弘選手は、1991年、東海大学から加茂周監督率いる横浜フリューゲルスの前身・全日空サッカークラブに入団しています。
日本代表にはファルカン監督時代にも招集されていますが出場機会はなく、加茂監督が日本代表に就任して最初のメンバーに招集され1995年1月にサウジアラビアで開催されたインターコンチネンタルカップ初戦のナイジェリア戦でさっそくスタメン出場しています。
以来、この年1997年も不動のレギュラーとして加茂サッカーの心臓部を担い続けました。
オフト監督が森保一選手を見出して代表に定着させ「オフトサッカーの申し子」と呼ばれたように、加茂監督も山口素弘選手を守備的MFとして抜擢、「加茂サッカーの申し子」として期待に応えてきました。
その山口素弘選手の最終予選も、他の選手同様、波瀾万丈の連続となりました。山口素弘選手のポジション・守備的MFは、DFを4バックにするか3バックにするかで、果たす役割がまるで違ってくるポジションです。
加茂監督は、チームの指揮を執り始めてからずっと4バックシステムを採っていたため、山口素弘選手のところには相棒として本田泰人選手とか名波浩選手が並び、攻撃と守備のバランスをとりながら試合を進めることに慣れてきましたが、1997年に入りDFを3バックシステムに組み替えたことから、山口素弘選手はワンボランチとして守備に回る比重が格段に増えてしまいました。
結局、チーム戦術として攻撃に入る場面では4バックシステムに切り替えるという約束事を加えたのですが、最終予選初戦のウズベキスタン戦で3失点してしまい、どうしても中盤で効果的なプレッシャーがかけられない弱点をつかれたのでした。
続くUAE戦を引き分けて、日本は第3戦のホーム韓国戦を「勝たなくてはならない」ムードで迎えてしまいました。
韓国戦は相手の布陣に対応して4バックシステムで戦うことになり、山口素弘選手も「これでようやく日本のサッカーができる」と気合が入ったそうです。
その韓国戦で、山口素弘選手は、自身のサッカー人生で最も輝く経験をします。そのことを、サッカーマガジン誌が別冊特集で出版した「ワールドカップ出場メモリアル写真集・日本代表1997挑戦の記録」(ベースボールマガジン社1998年1月発行)の中で、代表選手としてただ1人クローズアップする形で取り上げた山口素弘選手の、韓国戦の出来事を、伊東武彦記者が次のように活写しています。
「前半の0-0は予定通りだった。後半に入って55分、相馬直樹のシュートがポストを叩いた左サイドの攻めからリズムが良くなる。山口の先制ゴールはそんな状況で生まれた。」
「左サイドで相馬が持った瞬間に山口は右サイドに流れた。名波と中田にはマークがついていた。相馬は一度切り返した時点で山口の動きに気づいて、右足でロビングを送ろうとした。山口は『来るな』と思って身構えた。しかし、キックはDFに当たってコースが変わった。」
「ボールは高正云(コ・ジョンウン)に向けて飛んだ。山口の頭脳からは、この時点であるデータがアウトプットされている。高正云は右足のアウトサイドでボールをコントロールすることが多い。それはスカウティング・レポートにも記されていたし、セレッソ(注・当時高正云が所属していたクラブ)とのゲームでも観察していたクセだった。」
「普通ならば、前方への進出を抑えにいく。しかし山口は情報を思い出して、韓国ゴールの方向にプレッシャーをかけにいった。案の定、左足でトラップした高正云は、右足のアウトサイドで自分のゴールに向けてコントロールした。読みは当たった。体をボールと高正云の間に入れると、山口はボールを奪った。」
「あわてた高正云のファウル気味のチャージを振り切って前に出ると、呂比須が右のスペースに流れた。まず考えたのは、呂比須にオープンバスを出すことだった。しかしすぐに洪明甫(ホン・ミョンボ)が読んでいることが分かったので、呂比須をおとりに使って自分で行こう、と判断した。そこからは迷いはなかった。」
「洪明甫をかわしたところでシュートを打てたが、左から来たDFを切り返しでかわそうとした。しかし切り返しが足元に入り過ぎた。その時点でキーパーが前に出てきてるのが確認できた。ボールをすくい上げたのは、とっさの判断だった。」
「ボールが上がった時点で、山口は確信した。すくい上げたときに素晴らしい感覚が右足に残っていたのだ。」
「この先制ゴールは、勝利に結びつかなかった。(中略)山口は、ベンチの分析がピッチ上とずれていることを感じた。」
この伊東武彦記者の描写を読むと、山口素弘選手のサッカーのキャリアを代表するゴールが、どのようなインテリジェンスとイマジネーションのもとに生まれたか、手にとるように分かります。右足に残った素晴らしい感覚がゴールを確信させたという経験もサッカー選手冥利に尽きる体験だと思います。
韓国戦を落した日本代表は中央アジア遠征に向かいます。チームがまた3バックに戻した練習を始めたことで、山口選手はいらだちと不満をためていったそうです。
そしてカザフスタン戦、山口選手にとっては最悪の内容だったそうです。全体が間延びしてしまい、自分の役割も前にプレッシャーをかけるのか、後ろをカバーするのか中途半端になり「こんなのは日本のサッカーじゃない」と「いらだちMAX」に達していた時、後半ロスタイム、同点に追いつかれてしまいました。ショックでした。「いままでずっとやってきたことと違うじゃないか。」
ただ、山口選手は砂を噛むような気持ちになりながらも、必死にフラストレーションを抑えていたそうです。
その夜、加茂監督の更迭が発表されました。
そして選手たちが、とても部屋に戻る気になれずに立ち話を始めると、皆で集まって話しをしようということになりました。
この話し合いで、山口素弘選手は、自然と、さまざまな議論の「つなぎ役」の立場になりました。若手とベテランのちょうど中間に位置する年代からくる「つなぎ役」であり、攻撃と守備の中間に位置して果たす「つなぎ役」でもあるのです。
山口素弘選手は、期せずしてバスの移動の中でも、ちょうど中間のあたりに座っているそうです。ベテラン陣が後ろの座席、若手が前の座席、自然と山口素弘選手たちの世代が真ん中の座席になっていたのです。
このミーティングでは、絶好の「つなぎ役・山口素弘選手」の存在のおかげで、コミュニケーションが驚くほど良かったそうです。山口選手は「どの選手もクラブに戻れば『お山の大将』、誰もが言いたいことを山ほど持っている負けず嫌いの集団、だとすれば、思いを存分に吐き出させて同じ方向に持っていく。」
取材したサッカーマガジン誌の伊東武彦記者は「山口選手は、いつしか、そういう流儀を身につけていた」と評しています。
監督が岡田監督に代わってから、山口選手の役割が変わりました。第3戦の韓国戦のように、中田選手と名波選手ががっちりマークされた時、その隙をついて自分が活きることを考えてよかったのですが、今度は、あくまで2人を活かす黒子の役です。それは、ちょうど所属クラブの横浜Fでブラジル人のサンパイオ選手が果たしている役割そのもので、山口選手は心の中でサンパイオ選手に「サンパイオ、あんたになっちゃったよ」と語りかけながら、そのプレーを思い起こしたそうです。
そうしたチーム戦術の変化や遠征の疲れもあって山口選手は、中央アジア遠征から戻ったホームのUAE戦で初めてスタメンを本田泰人選手に譲っています。
その後、第7戦のアウェー韓国戦、第8戦のホーム・カザフスタン戦を、いいリズムの中で勝利した日本は第3代表決定戦に臨みます。ここで、山口素弘選手が、最終予選を通じてずっと背中を押し続けてきた中田英寿選手への声掛けが、とうとう効き目を表し始めます。
山口選手は、早くから中田英寿選手のゲームメイク能力の高さを分かっていました。そして、最終予選に入ってからは、実は、事あるごとに中田選手に「お前が中心になってやるんだ」と言い続けていました。中田選手は、最初の頃は聞き流すだけでしたが、このイラン戦でも同じように「お前が中心になってやるんだ」と声をかけると、今度は「本当にいいの? 好きなようにやるよ」と嬉しそうに答えました。
山口選手は「それでいいんだ。守りはなんとかするから、お前が中心になって攻めろ」と付け加えました。すると中田選手は真顔になり「なんとか点を取るから守り抜いてください」と答えました。
山口選手があきらめることなく、中田選手に声掛けしてきたことが、とうとう彼を本気にさせたのです。
山口選手がそう声をかけ続けたのは横浜Fのチームメイト・前園真聖選手のことが頭にあったからかも知れません。若い才能に溢れた選手を活かすには、絶えず声をかけて励まし安心感を持たせることが大切だと経験していたからに違いありません。
そして山口選手の言葉に後押しされた中田英寿選手が、岡野雅行選手の劇的なVゴールを呼ぶドリブルからのシュートを放ったのです。
別冊特集の中で、代表選手としてただ1人、山口素弘選手をクローズアップする形で取り上げた伊東武彦記者は、その記事を次のように締めくくっています。
「前回の(注・ドーハの悲劇の)経験者と、若い世代の間に立ってチーム作りの変化を経験してきた長い2ケ月が終わった。山口はピッチの上でも、ピッチを離れたところでもチームの『ボランチ』であろうとしてきた。そして長い戦いが終わり、山口はピッチの内外で本当の『ボランチ』になった。ボランチとは、『操縦桿』『ハンドル』といった意味である。」
うれしさ半分、悲しさ半分のイラン戦Vゴール、直前の母の死に別れができなかった呂比須ワグナー選手の「最終予選」
ジョホールバルでのイラン戦、劇的なVゴールで勝利した日本イレブンが、吹き出る汗を拭いながら余韻に浸っている中、山口素弘選手が、持っていた日の丸を呂比須ワグナー選手に頭からかぶせてやりながら、抱き寄せてハグを交わした姿がテレビカメラに捉えられています。
山口選手は、イラン戦が近づく中、呂比須選手が扁桃炎で体調を落し4日前には、故郷ブラジルで母親がガンのため泣くなり、悲しみにくれていた姿を見ていましたから、呂比須選手の複雑な胸の内を察して、自らハグして、しっかりと抱きしめてやることが自分にできることだと考えたのです。
呂比須選手は、そのあとのテレビ局のインタビューで、アナウンサーから開口一番「うれしいねぇ」と声をかけられました。呂比須選手は気丈にも「言葉にならないです」「皆さんが応援してくれたおかげです」と返していました。
そして「お母さんのこともあってね」と問いかけられると「今週は悲しいことがあったんで集中がとても難しかったんですが、お母さんがずっと応援してくれていたんで、今日のことをお母さんにプレゼントしたいですね。」
これだけでも、呂比須選手の最終予選は十分に波瀾万丈でしたが、ブラジルから来日して10年になる呂比須選手のサッカー人生も、波瀾万丈でした。
呂比須ワグナー選手は、1987年にブラジルから来日、当時・加茂監督が指揮していた日産自動車に入団します。ブラジル時代はMFでしたが加茂監督がFWにコンバートしました。ストライカー・ロペス選手の誕生です。
その後、Jリーグ入りを目指す日立に加入、さらには本田技研に移籍しています。この頃の移籍をロペス選手は「日産でも日立でも大物外国人が加入すると、外国人枠の関係で押し出される立場でした」と振り返っています。
とはいえ、ロペス選手は、日本での生活を続ける中で結婚し、次第に日本に帰化したいと考えるようになりました。
そのあたりのことについて、1998.1.1Number434号「1997年を語る・証言・呂比須ワグナー『歓びも悲しみも』」の中でノンフィクョンライター・平塚晶人氏の取材に答えて次のように話しています。
「なぜこんなに日本が好きなのか、自分でも説明できない。きっと心の深いところから出てくるからだと思います。ぼくは肉体が死んでも魂は何度でも生まれ変わると思っています。きっと前はぼく、日本人だったんじゃないですかね」
日本への帰化については、日立時代から申請していましたが、本田技研への移籍で仕切り直しになり1996年、JFLで本田技研が優勝を果たすと、その活躍が認められ1997年、Jリーグ・平塚への移籍と日本への帰化申請が進展し始めます。
そして、日本代表の最終予選がスタートした9月、帰化申請が認められると、加茂監督からさっそく招集がかかります。日本人「呂比須ワグナー選手」の代表入りです。
9月28日のホーム・韓国戦、いきなりスタメン出場を果たします。さらには中央アジア遠征のウズベキスタン戦では、途中出場ながら、あの井原選手からの超ロングフィードを頭で合わせ、日本を崖っぷちで踏みとどまらせる起死回生の同点ゴールを生みます。
続くホームのUAE戦も引き分けて日本代表は、サポーターからの大ブーイングを浴びるなど厳しい試合が続きましたが、この2試合とも負けずに済んだのは呂比須選手がゴールしたおかげで、そのあたりが評価されなかったのは気の毒なほどです。
第7戦のアウェー・韓国戦では名波選手の先制点をお膳立て、自らも相馬選手のクロスをきっちりとゴールに流し込む追加点で勝利の立役者となりました。
こうして呂比須選手の調子が絶好調になっていく一方、母国ブラジルからはお母さんの容体が悪化しつつある連絡が入ります。
悪いことは重なります。せっかく好調をキープしていた身体が、お母さんの容体情報による心労で、5日間も点滴が必要なほどひどい扁桃炎にかかり、コンディションをすっかり落してしまったのです。
呂比須選手は、帰国してお母さんを励ましたいという思いを強く持ちますが、実は、故郷では兄弟たちがお母さんにガンであることを伏せており、病気はよくなっていると伝えていることから、突然、日本から息子が帰ってきては、お母さんに内緒にしていたことがバレてしまうと説得され、逆に帰国できず代表に止まらざるを得ない複雑な状況に置かれていたのでした。
そしてとうとう、イラン戦を4日後に控えた11月12日、お母さんは死去してしまいます。呂比須選手は、火葬されてしまう前に一目でも会いたいと帰国を決心しますが、今度は移動の壁が行く手を阻んでしまいました。 マレーシアからの移動では火葬までに間に合わないことがわかってしまい帰国をあきらめざるを得なくなってしまったのです。
辛い気持ちの中で、呂比須選手はお母さんに誓います。いまの自分ができることは仲間とともに「ワールドカップ出場権」を勝ち取ることだ。そう心に誓って気持ちを奮い立たせました。それが、日本代表としてワールドカップ出場に挑戦している自分を応援してくれているお母さんに対する親孝行なんだ、と。
そんな呂比須選手の気持ちまではわかっていないマスコミが「どうして帰国しないんですか?」と質問をぶつけてしまいます。滅多に声を荒げることがない呂比須選手は珍しく声を荒げました。「勝つためにここに残ったんです。絶対に勝たなくてはいけないんです。」
イラン戦に途中出場した呂比須選手、ピッチの上でVゴールを見届けることが出来ました。
呂比須選手はこの「最終予選」について、前述の1998.1.1Number434号「1997年を語る・証言・呂比須ワグナー『歓びも悲しみも』」の中で次のように話しています。
「今のぼくの気持ちは、うれしさ半分、悲しさ半分なんです。母の死が近くなってきたとき、結果として帰らなかったことは、ぼくは今でも正しいことをしたと思っています。お母さんがぼくに、代表として戦えと言っているということなのだろうと考えました。」
「だからイラン戦ではお母さんの魂がぼくのとなりにいたんじゃないかと思います。」
「(注・ジョホールバルから)日本に帰ってきたとき、サッカーを通じて日本がひとつになってたじゃないですか。日本に来てから10年間ぼくはがんばってきたけど、こういう雰囲気にならなかった。それが2カ月間のうちに国がひとつになって。日本のために何かしたいというのがぼくの夢だったから、ずっごいうれしかった。お母さんもずっとぼくを応援してくれていたから、喜んでくれるんじゃないかなって」
「1997年は百年経っても忘れられない年になると思います。Jリーグ(平塚)に入って、念願の帰化が認められて、日本代表入りして、そしてお母さんの死を経験して、最後にW杯出場を決めて・・・・。」
平塚晶人氏は、こう語っています。
「代表入りしてからW杯出場を決めるまでの56日間は信じられないほどに凝縮された日々が続いた。呂比須は一瞬一瞬を、誰よりも深く胸に刻みつけるように過ごしていた。」
この最終予選を通じて「もっとも成長した選手」とか「実質的なMVP」と評された秋田豊選手の「最終予選」
秋田豊選手はJリーグがスタートした1993年鹿島に入団しています。鹿島では当初サイドバックでしたが、次第にセンターバックの一角を担うようになり不動のレギュラーに定着しています。日本代表には1994年のファルカン監督時代から招集されていますが、この当時は出場機会に恵まれていませんでした。
加茂監督になってからの1995年は招集されたりされなかったりを繰り返し、1995年10月のアディダスカップ・サウジアラビア戦第1戦で初出場をスタメンで飾り、第2戦では決勝ゴールをあげています。
招集されたりされなかったりの時代は1996年も続きましたが、96年11月のアジアカップ以降は途切れることなく招集され続けています。それでも出場機会にはなかなか恵まれず、やっと1997年のW杯アジア一次予選から出場機会を増やし、最終予選では加茂監督更迭の引き金になった第3戦韓国戦の途中出場以外、すべてスタメンフル出場、多くのサッカー専門家が「陰のMVP」「実質的なMVP」と評価する活躍でした。
「ホッとしました。これだけのプレッシャーは今までになかったですから。試合ごとにチーム力がアップしました。でもたった2カ月で変わるものがあるとすれば自信だけですよ。本大会では失うものがない。思い切りやるだけです。」
秋田選手は、最終予選後の97.12.10サッカーマガジン636号で、このようなコメントを残しています。
また、この後に発売された98.1.14Number435号では「W杯最終予選MVPインタビュー」と題された杉山茂樹氏の記事では「アジアのFWは、全然怖くなかった」。という見出しがつけられています。ちなみに最終予選MVPはNumber誌の採点トータル最高点だったからだそうです。
その杉山茂樹氏のインタビュー、一問一答から拾ってみます。
杉山 (注・ジョホールバルでのイラン戦で)岡野選手の決勝点が決まる直前にマハダビキアが右から際どいセンタリングを上げて、それをダエイがプッシュした。僕は思わずのけ反っちゃいましたよ。あのシーンは・・・・。
秋田 自殺点パターンでしたね。センタリングの球筋が。触ることは可能でしたけど、あえて僕は触らなかった。あの体勢でクリアしたボールを枠から逸らすことは難しいんです。あの瞬間、僕が自殺点を犯す確率とダエイがゴールを外す確率とを天秤にかけた。ピッチがスリッピーだったから、ダエイとて合わせるのは難しいだろうと。それで見送ったら案の定・・・。僕は意外と冷静に判断できた。
秋田 エムボマやエジウソン(注・柏レイソル)といった選手は、スピードがある上に、何をしてくるかわからない怖さがある。そういう選手と戦ってきてるから、逆に歯痒く感じましたね。アジアのレベルはこんなに低いのかと。アジアのFWは動きがだいたい読めるんです。崔竜洙(チェヨンス)にしてもインテリジェンスに欠ける。高さや強さ、スピードはまあまあなんですが、こちらの逆を取る動きが少ない。
Jリーグの外国人選手のほうが断然凄いなと。でもダエイだけは別格でした。彼ならJリーグでもトップクラスのFWとして通用するはずです。
杉山 (注・第3戦の韓国戦で)僕が何より驚いたのは、スタメンに秋田さんのなかったことです。3バックから4バックに変更して臨んだわけですが、僕はてっきり小村選手ではなく秋田さんが先発するものだと。
秋田 僕も出られるものと思っていました。その前の試合で結果を出したつもりでいたし、自分でも納得するプレーができた。大丈夫と思っていたから、すごくショックでした。
杉山 その前のUAE戦、ほとんどの選手が暑さでバテている時に、秋田さんの身体は抜群に切れていました。一方、小村選手の調子は休養明けということもあって、決して良くなかった。だから二重にショックだったのではないですか。
秋田 そこで思ったのは、やはりゴールなんだなと。点を取れるか否か。小村さんはカールズバーグ杯(96年2月香港)のスウェーデン戦で加茂さんの苦しい時に得点を決めている。そういうイメージが強いから使われているんだろうなと。(中略)
杉山 それで、あの(注・アウェーの)カザフ戦のヘディングシュート”怒りのゴール”が生まれたわけですか。感動しましたよ。
秋田 杉山さん、以前言ったじゃないですか。「DFがコーナーから頭で取れる1点は値千金のゴールだ」って。その言葉が頭に残っていたのと、それまでの鬱憤を晴らせたというのが重なって、「これがそういう意味を持つゴールなんだな」と思いました。加茂さん、見といてください。目に焼き付けて下さい。そんな感じでしたね。
杉山 秋田さんは長い間サブでした。監督とサブの選手は同じ一家の仲間なんだけど、対立関係にあることも事実ですね。秋田さんと加茂さんの間にもそうした面を強く感じます。(中略)秋田さんの能力を見抜けなかったことが、更迭に追い込まれた原因の一つではないかという見方もできます。
秋田 長い目で見たら、理解し合えない関係なのかもしれませんね。だって、加茂さんが解任か、続投かという瀬戸際にあったサウジ戦’(95年10月)で僕は点を取っているんです。「なんで結果を出したのにサブなんだ」とセルジオ越後さんも言ってましたけど、それでも加茂さんにとっては小村さんのほうが上だったんですね。その時「監督好みの選手にならなきゃダメなんだな」ってつくづく思いましたよ(笑)(中略)
代表に入っていないと、試合には出られませんから、辛抱強くコツコツやるしかないんですよね。そういう人間が最終的には一歩一歩上がっていくんです。若い選手はすぐフテ(くされ)てしまうけど、それではチャンスはなかなか巡ってこない。それよりも次のチャンスで結果出した方が絶対得策だ。4年間ずっと代表のベンチで試合を見ていてそう痛感しましたよ。
杉山 そして岡田監督が登場したわけですが。
秋田 岡田さんは監督就任が決まって我々の前に姿を現した時、すごく顔色が悪かったので、正直不安でしたよ。でも、練習やミーティングが始まると、コーチ時代とは目の色が違うんです。これはひょっとするかなと思いました。我々に対する指示もすごく細かく具体的でしたし、ここでボールを取りたいからこうして前から追い込んでいくんだぞ、という具合に。攻撃に関しても、選手の動きとか約束事とか、これまで選手間のみで行なわれていたことに道筋をつけてくれました。(中略)
それは本来普通のことなのかもしれないんですが、僕たちにはすごく魅力的に映った。こんな監督を待っていたんだってね。
Number誌のリード文は、次のように締めくくられています。
「数々の逆境をはね除け、紅白戦要員から這い上がった彼の活躍がなければ、日本のW杯出場はなかった。」
杉山氏の質問に答える秋田豊選手の話の中に、加茂監督の選手起用の判断基準を思わせる「やはりゴールなんだなと。点を取れるか否か。小村さんは(中略)使われているんだろうなと。」というくだりがあります。
秋田選手は「小村さんはカールズバーグ杯(96年2月香港)で点をとってる」と例をあげましたが、なんといっても、このW杯アジア予選の一番最初の試合、一次予選の初戦オマーン戦で1-0の貴重な得点をあげたのが小村選手でしたから、加茂監督にとっては「ホントに小村は頼りになる」選手だったのだと思います。
ところが、その小村選手はUAE戦でオフサイドを取られる勇み足を犯してしまい、日本が持ち帰るはずの貴重な勝ち点3をスルリと逃してしまいました。加茂監督が『DFであっても点がとれるかどうか』ということにこだわり過ぎたあまり、起用にこだわった選手のプレーで勝利を逃す羽目になり、更迭の一因となってしまいました。加茂監督自身は後悔はしていないのかも知れませんが、何とも皮肉なことです。
サッカー王国ブラジルのメンタリティを日本代表に注入したフラビオコーチの「最終予選」
この最終予選に、加茂監督・岡田コーチ(のちに昇格して監督)のほかに2人のブラジル人スタッフが帯同していたことは、あまり注目されることがありませんでした。1人はフィジカルコーチのルイス・フラビオコーチ、もう1人はGKコーチのマリオコーチです。
まだ発展途上の日本サッカー界には、フィジカルトレーニングを専門的に学んだ日本人スタッフで、日本代表チームのトレーニングを任せられるような方はいなかった時代です。
フラビオコーチは、ブラジルの幾つのも名門チームでフィジカルコーチの経験を持ち、国別代表ではサウジアラビア代表のフィジカルコーチ経験を経て、1991年に読売クラブのフィジカルコーチとなり日本と縁ができます。
そして1994年12月からは加茂監督体制の日本代表フィジカルコーチとして、ずっと代表選手のトレーニング、コンディション調整はもとより、選手たちのよき相談相手として精神的な面でも大きな役割を果たしてきました。
加茂監督は、最終的には途中退任を余儀なくされましたが、岡田コーチをはじめスタッフとして指名したコーチ陣が加茂監督の残した財産として、日本をワールドカップ初出場に貢献する人材であったことは特筆すべきことだと思います。
GKコーチのマリオコーチのことは、川口選手のことを触れた時にもご紹介していますが、もう1人のフラビオコーチのことは触れる機会がありませんでした。彼は、その情熱と日本文化や日本人気質を深く理解しながら、一方ではサッカー王国ブラジルで培った「勝者のメンタリティ」を代表選手たちに注入して、有形無形の貢献をしたコーチです。
そのことを記録に残し、長く記憶に留めたいと思います。
98.1.15Number435号が、そんなフラビオコーチにスポットをあてて紹介しています。タイトルは「フラビオは何をしたか」
カズ・三浦知良選手についての著作で知られるノンフィクションライターの一志治夫氏が、書き下ろしています。
「国立競技場で韓国に負けた時、彼は冷たい水を自らかぶった。その後、監督が代わってもフラビオは自分と選手を信じて戦った。しかしUAE戦でのドロー。背水の陣で臨んだ敵地韓国での試合の勝利に、彼は『New Sunshine again』と叫んだ。」
「その光を再び失うことなく、日本代表は重い扉をようやくこじ開けた。その鍵を持っていたのは選手だけではなく、いつもベンチにいた彼も、強く握っていたのだ。」(リード文から)
以下、一志氏との一問一答から抜粋してご紹介します。
一志 日本代表フィジカルコーチに就任されて、チームに対してどういう印象を持たれましたか。
フラビオ 日本の選手たちはテクニック的にも非常に優れていて、クォリティを持った選手たちなのに、なぜもっとそれを利用しないのか、スピードにも溢れていて、耐える力も強く、安定した力を持っているのに、なぜもっと自分を信頼して、自信をもって利用しないのか、それが驚きでした。そしてもう一つは、マリーシアがないように感じました。(中略)
一志 具体的にはトレーニング方法をそれまでとどう変えたのでしょうか。
フラビオ まず第一にボールを使ってのフィジカルトレーニングを取り入れた。多くのフィジコはボールを使わないトレーニングをする。けれども、私の場合はボールを使ってのフィジカルトレーニングを多用する。二つ目は瞬発力を重視したトレーニングを行なうようにしたこと。
そして、三番目はメンタル面のトレーニングです。代表というのは一つのファミリーであり、一つのクラブなんだ、旗は一つなんだという意識を持たせる必要があった。まず第一に、一国のナショナルチームのユニフォームを着るということに愛情を持つこと。ワールドカップ予選というのは、まさに戦争なんですから。とにかく、そういう気持ちで90分間戦わなくちゃいけない。そういった面でのメンタルトレーニングを常にやりました。
一志 実際には言葉で意識を変えていくのですか。選手と話すときは通訳を入れてたのでしょうか。
フラビオ 言葉で伝えます。ミーティングとか、練習前とか、休憩の時にね。そういうコミュニケーションはとても大切なことだと思います。もちろん僕は日本語が(注・あまりうまく)喋れませんけど、言いたいことは選手にはよく伝わっていたと思います。通訳が入るとどうしてもそこで瞬間的に切れるんですよね。そういうことがないように、手を握ったり、頭をなでたり、ジェスチャーというか、そういう直接的なコミュニケーションをとった方が、私の思いはより伝わるし理解してもらいやすい。どうしてもコミュニケーションがとれないときや、説明が必要なときは、カズとか岡田さんとか呂比須とか、そういう人が助けてくれたけど。
一志 最終予選ではいくつかの山場がありました。(注・第3戦)日本での韓国戦はどうでしたか。
フラビオ 日本で行なわれた試合だったので、衝撃は大きかった。日本での試合は勝たなければいけないと思っていたし、期待していた部分もあったから、韓国戦に負けて、正直言って水をかけられたような心境になった。試合が終わったとき、血が引いたような感じになったので、実際、私は床に置いてあった水を頭からかぶってしまった。悪くても引き分けで、それでグループ1位になれると私は信じていましたから。
一志 (注・第4戦の)カザフスタン戦ではリードしていて、最後の最後で追いつかれてしまった。ああいう場合の精神的な落ち込みを回復する術は?
フラビオ これは(注・カザフスタン戦に限らず)いつも言っていることだけど、最初の10分、そして最後の10分は非常に集中していけと。(中略)最後の10分は疲れがでてくるのは当然のことだけど、だからこそ集中しなくてはいけない。レフェリーが最後の笛を吹くまで集中し続けなくてはいけないんです。
90分間を信じて戦うことが大切であって、たとえばそれが80分とか、85分とか、89分とかでは意味がない。最後まで90分間を信じて戦うことしか意味がないんです。
一志 加茂監督が更迭されて、どん底の状態からどうやって士気を上げていこうと思いましたか。
フラビオ 予選を通じてやってきたことですが、最終的な目標は勝つということしかなかったわけで、それぞれの選手に行けるんだ、勝てるんだということを自覚させ、自信を持たせることが第一だと思った。「最後まで行くんだと信じて、毎日信じることが大切だ」と言った。「少しでも疑ったらだめだ」と。ブラジルでよく言う「ハートが足の先まで伝わっていなければならない」というようなことを言った。
あとは、自分が抱えている選手と言うのは、世界中で一番いい選手なんだ、と心から思った上で教えることです。そう私自身思うことが重要なんです。
一志 サブの選手への助言も同じでしたか。
フラビオ 自分にとってはサブの選手のほうが大事でした。サブの選手のお陰で勝てるという試合がかなりあったと思う。サブの選手というのは必要なときにいつでも試合の中に入っていけるようなコンディションじゃないといけない。そういう意味でレギュラー選手よりも難しいところもあって(中略)
たとえば下平(注・隆宏選手)は1回もゲームに出なかったけど、同じようにトレーニングして、いつでも出られるコンディションだった。岡野とも常に話ししてた。いつ出てもいいように。岡野に限らず、そういう話は常にしていた。
一志 日本でのウズベキスタン戦からイラン戦までの73日間という長い期間で、一番苦労した点は何ですか。
フラビオ 毎日同じトレーニングをしていたのでは飽きてしまったりするので、一つのことに慣れてしまわないような努力を自分はしてきた。
それから、この長い期間、継続して保たなければいけなかったのは、選手たちの結束でした。ベテランと若手が交じっているわけだから、その中での団結力ですね。ゲームの中でのことで言えば、グラウンドの外では友達を助けるのに、なぜグラウンドの中で友達を助けないのかといったことも話した。『何をしてもらいたいかを考えるのではなく、仲間に何をしてあげられるかを考えること。そういう気持ちになること。他の選手が疲れていたら、自分が動いて助ければいいじゃないか。お前は休んで、俺が行くという気持ちを持たなければならない』と。全員がそう考えれば、必ず組織力は増すんです。
また、合宿先にはリラックスルームがあるんだけれど、自分は常にそこにいるようにして、会話を持つようにした。彼らの会話は、かなりのことがわからないんだけれど、それでも一緒にいて、後でなんで笑ったのとか聞いたりしてね、
一志 彼らの日常生活に関しても意見を言うようなことはあったのですか。
フラビオ 自分の経験から得たもの、家族についてとか、自分の人生の経験を彼らと話すことはありました。たとえば、合宿に入ると家族と別れて長い間大変な思いをして試合に臨んでいるわけですから、「何のためにやっているのか、家族のためにもやっているし、自分のためにもやっている。こんな大変な思いをして、勝たないわけにはいかないだろう」というような話とかをかなりしました。
フラビオコーチへのインタビューは、このあとも「フランス大会に向けての抱負」や「ワールドカップ後の人生設計」について続きましたが、この書き下ろしを読んで一つ感じたことがありました。また「たられば」の話にはなりますが、あの「ドーハの悲劇」のイラク戦のハーフタイムの場にフラビオコーチのようなタイプのコーチがいたら、ああはならなかったのではないか、と。
あの場に、もしフラビオコーチがいたら、おそらくポルトガル語で大声で何度も叫んだのではないでしょうか。「まだ、何も終わっていないのに、なぜ、そんなに興奮しているんだ。レブェリーが最後の笛を吹くまでは、何も意味がないんだ。もう一度、気持ちを引き締めろ」と。おそらく、そのポルトガル語にラモス瑠偉選手やカズ・三浦知良選手は、ハッと我に帰ることができたのではないかと思えてならないのです。
この書き下ろしのリード文の最後に「日本代表は重い扉をようやくこじ開けた。その鍵を持っていたのは選手だけではなく、いつもベンチにいた彼も、強く握っていたのだ。」とあります。「ドーハの悲劇」の場には鍵を持つフラビオコーチのような存在はなく「ジョホールバルの歓喜」の場には鍵を持っていたフラビオコーチがいた。そう締めくくりたいと思います。
こうして何人かの選手と、それを支えてきたフラビオコーチの「最終予選」を見てきました。
決定的なヒーローとなった岡野雅行選手は、押しつぶされそうな極限状態の中でプレーすることを余儀なくされた中、仲間たちの言葉に気持ちをほぐされ、見事、大役を果たします。けれども、あとあと10年以上も、この試合は見れなかったといいます。見ようとすると、あの時の極限状態が蘇ってきて身体がブルブル震えてしまい、見れなかったのだそうです。なんという過酷な経験でしょうか。
その岡野選手のVゴールが生まれるまで、ゴールマウスを守り続けた若き守護神・川口能活選手もまた、ストイックな性格が故の心理的重圧にあえぎ、高校時代の恩師からの届いた1枚のFAXによって絶望の淵から立ち直ります。「もしあの時、あのFAXが届かなかったらと思うと」。川口選手もまた過酷な経験を強いられていたのです。
ドーハの悲劇の経験者でキャプテンの井原正巳選手は、加茂監督更迭の夜、自発的ミーティングでチームを結束させ、決してあきらめない強い気持ちを抱き続け、最後尾からのロングフィードを、望みをつなぐ同点ゴールに結びつけました。数々の修羅場を潜り抜けた大ベテランの存在証明のようなロングフィードでした。
同じくドーハの悲劇の経験者で、第1戦のウズベキスタン戦では大勝発進の大役者になったにもかかわらず、それ以後の無得点ゆえ激しいバッシングにさらされたカズ・三浦知良選手もまた、けっしてあきらめることなく最後まで求められた役割を果たし続けました。
代表メンバー最年少ながらワールドカップ出場に自信をもっていた中田英寿選手、しかし際どい戦いの連続に、次第に「運頼み」になりながらも、最後のイラン戦では自由自在なゲームメイクにより出場権獲得の立役者になりました。
最後のイラン戦、中田英寿選手からのクロスを見事同点ゴールに結び付けた城彰二選手、岡田監督の言葉を信じ、自らを信じて戦い続けました。
日本代表の10番を背負わされたゆえに対戦相手からの厳しいマークにさらされ、まったく自分らしさを出せなくなってしまった名波浩選手、彼もまた高校時代の恩師から練習グラウンドのフェンス越しにかけられた一言によって気持ちを切り替えることに成功し、アウェーの韓国戦以降、本来の「好きにやってみる」サッカーを取り戻しました。
加茂サッカーの申し子といわれた山口素弘選手、いろいろな葛藤を抱えながらもベテランと若手を繋ぐ役割、守備陣と攻撃陣を繋ぐ役割を愚直に果たし続けてW杯出場権獲得に貢献しました。
山口素弘選手がVゴール後の歓喜の中、日の丸をかぶせてやりながら抱擁したのは呂比須ワグナー選手でした。呂比須選手は、最終予選半ばから招集され3試合連続ゴールで貢献しながらも母国ブラジルの母の死という出来事があり「うれしさ半分悲しさ半分」のフィナーレになりました。
サッカー専門家の間では「実質的なMVP」と高い評価を受けた秋田豊選手、4年前から長いサブ生活、紅白戦要員を続けた末につかんだ不動のセンターバックのポジションで大きな自信を手にしました。
加茂監督、岡田監督と指揮官が代わる中で、選手のコンディション調整とメンタルケアを一手に引き受けたフラビオコーチ、ドーハの悲劇の場には彼のような存在の人はなく、ジョホールバルの歓喜の場には彼の姿があった、そう感じさせる「キーマン・鍵を持った人」でした。
ここまで、2ケ月半の中で、選手たちがどのような心理状態に置かれ、どのように揺れていたのか、キーマンとなった何人かの選手の「最終予選」をご紹介しました。
そのほかにも、左サイドからの駆け上がりで数々のチャンスを生み出した相馬直樹選手や、最終盤に招集されて、即ゴールという結果を出した中山雅史選手、高木琢也選手、中盤で相手選手にプレッシャーをかけまくる黒子役の北澤豪選手、本田泰人選手、そしてDF陣の名良橋晃選手、小村徳男選手、さらにはベンチ外となって出場機会がなかった選手を含めて、歴史を刻んだ最終予選登録メンバー31選手全員を、帯同スタッフとともに、あらためて記録に残し長く記憶に留めたいと思います。
GK 小島伸幸選手、川口能活選手、楢崎正剛選手 (3名)
DF 井原正巳選手、小村徳男選手、秋田豊選手、相馬直樹選手、名良橋晃選手、斉藤俊秀選手、中西永輔選手、柳本啓成選手、路木龍次選手、中村忠選手、鈴木秀人選手 (11名)
MF 北澤豪選手、山口素弘選手、下平隆宏選手、本田泰人選手、名波浩選手、森島寛晃選手、前園真聖選手、中田英寿選手、平野孝選手 (9名)
FW 中山雅史選手、高木琢也選手、西沢明訓選手、城彰二選手、岡野雅行選手、呂比須ワグナー選手、カズ・三浦知良選手、望月重良選手 (8名)
監督 加茂周(最終予選4試合)、岡田武史(最終予選5試合)
コーチ 岡田武史(最終予選4試合)、小野剛(最終予選5試合)
フィジカルコーチ フラビオ GKコーチ マリオ
ドクター 福林徹、宮田俊平
マッサー 徳弘豊、田中博明、並木磨去光
シェフ 野呂幸一
栄養アドバイザー 浦上ちあき
エキップメント 麻生英雄
総務 村野晋、山下恵太
プレスオフィサー 加藤秀樹
日本サッカー史上初のワールドカップ出場権獲得、それはすべて、加茂監督が残したコーチ、選手たちが達成した偉業でした。加茂監督だけがただ1人去ったことにより、残った人たちだけでミッションが完遂されたのでした。
日本サッカー史上初のワールドカップ出場は成し遂げられました。1994年12月にファルカン監督のあとをうけ日本代表監督に就任した加茂監督は1年後に「このまま日本代表監督を任せるにはあまりにもリスクが大きい」と評価され、一時は命脈尽きたかに思われました。
そして、2年後にもアジアカップ準々決勝敗退により「やはり加茂監督ではアジア予選突破は厳しい」と多くのサッカージャーナリストから指弾されましたが、日本サッカー協会は動きませんでした。
結局、加茂監督はアジア最終予選のさなか更迭されることになりました。
ここまでの流れを見れば、多くのサッカージャーナリストたちは「だから、あれだけ言ったのに」と気炎をあげることでしょう。
事実、前にも触れましたが、サッカーダイジェスト誌は98.1.7/14合併号の中で「この歴史的な監督交代は、大げさに聞こえるかもしれないが世論の力によって生まれたといっていい。かつてないほど注目を集めたワールドカップ予選で、日本代表は間違いなく国民のチームになっていた。(中略)」と書いています。
しかし、1995年の時点で、別の監督に交代させていたら「ワールドカップ出場権獲得」というミッションは本当に達成されたのか、誰にもわからないことです。もし別の監督に交代させていたら「ワールドカップ出場権獲得」というミッションは達成されなかったかも知れないからです。
それは1996年のアジアカップ準々決勝敗退の時も同じです。つまり、当時の議論は、別の監督に任せたら「ワールドカップ出場権獲得」というミッションが達成できるのか、わからないけれど、少なくとも加茂さんより高い確率で「ワールドカップ出場権獲得」を果たせる人はいたはずだという意味の議論だったのです。
ここに歴史の検証の難しさがあります。もっと早い段階で加茂監督に見切りをつけていたとしたら、果たして次の監督が選んだスタッフ、選手たちは、今回、ミッションを達成したスタッフ・選手たちと同等の結果を出せる陣容になったのでしょうか? 逆にそれまでの代表メンバーをガラガラポンしてしまって、有能な新監督の戦略・采配をもってしても、まとまることなく最終予選に臨んでしまった、というようなことがなかったのでしょうか?
歴史に刻まれたのは、一つは加茂監督はやはり交代させられたという事実です、もう一つは、新たに監督に就いた岡田武史という監督が「ワールドカップ出場権獲得」というミッションを達成したという事実です。
ところが、あれほど「リスクが大きい」と指弾され続けた加茂監督は、コーチ・スタッフ、そして選手全てを残して、たった1人でチームを去った結果、残ったコーチ、選手たちの手で「ワールドカップ出場権獲得」というミッションが達成されたのです。
コーチ・スタッフ、全ての選手は加茂監督が選んで残していった人たちです。その人たちがミッションを成し遂げたのです。この点を事実としてキチンと押さえ記録に残し、記憶に留めていく必要があります。
加茂監督は、岡田武史という人の監督としての資質までも見抜いていたわけではなかったと思いますが、コーチとして3年間使ったという理由で後を託しました。その岡田氏が、全くの突然にも関わらず、見事、監督として任を全うしたのです。結果オーライと言われる対応でしたが、岡田氏に後を託した加茂監督も「ワールドカップ出場権獲得」の一端を担ったことになります。
選手も全員、加茂監督が招集した、いわば「加茂チルドレン」です。加茂監督から岡田監督に代わって、選手の組み合わせはいろいろ変わりましたが、加茂監督が選んだ選手には変わりありません。その選手たちが「ワールドカップ出場権獲得」を果たしたのですから、加茂監督はアジア予選を勝ち抜く力のある選手をきちんと残していったわけです。
結局、加茂監督は、全てのコーチ・スタッフ・選手を選ぶという仕事においては何一つ間違っていなかったのですが、唯一、戦術、采配といった監督としてのオペレーションを間違っただけだったことになります。もっとも「戦術、采配といったオペレーション」は監督として最重要の能力ですから、そこに問題があれば交代やむなしということになりますが、全てを残して自分1人だけ、身を引いたことがベストの結果を生み出したといっても過言ではありません。
それだけに、あの中央アジア・カザフスタンの地から、たった1人で帰国した加茂前監督の寂寥感は察するに余りあります。その耐えがたい寂寥感と引き換えに歴史的成果を日本にもたらしたことになります。
加茂前監督は退任後も愚痴めいた言葉を一切口にしませんでした。それは自身の「男には、棺桶まで持っていかなければならないことが、たくさんあるんや」という男の美学からきています。
日本の長い歴史の中には、武将が自らの首と引き換えに多くの民と領地を守った史実がありますが、日本のサッカー史にも、自らの退任と引き換えに歴史的成果をもたらした指揮官がいたことをしっかりと記録に残し、長く記憶に留めたいと思います。
今回の「アジア最終予選」、波瀾万丈、歓喜と悲嘆が交錯する激動の73日間、一体、日本代表が、史上初のワールドカップ出場権を獲得できた理由は何なのか、さまざまな要素が絡み合う中で、真の理由がわかりにくくなってしまいましたが、詰まる所「加茂監督が1人だけ抜けたこと、あとは全てチームとして残ったこと」、これが出場権を獲得できた最大の理由だったと言えます。
事ここに至っては、残った事実こそが最善の結果であったと評価するしかないようにも思いますが、おそらく「加茂監督を辞めさせて、あの人に監督をやらせたらとか、あの人が監督をやっていれば」といった、強い自負心を抱いているサッカージャーナリストたちによる議論は、この先も長く続き、歴史の評価が定まるのは、かなり先のことになるような気がします。
一夜明けた日本列島「ジョホールバルの歓喜」でもちきり状態に、日本全体を明るくした快挙
翌朝のスポーツ紙各紙、そして全国紙も、この快挙を一斉に報じました。しかし締め切り時間の関係もあり、活字は「岡野Vゴール」と打った紙面もありましたが写真は間に合わず、ほかの写真を使っていた紙面がほとんどでした。
この時期、日本の社会・経済がの活力低下が指摘され、明るい話題が少なかった中での快挙に、いつもながらの「経済効果」試算の話題に加えて、このあと恩恵を受けると見られる銘柄が買われ、一時的ながらも株価上昇といったニュースも取り上げられるほどでした。
翌朝17日から18日にかけてのスポーツ紙、全国紙などが、いかに凄まじい情報量でこの快挙を日本中に伝えたか、つぶさに記録に留めたいと思います。
11月17日 日刊スポーツ 1面 岡野がVゴール、日本ついにW杯 終面 2万人絶叫、スタンドにブルー軍団、マレーシアがホームに。2面 初出場切符取った~ 岡田殊勲 3面 岡野V弾 延長後半決めたぞ 4面 カズ有終笑顔なし、エースに突然交代指令「何故オレが・・・」 5面 井原万歳 激闘2ケ月半ドーハの教訓生きた。 6面 日本人呂比須が涙「母が応援してまくれた」 7面 岡田様仏様 本大会も正式要請へ 22面 苦難バネに前進 韓国の厚いカベ、ドーハの悲劇乗り越え 23面 日本の悲願43年 それは長沼会長のひと蹴りではじまった 24面 芸能界サポーター喜び爆発 仏まで追ってサッカーワイドショー・三井ゆり、東山、江川氏らが名乗り 25面 フジテレビもエライ、W杯中継で7戦不敗、日本に夢を広げてくれた
11月17日 スポーツ報知 この日のスポーツ紙唯一の「岡野選手もみくゃ」写真
1面 バンザイ日本 岡野やったぜ歴史的Vゴール 終面 川口攻めた耐えた 2面 岡田監督辞任へ ありがとう絶妙采配 長沼会長「処遇は全くの白紙」 3面 ゴン先制弾、城同点弾、みんな、み~んな頑張った 4面 一緒にフランスだ 2万人サポーター燃えた吠えた 21面 続いたフジ不敗神話 98年アジア地区最終予選4勝1分け 23面 列島総サポーター サッカーくじ逆転成立も 24面 経済効果3000億円 W杯出場の祝杯が日本の景気盛り上げる
11月17日 スポーツニッポン
1面 日本W杯だ 悲願43年・・ついに世界の舞台に 延長岡野決めた 終面 岡田監督 奇跡の名将だ 崖っぷち就任から43日 2面 城同点弾、岡野決めた 途中出場強烈パンチ 3面 ゴン先制ゴール 4面 2万人 深夜の絶叫 この瞬間待っていたんだ 5面 胸張って2002年 24面 不滅フジ神話だ お茶の間万歳 中継不敗記録18に 25面 列島眠れナイト!! サポーター燃えた! 熱気は朝まで
11月17日 サンケイスポーツ
1面 日本勝った勝った 夢のW杯初出場だ 岡野がVゴール!! 終面 岡ちゃんやったね カズ代え流れ変えた フランスも頼みます 2面 ゴンがカズが井原が ドーハの悲劇から1480日 ジョホールバルの歓劇 3面 川口守った118分耐えた 4面 日の丸サポーターも万歳 おめでとう 5面 44年目の歓喜 ‘54年スイス大会初挑戦から泣いた、待った 27面 歓喜沸騰列島 経済効果1000億円
11月17日 東京中日スポーツ
1面 日本W杯 歓喜フランス 歴史的キップついに・・ついに!! 2面 列島バンザイ!! 岡田監督ありがとう 3面 城起死回生同点ヘッド 川口「攻めるGK」 4面 強敵イラン倒した 5面 ピクシー「日本とやりたい」待ってるぜ 8年ぶりだ ユーゴ決めた 19面 フジ・NHK衛星第一 W杯サッカー視聴率50%超すぞ!!
11月17日 朝日新聞夕刊
9面 はい上がったぜ 日本 W杯アジア最終予選の足跡 16面 岡田監督 最高の決断 世界の入り口やっと 17面 岡野決めた つかんだ FW5人たくましく
11月18日 スポーツ報知
1面 岡田監督続投宣言「最後までやりたい」 3面「フランスへ行けるんだ」激闘から一夜、日の丸イレブン実感じわ~り 4面 岡田の英断 FW2枚看板交代
11月18日 スポーツニッポン
1面 岡田監督「やる」「勝てる」続投意欲初めて口に 2面 理詰めの岡ちゃん カズ・中山交代も納得させた「規律」 3面 W杯ボーナス総額3億円 うれし~いけど、台所キビシ~イ 協会に”オクの手” 30面 フジWの歓喜 瞬間最高視聴率57.7%、平均視聴率47.9%
11月18日 日刊スポーツ
1面 岡田監督任せろ「W杯4強だ」 2面 カズ ショック隠し宣言「フランスもやる」 3面 Vゴール岡野 朝まで酔った 32面 イラン戦のために岡野隠した・岡田の声は神の声
スポーツ紙、全国紙の2日間の主な報道ぶりをご紹介しましたが、何といっても一番最初にご紹介した日刊スポーツの12ページ扱いは驚異的でした。しかも、どのページもほぼ全面使っての報じ方ですから頭が下がります。
このW杯出場権獲得によって、スポーツ紙のサッカー絡みの扱いは急増しました。岡田監督の話題を中心に、岡野選手、中田選手そしてカズ・三浦知良選手らの話題が連日、次から次へと年末まで続き、まさにW杯出場権獲得フィーバーの様相でした。
それにつけても思うのは、マスコミのご都合主義です。勝てば徹底的に「勝ち馬に乗る」、負ければ徹底的に「叩く」。
先に、主な選手たちが「最終予選」を戦い抜いた中で受けたマスコミからの容赦ない攻撃、それによる重圧、精神的苦痛、心の葛藤などをご紹介してきましたが、選手の中には「まるで我々をW杯に出場させたくない連中が書いた記事だ」とまで受け止めた例もありました。
ここまで来ると、もはやマスコミの「叩く」姿勢も本末転倒、逆にマスコミ自身が自制を失っていたことになります。ですから、こうして手のひらを返したように持ち上げるのを選手たちは「何を今更」と複雑な思いで受け止めてしまいます。
日本のワールドカップ出場権獲得を心から願うが故の「愛のムチ」と感じられる姿勢から完全に逸脱した「代表叩き」は「日本のマスコミの姿勢も、まだまだ発展途上」と切り捨てられてしまうレベルだということも痛感させられました。
テレビの大フィーバーぶり、監督・選手が各TV局にひっぱりだこ
「ジョホールバルの歓喜」のニュースは、すぐさまテレビ各局も報じ始めました。日本代表が帰国すると監督・選手が引っ張りだこになり、数日フィーバーが続きます。テレビの報道ぶりも、主な番組を記録として残します。
11月17日
97-11.17めざましTV・おめでとう日本代表(フジ30’10)
97-11.17おはようクジラ・日本中が燃えた夜(TBS16’40)
97-11.17おはようナイスディ・歓喜の渦、悲願のW杯初出場(フジ1H02’45)
97-11-17 B・T(ビッグ・トゥディ) 妻たちのW杯(フジ50’00)
97-11.17スーパーJチャンネル(後半)日本代表歓喜の一日(テレ朝13’40)
97-11.17スーパーJチャンネル(前半)日本代表決めたW杯って何(テレ朝21’15)
97-11.17スポーツMAX・二宮清純のコラム(日テレ4’35)
97-11.17ニュース23・それぞれのイラン戦(TBS9’20)
97-11.17ニュースステーション・ゲスト都並敏史(テレ朝16’15)
97-11.17ニュースの森・列島が揺れた夜・ゲスト釜本邦茂(TBS24’40)
97-11.17ニュースヒューマン・日本悲願のW杯・カズ他(フジ32’04)
97-11.17プロ野球ニュース・日本代表フランスへの道(フジ16’13)
11月18日
97-11.18TBSニュースの森・城、岡野生出演(TBS18’52)
97-11.18おはようクジラ・ジョホールバル戦士帰国会見(TBS34’02)
97-11.18おはようナイスディ・イラン戦から帰国(フジ22’00)
97-11.18スポーツMAX・カズ、北澤豪(日テレ8’25)
97-11.18スポーツTODAY・岡田監督、岡野雅行(テレ東17’20)
97-11.18ニュース7・ゲスト、カズ・北澤(NHK6’10)
97-11.18見ればなっとく・もう一度W杯熱狂列島、岡田監督、城彰二(TBS52’31)
97-11.18ニュース23・ゲスト井原正巳(TBS13’00)
97-11.18ニュースステーション・岡田監督、岡野雅行(テレ朝16’03)
97-11.18ニュースヒューマン・岡田監督(フジ18’12)
97-11.18プロ野球ニュース・ゲスト井原正巳(フジ18’10)
97-11-18スーパーサッカー(TBS27’11)
11月19~22日
97-11.19ザ・ワイド岡田監督夫人内助の功(日テレ12’00)
97-11.19ニュース23・ゲスト川口能活(TBS13’40)
97-11.19ニュースの森・多忙の日本代表(TBS15’20)
97-11-21知りたがり緊急特番・祝W杯出場(フジ53’30)
97-11.21ニュースステーション、井原正巳、山本潤子(テレ朝20’50)
97-11.21ニュースの森・川口能活、城彰二、井原正巳(TBS5’14)
97-11.21金曜TVの星「おめでとう日本代表」(TBS1H51’10)
97-11.22あの感動をもう一度・日本代表鹿島DF座談会(NHK-BS40’00)
97-11.22サタデースポーツ・ゲスト井原正巳(NHK10’28)
97-11.22スポーツうるぐす・ゲスト井原正巳(日テレ8’10)
97-11.23独占スポーツ情報・ゲスト岡野雅行(日テレ8’21)
11月17日から1週間、まさに怒涛の日本代表ウィークでした。朝・昼のワイドショーからゴールデンタイムの特番、そして夜のニュースショー番組まで、放送局もNHKから民放各局、これほどのテレビ番組洪水は空前のことでした。
こうしたサッカー日本代表への高い関心は、ここからが始まりでした。このあと翌年のフランスW杯、そして2002年の共催W杯まで、今回のようなテレビ放送のスタイル(朝・昼のワイドショーからゴールデンタイムの特番、そして夜のニュースショー番組まで)が続いていくことになります。「ジョホールバルの歓喜」が日本サッカーの「幸福な日々」の初日といってもいいでしょう。
少し遅れてサッカー専門誌、総合スポーツ誌、週刊誌、月刊誌等の報道
スポーツ紙、テレビの取り上げ方により少し遅れてサッカー専門誌、総合スポーツ誌、週刊誌、月刊誌等の報道が続きます。
サッカー専門誌、総合スポーツ誌(Number誌)については、すでに折々に取り上げてきましたので、一般の週刊誌、月刊誌の報道を記録しておきます。
1997.12.1週刊AERA ①カズと中田主役交代の時、②崖っぷちから再生させた強い人岡田3p
1997.12.4週刊文春 阿川佐和子の会いたい・三浦知良3p
1997.12.4週刊文春 進めオカちゃん3p(モノクログラビア)
1997.12.4週刊文春 代表イレブン隠されたタブーを明かす「崩壊寸前だった」5p
1997.12.5フライデー 岡野Vゴール! 日本代表全ドラマモノクログラビア4p
1997.12.5週刊朝日 W杯出場今だから明かせる舞台裏3p
1997.12.9週刊プレイボーイ 43年目の栄光71日目の歓喜、次は世界が待っている8p
1997.12.12週刊朝日 いざフランスへ日韓キャプテン対談・井原×洪明甫2p
1997.12.13週刊現代 サッカー代表、テレビも週刊誌も書けない美談のうらの罵り合い3p.
1997.12.25-1.1合併号女性セブン 日本を救える男「中田英寿(20)」表紙+モノクログラビア2p
1997.12.29週刊プレイボーイ 日本サッカー進撃SP ①秋田豊、②中田英寿4p
1997.12月号月刊BART 中田英寿「W杯で勝つことを考えている」3p
1998.1.4-12合併号週刊プレイボーイ W杯出場獲得立役者・岡野雅行、山口素弘、中田英寿5p
1998.1.6週刊ポスト これがW杯メンバー、カズ不要論も2p.pdf
1998.1月号文芸春秋 金子達仁・20歳のリーダー「中田英寿」誕生の夜10p
週刊誌、月刊誌の論調は、裏話、舞台裏といった視点が多くなっています。またいち早く、これからの日本サッカーを牽引するのは中田英寿選手だという論調も目立ちます。
それにしても、この日本サッカー史上初のW杯出場権獲得が、いかに社会的なインパクトが大きかったかを物語るメディアの扱いぶりです。「サッカーの時代ここにあり」の感を強く持ちました。
結果良ければ全て良しのムードの中、異彩を放ったサッカー専門誌「ストライカー」の記事、とてもサポートを尽くしたとは言えない日本サッカー協会の対応を敢然と指摘
日本のフランスW杯出場が決まって、テレビもスポーツ紙もサッカー専門誌も、お祭りムード、結果良ければ全てよし、少々のことは不問に付すかのような論調の中、月刊「ストライカー」誌は97年12月号で「日本サッカーへの緊急提言」と題した一大特集を組みました。
同誌の発売時期は、まだ第3代表決定戦前で、対戦相手は「イランかサウジか」という段階でした。ことと次第によっては「W杯出場権獲得失敗」もあり得る段階の発売ということで月に1回発行ならではの企画だったのかも知れませんが、そのあと、ほどなく「ジョホールバルの歓喜」で大団円を迎えましたから、この企画は異彩を放っていました。
項目は4つ設定され、
①サッカー協会のあり方を考える
②代表選手には自覚が足りないのか
③プロスポーツとしての”Jリーグ”のあり方とは
④ユース以下の育成に変革を
このうち「日本サッカー協会のあり方を考える」では「日本サッカー協会トップの体質改善を望む」というサブタイトルをつけ、昼間編集長自らが執筆して、加茂監督更迭における長沼会長の出処進退や、最終予選におけるサッカー協会のサポートについて、以下のような鋭い指摘をしています。
少し長くなりますが、長く後世に伝えるためにも記録として残す必要があると考え、主な部分を紹介します。(小見出しも原文のまま)
「売り言葉に買い言葉だった」では済まされない!
「カザフスタン戦後、長沼会長は『理事会に進退伺いを出す』と明言、しかし、少なくとも次回の理事会(11月13日)までは棚上げになっている。『複数の理事から、今、会長が進退問題を出すのはおかしいという発言があった。ワールドカップ予選はもちろん、2002年の開催準備に向けて、会長をサポートすることを全会一致で決定した』(小倉専務理事)」
「10月20日に行なわれた理事会では、会長自身が進退伺いを持ち出す前に、理事のほうから慰留を強く要請され、それに応じたという。だが、それでは2年前の啖呵(ワールドカップに行けなかったら、私がやめますよ)は何だったのか? 『あれは売り言葉に買い言葉だった』と長沼会長は理事会後にコメントしているが、それでは筋が通らない。何より、ファンが黙っていないだろう。」
「元強化委員の1人は、次のように憤慨する。『長沼会長は、加茂監督から岡田監督に代えた理由を『強化委員会の推薦があったから』としているが、2年前(注・いわゆるネルシーニョ事件の時、結局、加茂監督続投を決めた)と同じように、『オレが決めたんだから』となぜいわなかったのか。結局は(ワールドカップに行けなかった場合も)自分で責任をとりたくないのだろう。それに、2年前に『内容より結果を重視してほしい』といったはずなのに、なぜ予選敗退が決まっていないうちに加茂監督を更迭したのか。任期途中で解任してほしくはなかった。協会に踊らされた加茂監督も被害者』」
「この原稿の締め切り時点では、最終予選の結果は判然としていないが、万一フランスに行けなかった場合、長沼会長は、その椅子から潔く降りるべきだ。」
「理事会にも問題がある。加茂監督を続投させて長沼会長の責任を誰も問わず、そればかりか『全会一致で会長へのサポートを約束した』とはどういうことか。」
「『どんな議題でも理事会で通るわけではない。強硬な反対にあって、議題が通らなかったことが何度もある』(小倉専務理事)というが、理事会が単なる承認期間にすぎないといわれても仕方がないだろう。」
「かつて、報道陣に対して理事会がオープンになっていたという時期もあったという。これを機に、再度オープン化を望みたいものだ。」
アジアの中で発言力のない日本
「今回の最終予選に関して、日本サッカー協会が責められてしかるべきことが、もう1つある。」
「AFC(アジアサッカー連盟)における発言力のなさだ。そもそも本来、今回の最終予選は、1カ国集中開催の予定だった。しかも、日本をはじめとする東アジア勢に有利なマレーシア開催が有力だった。それが、中東勢の『棄権も辞さない』という反対にあって、急遽ホームアンドアウェーに変更。」
「組み分けについても、日本では”幸運だった”と歓迎されたが、これは韓国サイドが仕組んだこと、というのが真相らしい。実際に組み分けのクジを引いたのは、FIFA(国際サッカー連盟)のブラッター事務総長だが、裏での操作はどうとでもなる。韓国のチョン・モンジュン氏(FIFA副会長)が、自国に有利になるように働きかけたようだ。」
「第3代表決定戦にしても同じ。当初、マレーシアでの開催が決定していたはずだが、最終予選が進んでいくうちに雲行きが怪しくなってきた。結局は”グループAとBの2位がともに東アジアの場合はマレーシア、ともに東アジア以外の場合にはバレーン、一方が東アジアで一方がそれ以外の場合はマレーシアとバーレーンで抽選”となった。(その後、韓国も候補地の一つにあげられた) これも韓国と中東が裏で手を回したから。最初にマレーシア開催で決まったのは、韓国サイドの意向が優先されたためで、当の韓国の1位通過が決まった途端、中東が圧力を加えてバーレーンが候補に挙がってきた。」
「つまり、日本の意思が介入する余地は全くなかったのである。いや、日本協会はAFCに対して、その意思すら明確にしなかったのではないだろうか。それは日程表にも表れている。グループBの最終戦であるUAEvs韓国は、組み分け決定当初は、実は11月7日、つまり日本vsカザフスタン戦の前に組まれていた。それが開催都市やキックオフ時間が決まった時には、11月9日に変更されていたのである。」
「日本vsカザフスタタン戦の1日後に試合をすれば有利に運べるという、韓国サイドの意向が働いたのは間違いない。あのとき本誌編集部では、なぜ日本vsカザフスタンも11月9日にしないのか、ということが話題になった。(中略)」
(注・この第3代表決定戦の開催地の件と、UAEvs韓国戦の11月9日への変更については後日談があり、日本サッカー協会もFIFAに対して働きかけていたという、次の話があります。
11月4日になってFIFAから日本サッカー協会に「11月8日の日本vsカザフスタン戦をUAEvs韓国戦と同じ11月9日に合わせるように」という通達が入ったのです。さきほどの韓国サイドの意向があまりに露骨に思えたのでしょう。FIFAも「一応、不公平にならないよう日本に働きかけた」というアリバイ作りのような通達でした。
ところが、そう言われた日本としては、もうチケットも完売、放送も決まっている今になってそんなことできるわけないでしょう」という状況です。急遽、小倉専務理事がFIFAに出向いたのです。ところが小倉専務理事の移動中、FIFAから「変更の通達は取り下げ」という連絡が入ったのです。まさにアリバイ作りのための通達でしかなかったのです。
すでにFIFAに向かっていた小倉専務理事、そのまま帰るわけにはいかず、用件を「第3代表決定戦の開催地の件をマレーシアに決めてもらう交渉」に切り替えて、FIFAに乗り込みました。
FIFAに到着した小倉専務理事は「第3代表決定戦は中立地のマレーシアで行なうべきであり、バーレーンに決めるのは不当」とFIFA関係者に主張、それが認められて当初の予定どおり、マレーシアに決定したという経緯がありました。)
「もちろん、最も非難されるべきは、一度決めたことを簡単に覆すAFCだ。しかし、AFCに振り回されて、いつも後手に回る日本協会も情けない。」
「本誌でも何度も触れてきたが、こうした日本の政治力のなさは、94年のFIFA副会長選に起因している。あのとき、村田忠男日本協会事務局長(当時)がチョン・モンジュン氏に敗れさえしなければ、すべての状況が違うものとなっていたはず。今回の最終予選も、そして2002年ワールドカップの開催地も・・・・。」
「ここまで、サッカー協会に対しての批判を並べてきたが、プレス関係者の一員としての自戒の意味も込めていたことも断っておきたい。」
「3年前、協会が加茂監督の留任を決めたとき、なぜ、もっと強硬に反対の姿勢を見せなかったのか? それは『加茂監督でもフランスに行けるだろう』という甘い気持ちがあったからに他ならない。」
「『可能性を1%でも高めるためには、加茂監督以外の人物がいい』という自らが下した結論を最後まで押し通した当時の強化委員長と比べて、何とアマチュア的だったことか。あのとき雑誌と新聞が一体となってもっと強く訴えていれば、別の結果が得られたかも知れないと考えると、今さらながら残念でならない。」
「日本のサッカー界全体が、もっと成熟する必要がある・・・・。」
以上が、月刊「ストライカー」誌の「日本サッカーへの緊急提言」・「日本サッカー協会のあり方を考える。日本サッカー協会トップの体質改善を望む」の主な内容です。
一番最後の「日本のサッカー界全体が、もっと成熟する必要がある・・・・。」は、まさに自戒を込めて、サッカージャーナリズムも含めて成熟する必要があると締めくくっています。
この特集記事の指摘にもありましたように、最終予選における日本代表は、ホーム&アウェーの試合に伴う移動と、次の試合までの間隔などで、ずいぶん過酷なスケジュールを強いられました。日本人がよく言うのは「条件はどこも同じだから」というフレーズです。それは、言い換えれば「自分たちが精一杯のサポートを怠っていることの言い訳」として都合のいい言葉です。
しかし、サッカーにおける国と国との戦いは「武器をもたない戦争だ」と言われるぐらいナショナリズムが強いスポーツにおいては、自国代表を少しでもいい条件のもとで戦わせようという気概を持った協会を望みたいものです。綺麗ごとでは済まないのが世界のサッカー界だということです。
日本サッカー界初の歴史的偉業に挑戦した2ケ月半、「日本のサッカー文化」という花の「開花宣言」になったと言ってもいい、数々の記録的出来事、未知の体験、同時に「サッカーの怖さ」を目の当たりに知ることになった出来事
地球上最大のイベントと言われる「サッカーワールドカップ大会」、日本も韓国と共催ながら2002年には開催することが決まった中で、1998年フランスで行なわれる大会には、何としても出場経験を果たしておきたい状況が生まれました。
4年前にはあと一歩のところで出場権を逃がすという悲劇のドラマも経験している日本。
Jリーグスタートから5年目、すでに五輪代表も28年ぶりの出場を果たしている中、次はフル代表の番と、いやが上にも高まるフランス大会への出場権獲得。
一方では、日本代表を率いる加茂監督の采配に懸念の声が高まり、日本の絶対的エースとして長く代表を牽引してきたカズ・三浦知良選手の活躍にも陰りが見え始めてきた中で「頼むぞ日本代表」という激励に「出場を果たさずにはおかないぞ」といった意味も込められているかのような雰囲気の中で、9月7日、フランスワールドカップアジア最終予選の戦いが幕を開けました。
以来、11月18日のマレーシア・ジョホールバルでの第3代表決定戦で、劇的なVゴールにより出場権を獲得するまでの73日間は、日本サッカー史の中でも空前絶後ともいえる濃密な、そして日本列島全体を喜怒哀楽の浮き沈みに巻き込みながら過ぎた日々でした。
それだけに、この期間に生まれたさまざまな出来事は、数字的にも感覚的にも「日本のサッカー文化」の花が、これまで固いつぼみだったものが、まるで「桜の標本木」のつぼみようにポツリポツリと3輪、5輪とうとう花開いたと言ってもいいほどでした。
思えば1993年のJリーグスタートは、日本における「サッカー文化」の萌芽、芽吹き始めでした。その芽がつぼみとなり次第に膨らみ1996年、1997年と年が巡り来て、とうとう「日本のサッカー文化」の開花宣言ができる日が来たのです。
それは、数々の記録的な出来事となり、これまで日本サッカーが経験したことのない未知の体験であったり、日本のサッカーファンも、あるいは日本のマスコミなども経験したことのない未知の出来事が数多くありました。それは文化の花が開花した喜びでもあると同時に「サッカーというスポーツの、スポーツの範ちゅうを超えた怖さ」というものも、目の当たりに知ることになりました。
ここからは、その「日本のサッカー文化」の花がとうとう開花宣言を迎えたといえる出来事をつぶさに記録に残し、長く記憶に留めたいと思います。
ホームゲーム会場となった国立競技場、いずれも試合も超満員と言える観客数、海外での試合にも万単位のサポーターが駆けつけた
アジア最終予選のホームゲーム4試合は、すべて国立競技場でした。各試合の公式入場者数と警備関係者人数は次のとおりです。(警備関係者人数はスポーツ紙等の報道情報)
・9月7日第1戦ウズベキスタン戦 54,328人 協会職員・警備員700人 警察官20人
・9月28日第3戦韓国戦 56,704人 協会職員・警備員1116人 警察官350人
・10月26日第6戦UAE戦 56,089人 協会職員・警備員780人 警察官230人
・11月8日第8戦カザフスタン戦 56,032人 協会職員・警備員780人 警察官350人
4戦合計 223,153人
この当時はまだ8万人収容の横浜国際競技場も6万人収容の埼玉スタジアムも出来ていない時期でしたから、ホームゲームすべてを国立競技場で行ないました。その意味では、後にも先にもない設営でしたし、警備体制も空前の規模となりました。
「アジア最終予選」は当初は中立地での「セントラル方式」という案でしたから、ホーム&アウェー方式への変更が日本サッカーにとっては「サッカー文化」の花がつぼみから数輪花をつけることにつながったとも言えます。
海外で行なわれた試合でも、第7戦の韓国戦には日本から約15,000人のサポーターが応援に駆け付けました。会場となったソウルの蚕室スタジアムでは、韓国サポーターと日本のサポーターの間に黒い制服の警備隊が陣取り、スタジアムは期せずして韓国サポーターの赤、警備隊の黒、日本サポーターの青、警備隊の黒、そして韓国サポーターの赤に染まったコレオグラフィが見られました。
また第3代表決定戦のマレーシア・ジョホールバルのラルキンスタジアムは20,000人ほどのキャパシティしかないスタジアムでしたが、ほとんどを日本から駆け付けたサポーターと現地の在留邦人で占められ、公式発表の観客数は22,000人となっています。この時のスタジアムスタッフは200人、警察官が250人ほど出動したそうです。
アウェーの試合に万単位の日本人サポーターが応援に出かけるという、それまではなかなか想像がつかなかった現象が見られました。この行動は翌年、本大会が行なわれたフランスにも出かけるという流れに結びついたことはご存じのとおりです。
と同時に、入手できないチケット騒動という思わぬ副産物も生み出したわけですが、今回のサポーターの熱量が出発点になっていると言っていいでしょう。
テレビ視聴率も25%超が4試合、ジョホールバルのイラン戦は瞬間最大55.7%を記録
・9月28日第3戦 韓国戦 TBS 26.0%
・10月26日第6戦 UAE戦 日テレ 30.1%
・11月8日第8戦 カザフスタン戦 フジ 37.1%
・11月16日第3代表決定戦イラン戦 フジ 47.9%
第3代表決定戦イラン戦の47.9%は、4年前のドーハの悲劇を生んだ日本vsイラク戦の48.1%には記録上及びませんでしたが、今回は放送時間が約4時間と、試合時間が90分で終了したドーハの時の放送時間と比べて約1.5倍の長さを通じての平均視聴率で、キックオフからVゴールが決まった時までの視聴率(約2時間40分)だけを見れば49.6%を記録しており、瞬間最大視聴率も55.7%(後半終了時の23時54分)を記録しており、実質的には史上最高視聴率だったと言える記録でした。
マスコミ関係者も大挙してスタジアムに取材
・11月8日第8戦 カザフスタン戦・国立競技場
ライター・記者 400人、カメラマン400人、全国TVクルー200人、
中継局フジスタッフ80人
・11月16日第3代表決定戦イラン戦・マレーシア、ジョホールバル・ラーキンスタジアム
報道陣490人(日本からはライター・カメラマンなど総勢294人)
サッカージャーナリスト、サッカー解説者、フォトカメラマン、作家、タレント、さまざまなジャンルの人たちが「このままでは危ない」と議論して発言して、「こうすべきだ」と主張して提言して、そして最後はハラハラしながら祈るように見つめた表現者たちの足跡
アジア最終予選を通じて、テレビ、雑誌、スポーツ紙などさまざまなメディアで、サッカージャーナリスト、フォトカメラマン、作家、タレント、さまざまなジャンルの人たちが、喧々諤々の議論を交わし、ある時は「このままでは危ない」と悲壮な面持ちで発言、ある時は「あの時こうだったから、今度はこうすべきだ」と主張して提言、そして最後にはハラハラしながら、もう祈るような気持ちでジョホールバルでの戦いに固唾を飲み、岡野雅行選手のVゴールが決まった瞬間、快哉を叫び祝杯をあげ、ドラマチックな73日間は大団円となりました。
ここに、そうしたサッカージャーナリスト、フォトカメラマン、作家、タレントなど、さまざまなジャンルのたち表現者たちの73日間の足跡を記録に留めておきたいと思います。
総合スポーツ誌Number、サッカー専門誌などで表現活動を繰り広げたサッカージャーナリスト、フォトカメラマンたち
1997.9.25Number427 表紙川口能活、井原正巳、名波浩 特集「日本代表、最終決戦」
・緊急速報第1戦日本vsウズベキスタン戦【文・金子達仁、フォト・佐貫直哉、西山和明】
・緊急速報第1戦韓国vsカザフスタン戦【文・永井洋一、フォト・吉澤晃】
・日本代表、最終決戦【フォト・深野泰利】
・密着インタビュー川口能活【文・佐藤俊、フォト・佐貫直哉】
・いざ出陣! 【フォトはすべて佐貫直哉】
中田英寿【文・金子達仁】、井原正巳【文・杉山茂樹】、名波浩【文・杉山茂樹】、
城彰二【文・佐藤俊】、相馬直樹【文・平野史】、斉藤俊秀【文・杉山茂樹】、
・ライバル国徹底分析【文・後藤健生、フォト・西山和明、フォート・キシモト】
・韓国代表最新レポート【文・崔仁和、フォト・吉澤晃】
・日本代表最終チェック【文・杉山茂樹、フォト・西山和明、佐貫直哉】
・ドゥンガ代表を一喝する【文・金子達仁、フォト・西山和明】
・加茂ニッポンにこれだけは言いたい!
【発言順・セルジオ越後、金田喜稔、杉山茂樹、金子達仁、後藤健生、永井洋一、武智幸徳、平野史、加部究、田村修一】
・ベルリン、饗宴の夏「オペルサッカー97」観戦記【文・杉山茂樹、フォト・田山一仁】
・KAZU W杯への日々【文・一志治夫、フォト・斎門富士男、佐貫直哉】
1997.11.6Number430 表紙ヒクソン・グレイシー 「岡田ジャパンはどうなる」
・日本サッカー協会に英断を求む! 【文・金子達仁、フォト・西山和明】
・三浦知良「死闘前夜」【文・一志治夫、フォト・西山和明】
・ボランチ中田で活路を開け【文・杉山茂樹、フォト・西山和明】
1997.12.4Number432 表紙中山雅史
・We did it ! 「伝説が作られた夜」【文・金子達仁、フォト・佐貫直哉、西山和明】
・車範根 対日戦勝利の方程式【文・崔仁和、フォト・佐貫直哉】
・密着ドキュメント中田英寿と川口能活の63日
【文・金子達仁、フォト・佐貫直哉、西山和明、梁川剛、田山一仁、吉澤晃】
・最終予選全8戦プレイバック
【文・杉山茂樹、金子達仁、後藤健生、佐藤俊(清水秀彦解説)、フォト・佐貫直哉、西山和明、梁川剛、田山一仁、吉澤晃】
・徹底チェック「戦術&システム」「出場全選手採点」【文・杉山茂樹】
・徹底チェック「日韓対決」【文・後藤健生】
・徹底チェック「決定力不足」【文・福山桂】
・精密検証「なぜ日本は1位突破できなかったのか」【文・後藤健生】
・知られざる内幕「元横浜Fエドゥーが語る加茂ゾーンプレスの真実」【文・大野美夏、フォト・西山幸之】
・日本サッカー協会、間違いだらけの監督選び【文・加部究、フォト・西山和明、梁川剛、吉澤晃】
1997.12.18Number433 表紙パオロ・マルディーニ W杯出場国32ケ国決定・選ばれし者たち
・独占インタビュー中田英寿「楽しかったあの夜」【文・金子達仁、フォト・宮本敬文、西山和明】
・連載インタビュー三浦知良「夢の結実」【文・一志治夫、フォト・佐貫直哉】
・メルボルン発「32番目の歓喜と落胆」【文・後藤健生、フォト・アフロフォト】
・不滅のアズーリ【文・藤島大、フォト・沢辺克史】
・スペイン代表「無敵艦隊の真実」【文・杉山茂樹、フォト・清水和良/アフロフォト】
・アフリカが世界を制する日【文・西部謙司、フォト・原悦生、赤木真二/アフロフォト】
・ジャマイカサッカー紀行【文・フォトとも・近藤篤】
1998.1.1Number434 表紙中田英寿 1997を語る
・中田英寿が世界を知った日【文・金子達仁、フォト・田村謙知、梁川剛、山田一仁】
・呂比須「歓びも悲しみも」【文・平塚晶人、フォト・久家靖秀】
・川口能活「夢は、まだ終わらない」【文・佐藤俊、フォト・NOBU(オーガスト)】
・岡田武史「静かなる変貌」【文・金子達仁、フォト・久家靖秀】
・フランスW杯を予想する【文・杉山茂樹】
1997.10.8サッカーマガジンNo626
・長期連載企画95.10 ▷ 97.9 「順調なアウェーの調整、際立つ「わき役」の存在」【文・編集部 伊東武彦記者】
1997.10.15サッカーマガジンNo627
・残り10分で狂った最大の賭け最大の誤算【文・編集部 伊東武彦記者】
1997.10.29サッカーマガジンNo629
・霧を抜けるカギは選手の心にある【文・大住良之】
・アルトマイに消ゆ挑戦「加茂サッカー最後の日」【文・編集部 伊東武彦記者】
1997.11.12サッカーマガジンNo631
・残されたカードは「原形」に戻るだけ、「日本代表に告ぐ!! ソウルで散れ! 」【文・編集部 伊東武彦記者】
・日本代表同時進行ドキュメント「静かな主将の辛い『10.26』」【文・編集部 伊東武彦記者】
1997.11.19サッカーマガジンNo632
・最終予選ダブルチェックシリーズ「さぁ最終決戦へ」【文・大住良之、水沼貴史】
・日本代表同時進行ドキュメント「ソウルで演じた『4つ』の復活劇」【文・編集部 伊東武彦記者】
1997.12.3サッカーマガジンNo634
・ジョホールバルの歓喜、悲願のW杯初出場!【文・編集部 伊東武彦記者、平沢大輔記者、フォト・糸賀正、高野徹、中島光明】
・日本代表同時進行ドキュメント「歓喜のフィナーレ、決戦イラン戦までの日々」【文・編集部 伊東武彦記者】
1997.12.4サッカーマガジン増刊号
・オメデトウ、ニッポン【文・ジーコ】
・現地緊急座談会・MVPは秋田、中央アジアですべてが変わった!【出席者・財徳健治(東京新聞)、大住良之、後藤健生、水沼貴史】
・「ゾーンプレス」に込められた魂【文・編集部 伊東武彦記者】
・「加茂監督」は退いても予選を戦いぬいたのは「加茂サッカー」だった【文・大住良之】
・記者席での71日間・朝日新聞運動部サッカー班キャップ奮闘記【文・潮 智史(朝日新聞)】
・メガネの中学生ーー岡田少年との出会い【文・賀川浩】
・「贅沢三昧」支えた陰の主役たち【文・原田公樹(スポーツライター)】
・余話としてー個人的な感傷ー【文・武智幸徳】
1998年新年号 別冊週刊サッカーマガジン「ワールドカップ初出場メモリアル写真集」【フォト・糸賀正、高野徹、中島光明、Yoshiaki Shimada、Kaoru Hasebe、Ikuya Enomoto、Shinkichiro Hayashi、Georges Rakic、The Associated Press】
・中田英寿・ロマンチストの横顔【文・川端康生】
・笑顔がいっぱい【文・編集部 伊東武彦記者】
・ボランチ・山口素弘【文・編集部 伊東武彦記者】
・メガネの料理人・岡田武史製の美味しいごちそう【文・編集部 伊東武彦記者】
1997.10.29サッカーダイジェストNo388
・カズはいらない! 先発メンバーの刷新がフランスへの最低条件【文・特派 戸塚啓記者】
・岡田監督の続投決定・・選手選抜にも変化の可能性が・・【文・スポーツライター増島みどり】
1997.11.12サッカーダイジェストNo390
・UAE戦観戦記Ⅰ「オレは聞きたい、なぜ山口を外す」【文・柱谷哲二】
・UAE戦観戦記Ⅱ「終盤の拙攻が命取り、修正ではなく徹底を」【文・早野宏史】
・勝利への提言PART8「日本サッカー界すべてを変えよ」【文・市原育成コーチ 加藤好男】
・緊急対談「日本代表に告ぐ」【加藤好男vs六川亨編集長】
1997.11.19サッカーダイジェストNo391
・夢は残った!! 喜んでいる場合ではない【文・特派 戸塚啓記者、フォト・佐藤明、田川秀之】
1997.11.26サッカーダイジェストNo392
・カザフ戦、これが日本の実力なんだ【文・六川亨編集長】
1997.12.3サッカーダイジェストNo393
・刻まれた歴史そして世界へ【文・特派 戸塚啓記者、フォト・佐藤明、田川秀之、中野義晶】
1997.12.18サッカーダイジェスト増刊「ジョホールバル歓喜の全記録」(永久保存版)
【フォト・佐藤明、滝川敏之、田川秀之、中野義昌、石渡規善、上野雅志】
・アジア最高のサポーターたちへ、フランスが君たちを待っている【文・マイケル・チャーチ(AFCニュース編集長)、翻訳・田村修一】
・私たちも戦いました【文・川平慈英、都並敏史、小宮悦子(ニュースキャスター)】
1997.12月刊ストライカー No175
・本当の勝負を前にして”いい風”が吹いてきた【文・木村和司、フォト・木鋪虎雄、木田祐二】
・最終予選が日本サッカーに教えてくれたこと【文・後藤健生、フォト・阿部正之介】
・不屈の挑戦「秋田豊」【文・小崎貴紀、フォト・木鋪虎雄、阿部正之介】
・日本サッカーへの緊急提言(1)日本サッカー協会トップの体質改善を望む!【文・昼間聡欣編集長、フォト・阿部正之介】
・日本サッカーへの緊急提言(2)これからは若い指導者の時代だ!【文・田嶋幸三、構成・昼間聡欣、フォト・・木鋪虎雄、小内慎司】
・日本サッカーへの緊急提言(3)サッカー協会はプロフエッショナルな体制を即刻に確立せよ!【文・伊藤庸夫(元日本サッカー協会国際委員)、フォト・木田祐二】
1998.1月刊ストライカー No176
・特集フランスが待っている! 新・世界標準「中田英寿」【文・西部謙司、フォト・岡沢克郎、阿部正之介】
・NORIスポーツNo22「やったぜ! 日本代表、木梨、男泣き」【文・木梨憲武】
・シリーズ「日本サッカーへの提言・岡田監督留任の決定方法に異議あり!」【文・編集部、フォト・菅原正治】
・シリーズ「日本サッカーへの提言・世界最高峰の舞台で岡田監督はベターといえるのか!?」【文・後藤健生、フォト・菅原正治】
テレビでの発言を通じて表現活動を展開した評論家・選手・タレントたち
1997.10.5 NHK-BS 2H00’00 緊急特集・監督更迭「W杯をめざしてジーコの提言」
司会・中村泰人アナ・王理恵、VTRゲスト、ジーコ、スタジオゲスト、加藤好男氏、財徳健治氏(東京新聞)、柱谷哲二選手、都並敏史選手、中山雅史選手
1997.10.25 NHK 1H14’00 土曜特集「どうすればフランスに行けるか、これがフランスへの切り札だ。知られざる闘いの50年より」
司会・堀尾正明アナ、ゲスト、加藤久氏、木村和司氏、清水圭、高見恭子、山藤章二氏、あとから参加・釜本邦茂氏、ナレーション・蟹江敬三
1997.7以降随時放送 フジテレビ「さんまのサッカー小僧」明石家さんま、都並敏史
1997.11.27-12.4 テレビ東京「サッカーTV」W杯アジア最終予選総括・解説者編(1)(2)
司会・川平慈英、久保田光彦、出演・清水秀彦、金田喜稔、水沼貴史
1997.12.11-12.18 テレビ東京「サッカーTV」W杯アジア最終予選総括・サッカージャーナリスト編(1)(2)
司会・川平慈英、久保田光彦、出演・財徳健治氏(東京新聞)、六川亨氏(サッカーダイジェスト編集長)、大西純一氏(スポーツニッポン)
以上、この年9月下旬から12月(雑誌系は発行日時の関係で1998年1月の日付になっている)にかけて「総合スポーツ誌」「サッカー専門誌」「テレビ」を賑わせたサッカージャーナリスト、サッカー解説者、フォトカメラマン、作家、タレントといった表現者たちの活躍を抜き出してみました。
詳細を見ていくと、特にサッカージャーナリストの人たちの数は決して多くはなかったことがわかります。Jリーグスタートを機に「サッカー文化」の担い手として表現者の活動を本格化させた人や、前年のアトランタ五輪代表の若い選手たちをいち早くフォローしてきた気鋭の人たちが中心であり、まだサッカージャーナリストという生業(なりわい)が成り立つのかどうかわからない時期に、果敢に表現者としての道に踏み込んだ人たちのようです。
しかしながら、この73日間を通じて原稿依頼を受けたこの表現者たちや、各専門誌の編集部の人たちは、おそらく昼夜を分かたずペンを走らせ、シャッターを押し現像作業を続けたに違いありません。どれほど忙しかったことだろうかと思うと身震いするほどです。
サッカージャーナリスト、サッカー解説者、フォトカメラマンといった切り口で、あえて、その活躍の様子を記録に留めようとしているのは、このサイトが「サッカー文化」という大きな文化の全体像を伝えようとしているためです。
その意味で、ワールドカップサッカーアジア最終予選という、戦場のような過酷で厳しい物凄い世界の中味を伝えてくれるサッカージャーナリスト、サッカー解説者、フォトカメラマンといった表現者の人たちの活躍の様子を伝えることは「日本のサッカー文化」が花開いている様子の描写そのものなのです。
この73日間の出来事とともに歩んだ表現者たちが先駆けとなって、翌年以降「サッカージャーナリスト、フォトカメラマン」といった分野には次々と若手の表現者たちが参入して育っていきます。この73日間が多くの新しい人たちを惹きつけたといっても過言ではありません。
「サポーター」という名の表現者たちもまた「喜・怒・哀・楽」そのままにスタジアムで感情表現を出し尽くした初めての経験
この73日間に起きた「サポーター」という名の表現者たちの行動、日本代表を応援するという行為が、これほどまでに「喜・怒・哀・楽」の感情表現となって出し尽くされた経験は初めてのことでした。「日本のサッカー文化」がスタジアムという巨大な空間の中で一気に花開いたかのような活動でした。
「サポーター」という名の表現者たちの73日間を「喜」「怒」「哀」「楽」のキーワードとともに、あらためて振り返ってみます。
日本代表サポーターといえば「ウルトラス」、「ウルトラス」といえばリーダーの植田朝日さん。その植田さんが1998年3月に上梓した著書「熱狂ロード ROAD TO FRANCE」(ザ・マサダ刊)には自身の73日間の「喜」「怒」「哀」「楽」とともに、さまざまなエピソードが綴られていますので、それを引用しながら辿ってみたいと思います。
【楽】初戦・ウズベキスタン戦の国立競技場は「ワールドカップに行くんだ! 」というサポーターのワクワク感と、さまざまな仕掛けがスタジアムを彩りました。まず、大きなブルーのビニル風船と日の丸の小旗に染まったスタジアム全体の色彩が目を奪いました。
次にスタジアムを夢空間にした光景は、FIFAアンセムがスタジアムに流れる中、両国選手たちが入場して、勢ぞろいしたタイミングを計ったようにリーダーの合図でバックスタンド全体に膨大な量の紙吹雪が舞った瞬間でした。
植田リーダーによれば、その量は150㎝四方のダンボール箱20個分、それを準備したのは役割を買って出た一人の女性だそうで、新聞紙を広げた1枚分をお札の大きさに切り分けて、一人のサポーターに渡せるよう輪ゴムでとめるという作業を、国立競技場前に張ったテントに缶詰めになり試合開始直前までかかって仕上げたのだそうです。なんの対価があるわけでもない作業を、ただ、ただ日本代表のためにという1点だけでやり遂げる熱量と責任感。
著書「熱狂ロード ROAD TO FRANCE」には「そうして作った紙吹雪が、カクテルライトを受け、銀色にキラキラ輝きながら上空を漂うのを見て(注・その女性は)泣き崩れたという。」と綴られています。ここにも1人、大きなプレッシャーと戦いながら求められた役割を果たし終え、その緊張感から解放された安堵感と、目にした感動的な光景に、わけもなく、とめどなく涙が溢れ出た人がいました。
さらには、日本代表サポーター「ウルトラス」の面々が陣取るゴール裏に「どらえもん」の巨大フラッグがウルトラスのメンバーたちが歌い上げる応援ソングに合わせて、ゆらゆらと揺れ続けます。この「どらえもん」の巨大フラッグ、実は当初、セントラル方式でどこかの外国で開催される場合の応援フラッグとして作ったのだそうです。
それは、外国のスタジアムで現地の人たちにもアピールできるフラッグにしたいと考えた時、世界的に知名度が高い日本のアニメキャラクター「どらえもん」しかない、しかも都合のよいことに「どらえもん」のカラーは青だったというのです。
そうした誕生秘話を持つ「どらえもん」フラッグは国立競技場を埋め尽くした満員の観客にも大うけで素晴らしい雰囲気ができました。
試合は日本代表サポーターのさまざまな仕掛けに後押しされながら終始リードして日本が圧勝、この上ない「アジア最終予選」のスタートを切りました。
初戦・ウズベキスタン戦の日本代表サポーターは、サッカーというスポーツの楽しさ、素晴らしさを「サポーター文化」の発露という形で存分に見せてくれました。
【哀】日本代表サポーターの【楽】の時間は長くは続きませんでした。第2戦、猛烈な暑さの中東でUAE戦に引き分けてメディアは「ガッチリ勝ち点1」と報じるところが多かったのですが、むしろ選手の中に「勝てる試合を勝ちにいかなかった」と首をひねる選手が目立ち、少し陰りが出てきたのです。遠くUAEまで足を運んだコアなサポーターたちには、そのことがよくわかっていてフラストレーションになっていたのです。
そもそも当初のセントラル方式からホーム&アウェー方式に変わったことにより、ホームゲームとして4試合、日本国内で応援できるというメリットを得たのも事実ですが、多くのサポーターたちはアウェー戦応援のための莫大な旅費の増加という「あおり」を受けました。もしアウェーのUAE戦応援を選べば、中央アジアでのアウェーゲームは応援を諦めなければならないといった具合です。そこで植田リーダーは知り合いの旅行代理店に「さらに格安のツァーが組めないか」と談判します。
その結果、のちに「弾丸ツァー」の名で呼ばれるようになる、試合当日午前に現地入り、試合終了後即帰国という超格安ツァーが生まれました。まさに「哀愁のサポーター」です。
続く第3戦、ホームの韓国戦、山口素弘選手のサッカー史に残るビューティフルゴールで先制したまではよかったのですが、その後、なぜか国立競技場には雨が落ちてきます。
まるで、その雨に急かされるようにベンチが動き日本のバランスが崩れてしまったところを韓国に突かれ先制点を守り切れず逆転を許してしまいます。
呆然とする日本イレブン、スタンドのサポーターも信じられない思いで天を仰ぎます。その頬に強くなった雨足が打ち付けました。国立競技場の夕刻は涙雨に濡れる哀しいものとなりました。
そして、中央アジアの連戦の中、監督交代という衝撃が走り、最初のカザフスタン戦は先制した試合を後半終了間際に追いつかれ、次のウズベキスタン戦は先行された試合を後半ロスタイムに同点に追いつくという真逆の展開で2試合とも引き分けに終わりました。
ウズベキスタン戦では、日本代表サポーターもウズベキスタン観客からのアウェーの洗礼を受けました。1点リードされた日本サポーターがますます応援のボルテージをあげていくと、うるさいと感じたのかウズベキスタン観客からのいやがらせを受けます。著書「熱狂ロード ROAD TO FRANCE」にはこう綴られています。
「見たこともない果物の種のようなものや空き缶、飲みかけのペットボトルなどがバックスタンドの中央付近から容赦なく飛んできた。それが唇にあたって、口から血を吐き出しながら叫んでいるヤツがいる。俺の横ではうじきつよしさんが空き缶をぶつけられたものの表情ひとつ変えずに黙々と応援を続けていた。」
「そしてロスタイムに入る直前、(中略、注・同点となるヘディングが)ゴールに吸い込まれたのだ。やった! 思いが通じたぞ!! まるで勝ったような大騒ぎになり、俺もまわりの連中も感極まって、抱き合って泣いていた。」
「収まらないのはウズベキスタンのサポーターたちだ。怒りにまかせて、種や空き缶などをどんどん投げ込んでくる。それに怒った日本サイドからも、空き缶やオレンジで応戦するヤツが出た。」
「こりゃマズイ。『止めろ。投げ返すんじゃない』と叫んだがあとの祭りだった。投げ返したことで、ウズベク人たちの怒りがスパークし、何倍ものカンや瓶が飛んできた。俺たちはスタンドに1枚だけ出していた『大和魂』のフラッグを頭上に掲げて難を凌いだ。投げ付けられたタバコの火で旗の一部が焼けてしまうというハプニングもあったが、この旗がなかったらケガ人が多数出ていたのは間違いない。」
サポーターたちは、ほうほうの体でスタジアムをあとにしますが、一方では、あの同点ゴールに酔いしれ、自力突破の可能性という数字以上のものを感じながら帰国したのでした。
しかし日本国内のムードは「絶対絶命」「日本瀕死」、スポーツ紙の一面が報じる暗いムードにありました。次の第6戦、ホームUAE戦をどう応援していけばいいか、どうしたら日本代表の面々を奮い立たせられるか。植田リーダーを中心とする「ウルトラス」のメンバーは「歌を変えよう」と相談しました。それまでのウルトラスのテーマソングは坂本九ちゃんの「上を向いて歩こう」でしたが著書「熱狂ロード ROAD TO FRANCE」にはこう綴られています。
「これでは弱い、 日本代表は死にかけているのだから、夢があって力を与えてくれるようなものがいい。(注・♫上を向いて では)メッセージの温度も低いし、リズムも応援歌という感じではない。しかも日本人ならだれでも知っているようなもので、お披露目なしの一発勝負をかけられるようなもの・・・・。」
そうして選ばれたのが「翼をください」でした。
迎えた国立競技場のUAE戦、勝てば状況を一気に好転できる希望を込めて、国立競技場にサポーターの大合唱が響きました。
「♫いまぁ~~、私の~~、ねがいごとが~~、叶うならば~~、♫つばさをください~~」
哀愁を帯びたこの曲を唄うことにしたサポーターの心情、曲は「♫この大空に、翼をひろげ、飛んでいきたいよ~~~、」と気持ちを奮い立たせるように続きます。
日本代表のために、日本代表を後押ししたいがために、どうにかしたい、その思いから自然発生的に大合唱を始めた日本の応援サポーターほど素晴らしいサポーターはいないと感じた時でした。彼らは明らかに「表現者」でした。
【怒】スタジアムの中で「翼をください」を大合唱したサポーターたち、その願いも空しく引き分けに終わった日本代表の不甲斐なさに「可愛さ余って憎さ百倍」の心情になったのでしょうか、今度は怒りを募らせました。選手がスタジアムから出ようとする正門前で多数のサポーターが荒れ狂ったのです。最初の試合に勝ったあと、4試合勝ちから遠ざかっている日本代表。「おまえら応援するだけの価値があるのか」ということなのでしょうか。
ただ「ウルトラス」の植田リーダーは「暴動を起こしたヤツラの中にウルトラスの人間はいない」そう確信していると著書の中で述べています。
【喜】UEAとの試合後、サポーターからの強烈な怒りにさらされた日本代表。実はチームとしての戦い方を取り戻しつつあったところでしたから、そのあとは韓国、カザフスタンに快勝して第3代表決定戦、見事に「ジョホールバルの歓喜」をもたらします。最後はサポーターたちに極上の歓喜をプレゼントして壮大なドラマが完結しました。
韓国・蚕室スタジアムでのアウェー戦、実はウルトラス・植田リーダーは日章旗をはためかせるかどうか悩んでいたといいます。韓国人で満員になっているスタジアムで日章旗を掲げることなど、あまりに恐怖を感じることだからです。
それでも意を決して日章旗を掲げてみると、意外や意外、何の拒否反応もない、むしろ友好的と感じるほどで拍子抜けしたそうです。
と同時に「これが日韓共催のもたらした効果なのだ」と身をもって感じたそうです。
日本代表を応援する「ウルトラス」を中心としたサポーターたちは、この数年を通じて秩序だった行動ができるようになりました。けれども表現活動という意味では、まだまだ試行錯誤を重ねながらだったと思います。初戦の紙吹雪、青いゴミ袋など、とにかくできることをやりながら精一杯応援していくということです。
紙吹雪はその後使えなくなりました。そこで第8戦には紙テープでした。白とブルーの2色の紙テープそれぞれ1万本づつ、計2万本の紙テープが選手入場後、植田リーダーの合図とともにスタンドから外周トラックめがけて投げ込まれました。初戦の紙吹雪とはまた違った夢空間の出現でした。
この紙テープもまた、なんの対価があるわけでもない作業を、ただ、ただ日本代表のためにという1点だけでやり遂げる熱量と責任感をもった一人の女性が準備したものでした。初戦の紙吹雪を用意した仲間の女性の苦労を知っていたのかどうか、わかりませんが、同じように紙テープが入った山のようなダンボール箱を相手に孤軍奮闘して間に合わせたのです。
こうした紙吹雪や紙テープ、そしてサポーターの象徴である「12」の文字をあしらった巨大フラッグや「ドラエモン」フラッグ、さらには「翼をください」の大合唱、日本代表を応援する「ウルトラス」を中心としたサポーターたちは、表現者として力を合わせてスタジアムを彩りました。
国立競技場での4試合、そして韓国・蚕室スタジアム、マレーシア・ジョホールバル、そこには、紛れもなく日本代表サポーターという名の表現者たちによって「日本のサッカー文化」の花が開いたのです。
日本代表サポーターという名の表現者たちの73日間、その最後に「ウルトラス」植田朝日リーダーが著書に書き記した言葉を紹介して締めくくりたいと思います。
「俺はサッカーが大好きだ。だから日本代表が出ていなくてもW杯を観戦しに行ってしまう。そんなとき、俺はそこのピッチで戦う日本代表の姿を幾度となく思い浮かべたものだ。(中略)自分たちの選手に応援を送ることができるよその国のサポーターをどれだけうらやましく思ったことか。でももういやだった。正々堂々と、会場で日の丸を振ってニッポン・コールをやりたかった。もう十分すぎるほど待たされたのだから。」
「本来ウルトラスとは日本代表を応援するというひとつの目的のために存在し、規則も規約もないその場限りの集団である。だからメインスタンドがシーンとしていても俺たちは声を出せとは絶対言わない。もし一緒に声を合わせて応援したいと思ったら、それがすなわちウルトラスになった瞬間なのである。」
「代表を信じよう、諦めるなって、俺ははっきりいってこのセリフを4年間言い続けてきた。正直言えば、ふざけんな!! って言いたいさ。いつもいつも信じよう、声出して応援しよう・・・。これじゃ単なるお人よしだよ。でも俺たちサポーターができることって信じて応援することだろ。じゃあ可能性がまったくなくなるまで、みんな、代表を信じようぜ。」
「(注・人の)体温は計れるが、心の温度は計れない。だからサポートに熱中する心理を第三者は知り得ない。でも、これだけは知っておくべきだろう。夢や志と同様に、人の心には『熱中』という重要な要素があることを。それがあるのと無いのとでは、人生に充実度が全く違ってくるように思えてならない。」
こうして「日本のサッカー文化」が「開花宣言」できるところまできた様子を描写できるというのも、日本サッカー史上初のワールドカップ出場に向けた「アジア最終予選」という、73日間の出来事がもたらした、もう一つの成果と言えると思います。
何もかもが記録的な規模となった日本サッカー初のワールドカップ出場に向けた「アジア最終予選」により「日本のサッカー文化」のつぼみが花開いたのですが、その一方では「サッカーの持つ底知れぬ怖さ」が監督・選手たちを苦しめた73日間でもありました。
サツカー日本代表監督の家族が警備対象になり、マレーシアでの戦いを勝利して「これで生きて日本に帰れる」と安堵するほどの心理的重圧を背負っていた監督・選手たち、「サッカーの持つ底知れぬ怖さ」を思い知らされた73日間
加茂監督の更迭により、後を引き継いだ岡田監督、しかし指揮をとったウズベキスタン戦、そして国立競技場のUAE戦、勝利をあげられず厳しい批判に晒されます。
国立競技場でのUAE戦も引き分けた日本代表に対しては、怒りのサポーターたちが暴動を起こします。このサポーターたちの暴動については、UAE戦の試合をレポートした部分で詳細に記録していますので、ここでは重複を避けます。
暴動の余波と思われる事態は、あまり知られていない話ですが、数日後、三ッ沢球技場でも「ボヤ騒ぎ」という形で起きています。横浜・三ッ沢球技場で日本代表が行った非公開練習を狙ったかどうか定かではありませんが、日本代表を取り巻く不穏な環境は拭いきれていませんでした。
これまで経験したことのない怖さは、岡田監督とその家族に対して向けられた心無い仕打ちでした。
その当時、どの家にも職場にも、NTTの分厚い電話帳があって、だいたいの人は住所と電話番号を掲載しており、岡田監督も例外ではありませんでした。その関係で、岡田家には怒りのサポーターたちからの脅迫状や脅迫電話が山のように押し寄せたのです。
これを受けて警察は岡田監督の自宅を警護対象にしてパトカーを配置、お子さんも危険なので学校への送り迎えをするように、といった具合になります。監督本人も、電車には乗れない、繁華街には出かけられない、といった何とも物騒で不自由な目に遭ったのです。
そんな中でも岡田監督、ずっと子供たちと一緒に遊んでやれなかったと言って、第3代表決定戦前の、つかの間の休日に、当時大人気だったアニメ映画「もののけ姫」を子供さんたちと一緒に見るため映画館に足を運んだといいますから、やはり並みの人間ではなかったことを表しています。
そして、マレーシア・ジョホールバルでのイランとの決戦前夜、岡田監督は、日本にいる奥さんに電話を入れます。「もしW杯を決められなかったら日本に帰れないから別れてくれ。そこにいたら危ないから子供を連れて実家に帰れ」と伝えています。
何年か前までは、日本との試合には絶対負けてはならないという使命感を抱いていた韓国の監督・選手たち、「負けたら玄界灘に身を投げて国には帰ってくるな」と言われていたと伝わっていますが、岡田監督もその逸話が頭をよぎり「自分の場合は負けたらマラッカ海峡か・・・」と考えたそうです。とうとう日本でも、サッカー日本代表の監督を引き受けるというのは、そういう覚悟が必要な立場になっていたのです。
岡田監督は、その電話のあと、どう戦うか考え始めます。しかし「明日急に名将にはなれない。いまの俺の力をすべて出すしかない。命がけでやるけれど、だめだったら日本国民に謝ろう。悪いのは俺を選んだ会長だ」と開き直ったそうです。すると、怖いものがなくなったというのです。
極限まで追い詰められた人間の遺伝子にスイッチが入ったと振り返っています。
第3代表決定戦を劇的Vゴールで制し、ワールドカップ出場権獲得を果たした日本代表は、スタジアムからホテルに戻るバスの中、とてもお祭り騒ぎの気分にはならなかったといいます。
激闘で疲れ切っていたことに加え「これで日本に帰れる」という安堵感がバスの中を支配していたからだそうです。
監督も選手も「これで生きて国に帰れる」と心底思うほど、サッカー日本代表が受ける重圧は重くのしかかっていたのです。
これほど起伏に富んだ73日間は、日本サッカー史上初めてのことであり、その後も、これほどまでに感情の起伏の浮き沈みのある戦いを経験しているのかどうか、その後の歴史をひもとくしか術がありません。
ここまで、日本のサッカー文化を一気に開花させた数々の記録的出来事、未知の体験、同時に「サッカーの怖さ」を目の当たりに知ることになった出来事をまとめてみましたが、これらの体験を通じて、日本サッカーが世界的に見て、どの位置にいるかを考えてみます。
1991年以前の日本は紛れもなく「サッカー後進国」でした。そして1992年、1993年を経て「ドーハの悲劇」を経験しましたが「サッカー後進国」からは脱却して「サッカー発展途上国」の仲間入りをした程度になりました。
そして今回、フランスワールドカップ出場権獲得のための73日間の経験を経て日本は「サッカー新興国」の仲間入りをしたと言っていいでしょう。
ここから先は長い道のりかも知れませんが「サッカー先進国」の仲間入りを目指していくことになります。一歩一歩着実に、成長・発展・進化を積み重ねていくことでしか辿り着けない世界なのだと思います。
ちなみにFIFAランキングで、日本はアジア最終予選の第7戦・韓国戦以降3連勝したことが奏功、1月に21位からスタートした順位が最終的には14位まで上昇してこの年を終えました。
Jリーグ後期、日本代表選手抜きで開催、磐田が初制覇
Jリーグ後期はW杯アジア最終予選の開催方式がセントラル方式からホーム&アウェー方式に変更され日程も2ケ月半という長丁場となることになったことから、急遽、代表選手抜きのまま実施することになりました。
後期から加入した新外国人選手も多数に上りましたが、主な選手をご紹介しておきます。
浦和にベギリスタイン選手、ヴ川崎にアルシンド選手(札幌を退団後、一度帰国して2度目の来日)とジアス選手(以前、清水に在籍経験があり2度目の来日)
7月30日、後期が開幕しました。7月19日に前期が終了してから、わずか10日余りのインターバル、しかも4日前にオールスター戦を終えたばかりの日程でした。1節の試合で早くも記録的なゴールが生まれました。平塚vs柏戦、ホームの平塚がロペス選手の2ゴールなど6選手が計7ゴール、敗れた柏も4ゴール、両チームで11ゴールというJリーグ記録となる打ち合いとなりました。
8月2日の2節清水vs柏戦、清水サポーターが柏の延長Vゴール判定を不服として暴走、制裁金500万円科される。
8月15日、1年前、京都に電撃移籍したラモス瑠偉選手、またもヴ川崎に電撃復帰
8月16日の5節、横浜Fvs鹿島戦、5-3で横浜F勝利の試合、横浜F・山口素弘選手がボランチの選手として珍しいハットトリック達成
8月20日の6節、鹿島vs磐田戦、前節まで5連勝中の磐田、2-0で鹿島に敗れ連勝ストップも首位はキープ
7節以降、日本代表選手が不在の戦いとなる
8月23日の7節、G大阪vsC大阪戦、C大阪の横山貴之選手、Jリーグ通算4000ゴールのメモリアルゴールを記録
9月13日の12節、平塚vsC大阪戦、平塚・呂比須ワグナー選手、帰化申請が認められ、晴れて日本人選手として2ゴール、チームの勝利に貢献、呂比須選手は13節の鹿島戦のあと日本代表に招集される
9月20日の13節、ヴ川崎vs磐田戦、中山雅史選手のハットトリックなど6-1で磐田圧勝、再び首位にたつ
9月24日の14節、磐田vsG大阪の首位攻防戦を磐田が延長の末制し、首位キープ
10月1日の16節、市原vs磐田戦、磐田が奥大介選手の2ゴールなど5-0で圧勝、後期優勝を決定。
磐田は、95年シーズンから加入したブラジル代表キャプテン・ドゥンガ選手が強いリーダーシップでチームの成長を促し、今シーズン初めに監督に就任したばかりのルイス・フェリペ・スコラーリ監督が、前期の中断期間に辞任するという緊急事態にもかかわらず、監督代行となった桑原隆氏がうまくチームをまとめ、初のステージ制覇を果たしました。
1993年のJリーグスタートには名を連ねることができず、翌年、昇格によって参入したチームとして磐田が初めてステージ制覇を果たしたという意味で、記録的な優勝となりました。
後期の磐田は、スタートダッシュよく5連勝で首位にたちますが、アジウソン選手、ドゥンガ選手がケガで欠場したた6節鹿島、7節名古屋に連敗、首位を明け渡しました。しかし、ケガから次々と選手が戻ってくると、再び連勝が始まり、13節再び首位に浮上、14節には僅差で追うG大阪との試合をドゥンガ選手のVゴールで制し、15節、16節も連勝、最終節を待たずに優勝を決め、最終節の清水戦にも勝って9連勝で後期を締めくくるという強さを発揮しました。
前年まではオフト監督、スキラッチ選手といったカラーが強かったチームでしたが、いわば、その重しがとれたこと、今年前期も監督の途中交代の影響で、戦いが不安定になり優勝争いには絡めませんでしたが、桑原隆氏が監督代行として指揮を執ることになった際、ヘッドコーチに就任した山本昌邦コーチが、若手の能力をうまく引き出した結果、各選手が持っていた潜在能力が表に出てきた成果だと評価されました。
主力の名波浩選手を日本代表で欠いたままでしたが、中山雅史選手と藤田俊哉選手が安定した力を発揮、それに田中誠選手、服部年宏、鈴木秀人選手のアトランタ五輪組や奥大介選手などの若手が力をつけ、またMFドゥンガ選手、DFアジウソン選手が守備陣を引き締めて、他チームの監督が口を揃えて「後期の磐田にはとても勝てない」というほどのチームに変貌しました。
特に奥大介選手は、前期途中で辞任したルイス・フェリペ監督が、その才能を見出して起用、シーズンを通して経験を積むうち、桑原監督代行をして「うちのキーマンは奥」と言わしめる成長ぶりで磐田後期優勝の大きく貢献しました。
折しも日本代表がアジア最終予選の苦しい戦いを続けている中での優勝ということで、大黒柱の中山雅史選手の日本代表待望論につながるとともに、すでにグループリーグを突破しているナビスコカップでの戦いにも弾みがつくこととなりました。
浦和・ブッフバルト選手、惜しまれながら退団
この後期終了をもって、横浜F・ジーニョ選手が退団することについてはすでに触れましたが、浦和・ブッフバルト選手も退団することになりました。
ブッフバルト選手は、1994年7月、浦和に加入して以来3シーズン半、Jリーグでプレーを続け、浦和をそれまでのJリーグお荷物チームと酷評されていたチームを、闘志あふれるプレーと、常に全力でプレーするその姿勢で、たちまちチームの精神的支柱となり、1995年前期はチームを3位に躍進させる原動力となりました。
その後も強豪の一角と目されるチームの押しも押されぬ大黒柱として活躍したことから、本当に惜しまれての退団となりました。クラブは退団セレモニーでスタジアムの中に白馬を用意、ブッフバルト選手は白馬にまたがってスタジアムを1周するという花道の中、日本を去りました。
後年、今度は監督として浦和に戻り、また栄光を築くことになりますが、それはのちほど。
Jリーグレギュラーシーズン終了間際から、幾つかのクラブ出資企業首脳が発言、清水の経営危機も表面化
Jリーグ後期も終盤にさしかかった9月30日、スポーツ報知紙に「ヴェルディ解散も 渡邊読売新聞社社長爆弾発言」という刺激的な見出しの記事が掲載されました。
読売新聞社・渡邊社長の「爆弾発言」は毎年のように報じられ、主にJリーグ・川淵チェアマンに向けられるものが中心でしたが、今回は、前日の29日、読売新聞社・渡邊社長、水上会長、日本テレビ・氏家社長の3者が会合を持ち、前期は17チーム中15位、後期も、この日まで13位に甘んじている「ヴェルディ川崎」について協議したというのです。
3時間半に及ぶ会談は、ヴェルディのチーム改革について始まったようですが、おのずと、これまでも対決姿勢を示してきたJリーグ・川淵チェアマンへの批判に及んだそうで、会合を終えた渡邊社長は、記者団に次のように語りました。
「ウチ(注・ヴェルディ川崎)は25億円以上の赤字(注・氏家日テレ社長は3年間で50億円と発言している)で、JR(ジェフ市原)も10億だ。川淵(チェアマン)は各チームの赤字にあぐらをかいている。断じて許せない。(Jリーグを)脱退するか、改革させるか、ヴェルディをつぶすかだ」
このタイミングでの会合・発言についてスポーツ報知は「93年の開幕時から年々、観客減に悩むJリーグ。W杯アジア最終予選で日本代表が韓国代表に敗戦を喫したタイミングを計っての発言とも受け取れる。」と見立てていました。
読売新聞社・渡邊社長の発言から1週間後、今度はジェフ市原の主要出資企業のJR東日本・松田社長が定例記者会見で発言、それを受けて10月7日のスポーツ報知紙に「ジェフ解散ピンチ、撤退へ」という見出しが躍りました。
JR東日本・松田社長の発言は、Jリーグが1999年から移行を計画しているJ1,J2制に伴うチーム数の増加はJリーグの存続を危うくするという危機感が背景にあります。松田社長は「Jリーグの首脳はチーム数を多くして金もうけばかりに熱心だが、チーム数を多くすると選手層が薄くなり強い選手は育たない」「Jリーグの考え方は世界のトップ水準から30年くらい遅れている」と考えているというのです。
この発言についてスポーツ報知は「チーム名から企業名を外すことに反対している、ヴェルディ、ジェフ、フリューゲルスの各親会社は、それが認められないことについて、親会社として莫大な資金を使っていてもメリットがまったくないと苛立ちを強めている。しかも観客数も年々減少していて、経営的にも厳しくなる一方、加えて、W杯アジア最終予選で、もしウズベキスタンに負けようものならW杯出場は絶望的になり、サッカー人気の浮上は望めないことから、強い危機感から出ている発言とみられる。」と見立てています。
このあと、時系列的には、日本代表が「ジョホールバルの歓喜」によってW杯出場を決めましたので、渡邊社長も松田社長も振り上げたこぶしを降ろしかねてしまったと見えて、しばらく次の発言は聞かれませんでした。
読売新聞社・渡邊社長の「川淵(チェアマン)は各チームの赤字にあぐらをかいている。断じて許せない。」という発言を聞いた記者たちは「自分のチームの成績低迷、観客動員の低迷にあぐらをかいているのは親会社のほうではありませんか?」と切り返したくなったと思いますし、JR東日本・松田社長の発言にあった「Jリーグの首脳はチーム数を多くして金もうけばかりに熱心だが、チーム数を多くすると選手層が薄くなり強い選手は育たない。世界のトップ水準から30年くらい遅れている」という発言を聞いた記者たちは「チーム数が多くなると、逆に選手層が厚くなり強い選手が育つのが世界標準の考え方なのですが・・」と切り返したくなったと思います。
松田社長の定例会見時に、当の川淵チェアマンは日本代表の中央アジア遠征に同行していて、日本代表の戦いぶりにやきもきしていたことは確かですが、渡邊社長や松田社長の発言には「またか」といった程度の気持ちだったことでしょう。
それよりも、11月に表面化した清水エスパルスの経営危機には、Jリーグ首脳も慌てたことと思います。
Jリーグで唯一大企業の出資母体を持たないクラブ・清水エスパルスが約20億円もの負債を抱え倒産の危機に瀕していることが、運営会社の公表で表面化、そのためもっとも出資比率の高い㈱テレビ静岡が撤退を表明したのです。
クラブは、設立以来の危機感に乏しい経営と、成績も中位でJリーグ人気の下降により収益が伸びず赤字が累積していたのでした。
これにより、まずファン・サポーターが立ち上がり支援活動を始め、合わせてクラブが再建方法を早急に見出していくことになりました。
歯止めがかからない観客動員の低下、人気チームと2極化
Jリーグは特に後期、W杯アジア最終予選の開催方式がセントラル方式からホーム&アウェー方式に変更され日程も2ケ月半という長丁場となることになったことから、急遽、代表選手抜きのまま実施することになりました。
このこともあり、後期の平均観客動員数は9,651人と1万人を割り込み、年間の平均観客動員数も10,131人と過去最少の数値となってしまいました。それでも、地域密着型の運営を行った鹿島や浦和は観客動員数を大きく落とすことなくシーズンを終え、クラブ間の経営手法による格差が浮彫りになったシーズンでもありました。
この状況についてサッカー専門誌などのメディアは、概ね次のような見方をしています。
一つは、観客動員の減少については、これまでが独特のJリーグ人気によって支えられていた部分がなくなり、いわば、このぐらいの水準が、ある意味正常な水準であり、各クラブは、こういう水準を前提にした経営計画を立てるべきなのではないか。
二つ目は、鹿島や浦和のスタジアムに活気があるのは、チームとして強い弱いの問題だけではなくスタジアムを「劇場」「非日常空間」にできるかどうか、そのためにはクラブとしての個性、独自性といったものをサポーターとともに築けるかどうかのほうが重要だと思われる。
三つ目は、強力な親会社の支援を持たないクラブのあり方を、本気になって模索すべき時期にあることを清水の危機が教えてくれている。清水はそういうクラブだが、地域の情熱は、へたな親会社にぶらさがっているクラブより、よほど熱いものがあり、それをベースにしたクラブに変貌を遂げれば、むしろ新たなモデルになり得ると思われる。
Jリーグ各クラブの抱える問題は、このあとも表面化し続けます。1998年には、さらに悲劇的な出来事が起きることを、まだ、この時は、誰も知るよしがありません。
1999年からのJ2リーグ参加9クラブ決定、JFLは札幌が優勝、来期のJリーグ昇格を決める
1999年シーズンからJ1,J2リーグ制に移行するプランを進めているJリーグは、4月からJ2への参加受付を行なっていましたが、応募クラブの審査を行ない、10月9日、Jリーグ理事会において、下記9クラブを決定しました。(北から順に)()内は母体チーム
・ベガルタ仙台(ブランメル仙台)、・モンテディオ山形(NEC山形)、・大宮アルディージャ(NTT関東)、・FC東京(東京ガス)、・川崎フロンターレ(富士通)、・ヴァンフォーレ甲府(甲府クラブ)、・アルビレックス新潟、・サガン鳥栖、・大分トリニータ
1998年11月にはJ1参入決定戦が行なわれることになっており、その時点でのJリーグクラブから1チームJ2に降格して、1999年シーズンは10クラブでJ2がスタートすることになりました。
一方、4月20日、16チームでスタートした1996年第6回ジャパンフットボールリーグ(JFL)は、2回戦総当たりの30節で行われました。
この年は、前年2位以内に入ってJリーグ昇格を果たした神戸と、コスモ四日市が廃部のため抜け、かわりに全国社会人地域リーグ決勝大会で1位となった静岡・ジャトコと2位になった水戸ホーリーホックが昇格、これに年初、一旦クラブが破産宣告のため消滅した鳥栖フューチャーズに代わるクラブとして承認された「サガン鳥栖」がそのまま残り、16チームで優勝争いが行われました。
「サガン鳥栖」は、鳥栖フューチャーズの破綻後、チーム存続を求める5万人を超える署名があった事などを受けて、Jリーグ・ジャパンフットボールリーグ(JFL)の臨時実行委員会が、1997年2月1日、受け皿となる新チームの加入(実質残留)を決定したことにより生まれたチームでした。
同年2月4日、佐賀県サッカー協会などが任意団体「サガン鳥栖」を創設し、鳥栖フューチャーズの権利を引き継いでスタートしたのです。その後、サガン鳥栖は1998年に法人化され、1999年からのJ2リーグ参入を果たしていったことはご存じのとおりです。
この一連の処理は、Jリーグ・ジャパンフットボールリーグ(JFL)が、ファン・サポーターの熱意に応えた好例として語り継がれるべきことですが、注目度が高く複雑な規約に縛られているJリーグと異なり、比較的柔軟に処理できるジャパンフットボールリーグ(JFL)の事案だったからかも知れません。
さて、ジャパンフットボールリーグ(JFL)の戦いは、10月22日、コンサドーレ札幌が第28節ホーム大分戦で2-1で勝利して昇格とJFL優勝を決めました。札幌はリーグ最終戦も勝利して26勝4敗(全16チーム)でホーム無敗記録(ホームスタジアムの名前をつけて『厚別神話』と呼ばれ)での昇格達成となりました。その後、11月18日にJリーグの臨時理事会で正式に昇格が承認されました。
このシーズンの札幌は、前身の東芝に在籍していたこともあるパナマ代表のバルデス選手が鳥栖からの移籍で復帰、アビスパ福岡から世界的に有名なディエゴ・マラドーナの実弟であるウーゴ・マラドーナ選手、ジュビロ磐田からGKハーフナー・ディド選手らを補強、前年挑戦して果たせなかったJリーグ昇格を、見事達成しました。
この年の札幌は、このあとでも紹介しますがナビスコカップでもグループリーグを突破する快挙を成し遂げていて、エース・バルデス選手のリーグ戦40ゴールという記録とともに話題をさらいました。
札幌のJリーグ昇格には、地元テレビ局の強い後押しも少なからず働いています。北海道唯一のプロスポーツチームである「コンサドーレ札幌」に対する地元テレビ局の「チーム愛」はホームゲームを必ず5局あるどこかの局が放送するという形で表れていて、それが試合情報の告知や選手の露出アップにつながり、それが、さらにサポーターをスタジアムに向かわせるという相乗効果を生み出しているのです。
寒冷地というハンディを負っていながら、地元愛に支えられた札幌の昇格は、さまざまなハンディを抱えるJリーグクラブの一つのモデルを提示しているとも言え、来シーズンのJリーグでの活躍が楽しみです。
これで1998年Jリーグは、この年の17チームから一つ増えて18チームとなります。
この年のジャパンフットボールリーグ(JFL)では、やはり準会員の川崎フロンターレが僅か勝ち点1の差で3位に終わり、昇格条件2位以内というハードルを越えられず涙を飲みました。川崎Fは、このあとも昇格レースでしばらく苦難を味わうことになります。ちなみに2位は準会員資格を持たない東京ガスでした。
そのほか福島FCが経営難からチームを解散、西濃運輸も廃部となりました。
ナビスコカップは鹿島が初制覇
1997年のJリーグナビスコカップは3月8日に開幕し、決勝は11月29日に行われました。このうちグループリーグは3月8日から3月29日迄の日程でした。
参加クラブはJリーグの17クラブと、JFL所属でJリーグ準会員資格を持つコンサドーレ札幌・ブランメル仙台、ならびにJFL参加予定のサガン鳥栖FCの計20クラブを4チームずつ5グループに分け、各グループ1位と、各グループ2位のうち成績上位3チームの合計8チームが決勝トーナメント進出となった。
サガン鳥栖FCは、直前に解散したJリーグ準会員の鳥栖フューチャーズを実質的に承継するチームであることから、救済措置として特例的に参加を認められたものです。
なお、前年1996年の大会では、同一カードを土曜日と次週水曜日に連戦する変則ホーム&アウェーで2試合の成績をもとにして勝ち点を与えていた方式でしたが、これが複雑でわかりにくい方法だったため、今大会は通常のリーグ戦と同じく1試合ずつの勝ち点制としました。
グループリーグの結果、以下の8チームが決勝トーナメントに進出しました。
・グループA 1位市原、 ・グループB 1位札幌、 ・グループC 1位鹿島、2位浦和、 グループD 1位柏、2位名古屋、 グループE 1位磐田、2位横浜F
このうちJFLから参戦の札幌が、ヴ川崎、G大阪、横浜MといったJリーグ勢を押しのけて、JFL勢として唯一決勝トーナメント進出を果たしました。
決勝トーナメントは全てホーム&アウェーで行い、2試合の合計点数で勝敗を決める方式が採用されました。
第1戦は90分で終了。第2戦の90分終了時点で勝敗が決まらない場合は、Vゴール方式の延長戦→PK方式で決定する方式です。決勝も2試合連戦(ホーム・アンド・アウェー)となったのはこの大会が初めてでした。
準々決勝は10月15日に、第2戦が10月18日に行われ横浜Fが柏を、磐田が浦和を、鹿島が札幌を、名古屋が市原を、それぞれホーム&アウェーの2戦合計で退けました。
特に鹿島はJFLからの挑戦となった札幌に第1戦2-1、第2戦は7-0と圧勝、格の違いを見せつけました。
続く準決勝は第1戦が11月1日、第2戦が11月8日に行われ、鹿島が名古屋を2戦計1-0で辛くも退け、磐田も横浜Fを2戦計2-2の同点から延長の末辛くも退けました。
そして決勝、すでにJリーグチャンピオンシップでも年間王者を争うことが決まっている鹿島と磐田、新時代の両雄の対決となりました。
第1戦は11月22日、磐田スタジアムでの試合でした。このあと続くチャンピオンシップまでの4連戦の初戦という位置づけでしたから、両チームとも激しい闘志を燃やし相手に対する厳しいチェックの応酬のためファウルによる直接FKが合わせて22本、鹿島・名良橋選手がイエローカード2枚により退場処分を受ける中、1-1の同点で迎えた後半41分、鹿島がPKを獲得、これをジョルジーニョ選手がきっちり決めて2-1でものにしました。
続く第2戦は11月29日、雨のカシマスタジアムに14,444人の観客を集めて行われました。試合は第1戦と異なり一転、鹿島の攻撃が冴え特に攻守のつなぎ役として成長した増田忠俊選手の活躍で鹿島が5ゴール、磐田の反撃を1点に抑えて圧勝しました。
鹿島は準決勝までレギュラーで日本代表組の4人を欠いた中でも控えのDF陣がよく踏ん張り決勝まで辿り着いての初優勝で、昨年の年間王者に続く2冠目を達成しました。
日本代表・岡田監督契約延長、晴れてフランスW杯の指揮官に、W杯組み合わせ抽選で、日本はグループH、アルゼンチン、クロアチア、ジャマイカと同組に
11月27日、日本サッカー協会は、初のW杯出場権獲得を果たした日本代表・岡田監督との契約を1998年8月まで延長、正式にフランスW杯の指揮官を託すこととしました。
そして、12月4日、FIFA(国際サッカー連盟)による98フランスW杯組み合わせ抽選会がフランス・マルセイユで行われました。各大陸予選を勝ち抜いた30チームと開催国フランス、前回アメリカ大会優勝国・ブラジルを加えた32チームが4チームずつ8組に分かれてグループリーグを戦い上位2チームがベスト16に進出、そこからはノックアウト方式のトーナメント戦という試合方式です。
以前にもご紹介しましたが、アメリカ大会までの24チームから、今回32チームに増えたことで、各大陸とも前回と比べて最低でも1枠、欧州は3枠増えました。
ですから、いわゆる強豪と言われる国はほとんど出場してきましたが、欧州で言えばアメリカ大会で3位となったスウェーデン、南米で言えば優勝経験国のウルグアイが、アフリカではアンダー世代が強いガーナが出場できませんでした。
アジアからは日本が史上初の出場を果たしたほか、韓国、サウジアラビアに加え、第3代表決定戦で日本に敗れたイランが、豪州との大陸間プレーオフで勝利し、アジアから4チーム出場することになりました。
日本代表・岡田監督をはじめ、出場国の代表監督・サッカー協会幹部などが見守る中行われた注目の組み合わせで、日本はH組に振り分けられ、アルゼンチン、クロアチア、ジャマイカとグループリーグを戦うことになりました。
初戦であたるアルゼンチンは、4年前のアメリカ大会でマラドーナ選手が久々に大舞台に戻ってきて豪快なゴールもあげ「アルゼンチン快進撃か」と思われた矢先、マラドーナ選手がドーピング違反となり大会を追放され、結局、決勝トーナメント1回戦で姿を消しています。
マラドーナ選手の時代は終わりましたが、日本でもおなじみのFWバティストゥータ選手をはじめ、FWクレスポ選手、MFオルテガ選手そしてMFシメオネ選手ら、そうそうたるメンバーを揃えた強豪です。
クロアチアは旧ユーゴスラビアから分離独立を果たして初出場ではありますが、FWスーケル選手、MFボクシッチ選手、FWボバン選手、MFプロシネツキ選手、MFヤルニ選手など欧州の強豪クラブでレギュラーとなっている選手が数多くいる強豪です。
ジャマイカは未知の国ではあるもののイングランドリーグに所属している選手を5人揃えた侮れない国です。
対戦国が決まった翌日から、日本国内ではサッカーファンやマスコミの根拠のない楽観論が翌年6月の開幕まで続くことになります。そのあたりは翌年「伝説のあの年 1998年」の中で詳しくひもといていきたいと思います。
記録を残すという意味で、グループリーグ他の7組の組み合わせ結果を記録しておきます。
A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組
ブラジル イタリア フランス スペイン オランダ ドイツ イングランド
スコットランド チリ 南アフリカ ナイジェリア ベルギー アメリカ ルーマニア
モロッコ カメルーン デンマーク パラグアイ メキシコ ユーゴスラビア コロンビア
ノルウェー オーストリア サウジアラビア ブルガリア 韓国 イラン チュニジア
W杯抽選会記念試合に中田英寿選手が招待されフル出場
W杯抽選会を盛り上げる目的で、世界選抜チームvs欧州選抜チームの親善試合がマルセイユで行われ、W杯出場32ケ国から一人ずつ、日本からは中田英寿選手が招待されました。ちなみに韓国からは平塚で中田英寿選手のチームメイトになった洪明甫選手が招待され、日本の同一チームから2人の世界選抜選手を出したことになります。
世界選抜チームには、親善試合とはいいながらFWにバディストゥータ選手とブラジルのロナウド選手が並ぶという、ドリームチームです。中田英寿選手は彼らにパスを供給する中盤の選手としてスタメン出場を果たしました。20歳の中田選手は参加選手の中では最年少出場となり、その点でも注目されました。
この試合をマルセイユで取材、1998.1.1Number434号にレポートを寄稿したサッカージャーナリスト・金子達仁氏によると、試合が始まってすぐ、次のような不安を抱いたそうです。
「開始1分、右サイドのミッドフィルダーとして先発出場した中田は、センターフォワードのロナウドにボールを預け、自らも前方にあるスペースに猛烈な勢いで飛び込んでいった。素晴らしい走り込みだったし、もしリターンパスが出てくれば、決定的なチャンスが生まれたに違いない。しかし、ボールは出てこなかった。」
「中田は日本人である。残念ながら、長いサッカーの歴史において、日本人プレイヤーがヨーロッパや南米人に鮮烈な印象を与えたことはほとんどなかった。(中略)」
「そうした常識の中に飛び込んでいった中田がなかなかボールを回してもらえないのは、十分に予想できたことだった。」
「私は、世界のトップクラスと言われる人間の間にある日本人サッカープレイヤーに対する侮蔑と不信がいかに深いものであるか、かいま見たような気になってしまったのである。」
「ロナウドだけではなかった。バティストゥータもメキシコ人のベルナルも、パスを出す選択肢の中から中田を削除しているようだった。チーム最年少の選手として出場した東洋人にひたすらボールを供給したのは(中略)洪明甫だけだった。彼だけが、常に中田の姿を視界に入れ、ボールを持つとすぐに、ベルマーレのチームメイトに受け渡していた。」
このあと、金子氏はマルセイユまで試合を見に来たことを後悔しそうになったそうですが、わずか15分で、中田選手はロナウド選手やバティストゥータ選手の信頼を勝ち取るプレーを披露し始めたと書いています。
そのあとの金子氏の筆致は、次第に中盤の司令塔として君臨していく中田選手の様子を書き連ねる愉しさに溢れていました。
金子氏は、中田選手にひたすらボールを供給したのは洪明甫だけだった、と書いていましたので、もしそうだとしたら、中田選手が信頼を勝ち取るプレーができるようになったのは洪明甫選手のおかげであり、洪明甫選手がもっと称賛されるべきなのではないか思って試合映像をつぶさに見直してみました。
そこでわかったのは、中田選手が右サイドで、同じ右サイドの後方の位置にいた洪明甫選手にできるだけ近いライン際の位置にいてボールを呼び込むようにしていたという点です。ですから洪明甫選手がボールを持てば楽に受ける形になり、ボールに触れる回数が増やすことができたのでした。そこは中田選手らしいクレバーな試合への入り方だったと思います。
そして、後半に入るとキャプテンマークを巻いていたロナウド選手と、バティストゥータ選手が退いた際に起きたことを次のように書きました。「あろうことか、中田はキャプテンを任されることになった。」
金子氏の驚きの中に例えようもない嬉しさが込められていることが伝わってくる記述です。
中田選手がキャプテンマークを巻くことになった場面を映像で見ると、後半15分、2人が退いた時ロナウドがキャプテンマークを誰にも渡さずにベンチに戻ったため、レフェリーに促されて一番近い位置にいた中田選手が係員から受け取りに走り、そのまま試合も再開されそうになったので自分で巻いたという感じに映っています。
流れでそうなったとはいえ、試合を実況していたTBSの清水大輔アナが「キャプテンマークのご威光でボールが回ってくるようになったでしょうか」と言えば、解説の水沼貴史さんも「キャプテンマークを巻くと自然にそういう意識が生まれるんですかねぇ」とコメントしました。
金子氏のレポートは試合の最後のところを次のように締めくくっています。「試合が終わる頃、中田はずいぶんと前からヨーロッパでプレーしていたような雰囲気を漂わせていた。もはや、哀れさえ誘った試合開始直後の姿はどこにもなかった。」
金子氏がそこまで嬉しい気持ちになったのには理由があったからでした。それは2年前、イタリア・ジェノアのプレスオフィサーをしていた人物から「スーパーな日本人が出て来ない限り、今後10年間、日本人がヨーロッパでプレーする可能性はないだろうね。」と言われたことが、金子氏には「心の傷」といってもいいほどの侮蔑の言葉に聞こえていたのです。
しかし、この日の中田選手のプレーを見た世界選抜のパレイラ監督(94年W杯ブラジル優勝監督)が「(注・ナカタは)あと2~3年経てばヨーロッパでも一線級の選手として活躍するようにだろう。」と語っていたことを伝え聞いたのです。
「あと10年はムリだ」などとはもう言わせない、そう思うと無性に嬉しかったのでした。
こうして中田選手のFIFA親善マッチは終わったのですが、帰国して12月8日のテレビ朝日の「ニュースステーション」にゲスト出演した中田選手は、この試合についてこうやりとりしています。
ーーロナウドとバティの2トップはどうでしたか?
中田 特別すごいというわけではなかったし、ちょっと自己チューかなと。
本気でやってたわけはなかったと思うので、本気でやった場合、どうなのかな。
ーーああいう世界選抜のような試合に、どんどん出たいですか?
中田 本気でやってる試合じゃないんで、もう出なくていいって感じです。
これを聞いた金子氏は「相当に自信をつけたのだな」と感じたそうです。つまり、あの試合、人生で初めて世界的な選手をチームメイトにして戦い、信頼を勝ち取り、自分のレベルがコンプレックスを抱く必要のないレベルであることを知り、大いに自信を深めたに違いないというのです。
テレビでのあの言い回しは彼特有の「偽善者ぶり」の表れで、これからますます拍車がかかりそうだとも感じたそうです。
世界選抜チームに招待を受けるというのは、それまで日本選手では釜本邦茂選手、奥寺康彦選手、Jリーグスタート以降では1993年のカズ・三浦知良選手そして、この年7月に行われた香港返還記念試合に、アジア選抜の一員として選出された井原正巳選手、この4人しかいない、いわば日本のサッカー選手として成功した証しにもなる「名誉ある招待」と考えるのが一般的なのでしょうが、そんなことは中田英寿選手にとっては何の意味もないということのようです。
どうやら、これから先、登場することが激増するであろう中田英寿選手のことを記録するには、常に金子達仁氏のような「真意をつかめる人」の助けが必要になりそうです。
女子代表、3大会連続の世界女子サッカー選手権(1999年開催)出場権獲得
12月5日からアジア女子サッカー選手権が中国・広東省で開催されました。この大会は1999年開催予定のFIFA世界女子サッカー選手権の予選も兼ねており3位までに出場権が与えられます。
日本はグループリーグを3連勝で通過し準決勝に進出しましたが、準決勝では北朝鮮に0-1と敗北、3位決定戦に回りました。その結果、3位決定戦で台湾に2-0で勝利、3大会連続の世界女子サッカー選手権出場を決定しました。
女子代表は、この年6月、キリンカップサッカーで来日した中国女子代表と2試合対戦、国立競技場での第1戦で、過去一度も勝てなかった中国を初めて1-0で破るなど着々と力をつけています。
この年の女子代表は、これまで代表を牽引してきた、野田朱美選手、木岡二葉選手、半田悦子選手、長峯かおり選手、高倉麻子選手といった選手たちが代表を引退、19歳ながら代表キャリアが長い澤穂希選手を中心に東明有美選手、内山環選手、山木里恵選手、仁科賀恵選手、大竹奈美選手、酒井與惠選手、GK山郷のぞみ選手らが主力となっていました。
Jリーグチャンピオンシップ、まさに頂上決戦にふさわしい磐田、鹿島の激突は磐田が初の年間王者に
10月上旬に後期日程を終了して2ケ月ほど間隔のあいた97Jリーグチャンピオンシップは、12月6日、第1戦 磐田(ホーム)vs鹿島、12月13日、同第2戦 鹿島(ホーム)vs磐田の日程で行われました。
鹿島と磐田のカードはナビスコカップ決勝と同一カードとなりましたが、リーグ戦の2試合を含めて、ここまで鹿島の4連勝、特に直近のナビスコカップ決勝第2戦は、5-1と磐田を完膚なきまで押さえました。
それだけにチャンピオンシッブに賭ける磐田の気持ちは、第1戦の最初から現れました。
磐田は、ドゥンガ選手がブラジル代表のためチームを離れた関係で、奥大介選手をボランチに起用、本来、中盤を担う名波浩選手を、中山雅史選手の近くでプレーするシャドーストライカーに起用する布陣を敷きました。
開始わずか41秒、左サイドバックの山西選手からのロングフィードに反応した中山雅史選手が猛然とダッシュ、鹿島はDF奥野選手が付きますが中山選手はかまわずボールに食らいつくようにヘディングしましたが、鹿島GK佐藤洋平選手が処理しようとして出てきたところで接触、ボールはゴールインしたものの、中山選手はその場に倒れ込んでしまいました。
激しい闘志が、脳震とうを起こしながらの先制ゴールを生み、中山選手は後半2分にも豪快なジャンピングボレーで2点目をゲット、完全に磐田ペースでしたが、鹿島も反撃、まずジョルジーニョとビスマルクのホットラインから1点、後半43分にはマジーニョのヘディングで同点、試合はVゴール方式の延長戦に入りました。
延長は完全に鹿島ペースに変わり、延長後半13分、柳沢の決定的なチャンスで決まりかと思われたのですが外してしまいます。
これで試合はPK戦かと思われた延長後半終了間際、右サイドで清水範久選手、久藤清一選手、布部陽功選手のパス交換から、最後は清水選手が左足で、GKの手が届かないよう巻いて打ったシュートが見事左サイドネットに突き刺さり、劇的なVゴール。磐田が第1戦をモノにしたのでした。
続く第2戦は、第1戦にも増して激しい闘志と闘志のぶつかり合いとなりました。ファウル数は磐田が34回、イエローカードが磐田に4枚、鹿島はファウル数14回、イエローカード2枚飛び交う試合の中、前半41分には磐田DF・古賀琢磨選手が相手選手へのラフプレーのため退場処分となりました。それでも今年4連敗していた鹿島への苦手意識は第1戦の勝利で払拭できたことが大きかったと桑原監督代行は振り返りました。
後半31分には鹿島DF奥野遼右選手が相手の決定的チャンスでファウルしたとして退場処分となり10人対10人の戦いとなりました。
すると後半36分、思いがけない形で決勝点が生まれました。鹿島が自陣深くで本田泰人選手がGK佐藤洋平選手にバックパス、佐藤選手はボールを持ち直してからクリアしようと切り返したのですが、奥選手がダッシュしてきたためクリアを一瞬躊躇、そこに詰めていた中山雅史選手にボールをさらわれる形になってしまったのです。ボールを得た中山雅史選手は迷わず右足でシュートすると、ボールはフワリと無人のゴールに吸い込まれたのです。
鹿島の選手もベンチもサポーターも呆気にとられましたがゴールは認められました。残り時間、鹿島は必死の反撃を試みますが実らず、主審のレスリー・モットラムさんが笛を吹いてゲームセット。この瞬間、磐田の年間王者が決定しました。
試合後、圧倒的に攻めながら勝利をモノにできなかった鹿島サポーターの50人ほどがピッチに乱入、磐田選手を取り囲むなど、一時は騒然としました。統制のとれた鹿島サポーターの中で一部の心無い人間による不心得のため後味の悪い終わり方をした鹿島は、これを教訓にサポーターたちも成長していく契機となった試合でした。
今シーズンの磐田は決して順風満帆の1年ではありませんでした。ブラジル人のルイス・フェリペ監督を迎えてスタートしたものの、前期3節でスキラッチ選手が離脱、そのまま帰国したのを皮切りに、前期途中、1ケ月のリーグ戦中断期間にフェリペ監督がプラジル・パルメイラスからの監督オファーを理由に辞任、急遽、桑原隆監督代行のもとで立て直しを図りましたが、前期は6位で終了しました。
後期は、日本代表に名波浩選手を送り出す中での戦いを強いられましたが、桑原隆監督代行、山本昌邦ヘッドコーチがチームをよくまとめ、ブラジル代表キャプテン・ドゥンガ選手が入団以来発揮し続けていたキャプテンシーが浸透してきました。
ドゥンガ選手がケガのため欠場した夏場の4試合の中でチームは2連敗したものの、それ以外すべてを勝利、15勝2敗の圧倒的強さで後期を制覇、Jリーグ参戦4年目にして初タイトルをつかんだのです。
磐田を年間王者に導いたドゥンガ選手が日本でプレーしようと決めた理由とその成果
磐田の強さは、何といってもドゥンガ選手が注入した闘争心の強さでした。チャンピオンシップにおいても前評判は戦力、テクニック、経験などすべての面で鹿島優位でしたが、大黒柱の中山雅史選手をはじめ、藤田俊哉選手、服部年宏選手、古賀琢磨選手らの年長選手が、局面局面でイエローカードを恐れない激しいプレーをする集団になっていました。
ドゥンガ選手は1995年7月に磐田に加入しています。試合は8月12日スタートの後期からの出場で、すでに2年半在籍しています。
磐田にとってはもちろんのことですが、日本サッカーにとってもドゥンガ選手がJリーグでプレーしてくれたことは「巡り合い」とも言うべき幸福です。
ドゥンガ選手が翌年出版の形で日本のサッカーファンに遺してくれた著書「セレソン」に、日本に関心を持ったいきさつや日本での生活について書かれていますので、そこから紹介してみます。
「初めて日本に来たのは1984年のキリンカップ、ブラジルのインテルナシオナルでプレーしていた時代のこと」と言いますから、まだ21歳の頃で、皇居を訪れたり茶器や花瓶など日本の伝統的な品物をお土産に買ったそうです。
ドゥンガ選手は茶道の所作にみられる無駄のない動き、乱れた動きが一切ないところなどに強く惹かれていたり、磐田に近い愛知県・瀬戸市の陶芸家に学んでいたり、日本文化に対する関心が非常に高い人なのです。
さらには茶道や陶芸の際に交わした日本の「お年寄り」の人たちとの会話はドゥンガ選手にとって刺激的だったそうです。その人たちが持つ心の落ち着き、深い造詣が自分にも伝わってくるように感じ、その日本の「お年寄り」の持つ力が、人間の内部から人生の本質がにじみ出てくるような力だと感じていたそうですが、次第に、それは今日でもふつふつと湧き上がっているようなものではなく、過去の遺産によるものだったことを知ります。
「日本に来ることになるずっと前から、私は日本の映画を見ていたし、本を読んでいた。(中略)昔、世界は日本の愛国心や侍の精神を競ってコピーしたものだ。そしてそこには生活のスタイルわ守り、小さなことも大切にする人々が住んでいると思っていた。」
ところがドゥンガ選手、今も日本にはそういう伝統的な生活習慣が息づいているものだとばかり思って来日して生活してみたら、そういったイメージが次々と打ち砕かれ、そのたびにショックを受けてしまったそうです。
そして本で知った侍の知性の高さや集中力に憧れていた自分が、その日本で毎日のように選手たちに向かって「集中しろ」と叫んでいる始末だと嘆いています。
ただドゥンガ選手は、東京や横浜のような大都会ではなく、こじんまりした磐田で生活するようになったことが自分にとっては幸運だったようです。実は磐田と契約する前に横浜フリューゲルスの加茂監督が獲得を希望していたことからオファーを受けていたのですが、所属していたブンデスリーガ・シュツットガルトとの契約問題や加茂監督が日本代表監督に就任することになって、その話が流れたといういきさつがありました。もし、横浜フリューゲルスに加入して、横浜に住むことになっていたら、と「たられば」の話をしたくなるエピソードです。
ドゥンガ選手が持つメンタリティ、ドゥンガ選手が抱く日本文化に対する敬意、そういったことがベースにあってドゥンガ選手は「この愛すべき日本」のプロサッカークラブで、自分がブラジル、イタリア、ドイツといった世界のトップリーグで学んだことを、若い選手たちに、あるいは組織そのものに伝えていくという役割を果たすという貢献ができるのではないかと考えたのです。
これまでドゥンガ選手は、自分のプレーでチームに貢献することだけを考えて欧州に移籍して活躍してきたわけですが、日本のクラブへの移籍はドゥンガ選手にとっても、これまでとは全く異なる新たなチャレンジであり、その使命を全うすることで日本サッカーの発展に貢献したいという確固たる目標を持った移籍だったのです。
日本は「サッカー後進国」から「サッカー発展途上国」へ、そして「サッカー新興国」への道をひたすら歩み続けていかなければ「サッカー先進国」には辿り着かないわけですが、その過程で、こうした選手とプレーを共にすることが、いかに貴重なことか、あらためて思います。
そうした強い決意と使命感を持ったドゥンガ選手の指導が磐田で始まります。ドゥンガ選手のピッチ内での指導の様子は「まるで学校の先生と生徒」とか「試合中にドゥンガ先生に身体を揺さぶられながら教えを受けている若手選手」といった興味本位の枕詞がつきながらテレビ、スポーツ紙などのメディアで伝えられました。
それでもドゥンガ選手は、やみくもに自分の考えを選手たちに押し付けたのではなく、いまの日本人が持つメンタリティや自分たちとの心理的な違いをよく理解して、その中で「サッカーという勝ち負けが冷酷に決まってしまう試合をどう進めなければならないか」を説いていたのです。
最初は「とにかくよく怒る選手」と煙たがっていた磐田の選手たちも、ドゥンガ選手の教えが理にかなったものであり、それを徹底することが大事なのだという考えから来ていることを次第に理解していったに違いありません。そうでなければ、とてもおいそれとは年間王者を勝ち取れるチームにはならなかったと思います。
ドゥンガ選手の著書「セレソン」には、次のような一節があります。
「サッカーは会社と違い、何かあったら上司の判断に従えばいいというわけにはいかない。選手自身が判断を下し、行動しなければならない。監督がいちいちシュートしろ、パスをしろと指示を与えることはできない。日本人の選手にこの、自分で判断するという習慣が身につくまでにはまだ時間がかるだろう。
この習慣を獲得することは、日本という国にとっても大きな意味があることではないかと思う。それは判断力を養い、新しいメンタリティを創造することにつながっていくからだ。人々はまだ優柔不断で、ミスをすることを恐れているように、私には見える。」
ドゥンガ選手の著書はこのあと、日本社会の状況をブラジル社会との比較の中で述べていますが、上記の一節は1996年に約2年の名古屋での監督生活を終えてイングランド・アーセナルの監督に転じたベンゲル監督と同じ指摘です。
日本人の持つメンタリティ、日本社会にある行動様式を鋭く指摘しているという点で実に正鵠(せいこく)を射ています。
当サイトは、サッカーというスポーツが、世界にいかに多くの素晴らしい人材を有していて、その一部の人たちではあるものの、日本で指導やプレーをしてくれて、そこから日本人自身が気づかないでいる多くのことを教えられる素晴らしさ、幸福感というものも伝えたいと思っています。
特にJリーグスタート以降、ジーコ、ベンゲル、ドゥンガといった人たちは、日本が持つ文化の素晴らしさ、日本人が持つ公共心、誠実さ、慎み深さといった魅力に惹かれて、プレー以上の何か、勝つための指導以上の何かを日本に伝えていきたいという気持ちで日本での生活を選んでくれた人たちです。
こうした人たちを引き寄せることができる魅力を日本が持っている、そのことにも誇りを持ちたいですし、こうした人たちから指導を受けることによって、日本のサッカーが大きく成長できることも誇りたいと思います。
加えて「サッカー」という限られた分野の人たちの発言や書物ではありますが、日本の社会が少しでもインスパイアされて、いい方向に向いていく一助になればという気持ちを持って紹介しています。
ドゥンガ選手が日本で、磐田でやろうとしていたことは、まだまだ、とても満足できるようなものではなかったと思いますが、チームは徐々に確かな成長を遂げていきました。
その結果、このチャンピオンシップも、ドゥンガ選手をブラジル代表の試合で欠く中、キャプテンマークを巻いた中山選手の鬼気迫る活躍と途中出場した選手を含めて全員の「負けない気持ちの強さ」で、とうとう年間王者の称号を手にしたのでした。
この年、チャンピオンシップとナビスコカップ決勝を争った鹿島と磐田、この年が、その後続く2強時代の始まりでした。Jリーグに降りかかるさまざまな難問の中で、Jリーグがその価値を貶めることなく、質の高い国内リーグを擁する国として世界からの評価を高め、日本サッカーが成長・発展・進化している具体的な姿を、2002年W杯に向けて見せることができたのは、鹿島と磐田が毎年、覇を競い続けた功績によるものといっていいでしょう。
この年が、その始まりの年だったのです。
Jリーグアウォーズ、MVPにドゥンガ選手、得点王エムボマ選手、新人王に柳沢敦選手
ジュビロ磐田の年間王者で幕を閉じた1997年Jリーグ、12月15日Jリーグアウォーズが、今年も横浜アリーナで開催されました。年々ショーアップされ、すっかりオフシーズンの行事に定着したこの年は4000人もの一般ファンが招待された中での授賞式となりました。
選手間投票で決める今シーズンの年間最優秀選手(MVP)には磐田年間優勝の中心となったドゥンガ選手、得点王には、浪速の黒豹として、すっかり今シーズンのJリーグの人気をさらったエムボマ選手が25ゴールで輝きました。また新人王には鹿島の柳沢敦選手が選ばれました。
年間最優秀選手(MVP)のドゥンガ選手は、サウジアラビアで開催されているコンフェデレーションズカップにブラジル代表として参加しているため表彰式を欠席しましたが、1995年夏に磐田に加入して以来、チームメイトを叱咤激励、鼓舞し続け、この日表彰台でドゥンガに代わって受賞した中山雅史選手が「来年はあまり怒られないように頑張ります。」と受賞の弁を語ると会場はどっと沸きました。
この年のベストイレブンは、日本代表の中心となって活躍した選手が目立ちました。
年間王者の磐田から中山雅史選手(初)、ドゥンガ選手(初)、名波浩選手(2回目)、GK大神友明選手(初)の4人、鹿島からは、ビスマルク選手(2回目)、秋田豊選手(初)、相馬直樹選手(3回目)の3人、G大阪・エムボマ選手(初)、平塚・中田英寿選手(初)、横浜F・山口素弘選手(2回目)、横浜M・井原正巳選手(5回目)というメンバーでした。
また、この年の表彰で特徴的だったのは「報道という立場からサッカーの発展に貢献した」という理由で、サッカージャーナリストの賀川浩氏、牛木素吉郎氏、中条(ちゅうじょう)一雄氏の個人3氏と、週刊サッカーマガジンが団体として功労賞を贈られたことでした。個人のお三方は、いわば日本のサッカー記者の草分けといえる存在です。
賀川浩氏は、この時72歳、まだ現役バリバリのサッカージャーナリストとしてサッカー専門誌等に健筆を振るっておられました。もともと産経新聞のスポーツ記者として活躍された方で、このあとも長くサッカージャーナリストとして活動を続け、遂にはご存じのとおり、FIFA(国際サッカー連盟)から10大会にも及ぶワールドカップ取材歴を評価され日本人として初の「会長賞」を贈られた方として著名な方です。
また、これも後年、自身のサッカー関連の書籍・資料を神戸市立図書館に寄贈され「神戸賀川サッカー文庫」として公開されていることでも知られています。
牛木素吉郎氏は、この時65歳、読売新聞のスポーツ記者として活躍された方で、その後は大学で教鞭をとる傍ら『サッカーマガジン』誌で1966年の創刊以来連載コラムを執筆されています。特に毎年年末には、その年のサッカー界に功労があった団体・個人等を顕彰する「日本サッカー大賞」を自ら選定して発表、独自の視点でサッカーを愛されている方です。
この「日本サッカー大賞」で印象深いのは1995年の年間大賞として、Jリーグ年間王者に輝いた横浜Mや、福岡ユニバシアードで日本サッカー初の金メダルを獲得したユニバシアード代表などを押しのけて、NHK-BSの「サッカーダイジェスト」を選定、その功績を讃えたことです。
こうした着眼点は「サッカーの世界」がチームや選手たちだけで成り立っているのではなく、メディア、サポーター、ジャーナリストなどを含めた「サッカー文化の広い世界」として成り立っていることを示してくれており、そうした功績も大きな方です。
後年は「牛木素吉郎&ビバ!サッカー研究会」を主宰され、日本サッカー協会をはじめ多方面のメンバーたちとともにサッカー研究活動を続けておられます。
中条一雄氏は、この年71歳、朝日新聞のスポーツ記者として活躍された方で、日本サッカーの恩師と慕われているドイツのデッドマール・クラマー氏に日本の報道関係者として初めて接したことでも知られています。
中条氏の直近の最大のエピソードは、この年の「ワールドカップアジア予選」の日本代表について、連載していた「週刊朝日」のサッカーコラムで、「このままでは日本代表の本戦進出は不可能。もし日本代表が予選を突破したら、そのときは『サッカー評論家』の肩書きを返上して、『サッカー愛好家』を名乗る」と宣言したことでした。
中条氏はその時から「週刊朝日」誌上では「サッカー愛好家」と名乗られています。
96-97アジアカップウィナーズカップ、名古屋惜しくも優勝逃す
第7回目となった96-97アジアカップウィナーズカップ、日本からは、前回第6回大会覇者(1995年12月決勝)の平塚と、1996年元旦、第75回天皇杯覇者の名古屋が参戦しました。
平塚は準々決勝で敗退しましたが、名古屋はサウジアラビアのリヤドで集中開催された準決勝で韓国の蔚山現代を5-0の大差で下し決勝に進出、そのままリヤドで行われたサウジアラビアのアル・ヒラルとの決勝では完全アウェーの環境もあり1-3で敗退、惜しくも優勝を逃しました。
2002年日韓W杯に向け、ハード・ソフト両面で着々と準備進む
前年12月、クリスマスの日に、国内開催地10自治体が事実上決定し、年明け1月下旬には、落選した5自治体へのお詫び訪問を長沼会長自ら行なった2002年日韓W杯への対応。
この年は、日本代表のフランスW杯出場権を賭けた戦いに日本中が一喜一憂する中で「2002年日韓W杯開催準備委員会」のスタッフたちは、共催相手である韓国との調整作業、開催地となった自治体との準備作業に忙殺される日々でした。
それは、まるで陽の当たらない損な役回りの仕事の割には、何一つ見落しが許されない、神経をすり減らす緻密な作業でした。
韓国との調整作業は、前年11月、FIFAでのワーキンググループ初会合と同時に始まりましたが、最初はひどいものだったそうです。
スポーツライター・川端康生氏の著書「日韓ワールドカップの覚書」(講談社2004年刊)に登場する日本側スタッフの一人、広告代理店の電通から招致委員会に出向していた濱口博行氏が、いくつかのエピソードを紹介しています。
まず、FIFAでのワーキンググループ初会合の時から険悪なスタートになったといいます。ワーキンググループの場で韓国の鄭夢準氏が「大会名称は『コリア/ジャパン』でなければ、私は国に帰れない」とゴネ得したあの会合の裏方として、マスコミ対応の準備にあたっていた濱口氏は、その準備業務でも韓国側の態度に呆れてしまいます。
ワーキンググループで決まった内容は重要事項なので、事前の情報漏れに注意して両国同時発表しようと打ち合わせていたのですが、なぜか日本のメディアに漏れて流れてしまったそうです。韓国側スタッフは「これは絶対日本側が漏らしたに違いない、出所は岡野氏に違いない」と、何の根拠もないのに一方的に激怒してしまい、スタッフ同士の取っ組み合いになるほどでした。後になって漏らしたのは韓国高官だということがわかったのですが、とにかく対日交渉になると理性もへったくれもない態度で、これから先、大変だなぁとつくづく思ったそうです。
その会合から1ケ月後、今度は韓国で、今後の共同作業をスムーズに進めていくための打ち合わせをしようと集まった席でも、議論はなかなかかみ合わず、激昂した韓国の担当者が、いわゆる歴史問題を口にして日本側を批難する有様で、日帰りの出張にもかかわらず精神的な疲れでくたくたになり、先が思いやられてしまったそうです。
ただ、年が明けての会合から、空気が変わり始めたといいます。韓国側に「組織委員会」ができて事務総長に崔昌新氏が就任してから、韓国側のスタッフの態度もガラリと変わり始めたのだそうです。
崔事務総長自身が、過去のことを引きずらずに未来志向で日本と向き合う姿勢を率先して示したことから、組織委員会全体にも、その姿勢が浸透したというのです。
濱口氏は、その後も毎月のように韓国側担当者との会合を重ねるうちに、個人的な信頼関係が生まれ、お互いが史上初の共催という大事業に携われる誇りを感じながら励まし合っていこうと話したといいます。
11月1日の韓国・蚕室スタジアム、日本が初のワールドカップ出場に向けてライバルであるはずの韓国を破った日、掲げられた「Let’s go to France together(一緒にフランスへ行こう)」の横断幕は、決して儀礼的なポーズなどではなく、年明け以降、韓国で次第に醸成させていった「共同開催を成功させるために未来志向で臨もう」という機運の表れだと言っていいでしょう。
準備作業は国内各開催地でも始まりました。1月下旬には「国内開催地知事・市長会議」が開催されたのを皮切りに、2月、5月には国内開催地の実務担当者を中心とした「国内開催地連絡会議」が行われ、日本準備委員会からの情報をもとに必要な作業に取り組みました。その後、大阪、横浜、埼玉、新潟などでは地域への啓発活動や記念行事などが行われ、次第に地域の機運を高めていきました。
また、FIFAの会合(名称を「ワーキンググループ」から「プランニンググループミーティング」に改称)では、5月に、財政問題(特に大会で得られた入場料収入の、日韓両国とFIFAの取り分の問題)では、過去のW杯でFIFAが一定額ふところに入れていたものを、今回はFIFAがピンはねしてしまうと2ケ国の取り分が減り収支上相当厳しくなることを考慮して、両国がまるまる収入に計上できることが決まり、両国とも安堵することになりました。
一方、ハード面では横浜に1994年から建設が進んでいたスタジアムが10月に完成しました。3月に名称を「横浜国際総合競技場」とすることを決定していたスタジアムは、日本国内最大の72,327席(二層式)の観客収容能力を誇る施設です。
11月23-24日 FIFAアベランジェ会長、ヨハンソン副会長ら首脳陣が来日、2002年日韓W杯の準備状況の視察が目的で、24日には2002年W杯メイン会場に予定されている「横浜国際総合競技場・通称横浜スタジアム」を横浜市長らの案内で視察しました。一行は来日に先立ち韓国に立ち寄り準備状況を視察しました。
1週間前に日本がフランスW杯出場を決めた直後だけに、一行を迎える日本サッカー協会の関係者が、喜び一杯の表情で胸を張って迎えたであろう様子が目に浮かぶようです。W杯に出場経験を持つ国として2002年W杯を開催できることの重みを、つくづく感じながら迎えたでしょうし、日本サッカー協会の関係者は、それを成し遂げた日本代表選手たちに今更ながら感謝の気持ちを強く抱いたに違いありません。
12月19日 前の週12日に文部省より「財団法人2002年FIFAワールドカップサッカー日本組織委員会」の設立許可証が交付されたことを受け、この日、2002年ワールドカップ開催準備委員会を発展的に解散、財団法人2002年FIFAワールドカップサッカー日本組織委員会が設立されました。同時に略称をJAWOC(ジャウォック)とすることも決定しました。
JAWOC(ジャウォック)は、会長に那須翔・東京電力㈱会長、副会長に、長沼健・日本サッカー協会会長、岡野俊一郎・日本サッカー協会副会長、川淵三郎・日本サッカー協会副会長、平松守彦・大分県知事ほか学識経験者3名、
事務局体制として、事務局長以下、専従職員30名(総務部10名、ベニュー(開催地)部8名、国際部8名、広報部4名)
という陣容でスタートしましたが、事務局体制は年を追うごとに拡充され2002年には本部だけで140数名、開催地毎に置かれた支部を合わせると約400名もの規模となっていきます。
こうして、日本国内が1998年フランスW杯出場決定に沸く中でしたが、その次に来る2002年日韓W杯の準備も着々を進められていきました。
ブラジルが「コパアメリカ97」と「97コンフェデレーションズカップ」の2冠、
それに貢献したロナウド選手、FIFA世界最優秀選手に2年連続選出、
トヨタカップ97はドルトムントが制覇
1997年の海外サッカー情勢や国際大会を俯瞰しておきたいと思います。
まず、コパ・アメリカ97が、6月11日-6月29日の日程でボリビアで開催されました。南米10ケ国に加えメキシコ、コスタリカが招待され12ケ国で争われました。
3グループに分かれたグループリーグの結果、上位2チームと3位チームからの2つを加えて8ケ国が準々決勝に進出、次のカードとなりました。
ボリビアvsコロンビア、メキシコvsエクアドル、ペルーvsアルゼンチン、ブラジルvsパラグアイ
準々決勝ではアルゼンチンがペルーに屈するという番狂わせといっていい出来事が起こりました。その結果、準決勝はボリビアvsメキシコ、ブラジルvsペルーのカードとなりました。
準決勝では開催国ボリビアが3-1でメキシコを撃破、高度3600mの高地の優位を存分に生かした決勝進出でした。もう1試合、アルゼンチンを下したペルーがブラジル相手にどこまで通用するか注目でしたが、結果は7-0、ブラジルの圧勝でした。ブラジルのゴールはロマーリオと鹿島からパリ・サンジェルマンに移籍したレオナルドがそれぞれ2ゴールの活躍でした。
そして決勝、ブラジルと開催国ボリビアの対戦、高度3600mの高地での試合ということで注目されましたが、ブラジルがロナウド、エジムンドなどのゴールで3-1でボリビアを下し、コパ・アメリカ5度目の優勝を果たしました。
なお3位はメキシコでした。
12月12日から12月21日にかけて、FIFAコンフェデレーションズカップ97がサウジアラビアで開催されました。
この大会は、各大陸間王者国が、最強を競う大会として、過去2回(92年4ケ国、95年6ケ国)、キング・ファハド・カップという冠大会として(いずれもサウジアラビアで)開催されていましたが、この大会からFIFAが主催となり隔年で開催されることになりました。
この年は、開催国であり1996年アジアカップ優勝国のサウジアラビアをはじめ、次の8ケ国が参加しました。
・UAE (1996年アジアカップ準優勝)、・南アフリカ(1996アフリカネイションズカップ優勝 )、・メキシコ(1996 CONCACAFゴールドカップ 優勝)、・ウルグアイ(コパ・アメリカ1995 優勝)、・オーストラリア(1996 OFCネイションズカップ優勝)、チェコ(UEFA EURO’96 準優勝・優勝国ドイツ辞退のため代替出場)、・ブラジル(1994 FIFAワールドカップ優勝)
大会は4ケ国づつ分かれてのグループリーグの結果、ブラジル、オーストラリア、ウルグアイ、チェコが準決勝に進出、ブラジルvsチェコ、オーストラリアvsウルグアイのカードで準決勝が行われました。ブラジルはロマーリオ、ロナウドのRR(ロロ)コンビのゴールで決勝へ、もう1試合はオーストラリアが延長の末、ハリー・キューエルのゴールでウルグアイを下し決勝進出を果たしました。
決勝はまたもやRR(ロロ)コンビのゴールショー、2人ともハットトリックという離れ業でオーストラリアを寄せ付けず6-0で初優勝を果たしました。
ブラジルは、過去2回アルゼンチンがこの大会の主役となっていましたから、サッカー王国の威信を取り戻した大会となりました。3位はウルグアイでした。
96年秋から97年5月までの間争われた96-97欧州チャンピオンズリーグは、5月28日行われた決勝で、前年の欧州選手権を制したドイツ代表が多く所属しているボルシア・ドルトムントが、前評判の高かったユベントスを3-1で破り初優勝を果たしました。
トレンチコート姿がトレードマークのヒッツフェルト監督率いるドルトムントは、ユベントス所属経験があるアンドレアス・メラー、パウロ・ソウザ、ユルゲン・コーラーなどの選手をピッチに送り出し、相手の良さを消すことに成功したとして、名将としての評価を高めた試合でした。
ドルトムントのリベロとしてチームを牽引したマティアス・ザマーは、前年の96欧州選手権ドイツ優勝の立役者でもあったことから、この年のバロンドール(欧州最優秀選手賞)にも輝きました。
この年のブンデスリーガ勢は96-97UEFAカップでもシャルケ04が優勝するなど、前年夏からこの年夏にかけてドイツ勢強しを強く印象づけました。
一方、南米王者を決定するコパ・リベルタドーレス97は、8月に決勝が行われ、第1戦を0-0の引き分けで凌いだブラジル・クルゼイロが13万人のホームスタジアムの後押しを受けた第2戦、名古屋でプレーしていたエリベウトンの決勝ゴールで、ペルーのスポルティング・クリスタルを破り、実に13年ぶりに優勝、12月のトヨタカップへの出場権を手にしました。
12月2日に東京の国立競技場で行われた、第18回トヨタカップ(ヨーロッパ/サウスアメリカ カップ)は、欧州王者ボルシア・ドルトムントと南米王者ブラジルのクルゼイロの戦いです。
クルゼイロは、ヴ川崎の監督を辞任したネルシーニョ監督が率いて、いわば凱旋来日、この試合に合わせベベットらを緊急補強して試合に挑みました。一方のドルトムントは、ヒッツフェルト監督が欧州チャンピオンズリーグ制覇を手土産にバイエルン・ミュンヘンに迎えられたため、スカラ監督に代わり、ユルゲン・コーラー、マティアス・ザマーが怪我で日本遠征に参加できませんでした。
試合は、ドニゼッチ、ベベト、リベルタドーレス杯決勝で決勝ゴールを叩き込んだエリベウトンの3人を前線に揃え、GKにアトランタ五輪にも出場したジダが立ちはだかるクルゼイロに対して、守りの要2人を欠いたドルトムントがかなり不利と思われましたが、ドルトムントが2-0でクルゼイロを下し初優勝を果たしました。
圧倒的な存在感、ブラジル・ロナウド選手の呼び名は「怪物ロナウド」
12月、FIFAが世界最優秀選手の受賞者を発表、ブラジル代表でバルセロナで活躍、今シーズンからセリエA・インテルに移籍したロナウド選手が2年連続で受賞しました。
このFIFA世界最優秀選手の選出は、各国代表チーム監督の投票で行われるもので、過去の受賞者はW杯で活躍した選手など世界のトップと認められた選手が受賞しているのですが、1996年の選考では、まだ大舞台での活躍とは縁遠いロナウド選手が、加入して間もないバルセロナでの衝撃的なゴールラッシュにより異例とも言える初受賞に輝いたのでした。
そして、この年に入ってもコパアメリカ97、FIFAコンフェデレーションズカップ97でブラジル2冠の原動力となる活躍を見せ、96-97シーズンのバルセロナでリーグ戦37試合出場34得点を記録してリーガ得点王に輝き、実力が本物であることを見せつけ2度目の受賞となったのです。
特に、バルセロナでの1996年10月スペインリーグ第7節、コンポステーラ戦の1ゴール目は、前年の初受賞を決定づけたとも言える圧巻のゴールでした。
前半36分、センターライン付近の自陣でボールを持つと、相手DFが絡んできました。
まずロナウドの足元にファウルまがいのチャージを浴びせてきましたが、倒れることなく突進しようとします。倒れないと見るや、今度はユニフォームを引っ張って止めようとかかります。ユニフォームが伸び切っているにも関わらず構わず突進しましたから、たまらず相手DFの手からユニフォームが離れてしまいました。そこからは疾走のドリブルです。はじめにボールを持ったところから約40メートルほど進みます。途中、別のディフェンダーが捕まえようと近づきますが、とても追いつけません。ゴール前まで来ると次のDFが立ちはだかりましたので、2人をフェイントで交わし右方向真横に移動します。ボールが少し流れましたので、体勢を崩しながら右足でシュート、ボールはGKの届かないゴール左隅に突き刺さりました。
決められた相手DF数人は呆然と立ち尽くし、バルセロナのボビー・ロブソン監督は、一旦両手をあげて歓喜のポーズをとろうとしたものの、むしろ「なんてこった、この男は」と言わんばかりに頭を抱えるほどのゴールでした。
このゴールシーンはナイキ社のCMにも使用され「怪物ロナウド」の名を飛躍的に高めるきっかけとなりました。
ロナウド選手は1976年9月生まれ、この年21歳、日本選手では中田英寿選手と同学年(日本の学年設定で)にあたります。おそらくマラドーナ以来のスーパースターといっていい選手の登場でした。果たして母国のスーパースター・ペレの後継者の道を順調に歩むでしょうか。
ご存じのようにロナウド選手はインテル移籍を希望していましたので、この年夏のインテル加入は望みが叶った形にはなったのですが、バルセロナとのあいだではギクシャクしてしまいました。また、その後、度重なるケガとの戦いを強いられ、インテル時代は彼の選手生活の中では楽しい思い出の少ない時代になりました。
その後、98W杯フランス大会、2002年日韓大会そしてレアル・マドリーと活躍を続けましたので、その時期になりましたら、また詳しく書き留めたいと思います。
ロナウド選手の活躍で、UEFAカップウィナーズカップとスペイン国王杯のタイトルをとりながら「攻撃の戦術を持たない監督」として批判されていたFCバルセロナのボビー・ロブソン監督は「私の戦術はロナウドだ」と語ったことも、ロナウド選手のカリスマ性を一層高める語録となりました。
ロブソン監督は2冠に輝いたにも関わらず、バルセロナ監督を解任されてしまいました。「私の戦術はロナウドだ」と言っていたロナウドが去ってしまったのでは、致し方なかったのかも知れません。
そのボビー・ロブソン監督のアシスタントコーチをしていたのが、のちに欧州4大リーグのビッグクラブの監督として次々と欧州制覇を成し遂げるジョゼ・モウリーニョです。
さきほどのコンポステーラ戦を放送したHNK-BSの試合映像には、アシスタントコーチ時代のモウリーニョがロブソン監督に対して何やら進言している姿が映っています。こうした映像記録も貴重なものとして後世に伝えたいと思います。
1997年、この年の各カテゴリー国内大会
お正月の第75回全国高校サッカーについてはすでにご紹介しましたので、その他の大会をご紹介しておきます。
・第18回全日本女子サッカー選手権大会(1997年1月4日から1月19日)
日本女子サッカーリーグ(L・リーグ)参加10チームと、地域予選を勝ち抜いた10チーム、合計20チームが参加してトーナメント方式で行われました。
その結果、準決勝は、第14回大会以来のベスト4入りをした鈴与清水FCラブリーレディースを2大会ぶりのベスト4入りを果たした日興證券ドリームレディースが破り、また前年の準決勝と同じ組み合わせとなったプリマハムFCくノ一と読売西友ベレーザの対戦では3-2で、読売西友ベレーザが決勝に進出しました。
1997年1月19日の決勝戦の会場は、第10回大会以来となる国立競技場で、日興證券ドリームレディースvs読売西友ベレーザのカードとなりましたが、3-0で日興證券が快勝、4大会ぶりの優勝を果たしました。
・第9回L・リーグ(日本女子サッカーリーグ) (1997年6月から11月まで)
この年も2ステージ制(前期・後期)で実施され、前期にはナイトゲームも多く行われました。このころには専用グラウンドやクラブハウスをもつチームが多くなり、また世界各地から選手が集まりプロ契約選手も多く誕生するなどで「世界最高の女子サッカーリーグ」と呼ばれていましたが、前年に激減した観客動員の回復にはつながりませんでした。
特に前年のシーズン後に野田朱美選手(宝塚バニーズ)や、木岡二葉選手、半田悦子選手(ともに鈴与清水FCラブリーレディース)など、長年、女子サッカーを牽引してきた選手たちが引退し、次世代の育成が待たれたことも背景にありました。
前期は読売西友ベレーザがプリマハムくの一と同じ8勝1敗ながら90分以内での勝利の差で3大会ぶりに1位となりました。後期はやはり読売西友ベレーザが日興證券女子サッカー部ドリームレディースと同じ8勝1敗、90分以内での勝利数や得失点差、総得点数でも並んだのですが、当該チーム同士の対戦で日興證券が勝利したため、日興證券女子サッカー部ドリームレディースが1位となりました。
そして、年間優勝決定戦である「チャンピオンシップ97」が11月23日に行われ、次の結果となりました。
読売西友ベレーザvs日興證券女子サッカー部ドリームレディース(2-1)
年間優勝・日興證券女子サッカー部ドリームレディース(2年連続)
個人タイトルは次のとおりでした。
・最優秀選手:山木里恵選手(日興證券ドリームレディース)
・得点女王:アンネリ・アンデレン選手(鈴与清水FC) 19点
【ベストイレブン】
GK:小野寺志保選手(読売西友ベレーザ)
DF:山木里恵選手(日興證券ドリーム)、東明有美選手(プリマハムFCくノ一)、酒井與恵選手(読売西友ベレーザ)、大部由美選手(日興證券ドリーム)、
MF:ヘーゲ・リサ選手(日興證券ドリーム)、高倉麻子選手(読売西友ベレーザ)、澤穂希選手(読売西友ベレーザ)
FW:大竹奈美選手(読売西友ベレーザ)、大松真由美選手(日興證券ドリーム)、アンネリ・アンデレン選手(鈴与清水FC)
・第2回全日本フットサル選手権(1997/2/9(日)~1997/2/11(月・祝))
前年に「全日本ミニサッカー大会」から「全日本フットサル選手権」に衣替えして第1回大会が開催されたこの大会、今大会の決勝は、関東地域代表・府中水元クラブ(東京都)と、九州地域代表・三菱化学黒崎フットボールクラブ(福岡県)の争いとなり4-1で府中水元クラブが圧勝、優勝を果たしました。
・デンソーカップ大学選抜サッカー 日本大学選抜vs韓国大学選抜(1-0)
毎年春、大学の地域選抜チームによるトーナメント戦と、最後に東西対抗戦が行われてきた「デンソーカップ大学選抜サッカー」この年は2002年日韓W杯決定を記念して、韓国大学選抜を招待する形で、4月13日、東京・西が丘サッカー場で初めて開催されました。
試合は、日本大学選抜が盛田剛平選手のゴールを守り切り1-0で勝利しました。この時の韓国大学選抜には、のちに韓国のスター選手に成長する安貞桓(アン・ジョンファン)選手が背番号10をつけて髪をスポーツ刈り風に短くして出場していました。
・第21回総理大臣杯大学サッカートーナメント決勝 法政大vs駒沢大(0-3) 優勝 駒沢大
・第46回全日本大学サッカー選手権 決勝 駒沢大vs国士館大(3-1) 優勝 駒沢大
11月15日から11月23日の日程で、9地域の代表15校と総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント優勝校・駒沢大が参加して行われました。
準決勝には関東大学リーグの3校、駒沢大、国士館大、筑波大と、東海代表・中京大が進出、国士館vs筑波大の関東勢対決は、国士館が2-1で競り勝ち、駒沢大vs中京大は、駒沢のエース・盛田剛平選手とMF三上和良選手が共に2ゴールをあげるなど6-0で大勝、決勝進出を果たしました。
駒沢大vs国士館大の決勝は、国士館が昨年に続く連覇を達成するか、駒沢大が、夏の総理大臣杯との2冠なるか注目されましたが、試合は前半3分、4分と立て続けに駒沢大がゴールをあげて主導権を握り国士館の反撃を1点に抑え、3-1で今年の2冠を達成しました。
駒沢大は、一昨年2冠のあと昨年無冠に終わりましたが、今年また2冠を獲得したことになります。
この年の各大学主な選手とその進路
・駒沢大 MF三上和良⇒神戸、米山篤(3年)、盛田剛平(3年)
・国士館大 金沢浄(3年)
・筑波大 FW和多田充寿⇒神戸
・順天堂大 FW川口信男⇒磐田
・中京大 GK山岸範宏(1年)
・11月22日 関東大学サッカーリーグで早稲田大、初の2部降格
この年、71回を数える関東大学サッカーリーグで名門・早稲田大学が6位に終わり、2部リーグとの入れ替え戦にも敗れて、史上初の2部降格という、ある意味「事件」とも言える出来事が起こりました。
早稲田に代わって2部から昇格したのが慶応大ということも象徴的でした。早稲田大は、このあと数年低迷時期に入りましたが、どのような事情があったのか気になるところです。
3月 高校サッカースーパーリーグ(関東)始まる
「リーグ戦を行なうことで、より良い選手の育成と、地域のレベルアップを図ろう」という趣旨で、発起人の当時・習志野高校・本田裕一郎監督の呼び掛けに、関東の強豪校が賛同し、3月16日から8月20日の日程で「高校サッカースーパーリーグ」がスタートしました。
それまで勝ち抜き戦のトーナメント方式の大会しかなかった高校年代のサッカー界、リーグ戦方式により実戦の機会を増やし、育成とレベルアップを図るこの方式は、のちに「プリンスリーグ」として全国規模になっていく原型となったリーグでした。
・平成9年度インターハイ(高校総体)サッカー決勝 東福岡vs帝京(4-3) 優勝 東福岡
この年、伝説を作る東福岡がまず一冠
・第8回高円宮杯全日本ユース(U-18)サッカー選手権決勝 東福岡vs清水商(3-2) 優勝 東福岡、古賀誠二選手の2ゴールなどで東福岡が二冠達成 小野伸二選手擁する清水商、2年ぶりのタイトル奪還ならず
・第5回Jユースカップサッカー選手権決勝 清水ユースvs広島ユース(3-0) 優勝 清水ユース。清水は平松康平選手、市川大祐選手の2年生組の活躍で初優勝を飾りました。
・第6回全国女子高校サッカー 決勝 兵庫・啓明女学院vs埼玉(3-0) 優勝 啓明女学院(回目) 昨年と同じカードとなった決勝、今回は啓明女学院が雪辱を果たしました。
・ 第9回全日本ジュニアユース選手権 決勝 三菱養和SCvs横浜FJrユース(3-2) 優勝 三菱養和SC(2回目)
・第2回全日本女子ジュニアユースサッカー(U-15)選手権 決勝 横須賀シーガルズFCvs九州選抜 優勝 横須賀シーガルズFC
・ 第21回全日本少年サッカー大会 決勝 千葉・柏レイソルJrvs群馬・FC邑楽(1-0) 優勝 千葉・柏レイソルJr(2回目) この年は全国8296チームが地域予選に参加、柏レイソルJrは、その頂点に立ちました。
テレビ、スポーツ紙、雑誌系いずれのメディアでも「フランスW杯アジア最終予選」関係の報道が圧倒的でした。
特に、この年の後半は、2002年W杯の日韓共催が決まっていることもあり、日本がワールドカップに出場するかどうかが、国民的関心事にまで高まりました。1997年はスポーツの中でサッカーが話題の中心に躍り出た元年とも言えますし、社会全体の中でもニュースバリューが飛躍的に高まった年でもあります。
したがって、今年1年を総括する年末のスポーツ系テレビ番組でもワールドカップへの出場を決めた日本代表が中心の番組構成となりました。
選手では年の前半が前園真聖選手、後半は中田英寿選手にスポットライトが当たった年でした。
年間を通したテレビ番組では、TBSの「筋肉番付」というスポーツマッスル系のバラエティ番組の一つのコーナーとしてサッカー選手向けの「キックターゲット」コンテストが人気を集めました。前年に始まったこのコーナー、特に前年・大晦日の特番(約36分)で、前年の出場全選手の成績がテロップで流れたこともあって各チーム、各選手からリベンジのリクエストが多かったのか定かではありませんが、この年は毎月2~3回サッカーコーナーが登場しました。
種目も「キックターゲット」に加えて「ロングシュート」や「ブレインパニック」といった新企画も取り入れられたほか、ブラジルやイタリアロケも敢行、ロマーリオ選手やバッジョ選手も登場させるなど、日本発祥のエンターティメント型サッカー企画が海外で披露される形になりました。
このほかテレビ東京系列で放送されているナインティナイン(岡村隆史・矢部浩之)司会のオーディション番組「ASAYAN」では「Jリーガー発掘オーディション」が3月から7月まで4回にわたって放送されました。番組では京都サンガのラモス瑠偉選手がJリーガーとしてプロ契約に値いする選手を1名発掘するというプロジェクトで、ハガキによる応募総数7000名の中から絞り込みを重ね、最後は11人による1泊2日の合宿まで企画されて合格者を決めるという念の入れようで、テレビの持つ力が発揮されました。
雑誌メディアでのサッカー記事も飛躍的に増えました。とりわけ総合スポーツ誌Numberでの記事量は、いよいよ「サッカーの時代到来」を思わせる扱いで、年間26冊(1998.1.1号まで)のうち10回サッカー選手を表紙に持ってきて、13回特集記事を掲載しました。翌1998年は、いよいよフランスW杯に日本が出場することを考えれば、もっと扱い量が増えることになるでしょう。とうとう、こんな日が来たのだと感慨を覚えます。
【テレビ】
【サッカー専門定期放送番組】
・NHK-BS 毎週1回 BSサッカーダイジェスト 沖谷昇、栗田晴行、小平桂子アネット
96.3月まで放送された「Jリーグダイジェスト」を96.4.7放送から「BSサッカーダイジェスト」に名称変更、放送時間もサッカー専門番組では最も長いCM抜きの60分になってリニューアルスタートしました番組ですが、97.3.23放送をもって終了しました。
・NHK-BS 不定期 エキサイティングスポーツ 勝恵子、小平桂子アネット
97.4.6からサッカーのみを扱う番組ではなく、スポーツ全般について、その時々の注目されるスポーツを扱う番組となりました。初回はJリーグ開幕特集としてスタジオを酒場風にしてゲストを招きながらの3時間特番が放送されました。
その後は、他局のスポーツニュース同様、番組全体の一部としてサッカー関係が紹介される形となり、W杯アジア予選やJリーグなど、サッカーのボリュームの大きい日は35分から55分の時間を割いて放送される形になりました。
・TBS 毎週1回 スーパーサッカー 30分 生島ヒロシ、三井ゆり
この年も、生島・三井のコンビによる番組が続き97.9.13には放送200回を達成しました。
NHK-BSのサッカー定期番組が消滅した中、貴重な長寿番組となりました。
・テレビ東京 サッカーTV 30分 久保田光彦、川平慈英(97.4.3スタート)
前年秋に「ダイヤモンドサッカー」が終了して半年のブランクがありましたが4月3日「サッカーTV」としてスタートしました。Jリーグや日本代表も扱う中で、テレ東の伝統である海外サッカー情報も当然という番組です。
そしてテレ東のもう一つの特徴、提言、緊急特集、座談会なども盛り込みながら、銀座ソニービル内のオープンスタジオからの放送というスタイルをとりました。
【単発ドキュメンター系・カルチャー系番組】
97-3.17クローズアップ現代「カズ30才W杯への再挑戦」国谷裕子・ゲスト奥寺康彦(NHK28’05)
いよいよ始まるW杯アジア一次予選、4年前のドーハの悲劇を経験したカズ・三浦知良選手は「今度こそは」と再度挑戦する。体力消耗の激しいサッカーで30歳といえば厳しい年代、直近の試合でも相手の厳しいマークを受け、なかなか活躍できない。スピードの衰えが相手へのマークを容易にしてしまう状況になっていると指摘されている。
果たして、カズ・三浦知良選手はそれを克服して日本をW杯に導けるのかを探る。
97-2.1スーパースペシャル97・ラモス瑠偉(日テレ17’29)
97-3.22NHKスペシャル放送記念日特集「新情報革命」第2回「激化するスポーツ放送権争奪戦」ナビゲーター・高島肇久(NHK49’00)
2002年W杯の放映権をドイツの放送事業会社がスイスの会社と共同で獲得、その額1200億円、前回アメリカ大会の実に10倍。これはデジタル技術の進歩により放送チャンネル数を各段に増やすことができたため、人気スポーツソフトを独占しようとする動きの結果だ。激化するスポーツソフト争奪戦の行き着く先には何があるのか。最前線にいるヨーロッパにそれを探る。
これまで多くの人々が無料で見られたW杯を、これからは有料でしか見られない時代がくるのか? それは「見る権利」を奪うビジネスではないのか? 各国は一部の企業が独占しないよう規制すべきではないのか? しかし、そういった規制は放送権料をアテにしたクラブ経営を脅かすのではないのか? さまざまな利害が絡み合うこの問題、どのように収れんしていくのか。
97-6.15ビハインドザホイッスル・オフサイド(NHK-BS19’53)
97-6.21ビハインドザホイッスル・レフェリー向上(NHK-BS19’59)
97-6.22BBCセレクション「熱狂するフーリガン・厳戒体制のサッカー場」1996年制作(NHK-BS48’59)
NHKが提携しているイギリスBBC放送の番組からセレクションされた番組。1996年イングランドで開催された1996年欧州選手権での、悪名高い暴走サッカーファン「フーリガン」と警察との戦いを描いたレポート。イングランド警察は欧州選手権開催を前にオランダ・ロッテルダムで行われたオランダvsドイツの国際親善マッチを視察、そこで目にした過激なフーリガンの騒乱に気を引き締めて帰国、これまで2年近く各国と連携して進めてきた対策の真価が問われる欧州選手権、果たして警察は無事仕事を成し遂げられるか。
97-10.5緊急特集・監督更迭「W杯をめざしてジーコの提言」司会・中村泰人アナ・王理恵、VTRゲスト、ジーコ、スタジオゲスト、加藤好男氏、財徳健治氏、柱谷哲二選手、都並敏史選手、中山雅史選手(NHK-BS2H00’00)
前日カザフスタンにロスタイムに同点にされてしまった日本代表、アジア最終予選これまでの4試合を振り返り、監督交代となった今、これから日本代表はどうすべきかについてジーコからの提言をもとに議論する2時間、果たして、各氏からのゲキは代表に届くかどうか。
97-10.14ヒーローたちが泣いた日・川口能活「父に見せなかった涙」(日テレ16’20)
W杯アジア最終予選のゴールマウスを守り続ける不動のGK・川口能活選手、彼は言う「父と母がいたからこそ、いまの自分がある。あの時、親の心配する顔を見たくなかったので」と。能活少年に何があったのか。
97-10.25土曜特集「どうすればフランスに行けるか、これがフランスへの切り札だ。知られざる闘いの50年より」司会・堀尾正明アナ、ゲスト、加藤久氏、木村和司氏、清水圭、高見恭子、山藤章二氏、あとから参加・釜本邦茂氏、ナレーション・蟹江敬三(NHK1H14’00)
W杯アジア最終予選の第6戦、ホームUAE戦を翌日に控えて組まれた緊急特番。これまでの日本と韓国の50年の戦いの歴史を紐解き、そこから答えを見出そうという企画。
10月5日の放送といい、この放送といい「気が気でない」サポーターの気持ちを代弁するというか、いまの日本のサッカーファンの空気を映し出すことを意図した企画という意味で、これまでにない番組といえる。
97-11.18クローズアップ現代、国谷裕子、ゲスト岡田監督(NHK29’00)
ジョホールバルでのイラン戦勝利直後のインタビューで「W杯出場権というハードルはそんなに低いものではないと思います」と語った岡田監督、国谷キャスターから「W杯出場権というハードルはやはり高かったですか」とあらためて問われた岡田監督は「ボクにとっては、一つひとつの試合がハードルでした。どのハードルを倒してもダメ、この試合を越えたら、また次のハードルを越えなければならないという気持ちでした」と答えました。
そこから国谷キャスターとともに、アジア最終予選を振り返りました。
97-12.14漂流ニッポン・フランス行きを決めた岡田監督2つの決断(フジ11’24)
97-12.20 ’97サッカーの主役たち・川口、エムボマ(テレ東51’47)
97-12.22W杯へ試練の71日間・カズが語る(NHK59’05)
97-12.31スポーツドラマチック97「勇者たちの365日」司会、内山俊哉アナ、有働由美子アナ、ゲスト岡田監督、井原正巳選手、ねじめ正一(NHK45’17)
第一部テーマ「監督」ゲスト岡田監督とともにW杯アジア最終予選を振り返る。ゲストねじめ正一、第二部テーマ「選手」ゲスト井原正巳選手ほか各スポーツヒーローとともに、それぞれの今年を振り返る。ゲスト内館牧子。
【単発バラエティ系・ワイドショー系番組の主な番組】
【筋肉番付】
97-1.8筋肉番付キックターゲット・柱谷哲二、広長優志(TBS13’09)
97-1.25筋肉番付ブレインパニック・清水エスパルス選手(TBS5’55)
97-2.1筋肉番付・キックターゲット、井原、川口他(TBS14’00)
97-2.8筋肉番付・キックターゲット市船戦士登場(TBS11’41)
97-3.15筋肉番付・キックターゲット、セルジオ越後2度目(TBS6’30)
97-3.22筋肉番付・キックターゲット、ジーコ、ロマーリオ他(TBS36’01)
97-4.19筋肉番付・ロングシュート、ヴ川崎編(TBS10’20)
97-5.17筋肉番付・キックターゲットG大阪編(TBS9’41)
97-5.31筋肉番付・キックターゲット清水編(TBS9’34)
97-6.7筋肉番付・キックターゲット横浜F編(TBS10’49)
97-6.14筋肉番付・ロングシュート、清水編(TBS10’45)
97-6.21筋肉番付・名波、中山雅史他(TBS15’10)
97-7.19筋肉番付・キックターゲット、北嶋、エジウソン他(TBS15’00)
97-8.16筋肉番付・キックターゲット、京都サンガ編(TBS28’00)
97-9.6筋肉番付・キックターゲット浦和編(TBS7’28)
97-9.27筋肉番付・キックターゲットinイタリア(TBS17’25)
97-10.18筋肉番付・キックターゲット、バッジョ(TBS13’39)
97-11.15筋肉番付・キックターゲット日本代表SP、中山、名波他(TBS11’23)
97-11.29筋肉番付・キックターゲット札幌編(TBS9’40)
97-12.27筋肉番付・キックターゲット、ジーコ、レオナルド(TBS9’49)
97-12.30筋肉番付番外編・キックターゲット、ストイコビッチ部分(TBS5’32)
97-12.30筋肉番付番外編・キックターゲット、バッジョ他(TBS7’10)
【その他バラエティ系・ワイドショー系】
97-1.2さんまのまんま・新春大売り出し・中田英寿選手、元木大介選手、田中秀道選手、少し遅れて中山エミリ、北浦共笑(日テレ16’30)
この時まだ19歳になったばかりの中田英寿選手の貴重なバラエティ番組出演記録。このあと頑なにバラエティ系の番組出演を辞めた中田選手の数少ない番組の一つ。しかも、プロ野球選手の元木選手、プロゴルファーの田中秀道選手と並んでソファーに座り、さんまさんと絡むというレアなシチュエーション。遅れてきた中山エミリ、北浦共笑とのトークでは顔を赤らめ、さんまに突っ込まれる場面も。また中田選手が炊飯器が欲しいとリクエスト、「ごはんが入った炊飯器でもええのか?」と聞かれ「構いません」と答えて大うけ。最後に中山エミリとプリクラを撮影してお開き。
97-1.11TVおじゃマンボウ市立船橋イレブン生出演(日テレ50’10)
97-1.19ASAYANラモスの即戦力Jリーガー発掘プロジェクト・読売ユース出身・佐渡谷聡クンに注目(テレ東6’24)
97-1.20東京フレンドパークⅡ・川口能活、井原正巳(TBS52’24)
97-2.3東京フレンドパークⅡ岡野、池田伸(TBS52’15)
97-2.12とんねるずの生ダラ・ノリさんヴェルディ入団テスト受ける(日テレ42’35)
97-2.23スポーツ100%フットサル大会①(テレ東30’05)
97-3.2スポーツ100%フットサル大会②(テレ東23’35)
97-3.5とんねるずの生ダラ・J開幕ヴェルディ盛り上げ企画①(日テレ44’40)
97-3.12とんねるずの生ダラ・J開幕ヴェルディ盛り上げ企画②(日テレ7’25)
97-3.30ASAYANラモスJリーガー発掘会①(テレ東29’22)
ナインティナイン(岡村隆史・矢部浩之)、永作博美司会のオーディション番組で、京都サンガ・ラモス瑠偉選手とチームメイト望月聡選手がプロ契約選手を1名発掘するプロジェクトが昨年スタート。ハガキ応募者総数7000通の中から昨年12月の第一次オーディションに1600名が参加、そこから絞り込まれた187名が第二次オーディションに参加、その中から27名が第三次オーディションに進むことになり、この日その模様を放送、この日は岡山一成クン18歳(初芝橋本出身)、高木成太クン19歳(国見高校出身)などが参加、1名限定選考の予定が、12名による追加合宿・選考会にバージョンアップした。(ナレーション・川平慈英)
97-5.11おしゃれ関係・前園真聖(日テレ27’20)
97-5.20さんまのサッカー小僧・ゲスト川口能活(フジ42’15)
97-6.22ASAYANラモスJリーガー発掘会②(テレ東8’18)
97-6.29ASAYANラモスJリーガー発掘会③(テレ東18’54)
97-7.1さんまのサッカー小僧・ゲスト井原正巳(フジ40’45)
97-7.20ASAYANラモスJリーガー発掘会④(テレ東1’20)
司会、ナインティナイン(岡村隆史・矢部浩之)、永作博美、ナレーション・川平慈英
1月と3月にオンエアされた選考会から、6月の2週放送を経て11名の中から選ばれたのは、清水商時代に安永聡太郎選手、佐藤由紀彦選手たちと同世代の原裕樹くん(21歳)でした。原くんは清水商時代、厚い選手層の中スタメンは確保できませんでしたが登録メンバーとして高校総体、全日本ユース選手権の二冠を経験しています。その後、ブラジルで2年間武者修行して帰国、今回、応募総数7000通の中からラモス瑠偉選手、望月聡選手の厳しいメガネに叶ったのでした。
6月27日のオンエアでは京都サンガのユニフォームに袖を通した原選手がスタジオに登場、ナイナイの二人からや客席からも大きな祝福を受けました。
そしてこの日のオンエアでは、5月30日に晴れて京都サンガクラブ事務所を訪れ、松本育夫GMから契約書を提示されサインした様子が放映され、Jリーガーオーディションプロジェクトが完結しました。
原選手が契約した翌日、5月31日「スポーツ報知」紙には「ASAYAN選考、21歳原裕樹、サンガと契約」の見出しで、そのことが掲載されていて、本文では「シンデレラJリーガー」と形容されています。
97-7.22さんまのサッカー小僧・明石家さんま、所ジョージ、ゲスト中田英寿選手(フジ41’30)
レギュラー出演の都並敏史選手が骨折のため番組休みで所ジョージが代理出演という珍しい組み合わせに中田英寿選手が登場、さんま、所の二人に挟まれても自分のペースを崩すことなくトークを繰り広げた。
97-7.27フジ27時間テレビ・さんまのフットサル大会(フジ43’54)
97-8.26さんまのサッカー小僧・ゲスト岡野雅行(フジ41’00)
97-9.16さんまのサッカー小僧・ゲスト三浦淳宏、ジーコ(フジ41’15)
97-10.26おしゃれカンケイ・ラモス瑠偉(日テレ27’00)
97-10.28見ればなっとく・W杯アジア最終予選・韓国でカメラ20台取材(TBS51’40)
97-11.1TOKIO、キンキ、V6なんでも日本一に挑戦、どろんこサッカー(日テレ14’25)
97-11.1さんまのサッカー小僧・韓国戦直前応援SP(フジ53’32)
97-11.16さんまの爆笑道中スペイン&イタリアサッカー夢紀行(日テレ1H23’00)
97-11.17 B・T(ビッグ・トゥディ)妻たちのW杯(フジ50’00) 司会・佐藤充宏、芸能レポ・前田忠明
ついにW杯出場権獲得を成し遂げた日本代表、そこには代表選手を支え続けた妻たちの涙と喜びがあった。中山雅史選手の妻・生田智子さんに密着「妻たちのW杯」を追った。
97-11.18見ればなっとく・もう一度泣きたい! W杯熱狂列島、司会、生島ヒロシ、雨宮塔子、ゲスト・岡田監督、城彰二選手(TBS52’31)
ジョホールバルでの日本vsイラン戦を見守る日本各地の表情、手に汗握る応援の表情をカメラ30台を配置して追った。見ればなっとくの歴史的一日を振り返る。
97-11.19ザ・ワイド、岡田監督夫人の内助の功(日テレ12’00)
97-11.21知りたがり緊急特番、祝W杯出場(フジ1H55’30)
司会、八木亜希子、福井謙二、実況担当・長坂哲夫、解説・清水秀彦、パリから中継・田代尚子、FAX担当、西山喜久恵(あなたが選ぶMVP募集)
ゲスト、岡野雅行選手、川淵三郎、都並敏史選手、岡本夏生、山田まりあ
国民的大試合となったジョホールバルのイラン戦をもう一度、試合全部のほか家族の応援、第1戦からの苦闘など、秘蔵映像を交えて完全版、永久保存版としてぜんぶ見せます緊急生特番放送。
97-11.21金曜TVの星「おめでとう日本代表」(TBS1H51’10)
司会、薬丸裕英、中井美穂、進藤晶子アナ、ゲスト、井原正巳選手、川口能活選手、城彰二選手、中田英寿選手、(遅れて)岡野雅行選手、コメンテーター、木村和司、水沼貴史、スタジオ観客175名
・柱谷哲二がみたイラン戦、・フィールドの宇宙人・中田英寿選手の高校時代、・城彰二涙の理由、・磐田から中継出演、中山雅史選手、名波浩選手、・もうだめだ、川口能活選手、帰ってきたお助けマン、北澤豪、・左足のテクニシャン、名波浩選手、・左腕に誓った悲願、井原正巳選手、・野人と呼ばれて、岡野雅行選手(いま到着)、・韓国実況ブース、・鹿島4人衆、鹿島から中継出演、相馬直樹選手、秋田豊選手、本田泰人選手、名良橋晃選手、・母に誓った悲願、呂比須ワグナー選手、・ジーコスタジオ登場
97-11.22素顔が一番・奥寺康彦(日テレ28’30)
97-11.23だんとつ平成キング決定戦・お立ち台リフティング(日テレ12’52)
97-11.23ねばぎば!TOKIO・ラモス瑠偉とPK対決(フジ36’50)
97-11.25ザ・ワイド野人岡野育成法(日テレ12’50)
97-11.27スーパーモーニング・中山雅史(テレ朝28’58)
97-12.4さんまの第11回スポーツするぞ大放送(フジ14’00)
97-12.14スーパーナイト・岡チャンに秘密兵器、小野伸二推薦(フジ6’46)
97-12.15東京フレンドパークⅡ・城彰二、小菅真理(TBS49’39)
97-12.26スポーツ好珍プレー97決定版SP(フジ20’35)
97-12.30スポーツDAS・映像の王様SP、呂比須他(テレ朝18’37)
97-12.31今夜見せます泣かせます秘蔵名場面・日韓の44年(テレ朝9’52)
【ニュース系番組】
97-1.10ニュース23・ゲスト川口能活(TBS13’24)
97-1.11サタデースポーツ・井原正巳(NHK15’00)
97-1.12サンデースポーツ他1本・加藤久監督(NHK他14’25)
97-1.22スポーツTODAY・名波浩(テレ東10’10)
97-1.31ニュースステーション・岡野雅行特集(テレ朝18’25)
97-2.8サタデースポーツ・小倉隆史(NHK6’10)
97-2.23独占スポーツ情報・前園(日テレ13’50)
97-2.25ニュースステーション・ゲスト加茂監督(テレ朝8’06)
97-2.26TVじゃん・長島茂雄×加藤久(日テレ13’20)
97-3.2日本代表フランスへの道(TBS22’00)
97-3.21ニュースステーション・W杯アジア予選スタート特集(テレ朝25’00)
97-3.29サタデースポーツ・ゲスト三浦知良(NHK18’27)
97-4.7スーパーJチャンネル・ゲスト高木琢也(テレ朝23’50)
97-4.13独占スポーツ情報・ゲスト川淵チェアマン①(日テレ18’55+1’40)
97-4.14ニュースステーション・加藤久監督になる(テレ朝12’43)
97-4.16スポーツTODAY・稲本株急上昇(テレ東8’51)
97-4.19サタデースポーツ・衝撃のエムボマ(NHK12’43)
97-4.30スポーツTODAY期待の若手(テレ東7’30)
97-5.7ニュースステーションJ前7節川平劇場(テレ朝14’07)
97-5.23ニュースの森・サッカーくじ法案ゲスト、千野圭一(TBS13’45)
97-5.31ニュースイブニングW杯共催決定1年・現地ルポ(テレ東11’20)
97-6.1 BS-JリーグSP「西からの旋風」ゲスト松波正信、西沢明訓(NHK-BS1H30’00)
97-6.1 Grade-A・ラモス(フジ6’37)
97-6.1トランスワールドスポーツ・ブラジル代表(NHK-BS6’46)
97-6.2キリンカップ直前日本代表特集(日テレ50’01)
97-6.8静岡スポーツスタジアム・ゲスト三浦文丈(SBS22’05)
97-6.8独占スポーツ情報・ゲスト井原正巳、平野孝(日テレ14’23)
97-6.15W杯アジア予選緊急特集「W杯を語~る」(テレ朝23’30)
97-6.21 VIVAワールドカップ・サッカーの魅力(NHK-BSh1H29’59)
97-6.21サタデースポーツ・カズの決意(NHK7’43)
97-6.21栄光のワールドカップ・フランスへの道(NHK-BS2H00’00)
97-6.23スーパーJチャンネル・草サッカー試合エージェント(テレ朝8’17)
97-6.25フランスW杯への道・私とワールドカップ渡辺徹(NHK-BSh4’48)
97-6.28スポーツうるぐす・西沢明訓、中村忠(日テレ5’05)
97-6.29サンデースポーツ・加茂監督(NHK14’58))
97-7.2TVじゃん・中田英寿(日テレ6’03)
97-7.14スーパーJチャンネル・ゲスト川口能活(テレ朝28’00)
97-7.17ニュース11・ブランメル仙台の財政危機(NHK7’08)
97-7.19スポーツうるぐす・本田、ビスマルク、柳沢(日テレ10’25)
97-7.20サンデースポーツ・ゲスト本田泰人、柳沢敦(NHK11’35)
97-7.30Jスポーツプレミアム・G大阪新井場徹(Jスポーツ13’40)
97-7.31静岡キックオフ97・92-96高校総体名場面(静岡第一TV11’14)
97-8.2Jスポーツ・ホームタウンシリーズ清水(Jスポーツ13’07)
97-8.3独占スポーツ情報・川淵チェアマン(日テレ11’50)
97-8.11若きJリーガーの挑戦、三浦淳宏、萩村滋朗(NHK-BS2H00’00)
97-8.13ニュースステーション・カズ(テレ朝9’28)
97-8.24 Grade-A・リトバルスキー(フジ26’22)
97-8.27スポーツTODAY・沢登(テレ東7’40)
97-8.31いよいよ最終予選、清水圭のたのむぞ日本代表、代表選手に聞く他(TBS51’42)
97-8.31サタデースポーツ・ドーハ組4年目の夏、柱谷、松永、北澤(NHK21’24)
97-9.2スーパーJチャンネル・清水の国際少年サッカー大会(テレ朝15’54)
97-9.3Jスポーツプレミアム・ブッフバルトストーリー(Jスポーツ13’03)
97-9.3フットボールムンディアル・セリエA特集ロナウド(GAORA25’45)
97-9.5スポーツTODAY・日本代表の1300日(テレ東15’05)
97-9.6Jスポーツプレミアム・永島昭浩ストーリー(Jスポーツ13’05)
97-9.13Jスポーツプレミアム・鹿島の10番(Jスポーツ12’20)
97-9.21Grade-A・W杯アジア最終予選始まる(フジ16’43)
97-9.23ニュース23・日韓戦&呂比須(TBS14’50)
97-9.26ニュースステーション・韓国側の日韓戦(テレ朝15’15)
97-9.27ブロードキャスター・韓国戦前夜(TBS10’20)
97-9.28サンデースポーツ日韓戦分析(NHK21’56)
97-10.1スポーツニュース一括・磐田優勝ほか(テレ朝ほか39’38)
97-10.5,6スポーツニュース一括・加茂監督更迭(テレ朝ほか53’53)
97-10.8フットボールムンディアル・南米スーペルコパ(GAORA10’04)
97-10.13ニュースステーション・川平あきらめるな(テレ朝7’33)
97-10.13ニュースヒューマン・W杯ダメだったら(フジ6’14)
97-10.18ブロードキャスター・W杯ダメだったら(TBS9’40)
97-10.19サンデースポーツ・ドゥンガ、リティが提言(NHK12’51)
97-10.22おしえてアミーゴ・ブラジルサッカー少年(TBS36’15)
97-10.27スーパーJチャンネル・清水ユース育成(テレ朝16’05)
97-10.27ニュースステーション・UAE戦勝てず(テレ朝13’59)
97-10.28フットボールムンディアル・日本のサッカー事情(GAORA22’09)
97-11.1サタデースポーツ・韓国撃破(NHK22’17)
97-11.1スポーツうるぐす・韓国撃破(日テレ10’37)
97-11.1ブロードキャスター・韓国撃破(TBS16’57)
97-11.3ニュースステーション・韓国で燃えた(テレ朝14’20)
97-11.7ニュースステーション・がんばれカザフ戦(テレ朝16’30)
97-11.8サタデースポーツ・カザフ戦&ナビスコ(NHK21’48)
97-11.8ニュース11・川口能活(NHK8’08)
97-11.8ブロードキャスター・カザフ戦快勝(TBS15’30)
97-11.9サンデーじゃんぐる・W杯自力出場復活(テレ朝16’58)
97-11.9炸裂スポーツパワー・行くぞフランス緊急特集(TBS35’33)
97-11.10ニュースステーション・カザフに劇勝(テレ朝12’10)
97-11.10ニュースヒューマン・カザフ戦列島燃えた(フジ11’05)
97-11.12ニュースステーション・在日イラン人の悩み(テレ朝12’22)
97-11.14ニュースステーション・勝利の女神総動員(テレ朝19’22)
97-11.15ザ・ウィーク・特集いよいよイラン戦(フジ41’45)
97-11.15プロードキャスター・まもなくイラン戦(TBS15’30)
97-11.16ザ・サンデー・今日イラン戦(日テレ14’45)
97-11.16サンデースポーツ・特集W杯出場決定(NHK25’27)
97-11.16プロ野球ニュース・W杯出場決定直後特番(フジ35’36)
97-11.16決戦直前、緊急スペシャル(フジ48’00)
97-11.16新サンデーモーニング・今日イラン戦(TBS21’34)
97-11.16悲願達成なるか、フランスへの道(NHK-BS1H59’50)
97-11.17おはようクジラ・日本中が燃えた夜(TBS16’40)
97-11.17おはようナイスディ・歓喜の渦、悲願のW杯初出場(フジ1H02’45)
97-11.17スーパーJチャンネル(後半)日本代表歓喜の一日(テレ朝13’40)
97-11.17スーパーJチャンネル(前半)日本代表決めたW杯って何(テレ朝21’15)
97-11.17スポーツMAX・二宮清純のコラム(日テレ4’35)
97-11.17ニュース23・それぞれのイラン戦(TBS9’20)
97-11.17ニュースステーション・ゲスト都並敏史(テレ朝16’15)
97-11.17ニュースの森・列島が揺れた夜・ゲスト釜本邦茂(TBS24’40)
97-11.17ニュースヒューマン・日本悲願のW杯・カズ他(フジ32’04)
97-11.17プロ野球ニュース・日本代表フランスへの道(フジ16’13)
97-11.17めざましTV・おめでとう日本代表(フジ30’10)
97-11.18TBSニュースの森・城、岡野生出演(TBS18’52)
97-11.18おはようクジラ・ジョホールバル戦士帰国会見(TBS34’02)
97-11.18おはようナイスディ・イラン戦から帰国(フジ22’00)
97-11.18スポーツMAX・カズ、北澤豪(日テレ8’25)
97-11.18スポーツTODAY・岡田監督、岡野雅行(テレ東17’20)
97-11.18ニュース7・ゲスト、カズ・北澤(NHK6’10)
97-11.18ニュース23・ゲスト井原正巳(TBS13’00)
97-11.18ニュースステーション・岡田監督、岡野雅行(テレ朝16’03)
97-11.18ニュースヒューマン・岡田監督(フジ18’12)
97-11.18プロ野球ニュース・ゲスト井原正巳(フジ18’10)
97-11.19スポーツTODAY・W杯出場国あと1つ(テレ東8’35)
97-11.19ニュース23・ゲスト川口能活(TBS13’40)
97-11.19ニュースの森・多忙代表、清水他(TBS15’20)
97-11.21ニュースステーション、井原正巳、山本潤子(テレ朝20’50)
97-11.21ニュースの森・川口能活、城彰二。井原正巳(TBS5’14)
97-11.22あの感動をもう一度・日本代表鹿島DF座談会(NHK-BS40’00)
97-11.22サタデースポーツ・ゲスト井原正巳(NHK10’28)
97-11.22スポーツうるぐす・ゲスト井原正巳(日テレ8’10)
97-11.23セルジオが行く欧州サッカー紀行97・フランス、ユーゴ他(フジ51’56)
97-11.23独占スポーツ情報・ゲスト岡野雅行(日テレ8’21)
97-11.23炸裂スポーツパワー、ゲスト・ラモス瑠偉(TBS36’30)
97-11.23炸裂スポーツパワー・ラモス(TBS11’40)
97-11.26フットボールムンディアル・フランスW杯アジア最終予選(埼玉TV24’31)
97-11.29サタデースポーツ・ナビスコ決勝他(NHK19’35)
97-11.29スポーツうるぐす3夜分・トヨタカップ直前情報(日テレ15’39)
97-11.30炸裂スポーツパワー・岡田続投、代表料理人(TBS25’50)
97-12.1トヨタカップ特集・名勝負プレーバック&今年のみどころ(日テレ58’35)
97-12.3スポーツTODAY・中田英寿特集(テレ東13’25)
97-12.3プロ野球ニュース・ゲスト呂比須(フジ18’53)
97-12.4フランスW杯組合せ抽選会中継(NHK-BS1H25’00)
97-12.5ニュースステーション・W杯組合せ抽選会&今年の回顧(テレ朝23’20)
97-12.5ニュースの森・中田世界選抜&対戦国分析(TBS25’30)
97-12.6プロ野球ニュース・ゲスト中山雅史(フジ31’55)
97-12.8ニュースステーション・ゲスト中田英寿(テレ朝18’50)
97-12.10スーパーJチャンネル・植田朝日のコレクション(テレ朝9’07)
97-12.10スポーツMAX・中田英寿の全貌・インタビュー(日テレ6’47)
97-12.13サタデースポーツ・磐田年間王者、中山、奥、田中、藤田(NHK16’33)
97-12.13スポーツTODAY・磐田年間王者(テレ東7’00)
97-12.14サタデースポーツ・ラモス(NHK14’30)
97-12.14炸裂スポーツパワー・サッカー満載(TBS30’41)
97-12.15スポーツMAX・ストイコビッチW杯へ(日テレ10’30)
97-12.15ニュース11・今年の主役岡野雅行(NHK6’50)
97-12.17スポーツTODAY・今年の十大ニュース(テレ東8’19)
97-12.17フットボールムンディアル・97トヨタカップ(GAORA10’15))
97-12.20サンデースポーツ・ゲスト川淵チェアマン(NHK18’06)
97-12.21サタデースポーツ・川口能活(NHK19’27)
97-12.21炸裂スポーツパワー・今週もサッカーが熱い(TBS27’35)
97-12.22ブロードキャスター・スーパー20才・中田英寿(TBS17’20)
97-12.23ニュースステーション・特集W杯への軌跡(テレ朝37’55)
97-12.24フットボールムンディアル・97総集編(GAORA25’47)
97-12.25スポーツTODAY・日本サッカーこの1年(テレ東16’33)
97-12.28炸裂スポーツパワー・今年のスポーツヒーロー(TBS30’30)
【チーム応援番組】(地方からの収集分含む)
・毎週1回 Kick off マリノス TVK 25分
この年4月4日放送から、ナビゲーターがそれまでの卜部真由美さんから、マリノスOBの水沼貴史さんと中願寺香織さんの2人に交代しました。
・毎週1回 フリューゲルスアワー TVK 15分
・毎週1回 戦えベルマーレ TVK 15分
・毎週1回 GOGO! レッズ 埼玉TV 30分
ナビゲーター 上野晃アナ、五十嵐智子さん、この年1月24日放送で200回放送達成。
・隔週1回 GOAL FOR WIN ジェフ チバTV 30分
ナビゲーター 西野七海さん この年年末12月21日放送をもって終了しました。この間、3年9ケ月・79回の放送でした。新年からは月1回放送の「月刊ジェフくら」に衣替えして登場とのことです。
・隔週1回 CanDoレイソル チバTV 30分
この年4月13日放送から、ナビゲーターがそれまでの長崎雪絵さんから瀬川慶さんに交代しました。
・毎週1回 フォルツァ・ジュビロ SBS この年4月からそれまでの20分枠が30分に拡大。
ナビゲーター 上田朋子さん
・毎週1回 オーレ・グランパス 名古屋TV 25分
・毎週1回 グランパスTV CBC(中部日本放送) 15分
・毎週1回 ドラグラサンデー テレビ愛知 15分
・毎週1回 ビバ・グランパス 中京テレビ 15分
・毎週1回 グランパス・エクスプレス 東海TV 25分
・毎週1回 GOGOアビスパ 福岡放送 15分
ナビゲーター 南省吾さん、木村みゆきさん(吉本興業・福岡)
・毎週1回 Vダッシュ セレッソ テレビ大阪 5分
・毎週1回 フォルサ・アントラーズ CS放送 30分(この年秋から放送開始)
・毎月1回 めざせJリーグ フロンターレ TVK 15分
【映画(テレビ放映版・市販ビデオ)】
97.6「驚異のゴールシーン パワーストライカー・ロナウド」(59’23 字幕スーパー版、ベースボールマガジン社刊)
96-97シーズンのバルセロナ加入からの34ゴール、そのゴールシーンだけを編集したVTR、後半は練習風景、メディア対応の映像。ロナウドが「怪物」と評されるようになったバルセロナ時代の永久保存版ともいえるビデオ。
【月刊誌・週刊誌・全国新聞・スポーツ紙】
1997.1.10-25合併号隔月刊ポパイ 前園真聖・いま決断する男5p(一部欠落).
1997.1下旬頃週刊プレイボーイ 日本代表を救う7つの提言4p.
1997.2.下旬週刊宝石 前園真聖激白 横浜Fに決別ヴ川崎へ3p.
1997.3.10週刊女性 日本代表豪州合宿・司令塔中田クールに熱くカラーグラビア3p.
1997.3.21週刊朝日 どうなる2002年W杯テレビ中継3p.
1997.3.27週刊文春 W杯予選突破赤信号・加茂監督は酒びたり3p.
1997.4月号月刊現代 日本代表の実力を読む・奥寺、尾崎加壽夫、水沼貴史、司会二宮清純7p.
1997.6.3週刊プレイボーイ 今売り出し中’謎の男’中田英寿4p.
1997.6月号出典不明 中田英寿インタビュー3p(一部欠落).
1997.6月頃隔週刊Bart 加茂周、勝負の時「いい試合なんて関係ない、勝か負けるかだ」.
1997.6月頃隔週刊Bart 前園真聖、勝負の時by山崎祥之(サニーサイドアップPRプランナー).
1997.7下旬 週刊プレイボーイ・鹿島黄金時代が始まった4p.
1997.7隔月刊Views W杯への檄・川口能活モノクログラビア7p.
1997.9.5週刊朝日 ラモス復帰とヴ川崎の身勝手さにあきれる1p.
1997.9.5週刊朝日 篠山紀信が撮る世紀末の50人「中田英寿」(表紙).
1997.9.11週刊新潮 来るべきものが来たエスパルス破産の危機3p.
1997.9.14サンデー毎日 小宮悦子のおしゃべり時間・中田英寿アジア最終予選直前5p.
1997.9.15頃出典不明 加茂を辞めさせなければ日本は惨敗するbyセルジオ、富樫、マイケル・プラストゥ2p.
1997.10.15頃週刊プレイボーイ 金田喜稔のコラム「カザフ戦後、加茂監督更迭」1p.
1997.10.17週刊AERA W杯危うし! 今なお引きずる栄光と悲劇6p.
1997.10.26サンデー毎日 ジェフ市原親会社長爆弾発言、加茂の次は川淵か2p.
1997.10.28週刊プレイボーイ 今こそ日本サッカー存亡の危機を救え7p.
1997.11.21毎日「記者の目」W杯初出場・運動部荒井義行1p.
1997.12.1週刊AERA ①カズと中田主役交代の時、②崖っぷちから再生させた強い人岡田3p.
1997.12.4週刊文春 阿川佐和子の会いたい・三浦知良6p.
1997.12.4週刊文春 進めオカちゃん3p(モノクログラビア).
1997.12.4週刊文春 代表イレブン隠されたタブーを明かす「崩壊寸前だった」5p.
1997.12.5フライデー 岡野Vゴール! 日本代表全ドラマモノクログラビア4p.
1997.12.5週刊朝日 W杯出場今だから明かせる舞台裏6p.
1997.12.9週刊プレイボーイ 43年目の栄光71日目の歓喜、次は世界が待っている8p.
1997.12.12週刊朝日 いざフランスへ日韓キャプテン対談・井原×洪明甫4p.
1997.12.13週刊現代 サッカー代表、テレビも週刊誌も書けない美談のうらの罵り合い3p.
1997.12.25-1.1合併号女性セブン 日本を救える男「中田英寿(20)」表紙+モノクログラビア4p.
1997.12.29週刊プレイボーイ 日本サッカー進撃SP ①秋田豊、②中田英寿7p.
1997.12月号月刊BART 中田英寿「W杯で勝つことを考えている」6p.
【総合スポーツ誌】
1997.2.13Number411 表紙荻原健司
特別インタビュー・加茂周by永井洋一、前園真聖の移籍を巡る一番長い日by佐藤俊
1997.2.27Number412 表紙ユベントス、リッピ監督、GKペルッツィ、FWデルピエロ
名将列伝 マルチェロ・リッピ、ベンゲル奮闘記、名将になれなかったオフト
1997.3.27Number414 表紙カズ・三浦知良
燃えろ! 日本代表 三浦知良、川口能活、名波浩、ドゥンガ・ブッフバルト
1997.5.22Number418 表紙ストイコビッチ
欧州サッカー特集・W杯への道「戦場」 ストイコビッチ、ラウル、エメ・ジャケ
1997.6.19Number420 表紙柳沢敦
日本サッカー新時代の若き獅子たち 柳沢敦、Jリーグ新鮮宅急便
1997.7.31Number423 表紙伊良部秀輝
好評連載・三浦知良W杯への日々、 加茂ニッポン、最後の切り札の「名前」
1997.8.14Number424 表紙ブラジル代表ロナウド
史上最強軍団の全貌 ロマーリオ、ドゥンガ、 中田英寿「世界は遠くない」
1997.8.28Number425 表紙前園真聖
「復活」その意思と力 前園真聖ロングインタビュー、絶望からの帰還・小倉隆史
1997.9.25Number427 表紙川口能活、井原正巳、名波浩
日本代表、最終決戦 インタビュー川口、クローズアップ井原、名波、中田、城
1997.11.6Number430 表紙ヒクソン・グレイシー 岡田ジャパンはどうなる
1997.12.4Number432 表紙中山雅史
We did it ! 緊急速報日本vsイラン 密着ドキュメント中田英寿と川口能活の63日
1997.12.18Number433 表紙パオロ・マルディーニ フランスW杯選ばれし者たち32ケ国
1998.1.1Number434 表紙中田英寿 1997を語る 呂比須、川口、岡田監督
【サッカー専門誌】
サッカー専門誌は、週刊発行のサッカーマガジン誌、サッカーダイジェスト誌、月刊発行のストライカー誌、そして隔月刊発行のサッカー・アイ、そして海外サッカー専門誌として月刊発行のワールドサッカーダイジェスト誌、ワールドサッカーグラフィック誌の6誌体制で推移しました。
このうちサッカーマガジン誌は4月9日号で通巻600号となりました。600号は一つの通過点のようで特別な企画はありませんでした。
他にも技術専門誌などコアな読者層向けの雑誌もありましたが、日本のサッカーファンの層が概ね、①日本代表を頂点とする国内サッカーに関心が強い層、②海外サッカーのほうに関心が強い層、③若手Jリーガーへの関心が強いビジュアル系ファン層、この3つに分類される中、どの層のニーズにも応えられる体制になったと言えます。
前年にもアトランタ五輪出場を決めた日本五輪代表の活躍を報じた増刊号・別冊の発行が見られましたが、今回のフランスワールドカップアジア最終予選の日本代表の73日間のドラマは、サッカー専門誌にとっても歴史的な出来事でしたから、増刊号・別冊発行がありました。
すでに「日本サッカー界初の歴史的偉業に挑戦した2ケ月半、日本のサッカー文化を一気に開花させて数々の記録的出来事」という大見出しの中で「総合スポーツ誌Number、サッカー専門誌などでのサッカージャーナリスト、フォトカメラマンたち」という小見出しを設けて詳細をご紹介していますが、別冊で発行された冊子は次のとおりでした。
・1997.12.4サッカーマガジン増刊号「現地緊急座談会」「記者席での71日間」など。
・1998年新年号 別冊週刊サッカーマガジン「ワールドカップ初出場メモリアル写真集」
・1997.12.18サッカーダイジェスト増刊「ジョホールバル歓喜の全記録」(永久保存版)
【書籍】
「個性を束ねて勝つ ひとりの集団」加藤久著(講談社1997年3月刊)
表紙帯紹介文 「強い集団」を築く指導者がすべきことは? 勝つために「心と技術」をいかに磨くか? 現代風若者との「よりよい関係」の作り方とは?
スポーツ心理学、運動生理学に裏付けされた”理論”。Jリーガー、前日本サッカー協会強化委員長としての”実践”。いま「個の強さ」を活かし「強い集団」をつくる秘伝を明かす!
旺盛なる自立心、健全な闘争心、明快な判断力を教える。
「勝者のエスプリ」アーセン・ベンゲル著、岡田紀子翻訳(NHK出版1997年8月刊)
この書物については、1996年9月に名古屋監督からイングランドプレミアリーグの名門・アーセナル監督に就任するため日本を離れた際に、ベンゲル監督が日本サッカーに遺していった財産(レガシー)を記録するために、その多くを参照した書物です。
「伝説のあの年 1996年」の中の大見出し「Jリーグ後半戦スタート、いきなり名古屋・ベンゲル監督辞任、アーセナルに移籍」のところで紹介した内容もご覧ください。
[内容概略] ベンゲル監督は「サッカーとは、もともと場面場面で選手が自由に選択して表現することこそ本質なんだ」という信念から、選手が自己表現したいという意欲を削がないようにしながら、実際の試合の中で起きるシチュエーションに応じて、できるだけ細かく、具体的に選手に考えさせ、自分たちの選択でゲームを展開させていく練習を取り入れました。
名古屋での指導を通じて、日本人が常に厳格で、明確に定義された任務を求めているということに気づくまで、時間がかかったものの、最終的には「選手たちにもっと自立した、自由な表現を求める」指導に徹し、それができる選手を見極めて起用し、ストイコビッチ選手を中心としたチームプレーを軌道に乗せて、成果を出しました。
ベンゲル監督が名古屋というクラブに植え付けたかったのは、やみくもに定義された任務をこなそうとするサッカーではなく、場面場面で選手が自由に選択して表現しながらゲームを展開させていくサッカーであり、そこにこそ「勝者のエスプリ」があるということでした。
一方でベンゲル監督は言います。「そもそも監督という職業で、100%の信頼を勝ち取るのは無理なのではないだろうか。」と。「選手からは毎日、信頼できるかどうかというテストをされる。(中略)些細なウィークポイントでも発覚すれば、今までに獲得してきた信頼は一気に崩れ、批難の対象となるのはわかりきっている。どんな弱点も許されないのだから、これは自分の弱点に挑む永遠の闘いのようなものだ。(中略)仕事を通じて最低の経験をする時と最高の喜びを得る時を常に行ったり来たりしている」
それ故、ベンゲル監督は仕事への熱意を何よりも大切にして、ほとんどサッカー漬けの日々を送っています。素晴らしい指導者とは「サッカー指導者」という職業に情熱を注ぎ込むことを最大の喜びとして没頭できる人を指すようです。
「28年目のハーフタイム」金子達仁著(文芸春秋社1997年9月刊)
気鋭のサッカージャーナリスト・金子達仁氏の処女作
帯紹介文 「そして、アトランタ世代の闘いはフランスへと続いていく。ブラジル戦の奇跡は、大いなる歓喜の序曲にすぎなかった。28年ぶりのオリンピック出場を果たし、いくつもの『断層』を抱えながら史上空前の快挙を成し遂げた日本サッカー。歴史を作った川口能活、中田英寿、城彰二らの『物語』はW杯最終予選の苦難の道程をも予見していたのだ。」
[内容概略]日本五輪代表は28年ぶりに本大会への出場権を果たしたが、アジア最終予選から本大会にかけて五輪代表のチーム内に生じていた選手間、選手と監督間の意識のずれを当事者への丹念なインタビューを通じて明らかにした。
そして、ブラジル戦勝利という歴史的快挙の次戦ナイジェリア戦で、このチームは完全に崩壊したと断じている。特にナイジェリア戦のハーフタイムこそが、その引き金になったとして書籍のタイトルにもしている。
また、そのハーフタイムの出来事の一方の当事者である「中田英寿」という選手について1つの章を設けて書き下ろしているのも特徴。その後、多くのジャーナリストの多くの著作で語られる「中田英寿」像について、一番最初に注目したジャーナリストが金子氏であり、この著作がその嚆矢となっている。
「挑戦! 岡田ニッポン」サッカー日本代表担当記者編(太陽出版1997年12月刊)
まえがき抜粋 「本書は”岡田ニッポン”に胸を熱くするすべてのサポーターに捧げる、究極の日本代表観戦マニュアルである。
悲願達成に向けた選手一人ひとりの予選での苦悩はもちろん、グラウンドを離れた部分での知られざる素顔や隠れたエピソードも満載した、他に類を見ない一冊でもある。(中略)
栄光の選手たちの人柄やサッカーに対する思いを知ることによって、サポーターの皆さんの応援にもいっそう熱がこもることを我々は確信している。(中略)
フランス最大のスポーツ紙『レキップ』は、日本の予選突破確率をわずか20%とした。アルゼンチンとクロアチアにはなにがあっても勝てないと断言されているようなものだ。
しかし、我々は信じている。日本代表がジャマイカ戦後もフランスの地にとどまっていることを・・・・。
さぁ、本書を手に『みんなでフランスに行こう! !』」
「ROAD to FRANCE 写真集ワールドカップ1998アジア最終予選 日本代表 激闘の記録」(朝日新聞社1997年12月刊)
ジョホールバルの歓喜でエンディングを迎えたフランスW杯アジア最終予選、日本代表の激闘を数々の写真で振り返る完全保存版
1997年とは「日本サッカーが、長年の悲願だったワールドカップ出場権を初めて勝ち取った歴史的な年であり、その闘いを通じて日本に『サッカー文化』という花が、つぼみから3輪、5輪、咲き始めた年」
前年の1996年に「2002年W杯」の開催地が日韓共催という形で決まり、喜び半分ながらも前向きにとらえ準備にまい進することとになりました。10年前の1986年「ワールドカップの招致」と「日本リーグのプロ化、その強化によるワールドカップへの出場」という二つの目標を掲げてから10年、そのうちの一つが達成されたのです。
またアトランタ五輪サッカーに日本男子が28年ぶりに出場権を得たことも大きな前進でした。そして今年は何といっても98FIFAフランスワールドカップへの出場権を賭けた「アジア予選」という11年前に掲げたもう一つの関門への挑戦の年でした。
2002年W杯の開催国となったからには、その時が初出場では汚名でしかない、その前にフランスワールドカップに出場しておくことが、もはや「Must=義務」であるかのようなプレッシャーの中で「アジア予選」を戦うことなど、かつてなかった経験であり、あと一歩のところまで行った4年前の「ドーハの悲劇」の時に背負っていた十字架とは比べ物にならないほど重い十字架を背負っての闘いとなってしまったのです。
日本代表を率いる加茂監督には、前年末のアジアカップでベスト8敗退という結果であったことから多くの懸念が出され、それが加茂監督を次第に内向きにしてしまったこともあり、負のスパイラルに陥るかのように采配に対する批判は増幅していきました。
マスコミを中心とした批判の矛先は、そういった加茂監督に対する懸念について沈黙を保つだけの日本サッカー協会にも向けられましたが、協会は一向に動こうとはせず、とうとう9月上旬からの「アジア最終予選」に突入しました。
こうしてみると1月から最終予選までの8ケ月間、必死になって「加茂監督では出場権獲得という『Must=義務』は果たせない」と叫び続けた一部のサッカー関係者、ジャーナリストたちの声と、日本サッカー協会の沈黙から漂ってくる「何とかなるだろう」とか「大丈夫だよ」という楽観的な雰囲気が、まるで噛み合っていない奇妙な8ケ月だったといえるようです。
そして始まった「アジア最終予選」、年明けからずっと叫び続けてきた一部のサッカー関係者、ジャーナリストたちの懸念は3戦目にして現実のものとなりました。
そして4戦目、中央アジア・カザフスタンの地で唐突な監督交代劇が行われました。あとを引き継いだ岡田監督は、5戦目、6戦目と勝てない試合を続けたものの、少しづつチームを立て直し、ついに7戦目アウェーの韓国戦で勝利して上昇気流に乗り始めます。
「だからあれだけ言ったではないか」と叫び続けた一部のサッカー関係者、ジャーナリストたちは、日本サッカー協会の体質を強く指弾する一方で、岡田監督に対しても「経験のある監督ではない」という理由で「あとあとのことを考えてキチンとした監督にすべきだ」という論陣も張りました。
そういた声を尻目に、すっかり自信を取り戻した選手たちの本来の活躍で8戦目のカザフカタン戦を大勝、第3代表決定戦に駒を進めます。この頃になると岡田監督はもはや未経験の監督などではなく「そこいらの監督よりよほど自分のほうが考えに考え抜いている」と自信を持つほどの監督になっていて、第3代表決定戦のイラン戦も「絶対に勝つ」という不退転の気持ちで臨み、采配にも冴えをみせます。
そしてイラン戦の延長後半13分、歴史の扉が岡野雅行選手のVゴールによって開かれたのです。日本時間では深夜1時近くにもかかわらず、日本国中を歓喜の渦に包み込みミッションは達成されました。
「ワールドカップの招致」と「日本リーグのプロ化、その強化によるワールドカップへの出場」という二つの目標を掲げた日本サッカー界、11年目にして「ワールドカップへの出場」という二つ目の目標も達成されたのです。
1986年から「世界を追いかけ始め、いずれは世界に追いつき、いずれは世界を追い越すんだ」と走り続けてきた日本サッカー。「ジョホールバルの歓喜」は、ついに「日本サッカーが世界に追いついた」瞬間でした。
加茂監督は、年の初めからずっと「このままでは(W杯出場は)危ない」と言い続けられ、結局アジア最終予選のさなかに加茂監督がただ一人だけチームを去り、加茂監督が残した岡田コーチ以下スタッフ・選手たち全員によって達成された、世にも稀な偉業でした。
かつて日本中がこれほど喜びに沸いたことがあっただろうかと思えるほどの一体感に包まれた深夜から翌日でしたが、それは、そこまでの過酷な道のりを日本中が共有したからに他なりませんでした。サッカーワールドカップへの出場権を得るということが、これほどまでに過酷な道のりであることを日本中が初めて知った年だったのです。
それは「アジア最終予選」の73日間、サッカージャーナリストやサッカー解説者、フォトカメラマンなどの表現者たちが昼夜を分かたずペンを走らせ、シャッターを切り続け現像作業に没頭してくれて情報を全国隅々まで届けてくれたおかげであり、日本代表サポーターという表現者たちがスタジアムの中であらん限りの智恵を絞り試行錯誤を繰り返しながら応援を続けてきた様子をテレビ画面や冊子などの報道を通じて知り得たからです。
それはまさに1993年に萌芽した「日本のサッカー文化」の芽が年を経てつぼみとなって膨らんでいたものが、この73日間を通じて3輪、5輪と開花したかのようでした。
このあと毎年毎年、サッカージャーナリスト、フォトカメラマン、テレビ関係者、作家、タレントたちの活動は賑やかになり、年を追うごとに百花繚乱の様相を呈していきます。またサポーターたちや一般のサッカーファンも次々と思い思いのやり方で「サッカー文化」の花を咲かせていきます。
1997年は後年おそらく「日本のサッカー文化の開花宣言の年」と位置づけられるのではないかと思います。
その一方で、サッカーというスポーツに人々がのめり込み過ぎると起きてしまう怖さというものも、この年、日本が初めて味わったと言えます。これまで海外で、例えば代表選手がワールドカップの試合でミスをしたことを咎められて帰国してから射殺されてしまう例(コロンビア・エスコバル選手)などの出来事が伝えられてはいましたが、今年のアジア最終予選では、途中から指揮をとった岡田監督に対して脅迫電話や不審な郵便物が届くなどの異常事態が起きたことから、岡田監督の住宅と家族に警護が付けられたり、第3代表決定戦の時、選手たちが「もし負けたら日本にまともに帰れるのだろうか」と考えてしまうほどのブレッシャーにさらされました。
「サッカー文化」の花開く華やかさの反面、そうした怖さを持つのが「サッカー」の魔力とも言えます。
岡田監督は来年のフランスW杯本番の指揮を執ることが決まり、12月には本大会の組み合わせ抽選の結果、アルゼンチン、クロアチア、ジャマイカとグループリーグを戦うことが決まりました。日本代表は新しい年、新しい時代に突入することになったのです。
日本代表が主役だった1997年ですが、Jリーグにとっても変化の大きな年でした。Jリーグスタート前から日本サッカーを牽引してきてJリーグスタート時の盟主だったヴェルディ川崎が、この年元旦の天皇杯を制したとはいえ凋落の道を辿り始めました。
代わって1996年に初めて年間王者に輝いた鹿島アントラーズが、本物の強さを身に付け始め前期優勝とナビスコカップ初優勝を達成、次の盟主に名乗りをあげました。
1994年にJリーグ入りしたジュビロ磐田が、Jリーグスタート時の10チーム以外で初めて後期優勝を果たし、余勢をかって年間王者にも輝き、鹿島・磐田2強時代が始まった年でした。
一方では一部クラブの経営的な問題も表面化してきました。1月には横浜F・前園真聖選手をめぐってクラブが不誠実な対応に終始していたことが明るみに出て批判を浴びました。横浜Fは翌年不幸な事態に陥りますが、前園選手への対応あたりから根深い問題を抱えていたことになります。
清水エスパルスは年後半に経営状態の悪化が表面化して、あらたな対応が必要になってきましたし、ヴ川崎の親会社・読売新聞渡邊社長や、市原の親会社・JR東日本松田社長の発言なども世間を賑わせることとなりました。
Jリーグは1999年からJ1,J2リーグ体制となることが決まっていますが、J2に参加する9クラブが決まりました。現在の2部リーグにあたるJFL(ジャパンフットボールリーグ)ではコンサドーレ札幌が優勝、来期のJリーグ昇格を決めました。
Jリーグの選手の活躍ではエムボマ選手とドゥンガ選手の活躍が特筆されます。
カメルーン代表のエムボマ選手、G大阪に加入すると、いきなり開幕戦、衝撃のスーパーゴールを決めて日本のサッカーファンに強烈な挨拶をしました。その後も「浪速の黒豹」のニックネームと観客をどよめかせるプレーを連発、夏のオールスターゲームでも主役となる活躍で、最終的には得点王に輝いてシーズンを締めくくりました。
一方の磐田・ドゥンガ選手、エムボマ選手のような衝撃的なプレーで魅せるのではなく、常にチームを鼓舞し、必要とあらばピッチ上で若い選手を揺さぶりながら教えることも厭わない情熱でファイティングスピリットを注入していきました。
そして今シーズン後期、初優勝を果たすと余勢をかって年間王者も制覇するという躍進に導き、自身もJリーグMVPに輝きました。
日本人選手では必然的に、日本代表選手に注目が集まった年と言えます。とりわけ中田英寿選手は日本がワールドカップ出場を決めたイラン戦で、すべての得点に絡んだということで中心選手の座を不動のものにしました。その結果、12月のワールドカップ抽選会記念試合に日本から唯一招待され、その試合でも世界のスーパースターたちの中で堂々たるプレーを披露して、さらに評価を高めました。
また岡野雅行選手はイラン戦のVゴールを決め、一躍国民的ヒーローになりました。代表選手では川口能活選手、城彰二選手のアトランタ五輪代表組や日本に帰化して参戦した呂比須ワグナー選手も注目を集めました。
一方ではこれまでの日本代表を牽引して絶対的エースと呼ばれていたカズ・三浦知良選手が「アジア最終予選」の初戦の4ゴールを最後にゴールから遠ざかってしまい苦しみました。日本がワールドカップ出場を決めたイラン戦で途中交代によりピッチをあとにしたことが、カズ・三浦知良選手の時代の終焉を象徴しているようでした。
日本人選手では、新時代を担っていくであろう若手選手の活躍も話題になりました。G大阪の稲本潤一選手は、3月のナビスコカップでJリーグ公式戦最年少記録となる出場を果たし、4月のJリーグ前期第3節では、Jリーグ最年少ゴール記録を達成しました。
また横浜Mのルーキー・中村俊輔選手はJリーグ前期4節でチームの全ゴールに絡む3アシストを記録すると6節には得意のFKからJリーグ初ゴールを記録するなど、すっかりチームの司令塔に定着、その自信を手に臨んだ6月のワールドユース選手権でもチームのベスト8進出に貢献する活躍を見せました。
そうした日本人選手の活躍の一方、これまでJリーグを沸かせてきたスター外国人選手の退団もありました。前期シーズンが始まって早々、磐田のスキラッチ選手はケガのため離脱すると、そのまま帰国、引退となりました。1995年シーズンには得点王争いに絡み、最後は惜しくも福田正博選手にかわされましたが「イタリアW杯得点王」の名に恥じない活躍でした。
また浦和のブッフバルト選手も今シーズン終了をもって退団しました。ブッフバルト選手は1994年シーズン後期から3シーズン半、それまで低迷にあえいでいた浦和の守備陣を率いて奮闘、激しい闘志を前面に出しながらもクリーンなプレーぶりは浦和サポーターのみならず日本の多くのサッカーファンを魅了しました。
そして年とともにチームを強豪チームに生まれ変わらせた功績は、その誠実で温厚な人柄とともに、その後も長く愛され続けることになり、後年、浦和の監督として帰還したことはご存じのとおりです。
男子日本代表のワールドカップ初出場達成に日本中が沸いた中、ユースカテゴリーや女子も着実な成果をあげました。男子ユース代表は、ワールドユース2大会連続ベスト8、女子代表は3大会連続世界女子サッカー選手権(1999年開催)出場権獲得という快挙を成し遂げたのです。
前年、2002年日韓W杯共催が決まった中、それに向けたハード・ソフト面の準備が着実に進んだのも今年のニュースでした。
7月には、福島県沿岸に東京電力㈱が整備した総面積49haに及ぶ広大な敷地を持つ、日本初のナショナルトレーニングセンター「Jヴィレッジ」がオープンしました。全部で8面もの天然芝サッカーコートや宿泊施設、研修施設など各種サッカーに関する育成・研修に使われるだけでなく、さまざまな競技のトレーニングにも使用できる一大スポーツトレーニング施設が誕生したのです。
11月には横浜に建設中の日本最大のスタジアム「横浜国際競技場」をFIFA(国際サッカー連盟)の幹部たちが視察に訪れました。のちに2002年W杯の決勝スタジアムとなったことはご存じのとおりです。
その2002年W杯、日本における実施主体となる組織「財団法人2002年FIFAワールドカップサッカー日本組織委員会」が12月スタートしました。
このように1997年は、日本サッカーの大きな前進の年でした。
長年の悲願だったワールドカップ出場権を初めて勝ち取った歴史的な年であり、その闘いを通じて日本に『サッカー文化』の花がつぼみから3輪、5輪花が咲き始めた年でもあります。
また2002年W杯に向けた準備もハード・ソフト両面で進んだ年です。
来たる1998年は「世界に追いついた日本」がフランスW杯という世界の舞台に初めて立つ年です。果たしてこの年もまた「伝説の年」となるのか、ひも解いていきたいと思います。