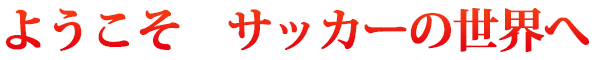現在につながる世界のサッカー、日本のサッカーの伝説の年は、まず1986年、そして1992年、1993年、1994年、1996年、1997年、1998年、1999年、2000年、2002年、2004年、さらに2010年、2011年、2012年、2018年、2022年、
実に多くの伝説に満ちた年があったのです。
それらは「伝説のあの年」として長く長く語り継がれることでしょう。
さぁ、順次、ひもといてみましょう。
伝説のあの年 1998年
1998年は、いよいよ日本サッカーにとって史上初の参加となるFIFAワールドカップフランス大会の年です。前年、日本中を巻き込んで艱難辛苦の末に自力で出場権を勝ち取った日本が、未知の舞台でどれだけの戦いができるのか、この年の前半はそのことでもちきりでした。
ですから、この年の後半がどのような日本サッカーの世界になるのか、あまり考えもせずに新しい年を迎えたのですが、実はこの年も1年を通してみると、かなり起伏に富んだ、前年とは違った意味で「伝説の年」になりました。さぁ、ひもといていきます。
元旦スポーツ紙、5紙が「W杯イヤー特集」を1面トップに、3紙がさらに別冊W杯特集で新年を飾る
年が明け元日、まず度肝を抜かれたのがスポーツ紙の1面トップ記事でした。日刊スポーツ、スポーツニッポン、スポーツ報知、サンケイスポーツ、デイリースポーツの5紙が「W杯イヤー特集」を組んだのです。岡田監督、中田英寿選手、城彰二選手らの写真をあしらって、それぞれ特集企画を打ちました。
さらにスポーツニッポン、スポーツ報知、サンケイスポーツの2紙は別冊でもW杯特集を組むという熱の入れようで、通常版と別冊版の合計のページ数は25ページに及ぶ量でした。いやが上にも今年がサッカーワールドップの年であることを印象づけました。
あれ? 何これ? と思ってしまう異色記事
こうした新年企画記事の中に、ちょっと異色の企画、異色の記事がありました。朝日新聞が元日からの新年企画で「現代奇人伝」という数日間の連載企画を打ったのです。その3回目、1月4日に中田英寿選手が取り上げられました。タイトルは「疾走する孤高の20歳『君が代』は歌わない」(このタイトルは東京本社版のタイトルのようで、大阪地域などでは若干違っている可能性があるようです)
記事はこの連載企画を担当している記者が中田選手にインタビューした内容に基づいているのですが「中田英寿選手はなぜ『君が代』を歌わないのだろうか」という、日本人にとってはセンシティブ(個人の信条やプライバシーにかかわるデリケート)なことに切り込んでいました。
この記事に関するインタビューは前年11月に行われていたようで、記者が「日本がワールドカップ出場を決めたマレーシア・ジョホールバルでの試合、テレビに流れた両国の国歌吹奏の場面、君が代が流れた時、中田選手は歌ってませんでしたね」とでも聞いたのでしょうか。
中田選手が「国歌、ダサイですね。気分が落ちていくでしょ。戦う前に歌う歌じゃない」と答えました。
記事は、特に中田選手が国歌を重んじないことに焦点をあてたものではなく、他のサッカー選手とはかなり毛色の違う、それでいてチームの中心選手である中田選手の人物像を浮き彫りにしようとする意図だったでしょうけれど、タイトルに「『君が代』は歌わない」とつけ「国歌、ダサイですね・・・・」というコメントを引き出して掲載すれば、企画の意図とはまったく違った受け止めをする読者が一定数出てくることは明白です。
日本代表選手の中で、ただ一人歌わずに目立っているわけではなく、他の選手の中にもいるように、中田選手自身も「国歌吹奏」を聞きながら気持ちの集中を高めているだけなのですが、「国歌、ダサイですね・・」などと言わなくてもいいことを言ってしまい、誤解の火に油を注ぐことになってしまいます。
この記事が、のちに中田選手の足を引っ張ることにならなければいいが、と思わせる記事でした。
天皇杯決勝は鹿島vs横浜F 3-0で鹿島完勝、前年のナビスコと合わせて二冠、全国高校サッカーは雪の国立、伝説の名勝負の末、東福岡が帝京を下し高校三冠達成
元日の第77回天皇杯サッカー決勝に駒を進めたのは、準決勝で磐田を3-2で逆転した横浜Fと、JFL・東京ガスを退けた鹿島でした。
準決勝で敗退した磐田は11月下旬からナビスコカップ決勝2試合、12月にJリーグチャンピオンシップ2試合、そして天皇杯と休みなしの連戦続きで疲労困憊の末力尽きた感がありました。一方の鹿島も磐田と同じ条件でしたが準決勝の相手がJFLの東京ガスということで、いわば格の違いを見せつけました。この年の東京ガスは、3回戦から名古屋、横浜M、平塚とJリーグ勢を撃破して準決勝まで進出、話題をさらったチームでしたが鹿島は3-1で退け決勝に進出しました。
決勝は鹿島vs横浜Fで争われました。約4万8000人の大観衆が詰めかけた国立競技場で躍動したのは、ビスマルク、ジョルジーニョのブラジルコンビと、秋田豊選手を中心とする日本代表4人衆、そして柳沢敦選手、増田忠俊選手といった若手が融合した鹿島でした。試合は3-0で鹿島の完勝でした。
4年前の第73回大会決勝では、加茂監督率いる横浜Fに屈した鹿島、その雪辱を果たして天皇杯初制覇、これでJリーグ三大タイトルをそれぞれ1回ずつ獲得、通算3冠目となりました。
第76回高校サッカーは「ここから、夢が始まる」の大会キャッチフレーズのもと、全国4118校、本大会出場48校の頂点を目指して1月8日決勝が行なわれ、東京・帝京と福岡・東福岡という名門校対新興校の対戦となりました。
東福岡は初優勝を目指す新興校とはいえ、前年夏の高校総体サッカーと全日本ユース選手権を制覇しており、この決勝は史上(全日本ユースがタイトルに加わってから)初の高校三冠に王手をかけた戦いという点でも注目でしたし、帝京は高校総体決勝で敗れている雪辱を期しての戦いという、まさにこの年の高校サッカー界の頂上決戦にふさわしいカードとなったのです。
当日は、午前中から雪が降り始め、試合が始まる頃はまさに降りしきる雪上の戦い、ピッチは降り積もった雪のため真っ白となり境目を示すラインもまったく見えなくなり、カラーボールが使用されての試合となりました。
通常、これでけの雪の中の試合となると、なかなかボールコントロールがままならず、いきおて蹴り合いに終始する試合になりがちですが、この決勝は違っていました。両チームとも不自由なボールさばきにもかかわらず、パスでつなごうという意識を高く保ったまま試合が続きました。
試合はインターハイの雪辱に燃える帝京が「夏以降、東福岡を意識してチーム作りをしてきた」という小沼監督の対策が功を奏し先制、しかし東福岡は前半のうちに同点に追いつくと、早くも前半29分、この大会ケガの影響で出番の少なかった古賀誠史選手と青柳雅裕選手を投入、帝京の作戦を意識して修正を図りました。
そして後半、雪は相変わらず降り続きますが、試合開始直後ほどの勢いはなくなりました。ピッチのうちペナルティエリアの部分だけは雪かきにより少し芝が見える程度になりましたが、雪が固まってきた分、ボールコントロールの難しさは増したことと思います。
その中で東福岡はエース・本山雅志選手をトップにあげ、タメを効かせて中盤の押し上げを待つ作戦が功を奏し、後半5分、本山選手のボールキープを見た途中出場の青柳雅裕選手が走り込み、それに合わせるように本山雅志選手がラストパス、青柳選手が鮮やかに帝京ゴールを陥れました。
雪のハンディをまったく感じさせない2人の見事なボールコントロールで生まれたゴールでした。
試合はその後、ボールの蹴り合いが徐々に増えてきましたが、お互い堅守を維持して時間が経過、帝京は長身の貞富信宏選手を投入して打開を図りますが、東福岡の粘り強い守備を崩せず、試合はそのまま終了のホイッスル。東福岡が選手権初優勝と高校三冠達成という偉業を成し遂げました。
東福岡の志波芳則監督は、準決勝3度目の挑戦で初めて決勝に進んでの初優勝ということで「悲願の」といった枕詞がつきそうなところでしたが、この年のメンバーであれば高校三冠ができるという思いが強かっただけに、むしろホッとした様子で大会を振り返りました。
この年の東福岡高校は、10番をつける司令塔の本山雅志選手を中心に、両サイドに古賀誠史選手と古賀大三選手の快速古賀コンビ、中盤に宮崎啓太選手、DFの中心に手島和希選手といった3年生の核になる選手に加えて、2年生のMF宮原裕司選手、DFの2年生コンビ、金古聖司選手、千代反田充選手といった3年生と同等の力を持った選手がレギュラーを占めており、大会参加校の中でもずば抜けた布陣を持っており「なっとくの高校三冠」でシーズンを完結させました。
帝京高校は夏のインターハイに続いて東福岡に屈し、この年は引き立て役に回ったことになります。
とはいえ、本降りの雪の中のハイレベルな決勝戦は、長い高校サッカーの歴史における名勝負として刻まれる試合となり、この年の東福岡、帝京のイレブンは長く語り継がれるメンバーになったことも確かです。
また決勝を戦った東福岡・本山雅志選手、帝京・中田浩二選手の両キャプテンが揃って鹿島アントラーズに入団することになったことでも話題になりました。
この大会は、東福岡の3年生メンバーをはじめ多くの逸材が揃った大会でした。この大会の主な出場選手と進路
FW 木島良輔(帝京→横浜M)
MF 本山雅志(東福岡→鹿島)、中田浩二(帝京→鹿島)、小笠原満男(大船渡→鹿島)、遠藤保仁(鹿児島実→横浜F)、古賀誠史(東福岡→横浜M)、加地亮(滝川二→C大阪)
DF 手島和希(東福岡→横浜F)
2年生以下
宮原裕司(東福岡)、金古聖司(東福岡)、千代反田充(東福岡)
大所帯になっていく「2002年FIFAワールドカップサッカー日本組織委員会」事務局、古参のメンバーが感じる寂寥感
前年12月に発足した「財団法人2002年FIFAワールドカップサッカー日本組織委員会」は、1月16日、東京・赤坂プリンスホテルで盛大な設立記念パーティを開催しました。
1986年、日本サッカー協会で村田忠男氏が単騎活動を始めてから12年、村田氏がいろいろな人から「あんた何やってるの?」と問い返された日々は過去のものになり、いまやサッカー、そしてワールドカップは、日本代表も初出場を決めたとあって、国民的関心事にまで高まってきました。
これから進める2002年開催までの準備を担う事務局体制も、これまでとはまったく異なり、出入国管理(ビザの発給)や税関、外貨交換に至るまで、いわゆる「ワールドカップ開催対策仕様」の体制となりました。これまで関わってきたサッカー界の関係者、広告代理店の出向者などに加え、関係省庁、開催自治体などを含めた混成部隊、しかも身分、肩書もそれぞれ違う人たちの集団で持っている思惑もまるで違うという人たちの寄り合い所帯になったのです。
特に、ビザの発給や税関、外貨交換などの準備や手続きは所管官庁にとっては「これは自分たちの仕事、サッカー関係者の余計な口出しはご無用」といった感覚が強く「組織委員会事務局」といった一体感とは名ばかりの空気になり、それ以前の「招致委員会」時代から関わっているメンバーにとっては、一つの目的に向かって力を合わせて邁進してきた気持ちのやり場がなくなってしまう寂寥感を覚える状況が生まれました。
ある意味「モチベーション」とか「やりがい」といったプラスアルファの気持ちなど無用、ドライな実務処理能力だけが求められる段階に差し掛かってきたのを、以前からの古参のメンバーは、なかなか受け入れられない時期が半年ぐらい続いたようです。
いよいよ日本代表サバイバルスタート、まずはダイナスティカップ98、岡田ジャパン日本、大会3連覇も収穫に乏しい大会、しかしFWの序列に決定的な差が出た大会?
3月1日からダイナスティカップ98が日本を会場に開催され、それに先立ち1月16日、日本代表候補29人が発表されました。
この中で目を引いたのが初招集のうちGKを除く3選手でした。鹿島・柳沢敦選手、増田忠俊選手、横浜M・中村俊輔選手、特に中村俊輔選手は、いずれはと思われていたものの、この段階ではまだだろうと見られていた中での招集でした。
岡田監督の「一人でも多くの有望選手を見てみたい」という気持ちの表れでした。
29人は1月24日からの宮崎キャンプに参加、続いて2月8日からの豪州キャンプを経て、3月1日からのダイナスティカップ98に臨む20人に絞られました。初招集の3人のうち中村俊輔選手は、豪州キャンプ序盤に肉離れを起こしてしまい離脱、アピールの機会がないまま選外となり、20人の枠に残れたのは増田忠俊選手(鹿島)だけで、さっそくサバイバルの洗礼を浴びることになりました。
ダイナスティカップ98は、日本のほか韓国、中国、香港の4チームによる総当たり戦で、日本は初戦が3月1日の韓国戦、スタジアム開きとなる横浜国際競技場での試合でした。韓国は洪明甫選手をはじめ主力数人を欠いての戦でした。
当日は雪交じりの雨と冷たい風という悪いコンディションでしたが、こけら落としのスタジアムを見たいという59,380人もの観客が詰めかけました。
ワールドカップイヤー最初の公式戦、しかも宿敵・韓国との試合、注目のスタメン、特にFWは中山雅史選手と城彰二選手の2トップでした。カズ・三浦知良選手と呂比須選手はベンチスタートとなりました。中盤は直近の豪州戦で退場処分を受けて、国際Aマッチ出場停止の山口素弘選手に代わり服部年宏選手、DF陣は4バック、もう一つの注目はGKに楢崎正剛選手を起用したことでした。岡田監督は「ワールドカップ本番で守りに回る時間が長くなった時、ハイボールに強くゴールマウスを背負った処理に安定感を見せる楢崎正剛も選択肢に入れておきたい」と狙いを語りました。
試合は前半18分、右からのCKを名波浩選手が左足で鋭くニアサイドに蹴り込むと、そこに走り込んだ中山雅史選手がドンピシャのヘッドで先制、このゴールは横浜国際競技場の記念すべき初ゴールとなり「何かを持ってる中山雅史選手の1998年」を予感させるゴールとなりました。
このゴール、明らかに名波選手と中山雅史選手の磐田ホットラインによるコンビブレーです。前年のアジア最終予選・第8戦カザフスタン戦、中山選手にゴールを取らせんがために何度もCKを送り続けた名波選手ですが、これだけ精度の高いコンビプレーが出来ると磐田での試合のみならず代表でもかなり威力を発揮するのではないかと思わせるゴールでした。
その3分後、日本は同点にされますが、試合は日本は名波、中田、服部の中盤のテンポの良いボール回しから何度かチャンスを作りペースを握り続けます。
しかし、これまで同様、作るチャンスを活かしきれない日本、ようやく後半44分、これも右からの名波浩選手のCKを今度は城彰二選手がヘッドで合わせ勝ち越し、2-1で韓国を下しました。
これで前年のアジア最終予選第7戦、蚕室スタジアムでの勝利に続き韓国に連勝、今回もキーマン・洪明甫選手を欠いての勝利とはいえ、少しづつ日本に韓国コンプレックスがなくなったことを、何よりも選手たちが実感したようでした。
この試合、FW陣のうちカズ・三浦知良選手と呂比須選手は最後まで出番がありませんでした。特にカズ・三浦知良選手は、前年のアジア最終予選第3代表決定戦で後半途中交代で退いて以来、今回も大事な韓国戦でも出番なしとなり、明らかな変化と言える出来事でした。
この時は誰も気に留めなかったと思いますが、この試合は、岡田監督に決定的な決意をもたらした可能性があります。
すなわち「FWの柱は城、序列的に次に中山か呂比須、カズは4番手」
やはり、この大会最大の宿敵韓国を下す決勝ゴールをあげた城彰二選手に対する期待度は、少なくとも岡田監督の中では確かなものになったことでしょう。
ダイナスティカップ第2戦は香港選抜との試合、中田英寿選手の2ゴールなど5-1で圧勝、この試合、カズ・三浦知良選手は後半31分からの出場でした。この日も会場は横浜国際総合競技場、詰めかけた50,743人の観客からは交代出場のカズ・三浦知良選手がコールされると場内からは割れんばかりの「カズコール」が起きました。
第3戦は中国戦、会場を国立競技場に移し53,226人の観客が見守る中、日本は3ボランチという守備重視の布陣を敷き、ボールを奪って速攻カウンターで点を奪うというシナリオを描きました。しかし結果は0-2の完敗、岡田監督が前年10月にW杯アジア最終予選の途中から日本代表監督に就任して以来、13試合目にして初黒星という結果となりました。
カズ・三浦知良選手と中山雅史選手の2トップ、トップ下に中田英寿選手という前線は、中田英寿選手が効果的なパスを出せずドリブル突破を試みるも潰される攻撃で沈黙、カズ・三浦知良選手は後半12分に城彰二選手と交代、中山雅史選手も後半16分に岡野雅行選手と交代しました。
大会は2勝1敗で日本と中国が並びましたが得失点差で日本が優勝、この大会3連覇となりましたが、日本イレブンにはまったく笑顔のない表彰式となりました。
馳星周氏、村上龍氏、W杯日本代表を論じるサッカージャーナリスト陣に参戦「サッカー文化」に新たな文化人が新風
98.3月26日号Number440号は「日本サッカー 決戦へのプロローグ」と題してサッカー特集号となりましたが、その号に作家の馳星周氏と村上龍氏が揃って「特別寄稿」を寄せました。
前年の「W杯アジア最終予選」を多角的に論じる形で、さまざまな分野の人たちが雑誌、テレビ等で発言し「日本のサッカー文化」の花のつぼみが開く一翼を担いましたが、年が明けて、その動きが加速しました。
村上龍氏は、元日のスポーツニッポン紙にも1面に「W杯とスポーツ紙の役割」と題して寄稿しており、いわば本格参戦に向けて年賀状がわりでした。
Jリーグは18チームによる前期、後期1回戦総当たり方式で実施、日程も前期は5月上旬から7月下旬まで「フランスワールドカップ」による中断の長いシーズンに
前年17チームという変則方式だったJリーグに、JFLからコンサドーレ札幌が昇格加入して、この年は18クラブによる前後期2シーズン制で行われることになりました。
10クラブでスタートしたJリーグも6年目にして最多の18クラブ、翌年からはJ1,J2制移行により、J1が16クラブに減るため、この年が最初で最後の最多クラブという点で注目の年であると同時に、初の入れ替え戦にあたる「Jリーグ参入決定戦」が行われ、残留サバイバルの年になるという新たな注目点も生まれました。
日程は前期が3月21日開幕、8月8日最終節、後期が8月22日開幕、11月14日最終節ということになりました。レギュラーシーズン終了後、J1参入決定戦が11月19日から12月5日まで行われ、前後期優勝チームが年間王者を争うJリーグチャンピオンシップが第1戦11月21日、第2戦11月28日の日程となりました。
前期の日程では、日本代表が史上初の出場となる「FIFAフランスワールドカップ98」への準備を含めて5月9日の12節で一旦中断、ワールドカップ終了後、7月25日の13節から再開、8月8日最終17節という異例の設定となりました。
Jリーグチームの中で新監督は、浦和・原博実監督、ヴ川崎・ニカノール監督、横浜F・レシャック監督、磐田・バウミール監督、名古屋・田中孝司監督、京都・ハンスオフト監督、G大阪・コンシリア監督(5月アントネッティ監督就任までの暫定)、C大阪・松木安太郎監督、神戸・フローロ監督、福岡・森孝慈監督の10人、新監督の多い年といえます。ちなみに日本人監督は、柏・西野監督、浦和・原博実監督、平塚・植木監督、名古屋・田中孝司監督、C大阪・松木安太郎監督、福岡・森孝慈監督の6人で、こちらも近年の中では多い年となりました。
Jリーグ監督の中で記憶に留めておきたいのは清水・アルディレス監督の契約更新です。清水は前年暮れにクラブの大きな赤字経営が明らかとなり、筆頭株主の㈱テレビ静岡が撤退、経営危機が表面化していました。そのためサポーターたちが中心となって31万人を超える署名と1500万円の募金を集めるとともに、新たな出資企業の呼びかけを行ないました。
その結果、新年になって地元物流大手の㈱鈴与が、子会社を通じて増資を行なうことを決定、これに、静岡鉄道㈱、静岡ガス㈱・㈱静岡新聞社・㈱小糸製作所が応じて、運営会社も株式会社エスパルスとして営業権を譲り受け、無事2月1日付で新たな経営がスタートすることになったのです。
アルディレス監督の契約更新は、ちょうどクラブの存続が危ぶまれる時期と重なったのですが「今、クラブを投げ出すわけにはいかない」と契約を延長したのでした。アルディレス監督ほどの知名度のある監督であれば、他に条件のいいオファーがあったであろうことは容易に想像がつきます。
清水エスパルスは、唯一の市民球団(全国レベルの規模を持つ大企業の出資会社がないクラブ)という、地域密着のJリーグ理念を体現するクラブだけに、この危機をサポーターを中心とした市民、地元企業そして監督の情熱で乗り越えたのです。
数十年に1人の逸材、小野伸二選手が浦和に入団、高原直泰選手は磐田、G大阪・稲本潤一選手も含めてプロの舞台に勢揃い
この年の新加入選手を見ていくと、有望高卒新人豊作の年という特徴があります。
有望高卒新人の代表格が、浦和に清水商から加入した小野伸二選手です。1月の高校選手権のところで名前が出なかったとおり、高校生活を通じて冬の高校選手権には縁がなかったことも、この人ならではの話題でした。
しかし選手としての可能性は専門家なら誰もが「10年に一度、あるいはそれ以上の逸材」と口を揃える選手で、多くのJリーグクラブが争奪戦を繰り広げました。
98.1.28号サッカーマガジン誌は、そんな彼を特集で扱えるのを待ち焦がれたような気持ちで巻頭から「王国の天才・ついに『彼』は現れた」という見出しを打って堂々5ページの特集を組みました。
そこでは、小野伸二選手がいかに凄い才能を持った期待の選手かを、さまざまな角度から紹介しました。そこから抜粋してみます。
「前年10月末、ちょうど日本代表がW杯アジア最終予選の戦いで苦戦しているさなか、大阪で開催された国体少年サッカー・準々決勝、静岡選抜vs北海道選抜戦で彼が見せたプレーに、思わず関係者の口から「まだ間に合う、いますぐ小野伸二を、次のアウェーでの韓国戦に連れていって欲しい」という声があがった。」
「(小野選手の母校)清水商には父兄やOBとは別に、部外者からなる『ベンチクラブ』というのがある。メンバーは試合の応援はもとより、しばしば普段の練習まで見学に訪れる。(中略)その一人、桜田さん(80歳)は、この10年、毎日のようにグラウンドに足を運んで選手たちの成長をつぶさに見守ってきた。その桜田さんが声を弾ませて言う。『名波を見たときには、こんな子は当分出てこないだろうなと思っていた。そうしたら伸二が現れた』
「(小野選手を獲得した浦和の)宮崎スカウトは確信めいて言う。『名波を超える逸材。10年に1人、いや、それ以上かもしれない』」
「1996年の秋(小野選手が2年生の時)、当時、市原のサテライトでヘッドコーチを務めていたヤン・フェルシュライエン現市原監督は、広島で行われた国体少年サッカーの部を初日から観戦して、静岡選抜の背番号8にクギ付けとなった。『ここ数年で私が見た若手の中では最高の選手、アヤックスのトップチームでもプレーできるはずだ』オランダ代表のオーフェルマルスをはじめ、数多くのトップブレーヤーを育ててきた若手育成のスペシャリストが舌を巻いたのだ。」
「(浦和の)宮崎スカウトが惚れ込んだのは、そのズバ抜けた視野の広さにある。『試合の流れを読んで、ゴールに直結したプレーができる子となると、小野は群を抜いている』」
「そうした視野の広さは独特の思考に支えられている。ボールをもらう前にまず考えるのは『遠くを見ること』だという。言い換えれば『もっともゴールに近い味方を探し出すこと』である。そうすることによって『近くも見ることができる』からだ。簡単な理屈である。」
「しかしそれを実際にグラウンドで表現するとなると、ことはそう簡単ではない。」
「パスコースは3つ持てとはよく言われるが、彼(小野選手)は5つも6つも持っている(宮崎スカウト)」
「まるでスタンドから眺めているかのような目線、それが高校生離れしたプレーの源になっているのだ。」
同誌の特集の極めつけは「才能では中田よりはるかに上」と見出しがついた清雲栄純ユース代表監督の談話です。小野伸二選手に対する期待を次のように語っています。
「高校時代の中田英寿(ベルマーレ)も良く知っているが、小野のほうがはるかに優れている。なかでも目を引くのは攻守の切り替えの早さ。守から攻はもちろん、相手ボールになってから、素早くディフェンスに移る動きは中田にはなかったもの。また大きな違いはボールを受ける時の体の向き。中田の場合、相手のゴールを背にしたまま、無造作にボールを受けることが多いが、小野の場合は常に半身の体勢でボールをもらい、相手のゴールを視野に入れている・・(以下略)」
ここまで、小野伸二選手のほうがはるかに上と書かれた内容を読むと、中田英寿選手も穏やかならぬ気持ちになるのではと思うほどの評価でした。
このあと、まもなく同誌の期待が実現する時が来ます。
高校時代に冬の選手権に縁がなかったといえば、この選手もそうでした。磐田に清水東から加入した高原直泰選手です。サッカー王国・静岡では全国大会で一つ勝つよりも県予選を突破するほうが難しいと言われている激戦ぶりを証明するような2人です。
この2人にG大阪のユースから一足先にトップチームでプレーしている稲本潤一選手を加えた3選手、いずれも冬の高校選手権に縁がなかった選手でありながら、このあとの日本サッカーを牽引していく存在となるという意味で、この年は象徴的な年といえるも知れません。少しミーハー的な言い方をすると、後年、この3人の世界を舞台にした活躍を定点観測的に追跡取材して、年に1回程度放送したフジテレビの「W杯をめぐる冒険」という番組があります。小野伸二選手、高原直泰選手、稲本潤一選手、冬の高校サッカー選手権に縁がなかった3人を取り上げているというのは、冬の高校サッカー選手権の主催テレビ局である日本テレビに何の気兼ねもなく番組を作れるというメリットがあったからではないでしょうか。
これも単に、当サイトがよくやる穿った見方かも知れませんが、一応、書き添えておきたいと思います。
ほかに、横浜Fには鹿児島実から遠藤保仁選手と東福岡から手島和希選手が、横浜Mには東福岡ら古賀誠史選手が入団します。
その中で、鹿島には本山雅志選手(東福岡)、中田浩二選手(帝京)、小笠原満男選手(大船渡)、山口武史選手(熊本・大津)、中村祥朗選手(奈良育英)の大挙5人入団します。前年のビスマルク選手、名良橋晃選手の獲得といい、クラブに必要だと思った選手は遠慮会釈なく獲得する鹿島の戦略を思い知るような補強です。
一方、大学出身者では磐田に順天堂大のFW川口信男選手、神戸に筑波大のFW和多田充寿選手と、駒沢大のMF三上和良選手が入団します。
Jリーグ開幕に先だって3月14日行なわれた恒例のゼロックススーパーカップ’98は、前年のリーグ覇者磐田と今年元旦の天皇杯決勝覇者鹿島、前年のチャンピオンシップを争ったチームの戦いとなりました。
試合は、鹿島がスーパーカップ2連覇で開幕に弾みをつけました。
ワールドカップ初出場のため中断はあるものの、98年Jリーグ前期、威勢よく開幕
3月21日、Jリーグ前期が開幕しました。この年の前期開幕は例年にも増して選手、クラブにとって重みの違う開幕となりました。
選手にとっては、迫りくるフランスワールドカップの日本代表選考が最終コーナーに差し掛かる中、中断までの12節が最後のアピールの機会となるからです。
クラブにとっては、翌年1999年から始まるJ1,J2、2部制のふるい分け順位を決める2年間の順位ポイントの2年目ということで、できるだけ、入れ替え戦対象順位になることを避けなければならないシーズンだからです。
開幕節、注目は2つのダービーマッチ(横浜Mvs横浜F戦、G大阪vsC大阪戦)、中田英寿選手の平塚vs前園真聖選手・カズ・三浦知良選手のヴ川崎戦、小野伸二選手のデビューとなった浦和vs市原戦、高原直泰選手のデビュー戦となった磐田vs京都戦など、いくつもありました。
中田英寿選手、ヴ川崎、前園真聖選手、カズ・三浦知良選手の前で、日本のエースにふさわしい活躍
もっとも試合時間が早く設定された、平塚のホームグラウンドで行われた平塚vsヴ川崎戦は、はからずも、いろいろな意味で話題になる試合でした。
開幕戦の最初の試合ということで、この会場では歌手の森進一さんがアカペラで「君が代独唱」しました。
この両チーム、1994年の開幕戦では昇格したばかりの平塚がJリーグ初代チャンピオンのヴ川崎に挑戦したものの5-1と大敗、スポーツ紙でセルジオ越後氏に「平塚のフロントは(昇格に向けた対策について)一体何をやっていたのか」とこっぴどく叩かれた屈辱の記憶がある試合でした。
その年、平塚のヘッドコーチをしていたニカノール氏が、ヴ川崎の監督に就任して初対戦の相手となったのも何かの因縁でしょう。
また、前園真聖選手にとっては、自分と入れ替わりで日本代表に招集され、そこから日本のエースと呼ばれる立場まで駆け上がった中田英寿選手と、新シーズン最初の試合で相まみえることになり、またカズ・三浦知良選手にとっても、アジア最終予選の第3代表決定戦で途中交代を命じられ、そのあと水を得た魚のように縦横にピッチを駆け巡り、岡野雅行選手のVゴールを演出、日本のエースの座を奪われた中田英寿選手との試合となりました。
意識するなと言われても意識したくなる絡みの試合となりました。
この試合を中継したNHKは「中田カメラ」という専用のカメラを用意、中田英寿選手の動きだけをとらえた画像を収録して、解説の木村和司さんをその画像を使って中田英寿選手の凄さを解説してもらう企画を組みました。
ちなみに、この試合、NHKが中継するJリーグ最初のゲームだったこともあり、放送のオープニングには「日本サッカーの夜明け」というタイトルを入れました。世界のサッカーの檜舞台、フランスW杯に初舞台を踏む今年は、日本サッカーの新たな夜明けが来たということなのでしょう。
日本代表・岡田監督が見守る中、中田英寿選手がリードを奪うゴールに相手を突き放すラストパス、そして圧巻は前半38分、相手CKからのボールを受けた中田選手は、左サイドライン際を持ち前のスピードで独走、約50mのドリブルを見せるなど大活躍、翌日のスポーツ紙も「日本の司令塔の貫禄」(東京中日スポーツ)と、まるで小野伸二選手を中田英寿選手との比較で絶賛した日本ユース代表・清雲栄純監督の談話(98.1.28号サッカーマガジン誌)を否定するかのような見出しを打ちました。
一方、ヴ川崎の前園真聖選手、カズ・三浦知良選手はコンビネーションがまだ不十分でいいところなく、試合は4-1で平塚が圧勝しました。
4年前の開幕戦の借りを返した平塚のメインスポンサー・フジタの藤田一憲社長は「4年前、ヴ川崎に完膚なきまで潰されたのを思うと夢のよう・・」と感極まった様子でした。
ヴ川崎の前園真聖選手とカズ・三浦知良選手、2人とも時代の容赦ない運命(さだめ)には抗うことができなかったのか、中田英寿選手の前に屈した試合でした。
小野伸二選手、日本代表・岡田監督の見守る中、トップ下でスタメンフル出場デビュー
浦和ホームで開催された浦和vs市原戦には平塚の試合を終えて移動してきた日本代表・岡田武史監督も視察に訪れました。
立錐の余地もないほどの観客(19,828人)で埋まった駒場スタジアムに、背番号28をつけた小野伸二選手の名前がコールされると、大歓声は一段と大きくなり地響きが起きんばかりになりました。
とはいえ、まだチームに合流して1ケ月、いかに小野伸二選手といえども、公式戦最初の試合から司令塔としてチームを牽引というわけには行きませんでした。トップ下のポジションでスタメン出場を果たしたものの、ペドロビッチ選手、ベギリスタイン選手といった外国人選手を含めて経験豊富な選手が揃う中盤の中で、やや遠慮がちな位置取りとプレーが見られ、小野選手自身も試合後に呼ばれた異例のインタビューで「今日は引き気味にプレーすることが多かった。次はもっと積極的に行きたいと思います」と語りました。試合は浦和が3-2で勝利、監督初采配となった浦和・原博実監督がうれしいスタートを切りました。
視察に来た岡田監督は「タレント(才能)を持ったいい選手だね」と言い残して会場をあとにしましたが1週間後の日本代表発表リストには小野伸二選手の名前がありました。
高原直泰選手は、高卒ルーキー開幕戦最速ゴール記録でデビュー
注目度では、中田英寿選手や小野伸二選手にはるかに及ばなかったものの、磐田のルーキー・高原直泰選手は開幕戦でいきなりゴールをあげ、その実力の片鱗を見せました。
1-0と磐田リードで迎えた後半25分、FWアレサンドロ選手に代わって投入された高原直泰選手、わずか3分後、藤田俊哉選手からの絶妙なパスを受けると相手DFと競り合いながら、難しい体勢から強引にシュート、ボールは見事ゴール右隅に突き刺さりました。
高卒ルーキーが開幕から出場わずか3分でのゴールは、1994年開幕戦でゴールをあげた城彰二選手の記録を上回る新記録というおまけ付きのゴールとなり、チームメイトから手洗い祝福を受け、磐田スタジアムも歓喜に包まれました。
それでも前年のJリーグチャンピオンチームは貪欲になっています。高原選手はそのあと守備をさぼったところをドゥンガ選手からキッチリと怒鳴られ、自身も追加点のゴールをモノにできなかった反省を口にしてプロ選手らしく初陣を飾りました。
このほか鹿島の柳沢敦選手も開幕戦ゴールでスタートを切るなど、Jリーグ新時代の到来を印象づける開幕節となりました。
昇格した札幌は、清水に4-1で敗れ、Jリーグの厳しい洗礼を浴びた形となりました。
このように注目のカードが多かったことが奏功したのか、開幕節9試合の平均観客数が19,030人と1993年、Jリーグ開幕年の5試合での平均観客数2万3,221人に次ぐ動員を記録、Jリーグ2年目以降、減り続けてきた開幕節の観客動員数に歯止めがかかりました。
フランスW杯への日本代表の初出場、小野伸二選手ら将来楽しみな選手たちのJリーグ入りで、まさに新たなファン層をスタジアムに引き付ける効果が期待できる結果となりました。
2節、ヴ川崎カズ・三浦知良選手、CKを直接決めて1-0の勝利に導き、浦和・小野伸二選手もうれしい初ゴール
2節、ヴ川崎は国立競技場に磐田を迎えました。試合は後半11分、ヴ川崎カズ・三浦知良選手が蹴ったCKを磐田GK大神選手がキャッチミスしてしまいゴールイン、開幕節のうっぷんを晴らす1-0の勝利に導きました。
浦和はアウェーの横浜F戦でしたが、0-1でリードした後半38分、小野伸二選手がゴール前、まったくフリーの状態で福永泰選手からのボールを受けると、あとはGK楢崎正剛選手との1対1、小野選手はまったくあわてることなく楢崎選手との間合いを詰めるとセオリー通り、楢崎選手の右脇を抜くように蹴り込み、うれしいJリーグ初ゴール、横浜Fを突き放す価値あるゴールとなりました。Jリーグの舞台でも高校時代と同じような自然体のプレーぶりは、横浜国際総合競技場の24,310人の観客とNHK-BSの中継を見ていた全国のファンを魅了しました。
4節、鹿島・柳沢敦選手、京都戦で4ゴール、4試合連続で早くも7得点のハイペース
4月1日の日本代表・日韓戦(共催記念試合・アウェー戦)をはさんで4節、鹿島・柳沢敦選手が京都戦で4ゴールの大暴れ、チームの6-0勝利の立役者となりました。柳沢選手はこれで開幕戦から4試合連続ゴール、合計7得点のハイペースで鹿島のエースストライカーの地位を固めつつあります。
4節、開幕以来3連敗で昇格後まだ勝利がない札幌は、4節にして初めて北海道の地でJリーグチームとして試合を行なう歴史的な日となりました。室蘭市入江競技場にG大阪を迎えての試合、後半23分に札幌のエース、テリー・バルデスがゴール、守ってはG大阪を零封して、うれしいJリーグ初勝利をあげました。
突然のように生まれた中山雅史選手の4試合連続ハットトリック、のちにギネス記録に認定
6節から9節にかけての4試合、とてつもない記録が生まれました。磐田の中山雅史選手が4試合連続ハットトリック、4試合合計で16ゴールをあげるという大記録を打ち立てたのです。この記録は、のちに世界のサッカー史でも初めてと認定され、1999年の「ギネスブック」に掲載されるほどの偉業でした。ちなみに1999年「ギネスブック」に掲載されることに決まった報せは、年末12月7日に行われたJリーグアウォーズの席上でした。
その16ゴールをつぶさに記録として残したいと思います。
中山雅史選手は、4日前の5節、横浜F戦で1ゴールをあげ、Jリーグ通算50ゴールを記録、チームも4-0で快勝して乗っている状態で迎えました。
4月15日、6節、アウェーC大阪戦、チームも9得点という記録的なゴールラッシュで9-1
1点目、前半39分、相手陣内左サイドでスローインを受けた名波浩選手がゴールライン際まで持ち上がり、得意の左足で速いクロスをゴール前に送ると、中山雅史選手が相手DFの間を抜け出すようにしながら、地面に着いた難しいバウンドのボールをピタリと右足で合わせてゴール。試合後、中山選手は「あれはロマーリオを意識したゴール」とお得意のゴン節で取材陣をけむに巻きましたが、まさしくそれは、1994年アメリカW杯準々決勝オランダ戦で、左サイドを駆け上がったベベトのクロス、難しいバウンドのボールを事もなげに合わせたロマーリオの先制点そのものの足技でした。
2点目、後半8分、センターサークル近くで得たFKをドゥンガ選手が、中山雅史選手のいた位置よりやや左外寄りに蹴り込むと、中山選手は間合いを図ってクルリとゴール方向へ身体の向きを変えボールをDFラインの裏に落とす頭脳的なプレーで、すばやくGKと1対1の状況を作り、GKの動きを冷静に見極めて頭上を抜くシュート、チームの山本コーチも絶賛のプレーでした。
3点目、後半13分、奥大介選手がペナルティエリア内で倒されPK、これを相手キーパーが右に飛ぶのをあざ笑うかのようにゴール正面にズドンと決めました。
4点目、後半25分、中山選手はペナルティエリアの外、ゴール右寄りでドゥンガ選手からのバスを受けると、手薄になっているゴール左寄りにドリブル、相手DFを振り切ってゴール左隅に蹴り込みました。
5点目、後半28分、ゴール正面、相手DFを十分惹きつけるようにしてボールをキープした藤田俊哉選手が右サイドでフリーで待ち受ける中山選手に余裕のラストパス、GKと1対1になってゴール右上隅に確実にゴールを決めました。
中山選手の5得点はJリーグで1試合最多得点のタイ記録(平塚・野口幸司選手、柏エジウソン選手に続く3人目)でしたが、この日チームは、奥大介選手が前半19分に先制ゴールをあげたのをはじめ、藤田俊哉選手が2ゴール、名波浩選手が後半37分、大花火大会の締めくくりとばかり1ゴールをあげて合計9ゴール、C大阪は森島寛晃選手が6試合連続ゴールをあげたものの、焼け石に水、磐田の1試合9得点は、その後も長く破られることのない記録となっています。
4月18日、7節、アウェー広島戦 0-5の完封勝利
1点目(4連続ハットの6点目)、前半11分、広島陣内右サイドで広島がクリアしようとしたボールに磐田サイドバック・古賀琢磨選手が反応、素早くオーバーラップの形で抜け出すと、寄せてきた相手DFを交わしてセンタリング、古賀選手と並走してゴール左側に上がっていた中山選手に渡り、古賀選手に引き付けられて相手GKが右ポスト側に寄っていたため、難なくゴールに蹴り込み先制。
2点目(4連続ハットの7点目)、後半19分、左サイドで服部選手が名波選手がパス交換したあとアレサンドロ選手にパス、それを見た名波選手がアレサンドロ選手の後ろから外側を回り込み、タメを作ったアレサンドロ選手が名波選手にパス、名波選手はゴールライン際まで走り込み、前節の先制点とまったく同じ左足で速いクロスを送ると、ゴール正面から中山選手がニアサイドに飛び込んでダイビングヘッド、ボールの軌道は見事に変わりゴールイン。
3点目(4連続ハットの8点目)、後半43分、アレサンドロ選手があげたクロスがCKとなり、左CKをドゥンガ選手が蹴りました。ボールは高くあがってファーサイドにいた中山選手に届きます。中山選手は相手DFに身体を寄せられることなく思い切りジャンプしてヘッド、広島GK下田崇選手が取ろうとした手をかすめてゴールに飛び込みました。
4点目(4連続ハットの9点目)、後半ロスタイム、最後尾でパスを受けた福西崇史選手が前線の中山選手めがけて縦パス1本、受けた中山選手はまたGKと1対1、相手DFがスライディングでカットしに来た直前、GKの位置を見極めて冷静に蹴り込みました。
中山選手の2試合連続ハットトリックはJリーグ元年の1993年、横浜Mのラモン・ディアス選手が記録して以来2人目の記録でしたが、この日チームは、後半26分、後半から投入されたアレサンドロ選手がゴールをあげて合計5ゴールをあげました。
守っては、後半27分にDFの要アジウソン選手がこの日2枚目のイエローカードを受けて退場、残り20分ほどを一人少ない中で広島を完封、終わってみれば0-5の圧勝でした。
4月25日、8節、アウェー福岡戦(会場・熊本) 1-7の勝利
1点目(4連続ハットの10点目)、後半8分、相手陣内左タッチライン際からのFKをドゥンガ選手が鋭くゴール前に送ると、ニアサイドで飛んだ福西崇史選手のヘッドをかすめる形になり、そのままファーサイドに流れると、そこで待っていたのが中山選手、ヘッドで押し込むとニアサイドをケアしていた相手GKも間に合わずゴール。
2点目(4連続ハットの11点目)、後半19分、奥大介選手からのパスを受けた中山選手、ボールを持ち出そうとするもミスしそうになったが、後ろから藤田俊哉選手がフォローに来たのを見てバックパス、藤田選手はその勢いでゴール右ポスト近くまで上がり、相手GKと1対1とみ見せかけて、ゴール正面にいた中山選手にマイナスのパス、中山選手は右足で難なくゴール。
3点目(4連続ハットの12点目)、前のゴールのあとも立て続けに2本のシュートチャンスをお膳立てしてもらいながら外していた後半28分、3度目の正直とばかり左サイドを突破した服部年宏選手がゴールライン際から得意の左足でマイナスのクロス、相手DFがクリアしようとダイビングヘッドを試みるも届かずボールは中山選手に、これを左足でかぶせるようにシュートすると、見事ゴール右隅に突き刺さりました。
4点目(4連続ハットの13点目)、後半44分、相手ゴール正面25mのところからドゥンガ選手が蹴ったFKは、相手DFとGKの間に落ちる絶妙のロビング、相手DFに当たったボールが目の前に来た中山選手はすかさず右足を一閃、文句なしのゴールとなりました。
この日チームは、前半19分、奥大介選手がヘディングゴールで先制、後半6分には名波浩選手がボレーシュートで2点目、後半34分にはドゥンガ選手がミドルシュート、中山選手の4点と合わせて合計7ゴール、福岡の攻撃を山下芳輝選手の1点に抑え大勝しました。
4月29日、9節、ホーム札幌戦 4-0の勝利
1点目(4連続ハットの14点目)、前半41分、相手ゴール正面約20mの位置で得たFkを蹴ったドゥンガ選手のボールは、DFにあたり相手GKディド選手がジャンプしてキープしようとしますがゴールラインを跨いでしまい右CKになりました。
それを、またドゥンガ選手が味方とサインを交わすこともなく、すぐにゴール前に放り込むと、ボールはゴール前にいた札幌のDFがクリアしましたが、頭をかすった程度になり、ファーサイドにいた田中誠選手のもとに届きます。迷わず田中選手は叩きつけるようなヘディングでゴール前に送ると、ボールは中山雅史選手のところで弾みました。これを、中山選手は身体をひねるように反転させながら右足でジャンピングボレー、ボールはバーを強く叩きゴールに吸い込まれました。
これまでの3試合連続ハットトリックはすべてアウェー戦、この日はホームに満員のサポーターを迎えての試合です。中山選手はさっそくサポーター席に走り寄り、お得意の右手を差し出して指さすパフォーマンスでゴールの喜びを分かち合いました。
スタンドでは日本代表・岡田監督も見つめていました。
2点目(4連続ハットの15点目)、後半27分、ペナルティエリアの外からドゥンガ選手が中山選手に送ったパスを札幌DF木山選手が先にキープしようとしたものの、ペナルティエリア外方向に中山選手が先にボールをつついた際、木山選手が右腕で中山選手を押し倒してしまいPKの判定、これを中山選手自身が左隅に蹴り込みました。相手GKディド選手もコースを読み飛びましたがコースとボールスピードが勝りPKは成功しました。
3点目(4連続ハットの16点目)、後半36分、センターサークルから15mほど相手陣内でボールを受けたドゥンガ選手はダイレクトで前線にパス、ボールは奥選手への見事なスルーパスとなりました。奥選手は一旦キープしますが相手DFが2枚寄せてきたと見るや、その後方から上がってきた中山選手にDFの間を抜くパス、これが「中山さん、どうぞ」というパスになり、中山選手は相手GKが右側のニアサイドをカバーするように飛んだのを見て、逆を突きファーサイドのサイドネットに突き刺すゴールを決めました。ラストパスを出した奥選手、藤田俊哉選手、奥選手にパスを出したドゥンガ選手が次々と祝福にやってきました。とうとう4試合連続ハットトリックという、とてつもない大記録を達成した瞬間でした。
この場面、ポイントはドゥンガ選手のダイレクトパスでした。この前の1分ぐらいの画面を見てみるとドゥンガ選手は、もう上下運動はせずに中盤でテクテク歩いてボールを動きを追っています。けれども、いざボールを受ける直前には2~3度奥選手の位置をチラ見しており、受けたボールを柔らかいタッチでダイレクトパスしています。まさに一瞬にして決定的な場面を作ったシーンでした。
後半35分も過ぎると、さすがのドゥンガ選手もせわしく動き回るのは苦になりますが、味方がボール支配しているゲームの流れを読んでいるからこそテクテク歩きしているわけで、その中でも常にチャンスの芽を見逃さない目配りだけは欠かしていないのです。
百戦錬磨、王国ブラジルのキャプテンの仕事ぶりをまざまざと見たシーンでした。
この日チームは、後半24分、奥大介選手のシュートがGKに弾かれてこぼれたところに詰めた藤田俊哉選手のゴールで合計4ゴールをあげました。
視察に来ていた日本代表・岡田監督は、次の試合会場に移動するため、中山選手がハットトリックを決めた時には会場を後にしていましたが、その知らせを聞くと「ワールドカップでもきっと点をとってくれるよ」と、中山当確ともとれるコメントを残しました。
中山雅史選手の連続試合ハットトリックは4試合で途切れますが合計16得点、その4試合の前後の試合でも1ゴールづつ決めており6試合連続合計18得点という考えられないようなゴールを決めています。それともう一つ、磐田がチーム全体としてあげた得点も、5節から9節までの5試合で合計29得点、これも歴史に残る大記録です。
中山雅史選手と磐田の大爆発、5つの要因
この中山雅史選手とチームの大爆発について、98.5.20サッカーマガジン誌が特集を組んで分析しました。同誌によると、
①中山選手の動きの質の向上、例えば、クロスが入ってきた時の飛び込むタイミングやスピードを調節している。これまでなら勢いだけで飛び込み、シュートをかえって難しくしていた。また、中山選手自身がパスの出し手にとって出しやすい位置にポジションをとることを常に意識しているため、ボールをもらった時、ダイレクトあるいはワンタッチでシュートできている。
②ゴールに向かう視野の確保の改善、磐田の山本昌邦ヘッドコーチが6節のC大阪戦の2点目を絶賛している。ドゥンガ選手の蹴ったFKを、中山選手は外に流れながら受けているが、これまでならゴールに背を向けたまま、外へ逃げるようにトラップすることが多かった(ゴールに向かう視野を狭めてしまっていた)が、この場面では、クルリとゴール方向に向きを変えボールが相手DF陣の裏に落ちるようにして、自分がGKと1対1の場面を作っている。
以上の2つ、動きの質の向上と視野の確保の仕方については、前年夏、山本昌邦ヘッドコーチが就任して以来、中山雅史選手に対してマンツーマンで指導した結果でした。中山雅史選手も、向上心という点では年齢に関係ない謙虚さで山本コーチの指導を受け入れた結果、飛躍的に改善されたのです。
③チームの布陣変更、4試合連続ハットトリックの幕開けとなった6節のC大阪戦、この試合から磐田は中山、アレサンドロの2トップから中山ワントップ、中山の後ろに奥大介選手を置く布陣に変更した。これにより中山選手の自由度が増し、奥選手のサポートが得られる効果も生まれた。さらに奥選手は好パスも出せる選手であることから、藤田、名波、奥とパスの出所が増えチャンスが増す。中山選手の得点が後半に多いのも、後半遅くなればなるほど相手選手が磐田のパスワークについていけなくなり、より正確なパスが中山選手に届くという効果も生んでいる。(4試合16点中の中山選手の後半得点は13点、チームの4試合25点中の後半得点は21点)
④コンディションを維持するフィジカルコーチの存在、2年前のオフト監督時代まではフィジカルコーチがいなかった磐田、昨年からブラジル代表でもフィジカルコーチ歴があるプリマコーチが、日本代表などで連戦が続く中山選手などのコンディション維持を担っていることも、身体のキレ、後半まで運動量の落ちない成果につながっている。
また、女優でタレント活動もしている(生田)智子夫人の栄養管理も見逃せない成果をあげている。
読めば納得のサッカーマガジン誌特集でしたが、もう一つサッカーマガジン誌の分析にはない理由を❺としてあげておきます。
❺それは、中山選手のゴールをお膳立てした選手の多さです。どういうことかと言いますと、中山選手の近い位置にいる攻撃的MFの選手のみならず、サイドバックの選手、ディフェンスの選手がこぞって中山選手のゴールをお膳立てしているのです。
4試合合計16ゴールをお膳立てした選手をもう一度ピックアップしてみます。
藤田選手、名波選手、奥大介選手、アレサンドロ選手、ドゥンガ選手、古賀琢磨選手、福西崇史選手、服部年宏選手、田中誠選手、実に9人です。
これは単なる偶然ではなく磐田というチームが「オレも中山さんのゴールをお膳立てしたい」「その仲間に加わりたい」という意識が強いチームだということの表れです。
中山選手はセンターフォワード、チームの点取り屋であるとともに、30歳です。ドゥンガ選手、アジウソン選手という外国人選手を除けば最年長でキャプテンも務めています。一般的なイメージからすれば「大黒柱イコール近寄りがたい存在」であってもおかしくないのですが、中山選手のいいところは、自分が決して技術的にうまい選手ではないことを自覚していて、その分、泥臭く最前線から相手を追い回したり、身体ごとゴールに飛び込むようなプレーを厭わずに続ける選手です。30歳を超えてなお向上心を持って居残り練習を続けている中山雅史選手をチームメイトは見てきています。
そしてサポーターからは「ナカヤマ隊長」と親しまれ、チームメイトからは「ゴンさん」と呼ばれるお調子もので、近寄りがたい存在とは真逆のキャラクターです。
それが、チームメイトを「チャンスがきたらゴンさんに点を取ってもらう」「自分もゴンさんのゴールのお膳立てがしたい」という気持ちにさせる原動力となっているのです。
その典型的な例が、前年11月のW杯アジア最終予選の第8戦カザフスタン戦でした。この試合、日本が早々と2点を先制しますが、久しぶりの招集となった中山雅史選手にはゴールが生まれていませんでした。それを見ていたチームメイトの名波浩選手は「このまま前半点がとれないと後半交代させられてしまうかも知れない」と考え、自分が蹴ることになっている右サイトからのCK、FKでは、全部中山選手めがけてキックを繰り出しています。
その結果、前半44分、ペナルティエリア右外側で得たFK、名波選手から中山選手にドンピシャのボールが渡り豪快にヘッドで叩き込むゴンゴールという形で結実しています。
いくらリードしているとはいえ、全部中山選手をめがけて蹴るというのは、いかにも名波選手らしい思考ですが、チームメイトの中山雅史選手という選手が、そうしたくなる選手だということの証左です。
同じことは、4試合連続ハットトリックの3試合目、福岡戦の3点目にも見られました。前のゴールのあとも立て続けに2本のシュートチャンスをお膳立てしてもらいながら外していた後半28分、それまでも繰り返し左サイドを突破していた服部年宏選手が「オレだって何としてもゴンゴールのお膳立てのメンツに入らなきゃ」と繰り出したクロスからのゴールでした。
この当時の磐田の雰囲気というのは「ゴンゴール」が飛び出せばチームは盛り上がり、チームメイトは誰もが、そのお膳立てのメンツに加わるために身を粉にして動き回るという珍しいチームだったことも、この、とてつもない大記録を生んだ要因であることを付け加えたいと思います。
その磐田、8節にチームは首位に浮上、10節にヴ川崎に首位を明け渡したものの、フランスW杯後の中断明けの前期、この時期の貯金がモノを言うことになりました。
森島寛晃選手が開幕から7試合連続ゴールのJリーグ新記録、9節には3選手がハットトリック達成のJリーグ新記録
開幕から9節までの間、他の選手にも記録が生まれました。
7節には、開幕戦から連続ゴールをあげていたC大阪の森島寛晃選手が、この日もヴ川崎戦でゴールをあげ7試合連続ゴールのJリーグ新記録を達成しました。8試合連続が期待された次の試合はノーゴールに終わり連続試合記録は途切れました。
9節には、ヴ川崎・高木琢也選手、浦和・大柴健二選手もハットトリックを達成、すでにご紹介した中山雅史選手と合わせ、この節だけで3人ハットトリック達成という新記録も生まれました。
10節、静岡ダービーで清水に敗れた磐田、開幕戦を落としたものの2節以降8勝1敗と快進撃を続けてきたヴ川崎に首位を明け渡しました。
11節、鹿島vs磐田戦、新・宿命のライバル対決、首位を走り6試合連続ゴールを続ける中山雅史擁するホーム磐田でしたが、試合は中山選手に負けじと柳沢敦選手がハットトリック、アウェー鹿島が3-0で快勝しました。しかし、柳沢選手は、この今季2度目のハットトリックの活躍にも関わらず、翌日発表されたフランスW杯日本代表最終候補25名からは外れてしまいました。
12節、W杯による中断前最後の試合、この節も清水・沢登正朗選手と札幌・バルデス選手がハットトリックを達成、開幕から12節で延べ15回のハットトリックが(うち中山雅史選手が4回)記録され、中断に入りました。
ここまでの12節、Jリーグは1994年をピークに前年まで徐々に観客動員を減らしてきましたが、ワールドカップに対する期待を背にした日本人選手の大活躍、小野伸二選手をはじめとした期待の10代選手の出現など新しい要因も加わり観客動員が上向きに転じました。
その中で、中山雅史選手の4試合連続ハットトリックなど、記録的な得点ラッシュも生まれサッカー人気再来ムードの中でワールドカップ本大会を迎えることになりました。
なお、この段階ではまだ移籍先が決まっていなかったため、まったく話題になりませんでしたが、フランスW杯終了後、中田英寿選手がイタリア・セリエAへの移籍を決めて平塚を離れました。そのため、中断前の12節、アウェーでのG大阪戦が、1995年平塚入団以来3年半近く在籍した、彼のJリーガーとしての最後の試合となりました。
その中断前の最後の試合で、すでに中田選手は顔にまで発疹が出ていて、平塚の植木監督も「W杯も近いし無理しなくていいぞ」と声をかけていますが不調をおして出場していました。中田選手の身体にはすでに深刻な異変が起きていたのです。
中田英寿選手に忍び寄る得体の知れない恐怖、1月はじめから4ケ月間、次第に追い詰められていく気持ちがストレスとなって身体にたまり危機的状況に
すでに日本全体がフランスワールドカップ初出場に向かって盛り上がる一方の中で、1人、追い詰められている代表選手がいました。
誰あろう、押しも押されぬ中心選手の中田英寿選手でした。
発端は、1月4日に掲載された朝日新聞記事でした。同紙の新年企画で「現代奇人伝」という連載があり、中田英寿選手が「疾走する孤高の20歳『君が代』は歌わない」というタイトルで紹介された記事です。
この記事掲載の翌日から、中田英寿選手は思いもよらない恐怖に苛まれることになります。この頃すでに中田英寿選手に密着して取材を続け、中田英寿選手に関する数々の著書を世に出している作家の小松成美氏が著書「中田英寿 鼓動」(1998年12月 幻冬舎刊)の中で、この時期には誰も窺い知ることのなかった中田選手の恐怖と苦悩の日々を綴っていますので、ご紹介します。
「中田が所属するベルマーレ平塚と日本サッカー協会に、ある思想団体から文書が寄せられたのは記事が掲載された翌日、1月5日だった。文面には、国歌をダサイと言った中田への抗議が綴られ、その中田に対してどのような指導と処分を考えているのか、ベルマーレ平塚と日本サッカー協会に問うていた。」
「以来、抗議文は定期的に中田と日本サッカー協会とベルマーレ平塚に送られてきた。新しい文面には、中田を国賊とする旨が記され、日本代表からの辞退や、発言に対する陳謝の記者会見が要求された。」
「1週間、1ケ月と経過する中で、事態は収拾するどころか波の如く広がっていった。抗議の文書は増えつづけるばかりで、中田のマネージメントをする次原(中田選手のマネジメント会社㈱サニーサイドアップ・社長)にも送られてくるようになっていた。その内容は、中田や次原が恐怖を感じるほどにエスカレートしていくのである。」
「事態を打開するためベルマーレ平塚や日本サッカー協会と相談した次原は、警察の指示を受け、最悪の事態を想定して警察に中田の身辺警護を求めた。」
「中田には警察から、一人だけで行動しないこと、自宅から出るときと戻るときはパトカーを配備するので、その時間を連絡すること、不審な者を見かけたらすぐに通報することなどの注意が与えられた。(中略)」
「中田への抗議文は、やがて脅迫めいた文章へと変わっていった。中田への身体への攻撃を思わせる文章を見るたび、次原は生きた心地がしなかった。」
こうした事態に、次原社長は中田選手の身の安全を守るため、私設のボディガードをつけ、ホテル暮らしをさせることにしたのです。
次原社長には、かつて所属選手の前園真聖選手が、スペインリーグ・セビリアからのオファーを受け移籍交渉を進めようとした時、横浜Fからの頑強な抵抗に遭い移籍が破談になった上、前園選手に「わがままな選手」というレッテルを貼られてしまい、マスコミからの厳しい批判に晒してしまうという苦い経験があったことから、中田選手はどんなことがあっても守らなければならないという強い決意がありました。
3月を過ぎても抗議行動は収まりを見せず、4月に入ると㈱サニーサイドアップの事務所にも抗議の電話がかかり続けたのです。
中田選手は、ボディガードに守られホテルに籠る生活の中で、自分を追い詰めてくる目に見えない人物がどこにいるのかわからない恐怖に苛まれていました。しかも、そのことを誰にも話せないため、ストレスが一層積もっていきました。そして、次第に皮膚に発疹が出始めたのです。
中田選手は4月下旬、皮膚への発疹の原因を突き止めてもらうため医療機関を受診しました。その診断結果はアレルギー疾患ではなくストレス由来の皮膚炎としか思えないというものでした。
5月に入ると発疹は顔にまで広がり、はた目にも痛々しいほどになりました。
小松成美氏の著書「中田英寿 鼓動」には、ワールドカップによるJリーグ中断前の最後の試合、前期12節、アウェーG大阪戦の試合のところから、次のように綴られています。
「5月9日、ガンバ大阪と戦うため、大阪・万博記念競技場を走っていた中田は、このままいけば、いつか体が腐敗してしまうのではないかという恐怖を感じていた。体を分厚いゴムが覆っているようで、自分の皮膚の感触は異様だった。息苦しくて、呼吸が荒くなっている。彼は皮膚の痛みから逃れるためにボールを追った。(中略)」
「(試合後)都内のホテルにたどり着き、ボディガードが帰ると、中田はベッドに横になって次原に電話をした。」
「もしもし、俺だけど。酷(ひど)いんだ、全身が。もう我慢できない」
「次原は中田の声を聞き、息を吞んだ。」
「俺、死にたくないんだよ。だから、もうサッカー止める。5月11日から始まる日本代表の御殿場合宿にはいかないよ。これでワールドカップにも行けなくなるけど、それでもいいんだ。とにかく、今日で、すべてを終わりにしたい」
「次原は動転する気持ちを抑えながら、中田の胸のうちを聞いていた。受話器から聞こえる中田の声は、次原の知る中田のものではなかった。今にも倒れてしまうのではないか、と思うほど、中田の声は弱々しく悲しげだった。」
「このことがマスコミに知れれば、必ずパニックが起こるだろう。」
「中田が、サッカーを捨てても今の苦しみから逃れたいという、本当の理由を知る人はいないのだ。」
「次原は、中田に言った。」
「今はとにかく、体のことだけを考えるのよ」
「中田との電話を切った次原は、すぐに日本代表のチームドクター、福林に相談を持ちかけた。翌日、中田を診察した福林は、1週間の御殿場合宿を休んで様子を見ることを勧め、電話で直接中田と話をした岡田(監督)もそれを了承した。」
近づくワールドカップ、日本代表メンバー絞り込みに向けてじわじわと高まる関心
3月にダイナスティカップを制した日本代表は、4月1日、日韓W杯記念試合の第2戦、韓国での試合に臨みました。日韓W杯記念試合の第1戦は前年5月21日、東京・国立競技場で行われ、この時は加茂監督が初招集した中田英寿選手の代表デビュー戦ともなり、試合は1-1の引き分けとなりました。
今回の第2戦、今度は岡田監督が、浦和に加入したばかりの小野伸二選手と、清水の高校生Jリーガー・市川大祐選手を初招集、逆にカズ・三浦知良選手を外すという選考を見せました。
3月27日に発表されたメンバーには、小野、市川両選手に加え1ケ月前のダイナスティカップメンバーから外れた柳沢敦選手、中村俊輔も再招集された一方、1990年9月の北京アジア大会に初招集されて以来、イタリア挑戦時期に辞退した以外、7年7ケ月にわたって日本代表の顔であり続けたカズ・三浦知良選手が外れたのでした。
前年のW杯アジア最終予選から続くカズ・三浦知良選手の不振は、3月のダイナスティカップでも上向かず、Jリーグが始まっても精彩を欠いたままでした。
31歳のカズ・三浦知良選手について、岡田監督はメンバー発表会見で「カズはこの試合では使う予定がない」と説明しました。これを受けカズ・三浦知良選手「若手中心のチーム編成という意図」と自分を納得させていましたが、フランスワールドカップが迫ったこの時期の代表落ちに、心中決して穏やかではなかったことでしょう。
また呂比須ワグナー選手も頬骨折治療中ということで外れました。
前述のとおり、新メンバーで大きなサプライズがありました。小野伸二選手は、すでに「選出されるのではないか」という観測が流れていましたので驚きはありませんでしたが、清水の高校生Jリーガー・市川大祐選手はマスコミをあっと言わせました。
岡田監督は発表会見で「16歳ぐらいから注目していて、この1年でグンと成長した。楽しみだと考えて選出した」と述べましたが、右サイドバックを主戦場とする市川大祐選手の選出は、代表でそこが手薄だという判断があってのことでした。
当の市川大祐選手はなにぶんにも高校生、まだ取材対応も初々しいというより、戸惑い気味という感じの対応でした。
そして4月1日に行われた韓国・蚕室スタジアムでの韓国戦、あいにくの冷たい雨が降り続き、ピッチコンディションも悪い中での試合、韓国は、直近の試合で日本に連敗しているだけにホームでの日本戦は何としても勝つという気迫に溢れていました。
日本は右サイドバックに市川大祐選手をスタメン起用、2トップには柳沢敦選手と中山雅史選手が入りました。
試合は前半26分にDF井原正巳選手が左わき腹を痛めて交代するというアクシデントがあったことも影響して押し込まれてしまう展開に。そして前半40分にアーリークロスからヘッドで韓国に先制を許してしまいました。
後半に入ると日本は積極的にミドルシュートを放つことに活路を求め、後半16分に実ります。相馬直樹選手のシュートが右ポストを叩きましたが柳沢敦選手がつなぎ、それを中田英寿選手がシュート、こぼれ球を中山雅史選手が粘り強くプッシュして同点に追いつきます。
すると岡田監督はすかさず後半20分に小野伸二選手と岡野雅行選手の浦和コンビを同時投入、逆転を狙いに行きました。
ところが後半25分、相馬直樹選手がファウル気味のタックルを受けて転倒、そのあと味方のパスミスが続いたところを突かれ、相馬選手がピッチ外に出て空いたスペースを相手FWが使いゴール、勝ち越しを許してしまいました。
それでも日本は攻め続け何度かシュートを放ちますが、あと一歩のところでゴールは奪えずタイムアップ、試合後、岡田監督は「何としても勝ってやろうという韓国の執念を感じた」と敗因を語りました。
悪コンディションの中にもかかわらず市川大祐選手をフル出場させ、小野伸二選手を25分間テストするという思い切った采配を見せた岡田監督、宿命の日韓戦にもかわらずワールドカップ本番までに少しでも選手層を厚くしたいという事情もにじませる試合でした。
その二人、市川大祐選手は韓国のスピードのある選手と対峙するという難しい仕事を17歳を感じさせないタフさでこなし、相手の力を考えれば立派な及第点という出来でした。小野伸二選手は、25分の中で重いピッチという悪条件もあってか2トップに対して決定的なパスを供給するという仕事は本人もチームとしても物足りない出来でした。しかし、チームメイトの岡野雅行選手とセットで送り出されるなどの配慮もあって、まずまずのデビュー戦となりました。
4月1日のソウルでの日韓戦のあと、代表選手は一旦各チームに戻りました。次の代表関係のイベントは5月7日の25名の代表選手発表です。この25名は、5月開催のキリンカップ2試合を経て、そのままフランスワールドカップ直前合宿を行なうスイス・ニヨンまでを約束されるメンバーです。
一般的に考えれば3月のダイナスティカップ、4月の日韓戦に招集されなかった選手がこのあと招集されるのは絶望的と考えられますが、4月1日の日韓戦に小野伸二選手、市川大祐選手と言うサプライズ招集を行なった岡田監督です。まだ何が起こるかわからない雰囲気も漂っています。
そんな中、4月から5月7日の日本代表発表までに行われたJリーグでは、中山雅史選手の4試合連続ハットトリックや森島寛晃選手の7試合連続ゴール、柳沢敦選手の今季2度目のハットトリックなど、さすがにワールドカップイヤーらしい華々しいアピールも見られました。
一方、海外からはフランスワールドカップグループリーグの初戦の相手となるアルゼンチンが強化試合でブラジルを撃破したというニュースが伝えられスポーツ紙上では、アルゼンチン対策のためにもこの選手を入れるのでは? といった観測記事が載ったり、5月6~7日にかけてはスポーツ紙各紙とも候補選手の当確予想記事が紙上を賑わせました。
岡田監督、25名の日本代表を正式発表、史上最高250名の報道陣、アルゼンチン戦に勝つ!、笑顔一杯の会見
そして5月7日、前日に行われた日本サッカー協会・強化委員会の会合に岡田監督が出席して25名の選考経過などを説明して承認されたこともあり、この日のスポーツ紙朝刊には25名のメンバー表が事前に掲載されました。
当日の記者会見に出席した岡田監督は、事前に記事が掲載されたことは織り込み済みとばかり、笑顔一杯で会見に臨みました。
この日会見場に集まった報道陣の数は250名、この様子を報じた1998.5.27サッカーマガジン誌によると、この数は10年前、1988年8月に、ディエゴ・マラドーナがゼロックススーパーサッカーの試合のため、イタリア・セリエA、ナポリを率いて来日した時や、1993年10月、いわゆるドーハの悲劇のあとに日本代表が帰国した時などで200名近い報道陣が集まった例があるものの、250人となると前代未聞とのことです。
日本が史上初めてワールドカップに出場する、その栄えある22名に向けた最終候補の発表ということで、いかに日本全体の関心が高いかを感じさせる数字だとサッカーマガジン誌は報じました。
岡田監督の25名の選考方針は「アルゼンチンとジャマイカの試合を自分の目で確かめた結果、ディフェンシブに戦わざるを得ないと結論付けた。その戦い方に合う選手を選んでおり、実績で選んだわけでもなく、将来性があるから選んだわけでもなく、ただ、ただフランスで勝つために必要なメンバーを選んだ」ということで「6月14日(初戦のアルゼンチン戦)に臨むにあたり、やり残したことがないように決めた。」ときっぱり語りました。
そして「アルゼンチンに勝つのは非常に難しいが勝てない相手ではない、1-0とか2-1の試合になると思うが勝つ」と笑顔一杯で宣言しました。
発表前日に行われた日本サッカー協会・強化委員会の会合で、25名選出について説明した岡田監督の方針に対して、強化委員会からは「大会直前まで25名で引っ張った場合、大会を目前にして外される3名に対する影響が大きいのではないか」という異論が出されました。
これに対して、岡田監督は、
「ディフェンシブに戦わざるを得ないという方針で、これからチーム戦術を浸透させるためには、途中で離脱する選手のリスクを考えれば、代わりに入る選手も十分戦術を理解した状態にしなければならない。」
「25人は、最終的に登録メンバーとして22人に絞らざるを得ないが、外れた3人が離脱するという意味ではなく、チーム戦術を理解している25人全員でフランスに入るというのが私の考えだ」と説明して、強化委員会の懸念を押し切った形での承認だったのです。
4月1日の日韓戦メンバーとの違いを含めて25名をご紹介しておきます。
背番号、氏名、(年齢)、現所属の順(敬称略)
【GK】
20 川口能活(22)横浜M
1 小島伸幸(32)平塚 ※日韓戦メンバー外
25 楢崎正剛(22)横浜F
【DF】
4 井原正巳(30)横浜M
3 相馬直樹(26)鹿島
5 小村徳男(28)横浜M
2 名良橋晃(26)鹿島
17 秋田 豊(27)鹿島
18 斉藤俊秀(25)清水 ※日韓戦メンバー外
19 中西永輔(24)市原
23 服部年宏(24)磐田
29 市川大祐(18)清水ユース
【MF】
13 北澤 豪(29)ヴ川崎
6 山口素弘(29)横浜F
10 名波 浩(25)磐田
15 森島寛晃(26)C大阪
8 中田英寿(21)平塚
22 平野 孝(23)名古屋
28 伊東輝悦(23)清水 ※日韓戦メンバー外
30 小野伸二(19)浦和
【FW】
11 カズ・三浦知良(31)ヴ川崎※日韓戦メンバー外
9 中山雅史(30)磐田
14 岡野雅行(25)浦和
18 城 彰二(22)横浜M
12 呂比須ワグナー(29)平塚※日韓戦メンバー外
【日韓戦メンバーから選外となった選手、その理由】
柳沢敦(20)鹿島 国際試合での積極性、環境変化の適応能力がまだ足りない。間違いなく日本の将来を担う選手だが今回はスタメンで使えるレベルにはないし交代で使うにも岡野のスピードとか呂比須のヘッドといった特徴に秀でた選手がいい。
中村俊輔(19)横浜M カウンターを狙うディフェンシブなサッカーの場合、ダイレクトパスがうまい小野伸二のほうが向いている。小野伸二はシュート力もある。中村選手はJリーグで成長著しいものの、小野選手との比較で落選となった。
【滑り込んだと言われる選手についての理由】
伊東輝悦(23)清水 ワールドカップ初戦・アルゼンチン戦などは押される展開の中で、何とか1点をもぎ取るサッカーをしなければならない。伊東選手が殊勲の1点をあげたアトランタ五輪のブラジル戦と同じ戦い方になることを考えた時、戦術眼に優れた伊東選手の価値を再認識した。
この発表での会見でも、翌日の新聞各紙の論調も「目立ったサプライズのない順当な選考」という雰囲気でした。
スポーツ紙各紙の取り上げ方は、現役高校生で選ばれた市川大祐選手や小野伸二選手の10歳台コンビ、そして4月1日の日韓戦でメンバー外となったカズ・三浦知良選手の復帰などが中心となった他、清水の伊東輝悦選手を「最後の一人25人目に滑り込み」といった見出しで取り上げたスポーツ紙もありました。落選した選手の中では複数の柳沢敦選手が複数のスポーツ紙で大きく取り上げられました。
5人のFWの中では序列が一番下になるであろうカズ・三浦知良選手に、人知れず忍び寄っていた『落選』の可能性
それにしても、フランスを目の前にしたスイス・キャンプの結果、誰か3人は落選しなければならないのですが、この段階では、岡田監督の「誰か3人外れるとは言っても25人全員でフランスに入り一緒に戦うと考えている」という説明に、記者団からも「大会を目前にして外される3名に対する影響は心配ないのか」といった質問までは出なかったようです。
1998.5.27サッカーマガジン誌は、本文特集の中でDF、MF、FWごとに、何人かの選手にスポットライトをあてて戦い方と選手起用の可能性について論評していますが、目を引くのはFWの部分です。「スタメン候補は中山雅史選手、城彰二選手、呂比須ワグナー選手の3人、カズ・三浦知良選手はFWではスタメン候補ではないが、布陣がワントップをとった場合、その後ろの1.5列目の位置で使われる可能性がある。」と、この段階ですでに、スタメンとしてのカズ・三浦知良選手の序列は4番手に落ちていると見ているのです。岡野選手はジョーカーとして残す可能性が高いですから、FW5人の中では一番下ということになり、25人から22人に絞る際、FWから1人落ちるとすればカズ・三浦知良選手ということになります。
サッカーマガジン誌のように、緻密に日本代表の各選手の状況や岡田監督の戦術、それにもとづく序列などを分析しているメディアは、この時すでに「FWから1人落ちるとすればカズ」と読み切っていたでしょうけれど、残された期間、何があるかわかりません。序列3位までの選手にケガでも起きれば、カズ・三浦知良選手の序列が浮上することもあります。
ですから、この段階では、まだ皆んな口をつぐんで何も言わないだけだったようです。
岡田監督自身も「25名発表の段階では、外す3人が誰かまで決めていない」と断言していますから。
Jリーグ前期12節(5月9日)で一旦中断、5月11日からフランスワールドカップに向けた日本代表活動開始
5月9日の前期12節をもって、Jリーグは7月25日の13節再開まで約2ケ月半、中断に入りました。日本サッカー界はフランスワールドカップに向けてすべてのモードが切り替わりました。
まず、5月11日から25名の代表選手による国内キャンプが始まりました。静岡県御殿場市で5日間行われた合宿には24名が参加しましたが中田英寿選手が不参加でした。
中田英寿選手、皮膚炎発症、静岡キャンプを回避
中田英寿選手は、発熱と発疹を伴う皮膚炎「自家感作性皮膚炎」を発症したため御殿場でのキャンプには不参加と発表されました。数日前の前期12節の試合ですでに発疹はあった中で休まずプレーしたため症状が進んだものと思われました。そのため静岡キャンプへの参加は見送り回復を最優先、投薬治療と疲れやストレスの軽減で症状が収まるのを待つことになりました。
静岡キャンプへの参加を見送って休養に入った中田選手の心の変化を、さきにもご紹介した、小松成美氏の著書「中田英寿 鼓動」には、次のように綴られています。
「中田を追い詰めた(思想団体からの)抗議活動と、それとあいまった肉体的な疲労は、中田のスイッチを一時的にオフにした。が、それで中田の魂が消滅してしまったわけではなかった。」
「ホテルのジムでたった一人走り出した中田は、自分が最も安心していられる場所は、やはりピッチしかないのだということを実感する。中田の体に内蔵されたスイッチが再びオンになった。」
のちにチームドクターの福林徹さんは、サッカージャーナリストの増島みどり氏の著書「ワールドカップフランス98 6月の軌跡」のインタビューで、中田選手を診察した時のことを次のように振り返っています。
「(日本代表との付き合いの中で)一番焦ったこと、とあえていうならば、やはり5月の御殿場合宿に中田が来られなかったことですね。あの時、(所属事務所の次原社長から)電話があって、初めて診断した時には、もうどうなることかと、私個人としては非常に不安でした。」
「皮膚の状態と発熱ですね。それと疲労、彼は心身とも本当に疲れていて、W杯なんてとてもとても考えられない、もう駄目だと、普段の中田と違って『意欲』というものが非常に薄れている状態でした。」
「偏食が原因だとか、色々とみなさんは書いていらっしゃいましたけれど、そういうことではないんです。」
「デリケートな問題であって、野菜が嫌いだからなるわけじゃあない。何よりもストレスです。ですから、ある意味で世間から隔離して、治すということに重点を置くと。」
「でも、それがまたストレスになりかねない。ですから、何よりも静かな環境を与えてみよう。それと治療にはどんなにかけても1週間、その二つを決めて集中しようとしました。(中略)」
「皮膚科のドクターには、毎日非常に長い時間をかけて、丁寧に治療を続けてもらって、それが結果的には非常によかったんだと思います。すぐに良くなりはじめましたのでね。中田はああいうところはプロですね。すぐに体を動かしてましたね。」
絶望の淵まで陥れられながら、何とか帰還した中田選手、その原因となった1月の記事は、日本サッカー界に対する社会の公器を使った言論空間における暴力行為
中田選手は多くの関係者の力もあって危機から脱しました。しかし、中田選手をここまで追い詰めることとなった今年1月4日の記事を看過するわけにはいきません。
中田選手は、前年11月に行われたこの記事に関する取材のあと、記者に対してこう連絡しています。
「『国歌、ダサイですね・・・』と言ったのは、国歌を軽視しているとか誇りを持っていないという趣旨で言ったのではなく、これから試合をする、その直前なので精神を集中したいので歌わないということを理解してもらうために言ったので、誤解を招く恐れがあるので『国歌、ダサイですね・・・』ということは書かないでいただきたい」
そうお願いしたにも関わらず、中田選手の意向を無視して書いたのです。
この記事が掲載されてしまったことで、中田選手はマスコミ不信に陥りました。中田選手がマスコミ不信に陥ったのは、いまに始まったことではなかったのですが、今回の1件は、その極めつけ、もうマスコミは信用しない、マスコミそのものと絶縁する、というほどの不信です。
この記者は、自らが持っている「社会の公器」を「凶器」にして中田選手に2つの「言論空間における暴力」を振るったと思います。
一つは「自身のペン=報道による暴力」です。もう一つは、この記事の読者からの反発という「世論による私刑(リンチ)暴力」です。この記事を書いた記者には、「自身のペン=報道による暴力」を振るったという意識が毛頭なかったのではないでしょうか? 言論の自由を持つ身として普通のことをしたまでだと思っているのではないでしょうか?
ましてや記事を読んだ読者による「世論の私刑(リンチ)暴力」など、あずかり知らぬことと考えているのではないでしょうか。
しかし、長い間に、そうした傲慢なマスコミの姿勢は、社会からの選別という裁きを受けていくことになります。
中田選手は、この1件を機に、自分の考えや取り組みを発信する手段をマスコミに頼ることを止めました。自らホームページを開設して直接ファンやサポーターに伝え、その反応を得るという方法に切り替えたのです。
この時は、それ自体が珍しい取り組みで「やはり異端児らしい」とすら揶揄されましたが、実はスポーツ選手など知名度の高い人が、マスコミを頼らず自らホームページやブログなどインターネットを使って情報を発信するという取り組みの先駆けとなったのです。
ここからは歴史を知った者の後付けの話になりますが、21世紀に入りインターネットの爆発的普及、SNSなど新たな情報発信ツールの登場により、その流れは知名度の高い人のみならず、社会一般の常識となっていきます。
その分、新聞をはじめとしたマスコミは「オールドメディア」と呼ばれ、その社会的役割をじわじわと減らしていくことになります。
20世紀、長らく社会のコミュニケーションツールとして全盛を誇っていたマスコミは、それが一部のごく僅かの記者だったとしても「言論空間における暴力」記事を書き、それによってどれほど人が深く傷ついても、時にはそのことによって自死に追い込まれていく人さえ出ても、社会の権力として君臨してきました。
それを傍で見ている一般人は、第4の権力が、時には個人を自死にさえ追い込んでいまう理不尽さ、不条理さに歯噛みしながらも、なすすべなく見送るしかありませんでしたが、インターネット空間という新たなツールの出現によって、個人でもオールドメディアを選ばないという選択が可能になったのです。
そのため、オールドメディアはじわじわと社会の人々の支持を失なうという、歴史の裁きを受けていくことになったのです。
1998年1月4日掲載のこの新聞記事が日本サッカー界の将来を担う大切な人材に対して行った「社会の公器」を「凶器」にして行った「言論空間における暴力行為」は、日本サッカー史の中にも永遠に記録されます。そして永遠に語り継ぎたいと思います。
中田選手は、この1件を機に、単にマスコミと距離を置き自ら情報発信を行なうというだけに留まらず、日本でプレーする、Jリーグの選手としてプレーすることを終わりにするという決意を固めました。
そこで、所属事務所の㈱サニーサイドアップ・次原社長に「フランスワールドカップ終了後に海外移籍が実現できるよう、必要なことは何でもするので取り計らって欲しい」と依頼しています。
そのため、次原社長は水面下で関係先との交渉や情報収集に奔走していました。
静岡キャンプから始まった報道陣の日本代表追っかけ行脚、まずは取材申請組+日替わリ組合わせて連日100人以上が監督、選手からのコメント取りに奔走
5月11日から始まった静岡・御殿場での合宿から「日本代表狂騒曲」とも言うべき、報道陣の追っかけ行脚が始まりました。
この様子を、集まった取材陣の1人でもあるサッカーマガジン誌が1998.6.3号から始まった密着企画「日本代表同時進行ドキュメント」の冒頭で次のように詳しく紹介してくれています。
「日本サッカー協会に取材申請をした報道陣が150人、そのほかにも日替わりでテレビスタッフやフリーランスの記者が集まる。
報道陣は、練習場で選手たちを出迎え、練習後は、あわただしく選手からとったコメントをノートに書きつけてメディアルームに送る。
連日100人以上の報道陣が選手たちの到着を待つ光景は、まるで朝晩の電車の到着を待つ地下鉄ホームの混雑のようだった。」
確かにその後毎朝のスポーツ紙には、各社それぞれの切り口で監督・選手たちからとったコメントをちりばめた記事が大きく掲載されました。単なる合宿ですから通常ならばベタ記事にもならない内容でも、日本中の関心はここにありとばかりに書き連ねてくれました。
5月10日「スポーツ振興くじ法」(いわゆる「サッカーくじ法」)国会成立、2000年からの実施が決まる
「スポーツ振興くじ法」(いわゆる「サッカーくじ(toto)法」)は、以下のスポーツ振興に必要な財源確保のため、宝くじのように広く小口の寄付を募るという考えのもと導入された法律です。
1. 誰もが身近にスポーツに親しめる環境の整備
2. トップレベルの選手の国際的競技力向上のための環境の整備
3. 国際的スポーツ活動への支援
4. スポーツ指導者の養成、資質の向上
スポーツ振興くじは、文部科学省の指導監督のもと、日本スポーツ振興センターにより運営・発売が行われています。プロサッカー(後年プロバスケットボールも追加)の指定された試合の結果または各チームの得点数を予想して投票し、的中すると当せん金を受けることができる仕組みです。
「スポーツ振興くじ法」の制度化は、平成4年(1992年)財団法人日本体育協会、財団法人日本オリンピック委員会から各政党及びスポーツ議員連盟等に要望書提出(1月)から実質的に始まりました。
その一方、青少年の健全な成長やスポーツのあり方をゆがめるものとして、日本共産党、日本弁護士連合会、日本PTA全国協議会など各界が反対して、国会への法案提出も3回延期された経緯があります。その間、所管官庁をめぐって財務省(当初は大蔵省)と文部科学省(当初は文部省)が激しい綱引きを繰り返しました。
前年12月には、国会の参議院文教委員会に、Jリーグの川淵チェアマンが参考人として呼ばれています。
この法案審議では「スポーツ振興くじ=いわゆるサッカーくじ」導入によって得られる収益が、所管する役所にとっては売上金の配分など、利権としてのうまみがあり、その背後にいる国会議員にとっても、その利権を握る「族議員」として利権にあずかることができる立場になることから、必ずしもスポーツ現場の資金不足に役立ててスポーツ振興を図ろうという説得力のある議論にならず「カネもうけ」ありきの議論に聞こえるような審議になっていました。
そのような中、前年11月の日本代表フランスワールドカップ出場権獲得が、法案審議入りの追い風となりました。川淵チェアマンが参考人として呼ばれた前年12月12日の夜には「フランスワールドカップ出場権獲得祝賀会」が都内のホテルで行われ「スポーツ議員連盟」に入っている多くの国会議員も参加したことから、年明けからの法案審議と成立に弾みがつき、この日の成立に漕ぎつけたのでした。
成立した「スポーツ振興くじ法」は以下のスケジュールと方法で実施されることになりました。
2000年10月と11月に試験発売開始・・・・静岡県で2度の試験発売。第1回は10月28日から11月4日、第2回は11月11日から17日
2001年3月3日 – 全国本格発売開始。当初は「toto売り場(toto特約店)」のみでの発売で、マークシート消込み方式のみ、
なお「スポーツ振興くじ法」第9条の規定により、19歳未満の者のくじ購入および譲受、当せん金の受け取りは禁止されている。また、プロサッカーリーグに関わる選手、監督、役員も禁止となっています。
この「スポーツ振興くじ」が目に見えて役に立っていることを示したのは学校のグラウンドの改善でしょう。それまで学校のグラウンドは土が当たり前で、子供たちが走って転べば膝を擦りむいたりすることが当たり前でしたし、雨の日はぬかるんで運動できない場でした。しかし、学校のグラウンドは徐々に人工芝や天然芝が敷き詰められて、子供たちがスライディングしても大丈夫、転んでも膝を擦りむかない環境になっていきました。
こうした全国津々浦々の環境整備からナショナルトレーニングセンターの整備など「スポーツ振興くじ」による成果はめざましいものがあり、後年「ギャンブル助長」だの「青少年健全育成の邪魔」などと言う声が減ったことは確かです。
「スポーツ振興くじ」が社会に定着したもう一つの要因に、マークシートに自分が書き込まなければ投票できないシステムから、いわゆる「宝くじ」のように運を天に任せる購入方式を導入したこともあげられます。
5月 AFCプレーヤーズオブイヤーアワード97 で中田英寿選手が優秀選手とベストイレブンに選出(最優秀選手は?)、井原正巳選手はアジア歴代最強DFに選出
キリンカップサッカー初戦はパラグアイ戦1-1の引き分けに
5月15日、静岡でのキャンプを打ち上げた日本代表一行は、キリンカップサッカーに臨むため東京に移動、皮膚炎発症のため合宿を回避していた中田英寿選手も東京で合流しました。
5月17日の初戦パラグアイ戦を戦いました。会場は国立競技場、観衆は50,340人。
【日本代表スタメン】(敬称略)
GK 川口能活、DF 井原正巳、小村徳男、秋田豊、MF 相馬直樹、名良橋晃、山口素弘、名波浩、森島寛晃、FW中山雅史、城彰二
※中田英寿選手はこの日、国立競技場の最上階にある部屋から観戦。
試合は前半7分、パラグアイにCKからのヘディングで先制を許し、その後はパラグアイが攻めてこなくなり、日本代表のカウンター攻撃のチャンスがつかめないまま後半へ、後半開始からは足をねん挫したDF小村選手に代え斉藤俊秀選手を投入。
後半18分には中山雅史に代えて呂比須ワグナー選手、森島寛晃選手に代えて伊東輝悦選手を投入。
後半33分には守りを3バックから4バックに切り替えるため鼻から出血した秋田豊選手をさげ前線に平野孝選手を投入。
後半41分、相手ゴール近くで得たFK、名波、城選手がボールそばに寄ったところ、相手の壁ができる前に左サイドで相馬選手が城選手にボールを出せと指示、意図を理解した城選手がすぐ相馬選手にパス、すかさず相馬選手は角度のないところから右足インサイドキックで正確にシュート、名手の呼び声高い相手GKチラベルト選手のスキを突いて見事ゴール、同点。
試合はそのまま終了しました。
※カズ・三浦知良選手、小野伸二選手、市川大祐選手それぞれ出番なし。
翌朝のサンケイスポーツは面白い記事を掲載しました。大見出しには「一瞬のスキをついた相馬のゴールはズルくはない!!」の文字、日本人の美意識である「正々堂々としたプレー」には見えなかったという理由で賛否両論が出ていたというのです。
そしてリード文の中で「だが、知性派・相馬は胸を張って主張した。W杯で勝つために必要なのは日本的感覚ではない・・と。」
武士道精神を大切にする日本人、しかし相馬選手のプレーは、その武士道精神に悖(もと)る、ズルいプレーだったのではなく、正当な頭脳的プレーだったと説明して理解を得たいという、時代を感じさせる記事でした。
このあと20年、30年と時を経てから、この議論、つまり、こういうプレーは武士道精神に悖(もと)るのではないか、いやいや、正当な頭脳的プレーだ、という議論を持ち出した時、日本のスポーツ界、というより、その時の日本社会全体は、どう反応するのか、その材料として記憶に留めておきたいと思います。
史上最高の観客を集めたキリンカップサッカー2戦目チェコ戦はスコアレスドローに
5月24日、日本代表はキリンカップサッカー2戦目をチェコと戦いました。会場は横浜国際競技場、観衆は66,930人、これは横浜国際競技場のこけら落としで行われた3月1日のダイナスティカップ・韓国戦の時の59,380人を大幅に上回る史上最高の観客数となりました。4年後に日本で開催される2002年W杯のメインスタジアムに想定されていることもあり、会場警備のシュミレーションも兼ねて、当日は機動隊員50人、警察官130人が配置されました。
【日本代表スタメン】(敬称略)
GK 川口能活、DF 井原正巳、斉藤俊秀、中西永輔、MF 相馬直樹、名良橋晃、山口素弘、名波浩、中田英寿、FW中山雅史、城彰二
この日は、雨模様にも関わらず横浜国際競技場には66,930人もの大観衆の中で、ワールドカップ前、国内での最後の試合、いわば壮行試合の意味合いもありました。
日本は、第1戦同様の布陣で、ケガをしたDF2人と中田英寿選手をスタメンに復帰させた変更のみ。したがってスタートからしばらくは守ってカウンター狙いの布陣、次に後半10分、中山雅史選手に代えて小野伸二選手投入、城の1トップ、2列目に中田選手と小野選手が並ぶ布陣に変更、後半32分に相馬選手に代えて呂比須ワグナー選手を投入、4バック、2トップの布陣にして戦うものの得点を奪えず、スコアレスドローで終了しました。
※カズ・三浦知良選手はこの日も出番はありませんでした。
カズ・三浦知良選手、全体練習後も黙々と孤独なシュート練習、遠くから見ていた岡田監督、思わず「よく練習するなぁ」、2人の胸中やいかに
キリンカップ2戦とも出番がなかったカズ・三浦知良選手、これで4月1日の日韓戦から3試合連続で出番なしとなりました。
このことについて、サッカーマガジン誌「日本代表同時進行ドキュメント」②の中で、伊東武彦記者は次のように書いています。岡田監督とカズ・三浦知良選手それぞれの心情に心を寄せながらインサイド情報を伝えてくれている味わい深い記事です。
「(チェコ戦の試合後)取材陣の待つミックスゾーンにFWの選手は中山雅史以外は姿を現さなかった。(中略)彼らは何かを抱え込んだような表情で帰りの車に乗り込んだ。」
「その頃、記者会見で岡田監督が注目すべき発言を口にしていた。記者の一人が『カズを使わないのはコンディションが悪いのか?』という質問を発した。それに対する返答は『前線は城を柱に考えているので、カズを使うと左サイドで重なってしまう』というものだった。さらに『カズの調子はそんなに悪くない』と付け加えた。」
「公の場で個人の名をあげて『柱とする』と発言したのは初めてのことだった。」
「FW陣のポジション争いは、この日の岡田発言を経て、新たな展開を予感させた。」
「前日の5月23日、昼、練習が終わり選手が三々五々、ロッカールームに引き上げるのを横目に、カズはグラウンドの周囲をゆっくりと走り、ストレッチをこなし、フラビオコーチを伴ったシュート練習をこなした。報道陣と談笑していた岡田監督は、カズのほうに視線をやると、一歩グラウンドのほうに歩み寄って『よく練習するなぁ』と呟いた。翌日のチェコ戦のスタメンについて岡田監督の頭にあったのは、パラグアイ戦と同じ城と中山であり、カズのスタメンの可能性はなくなっていた。」
「(カズは)最後は楢崎を相手にPKを蹴り、ストレッチを終えて引き上げる。その頃にはもうグラウンドには誰もいなかった。」
サッカーマガジン誌伊東記者のレポートが示すように、岡田監督の心の中では「このまま行けば、カズは使いどころがないな」と決まっていたようです。しかし静岡合宿が始まった時から、カズ・三浦知良選手は終始あきらめることなく自分にムチ打っていたのです。静岡合宿で行われた5Kmのクロスカントリーでは、1位市川大祐選手、2位小野伸二選手に続いていたカズ・三浦知良選手が最後に執念を見せて2位でフィニッシュ、そして全体練習後も最後まで居残って黙々とシュート練習を続けてきました。この10日間、孤独に耐えて自分を追い込み続けてきたカズ・三浦知良選手、次第に戦力としての序列が下がっていくのを感じていたその胸中や如何に。それを見つめて『よく練習するなぁ』と呟いた岡田監督の胸中も果たして如何に。
キリンカップの第2戦を前にしたスポーツ紙がこんな記事を1面で報じました。
「カズ(激白)、早く決めてくれ 落選の3人も先発の11人も、日本のため、自分が外れても」(5月22日スポーツニッポン)
「カズ宙ぶらりん不満、メンバー固定を、岡田監督に進言(?)、レギュラー落ち覚悟で」(5月22日日刊スポーツ)
報道陣に対して「監督によってやり方はいろいろあると思うけど」と断りつつも、まさに宙ぶらりんの状態に置かれ続けている今の状況を口にせずにはいられなくなったのでしょう。フランスに向かう前に「いらない」なら「いらない」とはっきりして欲しいという気持ちだったようです。
しかし、岡田監督は、最後の3人切りをフランスまで持ち越すことにしたのです。夢の舞台のすぐ近くまで連れて来られてから、誰か3人は外されることになるのです。
フランス本大会で善戦できそうな形までは作れたものの、勝てる処方箋を見いだせないまま終わった国内での強化
これで国内での強化試合は終わりました。これまでの岡田監督の「ワールドカップの戦い方」についての試行錯誤を総括するように、5月25日スポーツニッポン紙上でスポーツライター・金子達仁氏がこう述べていました。
「我々はフランスに何をしに行くのだろう。(中略)もう一度はっきりさせておきたいのだが「ディフェンシブな戦い」とは、実力的に上の相手から『勝利を奪うため』にとられる戦術であるはずだ。」
「私には岡田監督の考える『勝つための手段』が見えなかった。守りを固めて善戦しようという意図は見えたが・・。(中略)私はフランスには勝ちに行くものだと思っている。(中略)2002年のためには素晴らしい善戦よりも、もっと必要なものがあると思っているからである。」
岡田監督は、キリンカップの2試合とも引き分けに終わったことで、少なくともここまでは「フランスで勝つための戦い方」を示すことができませんでした。金子達仁氏はスポーツニッポン紙上で「岡田監督が胸の内に確固たる『勝つための手段』を隠し持っていることを心から祈る」と締めくくりましたが、岡田監督が勝てる処方箋を見い出せないままフランスに向かわざるを得ないことは明白でした。
こうして岡田監督と25名の選手たちは「誰か3人が落とされる」という自明の理を胸の奥にしまい込みながら、そして「善戦はできるかも知れないが、誰か点をとって勝てるのだろうか」という濃い霧の中に向かうような気持ちを、やはり胸の奥にしまい込みながら、5月27日12時、JAL便でスイス・チューリヒに向けて飛び立ちました。
成田空港には約1000人ものサポーターが、日本サッカー史に新たな歴史を刻もうとする日本代表を鼓舞するために駆け付けました。成田空港ロビーを埋めたサポーターの熱気と、監督・選手たちの気持ちとの間には明らかに温度差がありました。監督・選手たちに屈託のない笑顔を求めることは無理だったのかも知れません。
フランスW杯開幕直前、日本代表に激震、カズ・三浦知良選手落選、傷心の帰国、一方、中田英寿選手は「もう日本には戻らない」決意を胸に秘めフランスへ
日本時間5月28日未明、日本代表の一行がフランスW杯出場のための合宿地となっているスイス・ニヨンに入りました。
日本代表の一挙手一投足を追う報道陣との第二幕がスイス・ニヨンで始まりました。報道陣から日本中のファンに届けられた第1報は「中田英寿選手、ど派手な金髪頭で現地入り」というニュースでした。
中田英寿選手はこの時すでに、ある決意を胸に秘めていて、その準備も着々と進めていました。フランスに向けて旅立つ1週間ほど前、かねて準備していた自前のホームベージが開設されました。これで、自分と、自分を後押ししてくれるファンとの直接コミュニケーションが可能になり、何かと自分の発言を歪めて伝えることが多いマスコミの手を借りることなく、自分の考えをストレートにファンに届けることができるようになったのです。
もう一つ、新聞の見出しになった「ど派手な金髪頭」も、実は巧みな準備の一つだったのです。中田選手は、あの忌まわしい恐怖体験にほとほと疲れ果てており、また日本のマスコミとの冷え切った関係にも嫌気がさしていて、このワールドカップのあとは絶対海外移籍を実現させ、ゼロから再スタートを切る、日本にはもう戻らないと決意していたのでした。
それは所属事務所の㈱サニーサイドアップ・次原社長も同じでした。日本国内で中田選手が選手生活を続けるにはセキュリティ面のコストが無視できないところまで来ていて、何とか、このワールドカップでの活躍によって海外移籍を実現させるため、自分も最善の努力をしなければならないと心に決めていたのです。
そのためにはワールドカップという見本市に来る、世界中のサッカークラブの代理人という、いわば買付人の目に、中田英寿という「商品」が一目でわかるよう「金髪頭」にしたのです。
初めて明確にされた「レギュラー組」と「サブ組」、落選3人の絞り込みの目安に
スイス・ニヨンでの合宿初日に見られた明らかな変化を、サッカーマガジン誌「日本代表同時進行ドキュメント」③の中で、伊東武彦記者は次のように書いています。
「これまで、チームの基本戦術を確認する最初の練習の段階では、はっきりとメンバーを色分けすることはなかったが、今回は最初から明確に色分けされた。キリンップでのスタメン組だった城、中山の2トップをはじめとしたイレブンがイエローのビブスをつけ、あとのメンバーはビブスはない。」
「パスゲームの中、やや精彩を欠いたビブスなし組には、カズ、北沢と2人のベテランがいた。」
「メンバーを固定し、チームの戦術を磨き上げる岡田監督が、一方で心を砕くのが、サブメンバーの扱いだ。」
「キリンカップを戦っている最中に岡田監督はスイスに連絡を取り、ある要請をした。30日のメキシコ戦の翌日に、不出場だった選手たちで地元クラブを相手にゲームを行なうことにしたのだ。」
日本時間6月1日未明、スイス・ニヨンで合宿中の日本代表がスイス・ローザンヌでメキシコ代表とテストマッチを行ないました。戦術やメンバー等の情報漏れを防ぐため報道陣をシャットアウトして行われたこの試合、日本は先制したものの1-2で逆転負け、ただ監督も選手たちも勝負より内容とばかり勝ち負けにはこだわっておらず、練習の成果を出せたかどうかだけが関心事でした。
日本時間6月2日未明、サブ組が地元ニヨンのクラブ(スタッド・ニヨネ)と練習試合を行ない、カズ・三浦知良選手は呂比須ワグナー選手と2トップを組みハットトリック、3-0の全得点を叩き出しました。そこには、どんな試合でも全力を尽くすカズ・三浦知良選手の姿がありました。
一方で、この日の控え組の中から落選の3人が出るのは確実と、報道陣に取捨選択の絞り込み精度を高めさせる結果にもなりました。
6月2日 スポーツニッポン紙に「カズは落選しないはず」という川淵チェアマンの発言が載りました。「ここで落とすなら最初から入れない。落とすんだったら、まだ先のある若い選手を落とすはず」と断言調で語ったそうです。
一方で同紙は「ニヨンでの合宿初日からカズはいきなり古傷の膝痛が悪化、別メニューとなり、25人のメンバーが決まってから一度も試合への出番がない」とカズ・三浦知良選手の代表落ちがにわかに現実味が増していると報じていました。
さらに6月2日 毎日新聞朝刊は1面に「W杯最終メンバー、カズ、北沢は落選濃厚」の見出しで、残る1人は第3GKか市川になる見通しと報じました。なぜ全国紙が個人名を出してまで事前に報じたのか? 岡田監督は大仁強化委員長にもコーチ以下スタッフにも一切話していませんでしたから日本国内のサッカー協会関係の誰かから「おそらく」の但し書き付きで情報が出たのでしょう。この1件を機にサッカー協会は情報漏洩を徹底するよう対応策をとりました。
6月2日 夕刊フジ紙は「今夜22人決定、市川落選、あと2人はカズか北沢か服部か」と最新の岡田監督の選手起用情勢分析から、こちらも具体的な名前を報じました。
その頃、岡田監督は、翌日の登録メンバー22人発表を控えて、夜コーチ陣とミーティングを開きました。そこで岡田監督は各コーチに外す3人についての意見を聞いたそうです。それに対して各コーチがあげた3人の名前は、各コーチばらばらだったそうです。そこで岡田監督は「みんなの意見はわかった。明朝までにオレが一人で決める。誰になっても納得してくれるな」と確かめたところ、各コーチとも「任せます」といってくれたそうです。
灼熱のニヨンで岡田監督、努めて淡々とした口調で落選3名を発表、どよめき慌ただしく速報する報道陣
そして、6月2日(日本時間20時、現地時間正午) ついに合宿地のスイス・ニヨンで岡田監督が最終登録メンバー22名を発表しました。ここまで25名で合宿を続けている中、外れる3名を発表する形となりました。屋外の日差しの強い場所で行われた発表会見で、岡田監督は開口一番「22人は今朝決めました。外れるのは市川、カズ・三浦カズ、北沢の3人です」と述べると記者団からどよめきと、第一報を所属会社に伝える動きのため、記者団の塊が崩れかけました。
しかし、岡田監督は構わず「カズと北沢は日本に帰すことにしました。市川はそのまま帯同します」と付け加えました。
岡田監督の話が終わると同時に今度は記者団から矢継ぎ早の質問が飛びました。
以下、一問一答を記録しておきます。
Q.3人を落とした理由は?
A.市川は飛躍的に伸びると思ったが、壁にぶち当たって実戦ではまだ使えない。カズは、城をFWの柱と考えているので、残りのFWをどうするかと考えると使うチャンスがない。北沢は点を取るということを考えた場合、3バックでは使うポジションがない。
Q.カズと北沢は(外れたことが決まったあと)本人たちが日本に帰りたいと言ったのか?
A.本人たちはチームのために力になりたいと言ってくれたが、ショックが大きかったので、このまま帯同してもチームのためにならないと、私の判断で帰すことにしました。25人で最後まで戦えると思ったが、ショックが大きかった点は、私の見込みが甘かった。読みが甘かったです。
A.本人たち(カズと北沢)は残りたいと言ったわけですね。3人とも帯同させるはずだったのに帰すことにした?
Q.そうですね。25人から3人外しても明るい雰囲気でずっとやっていけると思っていたが・・・。でも想像以上にショックが大きかった。影響力が大きい選手だけに、チームにマイナスになると思いました・・。
A.通告は個別にしたのですか?
Q.全体でミーティングする前に3人を個別に呼び、話した。
Q.22人はどういう基準で選んだのか?
A.トータルで見てグループリーグ3試合を勝ちにいくための選手を選んだ。
Q.市川はどういう形で帯同させるのか?
A.オフィシャルなIDカードを用意している。
Q.GKの場合、大会期間中でも負傷者が出れば入れ替えは可能なのに3人を選んだのはなぜか?
A.全体の中でこのメンバーがいいと判断しただけです。
A.最終メンバーを決めて心境の変化はあるか?
Q.今は14日のアルゼンチン戦のことしか頭にないので、特に変わったことはありません。
A.2人以上故障者が出た場合はどうするのか?
Q.今までに選んだことのある選手を日本から呼ぶことになると思う。カズか北沢を再び呼ぶことはないと思います。
A.メンバーの決定は誰かに相談したのか?
Q.誰にも相談していない。今朝の11時まで自分で考え、あとは個別に部屋に呼んで伝えました。
A.12時からの全体ミーティングで他の22人の選手たちに伝えた時、選手たちの反応、表情はどうだった?
Q.これは仕方のないこと。集めた当初からわかっていたことです。皆プロフェッショナルですから、今後はチームのためと考えてくれるでしょう。
この選考について、それぞれのメディアが、それぞれの解説を試みています。ほぼ共通している点をいくつかご紹介します。
・GKを当初案どおり2人にするとカズ・三浦知良選手は残った可能性が高い。ところが第3GKを登録から外すとチームと一緒に練習ができないこと、また正GKの川口能活選手が退場処分などになってしまうと第2GKがピッチに入ったあと控えのGKがいなくなるリスクがあり、やはりGKは3人登録にしておいたほうがいいという判断があったのです。もともとFW陣の中で最下位の序列だったカズ・三浦知良選手は第3GKとの天びんの結果はじかれたということになります。
・北沢選手は点を取るということを考えた場合、3バックでは使うポジションがないと判断されました。北沢選手は前年のアジア最終予選で日本が中央アジア遠征から戻り、岡田監督が4バックシステムのチーム戦術立て直しのカギとして再招集した北沢選手が、岡田監督の期待以上の働きを見せてくれた選手です。
しかし、ワールドカップ本戦の強豪を相手に3パックシステム(両サイドのウィングバックを含めると5バックシステムになる戦術)の場合、前線は2トップ、2列目に中田英寿選手+前線への飛び出しができる選手の2人だけになります。最近3バックシステムで、チームで点がとれないのは2列目からの飛び出しが見られないためという考えが岡田監督の頭にあり、その役割を担う選手として森島寛晃選手、平野孝選手、北澤豪選手がいるのですが、結局その中から森島寛晃選手と平野孝選手を残し、北澤豪選手がはじかれたということになります。
落選者3名の発表を受けて、報道陣は他の22人(正確には市川選手を含めた23人)からコメントをとりに走る人や、自社に会見の詳報を送る人などに散らばりました。
FWのスタメン候補となった3人の選手は3者3様のコメントを発しました。
中山雅史選手は「ずっと代表で一緒だったカズさんが代表を外れることになりましたが、そまことについては・・」と問われたのに対して、小さく呻き声を出したあと遠くを見るような表情のまま約6秒間ほど沈黙して、やっと「まぁ、いろいろですね」とだけ答えて報道陣を後にしました。
呂比須ワグナー選手は「残念です。けど、このメンバーで戦うしかないんで・・」
城彰二選手は「残念です。ボクはカズさんを目標にやってきたし、カズさんにここまで引っ張ってきてもらったので・・。今度は、僕が引っ張る番だと思うし・・気持ちをもう1回整理して頑張りたいと思います。」
サッカーマガジン誌「日本代表同時進行ドキュメント」④の中で、伊東武彦記者が伝えてきた3人の落選劇には、岡田監督の公式発言とは違う事情があったようです。
「岡田監督は自室に呼んだ北沢に(外すことを)通告した。そして『チームに残ってくれるか?』と聞いた。」
「北沢は『これからのサッカー人生のこともあるし、家族もいれば相談する人もいる。この場では返事できない』と答えた。そして北沢はカズと話し合い、家族に電話した後にチームを離れることに決めた。岡田監督はその場で『俺が帰らせたことにするから』と2人に告げた。そして、その通りに報道陣を前にして話した。会見が終わった後ホテルに戻る車中で、岡田監督は終始無言だった。」
「ニヨンを離れる日、岡田監督は『誤算は25人でフランスに行けないこと』と話した。2人が外れてもチームに同行すると踏んでいたのか。そうでなければスイスに2人を同行させた理由がつかない。当初から外すことを前提にしながら、2人のプロ意識と経験にかけたのか。それならば最後のチャンスになる大きな目標を目前で奪われた2人のショックを、本当に想像できなかったのか・・。」
「(特にカズ・三浦知良選手と北澤選手の落選について)さまざまな憶測が飛んだ。しかし岡田監督の胸中にあったものは、戦いのすべてが終わるまで明かされることはない。」
一志治夫氏の著書「たったひとりのワールドカップ」には、岡田監督とカズ・三浦知良選手、北澤選手の「帰るか、残るか」のやり取りについて、こうあります。
「(記者会見の前)カズは、中山らと昼食をとっていた。当然のことながら、そこには沈痛な雰囲気が漂っていた。」
「昼食の直前、カズはフラビオコーチとボルトガル語で話していた。『僕たちがこのまま残ったら、チームの雰囲気のこともあるしよくないと思う。(かといって)チームを捨てたと思われるのも嫌だ』という内容のことをフラビオに話したという。
「カズたちが食事をしていると、フラビオコーチが通りかかり、手のジェスチャーだけで『これから岡田さんの部屋に行ってくる』と合図を送ってきた。」
「しばらくすると、エレベーターの前にいたカズたちのところに岡田監督がやってきて『25名で戦おうと思っていたけど、自分の考えが甘かった。フラビオから聞いたから、(帰る理由については)わかったから』と言った。」
「(岡田監督は)この段階で、カズと北澤を帰すと決めたのである。」
「フラビオはおそらく、カズと北澤のプライドをどう守ってやるべきか、プロのコーチとして進言したのだろう。」
カズ・三浦知良選手の落選発表から帰国会見まで、日本中で沸騰した議論の一部始終、「人間の尊厳を傷付けた」とまで評された出来事を克明に後世に
「カズ・三浦知良選手落選」のニュース、社会的関心事として大きく報じられ、それを受けて巻き起こった国内のさまざまな反応
「カズ・三浦知良選手落選」のニュースは、瞬く間に日本中はもとより海外にも広く打電され、いろいろな議論を巻き起こすことになりました。
国内では新聞・テレビなどを中心にマスコミ報道を通じて、各界各層からの反応や議論が巻き起こりました。単にサッカー界だけの問題ではなくなり、大きな社会的関心事として、さまざまな意見が飛び交いました。
これも、日本サッカー史上初めて出場するワールドカップサッカー、世界最大のスポーツの祭典ワールドカップサッカー、2002年には日本でも開催されるワールドカップサッカーなるが故の社会的関心と言えますし、近年の日本サッカー最大の功労者であるカズ・三浦知良選手が対象となったが故のことでもあります。
特に発表時間が、日本時間の6月2日の夜、テレビ各局が夜のニュースを流す時間帯だったこともあり、各局とも一斉に、いわゆる街の声を拾う中で、以下の3つの意見に集約されました。
・まず一つは、岡田監督が純粋にワールドカップに勝つために選択した結果が、日本サッカーに限りなく貢献したカズ・三浦知良選手といえども必要ないということであれば、それは仕方のないことで、いろいろと議論が巻き起こることを承知でカズ・三浦知良選手を外すのは相当勇気のいる決断だったと思う、という意見。
・もう一つは、カズ・三浦知良選手なら何かやってくれるのではという期待もあるし、これまでの日本代表への貢献や、外してしまうことによる社会的衝撃を考えれば、何が何でもカズ・三浦知良選手を外す必要はなかったのではないか、という意見。
・3つ目は、なぜフランスに行くまでは「カズ・三浦知良選手はチームにとって欠かせない選手だから」と言ってメンバーに加えておきながら、目前にして外すというやり方をしたのか、「カズ・三浦知良選手はメンバー外」であるほど不要な選手であれば、もっと前に通告すべきだったのではないか、ここに来て外すやり方は、組織をマネジメントする管理者としてはどうなのか、という意見。
6月第1週のテレビ・ワイドショー番組で「カズ・三浦知良選手落選」のニュースは群を抜く放送時間
テレビ番組の中でワイドショーと呼ばれる番組で扱われた「カズ・三浦知良選手落選」のニュースは群を抜く放送時間でした。
ワイドショーと呼ばれる番組で扱われたニュース項目の合計時間を集計したものを毎週単位で発表しているTBS土曜夜の「ブロードキャスター」の「今週のワイドショーランキング」というコーナーでは、6月1日から6月7日までの結果が次のようになりました。
1位 無念の帰国ーカズ代表落ちの波紋 5時間21分04秒
2位 岩手小2女児殺害ー隣人を逮捕 1時間46分17秒
3位 男の花道 元小錦 涙の断髪式 1時間38分02秒
4位 離婚迫られー35歳母 子供3人を絞殺 1時間21分52秒
5位 交際2ケ月 飯星景子”ジワッ”と婚 1時間21分48秒
この数字一つとっても、いかに社会的関心が高かったかがわかります。「サッカーの詳しいことは知らないけれど、カズ選手落選のことについては一言言いたい」という、日本がワールドカップに初出場することになったあたりから関心を持ち始めてくれた、新たな「ふわっとした関心層」が増えたことは明らかでした。
サッカー王国ブラジルでは国民すべてが「代表監督」と言われるほど多くの人が代表チームに対して一家言持っているようですが、ブラジルほどになるのはまだ遠い先にしても、2002年日韓W杯に向けて、日本国民も少しづつ日本代表に対して一家言持つ人が増えていくことを予感させる現象でした。
こうした声に対して、98.6.7に放送されたテレビ朝日のスポーツドキュメンタリー番組「Get Sports」の中でサッカー解説者のセルジオ越後氏がこう指摘しました。
「カズを外せば、国際経験豊富なのにとか、これまであれだけ貢献してきたのに、という議論が当然出るけれど、ボクは、この時点(6月2日)で外すべきではなかったと思う。もう今の段階では、そういう議論している場合ではないと思う。その議論は(5月7日に)25名を選ぶ段階で、カズを外すなら外して、当然、議論・反論は出るにしても、この6月2日時点では、もうその議論は冷めていると思う。」
「5月7日に25名の発表があった時には、カズはJリーグで点も取っていないし厳しいことは明らかだったけど、誰も何も言わなくて、何も言えなくて、(アルゼンチン戦まで2週間を切った)今更こういうことを議論してどうするんだと思う。」
またサッカーライターの金子達仁氏は「試験でいえば最後の追い込みの時期に、(カズ落選)を発表したことについてはどう思いますか?」と問われて「まぁ、(W杯出場が)初めての国ですから仕方ないですけれど、岡田監督の脳裏に(カズを外したことの影響が)残っていなければいいですれどね。監督の頭の中がアルゼンチン戦に勝つために何をするべきか、その1点に集中していることを期待します。そして、選手たちが『監督は正常心なんだ』と安心できるような表情や態度を見せて欲しいと思います。」
セルジオ越後氏はこう付け加えました。
「世論に対していいたいことは、ここまで岡田監督をあんなに支持していたのに(カズ外し)によって、特にサッカーを知らない人たちの意見や雰囲気をああだ、こうだと煽り立てて、せっかく国全体が一つにまとまって応援しようと盛り上がっていた気分に水を差さないで欲しいということです。ブラジルでもロマーリオ落選によって、それまで(ザガロ体制のブラジル代表に対する支持率が)80%から11%に落ち込んでしまい、フランスで開幕を迎えようとしているブラジル代表が大きなダメージを受けている。そんなことにならないように、ボクは、サッカーをあまり知らない人たちに『今は少し(いろいろ意見を言うのは)我慢してくれ』と言いたいぐらいだね。」
「それから日本サッカー協会に、ここは何とかしてもらいたいね。現場が安心して大会に集中できるよう、引き受けて欲しいね。」
しかし、セルジオ越後氏の「サッカーを知らない」コメンテーターがいろいろと煽り立てないで欲しいという虫のいい話が通るわけもなく、国内は静かになるどころか日に日に関心が高まっていきました。
カズ・三浦知良選手と北澤豪選手帰国会見、カズ・三浦知良選手「自分の魂みたいなものはフランスに置いてきたと思っている」
特に6月5日午前、帰国したカズ・三浦知良選手と北澤豪選手が成田空港で記者会見に臨み、落選したことについて一言の恨み言も発さず、前向きなコメントを述べ、さらには「自分の魂みたいなものはフランスに置いてきたと思っている」と名言を吐きました。
この潔い発言がまた、判官びいきの日本国民の琴線に触れ「カズ・三浦知良選手は潔し、それにひきかえ岡田監督は冷酷」といった風潮に火をつけたことも確かです。
カズ・三浦知良選手と北澤豪選手は、スイス・ニヨンを出たあとイタリア・ミラノに入り一呼吸おきます。日本に帰れば大勢の報道陣が待ち構えています。気持ちを整える会見で話すことについて頭の整理をするためにも必要な一呼吸です。
6月5日午前、カズ・三浦知良選手と北澤豪選手が成田空港での帰国会見には約100人ほどの報道陣が詰めかけました。サッカー担当のスポーツ記者で日本に残っている記者はもちろんですが、多くは芸能畑、ワイドショー系の記者たちでした。
約15分ほどの会見でしたが、その内容を記録しておきます。「自分の魂みたいなものはフランスに置いてきたと思っている」という名言を含む会見です。
【カズ・三浦知良選手と北澤豪選手の帰国会見】
Q.まず現在の心境は?
A.カズ・三浦知良選手
今日はお忙しい中、お集りいただき、ありがとうございます。
こういう形で帰ってくるとは自分でも思っていなかったんですけれど、自分がずっと志してワールドカップを目標にやってきて、このような形で帰ってきましたが、自分の人生もそうですし、サッカーもまだまだ続くと思うし、やり残していることがあるので、前向きに目標を持ってまた頑張りたいと思います。ここまでずっと支えてくれたファンの方とかには感謝していますし、今回、このようになって、あらためていろんな人たちに支えられているんだなと実感しています。これからもいままで以上に頑張っていきたいと思っています。どうも、ありがとうございました。
A.北澤豪選手
思ったよりも早く帰ってきてしまったんで、自分でも悔しく思っていますが、人生終わったわけではないし、まだまだ先に進んでいかなければならないし、自分としても、一つひとつの目標に向かって頑張っていきたいと思います。こういう時に自分の支えになっているものが浮き彫りになってきたので、そういう家族やファンの人たちのためにも、これから先、もっと頑張りたいと思います。今日はありがとうございます。
Q.イタリアに2日間滞在して、髪を金髪にしたのは何か大きな決意の表れでしょうか? そして気持ちの整理はつきましたか?
A.カズ・三浦知良選手
(金髪にしたことと決意とかは)全く関係ありません。イタリアは個人的に好きなので、ゆっくりさせてもらいました。いまは気持ちの整理はついています。
A.今日フランスに入るメンバーに、一言エールがありましたら・・。
【カズ・三浦知良選手が北澤選手を促すように小声で「エール」と言ったのに反応して】
A.北澤豪選手
いま一番大事なのは、こういう状況の中でも皆んながしっかり日本代表を応援して、必ず一次予選を突破してもらうということを願いたいですね。
Q.カズ・三浦知良選手
日本が一次リーグを突破して決勝トーナメントに出れるよう願ってるし、北澤もボクもこういう形で帰ってきましたけれど、自分たちの日本代表としての誇り、魂みたいなものは向こうに置いてきたと思ってるんで、絶対頑張ってくださいと言いたいですね。
Q.日本のサッカーファンに中には「残念だ」という声と「やっぱり」という声がありますが岡田監督から告げられた時はどんな気持ちでしたか?
A.カズ・三浦知良選手
いままでプライドを持って、日本代表として誇りを持ってやってきたので、自分自身、(落選に)絶対納得してはいけないことだと思うけれど、ただ、また目標を持って戦えばいいんだと、気持ちは切り替えました。
Q.岡田監督からどういう言葉で伝えられたんですか?
A.カズ・三浦知良選手
機内で新聞読んだんですけど、新聞のとおりだと思います。
A.北澤豪選手
帰ってきた理由に関しては、監督と自分がお互いに話して決めたことです。残っているメンバーの人たちに気を使ってもらっては自分としても避けたいし、残ったメンバーがそのために力を発揮できないようなことになってはいけないんで、それは話しました。
Q.スイスに行く前に聞きたかったのか、スイスでの合宿が終わる直前にサイが投げられるのと、どっちがどうだっか、いまどう思いますか?
A.カズ・三浦知良選手
そういうことは何も考えていなかったんで、何もありません。
Q.いま一番何をしたいですか?
A.カズ・三浦知良選手
いや、別に、特にしたいことはないですけど。
Q.やり残したことはありますか?
A.カズ・三浦知良選手
それはプレーヤーである以上、常に、Jリーグで優勝しても、また次の年優勝しなければならないと思うし、何か達成しても必ず次に目標が出て来るもので、これはもう辞めるまでずっと付きまとうものだと思っている。人生と同じで、これで満足ということはないのもで、まだまだやり残している、まだまだやらなければということを実感している。
Q.ヴ川崎の森下社長に伺いたいのですが、これで日本代表にヴ川崎所属の選手が20年ぶりにいなくなってしまったということになりますが、いかがですか?
A.ヴ川崎・森下源基社長
二人の選手が所属するチームの責任者として二点ほど感想を述べさせてください。
第一点は、結論から先に申し上げますと、どうして出発前に22人が決まらなかったのか、若い選手を試して結果的にダメだったということはあり得ると思いますが、少なくとも岡田監督を含めて日本サッカー協会の皆さんは、ここにいる2人の力というのは「ドーハ」以来、十分承知しているはずと思います。
その2人さえも向こうに行って試したいというのは、可能性を模索するという意味かも知れませんが、それは自信がないことの裏返しでもあると思います。
その2人があえて、こういう悲しい、悔しい思いで帰ってきたのは、マスコミ報道は(岡田監督の)勇気ある決断とか、いろんな意味でとらえているようで「非情なる采配」という評価もあるようですが、私は「非情なる采配イコール非礼なる采配」だとあえて言わしていただきます。なぜならこの二人がどういう選手であるか十分承知して、若い人たちにそういう判断を下すのとは立場が違うと思うのです。
第二点は、今度のこういう結果について、日本サッカー協会から我がヴェルディに二人を帰しますという報告はいただきましたが、それ以来、私のところにはなんら説明がございません。(中略)こうしたケアのなさが、二十二人の選出も含めた対応ができない(いまの協会を)象徴しているとあえて言わせていただきます。
ここにいるカズは、皆さんも知っているように、日本のサッカーをどれだけ引っ張ってきたか、そのことも含めて世界中にカズが落ちたというニュースが伝わっています。こうした人間(カズ)に対する扱い、ケアについて、実に不本意であり不愉快であります。
Q.カズさんは16年間サッカーを続けてきて、勝つために君が必要だと言われてずっとやってきて、今回は勝つために君は必要ないと言われた、この一言でいま挫折感を味わっていらっしゃいますか?
A.カズ・三浦知良選手
別にこういうことは初めてじゃないんで、ブラジルでもイタリアでも海外に出ていた時は、割としょっちゅう言われたし、特にブラジルでまだ10代でブロの世界がわからない時でしたけど1試合出て結果出せなかった時は、そのあと半年以上、紅白戦すら使われない時もあったし、それに比べれば、まだまだサッカーもやらせてもらえるし、ヴェルディでも戦えるし、日本代表の道だってまだまだ残っているし、そういう意味で、自分では挫折感とかは持たないようにしています。
カズ・三浦知良選手と北澤豪選手の帰国会見のあと「カズ落選問題」の議論は、ますますヒートアップしました。中には「カズ・三浦知良選手と北澤豪選手という人間の尊厳を傷付けたやり方ではなかったのか」というところまで踏み込んだ意見もありました。
スポーツジャーナリストの二宮清純氏、岡田監督の選考方法を口を極めて批判「こんなやり方は、非情なる決断でも勇気ある決断でも何でもない、単なる優柔不断、冷酷ですよ。」
カズ・三浦知良選手と北澤選手の帰国会見は午前でしたから、その日の午後のテレビ・ワイドショー系番組はさっそく、その模様を詳しく伝えました。
そんな中で特に口を極めて岡田監督のやり方を罵ったのが、スポーツジャーナリストの二宮清純氏でした。二宮氏は6.5放送の日本テレビ「ザ・ワイド」にゲストコメンテーターとして出演し、司会の草野仁キャスターの「今のところの皆さんの一般的な声は、これほどのサッカーの功労者・カズ選手をああいう形で落とすのはひどいじゃないかという感情も含めた意見、もう一つは、監督の方針に沿って論理的に選手を選んでいくことを考えれば、これは当然の判断だという意見が、交錯して結構大変な状況になってるようですが?」という問いに答えてこう述べました。
「誰を選ぶか、誰を落とすかについては監督の権限があるわけですから、私は感想はありません。」
「けれども、首の切り方というんでしょうか、マスメディアでは岡田さんの決断を『非情なる決断』とか『英断』とか『信念の決断』とか言ってますけど、こんなの大嘘ですよ。優柔不断なだけですよ。早めに22人にすればよかったんですよ。この決断の遅さ、優柔不断さ、決断できなかったわけですから。それがこういう騙し討ちみたいな形になってしまったわけですから。」
「私は同情論から彼ら(落ちた2人)を弁護しているわけではなくて、今回の岡田監督の見込みの甘さを言いたいんです。彼(岡田監督)はこう言ってるんです。『カズと北澤については予想以上にショックが大きかった、私の見込みが甘かった』と。」
「私の見込みが甘かった、と言ってますけど、ワールドカップのメンバーから外されるというのはサッカー選手にとっては死刑宣告と同じですよ。死刑宣告しておいて、予想以上にショックが大きかった、私の読みが甘かったと言ってるんです。この程度の読みしか出来ないしか出来ない人がワールドカップ戦えますか? アルゼンチン戦どうやって戦うんですか? この岡田監督の優柔不断さ、決断できないから人を傷付けてしまった。これは人間の尊厳にかかわる問題ですね。ボクは今回のことに関しましてガッカリしました。」と、一気にまくし立てるように答えたのです。
そして、まだ言い足りないと思ったか、続けました。
「おそらく岡田さんは早くからカズ、北澤あたりは必要ないと思ってたと思います。であれば早くから22人にしておけばよかったのに、テストマッチにも使わずに『彼(カズ)の国際的な経験が必要だ』とか思わせぶりな態度で、最後にこれです。騙し討ちですよね。」
「江戸時代でさえ、公儀介錯人が政治犯の首を斬る時は、黙祷して首に水をつけて斬るわけですよ。この人(岡田監督のやり方)はね、騙し討ちですよ。他の残った22人の選手たちも、もの凄く精神的なショックを受けてると思いますよ。これは『非情なる決断』ではなく単なる『非礼なる決断』!! 冷酷ですよ。何も弁護することありません。」ぴしゃっと断じました。
あまりの厳しい内容に、草野仁キャスターが話を少し柔らかくしようと思ったか、
「これは前にこのスタジオでも出た話なんですが、アメリカ代表あたりは、まず20人だけ選んでおいて、あとから2人を追加して、彼らを迎える形でまとまって現地に向かうというやり方をしている国もあるようですが、日本のやり方は極めてマイナス影響を及ぼす形になってしまったようですね。」と繋ぎました。
二宮氏の舌鋒は続きます。
「日本はマラソン代表の選考もそうですけれど、選ぶのがヘタなんですよ。岡田監督は、必要ないんであれば、5月にキリンカップのメンバーを選ぶ時に『カズ、もうお前の力衰えたから、悪いけど、ここは身を引いてくれ』と言ってれば、ここまで問題はこじれなったと思うんです。それが、さきほども言いましたように『お前の国際経験は必要だ』と思わせぶりな態度で連れて行って、二階にあげてハシゴを外すようなやり方でですよね。」
「カズと北澤が偉いと思ったのは、岡田監督に対して不平不満を一言も言いませんでしたよね。彼ら立派ですよ。他の選手に影響を与えたくないとか、彼らなりの精一杯の態度ですよ。岡田監督一人だけ、やってることが子供ですよ。単なるわがままですよ。」
二宮氏の岡田監督批判は果てしなく続きそうに思われたところで、草野キャスターが遮るように言いました。
「どうなんでしょうね、これは穿った見方かも知れませんが、三浦知良選手を外すということは、彼自身がこれまで築いてきたことや、いろいろと支持してくれる人たちのこと、さまざまな影響力の大きさから言って、なかなかこれは(外すことは)難しいことで、それを先送りしてしまったという見方もありますが・・・」
それに対して二宮氏は、
「昨年、ジョホールバルの(アジア第3代表決定戦の)時、カズと中山を外して呂比須と城を入れました。これは素晴らしい決断でした。けれども今回のことは、それとは全く別問題なんですよ。さきほども言いましたけれど、死刑宣告するならするで、そのやり方、礼儀というものがあるんですよ。カズが功労者だからということではなくて、一人の人間に対して、それだけの優しさとか、それだけの思いやりを持っている人が代表監督になるべきで、この人(岡田監督)にはまったくそれがありませんね。ただ冷酷なだけです。それを『非情なる決断』だとか『しょうがないこと』とか『立派な決断』であるとか・・・。メディアも一体何を考えているのか・・。」
次に、草野キャスターが「日本サッカー協会の対応はどうなんですか、結果的には岡田監督にいろいろなことを押し付けた形になっているんじゃないかという声も出ているようですけれど」と問うと、二宮氏は、
「それもありますね、岡田監督が昨年、日本代表の危機を救ったということもあって、日本サッカー協会も岡田監督に強く言えないところがあると思うんですね。」
「それにしても岡田監督はですね、ボクは指揮官としても甘いと思うんです。岡田監督は『25人から3人外しても明るい雰囲気でやれると思っていた』と言ってるんです。ワールドカップというのは武器のない戦争だって言われているぐらいの厳しい戦いですよ。ピクニックに行くんじゃないんですからね、この優柔不断さ、一体何なのかって思いますよ。」
草野キャスターが話しをどう振ってみても、二宮氏のコメントは、やはり岡田監督批判に結びついてしまいました。
ここで、かつてNHK-BSで「Jリーグダイジェスト」のキャスターを務めた経験があり、現在は草野仁キャスターのもとでサブキャスターを務めている勝恵子さんが、かつてのサッカー知識を生かして口を開きました。
「日本サッカー協会のサポートということを考えると、例えば最初に20人を選んで、あとで2人足すという方式でしたら、代表選手はどんどん国際試合を消化していって、国内でいい選手を見る他の協会スタッフがいればよかったと思うんですね。そういう人がいれば現地に行っている岡田監督と連絡を取り合って、足していくという方法もあると思うんですが、結局は、そういう体制にしようという考えが、サッカー協会にも岡田監督にもなかったということですかね? 」
これに対して二宮氏は、
「そういうサポートを、今のサッカー協会に望んでも無理なことでしてね。なぜなら、協会幹部の一人が『カズは選ばれるだろうね、ここまで来て落されるわけないよ』なんてことを平気で言っていて、落ちたあとに『岡田監督の勇気ある決断に拍手を送る』とか言って、とにかく支離滅裂なんですよ。ですからサッカー協会にはあまり期待しないほうがいいと思いますよ、本当に。」
二宮氏の大舌鋒会もそろそろと見たのか、草野キャスターが「二宮さん、これはスポーツ界全体に言えることだと思うんですが、このあたりで選手を決める際の、ちゃんとした尺度の設け方、あるいは、こういうものに対するシビアなものの見方というのをスポーツ界全体として形作っていく方向性が必要だと思うんですが・・・」と問うと、二宮氏は、
「まさにおっしゃるとおりで、今回のこともカズに対する同情論の問題ではなく、決定システムをもっとガラス張りにすることだと思うんですよ。こういう決め方をしているから、いろいろな穿った見方が出てくるんであって、サッカー協会も今回のことを教訓に、もっとガラス張りにするよう、エりを正してもらいたいですね。」
ということで、やっと話のオチがつきました。
岡田監督の「恩師」が辛い決断の胸のうちを代弁「私情を捨てて『鬼』になって切った」
このように、この番組では岡田監督批判一色だったかのような趣きでしたが、実はそうではなく、岡田監督は決して優柔不断でこうしたのではない、彼は外したくないカズを悩みに悩んだ末、まさに断腸の思いで切ったんです」と擁護する方がいました。
それは岡田監督が「恩師」と仰いで指導を受けている作家の濤川(みなかわ)栄太さんでした。
「カズの力、カズのスター性、カズの存在感、それから世界における名前の重さ、そういったことを一番よく知っているのは岡田ですからね。」
「そしてカズを一番好きなのは岡田じゃないですか? とにかく(カズを)誉めてましたね。『あれほど練習熱心な男はいない』と。確かに全盛期に比べれば、ちょっとパワーは落ちてきてますけど『カズの単なるプレーヤーの部分だけじゃなくて、チーム全体に対する、いい意味での影響力、これが物凄く大きいんだ』と」
「だから、カズを外したくないんだという気持ちが私にはビンビン響いてきましたね。だから岡田は、個人的な『情』だけで言ったら、絶対カズを使いたかったと思う。カズが衰えても使いたいと・・。」
「だけど、私情を捨てて『鬼』になって切ったんでしょうね。」
「岡田君はおそらく、(ワールドカップ)の第1試合、アルゼンチン戦の試合開始のポイッスルがなる瞬間まで、どうやったら勝てるか考え続けると思います。」
「その中で、A案、B案、C案、D案といった戦略戦術案があったんでしょう、スイスに行くまでは当然カズは戦力として入っているから連れて行ったんで、切るために連れてったんじゃないです。」
「それがスイスに来て、いよいよ緊迫してきて、試合の直前の段階になって軌道修正していく、そして彼は、最後の作戦をたてたんでしょうね。」
「こういう戦略でいく!! その大戦略を決めた時に、その作戦のためにはカズより、別な選手を使おうと考えたと思うんです。決してカズを否定したわけでも何でもなく、作戦の中でより良い駒を使わなければならないという、勝負師としての究極の判断ですよ。」
今回の問題は「監督と選手のサッカー文化の土壌の違い」とする意見あり「日本型企業社会が「サッカー型企業社会」に変化していく先駆け、とする意見あり
以上のように岡田監督の「カズ外し」を「単なる優柔不断、人間の尊厳にかかわる冷酷なやり方」と厳しく批判する意見と「いやいや、岡田監督は、個人的な『情』だけでいったら絶対使いたかったカズを『私情を捨てて『鬼』になって切った』」と胸の内を代弁する意見が交錯する、極めて根深く思える議論がなされた一方、「カズ落選」の出来事を監督と選手のサッカー文化の土壌の違いと分析したコラムや、「カズ落選」の出来事を「日本型企業社会」が「サッカー型企業社会」に変化していく先駆け、と分析したテレビ番組がありましたので、それをご紹介します。
98.6.24号サッカーマガジンコラム「ビバ! サッカー」サッカージャーナリスト・牛木素吉郎氏、「カズ落選」は岡田監督とカズ選手のサッカー文化の土壌の違いによるもの
「『これも一局の将棋』という「ことば」があるそうだ。(中略)ある局面で飛車を動かしたとして、それで1局の将棋が進行する。しかし、その場面で角を動かす手もあって、そう指したとしても、それはそれで勝負になる。その後の展開はまったく違うものになるけれども、こちらも『一局の将棋』だというこどある。(中略)」
「岡田監督は、カズのいないチーム作りを構想した。それはそれで間違ってはいない。しかし、カズを入れたサッカーを構想することも可能である。それはそれで『一つのサッカー』である。」
「どちらかが正しく、一方は間違っているというものでもない。どちらも成り立つが、指し手がどちらを選択するかである。」
「岡田名人はカズのいない指し方を選択した。それでいい。結果は対局者の責任である。(中略)」
「誤解を恐れずに端的に言えば、岡田監督はパスとチームワークのドイツ型を選択した。しかし、カズを軸にチームを組み立てれば、ドリブルと個人技のブラジル型のサッカーになる。選択肢としては、これもあり得る。」
「ドイツの文化とブラジルの文化の違い、岡田監督のサッカー文化とカズのサッカー文化の違い、というのはこじつけに過ぎるだろうか。文化の違いに『価値判断』を持ち込むのは適当でない。(中略)」
「代表選手に選ばれるのは『名誉』ではあるが、選ばれなかったのは『不名誉』ではない。監督と価値観が違っただけのことである。」
98.6.8 TBS新サンデーモーニング キャスター関口宏、アシスタントキャスター中江友里、有村かおりアナウンサー、ゲスト元日本代表・加藤久氏、諸井虔・秩父小野田㈱会長ほか、「カズ落選」は日本型企業社会が「サッカー型企業社会」に変化していく先駆けか
この日の「新サンデーモーニング」は、朝8時の番組開始早々、毎週恒例の「今週一番気になったニュースは?」という街の声を拾うコーナーから始まりましたが、関口キャスターも「圧倒的、9割近くがカズのことに関心があるという声でした」と驚き、この問題に53分もの時間を割いて、次の3点に焦点をあてていきたいと紹介しました。
①密室の通告をカズはどう受け止めた?
②岡田決断は非情な采配? その称賛と誤算
③到来! サッカー型社会とは?
このうち①と②について他の番組同様、さまざまな憶測、意見が交錯していることを紹介したあと、③到来! サッカー型社会とは? について長い時間を割きました。
同じTBS系の夜のニュース番組「ニュース23」の筑紫哲也キャスターが「実は世の中がそういう時代になっているということを、スポーツって、しばしば象徴的に示すんですね。」とコメントしたところを引いて、サッカーの世界に起きたことが、企業社会において、長年培ってきた「日本型」がいま、いや応なく押し寄せるグローバルスタンダード・世界標準の波に突き崩されている状況に重ね合わせ「『カズ』『サッカー』がいま日本に突き付けるのは・・・」というナレーションを付けました。
番組は、街頭インタビューの中にあった「ボクもカズと同じ年代なんですけど、いくら実績があってもダメな時は切られるんだ、日本にもとうとうそういう時代がやってきたんだ。」という反応に着目しました。
また経営者向け月刊誌「プレジデント」が、これまで表紙には経営者や各界のリーダーの顔を載せていたが、今月号は中田英寿選手を表紙に、本文特集では作家の堺屋太一氏と岡田監督が「勝てるリーダーの条件とは」というテーマで対談を掲載して、同誌の神田久幸編集長の「日本の企業社会もサッカー型に変わっていくのかな、という視点で企画しました。」という話しを紹介しました。
ゲストの諸井虔氏が意見を述べました。
「これまでの日本社会における経営のあり方というのは『全員経営』といいますか、みんなでお神輿担いでいくようなやり方でした。みんなで同じ方向を向いて頑張る、あまりチームワークを乱すようなことはしない。経営状態が悪化して何か手を打たなければならない時でも、社員を1割カットしてしまうやり方はせずに、全員の給与を1割カットするというやり方をとってきました。」
「しかし、最近になって『日本の経営者には戦略がない』と言われ、ワイワイみんなで議論していくうちに方針が決まるというやり方をしていることが指摘されています。あるいは決断できない、責任をとらないといった点も海外の経営者と比べて言われるようになってきています。」
「いままでは、どの会社も本業を中心に右肩上がりで成長できました。終身雇用や年功序列を維持しながらできました。しかし、これからは場合によっては本業を投げ打ってでも新しいことを始めなければ、国際競争の中で生き残れない時代に入ってきています。」
「そうなると社内のこれまでの人も仕組みも全部入れ替えなくてはならない、という場面が出てきます。その時、経営者は会社を守っていくためには相当非情なことを決断しなければならなくなります。」
番組はこのあと、厳しい国際競争社会の中で、生き残っていくためには経営者とともに、それぞれの社員たちの行動も変化を求められているとして、月刊プレジデント誌、評論家の堺屋太一氏と岡田監督の対談内容から引用しました。
岡田監督「サッカーでは、どこへ走っても、どこに蹴ってもいいが、だからこそ、どこへ走るか、どこへ蹴るかを自分で判断するしかない。ですから自分で判断させずに型にはめていくとプレー中の状況判断まで鈍くなってしまいます。」
「サッカーチームというのは、ある程度型にはめると一定レベルまでポーンと伸びるんです。ところが、そこから先は全然伸びなくなるんです。」
堺屋太一氏「日本の経済も、これまで役所が主導して、日本社会全体に同じ教育をして、みんなが欧米のまねをしてきて先進国の中レベルまでは来たわけです。ところが、そこから先、世界のトップレベルまではいけない現実にあります。今の日本の経済状況は、(型にはめたサッカーチームと)そっくりだと思います。
ここで、企業経営に関する専門家である日本ビジネスマン研究所の西山昭彦所長が、企業経営の環境変化について、
「これまでの日本の企業経営は、さまざまな規制に守られて、その枠の中で、一つひとつの局面でいちいちサインを出したりベンチが指示を出しながら進めていく『野球型経営社会』でしたが、これからは金融ビックバンに見られるような国際競争社会、すなわち完全自由競争社会、これは、サッカー日本代表と同じです。何をやってもいいけれど、勝つためには監督はもちろん、選手一人ひとりが、その場面場面でベストの判断をしなければならない『サッカー型経営社会』になっていくと思います。」
「今後、世界で戦うためには、企業経営においては特に『経営判断のスピードと、瞬時の的確な判断力』が要求されます。例えば一つのマーケットが生まれた時、それをいち早く取りに行くスピードを考えた時、これまで日本がやってきた、稟議とハンコの手続きをそのままやっていたら、電子メール1本でゴーサインが出る企業に勝てっこないと思います。」と解説しました。
番組はサッカー日本代表の中田英寿選手が「自分にはお手本はいらない」と語っていることにも着目、「彼は型にはめられることを嫌い、自分の瞬時の判断の確かさを信じて日本代表の中心選手になった。」と、企業社会でも、能力の高い人であれば若くても評価され登用される社会になっていくのかも知れないと示唆していました。
この堺屋氏と岡田監督の対談、西山所長の解説等を受けて諸井氏が発言しました。
「決断力、判断力そして、そのスピードの問題は経営者だけのことではなく、社員一人ひとりもスピードと判断力を高めていかなければならないということになります。日本代表では、岡田監督が大きな作戦をたてますが、試合の中では、中田英寿選手のように、一人ひとりが瞬時に判断していかなければならないわけで、企業社会でも社員一人ひとりがそれをやっていかなければならない。社員一人ひとりまで判断力を高めていかなければならないとなると、これは、ずいぶん時間がかかるなぁと感じました。」
最後に関口キャスターが「日本もだんだん『サッカー型経営社会』に変わって、確かに欧米に追い付いていくのかも知れませんが、なんか、これまで日本の企業経営が大切にしてきたもの、できるだけ仲良くとか、社員を守っていくというような風土が失われていくような気がするんですが」と振ると、
諸井氏が「これまでの日本はある意味『悪平等社会』に過ぎるようなところがあって、格差をあまりつけない社会でした。それをアメリカのような超格差社会にしてまっていいのかと言えば、そこまではしたくない、日本とアメリカの中間ぐらいのところがいいのではないかと思いますし、そういうビジョンははっきりしておかなければならないと思います。」と述べました。
このように、ちょうど、右肩上がりの成長を続けた日本経済が曲がり角を迎え、厳しい国際競争社会の中で生き残りを賭けて戦っていかなければならないこの時代、サッカー日本代表選手の生き残りを賭けた様子や、試合における選手の瞬時の判断の様子は、これからの日本の企業社会の姿の先駆けとなっているのではという視点に立った番組でした。
社会現象となった「カズ落選問題」、明快だった岡田監督の本心と、未経験の監督が招いた見通しの甘さ
6月2日のカズ・三浦知良選手の落選発表から、6月5日の帰国会見とその後の新聞・テレビなどの報道は、連日、各界各層の反応・意見を織り交ぜながら、繰り返し、その経緯を詳細に伝え続けました。
その中には、ヴ川崎関係者もありJリーグ関係者もあり、一般文化人・芸能人もあり、サッカーライターなどの専門家も数多く登場しました。
ヴ川崎関係者にはニカノール監督、ラモス瑠偉選手、柱谷哲二選手などの現所属の人に加え都並敏史選手のように、現在は別のクラブにいて、かつてカズ・三浦知良選手や北澤豪選手と長くプレーした人も含まれていました。
そのため議論は感情論も含めて、さまざまに入り乱れ、何が真相で、何が問題だったのかわからなくなるほど混乱しましたが、5月7日の25名発表から6月2日の3選手の落選発表まで、岡田監督が一貫して述べて来た内容を虚心坦懐に聞いていれば、岡田監督の本心は極めて明快だったことがわかり、なぜそういう判断をしたのかを考えれば、結局、岡田監督が昨年、加茂監督の後任として代表監督に就くまでは、どのカテゴリーの監督も経験したことがないのに、いきなり代表監督になってしまった、その経験のなさが招いた見通しの甘さによるものであることが明確にわかります。
その点を、はっきりと書き残しておきたいと思います。
岡田監督が選手選考で持っていた、極めて明快な本心
岡田監督は、25名を決めた5月7日から、繰り返し「25人でワールドカップを戦うんだ。」という言い方をしていました。この真意は「3人外れる選手はいるが、この選手にも残ってもらってワールドカップを戦う、自分の中ではあくまで25人で戦うんだ」という意味だったのです。
そのために、ベンチに入れるようにするためのスタッフ用のIDカードの手配や、滞在中の日当やボーナスなどの待遇面も抜かりなくしていたのです。サッカー協会は、試合に出ない選手に日当やボーナスは出せないということなので、岡田監督が自分のポケットマネーを出すことにしたいたのです。
一方で必ず、カズ・三浦知良選手のことを「単に技術や技だけではない形でチームに貢献できる選手だ。その意味で欠かせない。」と付け加えていました。
これを繋ぎ合わせると、岡田監督が代表選手の選考にあたって決めていた、極めて明快な本心が浮き上がってきます。
すなわち「最後は3人を外さなければならないということで、最終的にカズを外すことになったけれども、チームに貢献できる選手なので、そのまま帯同してもらいたい。カズは、そうしてくれると思う。」
そう本気で信じ切ってニヨンまで言い続けてきたのです。決して優柔不断だったためでも、最初から決めていて、騙す気持ちだっためでもなく、本気で「カズであっても22人から外れれば、25人として残ってもらえる」と考えていたのです。
ところが、岡田監督がカズ・三浦知良選手に最後通告してみたら一旦戻ったものの「帰らせてもらいます」という答えでした。残ってくれるとばかり思っていた岡田監督は、自分の見込み違いに気づきました。
ただ、岡田監督がいくら会見で「3人外れる選手はいるが、この選手にも残ってもらってワールドカップを戦うつもりだ」という話と「カズは、単に技術や技だけではない形でチームに貢献できる選手で、その意味で欠かせない。」という話をセットで繰り返し話しても、当のカズ・三浦知良選手が「あぁ、これは『外れるのはカズだけど、そのあとも帯同してくれよ』というメッセージだな」と感じなければ、何の効果もないし、メッセージとして受け取って欲しいと期待すること自体、無理な話です。
むしろ、カズ・三浦知良選手は、岡田監督がしきりに会見で言っているその話を見聞きして「試合に出る可能性は限りなく少なくなったかもしれないな。でも22人に残れればワールドカップメンバーという夢は実現できるから」と解釈していたと思いますから。
岡田監督が「自分の見通しが甘かった」と吐露した真意
岡田監督は3人の落選者を発表した会見で「自分の見通しが甘かった」と肩を落としながら吐露しました。その真意は、ここに至るまで自分が、カズ・三浦知良選手や北澤豪選手の胸のうちを察することができなかった、その見通しの甘さを思い知ったという意味です。
岡田監督は、カズ・三浦知良選手や北澤豪選手に、日本にいる時から「22人から外れることがあった場合でも、精神的支柱として25人とて残ってもらいたいんだけれど、いいか?」と腹を割って話しをしたことはありませんでしたし、そうする気持ちが頭になかったのです。
セルジオ越後氏や二宮清純氏などが「フランスに向かう前に決めておけば、こんな騒ぎにならなかったのに」と口を揃えていますが、岡田監督は「3人は外すけれど、その選手も一緒にフランスでやるんだ」という気持ちしか持っていませんでしたから「フランスに向かう前に決めておいたほうがいい」という発想が湧かなかったのです。
カズ・三浦知良選手に外れることを通告すれば「22人から外れるのであれば、代表メンバーではないんだから、残るのは勘弁して欲しいし、外れた人間が帯同してしまえば22人にも余計な気を使わせると思う」という話になるとは考えていなかったのです。
むしろ「わかりました、外れてもその役割で帯同しましょう」と言ってくれると思い込んでいたのです。
それまで、ずっと、そういう気持ちで会見もしてきたものですから、やれ「思わせぶりな言い方をしておいて」とか「二階にあげてからハシゴを外すようなやり方で」とか「25人みんな仲良くやっていきましょうなんて、子供のビクニックみたいなことを・・」といった集中砲火を浴びることになったのです。
では、なぜ、そんな集中砲火を浴びるようなことをしてしまったのか。普通に考えれば不思議でしょうがない変なやり方を、なぜ、してしまったのか。
それは岡田監督が、ここまで、どのカテゴリーの監督もまったく経験したことがない監督未経験者だったからです。そういう人がいきなり日本で最高の経験と技術を持つプロフェッショナル集団の、日本代表監督になってしまったからです。
二宮清純氏が言っていました。「ジョホールバルの時のカズと中山の2枚替え、これは素晴らしい采配でしたけど、今回はそれとはまったく違うんです。」
ところが岡田監督は、そこが理解できていませんでした。ピッチから選手を途中交代させるのと同じ程度の気持ちで最終メンバーから外してしまったのです。
しかも岡田監督としては、22人から外れても一緒に帯同してもらってチームの精神的支柱になってもらいたいと本気で思っていて、6月2日にそれを通告しても大丈夫だと思っていたのです。
カズ・三浦知良選手にとってのワールドカップが、自分のサッカー人生の究極の目標であることを、岡田監督は知識としては知っていたかも知れませんが、その目標を取り上げることが死刑宣告と同じなんだとは思っておらず、チームに帯同してフランス大会に残ってもらうんだとしか考えていなかったのです。
岡田監督は「これほどショックが大きいとは思わなかった。僕の見込み違いだった。プロ選手だから受け入れてくれて、そのあともチームに帯同してくれると思った。」と言っています。
実はショックが大きかったのは岡田監督自身だったと言っていいでしょう。カズ・三浦知良選手にとっての「ワールドカップ」がどういうものか何もわかっていなかったと気づいた自分自身に対してショックだったのです。これまで一度も監督という立場を経験したことがない人ですから、死刑宣告をどうやってすべきかについても何もわかっていなかったのです。
それが、まったく監督を経験したことがない未経験者の思考なのです。監督として、一度でも選手を何かの大会のメンバーから誰かを外すという決断をしたことがある人であれば、よほど用意周到に、その選手の心を傷つけないようにしないと大変なことになるということを骨身に沁みてわかっています。
そこが岡田監督の最大の弱みであり、よりによって、社会的関心が最大限に大きい今回、それを暴露してしまったのです。
カズ・三浦知良選手と北澤豪選手から「残るか帰るかは考えさせてください」と言われ「30分ぐらいしか時間がないから、それまでに返事をくれ」と一旦帰したあと、二人から「日本に帰らせていただきます」という返事をもらいました。
「そうか、25人のままフランスに入ることができなくなったな」と思っていた矢先、フラビオコーチが岡田監督のもとを訪れます。
フラジオコーチから「カズ・三浦知良選手、北澤豪選手は、自分のサッカー人生の集大成のつもりでワールドカップメンバーに入ることを目標にして頑張ってきた選手たちだ。その選手たちを最後の土壇場で外された。それはそれでいいけれど、本人たちは、このまま帯同することが、他の選手たちに余計な気遣いをさせ、かえって迷惑をかけると思うから、チームを去ったほうがいいと判断している。」といったようなことを言われたに違いありません。
選手たちのフィジカルコンディションだけでなく、精神的なケアにも心を砕いてきたフラビオコーチからそう言われて、岡田監督は、自分の見通しの甘さを思い知ったことでしょう。
これまで「ディフェンシブな戦い方の戦術を25人で練り上げ、最後は3人外れてもらうけど、そのままフランスを戦うんだ。外れたから帰りたいというなら帰れ」と考えてきたことがまるで甘い考えで、むしろ、カズ・三浦知良選手や北澤豪選手は「落ちた自分たちが帯同していることで、22人に余計な気を使わせてしまう」と考えていたのです。
岡田監督は、自分がそこまで思い至らなかったことに、フラビオコーチの訪問を受けて、言われて初めて気づいたのです。
それまで岡田監督は「日本代表監督は孤独です。結局誰にも相談できないんです。最後は自分で決めなきゃならないんです」という固定観念に縛られて、自分の考えていること、やろうとしていることが真っ当な判断なんだろうかと自問することなく、突っ走ってしまいました。
自分が何の監督経験もなく日本代表監督になったことで、経験から来る智恵や判断の確かさといったことが、まだ備わっていないのではないかと自戒することなく、とにかく自分一人で決めなきゃならないんだという信念に固執して、「25人を選んで、そのままフランスに全員で乗り込んで戦う、いやだと思うヤツは帰れ」というぐらい、自分が描いたロジックに何の疑問も持たずに6月2日まで引っ張ったのです。
「25人を選んだのは、ディフェンシブに戦う戦術を、可能な限り多くの選手に共有してもらって、いざ本番の時にその戦い方が破綻しないようにするため」だったはずですが、最後は「25人でフランスに入るんだ」ということだけが自己目的化してしまったのです。
ところが、いざ、本人たちに通告して初めて「あれ、自分の描いたロジック通りにいかないな」と感じ、そのあとフラビオコーチの訪問を受けて、自分の描いたロジックが、とんでもない甘いロジックだったことに気づいたのです。
その後、その見通しの甘さが引き起こした社会の衝撃の大きさに驚いたことと思います。
これまで疑いをもたなかった自分のロジックが甘かったことを思い知らさせてショックを受けたせいかどうか、岡田監督は落選者発表会見でも失敗を重ねています。
それは、カズ・三浦知良選手、北澤豪選手たちが帰国することに決めたことについて「俺が帰したことにするから」と打ち合わせたまではよかったのですが、会見で「(彼らが)想像以上にショックが大きかった。影響力が大きい選手だけに、チームにマイナスになると思ったので自分の判断で帰すことにしました。」と言ったのです。
カズ・三浦知良選手や北澤豪選手が帰ることを決めたのは「落ちた自分たちが帯同していることで、22人に余計な気を使わせてしまう」と考えたからです。岡田監督も、それを会見で言ってあげるべきでしたが、そのことに気が回らなかった自分に対してショックを覚えたあまり「彼らのショックが大きかったので」という言い方をしてしまったのだと思います。
強い日差しを浴びながら、立ったまま会見していた岡田監督は、遠目からは淡々として受け答えしているように見えましたが、間近にいた記者たちには、目は充血して、顔は引きつって、怒ったような表情に見えていたそうで、実際のところは、ある種パニックの心境だったと言っていいでしょう。それを務めて表情に出さないようしながら受け答えしていたのかも知れません。
岡田監督は、論理的に考え最適解を見出す思考能力の高い人です。そして、それに基づいて導き出した考えを貫く信念の強さも持ち合わせた人です。
だからこそ、前年秋のアジア最終予選の過酷な状況でも冷静さを失わず、針の穴を通すような難しいミッションを成し遂げられたのだと思いますし、その功績はいささかも貶められることはありません。
一方で、加茂前監督も誉めていた岡田監督のその「信念の強さ」ゆえ、時として自分が組み立てたロジックの陥穽に陥ることがあります。ですから、そのロジックに破綻が生じ、裏目に出た時には、惨憺たる結果を招くことを、図らずも露呈してしまったのです。
サッカーマガジン誌・伊東武彦記者は「(カズ・三浦知良選手と北澤選手の落選について)岡田監督の胸中にあったものは、戦いのすべてが終わるまで明かされることはない。」と、岡田監督の胸中を推し量ることは留保していましたが、上記のように明快だった本心と、監督未経験のため招いた見通しの甘さを岡田監督に確認すれば「そのとおりです」と追認するに違いありません。
昨年、加茂監督更迭のあとを受けて1試合限定で指揮をとったあと、国内のサッカージャーナリストたちは一斉に「これまで、どのカテゴリーの監督も経験したことのない人を、そのまま代表監督にするなんてあり得ない」と論じました。その人たちは、その後、ここまで沈黙を余儀なくされてきましたが、今回の「カズ外し」問題を見て「それ見たことか、言わんこっちゃない。だからダメなんだよ。日本サッカー協会は・・」と感じていることでしょう。
残念なことに、もはや岡田監督とともに動いている時計の針を元に戻すことはできなくなりました。時すでに遅しなのです。返す返すも残念です。
何といっても、その時の空気としては「ワールドカップ出場権獲得」という史上初の偉業を名成し遂げた岡田監督を降ろすわけにはいかないだろう」という空気が支配的でした。
仮に日本サッカー協会がワールドカップ本大会仕様の新監督探しを始めたとして「この人ならワールドカップ本大会監督としてふさわいのでは」という人を据えるところまで持ってくるのは、時間的に難しいだろうということもありましたから、なかなか強く「新監督を」と主張しにくかったこともあります。
けれども、やはりワールドカップ本番を戦うというのは、アジア最終予選の比ではないのです。並みの監督でさえも国の代表を率いてワールドカップ本番を戦う監督は難しいのです。豊富な経験と知略、それに加えて代表選手たちという強者(つわもの)どもを束ねる人間力を合わせ持った人でないと難しいのです。
どこの国も、自国のリーグなどで多くの成果をあげた、誰もが認める人が選ばれるべきもので、ましては、どのカテゴリーの監督経験もない人が、いかに今回出場権を獲得したからといって、情に流されて、そのまま選ばれるべきものではないのです。今回のカズ・三浦知良選手外しの出来事が、そのことを照明しました。昨年11月以降、少々時間がかかっても選定すべきでした。ギリギリ遅くても3月のダイナスティカップから指揮がとれるよう2月まで約3ケ月間、選定期間がありました、
ところが、歴史の事実は、そうなりませんでした。
したがって岡田監督とともにフランスワールドカップを戦うことになった日本代表は、そのプロセスで起きることも含めてすべてを受け入れざるを得ない運命(さだめ)にあったと言うべきでしょう。
ここまで「これでもか、これでもか」というほど岡田監督の言動や下した決定について書き綴りながら、一方では「そこまで書き綴る必要があるだろうか」という気持ちも抱いています。
岡田監督には「日本サッカーの歴史」という法廷の被告席に座ってもらって審判を受けてもらっているようなものです。
この時の「敗北という結果」という結果を知っている者の後付けで記述していますし、「将」としての結果責任として記述せざるを得ないという気持ちで記述しています。
歴史に「たられば」はないのですが、もし、違った結果であれば、これまでのような記述にはなり得ないのです。どうしても、こういう時には複雑な気持ちを抱きながら書き進めています。
来たるべき6月14日のワールドカップ初挑戦、その直前に起きた「カズ外し」問題によって、岡田監督をはじめとした日本代表も複雑な思いを胸にしまい込みながら、残りの日々を過ごすことになり、日本全国のサッカーファンも、各界各層も、さまざまな気持ちを交錯させながら、その日を迎えることになりました。
渦中のカズ・三浦知良選手、5月7日の25名発表から6月5日の帰国までの胸の内
5月7日の25名発表から6月5日の帰国まで、新聞・テレビ・サッカー専門誌などの報道を通じてカズ・三浦知良選手の心情を推し量りながら書き綴ってきましたが、三浦知良選手の胸の内は実際どうだったのでしょう。
カズ・三浦知良選手への長期間にわたるインタビューをもとにまとめられた、一志治夫氏の著書「たったひとりのワールドカップ」から引用します。
・4月1日の日韓戦メンバーから外れ、25名発表以降、キリンカップを通じても出場機会がなかったことについて
「僕は、岡田さんは自分のことをよく知っているから使わないのだ、と思っていた。どんな状況になっても、先発だろうが、途中出場だろうが、カズにはこれだけの実績と力があるから、もうここであえて使う必要はない、と。僕とか北澤は、これだけチームに長いし、いつ(ピッチに)入っても別に、戦術も理解してくれているし、戸惑うことはないだろうと見ているのだろうと思っていた。自分が使われていないということに関しては、そういうふうに理解していた。それは外される直前、最後の最後までずっとそうだった。」
・スイス・ニヨンに入ってから、膝の調子が思わしくないのではないかと報じられたりした中で6月1日の地元チーム、スタッド・ニヨンとの練習試合でハットトリックを決め、あとは6月2日の発表を待つばかりとなった頃の様子
「地元チームとの練習試合の2日前の夕方、約100発のシュート練習は、どの体勢からも思い通りの孤を描いて飛んでいった。」
「カズの中では、ワールドカップに向かっていく心身は、万全になっていた。どんな形でも、もし出場できたら、活躍できるという自信があった。三戦のいずれかでチャンスは巡ってくるだろうと、心待ちにしていたのだ。」
・6月2日、3人の落選者発表当日の様子
「僕は、その日、午前11時ぐらいまで寝ていたんです。日本からの電話で起こされた。日本では、(毎日新聞に出たことで)その前の日の夜に部屋に行って、岡田さんと怒鳴り合いになったとか出てたらしいけど、全然そんなことはない。僕、スイスで、それまで岡田さんの部屋に行ったことなんてなかったもの。」
「それで11時40分頃、岡田さんから直接、部屋に電話がかかってきて、『ちょっと来れるか』と言われて、『あぁ、いっすよ』って、そんな感じで行った。そのとき、僕は外す三人が決まって、その三人を帰すか、帰さないかを相談されるのかと思ったんです。」
「岡田さんも、ワールドカップを25人で戦うと言っていても、やっぱり外す三人の立場とか雰囲気とかいろいろあるでしょう。井原にはもう相談して決まっていて、井原には井原の意見があって、俺は俺の意見で聞かれるのだろう、と思った。まさか自分だと思うわけないからさ。それだったら、最初からここまで連れてこないっていうのもやっぱりあったし。」
「それで岡田さんの部屋に行ったら自分だった。」
「でもね、もう岡田さんの部屋に入って、岡田さんの顔を見たとき、そんな他人の相談なんかじゃないと、すぐ思いましたけどね。」
「岡田さんは、外す理由を『三試合を考えて使う場面がみつからない』って言った。それ以上はこっちも何も聞かないし、たぶん岡田さんの部屋には五分もいなかっただろうな。そのまま現地に残るか残らないかを話し合って、岡田さんから『帰るか、残るか』って聞かれたから、『チームを捨てたっていう感じにされちゃんうじゃないか。その帰し方だけはきっちりしててほしい』って僕は言った。」
「それで、『帰るか帰らないか考えます』って、岡田さんの部屋を出た。自分の心の中では帰るって決めていて、考えるって言った時点で帰るつもりだったんだけど。」
「あとは誰が外されたのかってことも別に聞かなかった。」
「やっぱり僕はいろんな意味で岡田さんを信じていたわけだから。僕の力を認めて選んでくれた、こういう風に使いたいと思っているから選んでくれている、と選手は当然思うよね。僕は岡田さんを信じていたし、岡田さんも僕を信じてくれていたと思っていた。でも、そうじゃないとわかったから、もうそれ以上その場で喋ることなんてないでしょう。別に僕と岡田さんの人間関係は終わらないけど、選手と監督としてはいったんそこで切れたわけです。お互いの信頼関係が。」
「岡田さんのことを嫌いになるとかそういう低レベルの問題じゃなくて、この時点における信頼関係は終わりますよね。加茂さんのコーチの時から三年以上一緒にやってきて、最終予選も一緒に戦い抜いたという意識もあるし、自分の力はある程度認めてくれたと思っていたし、だから選んだと思っているし、そういう信頼関係ができたと思っていた。男気を感じてやっているような部分もあった。しかし、そうじゃなかった。それ以上岡田さんの部屋で聞くことも、話すこともないでしょう。」
「僕は淡々としていたと思いますよ。もし、そのときのビデオがあったら見せてあげたい。それぐらい淡々としていた。」
「僕はいつもそうなんだけど、何かを得たときはそのとき喜んで一瞬で消える。優勝したとか得点王をとったとか。」
「だけど、悔しい思いをしたときは、その瞬間は淡々としているけど、家に帰ってからトーンが落ちたりすることが多い。だから、今回に関してはワールドカップを見てて胸が痛むとか、バッショとの(フランスで会おうという)約束が果たせなかったなぁ、とか、自分自身の罪や寂しさを感じる。(中略)」
「それで、僕は自分の部屋に戻って帰る準備をしていたら、キーチャン(北澤)が来て、『カズさんどうするんですか』って言うから、『え、お前(も)か』って。『そうです』『信じられねえよな、お前かよ』って。あるわけないと思っていましたから。」
・落選発表の岡田監督発言について
「岡田さんが『ショックが大きく、帰すことにした』と言ったと聞いて、僕もキーチャンもすごくショックだった。そう言われたことが。『最終的にチームが帰すことにした』でいいんだけど、なんでそういうふうに言ったのかなって・・・・。」
「僕は帰り方というのはすごく大事だと思っていた。大事っていうか、チームを捨てたように思われると嫌だし。僕としては、いままで日の丸のために戦ってきたと言ってたのがね、自分たちが外されたら、じゃあ帰るのかっていうふうに見られてしまったら、っていうのもあった。」
「でも、やっぱり僕たちと市川は違うからね。それは実績も年齢もやってきたことも、彼のいまの立場と僕の立場じゃ違うし、周りの選手たちに与える影響も全然違う。あのあと三週間以上も僕たちがチームと一緒にいることがいいかって言ったら、やっぱり難しいと思うんだよね。周りも気を使うだろうし、やっぱり僕も気持ちを切り替えたいというのもあったし、だから、結局最後は、チームのために帰るということにしておいてほしいということは言ったんだけどね。」
「それが『ショックが大きかったので帰らせた』となるとは思わなかった。」
・帰国会見後のマスコミ報道について
「翌日の新聞には、曲解して、『(カズ)納得いかない、岡田監督に』とか出ていたけど、そうじゃなくて、『納得してはいけない』と言ったんです。」
「自分は誇りをもってやってきて、絶対に力があるって自分を信じて、必要な選手なんだって、そう思ってやってきたわけです。外されたことで『あぁ、そうですか、実力の世界なんだからしょうがないです』という納得は、今回、絶対にしちゃいけないな、ということなんです。」
サッカーに対する飽くなき情熱とそれを支える逞しい身体を維持し続け「現役プロ選手を続けるサッカー人生」に送り続けたいエール
カズ・三浦知良選手は帰国会見で「自分の魂みたいなものはフランスに置いてきたと思っている」と名言を吐きましたが、「ドーハの悲劇」に続く今回の「ニヨンの悲劇」、この2度の悲劇を乗り越えて、その後も長年にわたってサッカーに対する飽くなき情熱を失わず、それを支える逞しい身体を維持し続けて、現役プロ選手生活を続けるカズ・三浦知良選手のサッカー人生に、私たちは、ただ、ただエールを送りたいと思います。
歴史を知ってしまっている者の「後付け」という誹りを受けることを承知で言うと、カズ・三浦知良選手が、現役生活を辞めようとしないのは「ドーハの悲劇」を乗り越えて、今度こそはワールドカップの舞台に立てる、夢が結実すると信じていた自分のサッカー人生が、今回の「ニヨンの悲劇」の落選によって、一生消えない痛恨事となってしまい、カズ・三浦知良選手のサッカー人生を、出口の見えないジャングルの中に迷い込ませているからではないかと思ったりもします。
カズ・三浦知良選手は、サッカー選手生活を続けているとはいうものの、その出口、終着点がどこにあるのかわからなくなったまま続けているのではないかという意味です。
けれども、それは、歴史を知ってしまっている者が「後付け」で悲劇の主人公を作りたがって描く妄想に過ぎないことです。
ただ、カズ・三浦知良選手というサッカー選手が究極の悲劇の主人公になり得るストーリーを歩んできていることも厳然たる事実です。
なぜなら、カズ・三浦知良選手というサッカー選手は、プロになってワールドカップという舞台に出ること、日本代表をワールドカップに導くことだけをサッカー人生の目標にしてきた選手です。そのためにブラジルに渡り過酷な環境、条件に耐えてプロ契約を勝ちとり、日本代表をワールドカップに出場させるためにブラジルでのプロ生活を切り上げ日本に戻ってきた選手です。
そして1993年「ドーハの悲劇」によって一度は夢を絶たれたものの、捲土重来、4年後に夢を結実させるところまで辿り着いた選手です。ワールドカップ開幕をあと2週間ほどに控えたところで直前合宿地のスイス・ニヨンまで来ることができた選手です。その選手が、まさしく最後の最後で代表から外されてしまったのですから、これ以上の痛恨事はありません。もうワールドカップの舞台に立つチャンスが巡ってこないことは年齢的に明白ですから。
まさに土壇場の土壇場というドラマ仕掛けのようなタイミングも一層、痛恨の深さを大きくしたと思います。
これがもし4月1日の日韓戦に呼ばれなかったことに続き、5月7日発表の25名にも呼ばれなければ、確かに痛恨の深さが浅くなった可能性があります。けれども、カズ・三浦知良選手は自らを信じ続けて4月1日以降も、試合に練習に全力を尽くし続けます。それが25名の中に入った要因かどうかは定かでありませんが、とにかく25名の中に入ってしまったのです。
そのため、最後の最後、土壇場の土壇場で外されるという衝撃的なことが起きてしまったのです。
そのタイミングであったことが、カズ・三浦知良選手の痛恨の深さを、一層深いものに、一生消えないほどの深さにしてしまったのではないでしょうか?
あれほど目標にしてきたワールドカップの舞台が目の前もいいとこ、まさに目の前で取り上げられたのですから。
その意味で、カズ・三浦知良選手にとって、ワールドカップの指揮をとる監督が岡田監督になったことが運命の分かれ目だったのです。
「あなたは日本サッカー界における究極の悲劇の主人公です。」と妄想を抱いて、こう問いを投げかけたいという衝動にも駆られます。
「カズ・三浦知良選手、あなたは、なぜ現役選手を続けているのですか、ご本人が折々のインタビューなどで話していることを額面どおりに受け止めたくても、どうしてもそう思えないのです。」
「二度の悲劇、しかも二度目は本当に目前でしたから、一生の痛恨事になってしまったのでしょう? それで『自分は何を区切りにサッカーを辞めればいいのか・・・』と、そのあと、ずっと彷徨い続けているんでしょう?」と。
でも、それは、悲劇の主人公を作りたがって妄想を抱いている者の、とんだ的外れの問いです。
カズ・三浦知良選手は、ひたすら、サッカーに対する飽くなき情熱とそれを支える逞しい身体を維持し続け「現役プロ選手を続けるサッカー人生」を歩んでいる、それだけなのです。それだけといっても、これ以上、凄いことはないでしょう。私たちは、ただ、ただスタンディングオベーションを止むことなく続けてエールを送りたいと思います。
日本サッカー協会、岡田監督の自宅周辺に警察の特別警戒を要請、前年に続く警戒体制
カズ・三浦知良選手と北澤豪選手の落選発表のあと、日本サッカー協会には抗議の電話やFAXが約500件入ったとのことです。日本サッカー協会は、両選手の帰国会見のあと、一部の過激なサポーターによる暴走や不測の事態に備え、岡田監督の自宅周辺に警察の特別警戒を要請する事態になりました。
前年のW杯アジア最終予選の時に次ぐ2度目の警戒要請となりました。
キャプテン・井原選手ケガ、果たして初戦は大丈夫か
6月2日、日本時間の20時すぎから行われた22人の最終メンバー発表が一段落して、またチーム練習が再開された直後、ミニゲームの中でDFの要・井原正巳選手にアクシデントが発生しました。右ひざ靭帯を少し損傷したというのです。初戦のアルゼンチン戦まで2週間を切ったこの時期の負傷、どうやら、それまでには回復しそうなケガのようで、井原選手の表情には笑顔もありましたが、日本代表、またしても悩みを抱えたのです。
岡田監督に「最も素敵なお父さん・イエローリボン賞」
同じ6月2日、日本では父の日に因んで「最も素敵なお父さん・イエローリボン賞」の選考授賞式が行われ、時の人でもある岡田監督がスポーツ界からの選出ということで受賞しました。今年で17回目となる同賞、サッカー界からは初めての受賞者となり、岡田監督の代理で八重子夫人が出席しました。
ちなみにこの年の受賞者は、岡田監督のほかに、政界から土屋義彦・埼玉県知事、経済界からは日立製作所の金井務社長、文化芸能界から歌舞伎俳優の中村橋之助さん、俳優の村上弘明さんでした。
この「最も素敵なお父さん・イエローリボン賞」を報じた3日の新聞各紙には、一方で「非情なカズ外し、岡田監督、仕事一徹」の見出しと、八重子夫人の「うちでは百点パパ」のコメントが隣り合わせに並ぶことになりました。
最後の国際試合ユーゴ戦、善戦するも見えない得点の形
日本時間6月4日未明、ユーゴスラビアと最後のテストマッチ。カズ・三浦知良選手がつけていた背番号11番を小野伸二選手がつけることになりました。1990年イタリアW杯以来8年ぶりにワールドカップの舞台に復帰したユーゴスラビアは、名古屋でプレーするストイコビッチ選手を中心に今大会も強豪国の一つに数えられており、仮想クロアチア戦となるうってつけの相手でした。
結果は0-1、日本はやはり強い相手から得点を奪うのは容易ではないように思われました。キリンカップのパラグアイ戦、チェコ戦、そしてローザンヌでのメキシコ戦、そして今回のユーゴ戦、あげた得点はわずかに1点、もはやテストの機会もすべて終了しました。
どういう攻めで得点をあげるのか日本のサッカーファンには何も見えないまま、岡田監督とそのメンバーが本大会で何かを見せてくれるのか、願望にも似た思いで見守るしかありませんでしたが、岡田監督は違っていました。
岡田監督は、これまでの試合と比べて、決定的なチャンスが作れて、これなら行けるとアルゼンチン戦に向けて大きな手応えを得たそうで、3人を外した直後のゲームだったけれど、選手たちも落ち着いてやれたことも大きかったというのです。
そして、エクスレバンに入ってから陣中見舞いに訪れたアーセナルのベンゲル監督に「オカダもいろいろ大変だろうけれど、無理しないで、そういう時は煙草でも吸って気持ちを楽にして」と声をかけてもらったことで、ずいぶん気が楽になったそうです。
ユーゴ戦の観戦スタンドには中田英寿選手のプレーを追う欧州エージェントの姿
このユーゴ戦、実は中田英寿選手のサッカー人生を左右する大きな岐路となる場でした。中田選手は、このワールドカップのあとは絶対海外移籍を実現させ、ゼロから再スタートを切る、日本にはもう戻らないと決意して、所属事務所の㈱サニーサイドアップ・次原社長に海外移籍を計らって欲しいと依頼しています。
そのため、次原社長は、欧州のエージェントの中から適任と思われるエージェントの選定に奔走し、イギリスのスポーツマネジメント会社に所属するコリン・ゴードン氏に「一度、中田英寿をぜひ見て欲しい」と依頼して、このユーゴ戦の場をセットしていたのです。
すでに何度かご紹介している作家・小松成美氏の著書「中田英寿 鼓動」(1998年12月 幻冬舎刊)の物語は、中田英寿選手の代理人になったゴードン氏が、スイス・ローザンヌで行われる日本vsユーゴ戦で、初めて中田選手のプレーを自分の目で確かめるため駆け付けるところから始まっています。
ですから、この項は小松成美氏の著書「中田英寿 鼓動」から引用する形で、経緯を記録することにします。
このゴードン氏が「中田英寿の移籍交渉を手掛ける」と判断しなければ、中田選手がいくら、もう日本に戻らず海外でプレーする」と心に決めていたとしても、絵にかいた餅になります。
その意味で、このユーゴ戦は中田選手の将来を決めるといってもいいほどの重要な意味を持つ試合であり、中田選手も所属事務所の次原社長から、そのことを告げられていますから、身震いが出るほどの気持ちでいたのでした。
中田選手がイギリスのスポーツマネジメント会社の関係者と初めて東京都内で接触したのは、2月21日のことだったといいます。そのスポーツマネジメント会社が中田選手の海外移籍の意思を直接確認したところから、水面下の活動が始まったのです。
その後、ゴードン氏は母国のイギリスで、前年まで清水エスパルスの監督をしていたオズワルド・アルディレス氏に会う機会があり(アルディレス氏はプレミアリーグ・トットナムの監督経験があることからゴードン氏と旧知の間柄だった)、その際、アルディレス氏から中田英寿選手について「彼は世界でやっていけるクラスの選手だ。失敗はないよ」と聞かされており、その意味でも中田英寿選手のプレーを確かめたかったのです。
通常、ワールドカップイヤーの年の移籍交渉は、ワールドカップが始まる前に水面下で交渉が行われるのが普通で、それがワールドカップ期間中に延びるケースというのは、評価の低い選手がワールドカップの舞台を自分のアピールの場にする場合、もしくは、ワールドカップの舞台を経て前評判がさらに高まることが確実視される場合のみだといいます。
中田選手は、まだ欧州各クラブの獲得候補リストに入っていない選手ですから、ワールドカップの舞台で自分をアピールして各クラブのスカウトや代理人の目に留まり獲得交渉に入ってくれることを目指すしか道はないのです。
そこでゴードン氏は、現地時間6月3日にスイス・ローザンヌで行われるユーゴスラビアとのテストマッチに、各クラブの関係者がまず見に来てくれるよう手配しました。小松成美氏の著書「中田英寿 鼓動」によると、ゴードン氏が次原社長に報告した当日の観戦クラブは次の12クラブだったといいます。しかし折しも航空会社エール・フランスのストの影響で、当日は5クラブしか会場に来れなかったそうです。
・イタリア・セリエA トリノ、ボローニャ、ラツィオ、インテル、ユベントス、ベネチア
・イングランド・プレミアリーグ アーセナル、リーズU、ニューキャッスル
・スペインリーグ レアル・マドリー、アトレチコ・マドリッド
・スコットランド・プレミアリーグ セルティック
試合当日、日本から駆け付けた次原社長と通訳のフジタ女史に、ゴードン氏は「ゲームが終わったミーティングしましょう」とだけ告げました。
スタンドのスカウトたちや関係者が関心を持っている日本代表の背番号8は、その頭髪の色からもすぐ目に付きました。
ゴードン氏は試合が始まって10分ほどで中田選手の実力の見極めがついたそうです。しかし、その一方で、中田選手が日本代表の中で「小さな違和感を抱えながらプレーしている」ことも見逃さなかったといいます。
ゴードン氏の手元に届けられている中田選手の資料の中に次のような記述があったといいます。「自分勝手なパスを出すことが多い中田は、周囲のリズムに馴染み、合わせられるようになるまで時間がかかるスロースターターである」
それを読んだゴードン氏は「それは間違っている。相手のリズムに合わないのではなく、中田のパスにある戦略が、2歩も3歩も先を行き過ぎているのだ。」だから資料にある「自己中心的」という評にも頷けたそうです。
そしてゴードン氏はこう感じたそうです。「ここで中田が見ている世界を共有しているのは、私だけなのかも知れない」と。
さらにゴードン氏は、観戦中に感じたことを次々とノートに殴り書きしていきましたが、その中に一つ、こういうメモを残しました。
「彼には優れた監督が必要だ。中田の才能をさらに磨き導ける監督を擁するクラブ、それを探さなければ」
ユーゴ戦が終わって、次原社長たちとゴードン氏たちはミーティングに入りました。けれども試合を見たチームのスカウトやエージェントからゴードン氏にひっきりなしに電話が入り、なかなかミーティングに入れなかったといいます。彼らは異口同音に「なぜあんな選手がいたことにいままで気がつかなかったんだろう」と言っていたそうです。
彼らに向かってゴードン氏が言った言葉が洒落れてます。「サッカーの神様は素晴らしい才能を天から無造作に撒くんだよ。確かに南米やヨーロッぱには大勢の才能がこぼれ落ちている。だけど、そのほかの広大な地に散らばった才能だってあるはずなんだ。僕らは、どこに落ちたか分からない才能を探し当てることを怠っていた。今、ようやく、その才能のひとつに巡り合えたってわけだ。」
次原社長はゴードン氏から今日の中田選手の印象を一通り聞き終えると、こう切り出しました。
「中田自身はこう言っています。『海外で自分の力を試したい気持ちも覚悟もあるけれど、移籍してもずっとゲームに出られないのでは意味がない。レギュラーとしてピッチに立てることを目標にしたいので、素晴らしい選手たちが揃っているトップクラスのチームより、自分にも出出場機会が与えられるミドルクラスのチームがいいのではないか』と。私もその考えに賛成です。」
それに対してゴードン氏はこう言いました。「私もプロサッカーの選手だった。その経験から中田の考えは正しいと思う。それに加えてもう一つ大事なことは、彼を理解し活かす戦術を授けてくれる監督のもとでプレーすることだ。そういう監督に出会えば、中田は自分がもっとたくさんの練習が必要なことを痛感するだろう。」
そして、こう続けました。「私は一日も早く中田の移籍先を決めなければと考えていましたが、今日の彼を見て考えが変わりました。彼の実力があればワールドカップのグループリーグ3試合が終わるのを待つべきだ。その3試合を見れば、必ず複数のクラブが新たに獲得に動く。異例だが、中田のために名乗りをあげたクラブをすべてテーブルの上に載せ検討していきたい。」
次原社長はこう答えました。「中田にはそう伝えます。6月14日、トゥールーズで行われるアルゼンチン戦のあと再会しましょう。試合の夜、選手にはわずかながら自由時間が与えられますので、ぜひ中田とゆっくり食事をしながら話をしてください。」
衝撃の発表の舞台となったスイス・ニヨン、その後のベースキャンプとなったフランス・エクスレバン、この2つがキャンプ地に決まった裏話
はからずも日本サッカー界を揺るがす歴史の舞台となったスイス・ニヨン、そして、そのあとワールドカップ期間中の日本代表のベースキャンプ地となったフランス・エクセレバン、この2つがキャンプ地に決まった経緯が、当時の日本サッカー協会・小倉純二専務理事の著書「平成日本サッカー秘史」(2019年4月講談社刊)で紹介されています。
「(フランスW杯)本大会出場が決まると、次にやらなければならなかったのは大会前、大会期間中のキャンプ地の選定だった。こういうのは、出場を早く決めたチームから、どんどんいいところを取っていく。出場がアジア第3代表決定戦までもつれ込んだ日本は出遅れた感は否めなかった。」
「キャンプ地がスイスとイタリアの国境に近い、W杯の会場地でいうとリヨンから車で1時間ちょっとの温泉地、エクスレバンに決まったのはフランス(サッカー)協会のおかげだった。」
「(話の)きっかけは、97年(12月)のトヨタカップだった。クラブ世界一を決めるトヨタカップには、欧州、南米の両方から大陸連盟や各国協会の幹部がやってくる。」
「その中の一人にUEFAのコンペテション委員長をやっているフランス人がいて、フランスサッカー連盟のベルベック副会長の伝言を携えて私のところへやってきた。」
「フランスサッカー連盟とは94年のキリンカップにフランス代表を招聘してから、親密なコミュニケーションがとれるようになっていた。」
「ベルベック副会長の伝言は『ワールドカップ初出場、おめでとう』ということと『大会期間中のキャンプ地はどうするつもりだ?』ということだった。」
「ベルベック副会長に連絡を取ると『もし、本大会の組み合わせ抽選会に来るなら、その時に視察して決めたらどうか。フランスサッカー連盟が全面的に協力するよ』という温かい申し出があり、それに乗っかることにした。」
「(97年)12月4日にマルセイユで行われた抽選会に乗り込んだ。(中略)岡田監督も出席した抽選会で日本はH組に入った。抽選会の翌朝、ホテルの前に車が2台迎えに来ていて、スタッフを二手に分けて(大会前のキャンプ地と、大会期間中のキャンプ地の)候補地を見て回った。」
「W杯出場を決めた後は岡田監督も選手も想像以上の狂騒に巻き込まれ、正直なところ、私もキャンプ地のことまで頭が回っていなかった。他の国の役員に抽選会で『明日、キャンプ地を下見に行く』と告げると、『えっ? まだ決めてないのか』と驚かれたくらいだった。」
「W杯初出場だから、とにかく何事にも不慣れで、それだけにフランスサッカー連盟のサポートは本当にありがたかった。」
その結果選定された最初のキャンプ地、スイス・ニヨンは、スイス西部の国際都市ジュネーブと、西部のもう一つの大都市ローザンヌとの中間地点に位置していて、その両都市もそうですがレマン湖の湖畔にある相当古い街のようです。ヨーロッパ全体の地図の中ではほとんどフランスの国境近くということになります。
本来なら古都散策ぐらいの息抜きもさせてあげたいロケーションですが、それどころではない気持ちで10日間近くを過ごしたのかと思うと残念ですし、選手たちの誰かが後年、ご夫婦ででも観光に訪れることはなかったのだろうかと思いを馳せても、おそらく「また訪れてみたい」という気にならない10日間近くだったのではないかと思ってしまいます。
6月5日に移動して6月27日に離れるまで、大会期間中のベースキャンプに選定されたフランス・エクスレバンは、スイス・ニヨンから約100Kmぐらい南方向に移動したところにあります。ここは西側にある湖に面しており温泉保養地として人気がある街のようです。
試合地と行ったり来たりではありますが20日以上滞在しましたから、選手たちも多少は街を楽しんだと思いますが、なにぶん成績が成績でしたから、いい思い出にはならなかった滞在なのかも知れません。
そもそも6月5日にエクスレバンに入った日本代表、カズ・三浦知良選手と北澤豪選手の離脱、井原正巳選手のケガと、気持ちが沈む材料ばかりのままエクスレバンに入りましたから地元小学生の歓迎の歌(「さくらさくら」を日本語で歌ってくれた)も堅い表情のまま聞き、そのまま宿舎に移動したそうです。
外国で地元の人たちから歓迎セレモニーを受けて滞在するという経験も初めてでしたし、気持ちが沈んだまま現地に入ったということで仕方がないのかも知れませんが、それは監督・選手たちの問題というより、むしろ日本代表選手団を率いる日本サッカー協会の目配りのなさを指摘すべきでしょう。
そもそも地元エクスレバンで、どういう受け入れを考えているのか情報をとるぐらいのことは当然ですし「どうやら子供たちの歌による歓迎セレモニーもあるようだ」という情報を掴んでいれば「仏頂面しているなよ、作り笑いでもいいから笑顔を見せて、状況によっては握手とか応じるんだぞ」ぐらいのことを移動のバスの中で言っておくべきでした。
まぁ、結果的に、せっかくの歓迎にも堅い表情のままでした、と記録するしかありません。
この小倉純二専務理事(当時)の著書には、スイス・ニヨンとフランス・エクスレバンが、他の候補地との比較でなぜ選ばれたのかまでは記録されていませんが、フランスサッカー連盟のありがたい協力なくしては設定できなかったと思うと、長く語り継ぎたい出来事だと思います。
フランスサッカー連盟とは、フランスW杯終了後、岡田監督が辞任したことで、後任の日本代表監督選びをする際、また深いつながりを持つことになります。
フランスサッカー連盟と日本サッカー協会のつながりを、この段階で理解しておくと、後任代表監督選びの話がスムーズに頭に入ってくることを記録しておきます。
フランスW杯チケット問題が表面化、サッカービジネスに巣食う悪徳業者の餌食になったか
日本代表の初舞台が目前に迫ってきた6月11日、現地フランスに行ってその晴れ舞台を直接応援すべく意気込んでいた日本人サポーターたちに冷や水を浴びせかける思いがけないニュースが飛び込んできました。
「6月14日のアルゼンチン戦を観戦しようと申し込んでいた日本人サポーター1万4700人分の入場チケットのうち、少なくとも1万人分がまだ確保できていない(朝刊発売段階では1万2000枚と報じられたが夜までに若干改善)」という衝撃的なニュースが、6月11日朝の新聞各紙、日中から夜にかけてのテレビ番組を通じて日本全国に流れました。
日本が初出場を果たすフランスW杯、日本からは、グループリーグの3試合を中心に、累計約4万人のサポーターが国内旅行代理店が企画した観戦ツァーに申し込んでいたようです。6月4日のスポーツニッポン紙によると、最も集客したのがJTBの8000人、近畿日本ツーリストの5900人、日本旅行と日通旅行がそれぞれ4000人と続くそうです。
またFIFA公認旅行業者(世界で17社)に昨年入札参加して、日本で唯一指定業者となったジェイワールドトラベルという会社も2000人集客したそうです。
入場券の定価は、席によって日本円で3400円から8400円となっているが、実勢価格(実際にツァー参加者に売られる価格)は3~4万円で、国内旅行代理店は、それに航空券・宿泊代等を含めたツァー料金を設定して集客しています。
6月4日の段階では、何の問題もなさそうに見えたチケット入手、実は、いざ出発が近づいて各旅行代理店が現地に「いよいよ出発ですから、手配したチケット、よろしくお願いしますよ」と確認をとったところ、次々と「手に入らない」という驚きの話になったようなのです。
この突然の事態を受けて、観戦ツァーを企画した国内大手旅行代理店が次々とツァーをキャンセルせざるを得ないと発表、少なくとも6000人が観戦予定者が観戦できなくなる状況になりました。
すでに出発予定日ということで成田空港には大勢の観戦予定者が集まりましたが、そこで旅行代理店から観戦ツァー中止の通告を受け、空港内は一時騒然となりました。
旅行代理店の中には、ツァー参加者から「最終的にチケットが入手できなくても、それを承知で参加します」という「同意書」を提出した参加者だけをフランスに連れて行くという措置をとったところもあり、同意した参加者は「可能性を信じて行く」とか「ずっと前から計画していたので現地に行くだけでも行く」といった切ないコメントを残しながら、この日は約1700人がフランスに出発しました。
この日夜のテレビ朝日「ニュースステーション」は久米宏キャスターの「このような事態は予測できなかったのでしょうか? 旅行会社の対応をまとめてあります。」と、事の経緯を紹介しました。
・そもそも今回のフランスワールドカップで発売されるチケットの総数は64試合分、合計250万枚。
・国内各旅行代理店が、そのチケットを間違いなく入手できる方法は、二つのルートがあり、一つはFIFA公認旅行業者(17社・チケット総数の5.3%)から購入するルート、もう一つは各国サッカー協会に割り当てられたチケットを、日本の場合は日本サッカー協会から購入するルート、しかし、それだけでは、国内の観戦希望者に十分行き渡るだけのチケット入手は到底難しいという見通しを、各旅行代理店は持ったようです。
・そこで、国内各旅行代理店は、公式スポンサーに割り当てられた分(総数の13.5%)や、各国サッカー協会に割り当てられた分(総数の23.5%)で売れそうにない分(自国と関係ない試合など)、そして開催国フランス国内の法人・個人向けに割り当てられた分(総数の52.3%)で、それぞれが消化しきれないチケットをかき集めて再販する「仲介業者」を頼った模様です。
・しかし、今回のワールドカップを実質的に取り仕切る「フランスワールドカップ組織委員会」は「仲介業者」を認めておらず、そこに流通したチケットは「闇ルート」からのものということになります。しかも「仲介業者」の中にも元請け、下請け的に複数の業者を経由しているケースがありチケットの流れがまったく不透明だというのです。
・そのためアルゼンチン戦だけでも約1万枚のチケットが一体どこで詰まっているのか、まったくわからないのが実態です。
では、こうなった責任はどこにあるのか、大元(おおもと)である「フランスワールドカップ組織委員会」がしっかりと管理しなかったためではないか、そう思って「ニユーステーション」は「フランスワールドカップ組織委員会」の報道担当を電話で直撃しました。
Q.日本の旅行代理店にチケットが届いていませんが?
A.チケットはすべて配布されている。現に昨日の試合は満員だ。
Q.日本の旅行代理店は「受け取っていない」と言っています。
A.我々は公認業者からチケットを受け取ったという「受領書」を日付、サイン入りで受け取っている。
Q.仲介業者は違法ですか?
A.販売を許可されているのは、「フランスワールドカップ組織委員会」「公認旅行業者(17社)」「FIFA(国際サッカー連盟)」の3つだけです。
この電話のやりとりは、結局、公式見解を聞かされただけで、知りたいことは何もつかめませんでした。そのかわりという感じで「ニュースステーション」は、イギリスでチケットの予約を受けていた業者が倒産したため、日本やベルギーの業者にも影響が出ていると次のように報じました。
「ロンドンにあるこの業者は公認業者ではないが、およそ4万枚の予約を受け付け、840万ポンド(注・日本円約18億円、テレビ字幕では240万ポンドと表示)の予約金を集めていた。ところが今月4日に倒産、破産管財人などが事務所を調べたところチケットは1枚も残っていなかった。被害にあったのはベルギーなどヨーロッパ各国のほか、日本の業者も含まれているとのこと」
つまり暗に、詐欺業者にチケット代金がかすめ取られたことを示唆していました。
翌12日のサンケイスポーツ朝刊は「パリのホテルでブラジルサポーターなど約1000人が『予約したチケットが入手できなかった。旅行代理店にだまされた』として建物内で大暴れして警察が出動する騒ぎになった」と報じました。
また、アルゼンチン戦、クロアチア戦、ジャマイカ戦の3試合合計で、まだ2万4000人分のチケットが手に入らず、これはツァー参加者全体(約4万人)の3分の2にあたるとも報じました。
この問題を扱った番組のコメンテーターの中には「前回の1994年アメリカW杯の時は、スタジアムのキャパシィがアメフト用スタジアムということで、どれも大きなスタジアムだったこと、参加国も24ケ国と少なかったことでチケット入手困難ということはなかった。今回、フランス大会はスタジアムのキャパシティは小さいし、参加国は増えたことで、そもそもチケット入手が厳しい環境になったことが背景にあると思う」と紹介する専門家もありました。
結局、ニュースステーションが報じた「認められていない仲介業者」というのは悪質なブローカーであり、しかも二重、三重に入り組んでいることから、試合直前になったら、ダフ屋から1枚10万円ぐらいで出回るのではないかといった指摘も出されました。
特に、日本の観戦ツァー募集の過程で、チケットがプラチナ化してしまい、それを嗅ぎつけたブローカーが、日本からの観戦者には高く売れそうだと思わせてしまった面もあると指摘する専門家もありました。
そして、国内旅行代理店が、W杯チケットの大量確保という初めての経験にも関わらず、チケット入手が確実でない見通しのまま、ツァー参加者を募集した認識の甘さ、無責任さも問われかも知れないと指摘する専門家もありました。
「フランスワールドカップ組織委員会」の事務局長などは会見の席で日本の旅行会社のツァー募集のパンフレットをかざして見せ「チケットが入手できる見通しがないのに募集をかけている」と指摘していました。
チケットが手に入らない問題は、日本だけではなさそうですが、日本の場合、初めて経験する国だけに、そういう悪徳業者に引っ掛からないようにする免疫がまったくなかった点が悲劇的でした。
国際サッカービジネス界にうごめく悪徳業者、国をまたいだチケット販売の闇、これも世界の舞台に初めて立つ国が経験しなければならない通過儀礼の一つなのでしょうか。
6月13日のスポーツニッポン紙は「明日いよいよ決戦、芸能人サポーターも続々出発」と、チケットを持った人、もたない人を含めて出発した芸能人の様子を伝えました。
同紙によると、ミュージシャンの徳永英明さん、電撃ネットワークらがフランスに向かったほか、ナインティナイン・岡村隆史、矢部浩之の二人はテレビ朝日の企画で渡仏、チケットは一人分だけとのこと、また落語協会で作るサッカーチームの監督兼選手の春風亭正明さんも現地抽選頼みのチケットに賭けて出発した、とありました。
さらに、スタジアムに入った日本人サポーターが頼りにする日本代表応援団「ウルトラス・ニッポン」のメンバー約200人もチケットが手に入りないまま現地入りしました。
「ここまで来て、日本代表の応援を諦めてたまるか」という気持ちで14日朝からチケット入手の行動を始めました。旅行会社が彼らに用意した資金は一説によると日本円で3000万円にのぼったそうです。すべてフラン紙幣とドル紙幣に両替された「軍資金?」を用心深く各自バッグに詰めてトゥールーズの街に散っていきました。
このチケット入手のことについてウルトラスリーダーの植田朝日さんと、メンバーの山崎利之さんが、2007年に出版された「日本サッカー狂会」(国書刊行会刊)の中でこう紹介しています。(敬称略)
植田 急に「券がない」と言われて地獄だった。もう正直、「ワールドカップ嫌だよ」という感じ。
山崎 (チケット持ってる人も)カテゴリーもバラバラですから、ある程度近い席って感じで交換(見知らぬ外国人が持っているチケットを見せてもらって、良ければ交換)して行くしかないんですよ。
植田 4枚、6枚とか集めて交換したいと思っても、(条件の)いい席と(こちらの)悪い席を取り換えてもらえるわけはないでしょう? だから、俺たちの席はどんどん悪い席へ移っていくことになる。
山崎 俺なんか、チケット交換してる時に、何度もダフ屋と間違えられてるんですよ。人相のこともあると思うけど(一同笑い)。
植田 誰にも文句言われない席にどんどん人を集めて、そこに核を作ってしまえば、みんなも応援はしたいから。(中略)場所なんかどこでもいい。10人ぐらいの核さえできちゃえば、1万人でも乗せることができるから。
試合が始まってからの応援の様子については、後の項に譲ることにして、ウルトラスのメンバーはこうして、まさに地獄のようなチケット入手の苦労の末、初戦を迎えることになったのです。
この1ケ月間「カズ落選問題」「チケット未着問題」と、社会的インパクトの大きい出来事を生みながら、とうとう地球上最大のスポーツの祭典「フランスワールドカップ」が始まり、世界の舞台に日本が初めて立つ日がやってきました。
フランスワールドカップ開幕、文化と芸術の国フランスらしい大仕掛けの前夜祭と開幕祭と銘打った開会式
6月10日、FIFAフランスワールドカップ1998が開幕しました。この年の大会には、世界174の国と地域が参加した各大陸予選を勝ち抜いた32チームが集結しました。
前日6月9日夜にはパリを舞台に大仕掛けの前夜祭が行われました。
この開幕祭を中継放送したTBSのオープニングには「発案ミシェル・プラティニ、構想5年、製作費11億円、十数万人が参加」という字幕が流れ「パリの街と世界の文化の融合」をテーマにしたイベントが始まりました。
最大の見ものは高さ20m、重さ38トンの4体の巨人な樹脂製のロボットのような人形、それぞれの名はラテン・アメリカを象徴する「パブロ」、ヨーロッパを象徴する「ロメオ」、アジアを象徴する「ホー」、アフリカを象徴する「ムーア」、四大陸を象徴するその巨人たちが、18時半頃、凱旋門、オペラ座、シテ島、士官学校の4か所で眠りから覚め、コンコルド広場を目指し、コンコルド広場に飾ってあるワールドカップトロフィーモニュメントを目指すという嗜好でした。
その巨人とともに、さまざまな形をした植物や動物などをかたどったコスチュームをまとって歩いたり、それぞれのロボット人形の高さ3mぐらいのミニチュア版がパフォーマンスを見せたり総勢4,500人もの参加者と、それを街中に響き渡るサウンドが盛り上げるという、パレードともカーニバルとも思える大イベントでした。
巨人たちの両足の部分には2台のセダン自動車が組み込まれ、それぞれの運転手が交互にゆっくり走らせながら進んで、5時間近くをかけてコンコルド広場に到着した4体のロボット人形は、高さ30mはあろうかというワールドカップトロフィーモニュメントを囲むように止まりました。
そして、サッカーボールを持った大人たち、子供たちがワールドカップトロフィーモニュメントの周りに作られたサッカーフィールドのようなステージに集まると、巨人たちが両手を広げました。するとワールドカップトロフィーモニュメント一番上のサッカーボールが照明に輝き始めました。「サッカー賛歌」ともいうべきパフォーマンスでした。
次に、ワールドカップトロフィーモニュメントのすぐ周りから、それぞれ、木と水と空気と大地を象徴するイブ・サンローランデザインのコスチュームをまとった4人の女神役が登場、約10mの高さまでせり上げられてパフォーマンスを披露しました。
続いてステージでは、ミニチュア版ロボット人形がパフォーマンスを披露、さらに4体の巨人が横一列に並んで、それぞれが胸に付けたゼッケンで「1998」の数字を作りました。
この頃から雨と風が強まり、巨人たちの胸につけたゼッケンも風に負けてはためくぐらいでしたが、コンコルド広場には6万人ほどの市民が詰めかけてイベントを見守ったそうです。
イベントはこれで終わらず、惑星をイメージした8個の大きなバルーンが登場、また、巨人とともに植物や動物などをかたどったコスチュームをまとって街を練り歩いてきた、すべてのチームが集結、最後は宇宙人のようなコスチュームをまとった人たちも大勢入場、地球から宇宙へというメッセージなのか、ワールドカップトロフィーモニュメントから1機の円盤型宇宙船が飛び立つという演出もありました。
シャンゼリゼ通りには、街灯毎に長さ4m以上もの出場国の国旗が掲げられ、開幕を待ちわびた多くの市民、各国サポーターたちが繰り出し、まさにお祭り騒ぎの賑やかさとなりました。
文化と芸術の国フランスの威信をかけた前夜祭、パリの街を舞台に繰り広げられた延々6時間におよぶイベントは、スケールの大きなアートとテクノロジーが融合したようなショーでした。
次に6月10日、大会初日、パリ郊外サンドニ・フランス競技場では開幕戦に先立ち、開会式セレモニーが行われました。
テーマは「子供の夢」、ピッチ全体が緑のシートで覆われて、緑の草原をイメージした庭に5つのカラフルな大きな花が開き、花弁の中心部に大きな丸いものが乗っています。
次にシートが取り除かれ、大きな花のモニュメントが残ると、大きな丸いものの皮がむけるように、中から大きなサッカーボールが姿を現しました。
次に屋根から宙づりにされた32人の人たちが出場国の国旗カラーデザインの衣裳をつけて降りてきました。そして、まるで空中ショーのようなパフォーマンスを見せます。フィールドでは芝を痛めないよう大きな平たい靴をはいた、着ぐるみの大勢の人たちがサンバのリズムを奏でるドラムを叩きながら踊り、空中ショーの32人は、グループリーグの組分け毎に隣り合わせになっていて、それぞれの国旗を翻して見せました。
その中に初めて日本の国旗がH組の国々と並んで翻ったことになります。
セレモニーを実況したNHKの野瀬正夫アナウンサーは「これまでワールドカップの本大会に出場したことがあるのは65の国と地域だけ、FIFA・国際サッカー連盟に加盟している国と地域は198ありますが、まだ、その3分の1ですよ」と解説の早野宏史さんに振ると「日本もここに参加できて、ボクも本当にうれしい気持ちがしてきましたね」と、あらためて初出場の喜びを実感したようでした。
最後に、5つの大きな花の中心の大きな丸いものから、無数の風船が空に向かって出ていきました。子供たちの夢が世界に届けというメッセージのようでした。
出場国を紹介したり、演出の内容を説明するような場内放送は一切せず、5つの大きな花、空中に浮かぶ5つの大きなサッカーボール、32人の空中パフォーマーが翻した出場国の国旗、ピッチで繰り広げられる大勢の着ぐるみの人たちのサンバの踊り、それら全体を映し出して15分ほどの開会式セレモニーは終わりました。
このあと開幕戦の両チームが入場、FIFAアベランジェ会長のメッセージ、フランス国歌の吹奏が行われ、13歳のフランス人少女による「フットボール憲章」の朗読、両国国歌の吹奏が行われ、いよいよ大会が始まりました。
前夜に6時間にわたるパリ市内を舞台にしたイベントを行なったあと、開幕戦直前のセレモニーでは、フランスのシラク大統領、フランスワールドカップ組織委員会のプラティニ委員長とも特に演説することなくシンプルにまとめました。これも開催国フランスの流儀なのでしょう。
当サイトでは、1986年メキシコW杯から、1990年イタリアW杯、1994年アメリカW杯と大会の模様を記録に残してきましたが、大会前夜祭や開会式セレモニーの内容までつぶさに記述したのは今回が初めてでした。日本が出場するということの重み、大会に対する関心の深さをそのまま反映した記録です。
前夜祭でごった返すパリの、とあるホテルの一室、ゴードン氏から次原社長に示された新たなリスト、そこにはユーゴ戦後の打ち合わせにはなかったクラブの名が
6月9日の前夜祭の夜、パリ市内のとあるホテルにイングランドのエージェント会社のケビン・ゴードン氏と中田英寿選手の移籍を任されている所属事務所・次原社長とそのスタッフが合流しました。
6月14日の日本代表の初戦、トゥールーズでのアルゼンチン戦を見に来る欧州各国リーグのクラブが、ゴードン氏の尽力でリストアップされ、そのリストが示される打ち合わせだったのです。
ここでも、作家・小松成美氏の著書「中田英寿 鼓動」(1998年12月 幻冬舎刊)から、その様子をご紹介します。
次原社長が目にしたリストには次のクラブが並んでいました。
・イタリア・セリエA ユベントス、サンプドリア、ペルージャ
・イングランド・プレミアリーグ アーセナル、トットナム、ニューキャッスル、アストンビラ、ニューキャッスル、サンダーランド
・フランスリーグ パリ・サンジェルマン、マルセイユ
・スコットランド・プレミアリーグ セルティック
次原社長は、中田選手の移籍がもう後戻りできないところまで来ていることを実感する一方、中田選手の移籍が、スポンサー付きとかジャパンマネー目当ての移籍などと疑われるようなことだけは絶対にしない、あくまで実力で掴んだ移籍と言われるものにしなければならないと、あらためてゴードン氏に伝えました。
ゴードン氏は「あなたの言うとおりだけれど、まったく心配ありません。中田選手はヨーロッパの各クラブが『金を出しても欲しい選手』になっています。」と答えるとともに、こう付け加えました。「中田選手のように大きなビジネスになる選手の周りには、金儲けのことしか考えない人間も群がりますから、そこは慎重に進めなければなりません。」
ゴードン氏はJリーグの移籍金に関する規定が、若い選手の足かせになっていることををすでに調べていて、
「中田選手は、移籍が難しいといわれるJリーグにあって、その条件を正式にクリアできる唯一の選手といっていいでしょう。ですから選手も、この機会を逃してはいけないんです。」
2人はトゥールーズでの再会を約束してミーティングを終えました。
開幕戦ブラジルvsスコットランド戦は、ブラジル、相手オウンゴールが決勝点
開幕戦は、前回優勝国がその栄誉を担うことになっています。今回はブラジル、ここまで16大会連続出場、世界で唯一の全大会出場を続ける絶対王国です。
対するはスコットランド、英国の一地域でありながらサッカーの母国の特権で英国4協会の一つとして欧州予選に出場、見事勝ち抜いて1990年イタリア大会以来、本大会にやってきました。
力の差はあるものの、第1戦の難しさは、歴代最多優勝回数を誇るブラジルといえども難しく、この日も「らしくない」プレーが続出しました。
それでも開始4分、キャプテン・ドゥンガ選手が放ったシュートで得たCKを、サンパイオ選手がヘディングで合わせ、ブラジルが先制しました。
日本のスポーツ紙各紙は「Jリーグで活躍している選手たちであげた先制点」と報じました。
ただ前半38分にはサンパイオ選手が相手選手を倒してしまいPKを与え、同点に追いつかれました。それでも後半28分、ドゥンガ選手から右サイドのカフー選手にロングバス、これをシュートまで持ち込んだボール、GKがはじいたもの味方DFに当たってしまいオウンゴールとなって、ブラジル勝ち越し。これが決勝点となり何とか白星スタートを切りました。
この大会、もっとも注目される選手の一人、ブラジルのFWロナウドは得点こそなかったものの、前半19分、相手ペナルティエリアの右外でボールをキープするとドリブルしながら反転、相手DF2人をかいくぐってシュートまで持ち込みました。ボールは惜しくもGKに弾かれましたが、今大会いけると本人も感じたであろう一撃でした。
夢の舞台フランスワールドカッブ、いよいよ日本代表が世界最高峰の舞台に登場
フランスワールドカッブが開幕すると、日本が参加する大会、しかも4年後には日本が開催国になる大会とあって、テレビも新聞も連日ワールドカップにニュース一色となりました。
あとは、この熱気がいつまで続くかという思いの中で、いよいよ、その日がやってきました。
あらためて、最終登録された22人の選手とスタッフたちを記録しておきます。
背番号、氏名、(年齢)、現所属の順(敬称略)
【GK】
1 小島伸幸(32)平塚、 20 川口能活(22)横浜M、 21 楢崎正剛(22)横浜F
【DF】
4 井原正巳(30)横浜M、 3 相馬直樹(26)鹿島、 5 小村徳男(28)横浜M
2 名良橋晃(26)鹿島、 17 秋田 豊(27)鹿島、 18 斉藤俊秀(25)清水
19 中西永輔(24)市原、 13 服部年宏(24)磐田
【MF】
6 山口素弘(29)横浜F、 10 名波 浩(25)磐田、 15 森島寛晃(26)C大阪
8 中田英寿(21)平塚、 22 平野 孝(23)名古屋、 7 伊東輝悦(23)清水
11 小野伸二(19)浦和
【FW】
9 中山雅史(30)磐田、 12 呂比須ワグナー(29)平塚、 14 岡野雅行(25)浦和、
18 城 彰二(22)横浜M
【監督】岡田武史、【コーチ】小野剛、 【フィジカルコーチ】ルイス・フラビオ、
【GKコーチ】ジョゼ・マリオ、
【団長】大仁邦彌、【総務】湯川和之、【主務】山下恵太、【プレスオフィサー】加藤秀樹、 【ドクター】福林徹、【トレーナー】徳広豊、田中博明、並木麿去光、【エキップ】麻生英雄、寺本一博(アシックス)、【栄養士】浦上千晶、【シェフ】野呂幸一、【コック】鈴木義之
※現地には日本サッカー協会・長沼健会長、強化委員会・今西和男副委員長など数人の幹部が滞在したが詳細不明
※ほかにエクスレバンに日本サッカー協会臨時事務局を開設、岡田武夫国際部長、小野沢洋広報部長ほか2名が滞在。
※また日本代表テクニカルスタッフ(主として対戦国スカウティングを担当)として、影山雅永氏、四方田修平氏も滞在
6月14日、フランス・トゥールーズ、日本代表第1戦、アルゼンチン戦
観客33,500人、天候・晴、気温20℃、キックオフ14時30分(現地)
フランスに入る直前での「カズ帰国」、キャプテン・井原正巳選手のケガと、やや動揺する要因を抱えながらエクスレバンで事前調整を行なっていた日本代表、はじめの頃、現地では花粉が飛んでいて、それに悩まされる選手、スタッフもいた中、井原選手のケガもよくなり、選手たちのコンディションは十分整った状態で、この日を迎えました。
岡田監督も最後の調整試合ユーゴ戦での戦いで、やれるという手応えを得て、6月8日にはアーセナル・ベンゲル監督の陣中見舞いを受け、ベンゲル監督から「あまり無理しないで」と声をかけてもらったことで気持ち的にもポジティブになって初戦を迎えることができました。
あとは岡田監督が描いた戦術で守り切れて、日本が点を奪えるのかというシンプルな試合予想となりました。
対するアルゼンチン、パサレラ監督のもと、派手さはないものの前線から最後尾まで実力派の選手を揃えた優勝候補の一角です。
岡田監督が送り込んだ先発は次の11人(敬称略・数字は背番号、(C)はキャプテン)
・GK 20川口能活
・DF 4井原正巳(C)、17秋田豊、19中西永輔、3相馬直樹、2名良橋晃
・MF 10名波浩、8中田英寿、6山口素弘
・FW 9中山雅史、18城彰二
対するアルゼンチンの先発は、
・GK ロア
・DF アジャラ、センシーニ、ビバス
・MF サネッティ、アルメイダ、シメオネ(C)、ベロン、オルテガ
・FW Cロペス、バティストゥータ
日本のスタメンの中で目を引いたのが3バックの一角、中西永輔選手です。これまで使われてきたDF陣といえば、小村徳男選手、斉藤俊秀選手でしたから、これは思い切った起用ですが、岡田監督は3バックの布陣ということで、5月のキリンカップ以降、単にこれまでのDF陣の延長で考えるのではなくニュートラルに考えて選手を見てきています。
そういう意味では中西永輔選手が一番岡田監督のイメージに合う動きをしてくれたということになります。
中西選手は、5月のキリンカップの2戦目、チェコ戦で初めて3バックの一角としてスタメンに起用されました。それは1戦目のパラグアイ戦で秋田豊選手が鼻骨を骨折したために巡ってきたチャンスでした。まさに岡田監督が最も心を砕いてきた「ディフェンシブな戦術を25人すべてに身体で覚えてもらい、スクランブルの際に破綻をきたさないようなチームにするんだ」という意図が試される起用でした。
中西選手は、ただひたすら岡田監督の意図どおりに動くことだけを考えて走り回りました。
その結果、国内での強化試合をすべて終え、スイス・ニヨンに移動してから最初の試合、日本時間6月1日未明、スイス・ローザンヌで行われたメキシコ代表との試合にも3バックの一角としてスタメン出場を果たしました。
報道陣をシャットアウトして行われたこの試合で、岡田監督は中央に井原正巳選手、左に秋田豊選手、左に中西永輔選手を並べる3バックシステムで十分やっていけるのではないかと考え、そのあとはすべてこの布陣で試合・練習を重ねアルゼンチン戦を迎えたのです。その意味では、岡田監督にとって中西永輔選手を使えることに気づいたというか、探し当てたことがアルゼンチン戦をポジティブな気持ちで迎えることができた大きな要素になっていると思います。
トゥールーズ競技場を埋めた日本人サポーターが掲げる日の丸の小旗が鮮やかだったアルゼンチン戦
歴史的な第1戦の舞台はフランス南部の都市トゥールーズ、あと100kmも南に行けばスペインとの国境、内陸部の人口約50万人の都市です。周辺地域を含めた都市圏人口規模では、パリ、リヨン、マルセイユに次ぎ、フランス第4の都市圏となっています。いかにも南仏らしい赤レンガの建物に彩られていて「バラ色の街」と呼ばれているそうです。
街を貫く川に大きな中洲がありスタジアムはそこに建っています。収容人員は37,000人ほどといいますから、日本がワールドカップ招致の際にFIFAから厳命された40,000人以上の収容スタジアムとは違っています。
ちなみにフランス大会で使用された10会場のうち5会場は40,000人未満のスタジアム、最小はモンペリエの34,000人でした。日本がW杯招致活動をした時のFIFAからのスタジアム基準、40,000人以上の施設という厳命は一体何だったんでしょう。
さてトゥールーズ競技場、スタジアムの周辺にはチケットが手に入らない大勢の日本人サポーターがチケットを求めてさまよっているのではないかと思われましたが、実は川の中州にあるスタジアムには川にかかる橋のところのゲートでチケットの有無をチェックされるため、スタジアムの周辺は閑散とした様子だったのです。サポーターたちは街の中でチケット探しをしたりしていたようです。
スタジアムの中はというと、小ぶりなスタジアムですから空席などは見られずほぼ満席の雰囲気です。6割ぐらいが日本人サポーターで、両手で日の丸の小旗をかざしている眺めは壮観です。チケット問題の関係もあり、どこが日本人サポーターのエリア、どこがアルゼンチンサポーターのエリアということなしに、入り乱れている感じのスタンドでした。
両国の国歌吹奏がありましたが「君が代」の吹奏に合わせて場内の日本人サポーターが、やっと「君が代」を唄えるとばかりにスタジアム全体に歌声が鳴り響きました。これまでワールドカップを見に行ったサポーターたちは、自分の国が参加していない、したがって「君が代」を高らかに歌える機会がないことを淋しく思いながら観戦していたのですが、今回遂に歌える機会を得たということで、ひときわ大きな声を張り上げたに違いありません。それを思うと、これぞ「ワールドカップ」を実感させる目頭が熱くなるシーンでした。
ロイヤルボックスには高円宮殿下ご夫妻も観戦していらっしゃいます。殿下ご夫妻はこのあとクロアチア戦、ジャマイカ戦ともに観戦のご予定だそうです。
国歌吹奏が終わるとすぐ「ニッポン、ニッポン、ニッポン」の応援コールが響き渡りました。ウルトラスの植田リーダーの狙い通り、タイミングよく応援コールを始めればスタジアム全体に散らばる日本人サポーターが呼応してくれているのでした。
応援席とピッチが極めて近く、テレビ画面で見ると、タッチラインのすぐ向こうにスポンサー看板が並び、そのすぐ後ろにサポーターが並んでいるように見えるぐらいの距離感でした。
最前列近くに席を確保できたサポーターにとっては、世界最高の舞台をこんな間近で見れるということで至福の喜びだったに違いありません。
対戦相手アルゼンチンは、前回1994年アメリカ大会、あのマラドーナのドーピング検査による薬物反応により大会から追放されたため、優勝候補の一角からいきなりガタガタとなり、決勝トーナメント1回戦でルーマニアに屈した苦い経験を持っています。
今大会は、1978年自国開催のワールドカップ優勝時のキャプテンを務めていたパサレラが監督として規律を重んじるチーム作りをしてきた、手堅いサッカーが持ち味のチームです。
試合は、アルゼンチンの様子見といった感じで始まりました。日本のサポーターはほとんど途切れることなく声を出し続け選手たちを後押しします。
ただ一つ想定外のことがありました。スタジアム内に時間経過を示す表示がなかったのです。お互いにとって想定外ではありますが、特にワールドカップという経験のない舞台の最初の試合での体験だけにペース配分の面でハンディになりかねません。急遽、日本ベンチは大き目の白い紙を2枚用意、それに数字を書き入れ、残り時間が選手から見えるようにベンチに貼り出しました。
サポーターの応援に後押しされたわけでもないでしょうが、日本が開始2分の山口素弘選手の遠目からの初シュート、9分には名波浩選手の右CKから大きく逆サイドに放ったボールを城彰二選手がキープして、またゴール前を横切るサイトチェンジのような折り返し、それに名波選手が反応しましたがゴールラインを割ってしまいました。13分には名波選手が送ったボールを相馬直樹選手がヘディングシュートを放ちますがオフサイドなど、幾つか、いけそうな攻めを見せていました。
やられた感のない失点、前半28分、それでも失点は失点、そのまま重く日本にのしかかる
こうして、前半20分過ぎまではアルゼンチンの繋ぐサッカーを寸断して互角の攻防を進めていた日本、ゴール前までボールを運ぶものの、なかなか決定的な場面というほどのチャンスは訪れませんでした。その後、アルゼンチンは中盤からドリブルを仕掛ける場面が増えてきました。
次第に日本が押し込まれてゴール前で守る時間が長くなってきた前半28分、試合が動きました。
日本のペナルティエリアの15mほどのところからベーロンが出したパスにCロペスが反応、右足のヒールで日本DF陣の裏に浮き球を送りました。これに秋田選手が素早く反応して小さくクリア、これを相馬選手がさらにクリアしましたが、大きなクリアとはならずに相手中盤のアルメイダに渡りました。
アルゼンチンは二次攻撃とばかりに、それをオルテガに送ると横にドリブルしてシメオネにパス、シメオネは腰を落として狙うようにして壁パスとばかりにオルテガに斜めのパスを繰り出しました。
それがオルテガに渡るかと思われましたが、その足先をかすめました。ちょうどその時、バティストゥータを前からブロックするようにマークしていた井原選手が、オルテガに渡るかというボールをカットできるかも知れないと足を伸ばしたのですが、ボールはオルテガと井原選手の間をすり抜けたのです。そして、井原選手はバティストゥータのマークを外す形になってしまいました。
すり抜けたボールは、ディフェンスに戻っていた名波選手に届いたのですが、ボールが二人の間をすり抜けてきたことから、名波選手がコントロールする間もなく右足にあたってしまったのです。当たったボールは浮いて、ちょうどバティストゥータが胸トラップして落とせる場所に飛んでしまいました。
胸に当たって落ちたボールをシュートしようとするバティストゥータの動きを察知した川口能活選手は、前にダッシュしながら右側に身体を倒してブロックを試みました。しかしバティストゥータはその動きを読み、右足でチョップキック、ボールは横に倒れた川口選手の身体の上を越えてゴールに吸い込まれてしまいました。テレビの時計計時がちょうど27’59を過ぎたところで、公式記録は28分となりました。
スタンドの日本サポーターたちも、日本時間の14日22時少し前、日本中でテレビ観戦していたファンも、一瞬何が起きたかわからないゴールシーンでした。プレゼントゴールのような形でゴールをゲットしたバティストゥータも、両手を軽く広げて拳を握りしめながら、ほんの一瞬だけ驚いた表情を見せましたが、すぐにチームメイトと喜びを分かち合いました。
試合を実況していたNHKの山本浩アナウンサーは「何かリズムを壊されて、息を吸っている間に点をとられてしまいました、ニッポン」と表現しました。
前半37分には左サイドからシメオネが入れたクロスにバティストゥータが高い打点のヘディング、ボールは右ポストに当たってゴール前に戻り、それをCロペス選手が押し込もうとしましたが川口能活がストップ、追加点は阻止しました。
そのまま0-1で前半を終了しました。
日本の中盤からDFにかけては、よく相手の攻撃を跳ね返しマイボールにするシーンが多いのですが、中盤から前線に入れるボールのうち、特にサイドからのクロスがほとんど通りませんでした。普段の試合なら一度作り直したり、崩しのパスを入れたりするところですが、相手MF、DF陣の危機察知能力、ボール奪取能力の高さを体感しているのでしょう。
とにかくシンプルにボールを入れようとする意識が強いためか精度が低くなり、長すぎてゴールラインを割ったり相手DFの網にかかるばかりでした。これがワールドカップという場なのでしょう。どうしても、いつもの精度が出せない攻撃ばかりになっていました。
ハーフタイムを終わって出てきた岡田監督にNHKのアナウンサーが一言インタビューをすると、岡田監督からは「絶対切れることなく集中して、必ずチャンスは来ると思うんで切れることなく集中していけ、ということを言いました。」という答えが返ってきました。
ハーフタイムのスタジアムをテレビカメラが映し出すと日本人サポーターの多い席が映り、磐田の山本昌邦コーチ、ナインティナインの矢部浩之さんが映り込こんでいました。こぶりなスタジアムらしく肩寄合う感じの座り方でした。
後半10分、最後尾近くから山口素弘選手が長いクサビのパスを入れると城選手がポストに入り中田選手に渡します。それを中田選手がペナルティエリアのすぐそばまで持ち込みますが、相手選手が後ろから一人、前から一人寄せてきたため身体が伸び切った状態でのシュートになりました。ボールはポスト左にそれましたが、やっと形らしい形になった攻撃でした。
後半16分、アルゼンチン、Cロペスに代えてバルボを投入。後半20分、日本は中山選手に代えて呂比須ワグナー選手投入しました。
後半20分から23分にかけては日本、自陣前にくぎ付けにされ相手FKを立て続けに浴びました。最後はGK川口能活選手が相手の波状攻撃を身を挺して食い止め、一旦、くぎ付け状態を切りました。
後半27分、アルゼンチン、DFセンシーニが指を痛めてチャモに交代。
後半31分、日本、センターサークル付近で得たFKを中田選手がすばやく右サイドを駆け上がっていた名良橋選手にロングパス、これが見事に通ったものの、名良橋選手はこれを止めずに右アウトサイドにかけるようにダイレクトシュート、しかし枠方向には飛ばず。やはり「止めていたら寄せられてしまう、はやく打たなくちゃ」という気持ちが、正確性の保証がまったくないダイレクトシュートに向かわせてしまったようです。
後半32分、アルゼンチン、シメオネの長いドリブルから右に流したボールが中央のバティストゥータに渡りフリーでシュートを許しましたがオフサイド。
後半33分、今度は日本、中盤でボールを受けた呂比須選手がドリブルで突進したところを倒されFK、これを呂比須選手が蹴り急いでしまいバーの上へ。これもピッチに入ってまだいくらも時間がたっていない呂比須選手の気持ちの余裕のなさでしょう。絶好の位置からのFKですから、じっくり自分の間合いをとって一発で仕留めてやるぐらいのゆとりがあればと思うのですが、傍で見ているほど生易しいものではないということなのでしょう。
後半36分、日本は右CKから名波選手が入れたボールが相手DFに弾かれたものの、これを相馬選手が拾い左サイドの山口素弘選手にパス、山口選手はゴールまで30mのところから正確なパスをゴール前に入れると秋田選手の頭にピタリと合いヘッドで叩きつけるように折り返します。
さきほど山口選手にボールを出した相馬選手がそのままゴール前に走り込み、秋田選手の折り返しに合わせようとスライディングを試みますが、わずかに合わず。
後半39分、日本、相馬選手に代えて平野孝を投入。
後半43分、日本、左サイドで平野選手がうまく処理してCKを獲得、これを蹴った中田選手のボールは相手DFに弾かれますが、日本が奪い返し右サイドの中西選手へ、中西選手はオルテガとシメオネ2人に挟まれますがスルリと間を割って入りペナルティエリアに侵入、ペナルティマーク付近にいた呂比須選手にグラウンダーのパスを送ります。千載一遇のチャンスでしたが呂比須選手のダイレクトシュートは寄せてきた相手DFに当たりゴールポストから外れました。
ロスタイムは3分の表示でしたが試合は45分+4分30秒を回ったところで終了ホイッスルが鳴りました。
中盤から最後尾の守りに関しては、やられた感のない試合でしたが、如何せん、日本の両サイドからのクロスがほとんど味方選手に合うことがないほど、普段どおりにやれないワールドカップのプレッシャーをまざまざと見せつけられた攻撃でした。
アルゼンチンの前線と中盤は、バティストゥータ、Cロペス、オルテガ、ベーロン、シメオネそしてサネッティの6人が入れ替わり立ち代わり、自在にボールを回しながら中央攻撃を何度も仕掛けてきます。
その結果、日本はファウルで止めることになり、そこで相手にFKの機会を与えてしまうという戦いになってしまいます。この試合で日本が犯したファウルは35回、この数字は第1戦を戦った32チーム中最多という記録を残しました。
必然的に日本は、自分の陣内での守りに時間が割かれるため、最前線の城選手と中山選手にボールを供給する中盤との距離が長くなってしまい、相手陣内でマイボールになったあとの攻めに時間がかかってしまう戦いになってしまいました。
そして、攻めに転じても相手の寄せの速さ、ボール奪取能力の高さを見せつけられ、攻撃に関しては、守る相手の役者が一枚も二枚も上のチームと試合をした体感が選手たちの中には残ったのではないかと思います。
その一方、GK川口能活選手を含めたDF陣は、それぞれ冷静に対応できたという手応えを持ったようで、収穫ではありました。
岡田監督は、交代枠を一人余して試合を終えましたから、采配に対する批判もありましたがバランスを崩してまで攻めに出た時に負うリスクの大きさを考えれば、このバランスを保ったまま同点を目指すという采配を責められないところもあります。
兎にも角にも、アルゼンチンの速く正確なボール回しを見せつけられてしまうと、我が陣営の攻撃の手薄感が際立ってしまう、そんな初戦だったと思います。
チケット問題、悲喜こもごも、それでも現地自治体の好意で大型スクリーン前で観戦
さて、チケットは無くても現地まで行ったサポーターと、チケットをより多く確保しようとした旅行会社等との衝突は、現地でも繰り広げられました。
旅行代理店の中には、手に入ったチケットを限られたツァー客に渡すため抽選会を実施するところもあれば、ダフ屋が横行しチケットの価格は高騰、1枚36万円で販売するダフ屋まで出現。背に腹は代えられないとダフ屋から20万円ほどで入手するところもあり、また、どうしても手に入らない代理店は、ツァー客から吊し上げのような批判を浴び、ただただお詫びするだけというところもありました。
6月15日のスポーツ報知朝刊によると、神奈川県のある家族は、高校、中学、小学生の4人の子供さんと両親合わせて6人、合計240万円を投じた大サッカー観戦ツァーが、チケット抽選のため2人しかスタジアムに入れない家族離れ離れの観戦ツァーになってしまったと報じていました。
このチケット問題を受けて、アルゼンチン戦を開催するトゥールーズ市は「日本人サポーターに、せめてスクリーンで試合を見て欲しい」と、市内のスポーツセンターと公園に試合を実況中継する巨大スクリーンを設置した。また座席も8,000席用意し、軽食や飲み物を無料配布したそうです。
スタジアムでは約37,000席のうち33,400席が埋まったといいます。6~7割が日本人サポーターだったそうですから単純計算で約22,000~23,300人、スタジアムに入れずトゥールーズ市が用意してくれたスポーツセンター内の巨大スクリーンの前で応援した約5000人、公園のスクリーンで観戦した人も合わせると約7,000人ほど、スタジアム、大型スクリーンともサポーターの数ではほぼ3倍とアルゼンチンを圧倒しましたが、試合結果はそうはいきませんでした。
チケット問題が表面化した日本時間6月11日には、どれぐらいの人たちが観戦できなくなるのだろうと見通しが立ちませんでしたが、結局、トゥールーズ競技場の収容能力に見合う観客が入り、そのうち日本人が6~7割だったといいますから、これ以上は無理なところに、さらに7000人ほどが入場できなかったほか、ツァー自体のキャンセルのために現地に向かわなかった人たち6000人ほどいるわけですから、そもそも存在しないチケットをあるかのように見せかけて旅行代理店からの予約申し込みを受けて予約金だけをだまし取った「空売り」や「二重契約」があったことは間違いなく、FIFAも事態を重く見て原因究明に乗り出さざるを得なくなりました。
国内各地もあちこちで大型画面前に大勢が集結、いわゆる「パブリックビューイング」文化の先駆け
一方、都内をはじめ全国のスポーツバーや大型スクリーンを備えている施設は、日本時間の放送時間帯が20~24時と仕事帰りの観戦にちょうどいい時間帯だったこともあり、どこも超満員の盛況ぶり、みな青いレプリカユニフォームをまとって日本代表の戦いぶりに一喜一憂しました。
新宿歌舞伎町にある映画館前の大型スクリーン前には約5000人が集結、六本木のディスコ「ヴェルファーレ」には約1800人が集結、40インチのモニター36台を組み合わせて巨大画面にして投影、人気タレントも大勢駆け付けて大盛り上がりの観戦となりました。
長野では、さる2月の冬季五輪で表彰式会場に使用されたセントラルスクウェアに170インチの大型スクリーンが設置され、時折雨交じりのあいにくの空模様にも関わらず約2000人が集結、まるでトゥールーズスタジアムで応援しているかのような熱い観戦となりました。
中山雅史選手、名波浩選手の出身地、静岡県藤枝市ではJR藤枝駅前広場にアストロビジョンを設置、続々と詰めかけたサポーターは最終的に約3000人、こちらも雨模様の中、ずぶ濡れのまま熱い応援が繰り広げられました。
2002年W杯の試合開催地に選ばれた大分市では、市内中心部のアーケード街に2台の大型ビジョンを設置、約3000人が集結、平松守彦県知事も加わり応援を繰り広げました。
プロ野球ダイエーホークスのホーム球場「福岡ドーム」では、プロ野球の試合終了後、アルゼンチン戦のパプリックビューイングに切り替えられ、約2万人のサポーターが縦10m、横35.2mの「ホークスビジョン」と呼ばれる大画面を見ながら応援を繰り広げました。
お気づきのとおり、まだ、この頃は国立競技場や他のJリーグスタジアムでのパブリックビューイングというアイディアがなく、福岡ドームの取り組みは、サッカー日本代表のパブリックビューイングの先駆けとなったのではないかと思われますので記録に留めておきます。
翌朝15日のスポーツ紙・全国紙報道は、概ね日本代表の健闘を称えるニュアンスでした。
・スポーツ報知「日本0-1 強豪アルゼンチン苦しめた!! 胸張れ世界デビュー」
・日刊スポーツ「日本1点涙 世界最強3トップ バティの1発だけ 候補アルゼンチンといい勝負」
・スポーツニッポン「日本惜しいっ0-1 歴史的初戦アルゼンチンに真っ向勝負、攻めた!」
・サンケイスポーツ「日本悔しいッ アルゼンチンに惜敗0-1」
・東京中日スポーツ「日本負けたアルゼンチン戦 よくやった!!0-1惜敗」
・毎日新聞夕刊「日本惜敗 W杯堂々の初陣 アルゼンチンに0-1」
新聞・テレビ等が報じたアルゼンチン戦は「これなら次はいける」「目標の1勝1敗1分けは十分可能」といった総括で、次戦クロアチア戦に対する日本中の期待は高まりを見せました。
しかし、同じメディアでも現地でシビアに試合を見ていた専門家は、こうした新聞・テレビの論調は「冗談ではない」と辛辣でした。
98.7月2日号Number447号に「緊急速報・日本vsアルゼンチン」をレポートした金子達仁氏は次のように語っています。
「おそらく日本では、2度の世界チャンピオンに輝いた国を相手に1点差の試合を演じたということで『日本善戦』だの『次につながる敗北』といったフレーズが氾濫していることと思う。もしかすると『決勝トーナメント進出が見えた』とやっているところまであるかも知れない。」「冗談ではない。」
「(中略)アルゼンチンは勝ち点3という最低限の収穫を手にしした。日本には何も残らなかった。(中略)」「私は、悔しい。」
「日本は自らチャンスを放棄してしまった。真の意味で善戦を演じるチャンスを捨てて、0-1という見せかけの善戦に逃げ込んでしまった。」
テレビ視聴率、サッカー中継史上最高60.5%を記録、ドーハの悲劇を大幅更新
日本サッカーの歴史的1戦、日本vsアルゼンチン戦をテレビ中継したNHK総合の視聴率が60.5%(関東地区)を記録、サッカー中継で過去最高として記録されている1993年のW杯アジア最終予選日本vsイラク戦、いわゆる「ドーハの悲劇」となった試合中継の48.1%を大幅に更新、史上最高を記録しました。
日本vsアルゼンチン戦の60.5%は、21時22分から23時30分までの平均視聴率で、23時23分の試合終了ホイッスルの時の瞬間最大視聴率は66.0%に達しました。試合はNHK衛星でも同時放送されていましたから、60.5%に衛星放送の6.8%を合わせると67.3%に達し、サッカーのみならず日本国内で中継された過去のスポーツ中継の中で最高記録となっている1964年東京五輪の女子バレー決勝日本vsソ連戦の66.8%を抜く「スポーツ中継史上最高視聴率」ということになりました。
テレビ視聴率に詳しい専門家によると、今回は「日曜日の夜、キックオフ時間がゴールデンタイムだったこと」「雨のため在宅者が多かったこと」「ニッポンの活躍が見たいという国民意識、特に35~50歳の年齢層の視聴がよかったこと」が揃ったことが要因ではないかと分析しました。
そして「土曜日の夜でキックオフ時間がゴールデンタイム」になる次戦クロアチア戦にも高視聴率が期待できそうとまとめていました。
アルゼンチン戦後の中田選手、中山選手交代に不満を岡田監督に表明、その夜、ゴードン氏と会った中田選手「チーム選びの最大の基準は監督を選ぶこと」と基準を伝える
この項も小松成美氏の著書「中田英寿 鼓動」から引用する形で、経緯を記録することにします。
中田選手は試合終了後、控室に戻る途中、右足の脛(すね)に強烈な痛みを感じたそうです。試合中は集中していて痛みを感じなかったのが、集中が解けた途端、出てきたのです。チームドクターの見立てでは「この傷は一生消えないだろう」というほどで15㎝ほどの長さの傷でした。アルゼンチンの選手に巧妙に受けたスパイクでした。
中田選手は後半16分の中山雅史選手の交代に不満を持っていました。それまで何度かパス供給を続けていく中で、次第に2人のイメージが出来つつありゴールの予感がしていたからです。中田選手はそのことを岡田監督に率直に伝えました。岡田監督はそれを聞きはしましたが、こう釘をさしました。
「お前と俺の考えがずれれば、それは、すぐにチームに跳ね返る。ヒデの言うこともわかるが、今は気持ちをひとつにしていくしかないんだ」
この小松氏の記述から推察すると、中田英寿選手は、自分の意に反して中山選手を替えられたことを引きずり、気持ちを切り替えて、平塚のチームメイトである呂比須選手をどう生かすかに全神経を集中するところまではいかなかったと思います。
思い起こせば、アトランタ五輪のナイジェリア戦のハーフタイムに続く2度目の、監督への不満表明です。今回は、押しも押されぬチームの大黒柱となった中田選手からの不満表明ということで、岡田監督は聞くには聞きましたが、暗に「二度と口にするな」と釘をさしたのです。
アルゼンチン戦の夜、中田選手は監督に外出の許可をとって次原社長とゴードン氏が待つホテルに入りました。
ゴードン氏は、あらためて中田選手にこう伝えました。
「あなたの実力がヨーロッパで活かされることは間違いない。ただ、最初にどの国の、どんなチームを選ぶかが、あなたの将来に大きく影響する。私が一番知りたいのは、あなたが何を基準にチームを選ぶかということです。」
中田選手はこう答えました。
「僕がヨーロッパのクラブに移籍するとしたら、一番大切なことの一つは監督のことです。正直に言って僕は、サッカーを始めてから今まで、完全に監督を信頼できたことがない。サッカーに関する考え方が食い違ったり、戦い方に疑問を持ったりしてきました。だから、移籍するチームを決めるときには、まず監督と話し合いをしたいです。僕が求めるのは、実践するサッカーの理論をすべて言葉にして表現できる監督、僕が百パーセント納得できるサッカーの理論を持っている監督です。僕がまったく疑うことなく信じられる戦略を提示してくれなければ嫌です。」
「そうじゃなければ・・・・。僕のプレーを信じ、僕の戦略を全面的に支持してくれる監督かな。そういう監督なら、話し合い、トレーニングを重ねてチームを作っていけると思うから。とにかく、どちらかのタイプの監督です。中途半端は駄目だと思う。」
ゴードン氏は「分かりました。あなたの求める監督を見つけ出しましょう。広いヨーロッパの中でなら、あなたの求める監督も見つかるでしょう。私は、そのために、地の果てまで駆けずり回る覚悟はできています。」と答えました。
そして2人は食事そっちのけでサッカー談義に盛り上がり、その様子は通訳のフジタ女史も呆れるほどでした。
以上、小松成美氏の著書「中田英寿 鼓動」から、中田選手がゴードン氏に伝えた内容を記述しました。
自分のサッカー観に絶対の自信をもった基準の表明です。「サッカーを始めてから今まで、完全に監督を信頼できたことがない。」という言い方は、それまでの日本のサッカー選手には考えられない言い方だと思いますし、世界のサッカー選手の中でさえも、ここまで言い切る選手はごく一握りではないかと思います。それほどまでに「自分のサッカー観のほうが正しい」と思っているということです。
それが中田選手の凄さであり、ゴードン氏も初めて中田選手のプレーを見た6月4日のユーゴ戦のメモに「彼には優れた監督が必要だ。中田の才能をさらに磨き導ける監督を擁するクラブ、それを探さなければ」と書き込んでいて「自分と同じ考え方を持った選手だ、やり甲斐がある」と感じたと思います。
その一方、この自らの信じるところを何ら臆することなく表明してしまう中田選手の、生来の流儀といってもいいやり方を、今後のサッカー人生の中で、どこまで貫き続けられるのか、ついつい心配になってしまうところです。
6月20日、フランス・ナント、日本代表第2戦、クロアチア戦
観客35,500人、天候・晴、気温34℃、キックオフ14時30分(現地)
日本代表の第2戦、舞台はフランス西部、大西洋にほど近いナント、人口約30万人の都市です。大西洋に注ぐロワール川の河口から約50km内陸に入ったところにあります。ベースキャンプ地のエクスレバンからは直線距離で500km以上離れた場所での試合となりました。
会場のボージョワール競技場は収容能力39,000人ほどですが、この日は公式発表35,500人とのことで、この日も一杯の観客で埋まったといっていいと思います。
スタジアムは、観客席を大きな屋根が覆っている関係で、応援している人たちにとってはありがたい競技場ですが、陽ざしはかなり選手を痛めつけそうです。
日本は、アルゼンチン戦から中5日、疲れはとれていてコンディションは悪くない中での試合となりましたが、この日のナントの気温は34℃、陽のあたるところでの気温は40℃ぐらいに達したといいますから、選手たちにとっては前年に体験したアジア最終予選の第2戦アウェーのUAE戦と同じぐらいの過酷な条件となったようです。
この過酷さがクロアチアにとっても相当なダメージになった場合、どちらがより大きいかの勝負になるかも知れません。
この日の日本の先発は次の11人、アルゼンチン戦とまったく同じでした。(敬称略・数字は背番号、(C)はキャプテン)
・GK 20川口能活
・DF 4井原正巳(C)、17秋田豊、19中西永輔、3相馬直樹、2名良橋晃
・MF 10名波浩、8中田英寿、6山口素弘
・FW 9中山雅史、18城彰二
対するクロアチアの先発は、
・GK ラディッチ
・DF ソルド、スティマッチ、ビリッチ
・MF ヤルニ、シミッチ、ユルチッチ、アサノビッチ、プロシネツキ
・FW スタニッチ、スーケル(C)
対戦相手クロアチアは、1991年に勃発した旧ユーゴスラビア内戦の末1995年に分離独立を勝ち取った国です。そのような背景からワールドカップ初出場ということになりますが、厳しいヨーロッパ予選を勝ち上がってきた実力は評価が高いチームです。
クロアチアのスタメンで目を引くのは、アレン・ボクシッチ、ズボニミール・ボバンという2人の世界レベルのプレーヤーが故障離脱していたことです。この2人が元気にスタメンに名前を連ねていたらアルゼンチンとほぼ同じぐらい脅威となったことでしょう。
ですから、この日のクロアチアは、慎重すぎるほど慎重な布陣と戦い方をしてきました。
ちょうど日本がアルゼンチン戦に敷いた布陣と同じ、守る時はウィングバックがDFラインに入り5人の陣形、攻めの好機の時だけウィングバックがオーバーラップするといった戦い方です。
開始2分、日本が左サイドで名波選手から相馬選手にパス、相馬選手が縦に走ってクロス、これまでの日本の得点パターンを思わせるような攻撃が出ましたが、これは相手DFに頭で跳ね返されました。上背のある相手DFの壁を越えるクロスが出せるかどうかが試された場面でした。
前半9分には2分の時と同じシチュエーションから名波選手がパスを繰り出しましたが受けた相手はオーパーラップしてきた中西選手、左足でマイナスのクロスを送りましたが、相手DFに足で跳ね返されました。
フィールドに紙吹雪のなごりが散らばって、風で少し飛んでいました。
前半10分、クロアチアが右サイドでプロシネツキがフェイントを入れながらゴール前にクロス、秋田選手がマークしていたスーケル、少し秋田選手から離れる動きをしたあとクロスのボールに右足を合わせハーフボレー、バーを越えて事なきを得ましたが、危険な男・スーケルの左足だったらと思うと、という場面でした。
前半12分になろうかという時、日本のゴール前に放り込まれたロングボールに対応した中西選手が相手選手を倒してしまいFK、ペラルティエリアの角付近でゴールまで20m弱、蹴るのはスーケル、得意の左足で右ポストの内側一番上を狙ったとわかるキックを繰り出しました。ボールは右ポスト外に外れましたが、怖さ十分の左足でした。
その直後、日本のカウンター攻撃、城がペナルティエリアの中に持ち込んで一度切りかえしてからシュート、それは相手DFにブロックされましたが、こぼれ球を拾った相馬選手が持ち込み左足でシュート、ボールはGKの逆を突くコースに飛びましたが右ポスト外にわずかに外れました。
前半17分、これはプレーではなくスタンドが映り、なぜかタレントのうじきつよしさんの横顔が大写しになりました。日本のテレビクルーによるものか国際映像かわかりませんが・・。
その映像の直後、日本が秋田選手から前線の城選手にクサビのパスを入れましたが城選手がヘッドで秋田選手方向に戻すように打つと、それが相手中盤アサノビッチへのパスになってしまいました。それをアサノビッチが前方に送ると、井原選手がクリアしきれず、ノーマークのスタニッチに通ります。スタニッチはドリブルでやや右に流れながらシュート、しかし川口選手の位置取りが良くファーサイドのコースも消していたことからシュートは左ポスト側に外れました。
スタニッチのシュート地点はペナルティエリア内でしたので、もしニアサイドに強烈なシュートが撃ち込まれたら危ないシーンでした。
日本が中盤でボールを持てる展開で少し前がかりになった時、相手にボールがわたると日本の両翼の裏が空きやすくなり、かなり決定的なピンチを招くことになりますので、不用意に相手にボールが渡らないようにしなければならない、一つの修正ポイントがはっきりしました。
前半19分、中盤でフリーでボールを持った中田選手から中山選手に当てるような強いパスが送られました。受けた中山選手が相手DFに押し倒される形になり日本のFK、ゴール前20mちょっとの場所です。
ここで名波選手と中田選手がボールサイドに立ちトリックプレーを見せます。前年のアジア最終予選のアウェー韓国戦でも見せた「ポヨン」です。名波選手が発案、岡野雅行選手が命名したこのトリックプレー、今回は名波選手がチョンとボールを蹴り上げると中田選手がロビングを相手DFの壁の後ろに落とすように上げました。
相手の壁のところに並んでいた城選手が意図を察していち早く振り向きボールのところに寄りましたが、如何せん、一度頭で前に送ったため、ボールはゴールラインを割ってしまいました。NHKの実況を解説していた山野孝義さんも思わず「いまのボールねぇ、落としちゃダメですよ、城、スライディングしてでも、ここはシュート打って欲しかったですよ」とコメントしました。
前半29分、NHK実況の野瀬正夫アナウンサーが解説の山野さんに「これまでのところ、どちらのペースだと見ていますか?」とたずね山野さんが「クロアチアのペースだと思いますね、クロアチアは最初から来るかなと思ってたんですけど、引き分けでもいいんじゃないか、というような戦い方をしていますね」という見立てをしたところで、クロアチアがこの試合初めてのCKを得ました。
左から入れたCK、後ろにこぼれたボールを中田選手が拾い、振り向くのが難しいと見て、ペナルティエリアの外側にいた城選手に横パスを送ります。城選手は中に運ぼうとしますが相手に寄せられそうになります。そこに相馬選手がフォローに来たことから城選手はヒールで相馬選手に出そうとしました。しかし、そのパスはズレてしまいスーケルに渡ってしまいます。
その時、副審が旗をあげ実況の野瀬アナウンサーも「オフサイド、オフサイド」と連呼しましたが主審はプレーを止めませんでした。スーケルに渡ったボールは中西選手がカットして事なきを得ましたが、解説の山野さんが「レフェリーがよく見てましたね。敵からのボールはオフサイドになりませんね」と理由を話してくれました。そして「いまのは、城の判断ミスなんですよ、あれは相手のゴール前でやるプレーですね」と付け加えると、野瀬アナウンサーが「自分のゴール前でやるプレーではない(いうことですね)」とまとめました。
中田選手から中山雅史選手にピンポイントのキラーパス、中山選手、見事なももトラップからシュート、この試合最大のチャンス
前半33分、中盤でプロシネツキがドリブルしながら突破しようとするところを名波選手がカットを試みると、今度は後ろを向き持ち直そうとしましたが、それを中田選手がかっさらう形でインタセプト、中田選手はそのままドリブルを始めました。その時、中田選手の前方10mほどのセンターラインあたりに中山雅史選手がいて、中田選手のドリブル開始と同時にゴール前への疾走を開始しました。
中山選手は、中田英寿選手とのコンビネーション作りの中で「ボクがボールを持った時点で、ゴンちゃんは相手のマークを外すことだけを考えてよ」と言われていたことから、マークしてくる選手の視野から消える位置取りをしようと走ったといいます。
中田選手も30mほど疾走、その間、前線の様子を確実に視野にとらえ右足で狙いすましたミドルパス、これがゴール前に走り込んだ中山選手の受け地点にピタリと届きました。
中山選手がそれを右太ももでトラップするとペナルティエリアに少し入った地点に落とすことに成功、ゴール正面でキーパーと1対1の絶好のチャンスを迎えました。
4月、4試合連続ハットトリックを達成した頃の中山選手であれば「いっただきぃ!!」と声をあげんばかりにキーパーの動きをよく見て左側に蹴り込んだでしょうけれど、今大会に臨んでからは相手の寄せの速さに、狙う暇を与えてもらえない気持ちだったと思います。キーパーとは10mほどの距離がありましたから左でも右でも打ち抜けたでしょうが、現に、右側から相手DFが捨て身のスライディングでブロックに来るのが目に入りました。
それでも中山選手は、右足のアウトサイドにかける気持ちで右側を狙ったと思います。キーパーが2~3mのところまで詰めてきたところでシュートしたのですがキーパーが左手を伸ばしてちょうど届いてしまいました。
実に惜しいチャンスでした。なかなか訪れないであろう限られたチャンスを生かすことはできませんでした。あまり大げさに悔しがったりしない中山選手もさすがにピッチに突っ伏して、こぶしでピッチを叩きつけました。
中山雅史選手の惜しいシュートから1分後、前半35分、今度はクロアチアにチャンスが訪れます。中田選手が左サイドからのスローインを受けて相手選手に寄せられながらもキープ、そのままペナルティエリアの前まで持ち込むとシュート、しかしブロックされたボールがアサノビッチに渡り40mほど疾走を許します。大きなストライドのアサノビッチに追走する山口素弘選手も身体を寄せるのが精一杯、しかし、アサノビッチはボールをカットされるのを恐れたかスピードダウン、右タッチライン際のスタニッチにボールを渡します。
スタニッチはマークにきた選手の寄せが甘いと見るや、左足でゴール前に低い弾道のクロスを入れました。それはスーケルからの合図によるクロスでした。スーケルは自分より前にいた中西選手を後ろから追い越すようにあっという間にボールに寄りました。
一瞬のうちに前に出られた中西選手は、あわててスーケル選手の腰のあたりを掴みにかかりますが振り切られ、引きずられるように倒れてしまいました。
スーケルは、川口選手の目の前でボールコントロールのため後ろ向きになりますが、身体を反転させながらシュートを打ちました。少し後ずさりしながらのシュートになったため威力が弱く、詰めていた川口選手はあわてて飛び込まず、スーケルが前を向いてシュートを打とうとするボールを両足に挟むようにスライディング、ボールを絡めとって事なきを得ました。
スーケルは味方に両手で「フォローに来てくれよ」というポーズをとりました。スーケルにゴール目の前でフリーでボールを持たれたという意味では大きなピンチでした。
続いて前半38分、右サイドセンターライン付近でボールを受けた秋田選手、前方に出すコースがないと見たかバックパスを出します。出した相手が井原選手だとすれば、かなり距離があるところに緩いパスを出しましたから、その間にいたスーケルにお誂え向きのパスになってしまいました。スーケルはドリブルで疾走、井原選手が少しでも外側に押し出そうとしながら必死に並走します。そこに中央後ろから中西選手が全速力でフォローに入り、そのままスライディング、見事ボールをカットして味方に繋げました。
ここもスーケル1人の突破だったことで助かりましたが、危うく致命的なパスミスとなるところでした。
前半ロスタイム1分の最後のプレーで日本CKを獲得、左から中田選手が打ったCKは大外、城選手に合いますがヘディングはゴール右にはずれ前半終了。
前半の途中から、クロアチアが無理に前線にボールを放り込む場面が減り、後ろでボールを回す場面が目立ちました。
時間は午後3時半近くですが、気温は34℃、ピッチ上は陽炎が立ち40℃近くになっているだろうという過酷な条件となってきました。
ハームタイム終了後、後半からクロアチアは、DFスティマッチに代えて、FWブラオビッチを投入しました。これにより最前線にいたスタニッチが一列下がって右サイドに入り二列目をスタニッチ、アサノビッチ、プロシネツキの3枚に厚くした形になりました。
けれども、その陣形を生かした中盤にボールを集めるサッカーはまだ見られず、後半しばらくは日本ペースが続きました。
日本は、ここが勝負どころと見たのか、後半16分、中山雅史選手にに代えて岡野雅行選手を投入しました。岡野選手はさっそく中田選手からのサイドへのパスに反応する形で突破を図り攻撃を活性化させました。
しかしクロアチアはバックラインを下げさせ、岡野選手に裏をつかせないように対応したため岡野選手にボールが出ても、すぐ相手DFが寄せてきて突破は見られなくなってしまいました。
後半22分、今度は、クロアチアがMFプロシネツキに代えて、同じポジションにマニッチを投入しました。
この時間あたりから日本の選手にも徐々に疲れが見え始めたのに加え、クロアチアのロングボールのため、前線と最終ラインの間が間延びしてしまい、それを突いて逆にクロアチアの中盤が動きのいいマニッチの効果もあり自由にボールを持つ時間が増えてきました。
25分には中西永輔選手ににイエローカード、アルゼンチン戦に続いて2枚目となったため、3戦目ジャマイカ戦は出場停止となりました。
27分、アサノビッチ選手からのセンタリングを受けたスーケル、GK川口能活選手が前に出ていたのを見てチョップキックでシュート、バーに当たって外れたもののヒヤッとする場面でした。
クロアチア、それまで抑え気味にしていた攻撃のモードが、プロシネツキ交代、マニッチ投入あたりから、積極的に前に出る場面が増えていたのでした。
クロアチア、アサノビッチからスーケルにクロス、スーケル、切れ味鋭い左足を一閃
そして後半32分、センターサークルの少し自陣側から名波選手が中田選手に出した縦パスを中田選手がダイレクトで軽く山口選手にはたいたのですが、それを山口選手と対面の位置にいたアサノビッチ選手が素早くカット、ボールはスーケルに渡り、それをアサノビッチに返すとアサノビッチは中央にスルーパス、これは井原選手がスライディングしながらカットしましたが、再びボールがアサノビッチのもとへ、今度はアサノビッチ、左へ流れながらペナルティエリアに侵入、そこから真横にクロスを入れます。アサノビッチ選手についていた秋田選手はジャンプしますが届かず、中央の井原選手そして右サイドの中西選手の頭をかすめるようにボールがスーケルに渡ります。
スーケルは左足でトラップしたあと、そのまま身体を90度ひねるようにして、また左足を振りぬくとボールは、ブロックに飛んだ中西選手の両足の間を抜け、川口選手の左下に飛んできました。川口選手が辛うじて手で弾こうとしましたが、弾ききれずワンバウンドしたボールが無情にもゴールに吸い込まれてしまいました。
日本が、中盤でボール奪取を狙っていたクロアチアの網にかかり、アサノビッチが持ち上がった時、相手のツートップがボールをもらえる位置に動いていて、アサノビッチがそこに正確にクロスを供給し、受けたスーケルが一発で仕留めるという、ここぞという時の正確性・集中力を見せつけられてしまいました。
やはりクロアチアはただの初出場国とはわけが違う国でした。
1点を許した日本、後半34分、DF名良橋選手をさげてMF森島寛晃選手を投入、DFも3パックから4パックに変更して、中盤を厚くして攻撃的に行きます。森島選手の投入はスーケルにゴールを割られる前に準備を始めていたのですが、後手に回ってしまいました。
さらに、MF名波浩選手をさげてFW呂比須ワグナー選手を投入したのは後半39分になってからです。
後半39分、右サイドでボールを受けた中田選手がペナルティエリアに張っている呂比須選手にピンポイントのクロス、呂比須選手が相手DFの前に出るように倒れ込むようにヘディング、頭ですらすようなシュートを放ちましたが、わずかにゴール左にそれました。
一方のクロアチア、後半43分、FWスタニッチを下げDFトゥドロを投入します。ガッチリと守りを固めたクロアチアの牙城は崩せずロスタイム2分、前線に入れる長いボールはことごとく相手に阻まれて47分6秒、試合終了ホイッスルが鳴りました。
日本は連敗となりました。
多くの専門家が指摘したのは、日本のミスの多さ、特にパスミス、日本は味方選手に丁寧に出すパスが持ち味なのですが、そのためスピードが緩いバスが多くなり、味方との距離が長い場合はカットされるリスクが大きくなります。また自陣で守っている中で味方選手の状況を確認もせずに出すバックバスによるミスなど、この大事な試合で、これほどミスが多くては勝てないという点が一つ。
そしてもう一つは、岡田監督の試合の流れを読む未熟さというか、勝利に向けて打つべき手が後手に回っているという点でした。岡田監督はアルゼンチン戦で得た守りの手応えを大事にするあまりバランスを崩したくない気持ちが強すぎて、勝ちに行く選手交代や布陣変更策の手を打つのが遅すぎたという点です。
そのため、やり方次第では勝つことさえできた試合だったけれど、この日の選手のミスの多さと監督の采配では負けて当然という評価が多かった試合でした。
選手たちにも悔いの残る試合だったと言えそうです。
スタンドの3分の2は日本人サポーター、おそらく23,000~24,000人といったところでしょうか。ハームタイムに実況の野瀬アナウンサーは「ニッポンのサポーターが8割以上いるんではないでしょうか」とコメントしました。解説の山野孝義さんも「ニッポンのホームといっていいですね」と応じましたから、かなりの割合に見えたことでしょう。もし8割だとすると28,000人ほどになり、まさに、かなりの数です。
そしてサポーターの「オ~~オオオ~~~ニィポン、ニィポン、ニィィッポン!!」の応援コールも場内一杯に響き渡る音量でしたから、第1戦に続き応援では相手を圧倒したようですが、試合終了のホイッスルの瞬間、静まり返りました。勝利を信じてほとんど休むことなく続けた応援でしたが報われませんでした。
岡田監督「惜しい試合でも負けは負け」
試合後の会見で岡田監督は質問に答える形で次のように述べました。
Q.連敗となりましたが?
A.目標は一次リーグ突破でしたが、決勝トーナメントに行くチャンスは少なくなりました。勝つしかない、チャンスは必ず来ると粘り強く思っていましたが、世界の壁、世界のゴールは遠かったという気持ちです。
Q.惜敗というもどかしさはあるか?
A.もどかしさと言いますか、選手には素晴らしい経験になる試合でしたが、ワールドカップは結果がすべて。惜しい試合でも負けは負けです。
Q.世界の壁と言われましたが?
A.個人の力ではかなわないのは大会前からわかっていました。それをチームの力、組織の力で勝負しようと思っていた。残念ながら結果は出ませんでした。
Q.具体的には?
A.相手1人に対して、2人の力で勝とうと努力してきました。
Q.スーケルにやられましたね。
A.失点は中盤での自分たちのミスパスが原因。そこから速攻でやられた。あそこで競り勝つか負けるかがポイントだった。
Q.暑さの影響はあったか?
A.両チーム同じことなんで。クロアチアより体力もコンディションも負けていないと思ったし、15分過ぎたら(相手に)疲れてくる選手が出てきて、中盤の攻撃で(こちらが)フリーになる選手が出てくると考えていたが。
Q.あと1試合残っていますが?
A.日本のサッカーはこれで終わりではありません。2002年、2006年とずっと続く。これですべて終わったわけではないんです。
Q.次の目標は2002年日韓共催W杯ですか?
A.日本のサッカーにとってはそうでしょう。しかし、私にとってはまだジャマイカ戦が残っている。いいサッカーをして勝ちたい。その一戦に全力を尽くすだけです。
Q.今後については?
A.攻守のどちらかができたら、どっちかができない。世界に追いつくには相当時間がかかる。ずる賢くやる時はやっていかないと数年かかる。選手たちはこれからもあるが、私は次が最後かも知れません。
アルゼンチン戦に続きチケット入手できた人、できなかった人、さまざま観戦模様、国内でも各地に応援の輪
翌朝の毎日新聞朝刊は、クロアチア戦観戦に来た日本人サポーター30人に取材、チケットの入手方法を聞いた結果を報じました。それによると30人中18人が観戦ツァーや日本サッカー協会の抽選販売といった、いわば通常のルート組で、7人がダフ屋から入手したと答え、相場は8~10万円だったそうです。残り5人は自分のツテで欧州に来てから入手した人でした。
また同紙は「フランス組織委員会」が、チケットの大量不足問題に対応するため、緊急措置として各国が売りさばけなかった券を回収、6月12日から14日にかけて日本の旅行代理店向けに印刷しなおして供給した券が含まれていたと報じました。そして「券不足でやみ値が10倍以上になる一方、相当数の余剰券が存在したちぐはぐな実情を示しており、組織委の不手際があらためて指摘されている」と締めくくりました。
またスタジアムに入れなかったサポーターのためにナント市が大型スクリーンを3ケ所に設置、スタジアムの入口では大型スクリーンへの移動方法を日本語でアナウンスしてくれる配慮もしてくれました。この日チケットを持たないままやってきた日本人サポーターは約4000人ほどだったようですが、最後までチケットが手に入らなかった約2000人が大型スクリーンに移動して試合に見入ったといいます。
それも空しく、試合終了後、呆然としたまましばらく席を立とうとしませんでした。
一方、日本国内でも各地でアルゼンチン戦に続き応援の輪ができました。
東京・新宿歌舞伎町の映画館前の大型ビジョン前には約12,000人(15,000人との情報も)が詰めかけました。これに対応して新宿警察署から約150人が警備にあたりましたが、あくまで混乱防止が目的、盗難抑止までは目が届かなかったためか、試合後、歌舞伎町交番に10人ほどが、観戦に夢中になっている間にスリ被害に遭ったと訴えました。中には背負っていたリックサックから財布はもちろんのこと携帯電話、手帳、本などありったけを盗られ、日本代表の敗戦とスリ被害のダブルショックとなった人もいました。
六本木のディスコ「ヴェルファーレ」には約1600人が集結、試合前にWOWOWアナウンサーの柄沢晃弘さんを司会に、サッカー解説者・信藤健仁さん、イラストレーター肥塚正さんによるトークライブなどで観戦を盛り上げました。
川崎・映画館チネチッタが映画用スクリーンを使って館内に約900人、場外のモニタースクリーン前に約1000人が集結、敗戦の瞬間には泣き出す女性も。
大阪・此花区舞洲アリーナの600インチ大画面前には約2000人が集結。
福岡・福岡ダイエーホークスのホームスタジアム、福岡ドームではアルゼンチン戦の時、ダイエーホークスの試合終了後だったことから、スタジアム内の「ホークスビジョン」を見ながら約2万人が応援しましたが、今回は試合中ということでスタジアム内スポーツバーの画面だけでの応援でしたが、それでも約1000人がホークスの試合そっちのけで応援しました。
テレビ視聴率、アルゼンチン戦をさらに更新、60.9%を記録
日本サッカーが歴史上初めてワールドカップの舞台で戦ったアルゼンチン戦は、歴史的試合にふさわしい60.5%のテレビ視聴率を記録、サッカー中継における視聴率の記録を大幅に更新したばかりでしたが、今回のクロアチア戦は、それをさらに更新する60.9%を記録しました。
特に、前年のアジア最終予選のヒーロー・岡野雅行選手が投入された後半、その岡野選手が右サイドを突破してクロスをあげた後半18分には瞬間最大視聴率67.9%、こちらもサッカー中継における記録を更新しました。
これについて専門家は「クロアチア戦の放送曜日・時間帯の関係で、翌日が学校が休みの金曜夜だったことから、母親と就学児童がともにテレビ観戦に向かったことが要因」と分析しました。
ワールドカップ初勝利を信じて、この日も日本列島は家庭でも繫華街でも、いたるところでサッカー日本代表の応援風景が見られた夜となりましたが、最後は落胆のため息が列島を覆い尽くして終わりました。
グループリーグ敗退決定、岡田監督辞意表明、専門家は冷徹に「善戦では済まないのがW杯」
日本がクロアチアに敗戦、翌日21日、アルゼンチンがジャマイカを破ったため、アルゼンチンとクロアチアが2勝、これで日本のグループリーグ敗退が決定しました。
これを受け、岡田監督が記者団に「責任をとります」と語ったことから、マスコミは一斉に「岡田監督辞意表明」を報じ「ジャマイカ戦を花道に」といった論調になりました。
さらに日本サッカー協会・大仁強化委員長が続投要請するつもりであることも報じ、岡田監督が「続投要請を受けても固辞」という姿勢であることから、後任監督選びに入る模様と付け加えました。
アルゼンチン戦、クロアチア戦ともに0-1だったことから、グループリーグ敗退が決まったとはいえ、まだ「ここまでは日本善戦」のムードが漂っていましたが、専門家の目は冷徹でした。「善戦するだけでいいなら、日本の力があればできることはわかっていた。W杯はそれでは済まない場、勝しかない場である」と厳しい指摘が出ました。
98.7.8サッカーマガジン誌で財徳健治氏は次のように書いています。
「(アルゼンチン戦、クロアチア戦とも)結果として残った0-1のスコアに、日本では善戦したとの声が多いらしい。賛成できない。『いつでも』とは言わないが、善戦するだけでいいなら日本の力があればできる。それくらいのことは分かっている。」
「W杯は善戦するための場ではない。慰めにしかならない声に加担したくはない。出場の目標をかなえた後は「w杯で勝つ」。それしかない。日本代表は厳しく内容を問われるチーム、存在になったのだ。むろん、選手たちも『善戦した』では満足していないはずだ。(中略)」
「アルゼンチンもクロアチアも試合の内容はどうあれ、日本から『勝ち点3』すなわち勝利を計算していたはず。(中略)結果として残るものの差、グループリーグ敗退と決勝トーナメント進出を考えると、これこそが圧倒的な違いとなるのだ。」
「W杯新入生の日本に、先輩たちのありがたい「鞭(むち)」。ズシリと感じた痛みにひるんでいては、明日につながる戦いはできない。」
また98.7月16日号Number448号で対談した金子達仁氏と、作家の馳星周氏は「善戦はもういらない」という見出しのついた対談で次のように語り合っています。
馳 「(観戦しにフランスに)来る前は、初出場だから(勝てなくても)仕方ないって思っていた部分があったのは認める。でも、スタジアムで分かった。勝たなきゃ満足できない。テレビで観てたらどうか分からないけどね。現地に来ていて、日本が本当に出るんだってことは、ものすごい感動たろうと思ってたけど、そうじゃない。ここで勝ってこその感動なんだって。」(中略)
馳 「(現地にいる間に)日本から電話がかかってきたり、かけたりするじゃないですか。『どうなの、そっちのテレビとか新聞の反応は?』って僕が聞くと、『善戦』『惜敗』だっていうじゃない。思わず叫んだよ。『死んでしまえお前ら! 』。編集者は『馳さんそんなに怒らないでも・・・』って、でも、これが怒らずにいられるか。」
金子 「もう善戦はいい。」
馳 「善戦、惜敗はいらない。頼むから勝ってくれ。ヤケ酒じゃなくて祝杯あげたいよね。壊れたいよ、壊れたい。実際に僕ら、ヨーロッパや南米の人間じゃないから、金子さんにヨーロッパのクラブチームがいいから観に行ってください、っていくら言われたって、まぁ、実際そうだとは思うんだけど、自分がその一員にはなれないわけでしょ。」
金子 「やっぱり、日本代表に勝ってもらうしかないんです、俺たち。」
馳 「そう、勝つしかない。」
風雲急を告げる中田選手移籍に向けた動き、移籍市場でも暗躍するサッカービジネスに巣食う悪徳エージェント
クロアチア戦を終えてグループリーグ敗退となった段階から、中田英寿選手の海外移籍に向けた活動が、急速に進み始めました。
一つはワールドカップ期間中に、エージェントを名乗りながら暗躍している有象無象の輩に、中田選手の所属事務所・次原社長が翻弄されかねない状況が生まれたためです。
ここからまた、小松成美氏の著書「中田英寿 鼓動」から引用する形で、経緯を記録することにします。
実はアルゼンチン戦が終わった翌日あたりから、次原社長の携帯には、多くのマスコミから中田選手の移籍先がどこになるのかを聞きたいと、ひっきりなしに電話がかかってきていました。一部のスポーツ紙が憶測で記事を書いていて、その確認のためでした。
さらに次原社長を悩ませていたのが、クラブの関係者やエージェントを名乗る見知らぬ人間からの電話でした。
そうした動きはロンドンにいるゴードン氏のもとにも届いていて、ゴードン氏は次原社長に連絡を入れました。
「クロアチア戦が終わったら、各クラブは中田獲得に向けて動き始める。中には胡散臭い話も多くなる。中田の名前はワールドカップの2試合で世界中に知れ渡ったから、怪しげな連中も大勢動き始める。」
次原社長は、中田選手のために数多くのエージェントと接触して、少しでも条件のいい移籍を実現したいという気持ちと、移籍市場という巨大なビジネスマーケットに巣食う得体の知れないエージェントから中田選手を守らなければならないという気持ちの間で揺れ動いていました。
グループリーグ敗退同士の日本とジャマイカ、両者に垣間見えたメンタルの違い
2戦を終わってエクスレバンで調整中の日本代表は、現地時間6月22日午後から23日午前にかけて変則的な休みが与えられました。岡田監督が「ここ(フランス)では休みはいらない」という方針だったこともあり、丸一日の休みにはせず半日×2という休ませ方をしたのです。
アルゼンチン戦、クロアチア戦に連敗した日本代表には明らかに変化が見られました。表向きは「ジャマイカ戦に全力を尽くす」「こんどこそ勝ちに行く」と、これまでと何ら変わらないコメントに聞こえますが、岡田監督も選手たちも、どこかトーンが弱くなっていたのです。
それもそのはずです。ワールドカップが始まるまでは初戦のアルゼンチン戦に監督も選手たちも全集中してきて、アルゼンチン戦に負けたあとも「次こそは」と気持ちを奮い立たせてきた結果として「グループリーグ敗退」という現実を突き付けられてしまったのです。
ここで更に対ジャマイカ戦に向けて気持ちを立て直せといっても、一度切れた気持ちを奮い立たせるのは、基本難しいことでしょう。集中力が高まっていればいるほど、その集中力が切れた時の落差が大きいと思います。
これは日本人の精神性によるところもあるでしょう。日本人は、物事に熱心に取り組むことを通じて集中力を高め、その精度を高めることができる国民性を持ってはいますが、逆にその集中がプツンと切れた時の反動も大きいという面です。
それがジャマイカ戦で、ジャマイカの持つ国民性との差にならなければと漠然と考えてしまいます。
そのことは岡田監督ものちにこう振り返っています。
「ジャマイカがアルゼンチンに5点も取られて負けているのに、試合後、選手たちがスタジアムのファンに向かって拍手しながら笑顔で引き揚げていったのをテレビで観てショックを受けました。」
「自分たちは昨日、クロアチア戦でなんでこうできなかったんだろう。ジャマイカと日本の敗戦に対するこの受け止め方の差は、一体何なんだ。」
「国民性とか、文化とか、歴史とか、そういう要素をすべてサッカーチームというのは象徴するのだろうか」
6月26日、フランス・リヨン、日本代表第2戦、ジャマイカ戦
観客39,100人、天候・曇り時々晴、気温25℃、キックオフ16時00分(現地)
日本代表の第3戦、舞台はベースキャンプ地のエクスレバンから西へ約80km、日本代表が試合を行なう3都市の中でエクスレバンからもっとも近い場所です。
リヨンは、都市単体ではフランス第3の都市ですが、都市圏の大きさでは第2の規模をもつ大都会で、フランスの新幹線にあたるTGVがパリからリヨンまで最初に開通したことでも知られています。
会場のジェルラン競技場は収容能力44,000人ほどですが、この日は公式発表39,100人とのこと、両国ともグループリーグ敗退が決まった同士の試合からか、やや空席があったようですが、ジャマイカサポーターはごくわずか、大半がブルーのユニフォームを着た日本人サポーターで埋め尽くされた感がありました。
この日の天候は午前からの雨があがり曇り時々晴で気温25℃、第2戦のクロアチア戦の条件に比べれば少しはマシというところだったでしょうが、湿度が高い分、気温以上に蒸し暑く感じる中での試合となりました。
この日の日本の先発は次の11人、クロアチア戦でイエローカードを受け累積による出場停止処分の中西永輔選手のところに小村徳男選手が入っただけの変更でしたが、布陣を攻撃的に変えました。これまでの2試合、ボランチの位置に山口素弘選手と名波浩選手を2枚並べていた布陣を、名波選手を1列上げて中田英寿選手と並べる形、右に中田選手、左に名波選手という布陣にしました。(敬称略・数字は背番号、(C)はキャプテン)
・GK 20川口能活
・DF 4井原正巳(C)、17秋田豊、5 小村徳男、3相馬直樹、2名良橋晃
・MF 10名波浩、8中田英寿、6山口素弘
・FW 9中山雅史、18城彰二
対するジャマイカの先発も、予想されていたFWのバートンを外し長身のゲイルに変えてきました。日本と中盤でボールを奪い合うことを避けて、後方からロングボールを前線に当てる戦術をとってきたのでした。
・GK ローレンス
・DF ロー、シンクレア、グッディソン(C)
・MF マルコム、ガードナー、シンプソン、ウィットモア、ドウズ
・FW ホール、ゲイル
対戦相手ジャマイカは、南北アメリカ大陸の間にあるカリブ海の島国です。キューバ島の南にあり当時人口約250万人程度、ワールドカップ出場枠が今大会から32ケ国に増えた恩恵を、日本同様受けた国で、北中米・カリブ海予選を3位で通過、本大会初出場を決めました。
英語圏の国で「レゲエボーイ」の愛称を付けられたジャマイカ代表チーム。とはいえ、何人かの選手はイングランド・プレミアリーグでプレーしており個人技では侮れない実力を持つチームです。
ワールドカップ初出場の日本代表を指揮して、これが最後の試合になることを心に決めていた岡田監督、試合前のミーティング、のちに「一度ぐらいは気の利いたことを言ってみたいと思っていた」と振り返った、とっておきの訓話を繰り出しました。
ある詩の一節を引用したもので、こう話したそうです。
「地球が誕生して数十億年、人間が生まれて数万年、その中の人生80年なんて短いし、サッカーのゲームなんて90分しかない。だからこそ、その一瞬一瞬を無駄にしなうよう、精一杯生きようじゃないか」
この詩の出典について、作家・井上靖の詩集「遠征記」からひいたと書いている方もいましたし、小説からひいたと書いておられる方もいましたが、どうも、井上靖の別の詩集「北国」の巻頭にある「人生」と題した詩ではないかと思います。
この訓話を選手たちはどう聞いたでしょうか? アルゼンチン戦、クロアチア戦、勝利がダメでも勝ち点、勝ち点がダメでも得点を、と身体と心を目いっぱい研ぎ澄まして、それこそ全集中して戦ったにもかかわらず結果が出なかった、そこから来るどうしようもない脱力感から、もう一度身体と心を立て直して「勝利」を目指し、結果としてダメでも最低でも勝ち点だけでももぎ取って帰るんだ、そういう闘争心に火をつけることができたとすればいいのですが・・。
岡田監督は、第2戦のクロアチア戦の翌日、ジャマイカがアルゼンチンに0-5で大敗したにも関わらず、ファンに向かって拍手しながら笑顔で引き揚げていったのを観てショックを受けたそうです。ジャマイカと日本の敗戦に対するこの受け止め方の差は、一体何なんだ、と。そのことも紹介してもよかったのではないでしょうか。「最後は、みんながそれぞれ持っているサッカーの楽しさを出し合って、笑顔で引き揚げるようにしようぜ、俺たちも」とか・・・・
この日のテレビ中継は、日本時間6月26日23時キックオフということで、NHKが22時35分から放送を開始しました。総合テレビでの中継は実況は山本浩アナウンサー、解説は木村和司さん。NHK-BSの実況は野地俊二アナウンサー、解説は加茂周さん。このあとの記述はNHK-BSの放送からひいています。
試合は立ち上がりから日本の攻勢が見られます。開始1分、最後尾からテンポよいパス回してセンターサークル付近の中田選手にボールが渡ります。中田選手はドリブルで持ち上がり右サイドの城選手にパス、城選手もドリブルで持ち上がってからフォローに上がってきた名良橋選手に戻すと、名良橋選手はダイレクトパスでペナルティエリア内に侵入していた名波選手に送ります。
そのパスは名波選手の隣りにいた相手DFがクリアを試みますが、目の前にいた名波選手へのパスになりました。名波選手はもらったパスをノートラップで強烈な左足シュート、ボールは惜しくもポストとバーの角のところを通過してしまいました。
いきなりの強烈なシュートでしたからスタジアムは一瞬大歓声に包まれました。
次に前半5分、左サイドから小村選手が相馬選手にパス、それをまた小村選手に返して相馬選手が左サイドを駆け上がります。小村選手は今度はやや中寄りの名波選手にパスを出します。名波選手は相馬選手の走りに合うように左足アウトサイドで押し出すようなパスを送ります。これは勝手知ったるコンビネーションの如くピタリと相馬選手に通ります。相馬選手は縦に走りながらゴール前に直角のクロスを入れると、そこに中山選手が相手DFと競り合いながら突っ込んできました。最後は中山選手が相手DF2人囲まれる形になりながら足を伸ばしてボールに触りに行きました。相手GKを含めて4人がもつれ合う形のプレーとなりましたがボールはクロスバーの上、日本のCKとなりましたが、これもいい形の攻めでスタジアムが湧きました。
前半9分、今度は右サイドで名良橋選手のパスを受けた中田選手が、左サイドでフリーになっていた城選手に距離・強さともに申し分ないパスを送りました。城選手には少なくとも3つの選択肢がある絶好のチャンスとなりました。一つはもちろんダイレクトでシュート、2つ目はワントラップしてのシュート、3つ目は右サイドに上がってきた中山選手にパスを出す、城選手は瞬時の判断でダイレクトボレーを選択しました。ボールは見事にヒットしたものの飛んだコースは右サイドのポスト外側でした。
悔しかったことでしょう。3試合目にして初めて絶好のフリーのチャンスをもらったのですから。解説の加茂さんは「同じ外れるにしてもバーの上に行ってしまうのと値打ちが違ういいシュートでしたね」とコメントしてくれました。
前半15分、この試合初めてジャマイカが日本陣内に攻め込みます。右サイドから中央2列目のウィットモアにパスが通り、ウイットモアは詰めてきた相馬選手をかわすと右ウィングのホールにパス、ホールがゴールライン際まで運ぶとゴール前にクロス、これは川口選手がパンチングで逃れると、今度は左サイドからクロス、これはゴール前を横切り小村選手が頭でコーナーキックに逃れました。
ジャマイカはそのCKからのボールをヘディングシュート、ゴールネットを揺らしましたが、GK川口選手についていた選手が守備を邪魔したとしてノーゴールの判定、事なきを得ました。
このシーンで目についたのは、右サイトからのクロスに対しても左サイドからのクロスに対しても日本のDF陣の寄せが甘く自由に蹴らせていたことでした。
前半22分、ジャマイカが中盤でガードナーがドリブル、センターサークル付近で名良橋選手のタックルを交わしフリーになると、さらにドリブルで30mほど突進、ペナルティエリアのすぐ前でウィットモアにパス、ジャマイカ4人に対して日本のDFが3人の形を作られました。ウィットモアはペナルティエリア内に侵入、やや右側に持ち直してシュートを放ちますがボールは川口能活選手の正面に。
解説の加茂さんが思わず「いゃぁ、危なかったなぁ」と口走る不利な場面を作られました。
前半25分を過ぎたあたりから日差しが出て蒸し暑さが増したせいか日本代表の動きがガクンと落ち中盤が間延びしてしまいました。
そんな中、前半28分、日本の最後尾で奪ったボールからパスがつながり、城選手まで届きます。城選手はドリブルで持ち上がりペナルティエリアのすぐ手前まで相手DF2人を引きつけ、並走してきたフリーの名波選手に横パスを送りました。名波選手はペナルティエリアのラインあたりでGKと1対1の場面から得意の左足でダイレクトにシュートしますが、ボールは大きくバーを越えてしまいました。名波選手は最後尾からのパスをまず受けて中田選手に出したあと約60mほど走ってからのシュートチャンスでしたから、抑えが効かなかったようです。
前半36分、ジャマイカ、ゲイル、ゴールまで25mあたりからミドルシュート、不意をつかれたシュートは右ポストの一番上あたりをかすめるように外れましたが、危ない一振りでした。
前半37分、中盤で中田選手が倒され日本のFK、右サイドに展開したボールを名波選手が切り返しから狙いすましたクロス、ファーサイドで待ち構えていた相馬選手がセオリーどおり頭で折り返したボールはゴール正面で待ち構えていた城選手のもとへ、城選手はももでトラップ、ボールを前方向に落として、そのまま左足でシュート、完全な崩しによるシュートでしたが、ジャマイカDFグッディソンの捨て身のブロックに合いゴールならず、城選手は思わず顔を両手で覆って悔しがりました。
日本、チャンスを逸したあとのピンチが交互にきて、2度目は仕留められ失点
そのあと、日本に目立たないミスが2つ続き、それが失点につながりました。一つ目は相馬選手のスローインの時、相手選手がスローインの邪魔をしていると見た相馬選手、思わずスローインを途中で止める形になりましたが、やり直しが認められずファウルスロー扱いに、二つ目は相手スローインのボールを受けた選手を後ろから抱え込んでしまったとして小村選手がファウルをとられ、相手FKのリスタートとなりました。
このリスタートからのボール、ジャマイカはDFにボールを戻してゆっくり攻めるかに思われましたが、最後尾から1本のロングボールを前線に放り込みました。このボールをFWゲイルが井原選手と競り合いながら横にヘディング、もう一人のFWホールを秋田選手がつぶしにかかったのですが、その裏からウイットモアがボールを拾うように回り込みゴール正面に、ウィットモアの前に相馬選手、その後ろに川口選手が重なる形になったため、川口選手はウイットモアのボールの出所が見えず、自分の右サイドに打たれたボールへの反応が遅れてゴールを割られてしまいました。
これで3試合とも日本は先制を許しました。
前半43分、日本、左サイド深い位置から相馬選手が入れたスローインを秋田選手がダイレクトで目の前にいた中田選手に送ります。中田選手は中央の広大なスペースにいた山口選手に送ると、山口選手は右に並んできた名良橋選手にパス、名良橋選手は狙いすまして前方ゴール前に放り込むと、中山選手が相手DFと競り合いながらもヘッドで合わせ、向かい側にいた城選手に折り返しました。
城選手に絶好のボールが渡ったかに見えましたが、城選手のジャンプのタイミングがほんの少し遅れてしまったため、ボールを下から持ち上げるようなヘディングになってしまい、ボールはゴールポストを大きく跨ぐようにして外れてしまいました。解説の加茂周さんも思わず「惜しいんだけどな」と呟きました。
前半44分、ジャマイカ自陣からシンクレアがロングボールを前線に送りますが、名良橋選手へのパスになりました。名良橋選手は中央の中田選手めがけて強いパスを送ったものの、中田選手についていた相手DFの長い脚が出てカット、これがセンターサークル付近にいた19歳ガードナーに渡ります。これを名良橋選手が奪いにかかりましたが、ガードナーは身体を翻してかわすとドリブルを開始、並走した名波選手をスピードで振り切りペナルティエリアのところまで運びました。途中からマークについた井原選手がゆく手を阻んだため立ち止まり後ろ向きにボールをキープ、そこに名波選手、相馬選手も戻ってきてガードナーを1対3で止めにかかりますが、またゴール方向に向きを変え井原選手の脇から突破にかかりました。
井原選手はボールを奪いに飛び込みますがかわされてしまい倒れてしまいました。すかさず名波選手もカットしようとしましたが股の間を通されてしまいます。次に相馬選手がボールを奪いにかかりますがガードナーは体勢を立て直します。そして、目の前に名良橋選手が寄せてきたと見るやガードナーはシュートを放ちました。ボールは枠方向には飛びませんでした。そのためレフェリーは日本DFの足にあたって外れたと判断したのかCKの判定となりました。
これだけ日本DF陣を相手に動き回ったガードナー、疲れ切って仰向けに横たわったものの、1人でほんろうした満足そうな表情でした。
この大会での躍動が目にとまり、イングランド・プレミアリーグ、ボルトンへの飛躍を果たしたガードナー、ボルトンには実に14シーズン在籍しましたから中田英寿選手がのちにボルトンに加入した時もチームメイトとなる縁を持っていました。
ロスタイム2分、日本、右サイドの名良橋選手から中田選手に渡ったボールを中田選手、中央を駆け上がったフリーの名波選手に、これを名波選手がDFの裏に落とすようなロビング、中山選手が反応してボールに追いつき右足でシュートしますが、ジャマイカGKが身体に当ててブロック、それを名良橋選手がゴール前にクロス、これは相手DFに当たって大きくはねた後、相手GKがCKに逃れました。
その右からのCK、名波選手が中田選手にショートパス、それを再び中田選手が名波選手にショートパス、今度は名波選手は左大外に井原選手が走り込んでいるのを確認、ゴールマウスを横切るようなスピードのあるクロスを送ります。ボールが井原選手のヘディングの打点より少し前に来たため井原選手はヘッドでなくスライディングしながら左足で折り返します。折り返したボールはコントロールが効かなかったために相手DFに渡りチャンスはついえました。
ロスタイムの日本の波状攻撃、特に中田選手と名波選手のコンビネーションでチャンスが生まれ、最後のどれかが枠に飛べば1点というところでした。
前半のジャマイカ、チャンスはそう多くはなかったはずですが、先制ゴールをあげたウイットモア、ピッチの中央、セントラルミッドフィールドでプレーする長身の彼が的確にボールを前線に送った時にチャンスが生まれており、まさに大黒柱が彼であることがはっきりした前半でした。
対する日本、過去2戦と比べれば決定的チャンスの数も多く、試合自体を支配していましたが、如何せん最後の決定力、これが差となってしまいました。
ハーフタイム、激しい雨が落ちてきました。
後半に向けた選手交代は両チームともなし。少し弱まったものの、雨のままの後半開始となりました。
後半2分、中田から名良橋へ、名良橋のクロスはCK、これを中田が左から直接狙ったかに見えるキック、ボールはクロスバーのわずかに上、ネットに転がりました。いつもは表情一つ変えない中田選手が「入れたかったな」という気持ちだったか、小さく顔を歪めました。
後半3分、ジャマイカが中央のウィットモアから左サイドのガードナーへ、これをガードナーが軽く前に出すとペナルティエリア内に上がってきたシンプソンに通ります。シンプソンは後ろに井原選手がマークに来ているのを確認しながら、左足でヒールパス、これをホールが拾うと、GK川口選手と1対1の状態に、川口選手がホールとの間合いを詰めてきたことからホールは右アウトサイドにかけてボールをゴールマウスを横切る方向に出しました。するとプロックしようと倒れ込んだ川口選手の右わき腹の下をすり抜けたボールは、DFに入った小村選手の足先に当たったあと右手拳あたりに当たってゴールラインを割りました。
それを見たジャマイカ・ホールはすぐさまハンドをアピールしましたが主審はCKのジャッジ、PKのピンチを免れました。
このあと雨の残る中、また強い陽射しが照り付けました。
前半8分、相手のパスをカットした山口選手から名波選手、中田選手と繋いだパスを中田選手は右サイドに流れながら前方にボールを出すと、中央から中山選手が走り込みペナルティエリアの右角あたりでボールに到達、さらに2歩ほど走り少し角度がなくなりましたがシュート、GKの逆サイドを突くコースに飛びました。相手GK、身体を目いっぱい伸ばしてボールをはじきました。そこに城選手が詰めて来ましたが無情にもボールは左方向に転がってしまい相手GKに蹴り出されてしまいました。
そのボールを中盤で受けたウイットモア、キープして一旦センターサークル付近でDFに返したあと右サイトを駆け上がります。DFからのボールはセンターサークル付近まで降りてきたゲイルに渡り、そこから右サイド前方のウイットモアに繋がります。ウィットモアが受けた地点はペナルティエリアから20mほど手前だったため、日本DF陣はウィットモアの後方に4人いましたが、それぞれ5~7m離れていました。
最初にウイットモアがボールをキープした時に、寄せてボールをDFに戻させた山口選手と相馬選手は、そのあとウイットモアに背を向けて彼から目を離していたため、ウィットモアがスルスルっと右前方を上がっていたのです。
ボールを持ったウイットモアはノーマークのまま縦にボールを運びペナルティエリアの線上をエリアの半分ほど進み切り返しにかかります。
この時、一番近くの日本選手が2mほど内側にいた小村選手、ウイットモアのシュートコースを消しにかかりますが、ウイットモアは切り返して左足に持ち替え、小村選手の重心が左足にかかったタイミングでシュートを選択、小村選手の後ろでは川口選手がニアサイドに構えていましたが、そのサイドは1m以上空いています。ウイットモアのシュートは、体勢を立て直し狙いすましてシュートブロックしようとした小村選手の右足先をかすめ、川口選手のニアサイド側、1m以上空いたコースに打ち込まれてしまいました。
時計の針は後半9分を回ったところでした。
ふだんセントラルミッドフィールドでプレーしているウイットモア、日本がDFラインをかなり上げているのを見て、ボールをもらう時もDFラインを確かめながら、オフサイドにかからない上がり方をしていました。
日本DF陣も、よもや上がっていったそのタイミングでシュートまで持ち込むとは思っていなかったのでしょう。さきほどのウィットモアの後方の4人の距離感、ペナルティエリアに侵入してきた段階でも小村選手1人、しかもまだ2m空けている守りがそれを表しています。不用意の誹りを免れない悔いの残るディフェンスでした。
後半10分、左サイドのスローインをもらった名波選手、ゴール方向に向き直してルックアップ、右サイドを駆けあがっていた名良橋選手を見逃しませんでした。20m以上の弾道の高いクロスはペナルティエリア内に侵入した名良橋選手にピタリ、これを名良橋選手、軽くジャンピングボレー気味に右足で合わせると、ボールは左ポストの下側を叩き外れてしまいました。
後半11分、最後尾から井原選手がクサビのパスを中田選手に、中田選手がはたいて山口選手、それを名波選手、また山口選手とつないで山口選手は最前線の城選手にスルーパス、これを城選手についていたDFがカットしようとしましたが、ボールが城選手に渡ります。ちょうどペナルティエリアの左サイドに入ろうという位置、ゴールまでは10mほどある距離でしたが城選手はワントラップからシュートを打ちます。しかしボールはゴールポスト左にはずれてしまいました。結果はどうあれ足に完全にヒットしていればという場面でした。野地アナウンサーが「決定的でしたぁ!!」と叫ぶと加茂さんも「これは本当に決定的ですよ。」いかにも恨めしそうなコメントでした。
後半14分、日本、ゴール正面20mの地点でFKを獲得、このタイミングで選手交代、城選手に代えて呂比須ワグナー選手、小村選手に代えて平野選手投入、2列目を平野、名波、中田の3人にしてDFを4バックに変更しました。
代わった平野選手がFKを蹴るとCKに、中田選手が蹴ったCKがこぼれてペナルティエリア外に、そこにいた平野選手がオーバーヘッドでペナルティエリアに送ると、ボールはゴール正面の呂比須選手の足元に、これをDF1人を交わして右側に持ち出しシュート、ボールはGKが右に飛んで辛うじて弾きます。こぼれたボールが走り込んできた中山選手の右側に、中山選手はボールをチョンと前に出しシュート体勢に入ろうとしましたが、蹴り出しがちょっとだけ大きくなってしまったため、一瞬早く相手DFのクリアにあってしまいました。
このあとテレビ画面にはセンターサークルあたりで名良橋選手に押しとどめられているGK川口能活選手の姿が映ります。CKの際に自分も上がって攻撃に加わろうとしたのでしょう。川口選手の焦りが見えた場面でした。
雨は弱くなったものの降り続いている状況です。
後半16分、ハーフウェーライン付近左サイドから名波選手のパスが中田選手に通ります。中田選手はドリブルでペナルティエリアまで持ち込み相手DFに囲まれながらも持ちこたえて、一旦ボールを下げます。そこに平野選手が走り込み得意の左足でシュートを放ちますが、ジャストミートせずゴール右側に流れました。しかし、そこに中山選手が待ち構えており、小刻みに下がりながらシュートを打ちました。しかし下がりながらのシュートだったため力が弱くGKにキャッチされてしまいました。
GKの目の前の位置に呂比須選手がいましたので、もし見えてれば呂比須選手にフワリとしたボールを渡すと呂比須選手がゴール正面でヘディングできたかも、という場面でしたが、それは「たられば」ということになると思います。
後半17分、中盤で山口素弘選手が相手のパスをカット、ダイレクトで名良橋選手に渡すと名良橋選手もダイレクトで縦パスを強く送りました。それが呂比須選手に通ります。呂比須選手は自分を追い越して右サイドを駆けあがった中山選手に出します。中山選手は中を見ながら走ったままクロス、ボールはペナルティエリア左サイドに走り込んできた平野選手に合いました。これを平野選手、走ったままの勢いでジャンプ、ヘディングしますが惜しくもGKが右に飛んで手の届く範囲に落ち弾き出されてしまいました。
後半27分、ジャマイカ、FWホールに代えてボイド投入。
後半28分、最後尾、井原選手から左サイド相馬選手にボールが渡ります。相馬選手、前が空いていて、前線の状況を十分見てからアーリークロス、これはDFの網にかかりましたがキックの距離感が残ったのではないかと思います。
中山雅史選手がW杯日本人初ゴール、日本、何度もチャンスを作った末、遂に歴史的ゴール
後半29分、日本が自陣左サイドでFK、相馬選手、名波選手、中田選手とボールが渡り逆サイドの名良橋選手に、名良橋選手は秋田選手に戻し、山口選手、名波選手と渡ります。名波選手が左サイドの相馬選手の駆け上がりに合わせるようにボールを送ると、相馬選手は2~3歩進んでから切り返してボールを右キックに持ち替えます。そしてルックアップ、前線遠いサイドの呂比須選手をターゲットに40mぐらいはあろうかという長いクロスを送ります。
ボールは呂比須選手に届き、呂比須選手はDF一人を挟んで前方に走り込んできている中山選手にヘッドでフワリとしたパスを送ります。中山雅史選手は勢いを止めずに身体を捻るようにかぶせてボールを当てにいきます。ボールは見事に右足にヒット、バウンドしてゴールに吸い込まれました。
長いクロス、折り返し、シュートという絵に描いたような崩しの、日本代表の歴史的初ゴールでした。
この初ゴールで、日本サポーターの応援ボルテージがまたあがってきました。
中山選手、右足を痛めた模様、交代を求めず痛みをこらえながらプレー
後半31分、異変が生じます。ペナルティエリア内で相手DFとボールを奪い合った中山雅史選手が、相手DFがクリアするため蹴り上げた足をもろに自分の右足外側に浴びたのです。中山選手は倒れたあと苦痛に顔を歪めました。すぐ立ち上がりましたが左足でケンケンしながらプレーに戻ったのです。この時、蹴られた右足の膝下の部分を痛めたのでしょうか。
その後のプレーには絡んでいたものの、やはり右足を相当痛そうにしていることは間違いありませんでした。チームドクターも「ただごとではない」と直感していたようで、ピッチに入ろうとしたのですが線審に制止されて待機している間に中山選手が立ち上がりプレーに戻ったため、直接診ることができませんでした。
後半32分、今度はセンターサークルの少し相手陣内で中田選手が相手DFから強烈なバックチャージを受けて倒れました。相手DFマルコムには即イエローガード、中田選手の右足首の後側に入ったタックルで、中田選手も相当痛かったようですが立ち上がりました。しかし2~3歩左足でケンケンするほどの痛みだったようです。
そのファウルの直前には「日本ベンチは小野の準備をしているようです」と、NHKの実況が伝えた矢先でした。
中田選手ものちに、この場面を振り返って「残り15分を切ってDFから足首にガーンとタックルを入れられた。あれは、はっきり言って物凄く痛かった。でも痛がらないように。残り時間を考えたらとても転がってる場合ではなかったし・・」と話しています。
後半34分、日本最後の選手交代、名波選手に代えて小野伸二選手投入。この交代、岡田監督の描いたゲームプランに沿った交代だったかも知れませんが、中山選手、中田選手と2人のケガ人をピッチに残したまま最後のカードを切ったことになります。日本ベンチの誰か一人でも2人のケガの状況を推し量ることはできなかったのでしょうか?
岡田監督自身も、特に骨折した中山選手を残したまま、小野選手を入れてしまい交代枠を使い切ってしまったことを「あと1分、中山の様子を見て動けなくなるのを確かめていれば、1人減った状態(動けない選手が1人いる状態)にせずに済んだし、同点に追いつく可能性もあったと思う。あと1分我慢できなかった。」と後悔しています。
後半35分、ジャマイカ、FWゲイルに代えて、FWバートン投入。
後半36分、ジャマイカゴール前でのボールの奪い合いからジャマイカ逆襲、ロングパスが右サイドのボイドに出ると、ボイド、ペナルティエリアのすぐ外で切り返して強烈なシュート、川口選手、反応して辛くも右手に当てコーナーに逃れました。
交代出場からわずか3分、小野伸二選手、股抜き後、果敢にシュート
後半37分、ジャマイカDFからのロングボールを名良橋選手が跳ね返すと、平野選手、山口選手とボールが渡り、右サイドに回っていた相馬選手に渡ります。相馬選手は前に持ち出すとパスコースに小野選手が顔を出したことからパス、小野選手は目の前に詰めて来た相手選手の両足の間を事もなげに抜いてボールをキープ、さらに詰めてきた別の選手もかわして左足でシュート、その距離ゴールまで20数mありましたが思い切りよく打ちました。しかしボールはジャストミートせずゴール右側に外れていきました。
ロスタイムに入ってすぐ、日本、右サイドからスローインを受けた小野伸二選手がゴール前の呂比須選手へクロス、ボールは相手DFのブラインドになった呂比須選手の肩にあたりゴール脇に外れていきました。ジャマイカ、MFシンプソンに代えてアール投入。
ロスタイム3分の表示。
ロスタイム1分、GK川口選手、ロングキックを前線に送ります。一度DFに跳ね返されたボールをマイボールにして呂比須選手、中山選手と繋ぎ右サイドの小野選手へ、小野選手自分で中に切れ込むと見せかけて右足アウトサイドで上がってきた呂比須選手にパス、呂比須選手、GKとの距離10m弱、トラップしている時間はないと見たか右足アウトサイドにかけるようにニアサイドに狙いを定めてダイレクトでシュート、しかし無情にもシュートはわずかに枠の外。
ロスタイム3分22秒ほどでタイムアップ。
日本、1点はあげたものの、またしても敗戦、ワールドカップ初挑戦が終わりました。
サッカーマガジン誌が伊東武彦記者のレポートで連載してきた「日本代表同時進行ドキュメント」も7週目のジャマイカ戦を持って脱稿となりましたが、そこには「スタジアムを打ちつける激しい雨音と、日本人サポーターの悲鳴が響き渡る中で逆転を目指した猛攻の果てに、岡田と選手が見た明日とは?」という言葉で締めくくられていました。
悲しい戦いの時はいつも「涙雨。」今回もまた、死力を尽くしてピッチをあとに控室に歩みを進める選手たちの頬には涙と雨のしずくが光っていました。
日本代表に立ちはだかった世界の壁、夢、抱いた根拠なき夢が、グループステージ3戦3敗270分で消え、日本サッカー史上もっとも濃密だった12日間の祝祭は終わりました
高鳴る心臓の鼓動、夢にまで見てきたW杯のピッチ、選手もサポーターも日本全国のサッカーファンも同じ夢を胸に臨んだフランスW杯、しかしW杯での勝利はおろか勝ち点1さえも、こんなに遠く厳しいとは・・・。
「出場するからには勝ちたい」「グループリーグ突破を目標にしたい」とまだ未体験の世界の舞台に対する希望、願望を抱いて戦ったものの、そう甘いものではないことを、戦った末に思い知らされました。
考えてみれば今大会、アジア最大のライバル・韓国が出場5回目にして、いまだ初勝利をあげられないほど苦難の道を歩んでいるのに、日本がおいそれと、それを上回る成果をあげられそうだと思うこと自体に無理があったことを思い知らされたのでした。
日本代表は3試合270分を通じて中山雅史選手があげたわずか1得点だけが初出場の証しでした。
3試合で得た唯一の得点だけを土産に日本代表、帰国の途に
中山選手、実は右足すね部分の腓骨(ひこつ)を骨折していたことが判明
ジャマイカ戦の試合終了直後、中山選手がレントゲンを撮るため病院に直行というニュースが流れました。検査の結果、右足の腓骨を骨折していたというのです。後半31分のプレーの時です。腓骨というのは膝から足首までの、いわゆる「すね」の部分にある2本の骨のうちの細いほうの骨です。もう1本の太い骨は脛骨(けいこつ)といい、こちらが折れれば大事(おおごと)ですが、腓骨は筋肉が付着している関係で、折れてしまっても太いほうの脛骨に問題なければ動きを続けられることがあります。
中山選手は痛みがあるにも関わらずこらえて、結局試合終了までプレーを続けていました。チームドクターは、すぐ、病院での検査を促しました。中山選手は日本サッカー史上、ワールドカップでの第1号ゴールをあげた選手ですから当然のようにインタビューのリクエストが来ていましたが、チームドクターは検査優先を通し、病院で骨折が判明したのです。
後半33分に相手DFから右足首に強烈なバックチャージを受けた中田選手も、腫れが次第にひどくなっていったようです。
岡田監督は、試合直後のNHKのインタビューで、
「3試合を通じて岡田監督自身が、この世界の舞台で感じたことはどういうことでしょう?」という質問に答えて、
「勝負というものがそんなに甘くないということはわかっていたが、もっともっと、やらなければいけないことがたくさんあるなと感じた。ただ、最後のこの試合で選手の持っている力を全部出させてやれなかったことは僕の責任だと思っています。」と語りました。
ジャマイカ戦のことは、2戦目が終わったあとのジャマイカの選手たちのふるまいが脳裏から離れなかったようで、岡田監督はのちにこのように語っています。
「ジャマイカは0-5で負けても笑顔で拍手してスタンドにアピールできた。なのに、こっちは0-1で負けてモチベーションを見失なった。この差は一体何なんだろうか? (中略)」
「もうちょっとW杯という大きな枠組みの中での1試合という捉え方が自分にできなかったのか、選手にもそうしてやれなかったのかな、とは思うんです。(中略)我々の設定した目標があまりにも単純で明確に過ぎた。もっと、老獪に、うまくごまかしながら3試合やらせてあげられなかったかな、と思うんです。でも、そうすると、そこまで集中できたかどうかはわからない。難しい判断です。」(増島みどり著「ワールドカップフランス98 6月の軌跡」1998年12月文藝春秋社・刊より)
岡田監督のこの自問自答は、この大会に臨むために自身が組み立てた戦略、それはアルゼンチン、クロアチアの試合を接戦でも何でも切り抜け、ジャマイカ戦に勝負を賭けられるようと描いた戦略が、実際には第3戦目には何も意味をなさなくなった時の「プランB」を用意していなかったことに気づいた自問自答だと思います。
岡田監督は「老獪に、うまくごまかしながら」という表現を使いましたが「もし2戦目までで決勝トーナメント進出を逃したら、ジャマイカ戦は徹底して楽しんでやるぞ、何も失うものがないと考えて、日本サッカーのいいところを見せるぞ」といった「プランB」でも用意できていれば違ったものになったと思うし、そもそもジャマイカのあの2戦目終了後のふるまいは「あとはプランBで行きますよ」とスタンドに向かって意思表示していたようなものだと気づいたのだと思います。
ただ最後に「そうすると、そこまで集中できたかどうかはわからない。難しい判断です。」と付け加えていましたが、それは日本代表という国民性や文化、歴史を背負った集団が、ジャマイカ代表選手たちのように簡単に「プランB」に切り替えられるのかどうかはわからないという意味だと思います。
岡田監督は、2戦目が終わった段階でジャマイカ代表のふるまいから、ある種のインスピレーションは受けたわけですけれど、それを「プランB」にまで落とし込むほどの時間も精神的余裕もなかったことでしょう。それは致し方のないことで、これこそが、ワールドカップ初出場のチームの限界であり、監督未経験の指揮官の限界でもありました。
リヨンでのジャマイカ戦を終えた日本代表は、エクスレバンに戻りキャンプをクローズして帰国準備にかかりました。
現地応援サポーター、全国各地のスポーツバーなどでのサポーター、テレビ観戦の全国のファン、歓喜の期待空しく12日間を終え、フランスのメディアは「日本のサポーターは世界一」と称賛
この日の公式入場者数は39,100人とのこと、ジャマイカサポーターはごくわずか、大半がブルーのユニフォームを着た日本人サポーター、アルゼンチン戦、クロアチア戦とチケット問題でスタジアムに入れなかった人が多かった2試合に比べ、両国ともグループリーグ敗退チーム同士の試合ということでダフ屋のチケット相場が大幅に値崩れ、日本円で15000~25000円程度で、希望した人が全員入れた初めての試合となりました。
これまで2試合敗戦とはいえ「次こそは」と意気込んでいたサポーターたちだっただけに、敗戦のショックは大きく、スタンドからは、その気持ちを表すかのように「カズコール」が響き渡りました。
日本代表サポーター「ウルトラス・ジャパン」のメンバーの中には、カズ・三浦知良選手が落選帰国した日に成田空港まで出迎えにいったメンバーや、フランスに応援に行った時にカズ・三浦知良選手のユニフォームをまとって行ったメンバーもいたほどですから、心情的には「カズさんがいてくれたら、こんな結果にはならなかったのでは」と考えるのも無理からぬことだったと思います。
そんな日本代表の応援サポーターの中には若い芸能人も含まれていたと6月27日の各スポーツ紙は報じていました。
「TOKIOの国分太一(23)、長瀬智也(19)、V6の井ノ原快彦(22)、森田剛(19)が、26日、リヨンのジェルラン競技場で、W杯サッカー「日本vsジャマイカ戦」を観戦した。日本の歴史的ゴールを目の当たりにした長瀬や森田は『絶対、後半に点をとってくれると信じてました。結果は負けてしまったけれど、日本のサッカーの歴史に残るゴンゴールを生で見られて本当に幸せです。満足です。』と興奮しながら話した。」
フランスワールドカップにおける日本のサポーターは、チケット問題に翻弄されたことが現地のメディアでも大きな話題となり、一部メディアからは「日本人サポーターが法外な値段でチケットを買い漁った」という批判を受けましたが、グループリーグの応援を終えた日本のサポーターたちに対して、現地メディアは総じて「最も熱烈で、最もさわやか」「日本のサポーターは世界一」と驚きと称賛をもって報じました。
なかでも試合後、スタンドで整然とゴミ拾いをする姿は「チケットはないがエチケットはある」と、見事に語呂合わせで称賛、フランス組織委員会の関係者も「整然としたゴミ拾いの姿はW杯初出場国の価値を高めた」と口を揃えました。
一方、日本国内での観戦は、試合開始が日本時間の午後11時ということもあって、第1戦のアルゼンチン戦、第2戦のクロアチア戦で見られたようなパブリックビューイング形式の賑わいはなかったものの、熱心な若者たちを中心に、ある街ではカラオケ店で、ある街ではスポーツバーで、ある街では地元放送局のロビーで、といった具合に観戦が行われました。
東京では、日本サッカーの「聖地」ともいえる国立競技場ではスタジアムの外にあるチケット売り場に設置されたモニター画面前に日本代表のユニフォームを着た約800人ほどが集まり観戦しました。
NHK総合が放送した日本vsジャマイカ戦の視聴率はビデオリサーチ社から平均52.3%と発表されました。NHK-BSでの視聴率5.6%を加えると58.1%、午後11時キックオフという遅い時間帯にも関わらず日本の初勝利への期待もあったためか高視聴率となりました。これで日本における歴代サッカー中継のベスト3が、すべて今大会の試合となり新たな歴史が刻まれました。
6月27日現地時間午前8時30分、エクスレバン出発前総括記者会見
日本サッカー協会・大仁強化委員長と岡田監督が別々に会見を行ないました。
日本サッカー協会・大仁強化委員長会見
「強化委員会の総評としては、3戦全敗、グループリーグ敗退は残念でしたが、チームはよく戦ってくれた。日本の持っている力を出し切ってくれた。」
「岡田監督の本格的な強化は5月のキリンカップからだったが、限られた時間の中で日本チームのベストを尽くし、相手チームの分析、その対策などをよくやったと思う。」
「戦い方のうちディフェンス面では1対1の強さが課題となる。1対1の強さが足りないため攻撃の人数も守りの組織に回り、攻撃が手薄になった。」
「フィニッシュについては大いに改善しなければならない。といっても釜本はいないしスーケルもいない。しかしクロスの正確性や、そのボールへの入り方は世界と差がある。またセットプレーからの得点をもっと増やさないと苦しい。」
「昨夜宿舎で岡田監督に続投を依頼した。しかし監督は3戦で結果が出なかったことは自分の責任であり辞めたいということだった。その意向は預かって、帰国してから再検討し協会理事会に委ねたい。協会として(本大会監督に)岡田監督を選んだのは間違っていなかったと今でも考えている。我々(強化委員会)に対する評価も理事会に委ねたい。」
岡田監督会見
「W杯出場が決まって、相手が決まって力を分析して、4バックでは無理と考え3バックにトライして大会に臨んだ。」
「選手たちは呑み込みも早く、非常にいいパフォーマンスを見せてくれた。ただ残念ながらアルゼンチン戦では緊張、クロアチア戦では詰めの甘さ、ジャマイカ戦ではゴールへ向かう意識が低くて、1勝もできなかった。しかし選手は100%力を出し切ることに最大限の努力をして、やってくれた。彼らとスタッフに感謝したい。胸を張って堂々と帰ってほしい」
Q. ジャマイカ戦は攻めているのに1点しか取れなかったが?
A. ゴールに向かうのが遅かった。チーム作りの段階で中盤のスペースにパスをつなぐ練習をしてきた。そのため自然と中盤でのパスの回数が多くなり攻撃が遅くなった。パスに固執しすぎたかもしれない。
Q. FWの柱の城が得点できなかったが?
A. 城はしっかりボールが止められる。シュートも打てる。総合力で城を柱にして、運動量のある中山やスピードのある岡野を組み合わせてきました。確かにシュートは外しましたけど、自分が信じてやったことです。後悔はしていない。
Q. 選手交代の時間がいつも同じだが?
A. 後半に入ってもまだ攻めを速くすればいけると思っていた。最後に小野を入れたのは、ゴールするのは中山か呂比須しかいないと思っていた。そのため中盤にタメを作れる選手が欲しかったから。
Q. 監督の経験不足は影響したか?
A. キャリアがあれば「ついてこい」と言える。自分にあるのは理論だけ。選手を納得させる分だけ仕事が増えた。苦しいと考えたことはなかったが。
Q. 今後については?
A. 辞めます。私はプロの監督として思い通りにやってきた。自分は職を賭けてリスクをかけてやっているという誇りが自分を支えてきた。ここで結果を出せないのに(留任という)安易な道を選んでは、今後、指導者として自分を信じられなくなってしまうし、選手にも信頼されなくなるだろう。だから、どんなことがあっても続けられないと大仁さん(強化委員長)に話した。代表監督は続けるつもりはない。
(クラブから)オファーがあれば考えたい。サッカーの仕事がなくなっても、身体は動くから家族は食わせていける。
岡田監督はそれまでの思いつめたような表情から打ってかわった、穏やかな表情での会見となりました。日本代表監督という任務から解放された安堵感がそうさせたのでしょう。
岡田監督と小野コーチは、強化委員会へのレポートを仕上げるため大会に残ることになり、選手と他のスタッフたちだけがエクスレバンを離れることになりました。
正午過ぎ、選手たちを乗せたバスがリヨンの空港に向けて出発しました。日本代表の戦いが本当に終わったことを感じさせる瞬間でした。
数か月間、日本代表を持ち上げ続け日本中に夢を抱かせたマスコミ、「宴のあと」今度は日本代表批判
グループリーグの最終戦・ジャマイカ戦を終えて日本代表の3戦全敗が決まると、マスコミの論調に変化が出始めました。これまで数か月間、日本代表を持ち上げ続けたマスコミが、3戦全敗、グループリーグ敗退に終わった日本代表の批判を始めました。
特に指揮官である岡田監督と、選手の中で城選手が標的となりました。
最初に火をつけたのはテレビでのヴ川崎・ラモス瑠偉選手の発言でした。ラモス瑠偉選手は、W杯全試合を放送したNHKの日本戦放送の際、試合前後に組まれた特番に3試合とも東京のスタジオで出演して、有働由美子アナウンサーとトークしながら番組を進行したのです。
第1戦のアルゼンチン戦後は日本代表の健闘を称えながらも「選手の中にはワールドカップを甘く考えている選手もいるように感じた。日本代表としての気持ちが感じられない選手がいたように感じた。まぁ気持ちを切り替えて次の試合に頑張って欲しい」と、控え目のトークでしたが、第3戦ジャマイカ戦に敗れ、日本3連敗が決まった後のトークは熱くなりました。
ラモス瑠偉選手はジャマイカ戦のハーフタイム時のトークでも「勝ちたい気持ちが伝わってこない、だらだら歩いてボールを奪う気持ちがない」と苛立たしそうに話していました。
ジャマイカとの試合が終わり、スタジオに切り替わった画面で、有働アナウンサーが打ち沈んだ様子で「はい、という結果なんですけど・・・、なんて言っていいかわかんないんですれど・・・・。」とラモス瑠偉選手の言葉を待ちました。
ラモス瑠偉選手もしばらく無言でしたが「ま、こんなもんです。」と絞り出しました。有働アナがすかさず「こんなもん、というのは?」と突っ込みました。
「ま、あまり言いたくないんですけど・・。ま、こういう結果になるのはある程度、予想してたんじゃないかな、何人かは。」
「どうして?」
「最初からね、結構、サッカー何人かなめてるんじゃないか、前から言ってるんですけど、ほかの国に戦争に行ってるのに、タレントっぽい、Jリーグでやってるような気持ちでやってるのが、こういう結果になったんじゃないかと・・・。」
「ジャマイカに負けたのは、結局(ジャマイカの選手たちが)すべての面で真剣に勝負に出てきてる、負けたくないという気持ちも、技術の問題じゃなくて、(日本は)気持ちの問題で負けたというのが悔しくてしょうがないですよね。」
有働アナは現地にいる松木安太郎氏を呼び出し「日本には何が足りなかったんでしょうかね」と意見を求めると、松木氏は「ラモスさんもさっきから何回もおっしゃってますが、戦う前の段階、なんとしてもこの勝負に勝つんだという気迫というか、そこからまず何か生まれてくるんじゃないかと・・。ちょっと気になったのは、ジャマイカの選手たちは普段すごく陽気なんですけどグラウンド上で歯を見せてる選手はいなかったんです。それに対して日本の選手は、戦場では白い歯はいらないんじゃないかと、僕自身はそう思いました。」
このあと全国各地のサポーターの声や呂比須選手のインタビューを挟んで、ふたたび有働アナがラモス瑠偉選手に話を振りました。
「ラモスさんは、日本の課題については、どう思いますか?」
「今回の日本代表は、やはりベテランの力が足りなかったんじゃないかと、どこの国でも見ていると、だいたい活躍している選手は32とか33とか経験ある選手ばかり、日本の場合はそういう面で足りなかったんじゃないかと思います。」
そして番組も終盤に差しかかる頃、有働アナが「ラモスさんは、ほんとうに日本代表にあったかく見つめながら、だからこそ厳しいんですが、今日も含めて3戦・・・」と問いかけると、ラモス瑠偉選手は「僕が言いたいのはね、日本のサッカーって、こんなもんじゃないです。もっとできるはずです。それは戦術とか技術ではなく「魂」をもってできるはずだったから僕は悔しいだけです。」
「私たちJリーグで引っ張ってきたベテランがいきなり無視された、それもすごく悔しいです。結局、誰が責任をとるのか、それも見てみたいです。日本のサッカーがよくなるためには、誰かがここで責任をとらなきゃならないと思います。そうでなければ本当のレベルアップにならないと思います。日本のサッカーは本当にこんなもんじゃない、それだけに悔しいです。それだけです。」
ラモス瑠偉選手のコメントは文字にすると少し強い口調に感じますが、3戦ともラモス瑠偉選手は努めて抑制的にコメントしています。もの静かに聞こえるぐらいの話しぶりが一層、ラモス瑠偉選手の胸のうちを表しているようで視聴者にはインパクトのある話しぶりだったかも知れません。
NHKの日本戦中継の視聴率は、アルゼンチン戦が60.5%、クロアチア戦が60.9%、ジャマイカ戦でも52.5%と、歴代の日本におけるサッカー中継のランキング1位から3位を占める高さで、この数字は、日本全体がこれらの試合に注目して放送を見ていたという数字です。
ですから、有働由美子アナウンサーとラモス瑠偉選手のトークは、大変な社会的影響力を持って視聴者に届いたのです。
放送終了後、NHKにはラモス瑠偉選手の発言に対する賛否も含めて合計15万5000件もの意見などが寄せられたそうで、これだけの量の意見・問い合わせは1995年の阪神淡路大震災の時の14万件を凌ぐ過去最高の反響になったそうです。
さすがに日本サッカー協会も座して看過するわけにもいかず「武器なき戦争とかいう発言は、お茶の間の素人ファンには聞こえがいいが、協会も現場も準備にベストを尽くした。その結果は素直に受け入れてもらいたい」と反論しましたが、世論は味方をしてくれませんでした。
このラモス瑠偉選手のコメントが口火となり、新聞、テレビ、雑誌などが次々と岡田監督そして、ラモス瑠偉選手が「サッカーをなめてるんじゃないか」と暗に批判した城彰二選手に批判の矛先を向け始めたのです。
ジャマイカ戦がおわった後の、それらの報道をピックアップしておきます。
【スポーツ紙・夕刊紙】
・6月27日 日刊スポーツ「我がニッポンこんなに弱いとは・・3連敗終戦」
セルジオ越後氏「日本は0-1とリードされたのに、中田も城も笑いながら出てくるんだから、何を考えてるんだろうか? 井原や秋田は厳しい顔つきで出てきてるのに・・。」
・6月27日 夕刊フジ「岡田ワンパターン采配」「長沼、川淵ら協会幹部も同罪」
奥寺康彦氏「怒り、イライラ・・・。わたしはいったいフランスまで何を求めてきたのだろうか。日本代表に言いたいことは山ほどある。しかし、これほどまでの無気力の試合を見せつけられると、試合終了と同時に放心状態になってしまった。」
リトバルスキー氏「日本vsジャマイカ戦を観戦して、わたしがすぐにしたことは、思い切り走ることだった。そうでもしなければ体中に蓄積したストレスが爆発しそうになったからだ。おそらく日本のサポーターも私と同じ気持ちだったろう。」
・6月28日 スポーツニッポン「あゝ 城に流された 不振でも「柱」指揮官判断鈍った」
【テレビ】
・98.6.27 TBS「ブロードキャスター・日本はなぜ予選リーグで敗退したのか」福留功ほか
(20’03)ゲスト・セルジオ越後氏
・98.6.27 フジ「土曜一番花やしき・日本代表はなぜ勝てなかったのか・徹底討論」
福井謙二ほか(1H05’30)出演者 二宮清純氏、金田喜稔氏、森保一選手、
岩本輝雄選手、大阪体育大・原田宗彦教授
・98.6.28 テレ朝「サンデージャングル・日本はなぜ予選リーグで勝てなかったのか」
中居正広ほか(7’42)コメント・セルジオ越後氏
・98.6.28 TBS「炸裂スポーツパワー・岡田ジャパンに足りなかったもの」吉田照美ほか
(52’50)出演者 清雲栄純氏、清水秀彦氏、草野満代氏、長谷川健太選手
・98.6.29 TBS「おはようクジラ・今週の気になる話題1位『全敗』」青島健太(19’00)
・98.6.29 日テレ「ザ・ワイド、日本代表帰国、再燃する責任の所在」草野仁ほか(16’57)
【週刊誌】
・98.7.20号 AERA「戦犯は城、カズが出ていれば結果は違った。ラモス発言が呼ぶ論争」2p
ともあれ、マスコミは、大会前、あれだけ岡田監督を持ち上げていたにも関わらず、3連敗に終わった途端、戦犯扱いです。それも節操のないマスコミの姿ではありますが、カズ・三浦知良選手外しと3連敗は、中山選手、城選手のメンタルにまで影響を与えたという意味で無関係ではありませんでしたから、岡田監督も批判を甘んじて受けるしかないと考えていることでしょう。
日本代表帰国、成田空港での「水(清涼飲料水)かけ」事件
6月29日15時06分、大会を終えて帰国の途につき成田空港に到着した日本代表選手たちを待ち受けていたのは、大勢の出迎えのサポーターの中に潜んでいた狼藉者からの城彰二選手に対する「水かけ(清涼飲料水)」という出迎えでした。
人垣の中から狼藉者の手がすっと伸びてきて、城選手が目の前を通り過ぎるのを見計らってペットボトルから水が放たれました。スーツを着た城選手の左ほほから肩口付近に水がかかりました。
決定的瞬間は東京スポーツ紙・紙谷光人カメラマンによって捉えられ同紙のトップを大きく飾りました。狼藉者の姿も永遠に画像に刻まれました。
それでも城選手は、少し顔をゆがめ手で拭き取ったものの、取り乱すことなく他の選手たちと歩調を合わせて進みました。
しかし、それは「FWの軸は城⇒カズ外し⇒頼みの城の不出来」という結果を招いた岡田監督の責任を背負い込んだ洗礼だったのです。
この事件が起きた日本代表の帰国について、サッカーダイジェスト誌に連載コラム「セルジオの天国と地獄」の1998.7.22号の中で、日本サッカー協会や岡田監督を次のように痛烈に批判しています。
「帰国のときに、どれだけ組織が空虚だったかを思い知らされたね。キリンカップのチェコ戦(5月24日)では、試合前の壮行会に長沼会長が顔を出した。でも選手が帰国のときはバラバラだった。長沼会長はひとりでとっとと帰ってきてた。いいときだけ顔を出して、ヤバイときには逃げ隠れするんだ。おまけに岡田監督は視察と称してフランスに留まってる。行きはあいさつしたのに、帰りはどうしたのって感じだね。一緒に帰るべきだし、大会を視察したいなら日本に一度帰って、そのうえでまたフランスに出発するべきでしょ。しかも、そんなワガママを協会は容認してる。」
「すべてを岡田監督に押しつけたから、最後に監督のブランドになにも言えなくなってたんだ。そんなことばかりしてるから、成田空港に帰ってきた選手たちはノーガートにされてしまったんだ。」
「顔を出すのはいいときだけ。(こういう)協会の姿を見て、選挙に落選した候補者の事務所を思い出したよ。(投票日までは)盛り上げるだけ盛り上げて、落選が決まると、あっという間に誰もいなくなる。(サッカー協会は)そんなことが許されてはいけない。(以下略)」
日本代表の初めての勝ち点、初めての勝利は、あとは4年後、アジア予選を免除されて行われる2002年日韓大会に持ち越されることになりました。今大会で奪った1ゴールをスタートラインとして未来に向かっていくことになります。
その2002年日韓大会に向けて、今回の大会を戦った監督・選手・スタッフたちには何が残り、何を受け継ぎたいと考えたのか、幾つかの視点からつぶさに記録に留めたいと思います。
日本はどう戦おうとして、なぜ勝てなかったのか、岡田監督のサッカーを検証
前年秋、W杯アジア最終予選で土壇場に追い込まれた日本代表を、本大会出場権獲得に導いた岡田監督、その岡田監督が本大会では日本より力が上の国と戦わなければならないという課題を前にした時、どういう戦い方をしなければならないのか、どういう戦い方ならば勝つ可能性を高められるのか、年明けから取り組んできたチーム作りは、その試行錯誤に費やされてきたと言います。
その岡田監督のめざすサッカーを論理的に組み立て、選手たちに納得する形で説明できるよう準備したのが小野剛コーチでした。小野コーチは、サッカージャーナリスト・増島みどり氏の著書「ワールドカップフランス98 6月の軌跡」のインタビューに答えて、そのあたりをつぶさに語ってくれています。
「3バックの導入を私たちコーチングスタッフが決断したのは3月頃です。ゴールデンウィーク中が最初の山場でした。あの数日間に岡田監督とともに延べ数百本のビデオを観たでしょうね。まずは徹底的に過去の試合を観て3バックのどこが悪く、どこがうまく行っていたのか、それを考えたんです。ある程度の傾向ははっきりしました。それと日本には3バックが向いていないという空気が作られていて、3バックに対してネガティブなイメージを持っていた。」
「次にそれらの原因を分析し、最後に新3バックのコンセプトの確立ですね。本当に寝ずに議論したんです。」
「ですから、私たちにとってW杯の勝負の日というのは5月11日、御殿場で合宿をスタートさせた日でした。何としても選手に納得してもらわねばならない。選手との真っ向勝負の日でした。それじゃあわからない、とか、何をやりたいんだかさっぱりとかでは、こちらの負けです。もう、ただでさえ時間がないのですから。」
「実は、その勝負に備えて監督と四方田たち(日本代表テクニカルスタッフ)とは、御殿場の一発目のミーティングの『予行演習』まで事前にしていたんです。想定される質問への答え、さらには、ハイここでその例のビデオを見てみよう、とかね。コンピュータ・グラフィックスを見せるタイミングまで図りました。」
「ミーティングは30~40分の短いものでしたが、うまく伝わったと確信しました。選手の理解力には本当に敬意を抱いたし、あれほど緊張したミーティングはその後もありませんでした。監督とは、練習はアルゼンチン戦まで35回、そのうち22回は戦術練習をすると決めて、プログラムを作りました。とにかく時間との戦いでした。」
「大事なことのひとつは、この3バックがアジアでこれまでやってきたものとは違う点です。簡単に説明すると、これまでのアジアバージョンは、一度食い付いたら話すな、噛み続けろというものです。これが今度は、食い付くチャンスは見逃さないが、しかし、相手がミスもなく再びセットアップしてきたらいったんは歯を離して、2度目、3度目を狙うという考えです。」
「W杯のレベルになると、噛んだままだと逆に振り切られてしまうんですね。逆サイドに展開され、押し上げた裏のスペースを一気につかれてしまう。だから、選手には一度間でまた離す、つまりチームが守備陣から攻撃まで同じタイミングでそれを実行する、そういう3バックのイメージをつかんでもらうためのビデオを、御殿場で見せたんです。」
「ただ通常のビデオはどうしてもボールを追ってますから、前線でボールに食いついた時の最終ラインの動きなどが画面にないことも多い。そこでそこのイメージを作るためにデータ入力をして、自作のコンピュータ・グラフィックスを作りました。」
「日本は守備的だったという人がいますが、これはまったく間違っています。あれほどの国際舞台で守備的な布陣を敷くには資格がいります。つまり『守備的な布陣を敷いたとしても点が取れる』という資格です。たとえばアルゼンチン、クロアチアですね。彼らにはそれが許されているんです。」
「重要なことですが、彼らは昨年の予選から段階を踏んで攻撃にかける人数を減少させているんです。人数が減少しているというのは、それだけの人数でも得点できるシステム、それを支える個々の技術の精度、これらを確立しているんです。」
「対して日本は、ボールを前線に運ぶにも全員でやらねばなりません。これが現実です。3人で点が取れる国ならいくら守備的でもいいでしょう。しかし、我々にはそれは許されない。リスクを冒してでも攻撃的に行くよりほかないんです。それが今回の3バックの基礎にある考え方です。だから、日本は3バックで守備的に戦ったというのはまるで違っています。(以下略)」
こうした岡田監督がめざしたサッカーについて、サッカーマガジン誌1998.7.15号で、日本代表に密着取材を続けてきた伊東武彦記者が「岡田サッカーの失敗」という見出しで、そのチーム作りを振り返っています。岡田監督がどのようにして戦おうとして、その結果どうなったのか、わかりやすくまとめているレポートですのでご紹介します。
「日本が互角以上のレベルと戦うためには、コンパクトな陣形でパスをつなぎ、スペースを作り、またパスをつなぐという丹念な作業を積み重ねていかなければならない。」
「ディフェンスラインが長いボールを前に蹴るばかりでは、日本の場合は攻めにならない。前線のストライカーに少ない人数でゴールまでつなげる力がないからである。」
「さらに長いボールを蹴るうちに、前後の距離が間延びして、相手にスペースを与えて守りの面でもリスクを負う。日本の命綱が攻守のバランスにあるのは、そうした理由からである。」
「(中略)ジャマイカ戦後に、岡田監督は言った。『これまでビルドアップを強調しすぎたせいで、1本のパスで相手を崩すような攻めに対する意識が低かった。ワールドカップでは、これまでやってきた遅攻も必要だとは思っていたが、それだけではやはり破れない。しかし速い攻めの意識付けをする時間がなかった。』」
「パスは回る、しかしゴールには近づけない。ましてや相手の急所をえぐるような崩しのパスは出せない。この日(注・ジャマイカ戦)の日本がのぞかせたのは、それまでのパスサッカーの限界だった。」
「(中略)振り返ると、ボールのキープ率に比べて、決定的なチャンスそのものが少なかったことがわかる。」
「3試合を通じて、決めなくてはいけないチャンスは、まずクロアチア戦前半33分の中山のシュート、ジャマイカ戦の前半37分に城が相馬の折り返しをゴール前で受けたシーン、同じジャマイカ戦後半17分に中山の折り返しを平野がヘッドで合わせたシーン、そして最後はジャマイカ戦後半29分に中山選手がゴールを決めたシーン、この4回だけしかなかった。」
「『惜しい』と思わせるシーンはそのほかにもあったが、いずれも(決めなくてはいけないというレベルではなく)、決まってもおかしくはないというレベルのチャンスだった。」
「もちろん少ないチャンスをものにできるかどうかで勝負の行方は決まる。しかし『2トップの決定力不足は、チャンスを多く作り出すことで補うしかない』と話してきた岡田監督にとっては、チャンスが少ないことが、失敗ということになる。」
「(中略)何の変哲もないパスゲームで日本代表をよみがえらせた岡田サッカーは、結局その『特効薬』の後遺症に敗れることになった。」
「3バックへの切り換えへの迷いがチーム作りを遅らせたとも言える。『日本の(中盤のパスワークでビルドアップできるという)特徴をなるべく殺したくないという考えでぎりぎりまで決断を延ばした』と岡田監督は言う。そうした迷いも含めて『後悔はしていないし、正しかったかどうかはみなさんが判断すること』という言葉を残して岡田監督は日本代表から去った。」(注・岡田監督が最終的に3バックで行くことを選手たちに伝えたのは、小野コーチの話にもあるように5月になってから)
「大仁強化委員長は、『限られた時間の中で、よくやってくれた。チームの抱える課題への対策、相手の分析力を高く評価している』とそのチーム作りについて話した。その上で、ディフェンス面の『1対1の強さ』、攻撃面では『距離のあるボールと前線へのパスの精度、フィニッシュ、クロスのタイミングと精度』を今後に向けた全体の課題として挙げている。」
「課題を言えば山ほどある。しかしそれらはワールドカップでの課題ではなく、普段からJリリーグで指摘されている日本人の課題である。それは日本サッカー全体が取り組んでいくレベルのねので、代表監督のチーム作りとはまた別だ。」
「岡田監督は失敗を認めた。次は強化委員会を含めた日本(サッカー)協会が、そのチーム作りの方向を検討する番である。(中略)岡田監督が最後に送ったパス。それを日本(サッカー)協会は、慎重に受けなくてはならない。」
日本をワールドカップ初出場に導いた「英雄・岡田監督」が、本大会で失敗した2つの根本的な理由。
前年秋、突然、日本代表監督を引き継ぐ羽目になった岡田監督。論理的に考え最適解を見出す思考能力の高さで、過酷な状況でも冷静さを失わず、針の穴を通すような難しいミッションを成し遂げ、日本をワールドカップ初出場に導き、一躍英雄となった岡田監督が、本大会では明らかに失敗してしまいました。
採用した戦術、選手起用、試合中の采配等、いろいろと指摘されていることは、根本的な失敗の理由から派生したものです。
ここまで、つぶさに岡田監督と日本代表各選手の様子を追ってみて、2つの根本的な理由が浮き彫りになりました。
それを、今回のワールドカップグループリーグ敗退の原因検証の総括として記録し、長く後世に語り継ぎたいと思います。
理由その(1) カズ・三浦知良選手を22人の中に残さなかったため、チーム全体のメンタルが大会直前になってガタガタになってしまったこと
カズ・三浦知良選手の離脱については「外された」「日本に帰国することになった」という捉え方で報じられ、岡田監督がカズ・三浦知良選手に対して「夢を直前になって取り上げた」とか「功労者をないがしろにした」とか「尊厳を傷つけるやり方をした」といった、感情的、情緒的な側面からの批判が表に出てしまいました。
つまり岡田監督とカズ・三浦知良選手の間の問題としてだけ捉えられてしまい、より重要で影響が大きかった「カズ・三浦知良選手が離脱したことによるチーム全体へのダメージ」については、ともすれば見過ごされていました。
そもそも岡田監督自身も、最後まで、外れる選手に対する考え方、すなわち「サブは嫌だ、試合に出られないから文句がある、そういうことを考え、それに耐えられないというなら、日本に帰っていいぞ、そんなケアが必要な選手なんて要らなかった」ということについては徹底していました。
しかし、誰かを外した時、具体的にはカズ・三浦知良選手に尽きるのですが、彼を外した時、残った選手たちにどういう影響があるのかという点については「プロなんだから割り切ってやってくれるばす」といった程度の認識で、残った選手たちのメンタルに影響を与えるかもしれないとまでは考えなかったのです。ましてや、残った選手の中で、特に絆が深かった何人かの選手たちのメンタルに深刻なダメージがあるかも知れない、などというところまでは、まったく思いが及ばなかったのです。
しかし、あらためて、この3ケ月ぐらいの経過を克明に追っていくと、日本代表が一つも勝てずに終わった背景には、カズ・三浦知良選手を22人の中に残さなかったため、チーム全体のメンタルがガタガタになってしまったという事実が浮かび上がってきます。
チーム全体のメンタルと言いましたが、特に井原選手、中山雅史選手、城彰二選手のメンタルがガタガタになってしまったことが大きいのです。
3人とも表向きは平静を装っていましたから、それほど話題になりませんでしたが「カズさんがいなくなってしまった」ことでメンタルに空いた穴を埋められないまま大会に臨まざるを得なかったのです。3人にとってはカズ・三浦知良選手との絆は、単なる先輩、単なるチームメイトではなく、心の拠り所だったからです。
象徴的だったのは井原正巳選手と中山雅史選手のケガです。井原選手は、カズ・三浦知良選手の落選発表の直後の練習でケガをしてしまいます。井原選手のメンタルがガタガタになった結果、心ここにあらずのプレーがケガをもたらしてしまいました。
井原選手は初戦のアルゼンチンに何とか間に合い、最悪の事態は免れましたが、チームキャプテンの、直前10日のブランクは3戦を戦う井原選手のコンディションにも影響が出ましたし、チームでのキャプテンシーやDFの統率といった面でも影響が出ました。
サッカージャーナリスト・増島みどり氏の著書「ワールドカップフランス98 6月の軌跡」の中で井原選手が「人生最悪の日」と6月2日のことを次のように語っています。
「もし人生最悪の日があるというなら、自分にとっては間違いなく6月2日だったでしょうね。昼飯の後、食堂で、監督から、『ここにいる22人で戦うことになった。市川は残る』そういう短い伝達があった。それだけのミーティングを終え、最初にカズさんの部屋に行きました。もう荷造りをしていて『とにかくオレは帰るから』と。何か夢でも見ているような感じでしたね。ここまでぼくらを引っ張ってきたこの人が帰る? そんな馬鹿な、って。帰る、それだけが聞こえていました。どういう顔をしてどういう声をかければいいのか全然わからなかった。それで中山の部屋になぜか足が向いて、あいつと二人で『どうしようか、これから・・・』って。何を話すわけでもなくただボーッと考えていましたね。(中略)」
「(注・誰がチームから離脱しても)間違ってもそのことで『残った』選手が動揺したりするようなことがあってはならない。それは十分理解していました。(注・外れた選手が帯同、離脱)どちらであっても、これまでと同じようにやるのだということは心に決めていました。でも今思っても、一番動揺しているのは自分だったのかもしれません。カズさん、キーちゃんにはずっと自分の前を歩いてもらって来た。引っ張ってもらっていた二人が目の前から消えるなんて、信じられなかったんです。帰るんだ、そう思ったら何かものすごく不安になったのを覚えています。」
「中山と『とにかくいつも通り平静を装ってやろう、声出して』と、まあ他愛もないことを確認してグラウンドに向かったんです。バスの中では景色を見ながら憂鬱でした。聞かれるんだろうな、みなさん(報道陣)に、カズさんのこと、キーちゃんのこと、チームのこと・・・・。それでミニゲームが始まって。」
「城との接触ですか? 『あれ? 変な着地したな」と一瞬感じました。でも次の瞬間、ひざに激痛が走りました。痛くて痛くて、すぐにヤバイ、これはかなりひどいだろうとは思いましたね。95年にやった個所と同じだったんで。でもなんでこんな時に・・・・と。ああいう着地をなんでしてしまったのかなんてわからないですが、でも、気持ちに動揺があったからだと指摘されても仕方がない、そういうシチュエーションですね。自分ではそんなつもりはまったくなかったのに、心のどこかで動揺していたのかもしれません。それが出てしまったのかもしれません(中略)」
「帰りのバスに向かう途中も最悪でしたね。もうカズさん、キーちゃんのことは聞かれるわ、監督やチームのことも聞かれて。当たり前ですけどね、キャプテンなんですから。でも『平静』を装って答えている自分のひざは、もうずきずき痛んでくるし、何だこの状況は? って、本当にめちゃくちゃでした。」
「さらに宿舎に戻ってから、ひざのこともあって岡田監督の部屋に一人呼ばれました。そこで『井原、お前がオレのやり方を信じられなくなったら、このチームは終わりだから』って言われました。監督も相当きつかったんだと思います。あの選択に関しては。そりゃそうですよね。岡田さんが全責任を一人で負うわけですから。(中略)」
「22人が発表され、自分より歳上だったカズさん、一緒にキーちゃんが帰り、一番若い市川が一人残ることになった。それから自分もケガをしてお先真っ暗、マスコミのみなさんにはたくさん質問をされ、監督にはお前がオレを信じられなくなったら終わり、と言われ、いやもう、本当にしっちゃかめっちゃか、とはあの日のことを指すんでしょうね。本当に何がなんだか分らない一日になってしまった。」
「あれからはもう、ひざの痛みとの戦いの日々でした。(中略)ひざの痛みがひく時と痛む時が交互にきて毎日が完全に躁鬱状態でした。あまりああいう精神状態を経験したことはありませんでした。ボクは信仰心は持っていないんですが、夜など、部屋の天井を見ながら、神様、一体オレが何をしたって言うんですか? それとも、もうドーハ経験者にはW杯には行くな、お前には結局そんな運なんてないんだ、ってことなんですか? って、聞いてしまいましたね。本当にしんどかった。それに長かったですね。」
3試合をすべて終えたあと、井原選手の涙はぬぐってもぬぐっても止まりませんでした。その理由を「今目の前にある1勝を逃したから、ただただ悔しかったから」と述べました。心の奥深くにある思いをあからさまに言うことは生涯決してないことでしょうけれど、井原選手の心を去来したのは、チームのメンタルがバラバラに壊れてしまった悔しさ、それを盛り返すことができなかった悔しさだったことは想像に難くありません。
それは中山雅史選手も同様です。4月にあれほど面白いように得点を重ねた中山選手ですから日本中の誰もが、もっと得点をあげてくれるに違いないと期待した選手です。
では、中山選手はなぜ1得点だけで終わってしまったのでしょうか? FWの選手というのは好調な時、そのポジティブな気分と研ぎ澄まされた得点感覚が持続されてこそ得点を重ねられる、ある意味非常にデリケートな「生き物」です。
磐田で4試合連続ハットトリックを達成できたのは、チームメイトの盛り上げ、サポーターの後押しといったポジティブな気分を持続できる要素と、チームメイトのどこからでもラストパスが出て来るといった恵まれた試合の中で得点感覚が鈍ることなく持続できたためです。
しかし、今回は盟友・カズ・三浦知良選手の離脱という中山選手にとって痛恨の出来事が起きてしまいましたから、FWとして、ゴールハンターとして、勇猛果敢な、獰猛な気持ちを奮い立たせるのは容易なことではなくなったのです。
中山選手は、前年秋のアジア最終予選の第8戦に、出場停止処分のカズ・三浦知良選手、呂比須ワグナー選手に代わって高木琢也選手とともに招集されました。
その時、カズ・三浦知良選手から「自分とともに戦って欲しい」と背番号11のユニフォームを託され、重ね着でプレー、見事ゴールした時には、わざわざスタンド方向に駆け出し、自分のユニフォームをめくって背番号11を観客に見せたほどの間柄、勝利を誓い合ったサッカー少年同士のような盟友なのです。
カズ・三浦知良選手の離脱という現実は、中山選手選手にとって、とても平静でいられるはずのない出来事だったのです。
ここでもまた、サッカージャーナリスト・増島みどり氏の著書「ワールドカップフランス98 6月の軌跡」で語っている中山雅史選手の6月2日の様子をご紹介します。
「6月2日の、あれは確か昼飯の時でした。22人が伝えられたのは昼飯の後でしたから、まだ選手には発表されていなかったんですが、キーちゃん(北澤)が、食堂で同じテーブルについて、その時、『ゴンちゃん、オレ、ビンゴだよ』と。驚いて顔を上げたら、『カズさんも・・』と。『ウソだろ?』そう言ったきりだったと思います。キーちゃんとは何も話せなかった。自分は残る。彼らは帰る。(中略)」
「(注・そのまま部屋に戻って)部屋からは出ませんでした。そうしたらノックの音がして、カズさんが部屋に来てくれたんです。握手して、『お前は残ったんだからがんばれ、いいな、絶対がんばってくれ、しっかりやるんだ』ってね。何も言いませんでした、オレは。」
「手を離したら、何となく・・・・抱き合ってお互い背中を・・・・その時、カズさんが、こう右手でゲンコツを作って、オレの背中、腰のあたりを物凄く強く叩くんですよ、『がんばれ、がんばれよゴン。お前なら絶対やれるんだから・・・・』って。あの時のドンドンって叩かれた感触、カズさんがああいう仕草で励ましてくれたこと、すべて、カズさんの気持ちを表していたんだろうな、と思います。ぶつけようのない悔しさ、残る者への期待すべてがこもったゲンコツだったんだと。本当にあの感触が忘れられない。」
「おかしなもんですよ、こっちが励まされたんですから。(中略)」
「カズさんとキーちゃんが控えでいたあの1ケ月でさえ、何をするべきか、どう振舞うべきか、二人がそれを先頭にたってやってくれたことは間違いない。あの人たちの精神的な強さに自分は何度も助けられたし、あのチーム(注・日本代表チーム)への影響力は計り知れないものがあったと思ってます。自分が言えるのはそれだけです。」
それでも中山選手は、その類い稀れなプロフェッショナルスピリットで3試合を戦い抜き、とうとう日本サッカー史にその名を刻む歴史的ゴールをモノにしました。中山選手にとっては「カズさんから受けたあの激励の感触、それを思えば身体がどうなっても何かを残さなくては」という気持ちだけで戦い抜いた3試合だったと思います。でも、それが精一杯、それ以上は無理といった状況だったと思います。それが証拠に、得点の直後、中山選手の足は悲鳴をあげてしまいました。あとでそれが骨折だったと知った誰もが、その精神力に驚嘆しました。
盟友・カズ・三浦知良選手の離脱の中でメンタルがガタガタになりながら、とにかく結果を出さなければならないという気持ちだけでプレーした結果、そのツケが体の損傷となって現われたのです。
中山選手が、そう何点も取れたなどとは思いません。Jリーグの試合だからこそあげられたゴールも、世界の舞台で対峙する選手たちはそう簡単にあげさせてくれないからです。それでも、カズ・三浦知良選手の離脱という、メンタルをかきむしってしまう出来事が起きず、むしろベンチから盟友のカズ・三浦知良選手が自分を鼓舞してくれるという環境があったなら、中山選手のプレーは、もっと違ったものになったのではないかと思うのです。
それは城選手についても言えることです。城彰二選手はまだカズ・三浦知良選手の離脱が発表される以前に「自分をFWの柱に考えている」という岡田監督の考えを知り期待を抱いていました。ただ、その時は「カズさんがいなくなってしまった中でのFWの柱」とまでは考えていなかったのです。あくまで5人のFWがいた中で、自分をスタメンに使ってくれるんだ、という気持ちなのです。そう考えていたところにカズ・三浦知良選手の離脱という現実を突きつけられ、城選手は怖くなってしまったのです。
ここもまた、サッカージャーナリスト・増島みどり氏の著書「ワールドカップフランス98 6月の軌跡」の中で、城選手が6月2日の発表の時に受けた衝撃と気持ちの混乱について、次のように語っていますのでご紹介します。
「あの日は、多分一生忘れないと思う。岡田さんが、食堂で、『ここにいる22人を選んだ。市川は残る』と言ったと思う。あっけないほど、ひどく短いミーティングだった。部屋に帰って練習までの時間、本当に長かった。自分の部屋は2階で近かったせいもあるんだけど、廊下では、カズさんたちが荷物を出す音や、話し声が聞こえていた。けれど、とても出る気にはならなかった。どういう顔をして会えばいいんだ、って。オレにはできなかった。結局、ドアに背中をつけて、黙って声や音を聞いているだけだった。(中略)」
「FWの柱って言われて、それはうれしいけど、一方ではこれはエライことになってしまった、カズさんの仕事なんて引き継ぐことできるわけないじゃないかって・・・どうしていいのかもわからないし、もう頭の中がこんがらかっちゃって。グラウンドでは、マスコミにそのことを聞かれるだろうなって予想はできていたけれど、『エースになったわけだけれど』と聞かれて、『いえ、違います』とも言えないし・・・本当に戸惑いましたね。頭の中が一日中ぐしゃぐしゃでした。(中略)」
「2日の晩は満足に眠ることができなかった。色々と考えてボーッとベッドに座っている。そうしているうちに何か薄明るくなってきたんだよね。(中略)」
「自分はカズさんについて行けばよかった。それが、呼び方はエースでも柱でも何でも、試合にすべて責任を負う立場になったんだって、今度は前とは全然違うことになったんだって、叩き込んだよ、頭を切り替えろって。グラウンドから戻ると部屋でそのことを考える。同時にカズさんが今まで何年も、こうした孤独に耐えて、寝てなかったのかぁ、それはもう凄い人だな、とあらためて考えることになったね。」
「カズさんが(注・離脱してから)一度、あれはミラノからだったのかな、フラビオ(フィジカルコーチ)の携帯に電話を入れてくれたんだ。オレ(注・城選手)と話せるか、って。ちょうど(注・オレが)席にいない時だったんだけど、いればきっと何かアドバイスをしてくれたんだと思う。でも、こっちからの折り返しの電話、ついにしなかったね。あそこで電話したら、愚痴をいいそうだったし、一晩かけて立場が変わったと気持ちを切り替えたのに、また戻っちゃいそうで、それが怖くて、カズさんには最後まで電話できなかった。あの日から、二度と考えまい、としたんだ。」
スイス・ニヨンに入るまでの城選手のメンタルは、あくまでカズ・三浦知良選手の離脱などという衝撃的なことを想定していないメンタルでしたから、予想外の出来事に、城選手もメンタルのバランスを崩してしまったのです。自分では切り替えたと思っても、頭ではそうできたつもりでも、心の中は、平常心とは程遠いメンタルになってしまったのです。
その結果、責任感が気負いとなり、微妙な得点感覚を狂わせ、次第に点がとれる気がしないプレーに陥り、最後は途中交代で大会を終えた城選手。その代償として「戦犯」の汚名を着せられながら成田空港では狼藉者から清涼飲料水をかけられる屈辱を味わいました。
岡田監督は「ワールドカップで勝つための」という命題を抱えて、自分が組み立てた戦い方をするために22人を選んだと言い、そのことに「後悔はない」と言っています。
選手というのは結局生身の人間ですし、メンタルの変調が身体を傷つけてしまうことさえあるのです。カズ・三浦知良選手を残さなかったことが、頼みとしたチームの要の井原正巳選手そしてFW陣の中山選手、城選手のメンタルを狂わせ、うち2人はケガ、残る城選手も空港で侮辱を受けるという代償も払うことになってしまったのです。
それもこれも、岡田監督が「カズ外し・帰国容認」という判断を下してしまったが故の結果です。
繰り返しますが、岡田監督が「プロなんだから、そんなことに左右されずにやってくれるはず」と思い描いたプランは、厳しい言い方をすれば「残された側の選手たち、生身の人間である選手たちのメンタル」特にカズ・三浦知良選手との絆が深かった選手たちのメンタルに対する影響を何ら斟酌することなく描いた、いわば空論と言われても仕方のない判断だったということに帰結します。
では、またぞろ歴史を知ってしまった者の後付けという誹りを受けることを承知で「カズ・三浦知良選手を残す選択」をどのようにすべきだったのかを、今後のためにも記述したいと思います。
まず、岡田監督の「守りを固めて、攻める時は全員で攻めに出てチャンスを多く作り、そのチャンスに賭ける」という基本戦略は間違っていなかったと思います。
その上で攻めをどう考えるかですが、やるべきだった事は、FW陣の間で「誰が出ても献身的に尽くす」という関係性を築くメンタル面のテコ入れだったと思います。
そのためにカズ・三浦知良選手を外さないで、役割をはっきりと与えるべきだったのです。カズ・三浦知良選手という選手は、基本的に監督の方針に非常に忠実な選手です。自分の思いは持っていてもチームとして決めたことを乱すことはしない選手です。
そういう選手に岡田監督はキチンとチーム内での位置づけを伝えた上で、役割を与えるべきでした。それは次のような内容になると思います。
スタメンは基本的には中山選手と呂比須選手、サブに城選手と岡野選手、カズ・三浦知良選手は彼らの気持ちを奮い立たせる役割と、本当の勝負どころだという時の切り札役です。
カズ・三浦知良選手をチーム内に置いてこそ発揮される彼の献身性であって、それを「メンバーからは外すけど献身的にやってくれ」というのは、あり得ない話なのです。
それから、スペースに走らず足元でボールをもらいたがる呂比須選手に、中田選手がボールを出しにくいということが言われました。それはカズ・三浦知良選手に対する中田選手のプレーでも言われました。中田選手はスペースに走り込んでくれる岡野選手や城選手と組みたがっているという話です。
しかし、中山選手と呂比須選手のスタメンで行くのですから、中田選手は相手の欲しがるところにバスを出してくれるでしょう。中田選手はそういう選手です。岡田監督も、そこは中田選手とコミュニケーションをとって「FWが誰であろうと点をとれるようにしてやってくれ」と言うべきでしょう。
「カズ・三浦知良選手をチームに残す」という判断を岡田監督がしていれば、もっと違った結果を得られた可能性があるという結論を導き出しましたが、では「落選者」は誰にすべきだったか、いつ通告すべきだったのかについても記述しておきたいと思います。
まず、5月7日の御殿場合宿参加メンバー発表は、どう考えても22名にすべきでした。キリンカップ以降は22名で戦う、そう割り切る必要がありました。岡田監督は「3バックシステムをチームとして熟成させ、誰が出ても破綻させないようにするためには、どうしても25名必要だ」と言い続けていましたが、現実に岡田監督がもっとも腐心したのは、3バックをどの選手に組ませるか、ということであり、最後に中西永輔選手というピースを見つけて、岡田監督の考える3バックシステムは一段落したのです。
もちろんレギュラー組の3バックにケガや退場処分などの離脱が生じた場合、ほぼ同じレベルで交代出場できるメンバーを一人でも多くしておきたい、しかも、それはDFの選手だけでなく、FWからMFまで11人全員のレベルを、3バックシステムで破綻しないレベルまで高めたいという気持ちは、心情としては理解できますが、登録メンバー22人の枠は動かせない数なのですから、どこかで踏ん切りが必要だったのです。
選手登録締切日である6月2日までの間に、もし誰かにアクシデントがあれば、入れ替えで対応しようという踏ん切りが必要でした。
なまじ「25人をニヨンで6月2日に22人にするけれど、そのまま残ってもらって、あくまで25人で戦うんだ」などという絵に描いた餅のようなことをしたために、チーム全体のメンタルまでおかしくしてしまったことは、後世への教訓にしなければならないと思います。
22人を決めたあと、練習で紅白戦を行なうには人数が足りませんから、数人をトレーニングメンバーとして帯同をお願いする必要があり、所属チームに同意を得る必要があります。後年、そうしたメンバーを「バックアップメンバー」と呼んで選ぶことが定着しましたが、この時も2002年大会を見据えて何人かに大会を見せながらトレーニングメンバーとして帯同させる方法をとるべきでした。
理由その(2) チームの中心・中田英寿選手のプレースタイル、すなわちスピードのあるFW選手に走ってもらいスペースにパスを出すスタイルを選択したために失敗したチーム作り
岡田監督がワールドカップ本大会に臨むチーム作りの過程で、誰よりも頼りにしたのが「チーム全体の柱」としての中田選手でした。
岡田監督は公の場では「チーム全体の柱」といった表現で中田選手のことを話題にすることがほとんどありませんでしたが、実は、守りに重心をおいた岡田監督のサッカーにおいては、好守ともに中田選手がいるから可能な戦略だと、まさに全幅の信頼をおいていたのです。
「守」から「攻」へスイッチを入れる役目、中盤の中田、名波、山口の3選手のコンビネーション、そしてFWへのラストパス、いずれも中田選手がいれば可能な攻撃パターンです。
岡田監督のこの戦略においては、中田英寿選手がFWの選手に対して送るラストパスこそが得点の可能性が最も高いパターンだと考えられましたし、中田選手自身も、それが最も得点可能性のある攻め方だと考えていたようです。
第2戦のクロアチア戦、前半33分に中田選手が中山雅史選手に送ったピンポイントのキラーパス、中山選手が見事なももトラップからシュートを放ったあのパターンです。
それは、一瞬にしてチャンスが生まれるスペースを見極めて、そこに針の穴を通すような、距離、速さともに計算し尽くされたピンポイントのキラーパスを出せる中田英寿選手の優れた戦術眼と高い技術があるからこそ出来る攻めです。
結果的には、3試合でこういう場面が何度も見られたわけではありませんが、紛れもなく最も得点可能性の高い攻め方でした。
ところが、この中田選手の「スピードのあるFW選手に走ってもらいスペースにピンポイントのキラーパスを出すスタイル」というのは、中田英寿選手の求める基準に合うスピードを出せるFWであることが条件となります。
残念なことに、足元のボールコントロール技術がどんなに高くても、ポストプレーを行なう身体の使い方がどんなに優れても、中田選手がスペースに出したボールに追いつけるスピードがない選手は失格になるのです。
その結果、代表メンバーからさることになったのがカズ・三浦知良選手であり、3試合一度もスタメンでは使われなかったのが呂比須ワグナー選手なのです。
岡田監督が、中田英寿選手のプレースタイルを選択したためにチーム作りに失敗したと表現したのは、スピードのあるFW選手に走ってもらいスペースにピンポイントのキラーパスを出すスタイルがあれば事足れり、あとは要らないという判断に繋がったからです。
今回の日本代表のチーム作りにおいて、日本より格上のチームからいかにして勝利もしくは勝ち点をあげるかということを考えた時に、守りの戦略をしっかりとチームに根付かせることが最大の課題であり、結局は、そのことに時間がかかり過ぎて、攻撃のパターンをもっと増やすところまで時間が足りなかったと言われています。
また、22人に限られている登録選手の中で、FWとして選択できる選手は、決めた攻撃パターンに合う選手に限られるという人数面の制約もあったと思います。
岡田監督にしてみれば、時間と人数の制約さえなければ、もっと攻撃のオプションを増やさなければ確実に勝利もしくは勝ち点をあげるところまではもっていきたかったと感じていたも知れません。
結局、中田英寿選手から送られるパスをゴールに結びつけることを期待された城彰二選手も中山雅史選手も不本意なパフォーマンスしか発揮できなかったとしても、それは結果論なのかも知れません。
もし、岡田監督にやれることがあったとすれば、それは、スピードのあるFW選手に走ってもらいスペースにピンポイントのキラーパスを出すという「中田英寿選手のプレースタイル」だけを選択するのではなく、カズ・三浦知良選手や呂比須ワクナー選手の足元にボールを出すプレーも、中田選手に要求することだったと思います。
中田英寿選手にしてみれば、そういうプレーをすると、相手DFに潰されるだけで攻撃にならないから、スペースに出さなければならないと考えていたと思いますが、すべてが潰されるだけなのか、ポストとしてはたくことすらできないのかと言えば、決してそうではないでしょう。
しかし、岡田監督には「中田よ、足元にボールを欲しがる選手には出さない、というならカズやロペが使えなくなる、そこまで言うならお前を使わないぞ」という考えはなかったようです。なぜなら、岡田監督は、チームの中心である中田英寿選手のプレースタイルを選択したチーム作りをすることに決めたからです。
岡田監督の中田選手に対する信頼は「絶大な信頼」にまで強固になったが故に、中田選手のプレースタイルに合わせただけのチーム作りをしてしまい、選手起用や采配にまで影響が出てしまったのです。
チームがエクスレバンに入って、アルゼンチン戦まで1週間ほどに迫った時にも、岡田監督は中田選手をホテル内にカフェに誘い、二人だけで意見交換しています。
それは、中田選手が練習でも試合でもミスした選手や、自分の意図通りに動いてくれない選手に容赦なく激しい言葉を浴びせたり、大げさな態度で不満を示すことが気になっていたためでした。
「不満を表すより、盛り上げてやったほうがチームのためになるのではないか」、筋道を立ててやんわりと諭したことに中田選手は理解を示し、それ以降、中田選手は変わったといいます。岡田監督は、中田選手が自分のプレースタイルを思いどおりに発揮できる近道を指南したわけです。
格上のチームに勝つために中田選手の戦術眼とキラーパスは、唯一といっていいほどの武器であり、前年のジョホールバルでの、城選手に送った同点ゴールにつながるパスのイメージを強く記憶しており、あれが出れば勝てると考えていたことは想像に難くありません。
結局、岡田監督は、FWの組み合わせも含めて「中田選手のプレースタイルに合わせたチーム作り」をしました。それ以外のプレースタイルは不要と切り捨てたのです。
岡田監督は「中田英寿選手のプレースタイルに合わせたチーム作りをすれば、カズ・三浦知良選手の居場所がなくなるのは仕方のないことで、それに従ったまでのことだ。」と言うでしょう。
しかし、カズ・三浦知良選手を外してしまったらチーム全体のメンタルがガタガタになってしまうという洞察力を働かせて、カズ・三浦知良選手や呂比須ワグナー選手といった足元の技術が高く、DFを背負ったプレーができる選手を活かす攻め方をオプションとして用意しておけば、もっと違った景色が見られたのかも知れませんが、そこはないものねだりなのかも知れません。
皮肉にも、日本があげた唯一の得点は、心密かにスタメンでの起用を熱望していた呂比須ワグナー選手が、途中交代で出場して中山選手に送ったパスから生まれたのです。岡田監督が「FWの柱は城」と宣言して、それにパスを供給してくれる中田英寿選手のプレースタイルを最重要視した戦略は実を結びませんでした。
繰り返しますが、日本代表の攻撃力を考えれば、中田英寿選手のプレースタイルに頼る方法が、考え得るベストの策だったのかも知れませんが、それに固執するあまり、他の攻め方をオプションを不要と切り捨ててしまったことが失敗だったと、あの1得点は物語っています。
中田選手の3試合は、さすがに日本代表の柱と言われるにふさわしいものだったかも知れませんが、一つだけ記憶に留めておきたいことは、この大会での中田英寿選手の目的は「日本代表を勝たせるプレー」に加えて「海外移籍を確実なものにするためにスカウトに高評価を得られるプレーをすること」だったという点です。
岡田監督は、そのことを、エクスレバンのホテルのカフェに中田選手を誘った時に知りました。岡田監督がさり気なく「ワールドカップが終わったらどうするんだ」と聞くと、中田選手は間髪を入れず「できれば、ヨーロッパのチームでやるつもりです」と答えています。
中田選手にとって、この大会は「日本代表を勝たせるプレーをする」ことと同じぐらいに「海外移籍を確実なものにするためにスカウトに高評価を得られるプレーをする」ことも重要でした。そして、日本代表を勝たせる結果には繋がらなかったものの、自分自身の海外移籍実現に向けた高評価に繋げることはできました。
岡田監督が「中田選手のプレースタイルに合わせたチーム作り」をして、それが中田英寿選手にとって「日本代表を勝たせるプレー」に繋がり、なおかつ「海外移籍を確実なものにするためにスカウトに高評価を得られ」れば、2人にとってこれ以上のハッピーエンドはなかったのですが、大会後、岡田監督と中田英寿選手は、見事なまで明暗を分けてしまいました。
以上、岡田監督本大会で失敗した2つの根本的な理由を明らかにしましたが、この時点での岡田監督に、それを求めても詮ないことです。
1998年4月から6月にかけての岡田監督の3ケ月間は、自分を信じ、自分の信念を貫かなければ、代表監督として立ち行かなくなるという強い思いだけを支えにしてチームを率いていましたから、考えに考え抜いて固めたプランは、まさにファイナルアンサーであり、寸分たりとも変更の余地のないプランになってしまっていたからです。
6月2日に、カズ・三浦知良選手を外したことによって生じた大きな社会的反響のところでも書きましたが、岡田監督は、論理的に考え最適解を見出す思考能力の高い人です。そして、それに基づいて導き出した考えを貫く信念の強さも持ち合わせた人です。
だからこそ、前年秋のアジア最終予選の過酷な状況でも冷静さを失わず、針の穴を通すような難しいミッションを成し遂げられたのだと思いますし、その功績はいささかも貶められることはありません。
一方で、岡田監督のその「信念の強さ」ゆえ、時として自分が組み立てたロジックの陥穽に陥ることがあります。ですから、そのロジックに破綻が生じ、裏目に出た時には、惨憺たる結果を招くことを、図らずも露呈してしまったのです。
かねて岡田監督が持論にしていたのは、とかく日本人は「感情面に流れる傾向が強く論理性が欠如している」ということでした。
朝日新聞社運動部の潮智史記者は1998年11~12月にかけて同紙に連載した「岡田武史の301日」(2001年には同新聞社から単行本化)の中で、岡田監督の持論を次のように紹介しています。
「日本人は苦境に追い込まれると、『みんなで手をつないでがんばろう、大丈夫、俺たちは強いんだ』と言って非論理的な空気を作り出して、やみくもに突き進むようなところがある。サッカーは論理的な思考と感情的な部分の両方があって、どちらかだけではだめ。そのバランスが重要だと考えている。それが日本人の場合、感情面に偏ってしまう傾向が強い」
この「情に流されず理をもって御する」持論は、皮肉なことに論理思考を重視するあまり、苦境の時に頼みとする「絆」とか「連帯感」といった感情面、言い換えればメンタル面の要素がすっぽり抜けてしまい、岡田監督の言う「どちらかだけではだめ。バランスが重要」の逆アンバランスに陥ってしまったのです。
22人として残った選手たちのメンタルへの影響を「情に流されることがあってはならない」と岡田監督自身が自分の心にフタをしてしまったかもしれません。
ただ、ただ残念としか言いようがありません。どこかで何かの力が働き、それが助言からなのか、さりげない会話の中からなのか、何か岡田監督の心の中に「まてよ! 論理的な部分と感情面のバランスはとれているだろうか」と思わせることがあったなら、ワールドカップ本大会の3試合がまったく違ったものになり、日本サッカーの歴史も違うものになっていたのではないかと、ついつい思ってしまいます。
ワールドカップ本大会に向けた日本サッカー協会のあり方はどうだったのか、協会上層部と強化委員会、それぞれについて
フランスワールドカップでの結果を受けて、日本サッカー協会に対しては、二つのことが指摘されています・
一つは責任の所在、もう一つは次に向けて何をすべきかという点です。
そして、それは日本サッカー協会上層部に向けられているものと、より現場に近い強化委員会に向けられているものがあります。
もはや日本サッカー界だけのものという枠をはみ出して国民的関心事にまで高まったワールドカップとそれに臨む日本代表、協会上層部と強化委員会は、そういた意味合いの変化に十分対応したやり方をしてきたのか、それとも国民的関心事にまで高まった環境変化に堪えるだけの意識もノウハウも持たずに、単純に従来の意識や、やり方だけだったのか、後世に伝える教訓の有無も含めて検証します。
【日本サッカー協会のあり方検証 その1】本大会に向けた日本代表強化のマッチメイクサポート不足の指摘、Jリーグとの調整の不作為
ジャマイカ戦を終えて日本代表が3連敗となった直後、サッカーダイジェスト誌がいち早く、サッカー協会の日本代表強化マッチメイクサポート不足を指摘しました。
98.7.15号でワールドカップ取材特派の戸塚啓記者は「協会サイドの熱意の欠如を浮き彫りにしたジャマイカ戦の敗北」という見出しで次のように指摘しました。
「強化委員会、理事会(注・協会上層部)、代表チーム、この関係を明確にするのも、世界レベルのチーム作りには避けて通れない道だろう。そもそも強化委員会はどんな権限を持ち、フランスに向けてどのように岡田監督と選手たちをバックアップしてきたのか。ジャマイカ戦での黒星は、現状での日本の限界を示したとともに、強化委員会や理事会といった協会サイドの熱意のなさを浮き彫りにした。」
「レネ・シモンエス監督のジャマイカは、猛烈なペースでテストマッチを強化することで、フランスに向けた強化を図った。彼らが日本から奪った勝ち点3は、テストマッチの数の違い、チーム強化にかける両国の温度差がもたらしたものでもあった。『強いと分かっていた相手』(岡田監督)に勝つためのサポートを、なぜ怠ったのか。」
「実力で負けてしまったのならあきらめもつく。実際、日本は世界に劣っていた。だが準備段階で勝負がついていたとすれば、これほど悔しく腹立たしいことはない。サポーターたちにばかりサポートを任せてきた理事会や強化委員会は、今回の結果をどう受け止めているのか。甘い立場にないのは監督と選手たちだけではない。」
サッカーダイジェスト誌・ワールドカップ取材特派の戸塚啓記者の指摘と相前後して、98.7.16Number448号でも「日本vsジャマイカ戦緊急速報『冷たい怒り』」という見出しで、サッカージャーナリストの金子達仁氏がこう指摘しています。
「率直なところ、いま、私は岡田監督に対しての怒りをまったくといっていいほど失ってしまっている。(中略)選手たちに対する怒りもない。(中略)もはや、全身の血が凍りつくような怒りの矛先は、違う方向に対して向けられている。」
「日本サッカー協会に対して、である。」
「2002年のために・・・。今回のワールドカップについて語られる時、ふた言目には出てきたのがこの言葉だった。経験のない岡田監督に指揮を任せるのは2002年のためであり、フランスでは勝ち負け云々よりも2002年のために何らかの収穫を得る方が重要だとされた。いつの間にか、フランス・ワールドカップは2002年のためのプレ大会のような位置づけに追いやられ、最後にはすべての批判に対する免罪符のようにして使われるようになった。」
「アウェーでの経験を積ませようとしなかったのも、攻撃に関するアイディアを持っている外国人コーチを招聘しなかったのも、ことごとく『2002年のために』とのスローガンとともに片づけられた。」
「フランスでの日本代表は、2002年につながる何かを手にしただろうか。日本サッカー協会は、ワールドカップに参加するだけで、何らかの収穫を得ることができると考えていたフシがある。勝てなくても3試合指揮を執れば岡田監督は名監督に成長し、選手たちは世界と戦えるようになるとタカをくくっていたフシがある。」
「岡田監督は名監督になっただろうか。日本人の世界に対するコンプレックスは払拭されただろうか。」
「『なった、払拭された』と答える方が大多数だというのであれば、私は何も言わない。日本サッカー協会は正しかった、フランス・ワールドカップを半ば犠牲にしてまで、2002年に備えたのは正しかったということになる。」
「だが、どれほど楽観主義に徹しようとしても、私にはどうしても、フランスでの日本代表が何かをつかんだとは思えないのだ。(中略)なぜ、こんなことになってしまったのだろう。」
「岡田監督は『すべての責任は私にある』と言った。(中略)これは真実ではない。そして岡田監督が辞意を固めつつある以上、同じように責任を持つ人々がそのまま居座るのは、どう考えても間違っている。(中略)」
「私は、協会の長たる人物の解任を要求する。『強化委員会』を名乗りながら、効果的な強化を図ろうとしなかったグループの抜本的な見直しを要求する。(中略)」
「皮肉なことだが、もし私の願いがかなったとしたら、それはフランス・ワールドカップに於ける日本の唯一の収穫ということになるかも知れない。」
サッカーダイジェスト誌で戸塚啓記者が指摘した「協会サイドの熱意の欠如」とNumber誌で金子達仁氏が指摘した「協会は、ふた言目には『2002年のために』という言葉で片づけてきた」という表現が、今回の日本サッカー協会の態度を端的に示しています。
日本サッカー協会の大仁邦彌強化委員長は「2002年のために」の意味合いを、今大会の結果にかかわらず岡田監督に続投を要請、この大会で得た手ごたえも課題も2002年に活かしてもらうことと考えていたようです。
サッカージャーナリスト・増島みどり氏の著書「ワールドカップフランス98 6月の軌跡」の中で大仁邦彌強化委員長は次のように語っています。
「ジャマイカ戦が終了して、岡田監督に『強化委員会の評価としては、今後も続投して欲しい。2002年を目指してくれないか』と言いました。(中略)」
「あの時点では、獲得の退任の意思は確かに固かった。でも我々としては本当に続投してもらいたかったし、将来のために何としても残ってもらいたかった。だから、この件に関しては帰国して落ち着いてからまた話そうと思ってました。しかし一気に新監督就任という流れが作られてしまって、これにはちょっと戸惑いましたね。」
この大仁強化委員長の認識にも、岡田監督の「22人になっても25人のままフランスで戦うんだ」という認識と同じ、何か常識とはかけ離れたものを感じます。つまり、岡田監督の、外された選手をそのまま一緒に残すことが、いかに非現実的かということと同様、大仁強化委員長が「続投を要請すれば受けてくれる」と考えていることが非現実的なのです。結果責任を監督が負うのは当然であり、通常の感覚を持つ人であれば、続投を要請されて「それはありがたいですね、では受けます」などということはあり得ないのに、そう思わずに要請しているわけです。
それもこれも、前年秋以降の加茂監督更迭、岡田監督緊急登板、アジア第3代表決定戦でのギリギリの出場権獲得、岡田監督続投以外に選択肢のなかった本大会監督選任といった経過の中で、日本サッカー協会には「こうなったからには、2002年は、フランス大会を経験した岡田を続投させて指揮を任せるのが最も合理的」と考えるようになったとしても不思議ではないかも知れません。
おそらく3連敗、勝ち点ゼロはサッカー協会にとっても岡田監督にとっても誤算だったのでしょう。1勝でもすれば立派なもので、そこまでいかなくても勝ち点1でも取れれば岡田で十分いけると考えたのでしょうけれど、それすらも結果を出せなかったとすれば岡田監督が続投を考えるわけにはいかなかったのに、協会のほうはそう考えずに続投を要請した、そんな図式でしょうか。
問題は、協会が「2002年も岡田に任せる」と考えていたのでしたら、なぜ、それが水泡に帰すような貧弱なサポートしかしなかったのかという点です。
グループリーグ突破という勇ましい目標を掲げて全力でチーム作りに取り組んでいる岡田監督が、せめて本大会で1勝、悪くても勝ち点の1や2をとらせてやるサポートを、なぜもっとできなかったのか、という点です。
サッカーダイジェスト誌の戸塚記者も、Number誌の金子氏も口を揃えて、テストマッチの少なさ、アウェーでのゲーム経験の少なさを指摘しています。ジャマイカと同じぐらいという贅沢は無理としても、協会は、本大会で1勝、悪くても勝ち点の1や2はとれるよう実戦経験を積ませる場をどうして作ってやれなかったのか、です。
これについて協会からは不作為の「言い訳」が聞こえてきそうです。「Jリーグとの調整もあり、なかなか協会だけの判断でマッチメイクを決められないので」とか「岡田監督のチーム作りの意向で合宿重視の強化にしたので」とか・・・。
その結果、ダイナスティカップとかキリンカップ、日韓戦など決まった大会だけ、しかもアウェー戦はごく僅かという貧弱な強化にしかならなかったのです。
金子氏が「フランス・ワールドカップは2002年のためのプレ大会のような位置づけに追いやられ、最後にはすべての批判に対する免罪符のようにして使われるようになった。」と指摘しているのは、ある意味、協会の本音をズバッと突いていると言えます。
フランス・ワールドカップを本気で勝ちに行くと考えれば、アウェー戦を多くした強化計画も、Jリーグとの調整も長沼会長が音頭をとればできる話ですが、長沼会長には、もうそこまでの熱意はなかったのです。年の初めには、そろそろ岡野俊一郎副会長に譲って2002年日韓大会成功に全力を尽くしてもらいたい、心の中ではそう決めていたのでしょう。
金子達仁氏が「協会の長たる人物の解任を要求する。」と怒りMAXでぶち上げた記事を長沼会長が目にしたなら「まぁ、そんなに怒りなさんな、それぐらいのことは考えているから」と呟いたに違いありません。
長沼会長が「フランス・ワールドカップを本気で勝ちに行くための強化やJリーグとの調整まで踏み込んで汗をかく気はなさそうだ」となると、強化委員会は無理なことをしてまで調整を図る必然性はありませんから「やれるだけのことをやるだけ」というスタンスになります。対外的には「すべては2002年のために」と言っておけば済む話です。
初めての世界大会に熱をあげて期待をMAXまで膨らませた日本全国のサッカーファンや、本気の世界大会に出るからには「善戦で終わってはならないのだ」と高揚したサッカー専門家たちほど、協会の人たちは熱くなっていたわけではなく、淡々と自分たちの立場でフランス大会を迎えていただけなのです。
こういう、協会と現場、そして取り巻くファンや専門家たち、それぞれの間に大きな温度差があったのが、今回のフランスワールドカップ日本代表だったのです。
ちょっと空しくなるような結末ですが、この当時は、協会幹部にはまだ「ワールドカップ日本代表が、すでに自分たちの恣意的な考えだけで環境を整えてやれば済むレベルを超えて、日本社会全体の共有物にまで、その価値が高まっているのだ」という認識が希薄で、その結果の不作為が、日本社会全体にどれほどの落胆と失望をもたらしたのかについても当事者意識が低かった結果です。
これまで、ネルシーニョ問題や、アジア選出FIFA副会長選の問題、そして2002年W杯開催地決定問題、昨年のW杯アジア最終予選での加茂監督更迭問題と、ことごとく指弾を浴びるような対応に終始してきた日本サッカー協会の体質を考えれば、今回もその延長線上にあるだけであり、それまでのことですが、これが、この先いつまで続くのかを考えた時、金子達仁氏のようにまだまだ「全身の血が凍りつくような怒りの矛先」を向け続けなければならないのかも知れません。
【日本サッカー協会のあり方検証 その2】日本代表を襲った洪水のようなマスコミの取材攻勢を制御できなかったサッカー協会
さる5月7日、岡田監督が25名の日本代表を正式発表した記者会見には、史上最高250名の報道陣が集まりました。
それ以来、6月27日のジャマイカ戦そして6月29日に成田空港に代表選手たちが帰国するまで間、日本代表は洪水のようなマスコミ取材攻勢にさらされ続けました。
今回、主として岡田監督が矢面にたって、マスコミの取材をさばきましたが、その負担たるや想像を絶するものがありましたし、岡田監督自身が、まるで「弁慶の仁王立ち」のような気迫を持って受け止めようとしていたことから出来たことでしたが、では選手たちがそれで守られたのかと言えば、そうではなかったのです。
岡田監督は、サッカージャーナリスト・増島みどり氏の著書「ワールドカップフランス98 6月の軌跡」の中でマスコミ対応について「メディア」という言葉を使って次のように振り返っています。
「メディアについて、フランスに残って試合の視察をした時に、コーチカンファレンス(監督会議)に出ました。その時に彼らは、W杯には魔物が住んでいるというけど、魔物の正体は何かといえば、これはメディアだと。もちろん、行く前にもジーコやアルディレスにも、ほかの大会と違うのはメディアがよりクレージーになるだけだ、といわれましたが。でも自分の解釈が間違っていました。」
「当初はメディアのプレッシャー(が魔物)だと思っていたんです。つまり自分だけへのプレッシャーなら耐えられると思っていました。でも少し意味が違っていたようです。」
「御殿場合宿からのあの2か月くらい、キャンプして環境もどちらかと言えば動けない中にいるわけで、そうした中で、メディアに選手がこう言った、監督がこう言ったと報じられる。あれ、オレこんなこと言ってない、こういう意味じゃない、あるいは質問もされてない、なんで分かるんだよ、とかね。常にメディアのものすごい一方通行なわけです。自分たちが反論する場がない。それによって選手が受けなくてはならないストレス、これがものすごく溜まっていると思いました。」
「ぼくらはもう年齢も言っているしある程度耐えられる。でもまだ若い選手たちが、そういうプレッシャー、つまり自分が発言したことの反響とか、行動への批判とか、こういうものに2か月くらい耐えなければならないとは、予想もしていませんでした。」
「だから、選手をそういうストレスから守り、指導するほう(監督コーチ等)に対しても、メディアが何を言おうが関係ない(から自信をもってやれと安心できるような)、そんな体制を整えるべきだと思いました。公式な、ぼくらを代理できるような立場と経験のある人にスポークスマンをやってもらい、ぼくが言った、選手がこう言った、というような部分を減らしてもらえれば、もっと集中できるのではないかと。」
「フランスは優勝したのに、メディアはジャケ(代表)監督ではダメ、と言っていた。でもそれをフランス協会の副会長は『ジャケは間違っていない』とメディアに対して言い続けた。アルゼンチンのパサレラ監督も、マラドーナを外すとか、選手を外し続けてあそこまで行ったわけですけれど、国民の猛批判に対して協会が4年間、彼をちゃんと守った。そういうものを日本も持ってもらう方向に行ってくれたら、と願ってます。」
代表チームにおいて監督と選手たちが苦労する、最も核心の部分を岡田監督がわかりやすく語ってくれていて貴重なインタビューです。
これについては協会側も同じ反省をもっていました。サッカージャーナリスト・増島みどり氏の著書「ワールドカップフランス98 6月の軌跡」の中では、サッカー協会・大仁邦彌強化委員長が、次のように述べています。
「(サッカー協会が)岡田監督に対してサポートできなかったのは、メディアとの関係についてでしょうか。22人枠の発表についても、実際に発表するところまで監督の仕事になってしまった。ほかにも、あまりにも全決定について監督が前面に出るような形をとり過ぎたために、監督の負担は多かったと思う。メディアとのことは今後も広報との連携の中でいい方法を考えていかないといけない。」
また、サッカー協会・小野沢広報部長にもインタビューしています。小野沢部長は、
「今回は、これまででは考えられないような注目度、関心を集め、それはそれで非常にうれしいことではあるんですが、同時に様々な点においての『温度差』も感じるようになりました。報道はその中でももっとも顕著な違いがあるものでした。」
「あちら(現地)では、毎日、日本から新聞をファックスしてもらい読むことはできました。しかし国内の雰囲気は分からないし、現地は非常に静かなわけですから、情報の発信地にいながら国内のリアクションが判らない。広報関係者にとっては非常に難しい状況だったと思います。」
「例えば6月2日、22人の発表の日にも、先に日本の朝刊に名前が掲載されていた。(中略)6月20日のクロアチア戦後、岡田監督が辞意を表明したのだから、関係者を会見に出してくれ、とリクエストが来る。この時は長沼会長に会見に出ていただいたんですが、記者からの質問も感情的で、押し問答のような質疑応答になってしまった。現場の岡田監督とこちら(協会サイド)の考え、みなさん(メディィア側)と広報、さらに現地と日本と、様々な温度差が一気に出てしまったような象徴的な会見になってしまって・・・。あのことなどを見ても、広報としてもっと公式コメントを利用して、早く対応してしまってもよかったのかもしれない、と反省しています。」
「あれだけの報道量と、現場での記者のみなさんの多さ、(中略)量ではほぼ世界に匹敵するものになった。次はクオリティ、質を追求して行かなくてはならないのではないでしょうか。色々な点で、代表をとりまく周辺も成熟していかなければならないと、強く思っています。」
岡田監督があげた「公式な、ぼくらを代理できるような立場と経験のある人にスポークスマンをやってもらう」という点や、小野沢部長があげた「広報としてもっと公式コメントを利用して」という点などは、次に活かせる話です。
前年のアジア最終予選の際にもすでに表れていた問題ではありましたが、やはり、日本サッカー界が経験する初めての世界の舞台、小野沢部長が実感したように「量ではほぼ世界に匹敵する」ほどの、いわばケタ違いの状況だったというこどでしょうか。
【日本サッカー協会のあり方検証 その3】選手に対するフィジカル・メディカルサポートの手厚さが、過保護にしてしまったかも知れないという反省。一方、心のリフレッシュ、メンタルケアなどについては、手つかずのまま、今後の課題として浮き彫りに
日本サッカー協会は、1993年のW杯アジア予選のあとから、日本代表に対するサポート体制を強化してきました。そうした対策を担当してきた関係者の言葉を借りれば「この4年間、日本代表については『すべて』で最高の対応をし、もうこれ以上はできない、誰にも文句は言われない、というホスピタリティもできた。これはおそらく、32ケ国中でもトップクラス」というほどのサポート体制を敷きました。
確かに、フィジカル面のサポートスタッフや専属調理師・栄養士の帯同、利用宿泊施設のグレードなど、まさに誰にも文句は言われないホスピタリティだったと言えます。
あまりの至れり尽くせりのせいか、選手の中には、まるでプライベートスタッフを得たかのような勘違いも見られたそうです。
サッカージャーナリスト・増島みどり氏の著書「ワールドカップフランス98 6月の軌跡」の中には、そのエピソードも紹介されていますので引用します。
・田中博明アスレチックトレーナー
「ジャマイカ戦の前夜、ぼくとナズー(並木トレーナー)は、練習も早く終わっていたから、20時でマッサージを終えるようにしよう、と決めていたんです。で、早めに片付けようとしていたときに、何気なく徳さん(徳弘トレーナー)に「徳さんも、もう終わりかい?」って聞いたんだよね。そしたら、人がいいんだろうね、徳さんは、「いえ、23時にあと1人来ます」って言うんだ。」
「自分自身があそこまでかなりイライラしてたこともあったし、これから3時間後に選手がマッサージに来るって聞いて、怒りが爆発してしまって。徳さんには悪いことをしてしまったと後で反省したんだけど、怒鳴ってしまったんだ。『それはどういうことだ。そんなの間違ってるぞ。こっちが決めた時間に来られないっていうんなら、もうやることはない! あと20分で来なさい! 』ってね。徳さんはキョトンとして、『はい、そうですね。電話して確認します』って、選手に早くするように確認を入れてくれたのね。それでその選手に言いました、ハッキリ
と。『自分たちの時間にすべてこちらが合わせるのが当然、という考えはおかしいことだよ』と言うと、わかった、と言ってくれたんで、それで済みましたけれど。」
「メディカルの反省としては、とにかく選手のためにやり過ぎた、ということだろうね。初めてだから、日本代表だからって、何から何まで彼らの要求をすべて聞き入れてしまったんじゃなかろうか。そこには強い選手を育てる、という一番大事なポリシーが抜けてたと思う。飲み物だって一人ずつのスペシャルを作るとか、最高級品の扱いをしてね。ここまでやるか、っていうくらい。もうあれ以上はないですよ。あれ以上だとあとはもう国賓とか、そういうレベルになってしまう。」
「代表の扱いがベターであるべきだとは思うが、あそこまでやることが果たして本当に選手のためになっただろうか。黙って『やってやる』ことがよかったのか。今、それをものすごく反省していますね。自分を含めて、ひとつの大きな勘違いの中で過ごした半年じゃあなかったかと。その意味では悔いが残ります。」
・徳弘豊アスレチックトレーナー
「自分は95年、加茂監督になった時から代表チームにかかわって来て、『代表ではすべてを一番良い扱いにしよう』という一つの目標の中でやってきました。しかし一方では、ともすれば選手は何ひとつしなくていい、というような拡大解釈を生んでしまったところもありました。ああ、このままではいけないと思いながらも、もう大きな流れができてしまっていて、トレーナーの責任者としてこれは最も大きな反省です。他国に比べても日本は過保護だったのではないだろうか、と自問自答の日々です。」
・並木麿去光アスレチックトレーナー
「今回の代表に与えられた環境は、というと、衛星、水分、栄養、睡眠をコンディショニングの4本の柱にして考えるんですが、これはもう完璧でした。たとえるなら、美空ひばり、石原裕次郎クラス(のVIPのサポート体制)っていうんですか。初めてでたのに、ですよ。」
「選手のアピールに対して応え過ぎたんではないか、という反省があります。自己管理の意味を勘違いさせてしまったかな、と。ああいう厳しい大会だからこそ、自分で自分を本当の意味で管理できるよう持っていかなくてはならなかった。」
「そういう点では、勝てると確信できるような『強さ』を持っていたチームではなかったかもしれません。メディカルスタッフとしての反省です。」
フィジカルコンディション作りに関しては、まさに「もうこれ以上はできない」ほどのサポート体制だったことがよくわかるエピソードですが、それが逆に選手たちを過保護にしてしまったのではないかと自問自答してしまうほどの手厚さだったのは、この時まだ、積み重ねた経験値から得た「程よいサポート」感をまだつかめていない結果なのかもしれません。
一方では長い隔離生活から来るメンタル面のリフレッシュ、ケアについては、なかなか表に出にくい面もあって、改善すべき点がありました。
ここまで、次から次へと引用させていただいている、サッカージャーナリスト・増島みどり氏の著書「ワールドカップフランス98 6月の軌跡」の中には、川口能活選手が、このメンタルリフレッシュ、ケアのことについてインタビューで語っています。
「メンタルコンディションについては、もう少しだけ自由な時間というのもぼくは欲しかったですね。今回、エクスレバンに滞在中何に驚いたって、ブラジルがディズニーランド(ユーロディズニー)で遊んでいるのをみたことですね。ええ、本当にたまげた、そんな感じでしたよ。彼ら優勝候補じゃないですか。でも家族連れでジェットコースターとか乗っちゃってる。あれはある意味でショックというか・・・・いいなぁ、あれぐらいリラックスできればなあ、と思いました。」
「初出場だし、もちろん遊びにいっているわけじゃあない。だけど、試合前になってくるとみんななんかイライラして、顔も引きつってくるんですよ。それがすごく分かりました。何よりいやだったのは、笑顔が消えてしまったことでした。笑うような精神状態じゃないんですね。ちょっとしたことでピリピリしてしまう。」
「自分は今回、彼女に励まされました。何気ない一言でずいぶん励まされたし随分楽にもなりました。ああいう存在がもっと身近にいればなあと、少し思ったんですね。」
「自分は勝負に集中していたつもりですし、みんなもそうでしょう。でもね、男だけの40日間って結構きついんです。ぼくは休みを増やしてもらいたい、というよりは家族とか、ガールフレンドとか、友人とか、そういう人と過ごす時間をもっと欲しかったですね。家族が来られるようになったのはアルゼンチン戦の後ですかね。みなさん宿舎にいらっしゃいました。(中略)」
「ブラジルみたいに、彼女も含めてファミリーで応援してもらう、みたいなやり方は、日本のマスコミのあり方だと無理なんでしょうか。籠の鳥とまではいかなくても、できるのは散歩くらい。その散歩でさえ、少し歩けばマスコミに会ってしまう。そういう環境をもうちょっと変えられたらと思いました。」
「でもホテルの中での環境は、これはもう恵まれ過ぎっていうぐらいでした。(中略)もうこれ以上は何も望めないっていう感じでした。でもブラジルもアルゼンチンも、2人部屋だったらしいですね。今回(日本は1人部屋なので)基本的にみんな部屋にこもる形になってしまう。これも良し悪しという面があったと思います。ブラジルのように振舞えなかったのは、自分たちの恵まれた生活にも原因があるのかもしれません。」
川口選手の話は、サッカー協会が「日本代表については『すべて』で最高の対応をし、もうこれ以上はできない、誰にも文句は言われない、というホスピタリティもできた。」と自信を持って語った内容を裏付けていて、むしろ「恵まれ過ぎた生活」がマイナスに働いたかも知れないと感ずるぐらいだったわけですが、ことメンタルのリフレッシュ面に関しては、反省点がありそうです。
おそらくサッカー協会にも岡田監督にも「遊びに行くんじゃないから」という考えが根っこにあったと思います。それは体育会系のスポーツ根性論の伝統から来る日本独特の潜在的心理がまだ色濃く残っていた時代でしたし、オフの与え方にそれが表れていました。またメンタルのリフレッシュについての知見の蓄積もなかったことでしょう。
川口選手が「ファミリーで応援してもらう、みたいなやり方は、日本のマスコミのあり方だと無理なんでしょうか。」と気の毒な心配をしていましたが、サッカー協会がメンタルヘルスの専門家と監督を交えて相談してリフレッシュプログラムを作り「日本代表のメンタルサポートをこのようにしてやります」とマスコミにも告知すれば済む話です。
また川口選手が「何よりいやだったのは、笑顔が消えてしまったことでした。笑うような精神状態じゃないんですね。」と振り返った部分も、うかつに笑顔を見せれば「にやけてる」とか「戦争のような大会に行ってるのに笑ってる場合じゃないだろ」という批判につながる日本独特の考え方が残っていて悩ましい限りです。
こうした心のリフレッシュ、メンタルの持ち方がフィジカルにも影響を与えたと、増島みどり氏の著書「ワールドカップフランス98 6月の軌跡」の中で、並木トレーナーが次のように述べています。
・並木麿去光アスレチックトレーナー
「トレーナーの立場で今回の反省といえば、古い言葉で悪いんですが、やはり『心技体』の『心』が足りなかったのではないかという点でしょうか。アルゼンチン戦を前にした頃から、選手たちの要求がだんだん子供じみてくるんですね。冗談を言っても、マジになる。目の前にある物を、それ取って、とか。岡田監督からの指令で、夜12時にはマッサージを終えるように、と一応決められていたんですが、それ以降にもこちらに向かって、マッサージが(並木さんの)仕事でしょ、とか。」
「精神的な疲労が肉体の疲労を招くという、典型的な例もありましたね。ゲーム中とてつもないストレスと戦っているうちに、それが疲労を呼んで思わぬ状態を引き起こす。アルゼンチン戦でも、そう熱くも湿度もないのに、秋田や中西がケイレンを起こしそうになった。」
「スポーツ界全体に言えることかもしれませんが、本当のリラックスをどういう形で得るのか、そういう大事な部分のケアがまだまだ十分ではないんですね。普段は何でもお金で片がつくわけです。ところが精神の安定というと非常に根本的な問題になる。だから対処できないんではないかと思う。サッカー強豪国でも必ず、メンタル面のケアをする立場の人はいますから。」
こうした心のリフレッシュ、メンタルの持ち方、ストレスがフィジカルに及ぼす影響などについて専門スタッフのもとでケアする体制は、この時はまだ、手つかずの領域だったようです。後年、この分野のサポートが当たり前になっいる歴史を、私たちは知っていますから。
ここまで「日本代表は、どう戦おうとしたのか、岡田監督のサッカーを検証」して、では「岡田監督が今大会で失敗した根本的な理由は何か」をえぐり出し、最後に「日本サッカー協会はどういうサポートをしてきたのか、してこなかったのか」を指摘してきました。
「フランスワールドカップ日本代表」の総括はひとまずこれぐらいにして、ここからは代表選手や帯同スタッフたちにとって、今回の「フランスワールドカップ」は何だったのか、選手・スタッフたちの「フランスワールドカップ」を記憶に留めて後世に伝えたいと思います。
日本サッカー史上、最初のワールドカップスコアラーとして歴史に名を刻んだ中山雅史選手、彼の心の中に刻まれた「フランスワールドカップ」とは
日本代表FW・中山雅史選手の「フランスワールドカップ」が、盟友「カズ・三浦知良選手」の離脱が起きたことによって、大きくメンタルを揺さぶられてしまったことは、すでに述べましたが、そうした不幸な出来事にも屈することなく、日本サッカー史上、最初のワールドカップスコアラーとして歴史に名を刻んだ栄光は、目に見える収穫がほとんどなかった今大会の日本代表にとって唯一といっていいほどの成果でした。
では中山雅史選手の心の中に刻まれた「フランスワールドカップ」とは、この歴史的なゴールだったのでしょうか。
すでに語り尽くされていることではありますが、中山選手は、5年前、1993年のアメリカワールドカップアジア最終予選で、井原正巳選手とともに「ドーハの悲劇」を経験した貴重な生き証人です。
その後、Jリーグで1994年に磐田が昇格後、その活躍を日本中の多くのファンが期待しましたが、しばらく怪我続きで鳴りを潜めていた時期が続きました。
1997年秋の「W杯アジア最終予選」も、初戦はテレビ中継のレポーターとして見ている側だったほどで、日本代表にはすっかりご無沙汰していましたが、岡田監督が指揮をとるようになった第8戦カザフスタン戦に招集されると、きっちり出場権獲得に貢献して、いわば日本代表の顔に戻ってきたのです。
中山選手は日本代表として戻ってくるまでの間、年齢を重ねても技の向上に対する飽くなき意欲を持ち続け、1997年夏から就任した磐田・山本昌邦コーチの指導に熱心に耳を傾け、貪欲に技を吸収しようとした努力がありました。
そして年が明けた今年、W杯による中断前まで12試合19ゴール、うち4試合連続ハットトリックという驚異的な数字を叩き出し、絶好調を維持したままフランスW杯に臨んだのです。
しかし、フランスW杯に向けた国内合宿のあたりから少しづつ調子が下降線に向きつつあった中で、盟友「カズ・三浦知良選手」を失った衝撃は大きく、そのメンタルはかなり傷ついたはずです。にもかかわらず、それを心にしまい込んで記録した「日本のワールドカップ得点第1号」は、中山選手の精神力の凄さの証明でしたが、それ以上にチームメイトも日本中のファンも驚嘆したのは、初ゴールの直後に骨折してしまっているにもかかわらずプレーを止めることなく試合終了ホイッスルが鳴るまでピッチに立ち続けていたことです。
このことも初ゴールと同様に永遠に日本サッカー史の中で語り継がれるに違いありませんし、ふだん、おちゃらけた振る舞いで周囲を明るくしてきた中山選手が、心の中に秘めていた闘魂とは、それほどまでに壮絶なものだったのかと、驚嘆させられます。
6月29日、戦いを終えて成田空港に着いた時は足の骨折によるギブスと松葉づえ姿でした。その代償と引き換えに、あの1点を得たのですが、中山選手の心に刻まれた「フランスワールドカップ」とは、その得点シーンではなく別のところにありました。
それは、前年夏から取り組んできた技の向上が実を結ぶまで、あとほんの少しだったプレーの感触だったのです。
またしてもサッカージャーナリスト・増島みどり氏の著書「ワールドカップフランス98 6月の軌跡」から引用させていただき、中山選手の心に刻まれた「フランスワールドカップ」を振り返ってみたいと思います。
クロアチア戦の前半33分「ヒデがボールを持った瞬間考えたのは、とにかくヒデから離れようということでした。」この時、中山選手はセンターラインのちょっち自陣側、斜め後ろの中田選手との距離は10mほどでした。
「そうしないと自分のマーク(相手DF)が動かないんでスペースができない。だから、彼(中田選手)から逃げる動きをしてDFを話そうと、そのことだけを考えて走り出したんですよ。それでハーフラインを越えた時に、右手からDFが自分に向かって走り込んできたこと、GKのポジション、全部がはっきりと見えたんです。それからパスが来るまで時間がすごくあって、何でだろう、多分本当の時間なんて1秒ぐらいのことなんだけどものすごく長く感じられた。」
「色々な手段を考えることができたんですよ、ああして、こうして、あれではダメだってね。不思議な時間でした。」
この時の時間を画像で実際確認してみると、中田選手がドリブルを始めてから中山選手にパスが届くまで約4秒ほどの時間がありました。瞬時の判断を繰り返している試合の中では、比較的いろいろなことを頭の中で判断できる時間だったのかもしれません。
「ヒデのパスはほとんど真後ろから追っかけてくるようなパスになるんで、これはまずどこで止めよう(トラップ)かと。最初はこの位置なら左足で止めて、と思ったんだけど、そうすると失敗した時ボールが左サイドに流れる可能性がある。じゃあ右足で止めて、すぐ打てる位置に落とすためには、って考えて、そうだ、右足のモモ、それもモモの外側だって決断して・・・本当にそのとおりに落とせたんですね。シュートも狙ったとおり、GKの左サイドを抜こうとした。本当にわずかな時間ですが、これ全部考えたんですよ。」
この話を聞いて思い出すのは、前年のアジア第3代表決定戦、いわゆるジョホールバルでの岡野雅行選手のプレーの話です。岡野選手は、延長前半12分と試合を決めた延長後半13分の二度、自分のプレーがまるでスローモーションのように鮮明に記憶に残る経験をしています。わずか数秒間のことであるはずなのに「こうしよう、こうすれば行ける」といった考えがはっきりと浮かんだ経験です。岡野選手はそれを「まるでスローモーションのように」と表現しましたが、中山選手は「すごく長く感じられた不思議な時間」と表現しました。話は続きます。
「すべて思いどおり、おそらく生涯もうできないかもしれないプレーでしたが、決められませんでしたね。後でビデオを見たら、GKの上にポンと浮かせて蹴っても良かったかもしれないし、逆にもっと右を狙っても良かったとは思いました。」
「でも、自分の判断と視野、技量からあれはあの時点の自分にとってベストのものだったと思うんで、むしろ後悔するとしたらコースのもんだいじゃあなくて、もっと思い切り打てば良かったかな、ということですね。GKの左手なんだから、弾いたボールに自分も含めて誰が詰められたかもしれない。それが悔しいです。」
「でも何がW杯だったかというなら、あのプレーしかない。自分では悔しくて・・・・。そうしたら名波が試合後、あんな難しいトラップをこの舞台でやるなんて、って言ってくれたんです。」
中山選手が「すべて思いどおり、おそらく生涯もうできないかもしれないプレーでしたが・・・」と心に刻み、それを同僚・名波選手が「あんな難しいトラップをこの舞台でやるなんて」と称賛したプレー、私たちも映像を通してではありますが、わずか4秒ぐらいの間に中山選手が、全力でゴール前に向かいながら、あれだけのことを瞬時に判断してシュートに結び付け、ゴールならず両手の拳でピッチを叩き悔しがったあのシーンを、ジャマイカ戦のワールドカップ初ゴールとともに永遠に記憶に留め語り継ぎたいと思います。
カズ落選のあと自分がFWの軸ということになったものの、本番のピッチで思うようにいかない中、見せた白い歯が心ないサポーターの逆鱗にふれ成田空港で「水かけ」の出迎えを受けた城彰二選手の「フランスワールドカップ」
城彰二選手は悲惨な体験をしました。自ら望んだわけでもないのにカズ・三浦知良選手の落選とともに「FWの軸は城」という立場を背負うことになって迎えた「フランスワールドカップ」
カズ・三浦知良選手の落選が、城彰二選手のメンタルにどう影響したかについては、すでに述べましたが、それでも何とか期待に応えなければと、もがきながら大会を迎えました。
突然訪れた立場に、以前望んでいた高揚感は失せてしまい、むしろ気負いがちにピッチに立ったものの、なかなか思うようにいかないプレー、時間だけがどんどん過ぎる中、焦りを鎮めようと考えたのが、できるだけ深刻そうな顔をせず、気持ちを楽にして、できれば笑顔さえ浮かべるようにすることと、リラックス効果のあるガムを意識的に噛むことでした。
しかし、一向にプレーが冴えない中でのその笑顔とガム噛みは「何やってんだよ、ガムなんか噛んで、にやけて」と心ないサポーターの逆鱗に触れることになってしまったのです。
その結果、大会を終えて帰国の途につき成田空港に到着した城彰二選手を待ち受けていたのは、大勢の出迎えのサポーターの中に潜んでいた狼藉者からの「水(清涼飲料水)かけ」という出迎えでした。
人垣の中から狼藉者の手がすっと伸びてきて、城選手が目の前を通り過ぎるのを見計らってペットボトルから水が放たれました。スーツを着た城選手の左ほほから肩口付近に水がかかりました。
それでも城選手は、少し顔をゆがめ手で拭き取ったものの、取り乱すことなく他の選手たちと歩調を合わせて進みました。しかし、それは「FWの軸は城⇒カズ外し⇒頼みの城の不出来」という結果を招いた岡田監督の責任を背負い込んだ洗礼だったのです。
かつて1993年秋のドーハの悲劇があった翌日、カズ・三浦知良選手が「日本に戻ったらトマトの洗礼が待っているかな」とサポーターからのキツイ出迎えを覚悟した時、国内から送られたスポーツ紙のFAXに「よくやった日本代表、感動をありがとう」という見出しが躍っているのを見て「これじゃダメなんだよぉ」つまり、サポーターがもっと日本代表を厳しく育てるぐらいじゃなければ強くはなれないんだと嘆慨してから4年、とうとう日本のサポーターもキツイ出迎えをする国になったのです。
しかも、その対象が4年前嘆慨したカズ・三浦知良選手に代わってFWの軸と期待された城彰二選手だったのですから、これも何かの巡り合わせと思わざるを得ませんし、城選手は自分のワールドカップでのパフォーマンスが批判を受けることを覚悟していたようで「仕方ないです」とコメントしました。必然的な通過儀礼だったのかも知れません。
城選手は帰国前、親しいジャーナリストに「俺、帰国したらすぐに言いたいセリフがあるんだ。『W杯で最高の体験をしてきました』」と語っていました。しかし成田空港での通過儀礼を受けた城選手は、その言葉を封印してしまいました。
栄光の3試合スタメンの先に待っていた屈辱の出迎え。城選手のW杯への挑戦はまたスタートラインに逆戻りしてしまいましたが、今度は海外で揉まれる経験を積んで「W杯で最高の体験をしてきました」と胸を張って言える日を目指すに違いありません。
前年のアジア最終予選の経験を経て一回りも二回りも成長したGK川口能活選手、3連敗の悔しさとともに「フランスワールドカップ」で得たもの
1996年のアトランタ五輪後に日本代表に招集され、それ以降、不動の守護神として日本のゴールマウスを守り続けてきた川口能活選手、GK枠3人、チーム最年長の小島伸幸選手、一つ年下の楢崎正剛選手とともにマリオGKコーチのもとワンチームを大切にしながらもレギュラーGKとしてチーム全体を鼓舞する役割も果たしてきました。
そんな川口選手にとって、3連敗に終わった今回の結果は悔しくもありつつ、信念をもってチーム全体を鼓舞し続けた自分の振る舞いに後悔はなかったようです。
NumberPLUS August1998で、金子達仁氏が、川口選手の「フランスワールドカップ」を次のように総括してもらっています。
「(クロアチア戦で)スーケルに点を取られた後、ディフェンダーがバタバタって倒れちゃったじゃないですか。(中略)やばい、チームが壊れるって。」
「(決勝トーナメントの夢が断たれて悔しい、倒れたくなる気持ちはわかるんですけど)俺たちにはまだあと1試合残ってた。3試合目でいい結果出して、3試合をトータルで評価してもらうしかない。1、2試合でできたことプラス、勝ちっていう結果を上乗せして、その上でフランスでの日本代表を評価してもらいたかった。」
「だから、チームが壊れちゃうような事態はなんとしても避けなきゃいけなかった。壊れてジャマイカにやられるようなことがあったら、3試合すべてが否定されてしまうような気がしたから。」
「(ジャマイカ戦のあと『他の国は死に物狂いで戦ってるけど、日本にはそういうものがない』と発言したことがマスコミから『みんな一生懸命やってるのに、一人だけそういうことを言うのは勘違いも甚だしい』って叩かれたけど)もちろん、みんな一生懸命やってくれてたのは間違いないですよ。だけど、必死さというか、死に物狂いさが感じられない時もあった。」
「それじゃダメだと思うんです。そうは見えないだろうけれど俺は必死にやってる、じゃなくて、誰が見ても必死さがわかるのがプロの必死だと思うから。」
「『フランスワールドカップ』で一番印象に残ったのは、何といっても日本のサポーターがいっぱい足を運んでくれたこと。ロッカールームから通路を出て、パッとスタジアムの様子が目に飛び込んできた時の感激は、たぶん、一生忘れないんじゃないかな」
この川口能活選手の総括を読むとグループリーグ敗退が決まっても、揺るぎないモチベーションを保ってジャマイカ戦に臨んでいた選手がいたんだということがわかります。川口選手はこうも言っています。
「ゴールキーパーっていうのは、ある意味観客と同じで、点を取ることに関しては、祈るしかない立場なんです。フランスでの3試合、俺はずっと祈ってた。」
もどかしかった気持ちが、ジャマイカ戦後のマスコミへのコメントになり「一人だけそういうことを言うのは勘違いも甚だしい」と叩かれてしまいました。
川口選手が「グループリーグ敗退が決まっても、3試合目でいい結果出して、日本代表を評価してもらいたかった。」こうモチベーションを保てたのはなぜか、を考えると、やはり、アトランタ五輪アジア最終予選、アトランタ五輪本大会、そして前年のW杯アジア最終予選と、不動の守護神として修羅場をくぐってきた経験値が思い当たります。
年齢こそ23歳と若いですが、その経験値は「決してあきらめない」という気持ちと「次のモチベーションを何におくか」という頭の切り換えを可能にする精神力を涵養したのだと思います。
惜しむらくは他のチームメイトとの関係性です。一つはGKというポジションの特殊性からくるチームメイトとの距離感、どうしてもDF同士、MF同士ほどの距離の近さは作れない関係性です。二つ目は「かなり暑苦しい男(ヤツ)、浮いてる男(ヤツ)」とみられがちなストイックな川口選手のキャラクターからくる関係性、三つ目は年代的な違いからくる距離感、これらの距離感によって、川口選手の思いがチームメイトに共感を得て共有されるまでに至らなかったのだと思います。ジャマイカ戦のあと川口選手は、ことのほか悔しさが募ったのでしょう。涙が止まらない様子でしたが、モチベーションがすっかり下がってしまった他のチームメイトとの差がそんなところにも表れたのかもしれません。なかなか世の中、うまく噛み合わないものです。
呂比須ワグナー選手の「フランスワールドカップ」
前年9月、呂比須ワグナー選手は、自身でも熱望していたブラジル国籍から日本国籍への帰化申請が認められ「日本人・呂比須ワグナー」となりました。
すると、さっそく当時の加茂監督が日本代表に招集、第3戦の韓国戦からスタメン出場を果たし、第4戦のカザフスタン戦、第5戦のウズベキスタン戦では0-1とリードされてW杯出場権がもはや絶望的になろうかという後半ロスタイム、井原選手からのロングフィードをヘッドで合わせて奇跡的な同点ゴール、そして第7戦の韓国戦でも2-0と突き放すゴールを決め、その決定力の高さを見せてくれました。
しかし、その後、呂比須ワグナー選手はブラジルのお母さんの病気容体が悪化するという報せを受けながら、あえて帰国せずに代表でプレーを続け、イランとの第3代表決定戦の前に訃報を受け取る悲しみをこらえて日本の初のワールドカップ出場という歴史的勝利に貢献しました。
日本人・呂比須ワグナー選手とブラジル人の血が流れるルーツとの狭間で心揺れ動く経験をしたわけですが、このフランスワールドカップでも、またしても日本人・呂比須ワグナー選手とブラジル人の血が流れるルーツとの狭間で心揺れ動く経験を強いられることになったのです。
それは初戦の相手がアルゼンチンだったためです。南米のサッカー大国同士の両国には、日本と韓国の複雑な両国関係から来るライバル意識以上の、強烈な意識があり、お互いのサポーターからの相手選手へのヤジ、罵りはもはや聞くに堪えない言葉が飛び交い、ピッチでの選手たちもレフェリーの見えないところで、格闘まがいの小競り合いが何度も繰り返される、まさにスタジアム全体が険悪になる間柄です。
呂比須ワグナー選手は、アルゼンチンとファイトできるブラジル人の血が流れていることを誇りに思いつつ、フェアな日本人・呂比須ワグナーとして試合できることを心待ちにしていました。ですからアルゼンチン戦のスタメンの構想から外されていると知った時の落胆は大きく「なぜ? どうして?」と答えの出ない自問自答を繰り返し一晩一睡もできなかったそうです。
そして、それは「呂比須ワグナーがスタメンではない」と知ったアルゼンチンにとっても驚きであり、意外だったようです。
サッカージャーナリスト・佐藤俊氏の著書「勇者の残像」(1998年11月リヨン社刊)には、そんなアルゼンチン側の呂比須ワグナー選手への警戒ぶりが次のように紹介されています。
「初戦(アルゼンチン戦)前日だった。日本の公開練習が終了し、ミックスゾーンの選手が一番最初に出てくる通路の前は、アルゼンチンのプレスを含めて多数の外国人プレスで賑わっていた。(中略)10人ほどの外国人プレスは、ブラジル生まれの日本人、呂比須ワグナーに大きな関心を示していた。(中略)」
「僕は、ブラジルでもイタリアでもない日本のひとりのストライカーに、なぜ彼らがこれほどまで興味を示し、なぜこれほどまで熱く語るのか正直言って理解できなかった。日本の2トップは城と中山である。彼らについて興味を示すならわかる。しかし、呂比須は、メンバーの中ではサブである。にもかかわらず彼らにとっては城や中山ではなく、呂比須なのだ。」
「ところがである。その謎は、オルフィーオ(エルモンド紙の記者)の一言で、簡単にクリアになった。」
「パサレラ(アルゼンチン代表監督)がロペスを警戒しているようなんだ。」
「パサレラは、(アルゼンチン代表の)キャンプ地ルトラで『日本で一番注意すべき選手は』という親しい記者の問いに『あのブラジル人』と、漏らしたというのだ。」
「W杯優勝国であり、日本は間違いなく勝ち点3を計算できる国である。選手個々の能力、経験、すべてに上回っているアルゼンチンにとって、基本的に負ける要素は見当たらない。あるとすれば満身からの油断だけだろう。」
「ただ、記者たちの話によると、アルゼンチンはコンディションが上がらず、パサレラは相当危機感を抱いていたという。(中略)そういう状況下で、パサレラは意図的に不安を搔き立てるように『呂比須』の名を口にしたのである。」
「パサレラの発言は、チームを刺激するためにブラジルの血が流れている呂比須の名前を使っただけなのか、それとも指揮官の第六感が呂比須のストライカーとしての危険な匂いを察知ししてそう言わしめたのか、その真意はわからない。」
「ただ、ブラジル人のいる日本をなめてかると痛い目にあうという危機感を選手に与え、日本との敗戦は予選突破の危機につながることを選手に知らしめたかったということは推測できる。」
「いずれにせよ、日本にブラジルの血が流れたストライカーがいることは、パサレラにとって無視できないことだった。アルゼンチンに対しての敵意を燃やし、完全と戦いを挑んでくるブラジル人と呂比須は同じ熱い血が流れているのだ。」
「石橋をたたいても渡らないと言われるほど慎重な彼が、そのストライカーに細心の注意を払うことはごく当たり前のことなのである。」
「(エルモンド紙の)オルフィーオ記者が、切り出した。『明日、ロペスは先発するのか?』、『先発ではない、サブとして途中出場することになるだろう。』」
「彼ら(記者たち)は、相手国の指揮官からおそらく最高の評価を受けて最も警戒されている選手を使わないということが理解できないようだった。特にオルフィーオ記者は、呂比須の起用が心理的に相手にプレッシャーをかけ、日本が有利に展開するための第一条件であると考えているようだった。」
「『本当か? 彼は、他のFWと比較して監督の信頼を得ていないのか?』」
「信頼されていないなら、メンバーに選ばれていない。それに使うか使わないかは戦術的なことでもあり、力がないとかそういう問題じゃないんだ。」
「『それで勝てると思うか? 』」
「『簡単に勝てるとは思っていないし、簡単に負けるとも思っていない。日本はこの日のためにコンディションを整えてきているから、アルゼンチンも相当苦しむはず』」
(中略)
「日本は、初戦を飾ることができなかった。(中略)」
「イタリアのアレサンドロ記者が『得点の予感を感じさせたのはロペスが出てきた数分だけだったとは、皮肉なもんだよ。しかし、なぜ日本はロペスを90分使わないんだ。』」
「おそらく、彼は見抜いたのだろう。呂比須はFWの中で飛びぬけて高い技術を持ち、ゴールへの姿勢も泥臭いとはいえ、一番感じることを・・・・。」
「僕は、岡田監督が城を『FWの柱』として考えていたこと、そして中山と城とは違うタイプのFWで、2人のタイプの異なるFWを起用することで相乗効果を狙っていたことなどを話した。」
「『でも、それはあいにくだな』」
「アレサンドロは、皮肉っぽくそう言った。彼は、そういった『形』と捉われて組み合わせばかりをあれこれ思案することよりも、能力のあるFWを前線に置くことのほうが重要だと言った。」
「日本のストライカーが1人で点を取れるようなズバ抜けた能力を持っているならば彼の言うことは正論である。しかし、日本は個人能力では対抗できないので相性のよさと組み合わせで対抗するしかなかった。」
「僕の言葉に、彼は腕を組みながら黙って耳を傾けた。そして長い沈黙が流れたのち」
「『ロペスだ』」
(中略)
「すべてのインタビューが終わり、ミックスゾーンの中央で日本の記者と話をしていると、昨日のように彼らが集まってきた。」
「クロアチアのレイッチ記者は、白髪混じりの頭を搔きながら、そうだなぁと余裕の表情を見せて日本を分析し始めた。(中略)」
「僕は、少し意地悪く聞いてみた。」
「『クロアチアは、当然(日本に)勝つ自信があるんだろう?』」
「彼は自信たっぷりに言った。『フフ、シュケルは止められないだろうね。彼は、日本にはいないイヤなタイプ、つまり点を取る優秀なストライカーだからね。ただ、ロペスが先発で出てきたらおもしろくなるんじゃないか』」
「(エルモンド紙の)オルフィーオ記者が『その通り』と相づちを打った。」
「『先ほど、ロペスと話をしたが彼はやはり普通の日本人のメンタリティとは違う。自分を使ってくれればゴールを奪う自信はあるし、勝つために活躍する自信はあるとはっきり口に出して言うブラジル人気質の人間だ。今日も後半が始まる前から出たくて出たくて仕方がなかった。自分をアピールすることをあまり美徳とせず、謙虚に支持に従うのが日本的風習というのならば、彼こそその静寂な輪の中に入れて、彼の闘志を日本の選手は肌で感じるべきだろう。その時に日本の選手が発奮すれば、(決勝)トーナメント進出の目は、まだある。しかし、所詮、俺たちと彼(ロペス)は違うというふうに冷めたり投げたりしたら、救いはないだろうね。でも、そういうのを必要としてオカダはロペスを起用しているんだろう? ならばもっと早く(ロペス)を入れるべきだと、私は思う。しかし、今日の(アルゼンチン戦の)結果には少々ガッカリしたよ。日本はもっとやれるはずだと思っていたから』」(中略)
「イタリアのベネラット記者は、僕が黙って聞いていると低い声で、ロペスはおもしろいと切り出した。」
「『私もロペスを評価している。彼はワガママで自己陶酔的だが、FWは、そのぐらいでないと務まらない。ロペスひとりのために10人が自己犠牲を払ってもいいと思うぐらいだ。残りの10人は彼だけのためにお膳立てをしても問題はない。彼が点を取れば勝てるのだ。日本はゴールへの攻撃パターンが少ないから、そのぐらい徹してたほうがうまくいくんじゃないか。ユーは、日本は全員で攻めないとゴールは奪えないと言ったが、彼ならロナウドにもバティにもなれる感じがしたよ』」
「中田や川口はともかく、思った以上に呂比須の評価が高かったことは、大きな驚きだった。出場した時間はわずかに25分だが、彼らはすでに呂比須の特徴とその能力を見抜いていたのである。」
「しかし、呂比須をまるで海外クラブチームの助っ人のように思っているのには、多少違和感を覚えた。彼らは、呂比須を含め日本というチームをまだ完全に理解していないようだった。」
(私は言った)「『ロペスは、確かに能力の高い選手だが、ベネラット記者が言うようなプレーは難しいだろうね。(中略)ただゴールだけを狙うというプレーは許されないんだよ。彼は、チームの中では他の選手と同じように好守に動き続けなければならないし、常に与えられた役割を果たさなければならない。それは決して個人を殺すというのではなく、そうしないと個人能力に劣る日本は世界を相手に戦えないからなんだ。日本というチームは、選手11人全員が自己犠牲をもって共通の目的を完遂しようとした時に、組織的にまとまってプレーできた時に力を発揮する、そういうチームなんだ。』」
「『そういうのが問題なんだよ』 (エルモンド紙の)オルフィーオ記者は、冷たく言い放った。そして続けた。」
「『日本は、よく戦った。それに、よく訓練されている。しかし、選手はそれ(戦術)にこだわり続けている。それじゃ勝てない。サッカーは、そうした形の上に創造性というプラスアルファがないと勝てない。いいゲームをすることと勝つことは別だからな。真面目すぎるような気がするよ、日本人は。日本のサッカーが画一的で単調な理由は、そういう国民性の問題なのか? ただ、ロペスだけは、いい意味でそれを打ち破ろうとしていた。オカダが言うには、日本は全員守備で全員攻撃だが、彼だけは攻撃に専念していた。ユーはどう思う?』」
「彼の言うことは理解できないことではなかった。むしろ、わかりきった当たり前のことである。しかし、日本は当たり前のことをしないのではない。できなかったのだ。守備に多くの時間を取られ、攻撃もカウンターだけに絞って練習してきた日本は「型」を失うと切れた凧のように右往左往してしまった。自分たちの型を失った時、自発的かつ能動的な攻撃を組み立てられるほどチームも個人も熟成していないのである。オルフィーオ(記者)が指摘したことは、常に日本が課題としてきたことだった。」
このあと佐藤俊氏は、日本が、真面目な国民性を生かしたサッカーでアルゼンチンに挑み、そこそこ戦えたのであり、結果負けたことを選手は本気で悔しがった。しかし、いまの日本の実力はそこまでであり、プロ化して6年、初めてのW杯、経験も歴史もないこれからの国なんだ、と日本サッカーの現実を話すと、記者たちは「イエス」口を揃え「なるほどそうかもしれない」と頷いたそうです。つまり、彼らは、日本がまるで何度もW杯に参加しているような錯覚で話をしていたところから目が覚めたという表情だったのです。
佐藤俊氏の、この外国人記者たちとの会話は、私たちをワールドカップの取材現場にいるかのような疑似体験をさせてくれました。
佐藤俊氏は、
・思った以上に呂比須の評価が高かったことは、大きな驚きだったこと。
・日本が、選手11人全員が自己犠牲をもって共通の目的を完遂しようとした時に力を発揮するチームだと話したことに対して、「そういうのが問題なんだよ」と冷たく言われたこと。
・しかし、問題であることは百も承知であり、まだまだ日本はこれからの国であることを理解してもらうしかなかったこと。
等々の会話を真正面から海外の複数の記者たちと交わしたのです。いわばサッカーの本場ともいえる海外の記者たちと、こうした濃密な会話ができるのはライター(記者)冥利に尽きるというものです。
話を「呂比須ワグナー選手の『フランスワールドカップ』」に戻せば、呂比須ワグナー選手もまた、カズ・三浦知良選手同様、岡田監督のもとでフランスワールドカップを戦うことになったことで、そのプロセスで起きることも含めてすべてを受け入れざるを得ない運命(さだめ)にあったとしか言いようがありません。
海外の記者たちが、いくら呂比須ワグナー選手を高く評価していたとしても、そう簡単に「やっぱりそうか」と同調する気にはなれませんが、ブラジル人の血が流れている呂比須ワグナー選手、そこから来る呂比須ワグナー選手のメンタリティに、僅かであっても希望を託してみたかったという気持ちはぬぐい切れません。
呂比須ワグナー選手自身も、そこに賭けて欲しかったという気持ちだった故に、不完全燃焼の「フランスワールドカップ」であったことは疑いようもありません。
出場機会を得られなかった選手たちにとっての「フランスワールドカップ」
今回のフランスワールドカップ、22人の登録メンバーの中でまったく出場機会がなかった選手が5人います。GKの小島伸幸選手、楢崎正剛選手、DFの斉藤俊秀選手、DF服部年宏選手、MFの伊東輝悦選手です。
ここまで、たびたび引用させていただいているサッカージャーナリスト・増島みどり氏の著書「ワールドカップフランス98 6月の軌跡」で、増島氏はこれら5人の選手にもインタビューして、彼らにとっての「フランスワールドカップ」は何だったのか語ってもらっています。
貴重な記録です。永遠に語り継ぎたい記録です。以下全員ではありませんが、引用させていただきます。
GK・小島伸幸選手にとっての「フランスワールドカップ」
その経験は、6月21日、クロアチア戦の翌日、ベースキャンプ地のエクスレバンで、控え組による地元クラブとの練習試合
「今回のW杯で、オレにとってはあの試合がすべてだった。誰も覚えてもいないぐらいの練習試合にすぎないんだけど、自分としては、あの試合で最高にして最大の収穫を得たんでね。」「試合開始直後だったか、向こう(フランス3部リーグの混成チーム、ビル・ブランシェ)のキーパーがケガで倒れてしまって、交代がいなかったんですね。そうしたら、岡田監督がものすごく申し訳なさそうな顔してオレに言うわけですよ、『小島、悪いんだけど・・・・向こうへ入ってくれるか』と。『そんなの気にしないでください』そう言ってね。その時点でオレは、ヨシカツ(川口)、ナラ(楢崎)の次、つまり3番手なわけですから。それが現実で、岡田さんに気を使ってもらうことじゃあないないと思った。」
「向こうの選手と軽く打ち合わせをして、って言ったって、フランス語なんてわからんし、もう適当適当。上がれはアップ、右はライト、左はレフト、そのくらい。いい加減なもんですよ。でも試合に集中し始めると、あることに気がつきましたね。あれ、この人たちアマチュアなのにサッカーに意図があるんだってこと。3部ですからやり方なんて別に関係ないって思っていたら、ところがどっこい、ちゃんと意図を持っている。」
「ただし、その意図に対して、体がついて行っていないからうまく行かないに過ぎないんでね。確か、日本は点取られてますよ。大会期間中はテレビ中継を見てましたから、フランス(代表)のサッカーももちろん観察していました。3部のクラブチームに過ぎないんだけど、なぜかフランス代表にも通じるんですよね。ボールの出し方とかさばき方、サイドへの展開、最後方から見ていて、ほらそっちだろ、こっちだろって、全部つながるんです。あれは本当に
新鮮な驚きでした。3部アマなのに、代表とベーシックな戦術がほぼ等しい。というか、同じベクトルに向かっているんですよ、サッカーが。」
「最後方から声を出していて、それに対するDFのリアクションなんかも素晴らしいものがある。コーチングへの反応ですね。試合をしていて、フランスのサッカーの奥行き、というか、伝統というか、とにかく強いはずだわ、って思っていましたね。あれで、もっともっとフィジカルを作って、技のレベルが上がって、コンディショニングをいれると、それが代表のあるべき姿で、彼らはその姿のもっとも原初的な部分なんですね。でも、太い脈でつながっている。どこかの知らないチームがポッと出て来て日本とやってるわけじゃあなかった。」
「日本では、といえば、別にそれがいい悪いではなくて、Jリーグだって、獲得している外国人選手や監督によって、やることが全然違うわけですよ。もうベクトルからして。高校生、アマチュアなんでもう代表とは何の関係もない。そういう中でやっているわけじゃないですか。代表だって、ブラジル人がやった時、日本の監督の時、それぞれに選ぶメンバー以上にやり方が違う。華やかな戦術はあっても、張り子のトラ、みたいなところがあるんじゃなかろうか、と。これが『サッカーにおける伝統』ってことなのか、と。それには本当に新鮮な驚きを感じました。」
「あれほどのことが勉強できるとは思ってもみませんでしたし、もし自分が代表のサブじゃなかったら、相手方の助っ人にならなかった、ああいうふうに、彼らの後ろからそれらを感じ取ることは絶対にできなかったと思うんです。(中略)」
「ええ本当に、すばらしい収穫の・・・・一応、私にとっての『Aマッチ』ということにしておきましょう。」
おそらく聞き手の増島さんも、いい話が聞けたと充実感を覚えたのではないかと想像します。出場機会のなかった選手から、これほど含蓄のある、後世の日本サッカー界もずっと考えていかなければならない「日本サッカーをどうやって作り上げ伝統にしていくか」というテーマに触れる話が聞けたのですから。
小島選手自身が語っていたように、この経験は、例えば指導者として海外に短期留学して、仮に同じシチュエーションの体験をしたからといって味わえるものではないのかも知れません。小島選手が、たまたま助っ人として何の予備知識も持たずに、いわば無心の状態で飛び込んだ試合体験をしたからこそ得られた「新鮮な驚き」だったのかもしれません。そう思いながら記録に残し記憶に留めたいと思います。
GK・楢崎正剛選手にとっての「フランスワールドカップ」
小島伸幸選手が、6月21日、控え組による地元クラブとの練習試合で相手チームの助っ人GKに入ったことについて、
「あのとき、自分も『ああ、ノブさん、この人、すごい人なんだ。もし、あれが自分だったら』って、そりゃあ思いましたよ。最終戦前の最後の対外試合でしょう。そんな時に相手のGKとして入れ、なんて、普通だったらあんなこと気持ちよくできないんと違いますか。自分はそう思いましたね。最後のところに来て、小島さんのすごい人間性と言うか、GKとして尊敬できる人だと改めて確認したような日でした。本当の意味で強い人だ、、そう思いました。」
「試合に出るからとか、出られないからとかではなくて、GKとしてやらなくてはならないのは、たとえ誰がピッチに立つんであっても、何があってもすぐにベストで出られる、そういうコンディションを維持することなんだと思う。今回、マリオ(GKコーチ)は、そうやってぼくらがいつでも100%の力を出し切って準備できるように、フィジカルもメンタルも、維持してくれたんですね。」
「休みがなかったんですが、マリオには、疲れているなら疲れているとはっきり言え、と言われていました。でもねえ、ハイ疲れましたなんて、そうそう言えるもんじゃないし、GK三人はよく練習しましたよ。マリオの足(右足)、あれだけ蹴っているわけだから、当然おかしくなるわけで、ぼくら三人は気がついていましたよ。明らかに足の状態がおかしいと。かなり痛んでたんではないかと、とね。でも、そういうことをいちいち口にしたりしなくても済むような、お互いを信頼できる関係にはあったと思っています。マリオがそれを知られないように隠しているから、こちらも知らないフリをする・・・・・暗黙の了解というんでしょうか。」
楢崎正剛選手は、代表選手の中で若い方から数えて2~3番目の若さですが、成熟した大人の風格さえ感じる話です。GK三人の、他のポジションとは違った特殊なグループ、しかも二人は出場機会がまったくない特異なグループがギスギスしないで乗り切れたのは、小島選手、楢崎選手がメンバーであったからこそ、とあらためて実感します。
DF・斉藤俊秀選手にとっての「フランスワールドカップ」
5月下旬のキリンカップの段階では、日本のDF陣は3バックの井原正巳選手、秋田豊選手は固まっていたものの、残る一人は小村徳男選手、斉藤俊秀選手、中西永輔選手の3人から岡田監督が誰を選ぶか決めかねていました。そのままスイス・ニヨンに入り最初のテストマッチ・メキシコ戦で岡田監督は3人の中から中西永輔選手をスタメンに起用しました。
「今回の遠征での変わり目はやはり、5月31日のメキシコ戦でしょうか。キリンカップでは自分もやれていたし、3バックは清水でやっていることもあったから、非常に組みやすかった。みなさんからは、ぼくは井原さんのバックアッププレーヤーというふうに見られているけれど、自分では必ずしもそういう認識ではないんです。ですからメキシコ戦まで来て、先発が永輔だったとき、正直言ってショックでした。ああ自分ではなかった、という。それをマイナス面でひきずることは全然なかった。」
「翌日6月1日、サブ組だけの練習試合があって、翌日井原さんがケガをして3日のユーゴ戦に(3バックの真ん中を任されて)フル出場して、7日の(サブ組によるフランス3部チームとの)練習試合と、3試合ほぼフル出場でしたね。でも(7日間で3試合でしたが)フィジカルではあまりキツくはなかったんですよ。試合をやれているという充実感もあったし、本番には出られなくてもむしろ、自分のサッカーに挑戦する意味もありました。(中略)あの1週間の3試合の経験は、気持ちの整理をつける意味でもよかったんです。」
「(日本の3試合の中で)一番印象に残ったのは、クロアチア戦でしょうか。あの試合は外から見ていてつくづく『ああ、90分の中でメンタルゲームをやられているなあ』と感じました。」
「あの日の前半のスーケルのジェスチャーなどを見ていると、どう見ても日本の守備は勝っていた。彼が味方のパスにイライラして、手を広げて『やってらんないよ』みたいな仕草をしていたんですね。ですから、ああこっちの術中に見事にはまっているな、と見ていたわけです。」
「後半も、スーケルをマークしていた永輔(中西)もよく耐えていて、もう32分、これで凌いで・・・・と思いきや、なんですね。あそこでゴールまで持っていかれるとは、やはりあのクラスのしぶとさを感じました。何故やられてしまったのか、あえて考えると、頭の中で考える材料の多さといいますか、情報処理能力の違いを感じた気がします。ぼくらも一応はコンピューターなんですけど、アルゼンチンやクロアチア、ブラジルクラスになってくると、もうスーパーコンピューターですね。」
DF・服部年宏選手にとっての「フランスワールドカップ」
「(3人の落選発表を翌日に控えた)6月1日の夜は、よく眠りましたね。もう考えても仕方ないって思っていましたから。(中略)夜中のホテル全体は静かなんだけど、慌ただしい、そんなムードだなと感じてました。結果的に自分は残りました。残ったけれども、その後のこともまた、これまで経験したことの内容な厳しいことの連続だったんで、まあ勉強、勉強の遠征になったわけです。」
「キリンカップの時ですね、自分が使われる形というのは、1点取って先行した時に中盤を固める、そういう役割でしょう。サブで出番を待つということ、これは思っていました。だから今回ほど点を入れて欲しいって思ったことはありませんでしたよ。それしか出る道がないと思っていたから。(中略)」
「3試合見たといっても、全然(これがワールドカップなんだ、という)実感がない。ハーフタイムで練習していても全然ワールドカップじゃない。普段と同じなんです。何なんでしょうね。あの不思議な感覚って。」
MF・伊東輝悦選手にとっての「フランスワールドカップ」
「(自分の出番の可能性を考えた時)クロアチア戦のあと、(ジャマイカ戦に向けて)メンバーを少し替えて、システムも4バックで行くのな、とも考えたけれど、6月21日の練習試合でメンバーもシステムも変更ないことがわかった。(中略)だから、あの練習試合ではちょっと気持ちがね、切れてはいないけど、がっかりしたかな。あー、もうチャンスないってね。」
「モチベーションの差については、人それぞれだと思うけれど、でも今回、自分はいいレベルをキープできたとは思ってる。サブだからなんて言って、自分の持ち分を忘れるようなことになると、モチベーションが下がる。それはあくまで自分の問題だからね、そこはそこで勝負をしていないとだめだから。今回の遠征でもそこだけはちゃんと考えてはいた。」
「あそこできちんとやっていないと、リーグに戻ってから良くない状態になるだろうとも考えた。(中略)」
「大会が始まってからは、試合を観るのが結構楽しみになっていた。オランダなんかは初戦を見て、ああ久々にかなり上のほうまで行くんじゃないかって思ってた。(注・オランダは準決勝進出)」
「大会が始まる前にも、ビデオでスペインのリーグ戦だったかな、これも面白く観た。自分はどちらかというと、ワールドカップの舞台に立ちたいという気持ちよりも、むしろ、海外の、スペインとかのリーグでピッチに立ちたい、そう考えているんでね。」
ここまで出場機会がなかった5人の選手の「フランスワールドカップ」をサッカージャーナリスト・増島みどり氏の著書「ワールドカップフランス98 6月の軌跡」から引用させていただく形でご紹介しました。5人とも、もっといろいろなことを語っており、増島氏がサブタイトルをつけたエピソードの部分とは異なる部分を紹介した選手もあります。
当方が引用させていただく際に注目したのは、代表選手クラスになれば、誰しもが持っている矜持、いわばプライドの部分と、まったく出番のない現実との折り合いをどうつけたのかという部分でした。
やはり、どの選手も自分なりにキチンと折り合いをつけて大会を終えたわけですが、5人5様、それぞれが違う形で折り合いをつけていることを知り感銘を受けました。一般的なフランスワールドカップの記録では、出場機会がなかった選手たちの胸を内を知ることができる記録は限られています。
今回、あえて5人全員の思いを記録して、長く後世に伝えることは、今回の取り組みの使命の一つだと考えています。
帯同スタッフたちが経験した「フランスワールドカップ」
すでにご紹介しているように、日本サッカー界初のワールドカップ挑戦にあたり日本サッカー協会は日本代表のサポート体制を、これまでにない量と質を備えて敷きました。すでにアトランタ五輪のころから、サポート体制の巧拙がチームの成果を大きく左右するとの経験値を得ていたこともあり、日本サッカー協会のサポート体制は選手たちも驚くほどの手厚さでした。
それは、2002年日韓W杯に向けてのシュミレーションにもなるとの思惑から、意識的になされた面もあって、やや過剰感を感じさせるほどの分野もあったようです。
サッカージャーナリスト・増島みどり氏の著書「ワールドカップフランス98 6月の軌跡」は、このサポート体制を担った帯同スタッフが経験した「フランスワールドカップ」にも焦点が当たっており、貴重な記録ですので、いくつかご紹介します。
福林 徹チームドクター
「中山(雅史選手)が(ジャマイカ戦の後半31分)ケガをした瞬間、彼はそう倒れたりする選手ではないですから、やはりひざだと思っていました。当初から『爆弾』とまではいかないまでも、ひざの件(半月板損傷)がメディカルスタッフの懸念事項にはなっていましたんでね。」
「ですから、徳さん(徳弘豊トレーナー)と慌てて走って行ったけれども、線審に制止されたままピッチの中には入れてもらえなかった。そうこうしているうちに、ゴンは立ち上がってしまったんですね。歩いていたし、これは大丈夫かな、と思ったんですけど・・・・。」
「でも、状況(1-2とリードされている状況)から言っても、メンバーから考えても、交代は難しかったんでしょう。結局代わらぬまま、骨折した人間話走らせてしまう事態になってしまった。(中略)個人として非常に悔いの残る場面になってしまった。」
「ゴンと二人で診察室でレントゲンを見て『骨にヒビが入ってるね』と言うと、ゴンは『折れていると聞いちゃ、もう歩けませんよ』って。そうですよ、骨折して走っていたなんて、いかに気持ちで持ちこたえていたか、それを思うと辛かったですね。」
(中略)
「今回、初出場でも、メデカルを含めサポートはかなり充実していました。次は、選手とコーチとの間で、メンタルを含めてどういうケアができるのか、一方通行から両面通行という形ですね。海外の強豪国では、代表専属ドクターを置くなど、体調管理は基本として確立されているようです。代表の医療システムについても理想に近づくために、この初出場を機に協会と検討していけたらと思います。」
田中博明アスレチックトレーナー
「(クロアチア戦が終わってからジャマイカ戦までの)あの1週間は、何かおかしな1週間でしたね。選手を見ていてどうにも勝てる気がしなかった。モチベーションということなんだけれども、クロアチア戦で落ちてしまって、全然上がって来ない。『おいおい、お前さんたちどうしちゃったんだい?』そんな感じだったね。」
「昨年のジョホールバルの時のチームは物凄かった。追い込まれて追い込まれて、土壇場で夢を実現させた彼らの目っていうのかな、形相が死に物狂いで、これで負けたらもうサッカーはできないっていうぐらいのもんだった。(中略)」
「W杯に行こう、というところまでは本当にすばらしかった。でも自分たちスタッフの役割も含めて、そこから後どうするのか、さあ一段階上がったけれどその次をどうするのか、そこには何もなかったんではないかと思う。ほかの国は、といえば、行ってからのことを知り尽くしていて準備していたわけで、そこには大きな違いがありましたね。」
「もっとじっくり、どういう大会でどうしなくてはならないか、腰を据えて考えなくてはならなかった。」
「そういう様々な経験不足が一気に出て来たのが、ジャマイカ戦の前だったんじゃないかね。自分も含めて、初の1勝をもぎとりに行く、そういう戦う集団ではなくなっていたとぼくと思いましたね。(中略)」
「2002年に向けて、単にピッチでの戦い方だけじゃなくて、こういったスタッフのことも継続して検討して欲しいですね。でないと無駄になってしまう。スタッフの多くは会社員や自営業で、2か月も本来の仕事を空けて代表に付いていたわけで、戻ってからは苦しいですよ、本当に。だからこそあの経験を生かしたいんでね。あらゆる意味において、代表スタッフのあり方、それはものすごく大切なことなんです。」
野呂幸一シェフ
「アルゼンチン戦の前は、見送りのとき(選手たちに)「行ってらっしゃい」と声をかけても無言で緊張していたようですが、試合後は(選手たちの様子は)随分と自信が出て来たというか、上り調子な感じでした。ですからそれを見て、ここからが勝負だぞ、と自分を叱咤して乗り切ったということでしょうか。代表の遠征では間違いなく体重も減りますが、今回の遠征では、肉体的にというより精神的に気を張り詰めていたんだと思います。」
「やはりもし一度でも食中毒を起こしてしまったら、ということですね。すべてが一瞬で終わってしまいますから。(中略)」
「食中毒もなく、無事にすべてが終わって東京魚国(野呂シェフの所属会社)の本社に挨拶に行った日、心臓が苦しくて動けなくなりました。役員室ですみませんと、横になって・・・・あの時、フランスでいかに張り詰めていたのかを実感しましたね。(中略)」
「(日本代表の結果は)3敗でしたが、私は日本代表は本当によくやったと、心から思っています。帰国してから自宅近くのすし屋で飲んでいると、周りのお客さん全員が評論家と化して『よくやった、じゃダメだ』なんてね。評論家になって何かを言うのは簡単だよ、って心の中でつぶやくこともありました。自分がわかっていりゃあいいんですから。でも彼らとともに過ごせたこと、少しでも手伝えたことは誇りです。」
「エクスレバンを出る日、選手を送り出してから残っていたスタッフのみなさんとTGV(フランス版新幹線)に乗り込んでパリに移動しました。しばらくしたら、ああ本当に無事に終わったと胸が一杯になり、ワインとビールで乾杯をしました。車窓に流れるフランスの景色を眺めながらみなさんと飲んだ、あの一杯が忘れられません。」
浦上千晶栄養士
「今回の遠征中はとにかく物理的に忙しい毎日でした。ニヨン、エクスレバンと2か所の移動でホテルが変わりましたし、そのほか、トゥールーズ、ナント、リヨンと合計5つのホテルで調理と食事を準備しなければいれない。その度に一から手順を作り直しますから、本当に忙しかった。96年からずっと代表で栄養の仕事をさせてもらってきましたが、さすがに今回ばかりは、私のカンピューターも途中から煙を吹き出してしまいましたね。」
「でも、あの日、フラビオコーチが私に向かって”You should go to stroll”(散歩に行きましょう)と、促してくれて・・・・。彼だってきっととても疲れていただろうし、もちろん忙しいのに、気を使ってくれたんだな、と思うと本当にありがたかったですね。出かけるといっても、ただホテルの周りを二人で雑談して歩くぐらいで終わりましたけれど、でも、あれは本当に気分転換になりました。」
「あの散歩のおかげで、怒涛のように流れていくW杯から一瞬離れ、どこかホッとすることができました。何か重要な事件が起きたという日ではないのですが、後から思うととても印象深い日でした。」
「加茂前監督の時から3年かかわって、途中、こういうポジションは不必要ではないか、悩んでそう話したこともあります。でも今回、サポートに加えてくださった。感謝してますし、将来こういったサポートが必要ならば喜んで経験を伝えたいです。」
「最後のメニュー?・・・・いいえ、パリに移動した6月27日の昼食ではありません。私は決勝トーナメントに行くつもりで、まだあと10日分のメニューを作っていました。」
寺本一博エキップメント(アシックス)
「日本からアムステルダム経由でリヨン・サトラス空港に到着する日本代表ユニフォーム類を受け取りに行くという作業がありました。緊張しましたね、ちゃんと着いてくれたか、問題なく(荷物検査を通過して)こっちに出てくるか。いろいろ考えました。」
「いざ到着して、荷物が出終わったら、はい持っていって下さいという感じで、実にあっけなく手元に届きました。ダンボールを数えたら250個ありました。エーッこんなに、という感じでした。」
「トラックに積んで、サトラス空港からエクスレバンに戻ろうとする頃は、もう夜中でした。高速なんかは電灯もなく真っ暗じゃありませんか。代表チーム専属のドライバーさんは運転はうまいんですが、帰りを急ぐため、えらく飛ばすわけです。真っ暗なのにスピードがどんどん出るし、あれは怖かったですね。一瞬考えましたよ、もしこの車で事故ったらユニフォームはどうなるんか、って。ドライバーさんに、もっとゆっくり、と引きつった顔して頼みましたよ。エクスレバンに着いて、遅くまで待っていてくれた麻生ちゃん(代表エキップメント)の顔を見た時は、本当にほっとしました。」
「選手にも衣類や道具に対して色々なこだわりもあって、それは代表では大切なことです。(中略)呂比須さんの海水パンツの件では、選手のこだわりっていうことについて勉強になりましたね。それはなくなったお母さんの形見だそうで、試合の時はそれをはかなくちゃダメなんですね。もちろんそのことはちゃんと分かっているから、会場に持っていくのは重要なチェック項目ですけど、横浜での壮行試合だったと思いますが、あの時は忘れてしまって・・・・。呂比須さんもぼくらも慌てました。麻生ちゃんと携帯で連絡を取りながらぼくがホテルに戻って部屋を探して、パンツ握りしめてまた競技場に戻って大慌てしました。海パンひとつで、と思われるかもしれませんけれど、選手にとってはそれは大事なことなんですね。」
ここまで、サッカージャーナリスト・増島みどり氏の著書「ワールドカップフランス98 6月の軌跡」に収録されている監督・選手・スタッフのインタビューから、多くを引用させていただき、今回の日本代表にとっての「フランスワールドカップ」の実相に迫ってきましたが、増島みどり氏自身が、この一冊にまとめたいと突き動かされた思いそのそものが、同書の「はじめに」の部分で語られています。
その志を多として、抜粋ではありますが記録し、後世に語り継ぎたいと思います。
「代表チームとともに帰国し、手元に残った5冊の取材ノートを見ながら、あの長く、一方で夢のように過ぎてしまった時間のほとんどについて、実は、結論や答えがそのまま手つかずに放り出されているのだと感じた。」
「『結局は、結果が出なかったことがすべてだ』と言い切ってしまう前に、自分自身が一体、日本代表の何を知り、何を知らずに、何を読み手に伝えていたのだろうかと思うと、まったく釈然としなかった。」
「3敗ということではなく270分を、欲を言うならスイスに出発してからの34日間を知りたかった。」
「ピッチに立った選手だけなく、この遠征に参加した選手全員の声を聞きたかった。」
「選手、監督、コーチだけではなく、エキップ、トレーナー、ドクター、栄養士・・・・できるだけ多くのスタッフの話を知りたかった。」
「かれらがどんなことを考えも何をやり遂げ、何ができずに終わったのか、何が足りていて何が足りなかったのか。それをただ外から見ているだけではなく、彼ら自身の言葉で表現してもらおうと考えた。」
「一見どうでもいいようなディテールと、過去にこだわることによって、何も起こらなかったように見えた日々が、立体的になってくるのではないか。」
「取材ノートと、ほぼ毎日つけていた日記のようなメモを見ながら、選手には帰国した後記憶を熟成してなお、胸を締め付けられるようなシーン、言葉、事件、風景、そういったのを話してもらい、インタビューはそのディテールを入口に、全体像に広げていくという手法で行なうことにした。」
「それによって何もないように見えていた日々が、選手にとって非常に大きな意味を持っていたことが鮮明になり、同時に、全体像も描けるようになるのではと考えた。」
「一人わずか2時間前後のインタビューで、彼らの考えが忠実に再現できたというなら、それは傲慢というものだろう。彼らが振り絞ってくれた一言一言すべてを文字にできたわけでもない。」
「しかし、多くの選手が沈黙を破ってくれた重みを何としても大切にしたかった。取材中、選手の誰一人として『結果はでなかったけれど、満足している』と答えたものはいない。」
「彼らは、言葉で何かを語ってはならないプロの『掟』を理解し、実践している。それが、彼らの多くが帰国して以来沈黙を守り続けた理由である。」
「しかし、結果はすべてて、であり、すべてではない。プロには、結果かプロセスか、などという逃げ道は存在しない。結果もプロセスもその両方を達成しなくてはならないからである。」
「彼らは、プロセスが結果を生み出すとの果てしない仮定を、英知と体力の限りを尽くして常に『科学的に』実証していく。偶然に、は依存しない。結果がなぜ出たのか、出なかったのか、それを明確に立証していく。これがスポーツ界でプロを名乗る人々の生き様である。」
「彼らが、W杯初出場という歴史的な事象の中で、いかに真摯な姿勢で現実を捉え、勇気を持って現実に取り組み、そうして今、重い結果と過程を背負って前進を試みようとしているか。39人ものインタビューで、それをみなさんに読みとっていただければと心から願って、書く。」
低迷する日本経済、閉そく感が増す社会のムードの中、ワールドカップ日本応援に光明を見出したものの、スカッとする場面がないまま初体験を終えた日本列島
この年1998年は、戦後最悪とも言える経済成長率のマイナスを記録し、景気は後退局面に入りました。企業ではリストラや倒産が相次ぎました。
この年の日本経済で最も注目を集めたのは、日本長期信用銀行の経営問題でした。最終的には金融再生法に基づく特別公的管理(一時国有化)適用で決着。そして日本債権信用銀行も特別公的管理に移行した年です。
完全失業率は過去最悪の水準に達し、有効求人倍率も過去最低を記録するなど、雇用情勢は非常に厳しくなりました。
一方、物価の下落が企業の収益を圧迫し、不況をさらに深刻化させるデフレスパイラルへの懸念が高まりました。また、1997年に発生したアジア通貨危機は、日本経済にも影響を与え、輸出の減少や景気の減速を招きました。
これらの要因が複合的に作用し、1998年の日本経済は非常に厳しい状況に置かれました。
そのため社会の閉そく感が増し、人々は何か明るい話題、国民を勇気づける話題をいつになく求めていた年といえます。
そのような経済社会情勢の中で迎えた日本サッカー界初のワールドカップ挑戦は、ふだんサッカーにさほど関心をもたない人々にも、明るい話題、国民を勇気づける話題として格好の出来事になったのです。
世界中の国々がサッカーを通じて、その国の人々の心を一つにする、ワールドカップサッカーが、そうした場であることを知った日本の人々は、日本代表がフランスで活躍してくれることを願って大会を心待ちにしました。
しかし大会直前になって、それまで日本サッカー界のカリスマ的存在であったカズ・三浦知良選手が日本代表から外れることを知り、日本中が一億総評論家と化するほどの大きな反響が起こりました。
一方、かねてから日本代表を応援したいと思っていたサポーターの人々は、ここぞとばかりフランスに向かおうとしたのですが、突然降って湧いたチケット不足問題に翻弄されました。
それでも多くのサポーターがチケットのあてもなくフランスに渡り、世界中の人たちを驚かせました。ただ、フランスで応援した日本代表サポーターは、スタジアムの中でも外でも整然とした応援と試合後のスタジアムのゴミ拾いのマナーで、現地の人たちから高い評価を得ました。
そして我らが日本代表のワールドカップ初舞台、日本国内では各家庭のテレビの前で、各地の屋外大型スクリーンの前で、スポーツバーのモニター画面の前で、グループリーグ3試合を見守りました。
初戦のアルゼンチン戦のあとは「よくやった、まだいける」という気持ちでした。しかし2戦目のクロアチア戦、祈るようにしながら見守る中、またも敗戦、これでグループリーグ突破は絶望的となりましたが、最後のジャマイカ戦、この相手なら勝ってくれるだろう、1勝はしてくれるだろうと思いつつ見守った試合にも勝てず、日本中の願いは叶いませんでした。
日本全体が閉そく感にある中、国民を勇気づける場になるのではないか、日本人の心が一つになるのではないかという思いで見守った3試合、スカッと心が晴れるような場面がないまま初体験を終えた日本列島でした。
スポーツという、勝ち負けがはっきりする場においては、心を一つにできるのは「勝利」をおいてないのですが、世界の舞台に初めて挑戦する日本が、そうやすやすと「勝利」を手にできるほど甘い場ではなかったということを、今回、日本中の人々が理解したのでした。
そして人々はまた、いま一つパッとしない日本の経済社会の日常に戻っていきました。
日本サッカー史上初のワールドカップ挑戦は、サッカー協会から監督・選手・スタッフそしてマスコミ、サポーターに至るまですべてが「未知」「未熟」「未経験」この3つの「未=いまだ」のもとでの挑戦でした
日本サッカー史上初のワールドカップ挑戦となった「フランスワールドカップ」その挑戦の記録を克明に辿っていくと、見えてくるのは日本サッカー界を覆っていた3つの「未」、すなわち「未知」「未熟」「未経験」のもとでの挑戦だったことが浮き彫りになってきました。
「未」は「いまだ」と読み替えたほうがわかりやすいかも知れません。
つまり「いまだ知らなかった世界」に飛び込み「いまだ成熟とはほど遠い体制」で「いまだ経験したことのない相手」と相まみえたということです。
「未知・いまだ知らなかった世界」
4年前にはアメリカで行われたワールドカップ、その前年1993年10月にあと一歩のところで出場権を逃し、アメリカ大会に出場した24ケ国の仲間入りを果たせなかった日本、2002年には日本でそれを開催することになっているとは言うものの、なにぶん、日本はワールドカップがどういうものか、世界最大のスポーツイベントだとか、時には戦争さえ誘発しかねない本気の戦の場だとか、言葉では聞いていても、実体験がない、いまだ知らない世界に乗り込む体験でした。
そのことから来る、いわば手探りの準備、戸惑いながらの対応などの連続だったと言えます。
例えば日本代表全体の運営、おそらくこれ以上は無理だろうというぐらいの手厚さで準備・対応した結果、過保護だったぐらいだとか、やり過ぎだと反省する部分が出た半面、メンタルケア、メディア対応など「そこまでは気が回らなかった」とか「それは知らなかった」ということで課題を残したところも出てきたのです。
知らない世界に乗り込むことが、いかに難しいことかを思い知らされました。しかし、一度、その世界を知ってしまえば、次からはその反省を生かしてやっていけばいいという財産を得た大会でもありました。
「未熟・いまだ成熟とはほど遠い体制」
これは主として日本サッカー協会の、日本代表を支える体制ということになります。遠くは加茂監督の続投問題に対する協会の恣意的と見える対応に始まり、前年のアジア最終予選の加茂監督更迭・岡田監督昇格、そして岡田監督の本大会指揮、代表選手22人の絞り込み、カズ・三浦知良選手落選問題、すべてが日本サッカー協会の、いまだ成熟とはほど遠い体制のもとでなされた準備です。
協会の意思決定システムが上層部の不透明な部分が見え隠れする時と、強化委員会に丸投げしているかのような時が、まだら模様に現れる不思議な、分かりやすく言えば未熟な体制のもとで準備された日本代表が、ワールドカップ本大会という場に放り込まれたということになります。
これらの指摘は、多くのマスコミからもサッカー専門家からもなされていることですので、日本サッカー協会自体も、多少なりとも認識があるはずですが、その指摘によって協会の役員構成、組織構成が左右されるわけではありません。
あとはどれだけ自浄作用を働かせるかに期待するしかありませんので、体制として成熟していくまでにどれほどの時間を要するのか、誰にもわからない種類の問題です。
「未経験・いまだ経験したことのない相手との戦い」
これは主として岡田監督のもとでの日本代表に言えることです。岡田監督自身がどのカテゴリーでも監督経験がなかった中で、ワールドカップ日本代表の指揮をとるために選んだ方法は、戦い方を徹底した理論武装で固め、情を徹底して排除し、理だけで臨む方法でした。
しかし、そこには、ちょっとした息抜きを与えてやることで得られる効果を経験していないが故に固められた、がんじがらめの合宿スケジュールや、選手の心理を掌握するという経験をしていないが故に進められてしまった間違った選手選び、理論だけを頼みにした戦い方の故に、3試合とも同じメンバー(スタメン)で戦うという硬直した采配など、未経験の懸念がモロに出てしまいました。
監督未経験の人が、いまだ経験したことのない相手と戦うために、相手を徹底的に研究して論理的に戦える方法を見出したまではよかったのですが、ある意味、それが限界だったというべきでしょう。ピッチで戦う選手たちのメンタルをしっかり見極めた上で、モチベーションを最大化したり、実際の試合の中で刻々と変わる展開に臨機応変に対応した采配を求めるのは難しかったというしかありません。
岡田監督自身は、大会の結果責任を一身に負い辞任しましたが、この大会の直後の段階では、「考えに考え抜いて決断してきたすべてのことに悔いはない」とすっきりした表情で語りましたが、後年、さまざまな経験を積み重ねていくに従い「歴史の針を戻せるなら、こうすべきだった」と感じることが出てくるように思いますし、それが自然なことではないかと思います。
こうして検証してきた結果明らかになった、今回の「フランスワールドカップ日本代表」の意味合いを、のちのちまで語り継ぎ、改善すべきこと、改革されるべきことがなされていけば、それこそが「フランスワールドカップ日本代表」の最大の功績・遺産だと言えますし、いつの日か必ず「日本サッカーの歴史」という法廷で、そのことが判断されるに違いありません。
サッカーが持つ不思議な魅力、世界の多くの国がそうであるように、「サッカーの世界最高峰の舞台、ワールドカップの舞台に立つことにより、その応援という行為が国を一つにする魅力」を知ったニッポン、しかし、それは勝つことによって初めて国中の一体感が本物になるんだということも知ったニッポン、世界の舞台に立ったという最初の目標には到達したものの、勝つという次の目標はお預けになった今大会、しかし、このあとも世界への挑戦が続く限り「国を一つにできる魅力」に酔いしれる日を追いかけ続けていくことになります。
このあと、長くワールドカップの舞台に立つ日本代表が世界に勝っていくためには「決断を先延ばしするリーダー」「決め事に囚われすぎるメンバー」「失敗を恐れる風潮」といった、これまでの日本型社会のありようを変えていかないといけない、という議論が
ワールドカップサッカーは、国と国との威信を賭けた戦いと言われ、またその国のナショナリズムとナショナリズムのぶつかり合いと言われます。
そして、その国のサッカーには、その国の国民性や文化、メンタリティーが色濃く反映されるスポーツとも言われています。
これまでワールドカップの舞台に立ったことのない日本は、国と国の威信を賭けた戦いがどの程度のものか肌感覚ではわかりませんでしたし、日本のサッカースタイルに、極めて日本的な国民性、文化、メンタリティーが反映されているといっても具体的にどのようなことが反映されているのかまでは明確に語れませんでした。
ところが、今回、すべてが初体験、未知の体験とはいえ、実際に体験したことによって、多くのことが具体的に見えてきました。
そして、それは、これまでの日本社会が長く放置してきた「とかく決断を先延ばしにしがちな組織、リーダーたち」といった点や「とかく決め事に囚われすぎて自ら打開に動こうとしない組織、メンバーたち」さらには「とかく失敗を恐れてリスクをとろうとしたがらない社会的な風潮」、「とかく個性ある人間の突出を是としたがらない教育」といった、これまでの日本型社会に起因していることを指摘する議論が出始めました。
すなわち、今後、2002年以降、長くワールドカップの舞台に立っていくであろう日本代表が世界に伍して勝利していくには、そうした悪しき日本型組織、日本型社会のシステムそのものを変えていかないと、とても世界に追いつくことなどできないと思うといった、根本的な指摘です。
そのことを、非常にわかりやすく提示して議論したテレビ番組がありました。その番組の議論を紹介します。「チームや選手たちの技術や経験だけではなく、そうした日本のサッカーを育んだ日本型システム自体に問題があるのではないか」という議論は「その国のサッカーに、その国の国民性や文化、メンタリティーが色濃く反映される」という定説に対して、現段階における「日本サッカーの姿」について解答を提示した議論として、おそらく初めてのものではないかと思います。
その国のサッカーが成長・進化を遂げていくとすれば、この部分について対策を練り、次に活かしていくことなのだと「目からうろこ」が落ちるような議論を紹介します。
フランスワールドカップの余韻もすっかり失せ、サッカー日本代表も次の戦いを見すえて動き出したころ、その番組はオンエアされました。
98.10.17NHK教育「未来潮流」という番組です。この日は「サツカーに学ぶ日本型システムの未来」というテーマで、進行役にセルジオ越後氏、討論メンバーに、コラムニスト・山崎浩一氏、作家・馳星周氏、文化人類学者・今福龍太氏が参加しました。
日本はなぜ勝てなかったのか、W杯に見た日本型システムの壁、決断を先延ばしする、決め事に囚われ過ぎる、失敗を恐れすぎる、個性より平等できた等々
冒頭、セルジオ越後氏が次のように問題提起しました。
越後氏 「日本が1勝もできなかった原因として決定力の差とかパワー、スピードなど技術的、体力的要因が指摘されるが、そうではなく、特に決断力の問題など日本型組織の問題が日本サッカーに反映されているからで、そこを直さなければならないのではないかと感じた。
例えば、日本vsアルゼンチン戦、相手にリードされた展開で、先に手を打ったのはリードしているアルゼンチンのほうだった。追加点を取りにきたのだ。日本が手を打たないでいるうちに、相手に先に次の手をうたれてしまう。日本型社会の欠点である決断力のなさ、決断の遅さが監督采配に出てしまっていた。日本型社会には失敗を恐れてしまう風土があり、当初予定していたプランを早まり過ぎて失敗したくないという意識が決断を遅らせる。
次に、日本vsクロアチア戦、残り15分ぐらいになってリードされてしまった。日本の試合はリードされてあとがない時になっても、当初決めたプラン通りの作戦しかやらない。状況の変化に応じてプランを変更してみようとはしない。これは日本の組織が持っている伝統的な思考スタイルだと感じた。
馳氏 ボクも日本の3試合を見ていて、毎試合判で押したような時間での選手交代に終始していたことについて友達と議論した。テレビ実況では「後半15分での交代にこだわっていた」と言い方をしてくれていたが、悪くいえば「柔軟性のない采配」ということになる。サッカーの試合というのはマニュアル通りにいくことなどない常に流動しているものなので、それに応じた柔軟な采配や選手の判断が必要なのだが・・。
それは選手たちにも言える。特にクロアチア戦の残り15分を見ていてそう思った。チームの決め事に囚われて、自分から打開に動こうとしない選手が多い。同じクロアチアと戦ったドイツの試合でも同じ状況があったが、この時のドイツはGK1人を残し全員攻撃に出た。監督から指示されたわけではないのに、選手が自らリスクを負って勝ちにいっている姿がありありと見られた。負ける時は1-0でも2-0でも同じ、であれば勝ちに行く、こうあって欲しかった。それは経験の差だけの問題ではなくドイツ人と日本人のメンタリティの差なのではないか。
やはり、これは監督や選手だけの問題ではなく日本人全体の問題だと感じた。
越後氏 決断の遅さ、判断力のなさの関連で言えば、これも日本人の特徴だと思うが、切羽詰まった時に初めて動く、いいかえれば切羽詰った状態にならないと動かない。昨年の岡田監督のジョホールバルでの決断がまさにそれで、切羽詰まった末に、カズと中山、FW二枚替えという大胆な決断をして成功した。しかし、年が明けて普通の状態になると、また決断の遅い指揮官に戻ってしまっている。
今福氏 岡田監督が掲げた目標は「1勝1敗1分」だったが、そこにも問題を先送りしたメンタリティを感じる。一つも勝てない、つまり3敗という見通しを立てるということは、破綻した結果を目標とすることになり、それはできないから1勝1敗1分という設定になっていると感じた。
日本人のメンタリティには強く破綻を恐れるところがある。失敗したくない、失敗は悪だという、失敗に対する過剰な恐れがある。
そのため、戦後の日本社会は小さな失敗を小さな修正で取り繕いながら問題を先送りしていたところがあり、最近の大企業の破綻も、それを繰り返したあげく、どうにもならなくなって潰れてしまった。
本来であれば、小さな失敗のうちに、一度「リセット」してやり直せばいい。やめるとか終わりにするというのではなく「一度ゼロに戻して」またやってみる。こうすることについて何も恐れる必要がないはずだが、日本が、経済の成長とともに立ち止まることを許されなくなったせいなのかどうか、そういう「やり直し」のメンタリティが作られなかったのかも知れない。
山崎氏 サッカーの試合には確実に起こることなどあり得ないほど流動的に常に動いているものなのに、日本の場合、作戦を立てる時に、最初から最悪の事態が確実に起こるかのようにして作戦を立て始め、そこから一つずつ消去法的に逆算して「このへんで折り合えば安全」みたいな作戦の立て方をしている。それは、普段から「リスク」というものを悪いこと、失敗というものは絶対犯してはいけないものというプレッシャーにさらされながら生きているためではないかと思う。
サッカーにおけるFWなどは失敗の連続のポジションであり、失敗を楽しむしかないようなスポーツだと思う。あれだけ攻撃しても一度も成功しなかった、けれども、そのプロセスをなぜ楽しめないのか。そういう文化がボクらには余りにも無さすぎる。
失敗を恐れずにやったという意味では、ジャマイカ戦で城選手がGKと1対1の場面でボレーを選択して外してしまった。あの場面でなぜトラップして落ち着いて打たなかったのかと批判されたけれど、その批判は、まさに結果論そのもので、FWとして当然のプレーだと思う。積極的にプレーした結果の失敗は、何もしないで失敗してこととは全然違うことを区別して評価すべきだと思う。
今福氏 それは、誰かが犯した失敗を忘れず責任を求めるという日本人の国民性でもあると思う。これも日本人のメンタリティの一つだが、失敗をすぐ忘れて切り替えることができない国民性でもある。だから戦犯さがしになり「あのプレーも原因の一つだ」となる。選手もまた、失敗を忘れてすぐ切り替えればいいものを、それができない。次こそはいいプレーをしなければとキリんでしまったりする。サッカーの試合は常に、いま、現在と一瞬一瞬の連続なのだから、すぐ切り替えればいい。
山崎氏 日本では子供たちへの教育のパターンとして「先生やコーチから言われたことに子供たちは従順に従う、疑問に口を挟んだり質問することはしない」という教育パターンだ。それが「質問して間違っていたら笑われる」とか「恥をかく」という具合に失敗というものに対する過剰な恐れを育んでしまっているのではないか。
越後氏 また、そういう教育のためなのか、そうでないのかわからないけれど、いまの日本の子供社会にはガキ大将がいないと言われ、子供社会で決断する人間がいない社会になっている。サッカー選手も小さい時からコーチの指示をキチンと守る訓練を受けてきており、その中のエリートが日本代表になっている。だから強烈なリーダーシップを発揮する選手がいなくなったのではないか。みんな平等にという教育がそうさせているのではないか。
馳氏 子供たちへの教育のおいて「みな平等に」という考え方が基本にあると思うが、それは幻想なのではないか、一人ひとり違う背景を持って育っているわけで、できれば、それぞれの個性に合った育て方をして欲しいが、特に戦後は、個性のある子は悪い子だ、みたいなことになり、子供たちは横を見ながら出過ぎないようにしようとしている。そういうのを変えたいと思いますけど、すぐには変わらないですよね。
山崎氏 日本の教育には「平等」と「個性」のダブルスタンダードがあると思う。一方で個性的であれというメッセージも出される。でも個性的であろうとすると抑圧がかかるダブルバインドみたいな構造になっているところもある。別にはっきりさせろとは言うわけではないけど、すごく窮屈だなと思うところがある・・。
今福氏 「平等」という概念に縛られず、「対等」という概念を持つことが大事だと思う。「それぞれ個性を持ちつつ自分のスタイルを持っているけど対等な関係である」という考え方。その考え方が薄くて、何か幻想的な「平等」という概念に囚われて、一人だけ飛びぬけてしまうと嫌われるという風潮になってしまう。「平等」という概念を取り違えているのではないか。
日本のサッカー選手は、日本のスポーツ教育、サッカー教育のあり方の中からしか育ってこないわけで、そうやって育てられ、作られた日本代表のサッカーが日本の社会制度を映し出しているのは、当然と言えば当然だと思う。
その関連で非常に興味深いのは中田英寿選手の言葉だ。彼は「自分の最大のライバルは小学校5年の時の中田英寿だ」という。どういうことか。彼はその頃FWをやっていて、うしろからどんなボールが来るか、見なくても全部わかったという。それが年とともにわからなくなり、アイコンタクトをしたり声を掛け合ったしないとダメになった。小学校5年の時は本能のままに動けていたのに。
そこで、ある時から彼は退化していった自分の本能を何とかして繋ぎとめる「逆トレーニング」を始めたという。つまり、チームのトレーニングでは画一的な動きを求められてしまい、本能的な動きを抑圧するようなトレーニングに対して、一種の反逆を試みた。その後ずっと反逆し続けてきた。彼がトレーニング嫌いと言われているのは、そういう画一的なトレーニングに対するものであり、本能を取り戻すための逆トレーニングの成果こそが、今日の中田英寿選手を生んでいると思うが、それはサッカー界では突然変異とも言える稀有なことかも知れない。
馳氏 突然変異で言えば、アルゼンチン戦のあと川口能活選手がつくづく「あの試合は勝ちたかった」と言っていた。なぜ?と聞いたら「だってアルゼンチンに勝ったら凄い大番狂わせで気分いいでしょう」とこともなげに言う。こういうメンタリティは日本の社会では突然変異でしか生まれてこないのだろうか。
越後氏 少なくとも学校とかサッカースクールとか、教える人が常にいて画一的なサッカーをする場所からは、突然変異の才能が出るのは難しいかも知れない。子供たちが先生やコーチもいない広場や公園でサッカーをする、あるいは学校やスクールであっても、先生やコーチのいない時間にサッカーをする、というのも日常的にあって欲しい。
そこには決まった子供たちだけが集まるのではなく、見知らぬ子も入れ替わり立ち代わり一緒に入って遊ぶ、毎日違うメンバーになり、その日その日でガキ大将も違っているような「遊び心」の子供社会が少なくなっていることは確かだと思う。そういう「遊び心」のある場が、突然変異的な才能を確実に生み出せるかどうかはわからないけれど、可能性はあるのではないか。
山崎氏 日本代表に初めて呼ばれた選手が、チームと自分の関係について、どういうメンタリティでいるか考えてみると、おそらく、初めて呼ばれた選手は日本代表という出来上がった組織の中に、まず自分が早く溶け込み、なじむことをを考えるのが普通ではないか。
もし自分が入ったら、この組織をダイナミックに変えられるのではないか、自分が一人入ることによって、もしかしたらこのチームは大きく変わるのではないか、とは、なかなか考えられないのではないか。これは日本では、個人と組織の関係でいろいろなところで同じだという気がする。
今福氏 いまのサッカー少年は小さい頃からポジション毎の役割分担というものを教えられていて、その結果FWをやりたいという子が減ってきていると聞いた。MFいわゆるゲームメーカーをやりたいという子が多いという。もう子供の頃から戦略的・戦術的なことばかり考えるというのは、すごく違和感を感じる。サッカーでは点を取る選手こそがヒーローであり、まず全員がFWをやりたいというところからスタートして、次第に適性に応じたポジションに移っていくものだと思うが・・・。
今後、日本サッカーのスタイルをどのように確立していけばいいのか、についての議論の出発点に
今回の議論では、日本代表が一つも勝てなかったのは、指揮官である岡田監督の決断の遅さや、選手一人ひとりが自主的に判断するというメンタリティに欠けていたためで、これは、これまでの日本型企業社会あるいは日本という国に共通した組織の欠点に起因していると指摘されています。
またストライカーをはじめ攻撃において失敗を恐れずにプレーする場面の少なさや、尖ったプレーをする選手たちが出にくい状況は「みな平等に」のような教育が長く続いたために、ガキ大将が育ちにくいことも影響しているという指摘もあります。
サッカーという世界共通のスポーツが、その国の国民性や組織社会の姿を、そのまま反映するスポーツであるという立場にたった場合、逆に日本人の国民性にあったサッカー、日本人のメンタリティをうまく活かしたサッカーとはどういうものなのかについて、解答を探していくことも、日本が世界で勝てるようになるため必要であるという議論が具体的に始まったことも確かです。
このあと、長い時間をかけて固まっていく日本らしいサッカースタイル、例えば組織的に動くことに非常に忠実な国民性と、高いアジリティ能力を活かして、早いパス回しで組織的に攻め、相手を翻弄するサッカースタイルを目指すべきなのではないかといった議論も同時並行で沸き起こります。
「とかく決断を先延ばしにしがちなリーダー」「とかく決め事に囚われすぎて自ら打開に動こうとしないメンバー」といった長く培われてきた歴史の中から育まれた国民性は一朝一夕に変えることは不可能ですから、2002年といった目前の大会で結果を求めていくとすれば「決断を先延ばしにしがちな」国民性とは無縁の外国人監督に任せるしかないとか、「とかく決め事に囚われすぎる」国民性を逆手にとって、オートマチックな動き、戦術を叩き込んで攻める、守るといったパターンを固めるといった方策をとっていくのは、ある意味、非常に理にかなったことなのかも知れません。
世界は熱狂の中で1ケ月間の祝祭、優勝は地元フランス、ブラジルは連覇の夢砕ける
6月10日、前回大会優勝国ブラジルにスコットランドが挑戦するカードで開幕した「フランスワールドカップ」は、日本代表がグループリーグの最終戦、ジャマイカ戦を終えた翌日、6月27日から決勝トーナメントに入りました。
グループリーグ8組、各グループとも4チームづつの総当たりで、ここまで大会全試合数64試合のちょうど半分、32試合が終了しました。
グループリーグの結果と順位
A組. 1位ブラジル 2勝1敗 勝ち点6 2位ノルウェー 1勝2分け 勝ち点5 3位モロッコ、4位スコットランド
B組. 1位イタリア 2勝1分け 勝ち点7 2位チリ 3分け 勝ち点3 3位オーストリア、4位カメルーン
C組. 1位フランス 3勝 勝ち点9 2位デンマーク 1勝1敗1分け 勝ち点4 3位南アフリカ 4位サウジアラビア
D組. 1位ナイジェリア 2勝1敗 勝ち点6 2位パラグアイ 1勝2分け 勝ち点6 3位スペイン、 4位ブルガリア
E組. 1位オランダ 1勝2分け 勝ち点5 2位メキシコ 1勝2分け 勝ち点5 3位ベルギー 4位韓国
F組. 1位ドイツ 2勝1分け 勝ち点7 2位ユーゴスラビア 2勝1分け 勝ち点7 3位イラン 4位アメリカ
G組. 1位ルーマニア 2勝1分け 勝ち点7 2位イングランド 2勝1敗 勝ち点6 3位コロンビア 4位チュニジア
H組. 1位アルゼンチン 3勝 勝ち点9 2位クロアチア 2勝1敗 勝ち点6 3位ジャマイカ 4位日本
今回のグループリーグは波乱のない強豪国が順当に勝ち上がった大会となりました。開催地が欧州ということで、欧州の強豪にとってはほとんどアウェー感がないというアドバンテージがありました。
今大会の南米勢は、個の能力の高いブラジル、バランスのとれたチーム作りをしたアルゼンチンの2チームに加え、名手GKチラベルトやDF陣の奮闘が持ち味のパラグアイ、サラス、サモラーノのいわゆるサ・サコンビを擁するチリがしぶとく勝ち上がりました。南米5チームでは唯一コロンビアがグループリーグ敗退となったのです。
アジア勢は4ケ国が参戦しましたが、すべてグループリーグ敗退、しかし前年のアジア第3代表決定戦で日本に敗れ、オーストラリアとの大陸間プレーオフで最後の最後に出場国に滑り込んだイランが本大会でアジア勢唯一の1勝を手にしたのですから、5大会ぶり2回目とはいえ、これが経験国の力なのでしょうか。
次回2002年大会を共催する韓国は、4大会連続、通算5回目の出場ですが、ここまで5大会勝ち点を1つもあげていない屈辱を晴らしたい大会でした。
韓国は初戦の相手がメキシコ、前半28分に、このシーズンからセレッソ大阪のメンバーとしてJリーガーとなっていた河錫舟(ハ・ソッチュ)選手が、ゴール正面25mからのFKを見事に決め、韓国が幸先よく先制しました。ところが、そのわずか1分後に河錫舟選手はメキシコの選手に後方からタックル、今大会から適用された「後方からのタックルは即退場」のジャッジ基準適用第1号となり一発退場、残り60分以上を一人少ない状況で戦わざるを得なくなりました。そのためメキシコに後半3点を許し逆転負けを喫しました。
韓国は第2戦のオランダに0-5の大敗を喫してグループリーグ敗退が決定すると、即日、車範根(チャ・ボンクン)監督の更迭を発表、車監督は1試合を残したまま無念の帰国となりました。
急遽、金監督代行のもとでベルギーとの最終戦に臨んだ韓国、先制されたものの後半26分、翌年から横浜Mに加入する、キャプテンマークを巻いた柳相鐵(ユ・サンチョル)選手が執念の同点ゴール、決勝トーナメント進出の可能性を残していたベルギーの野望を砕くとともに、史上初めての勝ち点1を得て大会を終えました。
そのほかのグループリーグの戦いの中では、D組のスペインが最終戦で悲嘆にくれることとなりました。スペインは2戦を終えて1分け1敗、最終戦の相手は同じく1分け1敗のブルガリア、どちらも勝った場合、もう一つの試合でパラグアイがナイジェリアに引き分け以下であれば決勝トーナメント進出の可能性を残しての試合となりました。
スペインは、この試合大爆発、大量6点を奪い6-1で圧勝したのですが、もう1試合のほうで主力を休ませたナイジェリアを相手にパラグアイが勝利、スペインの大勝は実ることなく大会を去りました。
決勝トーナメント進出16ケ国の大陸別内訳をみると、欧州10ケ国、南米4ケ国、アフリカ1、北中米1となりました。
決勝T1回戦、因縁のアルゼンチンvsイングランド戦、またも歴史に残る試合に
決勝トーナメント1回戦の組み合わせと結果
1998年6月27日 イタリア 1 – 0 ノルウェー 得点ヴィエリ(イ) 18分
1998年6月27日 ブラジル 4 – 1 チリ 得点サンパイオ(ブ)11分, 26分、ロナウド(ブ)45+3分 (pk), 72分、 サラス(チ) 70分
1998年6月28日 フランス 1 – 0 (延長) パラグアイ 得点ブラン(フ)114分ゴールデンゴール
1998年6月28日 ナイジェリア 1 – 4 デンマーク 得点メラー(デ)3分, B.ラウドルップ(デ)12分, サンド(デ)58分, ヘルヴェグ(デ)76分, ババンギダ(ナ)77分
1998年6月29日 ドイツ 2 – 1 メキシコ 得点クリンスマン(ド)74分, ビアホフ(ド)86分, エルナンデス(メ)47分
1998年6月29日 オランダ 2 – 1 ユーゴスラビア 得点ベルカンプ(オ)38分, ダーヴィッツ(オ)90+2分, コムリェノヴィッチ(ユ)48分
1998年6月30日 ルーマニア 0 – 1 クロアチア 得点スーケル(ク)45+2分(pk)
1998年6月30日 アルゼンチン 2 – 2 (延長pk4-3) イングランド 得点バティストゥータ(ア)5分(pk), サネッティ(ア)45+1分, シアラー(イ)9分(pk), オーウェン(イ)16分
決勝トーナメント1回戦のゲームでドラマチックだったのは、フランスvsパラグアイ戦、アルゼンチンvsイングランド戦でした。
フランスvsパラグアイ戦、フランスはグループリーグ2戦目のサウジ戦でジダンがレッドカードで退場、2試合の出場停止処分を受けたため、この試合まで欠場、しかし試合はパラグアイが守備的になったこともありフランスが一方的に攻めまくりました。けれどもGKチラベルトを中心としたパラグアイの堅い守りを崩せず、30本以上のシュートを放ちながらノーゴール、試合は今大会導入されたVゴール方式(この大会ではゴールデンゴールの呼称)の延長に入りました。
フランスにとっては押しに押しながらのPK戦となれば、いやな展開になると思われた延長後半9分、DFでキャプテンのローラン・ブランがゴール前まで上がって見事にゴール、ワールドカップ史上初めてのゴールデンゴールによる決着で、辛くも準々決勝進出を果たしました。
アルゼンチンvsイングランド戦は、因縁のカードがまた新たな因縁を生み出す展開となりました。1986年メキシコワールドカップ、準々決勝で激突した両国は数年前に発生した「フォークランド紛争」の当事国で、この時も因縁の試合と言われましたが、全盛期のマラドーナが「神の手ゴール」と言われる疑惑のゴールと「5人抜きゴール」と言われるワールドカップ史に残る2つのゴールを決めてアルゼンチンが勝利しました。その大会アルゼンチンは、そのまま優勝へと突き進んだのです。
「神の手ゴール」と言われる疑惑のゴールによって、両国の因縁はこのフランス大会にもついて回りました。
試合は両チーム2点づつを取り合って、全く互角の戦いとなっていたのですが、後半2分、事件は起こりました。
中盤でボールを受けようとしたイングランドの若き司令塔デビット・ベッカムをアルゼンチンのシメオネが後ろからドーンという感じ押し倒してしまい、なおかつ、シメオネがベッカムの背中に腕を立て体重をかけながら起き上がろうとしたため、ベッカムが頭にきたのかもしれません。
ベッカムは、シメオネが立ち上がって自分の脇を後ずさりしていくのを見定めるように、うつ伏せになっていた自分の右足を振り上げると、ちょうどシメオネに引っ掛かる形になり、シメオネは「やられたぁ」という感じで尻もちをつくように倒れました。
その行為は、ちょうど目の前にいたニールセン主審に見られてしまいましたから、明らかなベッカムの報復行為と受け止められ、シメオネにイエローカードが出されたのに続きベッカムは一発レッド、退場処分となりました。
実況していたNHKの野瀬アナウンサーは、ニールセン主審がレッドカードを掲げた時「あっ! レッドカード・・」とアナウンスするのかと思いましたら「あっ! 若さが間違った方向に出てしまったベッカム・・・・」と名言を発して、しばらく絶句したほどの事件でした。
その後、イングランドは防戦一方の展開となりましたが、失点せずに凌ぎ切りPK戦まで持ち込みました。しかし疲労のつけはPK戦に出てしまい、とうとう力尽きました。
この試合、12年前と同様、またしてもアルゼンチンがイングランドを退けたわけですが、イングランド国内では「1人の愚か者と10人の賢者」という表現で、ベッカムに轟々たる批難が浴びせられ、新たな因縁を生み出してしまいました。
それでもイギリス国民は、母国のニュースター、若干18歳のマイケル・オーウェンが評判どおりの活躍を見せ、彼に未来を託すことで、この敗戦を少しでも癒せるかも知れないシーンを、この試合で見ました。
すでにグループリーグ第2戦ルーマニア戦で途中出場ながらワールドカップ史上2番目の若さでゴールを決めているオーウェン、第3戦目からは続けてスタメンに起用されていました。
それは前半16分でした。自陣からベッカムが出したパスをセンターサークルの中で、後ろ足でチョンとさわり、自分の目の前、絶妙な位置にボールを落とすとドリブルで突進、自分の右側からショルダーチャージをかけてきた大柄なチャモをものともせずに前に出ると、次は目の前に待ち構えるアジャラの右横にボールを持ち出して、ゴール中央から遠ざかりながらも、詰めてきたGKロアの逆をつきシュート、見事左サイドネットに突き刺すスーパーゴールを叩き込みました。
走った距離約40m以上、相手DFを振り切るそのスピードは、すでに母国で「ワンダーボーイ(驚異の少年)」というニックネームをもらっているオーウェン、2-1と勝ち越すゴールでしたので、一時はイギリス国民を狂喜乱舞させるプレーでした。
グループリーグで日本が戦ったアルゼンチン、その時は日本にとってもそうでしたが、アルゼンチンにとっても大会初戦、アルゼンチンにしてみれば優勝を本気で狙っている大会ですから、間違っても初戦で躓いていられない、慎重の上にも慎重を期していた初戦だったのでしょう、それが日本にとっては負けたとはいえ、手応えのある試合になったのですが、決勝トーナメントに進んだアルゼンチンは、もはや慎重を期する必要などどこにもない、全力モードに切り替わっていました。
こうなった時のアルゼンチンは怖いということです。ただ怖いだけでなく狡猾なことも存分に見せつける怖さです。なにせ決勝で「神の手ゴール」を平気でやってしまうレベルの狡猾さだと言えます。やはり優勝を狙うレベルのチームの本当の怖さは、日本と戦ったぐらいのところにあったのではなく、この試合で見せつけられた気がします。
これでベスト8が出揃い、大会は佳境に入っていきました。
準々決勝イタリアvsフランス戦、イタリア、前回大会に続きPK戦に泣く
準々決勝のカードと結果
1998年7月3日 イタリア 0 – 0 (延長pk3-4) フランス
1998年7月3日 ブラジル 3 – 2 デンマーク 得点ベベット(ブ)11分, リバウド(ブ) 27分, 60分, ヨルゲンセン(デ)2分, B.ラウドルップ(デ)50分
1998年7月4日 オランダ 2 – 1 アルゼンチン 得点クライファート(オ)12分, ベルカンプ(オ)89分, C.ロペス(ア)17分
1998年7月4日 ドイツ 0 – 3 クロアチア 得点ヤルニ(ク)45+3分, ヴラオヴィッチ(ク)80分, スーケル(ク)85分
準々決勝は欧州勢が6チーム、南米勢が2チーム、順当といえば順当な勝ち残りでした。それぞれ優勝経験国vs未経験国の顔合わせになりましたが、優勝経験国のイタリア、アルゼンチン、ドイツの3ケ国が敗退したという点では波乱の結果といえるかも知れません。
イタリアvsフランスのカードは、準々決勝の中でもっとも関心を集めたカードでした。片や前回アメリカ大会で決勝まで駒を進めたイタリア、片や開催国であり初優勝の野望を抱くフランス。フランスは、決勝の会場でもある新スタジアム「サン・ドニ」に、グループリーグ2戦目以来戻ってきました。このあと勝ち進めば、ずっとこのスタジアムで戦うことができます。
試合は、司令塔ジダンが3試合ぶりに復帰、ジョルカエフ、プティと組んだ中盤が流動的に動き回ります。これに対してイタリアは伝統のカテナチオを、ベルゴミ、マルディーニ、カンナバーロ、コスタクルタのDF陣ががっちりと効かせます。
後半両チームベンチが動きました。最初にフランスが後半20分、ギバルシュとカランブーを下げ、FWアンリとFWトレセゲを同時投入、するとイタリアも後半21分デル・ピエロを下げ、ロベルト・バッジョを投入しました。
前回大会のスーパースターと、今大会スーパースターになるのではないかと目される選手が同じピッチに立った瞬間でした。
しかし、この交代はフランスのほうに分があったようで、ジダンからアンリ、トレセゲへのボール供給が増してきました。
しかしイタリアの堅守は崩せず試合は延長に入りました。延長前半12分、ロベルト・バッジョにゴールデンゴールで試合を終わらせるチャンスがきました。中盤のアルベルティーニから前線で構えるバッジョにロビングボールが送られました。バッジョは走り込みながら後方から来るボールをダイレクトで合わせにかかります。狙いはゴール左側のサイドネットです。バッジョの右足はイメージどおりにボレーで捉えました。あとはサイドネットに吸い込まれるのを見届けるだけです。
ところがボールは無情にもほんのボール半個分だけゴールポストを外れていきました。バッジョはまたもや勝利の神に見放されたかのようでした。
延長を終わっても結局0-0のままPK戦に突入しました。PK戦では守りに追われたイタリアの疲労が影響しました。2人目のアルベルティーニが外して、先に4人成功させているフランスに対し、イタリアの5人目ディビアッジョのキックはバーを激しく叩き失敗、万事休すでした。
フランスは決勝トーナメント1回戦のパラグアイ戦に続く薄氷の勝利、しかし、これがチームのムードを一段と上げることとなりました。
ドイツvsクロアチア戦の結果には世界中が驚きました。人口500万人に満たない国クロアチアが、これまで優勝3回を誇るサッカー大国ドイツを3-0で粉砕したからです。この試合には伏線がありました。
試合前の会見でドイツのフォクツ監督が古い神話を持ち出して「小国が巨人に挑む」と形容しました。客観的にみればそうでしょうけれど、それを当の監督が言っては明らかに相手に対する軽視発言となります。これにクロアチア代表は発奮しました。試合後、スーケルは「あの発言で我々は燃えました。絶対ぶっ倒すぞ、とね。今日は心で戦った。」と誇らしげに語りました。
この両国は2年前の1996年欧州選手権の準々決勝でも対戦していました。この時はクロアチアが1-1の同点に追いつき、いけいけムードが高まったのですが、DFに退場者を出して流れが変わって勝ち越しを許した苦い経験がありました。
ドイツ・フォクツ監督は、そのまま優勝に突き進んだ経験を持っていたことから慢心があったのかもしれません。
クロアチアは2年前のメンバー9人がこの大会にも出場しており「打倒ドイツ」は一つの目標でもあったのです。
クロアチアは前半40分、FWスーケルがドリブル突破を図ろうとするところを、ドイツDFウェルンスが後方からタックル、これが今大会から適用となった即退場基準にはまりレッドカード、クロアチアが数的優位に立つと一気に畳みかけました。
前半ロスタイムに、ヤルニが先制、後半35分にブラオヴィッチが追加点、そして、その5分後にはスーケルがダメ押しの3点目、完勝でした。
クロアチアは、1990年代初頭のユーゴ内戦のあと独立、1995年の欧州選手権地域予選から国際大会に出場し始めてからわずか4年目にして、ワールドカップベスト4入りを果たしたのでした。
ドイツは2年前の欧州選手権のヒーロー、ビエルホフにボールを集めますがクロアチアに封じられ、ベテラン・クリンスマンもいいところなく、なすすべなく敗退しました。
準決勝ブラジルvsオランダ戦、オランダ、試合に勝って勝負に負け
準決勝のカードと結果
1998年7月7日 ブラジル 1 – 1 (延長pk4-2) オランダ 得点ロナウド(ブ)46分, クライファート(オ)87分
1998年7月8日 フランス 2 – 1 クロアチア 得点テュラム(フ)47分, 70分, スーケル(ク)46分
最初のカード、ブラジルvsオランダ戦、両国とも欧州のトップリーグで活躍している実力派選手をズラリと揃えた、まさに重量級の対戦です。
両国スタメンを記録しておきます。
・ブラジル GKタファレル、DFアウダイール、ジュニオール・バイアーノ、ロベルト・カルロス、ゼ・カルロス、MFセザール・サンパイオ、ドゥンガ(C)、レオナルド、リバウド、FWロナウド、ベベト 監督マリオ・ザガロ
・オランダ GKファン・デル・サール、DFヤープ・スタム、フランク・デ・ブール(C)、ライツィハー、コクー、MFヨンク、ロナルド・デ・ブール、ゼンデン、エドガー・ダービッツ、FWベルカンプ、クライファート 監督フース・ヒディング
ブラジルのスタメンに2人のJリーガー(サンパイオ、ドゥンガ)、1人のJリーグ経験者(レオナルド)が含まれているところが誇らしい限りです。
オランダのフース・ヒディング監督は、前線に長身の選手を置きながらも、ハイボールを放り込むようなサッカーはせずに、フィールドを広く使ったパスサッカーでチーム作りをしてきました。テクニックと判断力、そして選手のスピードを生かして大型のチームでありながらソツのないサッカーでここまで勝ち上がってきました。
一方のブラジル、ある時は守備的MFサンパイオの攻め上がりでの得点、ある時は最前線のロナウドがボストプレー、おとりになるプレーでリバウド、ベベトが得点、さらにはロナウド自身の高い能力による得点など多彩な得点パターンでここまで勝ち上がってきました。
試合は一進一退、目が離せないレベルの高い試合となりましたが、両チームとも得点には結びつかず前半を終了しました。
迎えた後半、いきなり試合が動きました。開始20秒、左サイドのリバウドが、ゴール前に狙いすましてスルーパスを出すと、それに反応したロナウドがマークについていたオランダ・コクーのチャージを振り切るようにしてシュート、ボールはGKファン・デル・サールの股間を抜けてゴールに吸い込まれ、ブラジルが先制しました。
その後、オランダ・ライツィハーが接触時に右肩を痛め交代を余儀なくされたのに対して、ブラジルは後半25分、ベベトに代えてデニウソンを投入、予定通りの交代で攻撃活性化を図ります。
すると後半27分、またも中盤からリバウドがロナウドを走らせる絶妙のスルーパス、ロナウドはオフサイドの網をうまくスリ抜けペナルティエリアに突進、GKファン・デル・サールと1対1という場面になりましたが、背後からオランダ・ダービッツが捨て身のタックルをかけるとノーファウル、ボールはゴールポスト右にわずかにそれました。ロナウドはタックルを受けた足が痛んだようですがPKとはなりませんでした。
危うく難を逃れたオランダ、後半30分、ここで身長190㎝のFWファン・ホーイ・ドンクを投入、パワープレーも辞さない戦術に打って出ました。この作戦が後半41分に実を結びました。
オランダは最後尾からブラジル陣内に放り込んだボールの後処理で、コクーが相手と競り合いながら一瞬早く出したボールが右サイドフリーのロナルド・デ・ブールにわたりました。ロナルド・デ・ブールはまったくフリーの状態で練習時のキックのような正確なボールを入れると、これがゴール正面のクライファートにドンピシャ、クライファートもヘディングシュートーの練習のようなきれいなフォームから、ゴール右サイドに豪快に叩き込みました。
この場面、ロナルド・デ・ブールがまったくフリーの状態でコクーからのボールを受けることになったのは、左サイドバックのロベルト・カルロスが中に絞り過ぎて、自分の背後のスペースをまったくケアしていないためでした。
またクライファートのヘディングシュート、ブラジルDF陣はオランダFWファン・ホーイ・ドンクにアウダイール、クライファートにジュニオール・バイアーノがつく形になっていましたが、どちらも競り合うジャンプができないまま許したシュートでした。
同点となり試合は延長に入りました。すると、今度はブラジル、ロベルト・カルロスが汚名挽回とばかり、たびたび相手左サイドをえぐりゴール前にクロスを入れるプレーを連発、一つ合えばという場面を次々と作り出しました。延長前半3分にはロベルト・カルロスのクロスをGKファン・デル・サールが弾いたところをロナウドがオーバーベッド、ゴールポストをカバーしていたロナルド・デ・ブールが辛くもクリア。
続く延長前半4分には、ゴール前ペナルティエリアの外でボールをキープしたロナウド、DFのマークを交わしながら強烈なシュート、ファン・デル・サールが横っ飛びでパンチング、これもオランダ、難を逃れました。
するとオランダも徐々に盛り返し、延長前半12分、最後尾のフランク・デ・ブールから縦1本が左サイドのクライファートに届きます。これをクライファート、角度のないところからシュート、惜しくもボール半個分、右ゴールポスト脇にそれていきました。
試合は延長後半に入ります。その1分、センターサークルの自陣側で中盤からのパスを受けたロナウドが見せます。ボールを持つとすぐさま反転してドリブルを開始、すぐトップスピードに入ると、前をふさごうとしたDFをかわして突進、あっという間にペナルティエリアに到達しました。あとはGKと1対1になりシュートという場面で、背後からフランク・デ・ブールが決死のタックル、ボールをヒットしてCKに逃れました。一つ間違えばPKと一発退場のオランダ、ここも辛くも難を逃れました。
そのあともブラジルの攻勢が続きましたがオランダもよく凌ぎ、ついにPK戦にもつれ込みました。
GKの比較でいえばオランダのファン・デル・サールのほうがブラジルのタファレルより1枚上という感じでしたが問題はキッカーのメンタル、疲労度、どちらに転ぶかわからないPK戦となりました。
PK戦はブラジル先攻、まずロナウドが強いボールで決め、2人目のリバウドもきっちり決めます。一方のオランダ、1人目のキャプテン・フランク・デ・ブールが落ち着いて決め、2人目ベルカンプも続きます。
ブラジルは3人目にエメルソンを持ってきました。エメルソンは左に飛んだファン・デル・サールの裏をかき正面に蹴り込みました。オランダの3人目はコクー、一度セットしたボールの位置が少しずれたのをレフェリーに指摘され置き直しました。そして蹴ったボールはポストの右方向、いいボールでしたがタファレルの読みと完全に一致、弾き出されてしまいました。
ブラジルは4人目、キャプテン・ドゥンガが方向を読まれながら手の届かない高さに蹴り込み4人連続成功。
オランダの4人目はロナルド・デ・ブール、タファレル、今度は左と読み切ったか、またもボールを弾き出しました。
これで決着、ブラジルがPK戦の末、難敵オランダを退け決勝進出を果たしました。
PK戦に入るまでの試合は、互角に見えましたが実際にはボール支配率などでオランダが上回っておりゲームを支配していたのはオランダでした。しかし準々決勝のアルゼンチン戦で左サイドバックのヌマンがイエローカード2枚による退場処分を受け、この試合出られない影響が出たとも言えます。
オランダはヌマンの控えの選手も負傷していたため、仕方なく右サイドバックのライツィハーを左サイドに回し、本来は中盤のコクーを右サイドバックに配置していたのです。後半開始20秒のロナウドの突破に対応したコクーは懸命にユニフォームを引っ張りながら食い下がりましたが、慣れていない対応か出てしまいました。
辛くもPK戦を制したブラジル、オランダのGKファン・デル・サールはナンバーワンGKの呼び声が高い選手でしたが、ブラジルのキッカーはボールの強さと質でファン・デル・サールに仕事をさせませんでした。ファン・デル・サールは4人目のドゥンガのキックを「もう少しで触れたのに」と悔しがりましたが、ドゥンガが蹴ったボールも、横っ飛びに飛んだファン・デル・サールが伸ばした手の上を通る高さでしたから止められなかったのです。
一方、オランダのキッカーは、タファレルのイチかバチかの読みに捕まるボールを蹴ってしまいました。
ファン・デル・サールの悔しさが物語るように、オランダは試合には勝っていましたが勝負に負けてしまいました。大会屈指の好ゲームはこうして終わりました・
準決勝フランスvsクロアチア戦、フランス、テュラムの2発で決勝へ
翌日行われたもう一つのカード、フランスvsクロアチア戦も勝負の行方が読みにくい試合となりました。フランスは決勝トーナメント1回戦パラグアイ戦で延長後半のVゴール(ゴールデンゴール)、準々決勝イタリア戦は延長PK戦までもつれ込んだ試合を制して、まさに薄氷の勝ち上がりでした。
クロアチアのほうは、決勝トーナメント1回戦ルーマニアとの試合を1-0、ドイツとの準々決勝を3-0で完勝して意気上がる進出です。
両国スタメンを記録しておきます。
・フランス GKバルテズ、DFテュラム、ローラン・ブラン(C)、デサイー、リザラズ、MFカランブー、デシャン、プティ、ジダン、ジョルカエフ、FWギバルシュ 監督エメ・ジャケ
・クロアチア GKラディッチ、DFスティマッチ、シミッチ、ビリッチ、MFスタニッチ、ソルド、アサノビッチ、ヤルニ、ボバン(C)、FWヴラオビッチ、スーケル 監督ブラゼビッチ
試合は前半フランスが押し気味に試合を進めジダンが6本ものシュートを放つなど積極的でしたが、いずれも精度を欠き、前半の途中からは攻め疲れからか、今度はボバンを中心としたクロアチアの攻勢を許しました。結局0-0のまま折り返しましたが、試合は後半直後に動きます。
まずクロアチアが先制します。後半開始わずか30秒という時間でした。右サイド、センターライン少し前で、スーケルからのボールを受けたアサノビッチが中へ切れ込みます。視線の先には左タッチライン際にヤルニが待ち構えています。一方、ボールを出したスーケル、フランス各選手の視線がアサノビッチからヤルニにボールが渡るであろう流れを意識してスーケルから目を離しました。
それをスーケルとアサノビッチは見透かしたようなコンビプレーを見せました。何とアサノビッチはヤルニの方向を向いていながら、自分の斜め後ろ方向にいるであろうスーケルの方向にフワリとしたパスを出したのです。
スーケルはゴール正面でまったくのフリーの状態でボールを受けました。あとはGKバルテズが向かって来るのを見定めて冷静にゴールに流し込むだけ、スーケル万全のゴールシーンでした。
すると、今度はフランスがお返しとばかりのプレーを見せました。スーケルのゴールのあとのキックオフ、フランスがクロアチア陣内に攻め込んだところをクロアチア・ボバンがカット、そのままターンして持ち出そうとした時、少し気を緩めたのでしょうか、背後からフランス・テュラムがボールにチェックをかけると、これがゴール前中央のジョルカエフに渡ってしまいます。するとテュラムはすかさずジョルカエフとのワンツーを意識してゴール前に走ります。ジョルカエフも見事にその意図を察して柔らかくパス、テュラムもGKラディッチが向かって来るのを見定めて、ゴール右側に流し込みました。
スーケルのゴールからわずか1分後、後半1分30秒のことでした。
そこからフランスは優位に試合を進め始めました。後半5分には右CKからのボールの跳ね返りを右から中央から最後は左から次々とボレーシュートを放ちサン・ドニ競技場の大観衆を沸かせます。後半16分にはセンターライン付近の右サイドでボールを受けたアンリが縦に疾走、そのままペナルティエリア内まで持ち込みシュート、若きFWの躍動にまたまたサン・ドニの大観衆が湧きました。
そして迎えた後半24分、フランスは、センターライン付近からジダンが右サイドのテュラムに大きく展開します。テュラムはボールを前に持ち出すとワンツーを要求する走りで縦に出ます。テュラムからボールを受けたアンリは意図を察して前に走り込んだテュラムにボールを出します。しかしボールはクロアチア・ヤルニの網にかかりそうになりました。そこをテュラムはあきらめず体勢を崩したヤルニからボールを奪いました。ペナルティエリアの右角のあたりです。テュラムは迷うことなく、そこからシュートを放ちました。ボールは横っ飛びに飛んだGKラディッチの手をかすめ、巻くように曲がってサイドネットに突き刺さりました。
ジダンからのボールを受けたテュラムの、まさに意図したとおりのゴールでした。シュートが決まったあとのテュラム、膝立ちの姿勢で腕を組み「また決めちゃったよ」といった表情でチームメイトの祝福の渦に消えました。
これでフランスは2点リード、盤石の体制で決勝に勝ち上がるかというところでしたが、後半29分、キャプテンで守備の要、ローラン・ブランが退場処分を受けてしまう事態が起きてしまいました。クロアチアゴール近く左サイドからのフランスのFKの場面でした。クロアチアのビリッチのマークを受けてユニフォームを引っ張られたブランは、それを振り払おうとしてビリッチの口元あたりを手で押してしまいます。押されたビリッチはいかにも額あたりを殴られたかのように大げさに倒れ込みましたが、それを見ていたレフェリーには、明らかにブランのラフプレーと映ったのでしょう。このプレーでレッドカードが出されてしまいました。
試合はそのままフランスが勝ちましたが、ブラジルとの決勝に守りの要、そしてキャプテンのブランを欠くことになった影響が心配される退場劇でした。
3位決定戦、クロアチア、執念の勝利、オランダ、またしても試合に勝ち勝負に負ける
1998年7月11日 オランダ 1 – 2 クロアチア 得点プロシネツキ(ク)14分、スーケル(ク)36分
両国スタメンを記録しておきます。
・オランダ GKファン・デル・サール、DFヤープ・スタム、フランク・デ・ブール(C)、ヌーマン、MFコクー、ヨンク、セードルフ、ゼンデン、エドガー・ダービッツ、FWベルカンプ、クライファート 監督フース・ヒディング
・クロアチア GKラディッチ、DFスティマッチ、ソルド、ビリッチ、MFスタニッチ、ユルチッチ、アサノビッチ、ヤルニ、プロシネツキ、ボバン(C)、FWスーケル 監督ブラゼビッチ
試合は、これまでのオランダの戦いぶりそのまま、中盤を支配して積極的に攻撃を仕掛けたのに対して、クロアチアは守りを固めてカウンターを狙う展開となりましたが、先制したのはクロアチアでした。前半13分、左サイドのヤルニからのパスをプロシネツキが決めました。対するオランダも前半21分、中盤のゼンデンがミドルシュートを決め同点としました。
しかしクロアチアは前半35分にボバンからのパスを受けたスーケルが決めて再びリードを奪います。
後半もオランダの猛攻は続き、合計シュート数はオランダの20本に対してクロアチアはわずか5本、しかしゲームに勝ったのはクロアチアでした。オランダは準決勝のブラジル戦に続いて、またしても試合に勝ってゲームに負けてしまいました。
この大会のクロアチア、FWのアレン・ボクシッチをケガで欠いていましたので、それが守りを固める戦術の大きな要因になったかも知れませんが、ボバン、スーケル、プロシネツキ、アサノビッチ、ヤルニという能力の高い選手を揃えていました。
前にも書きましたが、人口600万人のアドリア海に面した小国クロアチアは、この大会で、その国旗デザイン、チェッカーフラッグとともに一躍世界に名を知らしめました。数年前、厳しい内戦を経験して勝ち取った独立、今回の世界3位は、その新しい国の誇りとなり、国を一層一つにする出来事となりました。
そして、この試合、通算6点目を決めたスーケルは大会得点王のタイトルも獲得、満面の笑顔でチームメイトとともに喜びを分かち合い、3位決定戦でありながら決勝に勝るとも劣らない歓喜のフィナーレとなりました。
実は試合前、準決勝フランス戦で、フランスのキャプテン、ローラン・ブランを退場に追い込む倒れ方をしたクロアチア・ビニッチに対して観客が執拗なブーイングを浴びせるという異様な光景が見られましたが、クロアチアはそれをもバネにして勝ち切ったのでした。
グループリーグで日本が戦ったクロアチア、日本は結構攻撃面でも手応えがありましたが、こうして大会全体を振り返ってみますと、クロアチアにしてみれば日本戦もシナリオ通り、冷や冷やしたとか危なかったという試合運びではなく、極端に言えば日本を掌の上で転がした試合運びだったといっていいのかも知れません。
大会前は、クロアチアとはどれほどの力のあるチームか測りかねた日本ですが、大会が進むにつれ、とてもとても初出場の日本が倒せるような低いレベルではなかったどころか、3位にまで上り詰める強豪だったと思い知ることになりました。
ベスト8で今大会随一の力を持つと言われたオランダに屈した優勝候補の一角・アルゼンチン、そして、そのオランダを3位決定戦で破ってしまったクロアチア、この2チームがグループリーグの相手だったということは、結果、日本のグループリーグ敗退は必然といっても過言ではなかったと思います。
そう思うと、日本のワールドカップ初挑戦は、強豪相手の気の毒な体験だったと思えてきて、少し気持ちが楽になるのを感じます。
一方敗れたオランダ、結局4位で大会を終えましたが、今大会、非常に高い評価を受けました。辛口批評で通っているサッカー評論家のセルジオ越後氏も、サッカーダイジェスト誌に連載しているコラム「セルジオ越後の天国と地獄・第239回」(1998.7.28号)で、オランダを絶賛しました。この日のタイトルは「凄かったオランダ、最高のチームだ!!」
セルジオ越後の批評で、こんな誉め言葉は滅多に見ませんので、ある意味驚きました。本文で何と書いているかといいますと、
「もっとも印象に残ったチームはオランダ、間違いなし、ダントツだ。久しぶりに強いオレンジ軍団を見せてもらった。おそらく日本のファンに強烈なインパクトを与えたはずのこのチームの良さは、何といっても総合的なバランスにある。(中略)」
「左右のバランスがいい、攻撃と守備のバランスもいい、選手層は分厚く、出場停止やケガ人が出てもチーム力がまったく落ちなかった。(中略)」
「そして特筆すべきは、1試合も守備的な試合をしなかったこと、すべて攻撃的にゲームを進めたことだ。(中略)ブラジルやアルゼンチンさえ引かせてしまう迫力は痛快というしかなかった。戦いぶりはいつも自信にあふれてた。」
オランダは、準決勝・ブラジル戦、3位決定戦・クロアチア戦ともに「試合に勝ってゲームに負けた」という結果でしたが、どんなチームをも引かせてしまう迫力は痛快で強烈なインパクトを残したということのようです。
ワールドカップは、時として、魅惑のチームであっても優勝するとは限らない難しい大会ですが、今大会のオランダもそれに当てはまったということでしょう。
決勝は開催国フランスvs前回大会優勝国ブラジル、試合は意外な結末、地元フランスがエース・ジダンなどの活躍で圧勝、体調不良のロナウドを出場させたブラジルを3-0で粉砕、歓喜の開催国優勝
決勝のカードは、開催国vs前回優勝国、欧州vs南米、いわば世界のサッカーファンが期待したとおりのカードになりました。言い換えれば、どちらが優勝してもいい、そんなカードです。
決勝 1998年7月12日 21時キックオフ ブラジル 0 – 3 フランス 得点ジダン(フ)27分, 45+1分、プティ(フ)90+3分 会場、サン・ドニ競技場 天候・晴、気温27.5℃、湿度60%、観客75,000人、主審サイト・ベルコーラ(モロッコ)
両国スタメンと交代選手を記録しておきます。
・ブラジル GKタファレル、DFカフー、アウダイール、ジュニオール・バイアーノ、ロベルト・カルロス、MFセザール・サンパイオ、ドゥンガ(C)、レオナルド、リバウド、FWロナウド、ベベト
(交代)46分レオナルド⇒デニウソン、74分サンパイオ⇒エジムンド 監督マリオ・ザガロ
・フランス GKバルテズ、DFテュラム、ルブフ、デサイー、リザラズ、MFカランブー、デシャン(C)、プティ、ジダン、ジョルカエフ、FWギバルシュ
(交代)57分カランブー⇒ボゴシアン、66分ギバルシュ⇒デュガリー、76分ジョルカエフ⇒ビエイラ 監督エメ・ジャケ
この決勝は、試合開始前からマスコミがざわつきました。試合前にマスコミに配られたブラジルのスタメンにFWロナウドの名がなかったからです。
結局、試合開始直前にはロナウドスタメンと判明しましたが、ロナウドはこの試合、フランスのエース・ジダンの引き立て役でしかありませんでした。
準決勝のオランダ戦で得点を決めPK戦でも最初のキッカーとしてきっちり役割を果たしていたロナウドに何があったのか、それは試合の翌日以降、明らかになっていきました。
一方のフランス、キャプテンのローラン・ブランが前の試合レッドカードを受けたため出場停止、試合前のいつもの幸運を呼ぶ儀式、GKバルテズのスキンヘッドにローラン・ブランがキスをするという姿がこの日は見ることができませんでした。
しかし、試合が始まると、さっそくフランスはジダン、ジョルカエフ、プティを中心とした攻撃がブラジルを攻め立てます。
前半3分、ジョルカエフとのワンツーパスをゴール前で受けたジダンが相手DFの股を抜いてギバルシュにラストパス、ギバルシュはフリーでGKの正面でボールを受けましたが最初のトラップで少しボールが流れてしまい、シュートをゴール左に外してしまいました。ジダンは自陣でボールを受けてからのドリブルとワンツーパスで約60mを走ってのチャンスメイク、本人も今日は調子がいいと実感したのではと思わせるプレーでした。
またジョルカエフもジダンへのリスペクトが強固であることを、この距離の長いワンツーパスが物語っているプレーでした。
一方のブラジル、前半24分、右サイドでカフーがCKを得て、これをレオナルドがキック、ボールはゴール正面のリバウドに、リバウド少し下がりながらもヘディングでミートしたボールがゴール上部へ、これをバルテズ跳びあがってキャッチ、そのままゴールライン上に倒れ込みましたがボールはきっちり両手でゴールラインの外へ置き、難を逃れました。
すると今度はフランスにCKのチャンスが巡ってきます。前半27分、右サイドでブラジルからボールを奪ったテュラムがしぶとくボールをキープ、しかしブラジル、ロベルト・カルロスもすかさず奪え返しましたが、ボールは相手陣内へ、ロベルト・カルロス、ゴールラインを割らないよう追いかけましたが相手にCKを与えてしまいます。
CKを蹴るのはプティ、何度も練習してきたパターンであるかのようにニアサイドに早いボールを送ると、ゴール前一番遠いところにノーマークでいたジダンが、まるでボールの到達地点をわかっていたかのように走り込んできて勢いよくジャンプ、頭でボールを見事に捉え、自分より後ろ側にあるゴールに叩き込みました。
奇しくも両チームの10番同士、24分のリバウドと27分ジダンのヘディング合戦は、文句なしにジダンに軍配があがりました。
ちょうどジダンの到達地点でジダンと競ることになったレオナルドは、結果として競ることになった位置関係で、遠いところからジダンを自由に前に走らせたブラジルの守りが責められる失点でした。
その後、ややフランスが押し気味に試合を進めます。ブラジル・ロナウドは何度かボールを受けて突破を試みますが、ことごとくDFに阻まれ、本来の調子から程遠いことは明らかでした。
前半も終わろうという44分、最後尾テュラムから前線に放り込みのパスが出ました。それが最前線のギバルシュとブラジル、ジュニオール・バイアーノのところに落ちますが、ジュニオール・バイアーノのヘディングがかぶってしまい、ギバルシュが難なくフリーでペナルティエリア内に侵入、まったくのフリーでGKタファレルの真正面から左足でシュートを放ちますが、何とタファレルの正面に打ち込んでしまいます。
これだけ正面からフリーでシュートが打てれば、あわてなくても左右どちらかの隅を狙いすましてゴールを奪えそうですが、何やらグループリーグ3連敗したアジアの初出場国のFWを連想させる凡ミスでした。外したギバルシュのもとには誰が近寄って慰めるでもなく、叱咤するわけでもないポツンと1人、何かをつぶやいている表情が国際映像で大写しになりましたが「どうして自分はこうも運に見放されるのだろうか」とでもつぶやいたでしょうか。もし、そうだとしたら、その理由を次の場面で知ることになります。
実は、天が幸運を授けたのはギバルシュではなく別の選手でした。ですから、ギバルシュの役割は、ここから始まる主役登場の前座に過ぎなかったのです。
新将軍ジダンの誕生、主役の星のもとに生まれたスーパースター
ギバルシュの凡ミスシュートでCKを得たフランス、右CKからプティが入れたボールはファーサイドに流れ、ギバルシュがキープしてゴール前にグラウンダーのクロスを入れましたが相手DFがクリアして、今度は左からのCKに変わります。
すでに前半ロスタイム、蹴るのはジョルカエフ、1点目と同じく今度もジダンは密集の中にはおらず、ペナルティエリアのライン付近にブラジル・レオナルドと2人だけでいました。しかしジョルカエフが助走を始めたと同時に、ジダンはレオナルドの後ろから全力でニアサイドに走り込みました。その途中、走り込んできたジダンに気づいたドゥンガが身体を寄せようとしましたが、ジダンのスピードとパワーに振り切られ、哀れにも吹っ飛ばされ、ピッチに転がされてしまいました。ドゥンガが転がされた場面、レフェリーは見える位置にいたのですが、目線がCKのジョルカエフのほうからゴール前の密集には戻っておらず、どうしてドゥンガが転がったのか、わからなかったのかも知れません。こうした、ちょっとした行き違いが歴史的なプレーとして永遠に残るところがワールドカップの摩訶不思議なところです。
ドゥンガを蹴散らしたジダンは、ジョルカエフが蹴ったボールの軌道を見定めて、ここだと思った地点で立ち止まります。
ボールは寸分違わずジダンの方向に向かって飛んできました。ジダンの前ではブラジル、ロナウドが後ろ向きになりながらクリアに飛び、それに合わせるようにフランスのプティも飛びました。
しかしボールは2人には当たらず、その陰で待ち構えていたジダンがジャストミート、ボールはゴール左、ゴールラインの前で構えていたロベルト・カルロスの股間を、目にも留まらぬ速さできれいにすり抜けて弾み、ゴールに吸い込まれていきました。
何というデザインされたセットプレーでしょう。1点目の右からのゴールといい、この2点目といい、まさにジダンのヘディングのためにデザインされたゴールとしか言いようのないファインゴールでした。
それにしてもブラジルのジダンに対する無警戒ぶりにも少し驚きます。1点目以降、CKの時のジダンの位置取りははっきりしているのですが、まったくケアがされていませんでした。辛うじて気づいたドゥンガが転がされてしまっては、どうしようもありません。そういう状況を作ってしまい、主役の座に就く星の下に生まれるのもスーパースターの条件なのかも知れません。
紛れもなくフランスの新将軍・ジダン、フランスワールドカップの主役・ジダン誕生の瞬間でした。
この一連の流れの前に絶好のチャンスを逃したギバルシュの役割とは、フランスの控えストライカーの切り札でも何でもなく、新将軍・ジダンを引き立てるための道化役でしかなかったのです。フランスワールドカップの主役の星の下に生まれたジダンの完璧なゴールシーンに目を奪われながらも、主役登場の前の道化役のようだったギバルシュの凡ミス、彼もまた、自らがそういう星の下に生まれた運命(さだめ)にあったことを痛感したかも知れません。
前半のロスタイムに生まれたフランスの2点目、願ってもない時間帯に追加点を奪い前半を終了します。
ワールドカップ連覇を狙うブラジルも、このままでは終わりたくありません。後半からレオナルドに代えてデニウソンを投入、かき回しにかかります。フランスのほうは前がかりになる必要がなくなりましたから、しっかり守りを意識してカウンターを狙う戦法に切り替わりました。
ブラジル、デニウソン投入の効果がすぐ表れます。後半10分、左サイドをドリブルで突破にかかるデニウソンをカランブーが斜め後ろからタックル、カランブーにはイエローカードが出てブラジル、ペナルティエリアの手前10mの地点からFKのチャンス、これをドゥンガが外側に回り込んだロベルト・カルロスにパス、これをロベカルがクロス、ボールは右サイドで待ち構えていたロナウドに渡ります。ロナウド、この試合初めてといっていいチャンス、角度のないところでしたがシュート、しかしBKバルテズの正面、彼を弾き飛ばすほどの威力はなく、がっちりキャッチされてしまいました。
フランスは、すぐさまイエローカードをもらったカランブーをさげ、左サイドのロベルト・カルロスとデニウソンの連携対策として守備的MFのボゴシアンを入れました。
後半17分、またギバルシュに決定的なチャンスが訪れますが、やっぱり決められません。とうとう後半21分、デュガリーと交代となりました。思えば今大会のフランス、初戦の南アフリカ戦ではデュガリーが先発、フランスの今大会最初のゴールをあげたのですが、第2戦でデュガリーはケガ、デュガリーの代役を誰にしようか3人試したあげく、第3戦の途中から出場したギバルシュがここまで務めてきました。
デュガリー以外に頼れるFWがいないフランス、ケガあがりのデュガリーを使うしかないという感じでした。
後半22分、フランスがカウンター攻撃を仕掛けます。上がっていったのはDFデサイー、前方に出たボールを追ってブロックに入ったカフーに後ろからチャージ、これがイエローカードとなりこの日2枚目、退場処分となりました。
ブラジルは後半28分、守備的MFサンパイオを下げFWエジムンドを投入、攻撃の圧力を強めようとしますが、10人となったフランスは、ますます守り中心の布陣に切り替えます。後半30分には最終ラインに下がったプティのポジションにヴィエラを入れ、中盤のジョルカエフをベンチに下げます。
ブラジルは数的優位を生かし中盤を支配、攻撃の場面が増えますが最終ラインではオフサイドの網にかかったり、DFに止められてなかなかシュートまで持ち込めません。逆に後半37分、前がかりになったスキを突かれジダンからデュガリーにパスが出ます。
デュガリー、GKと1対1の絶好の場面を迎えました。しかし久しぶりのピッチでシュートの感覚がまったく戻っていなかったか、右足から放たれたシュートは無情にもゴール左に外れてしまいました。
残り時間が刻々と少なくなる中、ブラジルはデニウソンやエジムンドが必死にドリブル突破を試みますが、ことごとくフランスDFの網にかかりなすすべがありません。ロスタイムに入って25秒、そのエジムンドからデニウソンにスルーパスが出ました。ゴール左側、GKとの距離わずか5mのところからデニウソンの左足、強烈なシュートが飛びました。しかしボールはバーの上をこすりながら通過、これも実りませんでした。
そして、いよいよ決勝は、フィナーレを迎えます。歓喜のホイッスルの前に、もう一幕残っていました。
後半ロスタイム1分半を過ぎたところでブラジル・リバウドが遠目から打ったシュートが相手DFに当たりCKとなります。左からデニウソンが蹴ったCKは、フランスが回収、ボールを持ったデュガリーがゆっくりと前に運びます。デュガリーの右横からヴィエラが追い越すように上がりましたが、もう一人、ペナルティエリア内にいたエマニュエル・プティが全力で前に走り出し、センターラインを越えたあたりでデュガリーを追い越し、2人残っていたブラジルDFの間に割って入ろうとします。
するとデュガリーは右前方のヴィエラにパス、前のDF2人の目がヴィエラに引き付けられたのを見計らってプティはオフサイドにかからないよう、2人のDFの間に位置をとりました。そこにヴィエラからスルーパスです。ペナルティエリア内、左45度の角度から、出てくるGKタファレルの位置を見極めてゴール右隅を狙い落ち着いてシュート、ボールはゆっくりとゴールに吸い込まれていきました。
時すでに後半ロスタイムに入って3分経過、まさにフランスの優勝を告げるホイッスルがなる直前、華を添えるダメ押しの3点目でした。プティは、前でボールをキープしたのが足を痛めている感じのデュガリーでしたので、もし相手にボールを奪われてショートカウンターを食らったら大変、これは自分がフォローにいかなければと全力疾走を始めたのだと思います。
ところが、意外にもブラジルの反撃意欲は弱く、デュガリーが順調に上がり始めたので、このまま行っちゃえとばかり走り続けたのではないでしょうか。
もし、フォローがプティ1人だけでしたら、ゴールまで持ち込む展開にはならなかったと思いますが、若いヴィエラも同じ意識を共有してサポートに走りブラジルのDFを引き付けて、自陣から約80m走ってきたプティにラストパスを送ったのです。まさに絵にかいたようなカウンター攻撃にブラジル守備陣はお手上げのまま試合を終えるしかありませんでした。
こうして主役・ジネディーヌ・ジダン、脇役・プティ、ジョルカエフ、引き立て役・ブラジル、ロナウド、フランス、ギバルシュらによる、開催国フランスの初優勝の劇場は大団円を迎えました。
トリコロールの勇者・優勝パレード、ジャンゼリゼ通りに120万人? ラ・マルセイエーズの歌声パリの街に響き渡る
フランス代表が勝ち進むにつれ、フランス国民のボルテージは日毎に高まっていきました。決勝戦の日は、パリ市庁舎前に設置された巨大スクリーンを前に数万人の人たちが集結、優勝の瞬間を見届けました。その夜の凱旋門に優勝スコアが電光表示され、出場停止で出られなかったキャプテン、ローラン・ブランの顔が大映しで浮かび上がる中、ジャンゼリゼ通りには100万人もの人々が繰り出し、夜を徹して優勝を喜び合いました。
そして優勝を決めた翌日は、パリの街中にフランス国旗・トリコロールの旗が心地よい風になびく中、トリコロールの勇者・フランス代表の優勝パレードが行われました。
凱旋門からコンコルド広場に続く幅77m、距離にして約2kmのシャンゼリゼ大通りには計測不能の人々が集まり、120万人とも150万人とも言われました。
人々は二階建てバスに乗り込んだエメ・ジャケ監督、ジダンらとともにフランス国歌ラ・マルセイエーズを合唱、ブラン、デシャン、ジダンらが代わる代わるワールドカップトロフィーを高々と掲げるたびに、地鳴りのような歓声に沸き立ちました。
シャンゼリゼ大通りがこれほどの人々で埋め尽くされたのは歴史上初めてのことと言われ、興奮と熱狂は翌日7月14日のパリ祭(フランス革命記念日)も続きました。パリ祭でフランス軍隊のパレードが行われましたが、ジャケ監督とデシャン選手がワールドカップトロフィーとともに登場、観衆はフランスの英雄にあらためて大きな喝采を送りました。
こうしてフランス国民は、開催国として優勝を果たしてワールドカップサッカーの喜びに存分に浸ったのでした。
ザガロ体制の誤算、ジーコのスタッフ加入、ロマーリオの落選とロナウドの急変
ブラジルは、試合開始1時間前にロナウドの名がないメンバー表をフランスに渡しました。そのため、このニュースは試合に先立ち世界中に打電されました。しかしザガロ監督はロナウドの懇願もあり、試合に出すことを決め、一度エジムンドと書いてフランスに渡していたメンバー表をフランスの了解を得て、試合開始前45分に書き直したのです。
実は、決勝当日の朝、宿泊先のホテルで卒倒しているロナウドを、同室のロベルト・カルロスが気づいて、あわてて監督・ドクターに急変を告げたのです。これでブラジル代表はチーム全体がパニック状態に陥ってしまいました。その後、ロナウドは平静を取り戻したことから、監督に先発出場を願い出て、結局スタメン出場したのですが「怪物の抜け殻」のような状態で、エースを失ったブラジルは、もはやフランスの敵ではなくなってしまったのです。
ロナウドの急変は、何も原因がなかったところに生じたものではなく、それまでに彼が受けていた、ある意味、常軌を逸したプレッシャーの結果生じたものだと言われています。
それは、どの大会でも優勝を求めるブラジル国民、メディアからの期待とプレッシャーに加え、彼を商品としてみているエージェント(代理人)からのプレッシャー、そして、もっと強烈にプレッシャーをかけたのがスポーツ用品メーカー「ナイキ」だったと、Number誌別冊・NumbberPLUS August1998の中で、マーティン・ヘーゲレ記者が次のように書いています。(翻訳・安藤正純氏)
「W杯優勝を契機に、一気にビジネスの世界で優位を確保するため、ナイキはロナウドにこう言って迫ったという。『優勝を保証してくれ。決勝戦では最低でも2点を取って、スーケルと並んででもいいから得点王になってくれ』」
「期待されるのは悪いことではないが、過度になればなるほど心は蝕まれるものである。ロナウドは心の病に冒されてしまった、と言えまいか」
時としてスポンサーという存在がスポーツチームに大きなプレッシャーになるというのは、よく知られていますが、個人選手レベルにこれほどのプレッシャーがかけられているサッカービジネスの巨大さ、恐ろしさをあらためて痛感します。
ブラジルについては多くの専門家が優勝はおろか、上位進出も難しいのではないかと見ていました。それは、特にDFに脆さがあり組織プレーも確立されていないためという理由でした。ですから決勝まで勝ち上がったのは、むしろ驚きを持って見られました。
ロナウド、リバウド、デニウソン、カフーら個人技の高さは抜きん出ていましたが、それらが不発に終わった場合は決勝のように見る影もないチームになるというわけです。
前回大会で優勝を果たしたブラジルですが、指揮をとったパレイラ監督のサッカーは、魅惑的で華麗なブラジルサッカーとは程遠いという批判を浴び、パレイラ監督をアシスタントコーチとして支えていたザガロ氏が、かつての夢をもう一度ということで監督に再登板した経緯があります。
ザガロ監督の最初の目標は1996年アトランタ五輪での金メダル獲得でした。サッカー界の王者ブラジルが唯一手にしていないタイトルが五輪の金メダルだったからです。
ところがこの目標は思わぬ躓きで狂い始めました。アトランタ五輪グループリーグの初戦、日本戦に0-1で敗れるという不覚をとったのです。
歴史を辿ると見えてくるものがあるとすれば、この日本戦での不覚が、栄光に包まれたザガロ監督神話崩壊の序章だったと言っても過言ではありません。
アトランタ五輪では結局、準決勝でナイジェリアに敗れ銅メダルに終わりました。そして1998年フランスワールドカップに向かいます。ロナウドが次第にフル代表の主軸として定着すると、そこにロマーリオが加わり、RO-ROコンビという新たな魅力によってブラジルの前途は明るいかに思われましたが、逆にRO-ROコンビ頼みという弊害が表れ、チーム力が落ちてしまいました。
特にワールドカップイヤーに入った今年2月に行われた北中米カリブ海サッカー連盟主催のゴールドカップサッカーでアメリカに敗れる事態になり、あわててブラジルサッカー協会は、ジーコをテクニカルディレクターとしてザガロのサポート役につけましたが、これが選手たちに「ザガロ監督は協会の信頼を失っているのか」といった余計な動揺を与えることになり、決して効果的な対策とは言えませんでした。
そして大会登録メンバーの最終的な絞り込みの中で、ブラジル代表からは3人の有力メンバーが代表落ちとなったのです。MFジュニーニョ・パウリスタ、MFフラビオ・コンセイソン、そしてFWロマーリオです。
3人ともケガ、このうちロマーリオについてはコンディション不良もあって、という説明が付きましたが、最後の最後、フランスに入ってからの代表落ちは、まるで日本代表からカズ・三浦知良選手が外れたのと似たような衝撃をブラジルサッカー界に与え、世界中に与えた衝撃度から言えば、むしろ最大のニュースとなったのです。
ロマーリオが落選発表直後の会見で涙ながらに「自分は十分やれるのに」と訴えた場面は世界中に打電されましたが、ロマーリオの落選に衝撃を受けた選手がもう一人いました。それはロナウドでした。
彼は、ロマーリオとコンビを組むことによって精神的に安心してプレーに専念できる状況にあったのですが、そのロマーリオを失ったことで、いわば心の支えを失った不安感に陥りました。
つまり、日本でカズ・三浦知良選手が外れたことによって社会に大きな衝撃が走ったと同時に、FWの軸に指名されていた城彰二選手のメンタルにも大きな衝撃を与え、心の支えを失った不安感から来る不調に陥ったと同じことがブラジル代表内でも起きていたのでした。
もともとジーコテクニカルディレクターや、キャプテン・ドゥンガ、サンパイオ、レオナルドなど、日本と縁が深いブラジル代表は、アトランタ五輪の初戦や、ロマーリオとカズ・三浦知良選手のことで、ますます奇縁を深めているような気がします。
こうした、いろいろな事情を抱え込んだままフランスワールドカップに臨んだブラジル、勝ち進みはしましたが、結局、中盤のパスワークで崩すサッカーとは程遠い、GKタファレルのファインプレーを含めた個人技頼みのサッカーで決勝まで辿り着いたに過ぎなかったのです。
そして決勝、ザガロ監督は、試合前の控室で血の気が引いて青ざめているロナウドを、それでも使うことに決めました。結局ロナウドと心中することにしたのです。しかし、すでに書いたように「怪物の抜け殻」がピッチを右往左往しているブラジルは、鉄壁の守備力と連携のとれた組織力を誇るフランスの敵ではなかったのです。
しかし、次は日韓大会、ブラジルがこのまま黙って引き下がるでしょうか? 日本とは殊のほか関わりが深いこの国が、2002年に見せてくれるサッカーを楽しみにせずにいられましょうか。
「気の抜けたシャンパンサッカー」と批判にさらされたエメ・ジャケ監督、4年がかりの揺るぎないチーム作りが花開く
1990年イタリアW杯の出場を逃し、1994年アメリカW杯も「パリの悲劇」で出場を逃した1998年開催国フランス。
1994年、フランスは、シャンパンサッカーと評された攻撃的なスタイル、個人技に頼ったスタイルを捨て、攻守のバランスと組織力の強化を重視したエメ・ジャケ監督に向こう4年間のチーム作りを託しました。
1994年5月、キリンカップサッカーで来日したフランス代表には、エリック・カントナ、ジャン・ピエール・パパン、ジノラといったスター選手が加わっていましたが、エメ・ジャケ監督は、それらの選手を、個人技に頼ったスタイルの象徴と考え、徐々に外したチーム作りを進めました。
そして、ローラン・ブラン、マルセル・デサイー、ジネディーヌ・ジダン、ティディエ・デシャン、ユーリ・ジョルカエフ、エマニュエル・プティらを中心としたチーム作りが功を奏し始めたものの、マスコミからは「気の抜けたシャンパンサッカー」と批判にさらされました。1996年欧州選手権ではベスト4に進出しながら「ジャケ不要論」まで飛び出す始末です。
しかし、ここでフランスサッカー協会は一貫してエメ・ジャケ監督を擁護、チーム崩壊につながる動揺を食い止めました。(今回初出場した日本の岡田監督は、大会後のコーチカンファレンス(代表監督会議)で、このフランス協会のマスコミ対応を知り、日本でもかくありたいと語ったことは前にご紹介しました)
迎えた今大会、決勝T1回戦のパラグアイ戦では延長Vゴール(この大会はゴールデンゴールと呼んだ)、続く準々決勝イタリア戦はスコアレスドローの末PK戦、2試合続けて冷や冷やものでしたが、鉄壁の守備力と連携のとれた組織力で乗り切りました。
結局、ジャケ監督のチーム作りは、軸となるFWの不在という課題は残したものの、今大会、ゴールを記録した選手は9人に達しベスト4進出チームの中でもっとも多い、いわば、どこからでも点がとれるチームに仕上げたとも言えます。
またGKバルテズ、そしてブラン、デサイー、テュラム、リザラズの不動の4バックとデシャン、ブティのボランチを中心とした守備力、連携のとれた組織力が、決勝で、最終的にはブラン、デサイーの2人を欠いてもなお崩れない強さを見せ、ここでもまたジャケ監督の、鉄の意思によるチーム作りの正しさが証明されました。
このジャケ監督が、開催国というプレッシャーを跳ねのけて優勝を果たした最大の功労者であることは疑いの余地のないことですが、そういうチーム作りを可能にしたのは、フランスサッカー協会が20年以上前から始めた全国レベルでの選手育成システムが成果をあげ始め、さらにはトップレベルの選手のフィジカル強化プログラムが成果をあげているためだと評価されています。
日本は、たまたま次回の開催国ということと、フランス出身のアーセン・ベンゲル監督の知己もあって、今回フランス大会を機にフランスサッカー協会との親交を急速に深めることになりました。
かつてはドイツが日本サッカーのお手本だった時代から、選手育成、指導者交流を含めてフランスとの関係を強めていくことになったのは時代の必然なのかも知れません。
出場国が32ケ国に拡大され全試合数が64試合に増えて初めての大会、その成果と課題
試合数は増えても観客動員数は前回アメリカ大会に及ばず、しかしコンパクト感があり前回大会のような選手軽視、商業主義などの批判は出ず
今大会は、出場国が32ケ国に拡大されて全試合数が64試合に増えて初めての大会でした。しかし収容人員40000人以下のスタジアムも多かったことから、総観客動員数は278万5000人、1試合平均43,517人と、前回アメリカ大会の総数約358万7000人、1試合平均約68,990人をそれぞれ大幅に下回りました。
それでも前回アメリカ大会が広大な国土に分散した会場のため各国チームが移動に苦労したり、欧州のテレビゴールデンタイムの放送に合わせるためキックオフ時間が正午など、選手の試合環境を無視した商業主義に毒された大会だったのに比べて、フランスの場合、国土自体がコンパクトであり、各国チームの移動もさほど過酷な条件にならなかったという点では好評でした。ただ、季節的に6月は気温が上がり、かなり体力を奪われる条件の試合があったことも確かでした。
世界中でテレビ観戦した人は述べ370億人と言われ、地球上最大のスポーツイベントの関心の高さが、この大会にも現れました。
スーパースター・ジダンの誕生
開催国フランスが初優勝、史上7ケ国目の優勝国となりました。今大会は、そのフランスから1人のスーパースターが誕生した大会として永遠に記憶されることになるでしょう。
その選手は、フランス代表の背番号10、アルジェリア系フランス人のジネディーヌ・ジダン、26歳。出身地の地名をつけて「マルセイユ・ルーレット」と名付けられた、身体を回転させてボールを扱う技に代表される華麗なボールタッチ、なかなかボールを取られない懐が深いボールキープ、意表を突くラストパスなど天才的なプレースタイルが今大会、世界中の人々を魅了しました。
また、正確なシュート、一瞬でマークを外してしまうスピードあふれる身のこなし、強烈なヘディングなど万能型の司令塔であることも披露しました。
一方で、寡黙な中にカッと熱くなる性格を隠した人間臭いプレーヤーという面も明らかになりました。今大会も2戦目サウジアラビア戦で相手選手と交錯した際、倒れた相手選手を跨いだ足で相手選手の腹部あたりを踏みつける動作を見せました。これが目の前にいたレフェリーによってレッドカードと判定され、2試合出場停止処分を受けたのです。
しかし、最後は優勝を手繰り寄せる圧巻の2ゴール、まさに天才の名を欲しいままに躍動してスーパースターの座に上り詰めました。
かつてマラドーナがそうであったように、フランスの子供たちはもとより世界中の子供たちが「マルセイユ・ルーレット」を何度も練習する、憧れの選手、目標となる選手になったのです。
これまでフランスに君臨していたのは、初代・将軍と呼ばれたミシェル・プラティニでした。プラティニは欧州選手権こそ制覇しましたがワールドカップでは3位が最高成績でした。いまジダンは完全にプラティニを越えて新将軍の座に就いたのです。
このあと、しばらくジダンの時代として、数々の素晴らしいプレーで世界のサッカーファンを魅了していくに違いありません。
若いFWの躍動、スーパースター候補だったロナウドの屈辱と挫折
今大会、若いFWの躍動が目に付きました。イングランドのマイケル・オーウェン18歳、フランスのダビド・トレゼゲ20歳、フランスのティエリ・アンリ21歳、ブラジルのロナウド21歳、オランダのバトリック・クライファート22歳。
ちなみに大会最年少出場選手はカメルーンのエトー、のちにカメルーンのエースストライカーに成長する彼が、この時まだ17歳、グループリーグ第2戦のイタリア戦で後半21分から出場、ワールドカップデビューを果たしました。
FWではありませんが、日本の小野伸二選手はエトー、オーウェンに次いで3番目に若い年齢でデビューを果たしています。
ブラジルのロナウドは、ここ2年間、サッカー界をもっとも沸かせ「怪物」のニックネームも付けられた、今大会のスーパースター候補の一人でした。
さきに書いたように決勝当日朝の急変により、決勝では「怪物の抜け殻」と揶揄される存在感のなさで、ジダンの引き立て役に回ってしまいましたが、サッカーダイジェスト誌98.7.29号は彼の未来を予言する次のような文を寄せて、今大会の彼を労いました。
「一度も出場できなかった前回大会(注1994年アメリカワールドカップ)から4年、その間世界最優秀選手に2度も輝いた恐るべき21歳は、自らがもっとも求めていた最高の舞台で、最大の屈辱と挫折を味わった。神は、怪物に最後の試練を与えた。」
「だが、それもまた、神の心憎い演出かも知れない。この男が本当に輝くのは、21世紀こそふさわしい。時代は新たなるジェネレーションの、新たなるセレソンを求めている。」
新しいジャッジ基準の適用、後方からのタックルに対する罰則の厳格化、日本からはもう一人の岡田氏、レフェリー・岡田正義氏がW杯審判団に選ばれグループリーグで主審を担当
ワールドカップでは、FIFAがジャッジ基準を変更する場合、しばしば新しい基準のお披露目となることがあります。
今大会からは、特にボールを持った選手に対して後方からタックルを仕掛けるプレーが大けがにつながると指摘されていたことから、後方からのタックルに対しては一発レッドカードの対象とすることが決められ開幕戦から適用されました。
この厳罰化の不名誉な第1号となったのは、大会4日目、グループリーグE組の韓国vsメキシコ戦、韓国の河錫舟(ハ・ソッチュ)選手でした。(グループリーグの項で紹介済み)
このほかのジャッジ基準では、前後半のロスタイムの表示が決められました。のちに「アディショナルタイム」という呼称になった「余分な時間」の管理、それまでは主審のみが把握していて、選手や観客には示されていなかったのですが、この大会から時間が1分単位(秒単位は切り捨て)で、主審から予備審判(のちに第4審判の呼称)に伝達され、予備審判が場内に表示する方式が採用されました。
この変更は、前年に行われたワールドカップアジア最終予選の日本vsUAE戦において、負傷者があって多少多めに取られるはずだったロスタイムが極端に短く、日本代表サポーターが猛抗議した出来事がきっかけになったといわれています。
この説を裏付ける資料は手元にはありませんが、もうそうであれば、日本のサポーターが明確な意思表示をしたことでFIFAの競技規則を変えたことになり歴史的な役割を果たしたと言えます。
この大会、日本人レフェリーの岡田正義氏が審判団に選出されました。岡田レフェリーはこの時40歳、日本代表が歴史的初戦・アルゼンチン戦を戦った翌日、グループリーグG組の初戦、マルセイユで行われたイングランドvsチュニジア戦で主審を任されました。岡田レフェリーは冷静なジャッジで試合を裁き、イングランドに対してイエローカード1枚、チュニジアに対してイエローカード3枚を出し、退場者は出さずに2-0でイングランドが勝利した試合を終わらせました。
ちなみにワールドカップで主審を務めたのは、1986年メキシコ大会、1990年イタリア大会と二度のワールドカップで主審を務めた高田静夫氏以来2人目となりました。
偶然にも日本代表監督と国際主審、2人の岡田氏がフランスワールドカップの舞台にたったことになります。
日本人サポーターの多くが巻き込まれたチケット問題とその教訓
今回のワールドカップ、日本が初出場ということで、多くの日本人サポーターが旅行代理店などを通じて申し込み、フランスへの出発を楽しみにしていた矢先、開幕となる6月10日直前になっても、日本戦観戦ツアーの申込分の一部のチケットが旅行代理店に到着しない事態が発生、一気に大問題になったことは、すでに書きました。
原因としては、日本人サポーターのツァー募集数と実際の入場者数から、存在しないチケットに対して予約を受け付け予約金をだまし取ったと見られる「空売り」や「二重契約」といった悪質な詐欺行為の存在が明らかになっていました。
この問題は、日本人サポーターだけがだまされたものではなく、ブラジルなど多くの国のサポーターが巻き込まれたもので、数少ないフランスワールドカップの失態の一つとなりました。
結局、チケットを持たないまま現地に向かった日本人サポーターは、旅行代理店や本人が奔走して高額に跳ね上がったチケットを入手するはめになったり、結局入手できずスタジアム観戦を断念せざるを得ない人も出ました。
それでも特に初戦・アルゼンチン戦の開催都市トゥールーズ市は、こうしたサポーターの苦境を救うべく市内に大型画面を設置した観戦エリアを用意してくださり、飲み物や軽食まで提供する「もてなし」を用意してくださいました。
サッカーを愛してやまないサポーターたちが見られない心情を理解してくださる「サッカー文化」が生活に根付いた国での開催であることに救われたケースでした。
この一連の事件により、FIFAは不正を働いた疑いが強いとして、カメルーンとコロンビアのサッカー協会を調査、またFIFAのゼップ・ブラッター次期会長は、悪質なブローカーの存在を許した主催者側の不備を認め、次大会以降のチケット販売は、大会開催国の組織委員会が扱うのではなく、FIFAの直接管理下で販売する方針に切り替えました。
つまり世界各国のサッカー関係者の中には、こうしたビッグイベントを自らの私腹を肥やす場としか考えない輩がいることも明らかになった大会でした。
次大会といえば2002年日韓W杯になります。この方針変更は、新たなチケット販売システムということで、慣れないFIFAの不手際が表面化して、新たな問題を引き起こすことになろうとは、この時はまだ誰も予測できませんでした。
サッカーと向き合っているのではなく、サッカーが日常に溶け込んでいる「本物のサッカー文化」を体感
大会期間中、多くのジャーナリストが現地に入りましたが、その中で日刊スポーツ評論家の肩書で取材をしていたセルジオ越後氏が、98.7.14付け同紙に、大会全体を通して感じたフランスをはじめとした欧州の「サッカー文化」、いわば「本物のサッカー文化」について次のようなレポートを寄せています。日本がこれから目指す「本物のサッカー文化」を考える上で示唆に富んでいます。
「サッカーは文化なんだ。地元のフランスと前回優勝のブラジルとの決勝を見て、その思いを強くしたよ。(中略)この2つの国のサッカーが強いことをあらためて認識した。そして、強い理由が、サッカーが文化として根付いているからだということも再認識できたな。」
「シラク大統領は、毎試合代表のユニフォームを着てフランスを応援していた。政界や財界、老若男女、だれもが声を出して、代表をバックアップし、大会を楽しんでいた。サッカーに向き合うのではなく、サッカーとともに歩む、単なるブームではなく、人々の心がサッカーとともにある。だからこそ文化なんだ。」
「かつてのペレやガリンシャ、ベッケンバウアー、クライフ、彼らはサッカーやスポーツの枠を超えてみな国民の英雄だった。プラティニやジーコもそうだ。国民に愛され、親しまれ、厳しい目にさらされたからこそ、彼らは強くなれた。今の日本の代表選手に、本当の意味での英雄はいるかな。英雄を作り出す土壌が、まだ日本にはないんだよ。」
こう書いたセルジオ氏は、4年後のワールドカップには、今大会飛び出したロナウドやオーウェン、クライファートなどの若い英雄候補が日本と韓国にやってくるけれど、果たして彼らをどう迎えることができるか試されると述べています。
「彼らと、単なるよその国の選手として向き合うだけか、それとも、英雄候補たちのプレーを心から楽しみ、厳しい目で見る、心からサッカーとともにある日韓大会にできるか」というわけです。同氏は最後にこう書いていました。「もう、日韓W杯開催まで4年しかないんだ」
確かに優勝したフランスの、当日夜から翌々日パリ祭の日までのパリのシャンゼリゼ通りの人出を見ると「本物のサッカー文化」というのはこういうことなんだ、と痛感させられます。日本代表がフランス大会で戦った試合のたびに、新宿・歌舞伎町の大型ビジョン前に1万人もの人たちが詰めかけて、勝負の行方を見守ったりした状況を見て「日本にもどうやらサッカー文化の芽がふいた」と喜んだものですが、シャンゼリゼ通りの人の数といったら、それこそ桁違いです。まさに「心からサッカーとともにある」というのは、こういうことなんだと実感させられます。
そして、それはまた、その国で実際にプレーしてサッカーを楽しんでいる人たちの層の厚さ、そのプレーの質の高さともシンクロしているんだということを、日本代表GK小島伸幸選手が教えてくれました。小島選手は結局本大会での出場機会がありませんでしたが、それと同じぐらい貴重な体験をフランス3部リーグの混成チームとの練習試合でできたと話していました。
小島選手のこの時、このチームのGKが試合開始早々ケガをしてしまい、急遽代役でGKを務めたわけですが、そこで感じたことを語ってくれていました。
「試合をしていて、フランスのサッカーの奥行き、というか、伝統というか、とにかく強いはずだわ、って思っていましたね。あれで、もっともっとフィジカルを作って、技のレベルが上がって、コンディショニングをいれると、それが代表のあるべき姿で、彼らはその姿のもっとも原初的な部分なんですね。でも、太い脈でつながっている。どこかの知らないチームがポッと出て来て日本とやってるわけじゃあなかった。」
「日本では、といえば、別にそれがいい悪いではなくて、Jリーグだって、獲得している外国人選手や監督によって、やることが全然違うわけですよ。もうベクトルからして。高校生、アマチュアなんでもう代表とは何の関係もない。そういう中でやっているわけじゃないですか。代表だって、ブラジル人がやった時、日本の監督の時、それぞれに選ぶメンバー以上にやり方が違う。華やかな戦術はあっても、張り子のトラ、みたいなところがあるんじゃなかろうか、と。これが『サッカーにおける伝統』ってことなのか、と。それには本当に新鮮な驚きを感じました。」
「あれほどのことが勉強できるとは思ってもみませんでしたし、もし自分が代表のサブじゃなかったら、相手方の助っ人にならなかった、ああいうふうに、彼らの後ろからそれらを感じ取ることは絶対にできなかったと思うんです。(中略)」
「ええ本当に、すばらしい収穫の・・・・一応、私にとっての『Aマッチ』ということにしておきましょう。」
このセルジオ越後氏の示唆と、小島伸幸選手の経験が教えてくれているのは、サッカーがこの日本に文化として根付き、英雄を生み出す土壌が出来るまでは、まだまだ長い年月が必要だろうということです。でも、日本にも、少しづつJリーグのある街が増えていって、その街の人々の心がサッカーとともにある、地元サッカークラブとともにある、地元クラブとともに歩んでサッカーのプレーも楽しんでいるという姿が増えていけば、いつの間にか、日本全体として、子供たちから高校生、アマチュア社会人に至るまで、自然と同じベクトルでサッカーを楽しんでいる、そうやってサッカーが文化として根付いていくだろうという手応えは持てます。そう希望を持っていきたいと思います。
グローバル化社会、多民族共生社会という現代世界の縮図、開催国フランス代表がワールドカップで示した姿
ワールドカップは、激動する世界の「いま」を映し出す鏡とも言われます。今回もまた、グローバル化が進行し、多民族共生社会を受け入れていかなければならない現代にあって、フランスワールドカップで、開催国フランス代表が示した姿は、まさに現代世界の縮図だと指摘した議論がありました。
さきにご紹介した98.10.17放送NHK教育「未来潮流」の中で、そのことが議論されていました。その部分を収録します。
セルジオ越後氏 今回のフランス大会で強豪国がとった戦術は、まず負けない戦術の徹底、相手国の必勝パターンの徹底的な潰し、キーマンとなる選手潰しがまず最優先となり、起用される選手もその基準で決まる。そして次に、勝つ戦術を加える。それを、どれだけ組織的に高められるかが大会での成績に直結している。
相変わらず高い身体能力を誇ったアフリカ勢も組織サッカーの前に押さえこまれたし、スーパースター候補だったロナウドも最後は封じ込まれた。組織サッカーを究極まで高めたフランスとオランダが勝ち進んだことが、現代サッカーの潮流であることを示している。
今福龍太氏 相手国の必勝パターン潰し、キーマンとなる選手潰しが顕著に見られ始めたのは前回アメリカW杯大会からだという気がする。特に決勝のイタリアvsブラジル戦はその最たる試合で結局相手に点を与えないことを最優先にしてPK戦までいった。
山崎浩一氏 サッカーというゲームは本当に変なゲームだ。最初からパラドックスを孕んでいる。(注・一見単純そうで簡単なスポーツに見えるが、守りをおろそかにしては勝てないという難しさを持っている。しかし、結局は点をとったほうが勝ちというふうに、矛盾しているようでもあり逆説的でもある面を孕んでいる)
攻撃と守備という矛盾することがチーム戦術の中でぶつかり合いながら、それを克服する戦術や技術が発展してきたが、いまや、それが飽和点まできてしまい、身もふたもない点取りゲームになりつつあるという、結構、危ない段階に世界のサッカーが来ているんではないかという気がしている・・・。
今福氏 どうしてこのように世界のサッカーが似通った戦術をとったり、サッカースタイルが画一化しているのかを考えた時、いまスポーツの世界を含めて広い意味の世界を覆い尽くしている「世界資本主義」いうものがキーワードとしてあるのではないか。
この「世界資本主義」いうものが、1つはビジネスいわば経済活動の場面で顕著になっている。サッカーをビジネスいわば経済活動という切り口で見た場合、サッカー選手のサクセスストーリーが非常に画一化してきている。
名も知れない小さなクラブでサッカーをしていた少年が、地方の大きなクラブにスカウトされ、そこで活躍すると、今度はその国の首都にある大きなクラブに引き抜かれ、最後にはイタリアなど世界最高峰のリーグのクラブに高額の移籍金で移籍していくというふうに・・。若い選手を養成する最初の小さなクラブは、はじめから売れる人材を作り出すという目標を持っているので、その人材発掘もビジネス的に行なわれる。
サッカー選手のマーケットは非常にグローバルに行なわれているから、選手の出発点は世界各地に散らばっているけれど、最後は優秀な選手のプレースタイルも価値観も次第に一元化され画一化されていく、そういう状況が世界のサッカー界を覆い尽くして、似通った戦術や、サッカースタイルの画一化を招いているのではないか。
馳星周氏 まさに「資本の原理」によってでしょうね。それからインターネットの普及による情報の画一化も影響していると思う。例えば日本にいても ブラジルにいてもちょっとネットで接続すれば誰でも瞬時に等質の情報が手に入れられる。
全世界的に距離が縮まってるし 情報が画一化されているので「戦術やサッカースタイル」が似てくるのは当然なのかも知れない。
山崎氏 グローバル資本主義がサッカーの世界を覆い尽くしてしまっている結果として「持てるクラブ」と「持たざるクラブ」の差が大きくなっているのは確かだ。「持てるクラブ」のほうはバブル状態にまで入っている。このまま行ってどこかで折り合いがつくのか、あるいは崩壊してしまうのか、どうなんだろうと思う。
馳氏 「持てるクラブ」と「持たざるクラブ」の格差の拡大は、いわば「資本の寡占化」であり競争の激化、格差の発生そのものだと思う。でも、そのように全世界的になっていくかどうかと言えば、そうでもないと思う。
今福氏 サッカーに限らず、これまでスポーツの世界を支配してきた国ごとの囲い込み、それがオリンピックでもワールドカップでも国別対抗という形で現れ、それが、各国のナショナリズム高揚の重要な道具として使われてきた。20世紀はそういう時代だった。
ところが、サッカーの世界に見られるように、グローバルな選手の移動によって、その国の中に、民族的ルーツも言語も文化も違う選手たちが無数に存在する状況が生まれた。すると、これまで主として同じ民族の選手たちで固められた国の代表選手の中に、移民という形であったり、サッカーによる移籍を通じて、多様な民族が混ざりあうチームが珍しくなくかった。
それが顕著に現れたのは開催国であり優勝国のフランスだった。フランスは歴史的にはどちらかというと排他的な政策をとってきた国だが、今大会のフランス代表を構成するメンバーのルーツや文化的な背景を確認してみると、これほどまでに多民族化しているのかと思うほどだ。
それを象徴的に見せてくれたのが、準決勝のオランダ戦でフランスがあげたDFテュラムの2点目だ。あの得点に至るパスの流れを見てみると、まずガーナ出身のDFデサイーがボールをヘディングでマイボールにしたところから始まっている。次に、それを生粋のフランス人プティが受け、フランス国内にあるバスク地方の出身者であるリザラズに渡す。リザラズはアルジェリア移民のジダンにパス、ジダンは大きく逆サイドに展開、カリブ海の旧フランス領グァダループ島出身のテュラムに、受けたテュラムは、同じグァダループ島出身のアンリとワンツーパスを交換してゴールに向かい思い切りよくシュート。
6人の男たちによるこのゴールは、まさに現代の縮図とも言える多民族国家フランスならではだった。
しかも、今大会、毎試合のように観戦に訪れたフランスのシラク大統領は、フランス代表の活躍をフランスのナショナリズムの高揚に結び付けようと考えていた。年々移民が増え続けていく中で、国内に生ずるさまざまな摩擦を乗り越える手段として、この多民族集団によるフランス代表の活躍を賛美して、これまでとってきた、かなり排斥的な政策を転換して、多民族集団の統合という形で賛美して、実は、国という枠組みのナショナリズムの強化に利用しようとしているところがある。
これまでサッカーがもっていた自国民族によるナショナリズムの高揚という枠組みを、フランスは一旦解体してみせたかのようにして、実はもう一度、新しい形のナショナリズムの高揚に利用しようと考えているのではないかと非常に感じた。
けれど、国家という原理の中に美化するという動きを、やはりサッカーはどこかでそれに抵抗して行くべきだろうと僕は思ってる。
あのサッカーシーンをみながら、我々日本社会が近い将来に直面するであろう姿について考えさせられた。
越後氏 日本はいまは単一民族国家だけれど、次第にそうなっていくのではないかという気がする。
馳氏 他とは違う文化だからといって、自分たちだけを特別な位置に置いておくってことも これからどんどんできなくなってくと思う。
今福氏 今回のジャマイカ代表を見ていると、イギリス代表になれなかったジャマイカ人の移民の子供たちが、ジャマイカの代表になってでそのワールドカップに出てる。フランス代表とは逆のケースですけど。英国人なのかジャマイカ人なのか、っていう二者択一じゃなくなって、自由な選択がサッカーの世界で起こっている。言い換えれば、サッカーを通じてかなり自由なアイデンティティを手に入れようとしているんだっていう言い方も可能だと思う。
サッカーの世界で、新しいケースが出現することによって、何か新しい世界が見え始めてきてるのかも知れない。
山崎氏 サッカーにおける日本と世界の関係をイメージする時にやっぱりどうしても、世界というのが日本より高いところであって、自分たちはそれに合わせていく、みたいな世界観しか、今まで持ってなかったと思う。でも、そんなふうに勝手に壁を作るんじゃなくて、こっちから(日本から)も、世界の一部、グローバルスタンダードを一緒に作ることもできる。そういうふうに考え方を変えないと、いつまで経っても、世界に追いつけとか、世界は遠かったみたいな、ちょっと不満な結果になってしまう。これからは世界観のちょっと変えてみようと思う。
2002年日韓W杯という舞台は、世界の変化をどのように映し出すのか
今回フランスワールドカップは、多くの国が、移民などにより多民族社会化していく中で、かつて単一民族社会をベースにして唱えてきたナショナリズムの高揚を、多民族で構成された代表チームの快挙を利用してナショナリズムの高揚に結び付けようという思惑が働いていることを示しました。
ワールドカップという舞台は、そういう「世界の変化」をも映し出す舞台だというわけです。
4年後の2002年は、これまでとはまた違った舞台設定、すなわち日韓共催という設定でのワールドカップになります。今回、フランス代表の快挙から見えてきた「世界の変化」が、次はどのような形で見られるか、ジョン・カビラ氏のエンディングナレーションの最後のフレーズ「その時日本はどんな社会になっているのでしょうか。そして世界は日本人の目にどのように映し出されるのでしょうか。」を4年後、確かめたいものです。
次回開催国日本、日本組織委員会(JAWOC)本格的な準備活動開始、フランス大会から最大漏らさず学習、すべてを吸収すべく多くの関係者が渡仏
今回のフランスワールドカップ、日本が史上初めて出場した大会としての意義に加えて、次回2002年日韓大会を開催する国にとって直前の大会として、最大漏らさず学習して、すべてを吸収しようとした大会としても意義深い大会でした。
これまで、外国のサッカー協会と国をあげて交流する機会を持てなかった日本にとっては、フランスサッカー協会は、まさに、あらゆる面で先生役として頼る相手になったのです。
2002年日韓大会「日本組織委員会(JAWOC)」は、まだ前年12月に立ち上げられ、この年1月に「設立記念レセプション」ということで、お披露目したばかり。
このフランス大会を現地でつぶさに視察して、最大漏らさず学習して、すべてを吸収しようというのが最初の本格的準備活動といってもいい段階でした。
試合開催都市視察に約80名が渡仏
フランス大会で勉強する一つの目的は、試合開催都市がどんな準備をしていて、どんな対応をするのかを視察することでした。
「日本組織委員会(JAWOC)」は、国内開催都市関係者を含む合計約80名を4グループに分けて派遣、フランス各地のスタジアム施設、競技運営方法、警備、報道対応、スポンサー対応、交通アクセス、開催地の地域状況などを視察しました。
日本で初めて経験する大会運営ですから、細かいところまで最大漏らさず学習して、すべてを吸収しようというわけです。
この視察に対して、フランス組織委員会の多大な協力があったことは言うまでもありません。さらにはフランス組織委員会が、運営業務について開催した「オブザーバーカンファレンス」にも参加、貴重な知見を持ち帰りました。
「日本組織委員会(JAWOC)」事務局員による4回の現地短期研修
フランス大会組織委員会は、次回開催国の組織委員会事務局スタッフを対象に、大会期間中、4回の短期研修を開催しました。
テーマは、・試合開催地運営、・総務一般、・IT、・メディアPRなど、各回ごとに異なり、日韓両国からそれぞれ担当スタッフが参加しました。
「日本組織委員会(JAWOC)」事務局代表1名参加の長期研修
フランス大会期間中を通じた長期研修ということで、日韓両国組織委員会から各1名が、FIFA事務局、フランス組織委員会事務局に出向の形で参加、大会全体を通したノウハウの把握に、貴重な現場での経験を積みました。
月刊ストライカー誌は、1998年10月、11月号連載で「フランスワールドカップから得たもの」と題して、この視察メンバーの一人、元日本サッカー協会国際委員・伊藤庸夫氏のレポートを掲載しました。伊藤氏は6月1日から7月15日までの1ケ月半、フランス中を駆け回り、日本がワールドカップを開催する上で問題となる点、課題となる点を拾い上げ、その対応策についても言及しています。あげられたテーマは次のとおりです。
・スタジアムへのアクセス問題、公共交通機関でのアクセスか不十分な場合の対応策
・安全対策(1)フーリガン対策、(2)出場チームの安全確保
・プレス(報道関係者)対策、フランス大会に集まった報道関係者は12000人に至れり尽せり
・スタジアムでのVIP対応、ホスピタリティ(おもてなしの場)W杯では必須事項
・ボランティアの活用、フランス大会は事務局500人とボランティア12000人で運営された
これら、持ち帰られた貴重な視察情報をもとに2002年大会への準備が進められることになります。
7月10日、パリで「2002年日韓共催レセプション」を開催、FIFA新会長のブラッター氏も来場、お披露目も兼ねたレセプションに
「日本組織委員会(JAWOC)」によるフランス大会視察は、役員を対象としても行われましたが、合わせて、韓国委員会と共催で「2002年日韓共催レセプション」を開催しました。
レセプションはワールドカップ決勝の2日前、7月10日、パリ市内のホテルで行われ、日本組織委員会(JAWOC)の宮澤喜一最高顧問(元総理)、那須翔会長(東京電力会長)、長沼健日本サッカー協会会長をはじめ多数の関係者、韓国側関係者が参加しました。
このレセプションは、FIFAの公式行事という位置づけでしたので、FIFAからは新たに会長に就任したゼップ・ブラッター氏も訪れました。ブラッター氏の登場により会場は、さながらFIFA新会長のお披露目のような雰囲気になり、ワールドカップ取材のためパリに滞在していた報道陣をはじめ多くの関係者が取り囲みました。
またフランス大会期間中、開幕式、決勝戦の会場となったサン・ドニスタジアムのメインゲート脇に「2002日韓共催ワールドカップPRブース」を設置、PRパネル展示、PRパンフレット配布、PRビデオ放映などの活動を行ないました。
こうしたフランスワールドカップ期間中の、さまざまな視察・交流によって日本サッカー協会は、地元フランスサッカー協会とはじめて協会同士の濃密な関係を築くことができました。
こうして築いた関係を生かして、まもなく日本サッカー協会は、次期日本代表監督選定にあたってフランスサッカー協会に頼ることになります。
この時はまだ、表面化していませんでしたが、まもなく日本サッカー協会、特に次期日本代表監督選定について実務担当を任された大仁強化委員長が、フランスサッカー協会からのアドバイスをもとに活動を始めることになります。
7月31日、岡田監督契約満了会見、突然の就任から始まった「300日戦争完結」
日本中が熱狂し、そして落胆したフランスワールドカップ、フランスの初優勝で幕を閉じたフランスワールドカップ、世界中の注目を集めた4年に一度の祝祭が終わって3週間ほど経った7月31日、岡田監督が契約満了の会見を開きました。日本サッカー協会の会議室には100人ほどの報道陣が詰めかけました。
前年10月4日にカザフカタン・アルトマイのホテルで監督に就任してから301日、「私自身は就任した10ケ月前と何も変わっていないですが、周りの見る目が変わりました。まるで10年分を生きたような経験でした」と回想しました。
この日の記者会見では「岡田監督の300日戦争」が、これからの「岡田武史」をどのように導いていくのかについてまでは語られませんでしたが、これまで何度も引用させていただいている、増島みどり氏の著書「ワールドカップフランス98 6月の軌跡」の中で、まさに大トリの役者のように最後の語り手として登場「岡田武史のこれから」を次のように語っています。
「(ベースキャンプ地のエクスレバンに)ベンゲルが来てくれた日に、監督っていう仕事について話し合うことができました。責任は負う。プレッシャーはものすごい、苦しい。でもね、(選手という)人を扱う職業ですよね。だからその喜びったら(ハンパ)ないわけです。『しんどいけれど、オカダ、それがドラッグ(中毒)になるんだよ』って、彼も言っていました。」
「その意味がわかりますね、いま。プロの監督として現場に立ちたいです。本当に中毒なのかもしれません。けれども、そういう苦しさと同時に喜びを教えてくれたのは彼ら代表選手です。それには感謝している。」
「サッカーの指導者としてW杯はやはり夢です。目標です。だから『いつ』とかそういうことではなくて、常に、監督であることの延長線上にW杯という大きな目標を抱いていきたい。本当にそう思っているんです。」
まさに岡田監督の「300日戦争完結のホイッスルは、同時に、次の目標に向けキックオフの笛」といったところでしょうか。
増島みどり氏の著書「ワールドカップフランス98 6月の軌跡」も、この岡田監督の話で完結しています。「伝説の年1998年」を語る時、この書物は欠かせない記録だったことをあらためて記しておきたいと思います。
この7月31日の時点では、未来の歴史を誰も知りませんから、あとになってから言えることですが、岡田監督のその後のサッカー人生は、誰もが知る栄光に包まれています。今回の思いがけない代表監督経験を、その後の岡田監督自身が見事に糧として活かしたことがよくわかります。
そんな岡田監督を、この時すでに慧眼をもって評した方がお一人いらっしゃいます。そのことを記録に残して長く記憶に留めたいと思います。
日本サッカー協会・高円宮名誉総裁のおことば「日本サッカー界は岡田さんを大事にしなければならない」
その方は、日本サッカー協会名誉総裁の高円宮殿下です。高円宮名誉総裁はフランスワールドカップの日本代表戦と、韓国の第1戦観戦のためにフランスを訪問されました。その時のことを、高円宮妃殿下久子様が著書「宮さまとの思い出」(産経新聞社2003年11月刊)に次のようにお書きになっていらっゃいます。
「フランスでは、宮さまが、『ぜひ行きたい』とおっしゃって、合宿中の日本代表を訪問されました。選手のトレーニングを熱心にご覧になった後、宮さまはちょっとだけ参加されて、それはお嬉しそうにドリブルの練習もなさいました。」
「岡田武史監督に、『えっ? 殿下はサッカー部にいらしたのではないのですか』と言われた時も、お嬉しそうでしたね。その時は、日本代表の技術面や精神面の特徴や課題といったことについてまで、岡田監督と本当にいろいろなことをお話しされたようです。」
「フランス大会の終了後、岡田監督は監督をお辞めになりましたが、それから宮さまはよく、こうおっしゃっていました。『日本サッカー界は岡田さんを大事にしなければならない。ワールドカップを実際に経験した日本人監督は岡田さん以外にいないのだから。この先、『日本のチーム』を作るために必ず岡田さんの力が必要となる。非常に貴重な存在ですよ』と。」
「フランス大会については、結果的に日本代表は三戦全敗でしたが、宮さまは、日本人サポーターのマナーが非常によかったことが、FIFA(国際サッカー連盟)から高く評価されたことを心から喜ばれていました。」
高円宮名誉総裁は、2002年11月21日、享年48歳という若さで突然薨去されました。
のちに2007年11月、当時日本代表監督を務めていたイビチャ・オシム氏が突然脳梗塞で倒れ、代表監督を続けられなくなり、日本サッカー協会は岡田武史氏に再登板を要請しました。
このことを思うと高円宮名誉総裁が「この先、『日本のチーム』を作るために必ず岡田さんの力が必要となる。非常に貴重な存在ですよ」と語っておられたことの先見性に驚くとともに、岡田監督のことを慧眼をもって見ていらっしゃったことが伝わってきます。
中田英寿選手の移籍交渉加速、次原社長の奮闘続く
パリで中田選手、次原社長合流、そのあと中田選手帰国と入れ替わるようにベルマーレ平塚・上田氏と合流
6月28日、リヨンからパリ経由で帰国の途につく日本代表でしたが、パリからの飛行機便までの間、自由時間ができたことから、中田英寿選手はチームの許可を得て外出、所属事務所の次原社長らと合流しました。
次原社長は、クロアチア戦後のミーティングを終えた後も精力的にフランス、イギリスのクラブを訪問したり、ロンドンにあるエージェント会社のケビン・ゴードン氏の事務所を訪問したり、休むことなく活動を続けていて、合流したこの日も、わずかな自由時間を利用して、パリ・サンジェルマンのクラブハウスを見せるため同行しています。
その後、他の代表選手とともに帰国する中田英寿選手と別れた次原社長は、6月29日、ケビン・ゴードン氏とともにパリ市内のホテルで、フランスに入っていたベルマーレ平塚の上田栄二チーム統括部長代理と合流、中田選手の移籍交渉について打ち合わせを行ないました。
上田氏は、日本サッカー協会の強化委員でもあることから、フランスワールドカップの視察という仕事も兼ねてフランスに入っていたのでした。
ベルマーレ平塚にとって中田英寿はチームに絶対に欠かせない選手なのですが、中田選手が日本のサッカーで力を持て余していることも重々承知していて、彼にはJリーグでは及びもつかない激烈な環境が必要だと考えるようになり、フランスワールドカップが終わったら欧州に移籍することを了解していたのです。
上田氏は、ゴードン氏から中田選手の評価やワールドカップにおける日本代表の印象について話しを聞いたあと、最後に、現在、中田獲得に名乗りをあげ、検討したいと伝えてきたクラブについて話しを聞くことになりました。
ここからまた、小松成美氏の著書「中田英寿 鼓動」から引用する形で、経緯を記録することにします。
「最後に、ゴードンは、中田の移籍について名乗りをあげ、検討したいと申し出たクラブのリストを読み上げた。」
「アストン・ビラ(プレミアリーグ)、ニューキャッスル(プレミアリーグ)、セルティク(スコットランドリーグ)、クリスタルパレス(プレミアディビジョン1)、サンダーランド(プレミアディビジョン1)、パリ・サンジェルマン(フランスリーグ)、マルセイユ(フランスリーグ)、ユベントス(セリエA)、サンプドリア(セリエA)、ペルージャ(セリエA)」
「ゴードンは上田に詳しい状況を説明した。『実は、アーセン・ベンゲル監督が率いるアーセナルをリストから外すことにしました。アーセナルは、フランスリーグのあるクラブと提携していて、中田を獲得した後、フランスに12ケ月レンタルする可能性があるかも知れない、と言ってきたのです。私としては、中田の移籍をクラブ側の算段のために複雑にしたくないと思っています。彼の実力があれば、クラブと対等に話し合い、移籍を進めていくことが十分にできます』」
「ゴードンは身を乗り出して指を組んだ。『これは驚くべきことです。ヨーロッパの選手でも21歳の若さで、これほどのクラブから必要とされることはないでしょう。今大会で世界的に有名になったリバプールのエースストライカー、あのマイケル・オーウェンに匹敵する注目度ですよ。』」
「このあと、中田がヨーロッパに戻り、1週間で各クラブを回り、最終的にクラブを絞り込むことになっている、と次原が補足した。」
「9月からのシーズンに間に合うように、7月の中旬までにはクラブを決定し、下旬には日本を発って、正式な契約に臨みたいと思っています。Jリーグ前期の中断後の再開が7月25日ですが、中田は自分の気持ちにけじめをつけるため、それ以前に出発したいと思っているようです。(中略)」
「ゴードンの傍らで何度も頷いた上田は、中田が1ケ月もしないうちに日本を離れることが決定的になったことを認めた。」
日本代表が帰国した6月29日からわずか2日後の7月1日、都内のホテルに滞在していた中田英寿選手は極秘に出国しました。行先はロンドン、現地で待つ次原社長、ゴードン氏らと合流したのは時差の関係で、現地時間の6月30日夕刻でした。
翌7月1日、中田英寿選手を交えた本格的なミーティングが行われました。先日、ベルマーレ平塚の上田氏に示された候補クラブから、どこに絞るかが話題の中心でした。
中田選手は、こう話したそうです。
「生活環境は自分の中では大きな位置を占めるよね。そこで暮らすんだから。生活や食事の面を考えれば、やっぱりイタリアかな。イタリアなら、しばらく滞在したこともあるし、イタリア料理なら毎日でも大丈夫だから。」
その話を受けてゴードン氏が提案しました。
「私はプレミアリーグのアストンビラがいいと思うけれど、ヒデが望むイタリアのチームならユベントスやサンプドリアとなると、レンタルされる可能性やチーム内で競合する選手が考えられる。とりあえず『ペルージャ』を一度訪れてみたらどうだろう。ペルージャは、絶対に中田が欲しいと、私にもベルマーレ平塚にも熱烈なアプローチが続いているからね。監督の話を聞いてみるのも悪くない。」
「実はセリエAのボローニャからも真剣な問い合わせがきているんだ。せっかくイタリアに行くんだから、ペルージャの後にポローニャに寄ってはどうか。」
ミーティングでは、最終的に中田選手が視野に入れるチームはアストン・ビラ、ペルージャ、ボローニャに決定しました。
FIFA新会長にブラッター事務総長就任、アベランジェ前会長、体制の継承に成功
5月下旬、フランスW杯開幕直前に国際サッカー連盟(FIFA)の総会が開催されました。主な議題は新会長選挙でした。24年間にわたってFIFAに君臨してきたアベランジェ会長が勇退を決めたからです。
前年の「2002年W杯開催地決定」の過程で世界中の人たちが知ることになったアベランジェとUEFAヨハンソン会長との確執は、さらに激しさを増していて、当然、この選挙にはFIFA副会長でもあるヨハンソン氏が立候補しました。
ヨハンソン氏は、風貌こそ強面ですが原則を重んじる高潔な人柄で知られ、日本もW杯アジア予選の開催地問題や、日韓W杯共同開催の進め方に関するワーキンググループなどを仕切った方です。
対抗馬にたったのは、アベランジェ会長の番頭役として長年事務総長を務めてきたブラッター氏でした。当初はブラッター氏では役不足と見られていたこの選挙、ふたを開けてみればブラッター氏の勝利となりました。
ヨハンソン氏の当選を阻止すべく、アベランジェ会長があらゆる手段を講じて工作したであろうことは明白でした。日本はFIFA内部に情報源を持っていませんから、流れてくる情報から判断するしかありませんでしたが、アベランジェ会長が前年「2002年W杯開催地決定」の際に自ら苦渋の選択を迫られた時の借りをキッチリ返したというのが、もっぱらの見立てでした。
ブラッター氏はスイスの時計メーカーから転職したエリートビジネスマンで、数か国語をあやつり、法律にも精通した有能なFIFAの実務最高責任者でした。アベランジェ前会長の後押しとはいえ、新会長に就くと独自のビジネス感覚を発揮し始めます。彼の最初の大仕事は「2002年W杯を成功裡に終わらせること」ですが、彼の成功の論理は「FIFAが潤うこと」にあり、それが日韓W杯を準備する両国関係者に新たな難問を突き付けることになります。
アジア選出FIFA理事選、小倉氏の当選ならず、いまだFIFAに足場築けず
FIFA(国際サッカー連盟)総会に先立って行われたAFC(アジアサッカー連盟)総会で、アジア選出のFIFA理事選挙が行われました。日本サッカー協会・小倉純二専務理事が立候補していましたが、改選枠2名に対して得票数21票を獲得したものの3位に終わり落選となりました。1位がタイからの候補で25票、2位がサウジアラビアからの候補で23票でした。
アジア選出のFIFA副会長に、すでに韓国の鄭夢準氏が就いていて、今回も無投票で再選されたため、FIFA理事が東アジアばかりに偏るのは避けたいという「地域バランス論」の前に屈した形となりました。
日本サッカー協会、長沼健会長から岡野俊一郎会長にバトンタッチ、強化委員会を改組「技術委員会」体制に
7月19日、日本サッカー協会・長沼健会長が勇退を表明、翌7月20日の評議委員会で役員改選が行われ、岡野俊一郎副会長が第9代会長に就任しました。副会長には川淵三郎氏と、新たに釜本邦茂氏が就任しました。釜本氏は「強化担当」副会長ということで、日本代表の活動も所管することになりますが、この人事が1年後、2年後の日本代表の活動、特に日本代表監督との一触即発の関係をもたらすとは、この時まで誰も知るよしがありませんでした。
この役員改選に合わせて、強化委員会も指導委員会と統合、・日本サッカーの強化、・指導者育成、・選手育成をトータルで管轄する「技術委員会」としてスタートすることも承認され、初代技術委員長には、強化委員長だった大仁邦彌氏がそのまま選任されました。
日本サッカー中興の祖・長沼前会長
退任した長沼会長は、会長に就任した1994年から、さまざまな問題に直面し、日本サッカー協会の運営が個人商店的体質だとか、一部の幹部による密室での意思決定だとか、マスコミをはじめサッカー界を取り巻く各方面から大きな批判を受けることが多かった4年間でした。
1994年には、アジア選出のFIFA副会長選挙で日本から立候補した村田忠男氏の当選を果たせなかったばかりか、もっとも当選を阻止すべき韓国からの立候補者・鄭夢準氏に当選を許す失態を犯し、それが2002年W杯開催地決定を日韓共催にしてしまう要因となったところから長沼体制はスタートしました。
1995年には、強化委員会が作成した日本代表監督の評価報告書で「加茂監督に代わる監督を」という提言がなされ、それに沿ってヴ川崎・ネルシーニョ監督と交渉を進め契約直前まで進んだ話を取消し、加茂監督続投を一部の幹部により密室で決めたと批判される出来事がありました。
1996年には、2002年W杯開催地決定に関するFIFAの趨勢、韓国の猛烈な工作活動を読み切れず、なすすべなく「日韓共催」を受け入れざるを得ない結果となりました。
1997年には、日本代表・加茂監督で臨んだフランスW杯アジア最終予選のさなかに、突然「加茂監督更迭・岡田コーチ昇格」を決め、またしても「一部の幹部が密室で決めた」と、猛烈な批判を浴びました。
このように、何かにつけ批判を浴び続けてきた長沼会長ですし、フランスワールドカップで日本代表が1勝もできずに大会を終えた責任を負う形で岡田監督が辞任したのに合わせて、協会トップである長沼会長も責任の所在を明らかにする辞任と受け止める見方もありますが、当の長沼会長は「辞任の弁」を公には一言も発せずに退任しました。
マスコミをはじめ、これだけ批判を浴び続けた長沼会長にすれば「何をか言わんや」という気持ちだったのかも知れません。
とはいえ、日本サッカー協会初の内部昇格での会長となった長沼健氏が勇退したとあらば、日本サッカーの申し子のような長沼氏の事績を記録に留めないわけにはいきません。
なぜなら、長沼氏は、青年時代から常に戦後日本サッカーの中心を歩んでこられた方だからです。その経歴がいかに傑出しているかをあらためて記録しておきます。
・1954年には、日本が初めてワールドカップ地区予選に参加したスイスW杯予選の対韓国戦で記念すべきW杯予選における日本代表の第1号ゴールを決めました。この時24歳でした。
・1962年には、当時の日本サッカー協会・野津会長が同じ広島出身だったこともあり、推挙されて日本代表監督に就任。この時32歳でした。(コーチには今回会長に就任した岡野俊一郎氏)
・1968年には、すでに日本代表を指導するため1960年から来日していたドイツのデッドマール・クラマー氏が技術・戦術面を担当して岡野コーチがそれを補佐、長沼監督が選手を束ねるという役割分担で強化してきた成果が表れ、メキシコ五輪銅メダルという偉業を達成しました。その翌年、一旦岡野氏に代表監督を譲りますが1972年に再び復帰、1976年まで通算11年間代表監督を歴任しました。
・1976年、日本サッカー協会専務理事に就任。長沼氏はかねてから日本サッカー協会の財政基盤強化の必要性を強く感じていたため、野津会長の個人的資金繰りによる運営から、日本リーグを構成する大企業の協賛が得られる体制に移行させるため、会長選任も自ら主導した上で専務理事に就任したもので、当時のサッカー専門誌には「長沼の無血クーデター」などと書かれました。
・その後も協会財政と運営を実質的に取り仕切りながら、会長の選任を引き続き主導して3代の会長に仕えました。
・協会運営面では、不振に陥ったサッカー界の最大の原因を、サッカーのピラミッドが日本にできていないからだと考え、底辺の拡大と各年代別の分厚い日本代表チームの構成を目指しました。
・協会財政の改善に向けては、ペレや釜本邦茂選手の引退試合を、広告代理店・電通と組んで企画、多額の純益を出す一方、選手登録制度による入会金収入などで、それまでの累積赤字を一掃しただけでなく、日本サッカー協会を潤沢な資金を持つ団体に成長させました。
・選手登録制度による入会金徴収は、中体連から猛反発を受けたりしましたが、その資金を小・中学生のサッカースクール開校や、ユース年代の海外派遣などに投入して、底辺拡大の芽を育てる目的でもあったことから、反発に屈しませんでした。
・また、生来の親分肌で人柄も素晴らしかったことから、協会運営に必要な人材を、日本リーグを構成する大企業のうち、丸の内御三家と呼ばれる三菱重工、日立製作所、古河電工の各社から専門知識のあるサッカー関係者を協会に引き抜き陣容を強化しました。
・1987年、平井会長から藤田会長への交代を機に専務理事から副会長に就任。「プロリーグ化」推進を協会サイドから強力に後押ししました。
・1994年、島田会長の後任として第8代会長に就任しました。
・1996年、「2002年W杯招致」を日韓共催の形で実現しました。
・1996年、日本サッカー協会75周年記念事業の一つとして「75年史」刊行しました。
・1997年、「ナショナルトレーニングセンター(Jヴィレッジ)」を福島県にオープンさせました。
・1997年、W杯アジア最終予選のさなか、加茂監督更迭・岡田コーチ昇格の荒療治を行ない、日本代表、初のW杯出場権獲得を果たしました。
・1998年、日本代表のフランスW杯初出場を会長として見届けました。
長沼会長がかねがね語っていた4つの夢というのがありました。
1.プロリーグ化(Jリーグのスタート)、2.W杯日本招致、3.ナショナルトレーニングセンターの新設、4.日本代表のw杯出場。
長沼会長は、この4つの夢をすべて実現させたのです。そして4つ目の夢である「日本代表のw杯出場」が実現した1998年のこの年、会長を勇退したのです。
勇退表明は、フランスワールドカップの決勝が行われた2日前、7月10日にパリで開催した「2002年日韓共催レセプション」から帰国してわずか10日後、まさに思い残すことはない心境での勇退表明だったことと思います。
長年にわたって日本サッカー界を牽引して、最後は頂点に君臨した日本サッカー界のドンといった感じがしますし、この「伝説の年シリーズ」でも1994年の、アジア選出FIFA副会長選挙(村田忠男氏惨敗)の時や、1996年の、2002年W杯日韓共同開催に至る招致活動の問題、そして1994年の日本代表加茂監督選任から、1995年のいわゆるネルシーニョ事件、さらには1997年の更迭に至る問題などの都度、厳しいマスコミの批判に同調するように、長沼会長を頂点とする日本サッカー協会の閉鎖的体質、時代錯誤的な認識について、厳しい論陣を張り続けてきました。
しかし、一方では「日本サッカーをひたすら強くしたい」「そのために必要なことへの努力は惜しまない」という長沼会長が、私心のない情熱と、4つの夢を掲げて、その実現のためには地球を何周しようと、どんな劣悪な場所であろうとも行くんだという強い意思をもったリーダーであったことも事実です。
そんな長沼前会長のエピソードは、後年(2004年)テレビドラマ化された「熱き夢の日々 日韓ワールドカップ真実の裏側」(フジテレビ)でも紹介されています。
それは「2002年W杯日本開催」の支持をとりつけるために、地球を15周するほど世界各国を飛び回った、その行脚の中で北半球から南半球へと移動した際、真夏から真冬の温度変化のため一度だけダウンしてしまったことがあるというエピソードです。宇津井健さん演じる長沼会長が高熱を出し、翌日の訪問までに何とか回復しなければならないと、その日だけは観念して静養したというドラマになっていました。
このテレビドラマは、前にも引用させていただいた、スポーツライター・川端靖生氏の著書「日韓ワールドカップの覚書」をドラマ化したもので、テレビドラマ、著書ともに貴重な作品となっています。
また、前年1997年12月には、2002年W杯の国内開催地決定の際、候補地15都市から10都市に絞らなければならないという苦渋の決断を迫られました。外された5都市の中には自らの出身地である広島市も含まれていましたが、私情を挟まず決定に従い、また外された5都市からいろいろな意味で批判を受けるのを覚悟で「お詫び行脚」に出向いています。いやなことも逃げずに引き受ける潔さ、胆力といった点でも素晴らしい方でした。
これまで、この「伝説の年シリーズ」では、例えば加茂監督継続にこだわったのは「自分の大学の同窓だからではないのか」とこき下ろしたこともありました。長沼会長が「最終的にはオレが決めるんだ」という立場から出した答えが、どう考えても社会的に受け入れられない答えであれば「どう考えても、そう決めたのは、自分の大学の同窓だから、だろう」という穿った見方になるのは自然の成り行きです。
ですから、長沼会長が決めてきたことが、終始一貫、私心のない決め方、つまり「加茂であれば絶対出場権獲得できる」という信念一途だったのであれば、誤解を招く残念な決め方だったのかも知れません。
もう一つ、長沼会長自らも悔やんでいると思われるのは、共催で決着してしまった2002年ワールドカップの開催地決定です。これは長沼会長が、日本サッカー界の中では類い稀れな「サッカー人」「スポーツ人」であったにしても、「権謀術数の限りを尽くさなければとても勝ち抜けない国際サッカービジネス戦争の世界」に関しては、何の知識も経験も持ち合わせていなかった、日本サッカー界だけでしか通用しない「サッカー人」「スポーツ人」だった結果だと思います。
致し方ないと言ってしまえばそれまでですが、せめて1歳後輩で、招致活動に1986年から1994年まで8年間も孤軍奮闘、取り組んでいた村田忠男氏の様子をすぐそばで見ていながら、何か手立てを講じてやれなかったものかと思うと、むしろ不思議なぐらいです。
村田忠男氏が「何でもオレがやる、オレにしか出来ない」というタイプの人物だったとは思いますが、長沼前会長ほどの洞察力や国内各方面への人脈をもっと活かしていれば、アジア選出のFIFA副会長選挙に村田氏がむざむざ惨敗してしまう、それによって、相対的に韓国を利してしまうことはなかったと思います。
「あの時、そう気づいていれば、やっていたよ」とご自分も振り返るに違いありませんが、そのことだけはどうしても指摘しておきたいと思います。
いずれにしても「日本サッカー中興の祖」と言って間違いない、そして功罪相半ばするところもある偉大なリーダーの勇退です。
前年10月、W杯アジア最終予選のさなかに加茂監督を更迭した時「加茂でダメだったら自分も責任をとる」と言っていた長沼会長の責任はどうなるんだ、という批判がくすぶりましたが、岡田監督の手で見事W杯出場権を獲得して、責任論は沈静化したかに見えました。
また、つい2週間前の6月29日、フランスワールドカップで3戦全敗して寂しく日本代表が帰国した時にも、サッカーダイジェスト誌の連載コラムの中でセルジオ越後氏から「帰国のときに、どれだけ組織が空虚だったかを思い知らされたね。キリンカップのチェコ戦(5月24日)では、試合前の壮行会に長沼会長が顔を出した。でも選手が帰国のときはバラバラだった。長沼会長はひとりでとっとと帰ってきてた。いいときだけ顔を出して、ヤバイときには逃げ隠れするんだ。」と痛烈な批判を受けました。
しかし、長沼会長は、黙して語らずを貫きながらも、いずれ自らケジメをつけなければならないと決意していたのでしょう。今回、いわば任期を全うする形で勇退したことで晩節を汚すことなくバトンタッチを果たしたことになります。
「サッカーむら」という独特の固い結束を誇る日本サッカー協会の閉鎖的体質、時代錯誤的な認識は一朝一夕には改善されそうにありませんが、それによって長沼会長の業績が貶められるものではありません。自分たちが棲む「サッカーむら」をもっとよくしたいという純粋な気持ちがエネルギーとなって、さまざまな取り組みを実現させていった功績は、日本サッカーの成長・進化・発展の軌道を確かなものにしました。
あらためて長沼会長の功績をこうして記録に留め、長く記憶して語り継いでいきたいと思います。
これに先立ち5月29日、前年発表された「JFA行動宣言」を具体化するため議論・検討が進められていたアクションプランである「JFAサッカー行動規範」が発表されました。
前年の「JFA行動宣言」(「伝説の年 1997年」の9月のところで紹介」)は、日本サッカー協会が創立100周年を迎える2021年に向けた行動宣言(行動目標と言い換えてもいい宣言)ですが、今回の「JFAサッカー行動規範」は、そのためにどうすべきかという指針を示したものと言えます。これについても全文を紹介、記録して長く記憶に留めたいと思います。
JFAサッカー行動規範 (1998年5月29日)
1.「最善の努力」どんな状況でも、勝利のため、また一つのゴールのために、最後まで全力を尽くしてプレーする。
2.「フェアプレー」フェアプレーの精神を理解し、あらゆる面でフェアな行動を心がける。
3.「ルールの遵守」ルールを守り、ルールの精神に従って行動する。
4.「相手の尊重」対戦チームのプレーヤーや、レフェリーなどにも、友情と尊敬をもって接する。
5.「勝敗の受容」勝利の時は慎みを忘れず、また、敗戦も誇りある態度で受け入れる。
6.「仲間の拡大」サッカーの仲間を増やすことに努める。
7.「環境の改善」サッカーの環境をより良いものとするために努力する。
8.「責任ある行動」社会の一員として、責任ある態度と行動をとる。
9.「健全な経済感覚」あらゆる面で健全な経済感覚のもとに行動する。
10.「社会悪との戦い」薬物の乱用、差別などのスポーツの健全な発展を脅かす社会悪に対して、断固として戦う。
11.「感謝と喜び」常に感謝と喜びの気持ちをもってサッカーに関わる。
前年の「行動宣言」に続く今回の「行動規範」を記録しながら、つくづくサッカーの世界の奥深さというか、不思議さといった思いにとらわれます。
特に、1996年の「2002年W杯開催地決定」の時の日本と韓国の招致活動や、日本サッカー協会の対応、1997年の「フランスW杯アジア最終予選」に至る日本代表監督の問題などを記録する一方で「行動宣言」や「行動規範」の文言を書きつづると、その奥深さ、不思議さの度合いが一層深まるのです。
なぜなら「2002年W杯開催地決定」に至るまでに現れたFIFAを巻き込んだ政治力学から来る理不尽さや不条理さ、あるいは「フランスW杯アジア最終予選」の経緯に見られた天国と地獄を行き来するような過酷な戦いの様相、監督・選手・サポーターたちの心理的な混乱、葛藤といった心震えるような世界に比べて、「行動宣言」や「行動規範」に描かれている世界の、何と凛とした平穏な心安らかなことか。そのあまりの落差に、奥深さ、不思議さの度合いが一層深まるのです。
凡庸な者が読むと「行動宣言」や「行動規範」に描かれている世界は、あまりに綺麗事に過ぎる、あるいは建前論に過ぎると感じてしまうのですが、決してそうではないのかも知れません。
現実の「決め事」の世界や「勝負事」の世界は理不尽さや不条理さの海であり、過酷な戦いに翻弄される心震える世界であることは避けようのないことですけれど、だからと言ってそれに流され、それに毒されてしまってはいけない、どんな時も心だけは凛として、穏やかに保たなければならない、それが「サッカー」に携わっている者の普遍的なありようなのだと言っているに違いないのです。
それは、あたかも封建時代を生きる武士の心のありようと同じなのではないかと感じます。あの時代に生きた武士は、まさに理不尽さや不条理さの海に生きていたのであり、過酷な戦いに翻弄される心震える世界に生きていましたが、決して流され毒されることを潔しとせず「武士道」という普遍的な境地を矜持として生き抜きました。
「行動宣言」や「行動規範」には、それに通じる精神を感じるが故にサッカーの奥深さ、不思議さの度合いが一層深まるのです。
日本代表後任監督選び、水面下でスタート、新聞辞令も活発化
フランスワールドカップ日本代表を指揮した岡田監督の辞任によって、日本サッカー協会は、必然的に後任監督選定に入ったわけですが、新聞辞令は、まずクロアチア戦に敗れて2敗となりグループリーグ突破が絶望的となり、岡田監督が辞意を漏らした翌朝6月22日から始まりました。
まず、スポーツ報知紙が「岡田後任、ベンゲル氏浮上」と打ったのです。その後も、スポーツ紙各紙は、独自の憶測記事を次々と掲載、スポーツ紙の上では賑やかに人事予想が飛び交っていました。
その頃、日本サッカー協会は、水面下で行動を始めていました。
6月26日のジャマイカ戦後、岡田監督が大仁強化委員長に辞意を伝達したことを受けて、7月2日、強化委員会会合で、あらためて岡田氏を慰留するか、新監督で行くかを議論、新監督で行く方針を決定しました。
それから、大仁委員長ほか強化委員会メンバーが(監督人選のため)、情報収集と候補者への打診作業を開始しました。
強化委員会メンバーは、まずベンゲル氏に打診しますが、ベンゲル氏はアーセナルと4年契約を結ぶことが判明、日本代表監督招請を断念しました。
そのため、強化委員会メンバーは、協会として用意した候補者リストを携えてフランス、オランダを訪問、絞り込んだ数人と面会しています。
その際、フランスサッカー協会を訪問、あらたにフランスサッカー協会からの数人の推薦を受けています。
7月12日、大仁委員長ほか強化委員会メンバーが、フランスサッカー協会からの推薦があった、フィリップ・トルシエ氏とパリで初めて接触しました。この日はフランカワールドカップ決勝フランスvsブラジル戦の日です。フランス国内がその話題でもちきりの中での接触でした。
この、初めての面会の日のことについて大仁邦彌氏は、のちに、2022年6月、日刊スポーツ紙が企画した「2002年W杯 20年後の証言」のインタビューに答えて次のように述べていいます。
「98年W杯フランス大会後(新監督選びのため渡仏した際)に、フランス協会のベルベック副会長(ベルバックの表記もある)から「(W杯に出場した)南アフリカの監督をやっていた若い、やる気のあるやつがいる」とトルシエ監督を薦められて、(日本代表監督の話をするため)フランスで初めて彼に会った時は真摯(しんし)で謙虚な印象だった。」
一方のトルシエ氏は、日本サッカー協会からの初めてのコンタクトについて、のちに出版した「情熱」(2001年12月、日本放送出版協会刊、ルイ・シュナイユ氏との共著)の中で、次のように語っています。
「1998年6月、ぼくは初めてのワールドカップに挑んでいた。フランスW杯に出場した南アフリカの監督として、アフリカでの9年間の監督生活を締めくくる大会だ。(中略)大会が始まる前、フランスサッカー協会のヴェルベック副会長から電話があり、近々、日本からオファーがあるかもしれないと聞かされてはいた。」
「日本サッカー協会から興味を持たれていることを知っていたぼくは、日本対アルゼンチン、さらにはクロアチア戦を注意深く観察した。」
「7月12日、フランス対ブラジルの決勝戦の日、日本サッカー協会の人から携帯電話に連絡が入った。(中略)電話の向こうの相手と、近くのホテルで午後2時に会う約束をした。ぼくは良い印象を与えられるよう、スーツにネクタイ、メガネをかけて行った。」
「日本サッカー協会の役員ふたりと通訳を含む3人がぼくを待っていた。(中略)45分の話し合いが終わり、彼らと別れたとき、自分としては悪い印象を与えた気はしなかった。彼らにとっては、日本で大変な人気だというアーセン・ベンゲルのイメージがぼくと重なっていたのかもしれない。」
2022.10.22に「webスポルティーバ」に掲載された田村修一氏の記事「フィリップ・トルシエの哲学」によると、この時「フランス協会が作成したリストには、レイモン・ドメネク(当時フランス五輪代表監督、のちのフランス代表監督)や、ギィ・ステファン(現フランス代表コーチ)らと並び、フィリップ・トルシエの名前も記されていた。」とあります。
やはり日本サッカー協会が、フランスワールドカップの際に、次期ワールドカップ開催国としてフランスサッカー協会と太いパイプを得られた効果と言えるリスト提供だったようです。
フランス協会としても、次期開催国・日本の代表監督にフランス人を送り込むことができれば、サッカーの世界界におけるフランスのプレゼンスを高めることに繋がりますから、本気でリストを作ったことと思います。
この記事の中でトルシエ氏は「最初にコンタクトしてきたのは、加藤久さんだった。自分は代理人を伴って会った」と語っています。
この頃の加藤久氏は、1996年にサッカー協会・強化委員長を辞したあと、1997年にヴ川崎の監督に就任、97年前期だけで引責自任後、東京工業大学の博士課程に進学していたことから、強化委員会メンバーではなかったように思われるが、トルシエ氏が「最初にコンタクトしてきた」と語っているところを見ると、新監督選定のために渡仏したメンバーに加わっていたのかも知れませんが、ホテルで会った日本側のメンバーが大仁邦彌氏強化委員長と加藤久氏だったのか、真偽のほどは不明です。
フィリップ・トルシエ氏は、フランスワールドカップに南アフリカ代表を率いて参加しています。さきほど自身が語っていたように、初めて代表監督としてワールドカップを経験したのです。南アフリカは長い間アパルトヘイト政策をとってきたため、スポーツを含めて国際社会から締め出されていましたが、アパルトヘイト政策を撤廃とともに国際社会に復帰、ワールドカップにもこの大会初出場を果たしました。
フィリップ・トルシエ氏は、1997年、ナイジェリア代表監督、ブルキナファソ代表監督を短期経験、1998年になってから南アフリカ代表監督に就任しています。つまりアフリカ予選を勝ち抜いた監督としてではなく、出場が決まったあと就任したのです。
グループリーグはフランス、デンマーク、サウジアラビアと同組、2戦を終えて1分1敗の第3戦目、サウジアラビアに勝てば決勝トーナメント進出の可能性をわずかに残しての試合、先制したものの逆転されてしまいます。しかし、後半ロスタイム、執念のPKを決めて引き分けに持ち込みました。決勝トーナメント進出を逃したことでトルシエ監督は辞意を表明、フリーの身になっていたことになります。
この時の南アフリカ代表は、アパルトヘイト後の国民を一つにまとめる象徴としての期待を集めていて、日本でも、フランスワールドカップの特徴ある参加国を紹介するNHKの夜のニュース番組「ニュース7」で6月24日放送時に4分弱紹介されており、この時、インタビューに答えているトルシエ監督も日本のお茶の間に初めて映っています。この時、日本サッカー協会の関係者が「この人がリストに載っているトルシエ氏か」と気づいたかどうか。
トルシエ氏とパリで初めて面会してから1週間後の7月19日、サッカー協会理事会で、勇退する長沼会長の後任人選として岡野俊一郎副会長が選任されました。翌7月20日、サッカー協会評議委員会で、岡野俊一郎が新会長に正式決定、代表監督を諮問する強化委員会は「技術委員会」に改組、技術委員長は、強化委員長から継続して大仁邦彌氏が就くことになりました。
新たにスタートした岡野俊一郎会長に、大仁技術委員長からフィリップ・トルシエ氏有望との感触が報告され、他に有力な候補者も現れなかったことから、フィリップ・トルシエ氏と本格的な交渉に入ることが決まりました。
7月31日、岡田監督の任期が満了となりましたので、大仁技術委員長らは、フィリップ・トルシエ氏との交渉に全力をあげることになります。
8月8日付けのスポーツ各紙は「日本代表監督にトルシエ氏、2002年はベンゲル氏」の見出しで、前日の8月7日開催された第1回の技術委員会の模様を伝えた大仁技術委員長からの取材記事を掲載しました。
大仁委員長は「トルシエ氏の任期は2年になると思う。トルシエ氏は五輪監督も兼ねる方向で、2000年シドニー五輪、2000年アジアカップの成績次第では任期延長の可能性もある。だが2002年日韓W杯では、ベンゲル氏招へいで固まっており、ベンゲル氏も2000年以降については、監督就任に支障はないと思われる」と語ったという内容でした。
ちなみに、この時の日刊スポーツ紙では見出しが「トルシエール氏」となっていましたから、まだ呼び名が定まっていなかったことがわかります。
この報道は、協会トップの了承を得た日本代表監督人事の最初のブリーフィングといっていい出来事でした。
このあと、日本サッカー協会はトルシエ氏に対して、正式に契約交渉を行なうため8月中の来日を要請しました。
中田英寿選手の移籍交渉いよいよ大詰め、最後は中田選手がきっぱり決断
7月1日、イギリス・ロンドンで、エージェント会社のケビン・ゴードン氏、所属事務所の次原社長、通訳のフジタ女史とミーティングを行なった中田英寿選手は、イングランド・プレミアリーグのアストンビラ、イタリア・セリエAのペルージャ、ポローニャに絞って検討することを決め、翌日からイギリス国内、イタリアと移動して、それらのクラブを訪問しました。
ここからまた、小松成美氏の著書「中田英寿 鼓動」に描かれている経緯をご紹介することにします。
最初に訪れたイギリス・バーミンガムのアストン・ビラで、魅力的な環境と自分に対する高い評価を聞かされた中田選手の心は動きましたが、一方で「ほかも見てから」というスタンスは変えませんでした。
次に一行はイタリアに入りました。ローマ空港に到着するとペルージャのGM(ゼネラルマネージャー)を筆頭に8名もの人たちが出迎えてくれました。
その中に一人の日本人がいました。彼の名は堀田正人氏、スペインを拠点に活動しているFIFA公認ライセンスを持つエージェントで、前年1997年からペルージャのクラブ代理人を務めていたのです。
堀田氏は、これまでJリーグのクラブに対して、例えば、この年1998年、横浜F(フリューゲルス)の監督に就任したカルロス・レシャック、そして、そのレシャック監督に誘われるように加入したレディアコフ選手、パウロ・フットレ選手の移籍を手掛けていました。同じ時期に横浜M(マリノス)に加入したゴイコエチェア選手もそうでした。
堀田氏は、ペルージャの代理人に就任すると、さっそくJリーグの日本人選手のリサーチを開始、ちょうどフランスW杯アジア最終予選で活躍した中田英寿選手のプレーを見て、中田選手の素晴らしさを見抜きペルージャに獲得を進言したのでした。
ペルージャはフランスワールドカップが始まる直前に終わった97-98シーズン・セリエB(二部リーグ)で、プレーオフの末、セリエA昇格を勝ち取っていて、9月から始まる新シーズンまでには、何としてもチームの中核となる選手を獲得しなければならない状況にありました。
この日、ペルージャ側のメンバーで最高位の人物は、若干24歳、ペルージャのオーナーであるガウチ家の御曹司、アレッサンドロ・ガウチ氏でした。ガウチ氏もフランスワールドカップでの中田選手のプレーを直接見ていて、中田選手獲得を至上命題にしていたのでした。
ペルージャ・カスタニエル監督との会食、中田選手の心に深く残る
ペルージャ側の昼食に招待された中田選手ら一行は、はじめて、そこでペルージャのカスタニエル監督と会話することになりました。
カスタニェール監督は実は前年のセリエBでの戦いの終盤、セリエA昇格が絶望的になりつつあった時に、アレッサンドロ・ガウチ氏の要請を受けて監督に復帰した、ペルージャのOBでもありセリエAでも有数の名将でした。
カスタニエル監督は、その絶望的な状況からチームを立て直し、奇跡的ともいえるセリエA昇格を果たしたのですが、そのままの戦力では、また1年でセリエBに逆戻りすることは必至だと考えていて、チームの柱になるような選手が欲しいと考えていたのです。
そして、アレッサンドロ・ガウチ氏から「フランスワールドカップに出場する日本の中田選手という選手をよく見ておいて欲しい」と言われ、テレビ観戦ながら中田選手の3試合を食い入るように見ていて「この選手はイタリアでも十分やっていける選手のようだ」と手応えを持っていたのでした。
そういう下地があったせいか、カスタニエル監督と中田選手の会話は、まるでカスタニエル監督が考えているサッカーと中田選手が希望している監督像、チーム作りを摺り合わせるかのような具体的かつ真剣な内容となり、それをゴードン氏が最大漏らさず聞き入るという3人だけの世界ができた昼食会となったそうです。
昼食後、中田選手は多くを語りませんでしたがカスタニエル監督との会話に大いに心を動かされたことは明白でした。
その夜、中田選手、次原社長、ゴードン氏、フジタ通訳の4人はペルージャから移動して、ガウチ家が所有する中世の古城そのままのお城に招待され晩餐会のもてなしを受けました。
その席で、アレッサンドロ・ガウチ氏から「ペルージャは中田選手獲得のため、どんな希望も受け入れるので、この場で中田選手移籍を承諾して欲しい」と迫られました。
しかし、次原社長は「移籍は、ペルージャとベルマーレ平塚の交渉が成立しないと実現できないので、その要請には応じられない」と断ります。
そして中田側の4人は「ペルージャへの即答を避け、検討のための時間を確保する」という意思を確認して、その夜の晩餐会をあとにしました。
イギリスからイタリアに入っての長い一日は深夜になって、やっと解放されたのですが、次原社長は、翌朝、その短い眠りさえも妨げられる目にあってしまいます。
翌7月6日午前6時、次原社長は、すでに日本時間午後1時になっている日本からの国際電話で叩き起こされました。
それは共同通信社からの電話で「イタリアの新聞に、中田のペルージャ移籍はほぼ決定という記事があるが、その真偽を確認したい」というものでした。
次原社長は「そんな事実はありません」ときっぱり否定して電話を切りましたが、共同通信社はイタリアの新聞の内容を転載する形で日本中に配信してしまいました。
そこには「中田が日本企業のスポンサー付きでイタリアに移籍する」と書かれていました。それは中田選手がもっとも嫌う形であり、まだ何一つ決まっていない段階での、そういう報道は中田選手の顔に泥を塗る行為だと次原社長は怒りに震えました。
次原社長はアレッサンドロ・ガウチ氏に「なぜ、こういう報道が出たのか説明して欲しい」と問い詰めると、ガウチ氏はすぐに調べ地元マスコミが憶測で書いた記事のようだと説明するとともに「我々もスポンサー付きで選手を獲得するほど困ってはいない」と釈明、翌日記者会見を開いてペルージャ側の考えを話すと付け加えました。この報道がベルージャ側からのリークではない保証はどこにもありませんでしたが、ここはガウチ氏の言葉を信じるしかありませんでした。
その騒ぎが一段落すると、今度は、次に訪問予定のボローニャの担当者から電話が入りました。担当者は「ペルージャの件が事実でないなら、すぐペルージャを断ってボローニャ1本に絞って欲しい」と迫ってきましたが、中田選手は「ペルージャは選手としての僕を認めてくれていることがわかったので、断りはしない」という意思を示したため、それをボローニャの担当者に伝えると「オーケー、イッツ、オーバー」と電話が切れたのです。
中田選手は、あと2日に迫った滞在期間の中でアストン・ビラかペルージャ、どちらにするか選択を迫られる段階を迎えました。
日本国内のスポーツ紙に「中田、ペルージャ移籍決定」の一斉報道
7月7日、ロンドンに戻った4人(中田、次原、ゴードン、フジタ)は、前日共同通信が配信した記事をもとに、スポーツ紙が「中田、ペルージャ移籍決定」と報じたことを知りました。それがこの記事です。【日刊、報知、サンスポ、トーチュー】
その夜、ペルージャのアレッサンドロ・ガウチ氏が会見を開きました。事前のプレス資料には「ペルージャと中田選手は移籍交渉中」と記されていましたが、会見でガウチ氏は「すでに我々は合意しました。後日、ベルマーレ平塚に出向き、正式な契約を済ませたいと思っています。」と語ったのです。
この会見を受けて、イタリアのマスコミ報道も「中田、ペルージャ移籍決定」となったことから、またしても次原社長は否定に追われ、ベルマーレ平塚も「ペルージャから獲得の意思は伝えられたが、その後コンタクトは一切ない」とコメントを出しました。
7月8日、ロンドンで4人は最後のミーティングを行ないました。ゴードン氏は、ベルージャの一連のマスコミを利用したデモンストレーションについて「サッカーの世界ではよくあることなので、失望しないで欲しい」と語り、中田選手に向かって「アストン・ビラとペルージャ、どちらにするかは君に任せるからね」といいました。
欧州のサッカービジネスに知悉していて、その一方で中田選手の才能を誰よりも評価している35歳の若きイギリス人エージェントと仕事ができたことは、中田選手にとって実に幸運なことだったと言えます。
中田選手は「日本にいるのはもういやなんだ。息苦しくてね。すぐ戻ってくるよ。次に来る時は入団発表に時だね。」と答えました。
7月9日、中田選手は日本に戻りました。そして7月10日、ベルマーレ平塚がJリーグ前期の中断後の再開に向けてチーム練習を始めていた仲間たちに合流しました。しかし、ジャマイカ戦で痛めた足首の痛みがひどく練習の切り上げを余儀なくされました。
その後、記者会見を開きましたが、クラブハウスに集まった50人ほどの記者たちに対する中田選手の答えは「報道は事実ではない」というだけで、それ以上の話を頑なに拒みました。
7月11日、中田選手は日本代表のチームドクターを務めている福林医師を訪れ、足首の診察を受けました。結果は水が溜まっているため10日間ほどの練習禁止でした。
中田選手が日本に戻ると、後を追うようにプレミアリーグのアストン・ビラから新たな要請が来ました。それは「契約の前に一度直接プレーを見たいので、中田選手が渡英してくれるか、チーム関係者を日本に派遣して見せてもらうか、どちらかをお願いしたい」というものでした。
中田選手は、もうこれ以上、出国したり大勢の前で練習を見せたりすることに伴う混乱は避けたいと判断、その要請をゴードン氏を通じて断りました。なにより今年1月以降、中田選手を執拗に批難し続けてきた思想団体の動きがおさまる気配がなかったためです。
アストン・ビラを断った形になった中田選手に残った候補チームはペルージャだけになったはずですが、実は「オーケー、イッツ、オーバー」と一度は交渉を打ち切ったイタリア・ボローニャが、その後、契約交渉したいと言って来たのに続き、7月14日、フランスのマルセイユからも飛び込みオファーが届きました。またスコットランドのセルティックからも、あきらめずオファーが届いていました。
一方、ペルージャからは「中田中心のチームを作るため2人選手を補強した。いずれもパルマからストラーダ選手とゼ・マリア選手」との情報も入ってきました。
7月17日、中田選手は次原社長のオフィスでミーティングを行ないました。次原社長は、結局どのチームを選ぶべきなのか、ますます悩みを深めていましたが、当の中田選手の考えは明快でした。
「もう、迷っていても仕方がないからね。ボローニャとセルティックは、ペルージャに行った時、切ったでしょう。マルセイユも凄くいいチームだと思うけど、少し遅すぎたね。それからアストン・ビラだけど、練習にも参加できないんだし、今回は難しいでしょう。俺、ペルージャに決めようと思う。胡散臭さはあったけど、チームが俺のサッカーを必要としているんなら、やり甲斐もあるし、あそこまで『欲しい』って言ってくれるんなら、レギュラーだって間違いないだろうし。」
さらにこう続けました。「ヨーロッパに行っても、一つのクラブで終わるつもりはない。絶対に売れる選手になる。必ず実力で、もっと大きな移籍を勝ち取るよ。だから、今はペルージャで決まり。」
次原社長は、中田の身の安全を考え、このあとの行動はすべて極秘で進めることにしました。この頃、中田本人にも日本サッカー協会にも中田選手の生命が危ぶまれるような抗議文が届いていたからでした。
こうして、出発は7月22日、記者会見は成田空港そばのホテルで行ない、その足で飛行機に乗り込むことに決まりました。
中田選手、個人マネージャーとして後藤祐介氏と契約
中田選手は、いよいよイタリアに旅立つことが決まったことを受け、一人の知り合いに、こう願い出ました。
「俺と一緒にイタリアに行って欲しい。ペルージャには入団の条件として、個人マネージャーの同行を認めさせるから。俺のそばにいて見ていて欲しいんだ。俺が戦うのを。」
まるで、恋人に一緒に来て欲しいと言うように願い出た相手は、次原社長の事務所のスタッフでもあった後藤祐介氏でした。
後藤祐介氏と中田選手との出会いは、1996年7月、アトランタ五輪大会で、ブラジル撃破を果たしながらグループリーグ敗退となって帰国した夜のことでした。五輪代表キャプテン・前園真聖選手が成田空港に迎えに来てくれている友人として、その車に乗せてもらったのです。
その夜、後藤氏は前園選手を都内のマンションに送り届けると、厚木にあるベルマーレ平塚の寮まで送ってくれたのです。
中田選手は、車中でアトランタ五輪での自分の満たされない思いを、初対面にもかかわらず、後藤氏にぶつけたのですが、後藤氏はサラリと受け止め、それ以上の詮索をしなかったことが中田選手には嬉しく、これを機に交流が始まったのでした。
後藤氏は前園選手と同じ年齢で、帝京高校サッカー部の経験がありました。卒業後2年間アルゼンチンに放浪の旅に出て帰国後、役者の勉強をしながら次原社長の会社でイベント関係の手伝いをしていました。
その後、次原社長が前園選手のマネジメントを引き受けることになった際、サッカーを知っている後藤氏が前園選手サポートの一員となったのです。
前園選手は第70回全国高校サッカー選手権に出場した高校3年の時、準々決勝で帝京高校に全国制覇の夢を阻まれています。
数年後に、次原社長の事務所でスタッフの一人だった後藤氏が、その時の帝京高校サッカー部員だったことを知り、懐かしい話に花が咲き、急速に打ち解けたであろう様子が目に浮かぶようです。
そこから親友同士になった前園氏と後藤氏、その縁でアトランタ五輪帰りの夜、中田選手は後藤氏と出会うことになったのです。それ以来、中田選手も後藤氏と、心を許せる兄貴分のように感じて交流するようになっていました。
中田選手は、今年に入り、あの朝日新聞記事を発端とした、思想団体からの猛烈な抗議活動が原因で、過度のストレスから来る高熱と皮膚炎を発症した時期、5月9日のG大阪戦のあと新幹線で横浜に戻るにあたり、後藤氏に電話を入れ「新横浜駅まで迎えにきて欲しい」と依頼しました。もはや身体全体の痛みで、とても自力で隠遁先となっている都内のホテルまで帰れないと考えたためでした。
中田選手は都内までの車中で、後藤氏に思い切り弱音を吐いてしまいます。「俺、もうサッカーやめようかな。」
すると後藤氏は「本当に嫌なら、やめてもいいよ、他の仕事だってできるし、また復帰するこたもできるだろ」と明るく答えました。中田選手は、それが後藤氏の真意でないとしても、自分の心を察してくれたことが嬉しく、自分のありのままを話せる大切な人として、自分の中で確実に、単なる兄貴分を超えた大きな存在となっていったのです。
中田選手からの突然の願いを受けた後藤氏には、これまで中田選手の才能と、人知れず抱えていた苦悩を一番近くで見ていたという自負がありました。これまでは次原事務所のスタッフの仕事という枠を超えて、兄貴分として親友として中田選手を支えてきた一方、5歳も年下の中田選手から、多くのことを教えられても来ました。
後藤氏はすでに役者として、多少なりとも仕事をしている身でしたが、中田選手が自分を必要としているならと考えていました。
小松成美氏の著書「中田英寿 鼓動」の中では、後藤氏がこう言って承諾したと記されています。
「俺、仕事でも人生でも、焦ってないから。お前とイタリアに行けば、俺だって、これまでに考えたこともない人生が開けるかも知れない。いつか、帰ってきて、また役者をやったとしても、その経験は俺の血や肉になるだろうから」
こうして26歳の個人マネージャー・後藤祐介氏は誕生しました。これで、中田選手が未知の世界で暮らす不安が大幅に軽減されるであろうことは明らかですが、一方では、自分以外の人生を巻き込んでしまうことになるのも事実でした。
98ナビスコカップ 磐田が市原を下し初優勝
1998年のJリーグナビスコカップは5月16日からグループリーグが始まり、7月19日に決勝が行われました。これは日本代表がフランスW杯に出場する期間、すなわちJリーグのリーグ戦が中断する期間を利用したことによる極めて短期決戦の大会となりました。
グループリーグは5月16日から6月6日、Jリーグ18チームとJFLで準会員の川崎F、ブランメル仙台を合わせて20チームを抽選で4グループに分け、総当たりのリーグ戦を行ない各グループ首位チームだけが準決勝に進むという規定でした。
グループリーグ戦の結果、磐田、鹿島、清水、市原の4チームが準決勝に進出しました。
準決勝は磐田vs清水、鹿島vs市原の組み合わせて7月15日、一発勝負で行われました。その結果、磐田vs清水戦は、W杯日本代表として不在だった選手たちがチームに戻った中で、磐田は中山雅史選手がW杯での骨折のため欠場、ドゥンガ選手もブラジル代表が勝ち進んでいたため、まだ合流しておらず、会場も清水のホームグラウンド・日本平スタジアムでしたが、磐田・藤田俊哉選手、ルーキー・高原直泰選手のゴールで2-0、磐田が決勝に進出しました。
もう一つの準決勝、鹿島vs市原戦もW杯日本代表として不在だった選手たちがチームに戻った中での試合となりましたが、市原のマスロバル選手がハットトリック、鹿島の得点を2点に抑え3-2で勝利、市原が決勝に進出しました。
決勝は7月19日、国立競技場で磐田vs市原の戦いとなりました。4万人を超える観客が見守る中、熱戦が期待されましたが、磐田が川口信男選手の2ゴールに奥大介選手、高原直泰選手のゴールで4得点、守っては市原の攻撃を完封して勝利、まさに王者の貫禄でナビスコカップ初優勝を果たしました。
決勝でダメ押しゴールを決めた高原直泰選手、同期のライバル小野伸二選手がフランスワールドカップのピッチに立ったのを見て大いに刺激を受けたことでしょう。中山選手が同じフランスワールドカップで骨折してしまい、不在の中「やっぱりゴンさんがいないと勝てないのか」と言わせたくない思いもあったことと思います。
これで一気に自信をつけました。翌日のスポーツ紙も「高原、ゴン2世襲名」と見出しを打って活躍を讃えました。
市原は初の決勝進出でタイトル奪取を狙いましたが、立ちはだかった壁は、あまりにも高い磐田という壁でした。
7月22日、中田英寿選手、成田空港でセリエA・ペルージャ入りを発表 26日、現地での第一声、流暢なイタリア語はイタリアメディアより日本サッカーファンの度肝を抜く
いよいよ日本を発つ日が近くなった7月20日、中田選手は成田で行なう記者会見について、自分の希望を次原社長、担当弁護士と相談して一つの文書にまとめました。その内容は「会見で自分が話した言葉を、活字メディアはすべて掲載すること、テレビメディアは編集なしの映像を流すか生中継映像にすること」というものでした。
中田選手は、もはや、報道の自由を盾に、曖昧な情報や嘘がこれ以上、大量に流されることに耐えられなかったのです。
しかし、次原社長は、取材に規制を加えるようなこの方針を報道各社に伝えた場合に、中田本人だけの問題ではなく、他の各方面にも影響が出るのではないかと懸念して、日本サッカー協会の小倉純二専務理事に相談しました。
小松成美氏の著書「中田英寿 鼓動」の中で、小倉専務理事は次のように応じたと紹介されています。
「日本のサッカーはマスコミによって支えられている。マスコミとの信頼関係を損なうわけにはいかない。現状でそうした行動を起こせば、最悪の場合、中田を日本代表に招集できなくなるかも知れない」
次原社長から、このサッカー協会の見解を聞いた中田選手は、協会や他の日本代表選手に迷惑がかかることは望んでいないと、作った文書を破り捨てました。しかし中田選手の心が晴れませんでした。
そして7月22日午前11時、ホテルに設営された記者会見場に集まった200人ほどの報道陣を前に、中田選手は短いコメントを発表しました。質疑応答には中田選手は一切応じず、その分、ベルマーレ平塚の重松社長が全部を引き受ける形となりました。午後から夕方にかけてのテレビ番組が一斉にこのニュースを報じました。
イタリア時間22日の夜、ドイツのフランクフルト経由でローマの空港に着いた中田選手、次原社長、後藤マネージャー、フジタ通訳の4人は、日本のマスコミからの依頼されたイタリア人記者やカメラマンたちの攻勢にさらされました。ペルージャ側の担当者と合流がうまくいかなかったため、さながらパパラッチの追跡劇のようなことになってしまったのです。
翌23日からベルマーレ平塚の上田統括部長代理も加わって、ペルージャとの本格的な交渉が始まりました。24日にはイギリスからゴードン氏も合流して契約をまとめ、7月24日18時から記者会見が行われる段取りとなりました。
しかし、23日午後から始まった契約交渉は、まずイタリア語で書かれた分厚い契約書案を英語と日本語に翻訳する作業から始まったため遅々として進まなかった上、ペルージャと中田本人の契約年数、他クラブへの移籍時に発生する移籍金(ちなみにペルージャがベルマーレ平塚に支払う移籍金は330万ドル、日本円約4億5000万円)、契約期間前に移籍した時に中田選手がペルージャに支払う違約金などについて、双方の主張が大きく食い違い、翌24日になっても延々と続き、記者会見の時間がきてもまとまる気配はまったくありませんでした。
中田選手は24日の交渉の間は別室で1人待機させられていたのです。
しかたなく双方は、5年の契約期間だけを定めた契約書を作り直して、それに中田選手がサインすることで、とりあえず会見に臨むことになりました。
ガウチ家が所有する古城の中庭にしつらえられた会見場で、ガウチ会長が歓迎のメッセージを読み上げたあと中田選手が簡単に挨拶して質疑応答に入りましたが、細かい質問が続き会見が長くなりそうな気配を察したアレッサンドロ・ガウチ氏が中田選手に目配せしました。もう、いつ切り上げてもいいぞ、という合図でした。
そんな時、記者からお誂え向きの質問が飛びました。「イタリア語で何か一言を?」
すると、中田選手がいきなり大きな声で、イタリア語でこう話したのです。
「Basta Adesso ho fame (バスタ アデッソ ファーメ グラッツェ)」(もう終わりにしようよ、お腹が空いたから ありがとう)
これには会場の記者たちも一本とられた、という感じで笑い声とともに思わず拍手も沸きました。この場面が日本で放送されると、日本のサッカーファンは、その流暢なイタリア語、しかもウィットに富んだ言葉を淀みなく話す姿に度肝を抜かれました。21歳の日本人青年が世界最高峰のリーグと言われるイタリアリーグに参戦する、その準備を中田英寿選手はきっちりとしてきたことにあらためて驚かされる場面でした。
ちなみに、この会見で初めて披露された背番号7のついたユニフォーム、実は当初ペルージャ側が背番号8のついたユニフォームを7に変更したことから、日本のマスコミは「中田、わがままを通して7をゲット」という論調で報じました。しかしペルージャ側は、ワールドカップ日本代表で中田選手がつけていた「8」が望みなんだろうと勝手に解釈して作っていただけで、中田選手が「自分はむしろ7を長くつけているので、そのほうがいい」と伝え「それは何の問題もない」ということで当日までに用意されたいきさつがあります。
中田選手がすっかり口を開いてくれなくなった日本のマスコミとの関係を象徴する報道です。
中田選手は、翌25日からさっそく、ペルージャの合宿地、車で2時間ほどのスポーツリゾート地・ノルチャに移動、チームとの練習に合流しました。しかし、中田選手にはまだ、あのジャマイカ戦で受けたタックルから来る足首の痛みがひかないという問題がありました。けれども中田選手は、合宿のはじめから「なんだコイツ、使えないヤツじゃないか」と思われることだけは絶対に避けなければならないと、足首の痛みをこらえて全てのメニューを何食わぬ顔をして、しかもランニングなどでは無理してでもチームメイトをリードするよう振舞いました。
その分、練習が終わると足首は小さなラグビーボールほどに腫れ上がり、アイシングとマッサージに専念しなければならませんでした。果たして足首が悲鳴をあげて壊れるか、痛みがひいてくれるのか、賭けにも似た日々が続きました。
合宿は8月9日まで続きましたが、アイシングとマッサージを続けた効果が表れ、徐々に痛みがひいていきました。中田選手の足首は壊れることなく持ち直したのでした。
プロスポーツ選手の宿命といえるのがケガに強い身体の丈夫さに恵まれるかどうかです。選手としての寿命もそうですし、日々のプレーのパフォーマンスを高く保てるかどうかを左右してしまうからです。
中田選手はご両親から宝物のような頑健な骨格・肉体を授かった、運に恵まれた選手のようです。
もう一つ、この合宿で発揮されたのは、激痛をこらえてでも目の前のプレーをやりきる強靭な精神力でした。人間、痛みに耐えるのは普通の生活でも並大抵のことではありません。それをフルパワーで身体に負担がかかったまま生じる痛みに耐えるのは、想像を絶する苦しさだと思います。
しかし、中田選手は、いまの自分は、その痛みに耐えること以上に大事な局面あると考えた場合、その激痛に耐えきる精神力を持っている選手なのです。
これは、アスリートにおける「心・技・体」のうち「心」と「体」が類まれなレベルにあることを物語っています。
中田選手は、若干21歳にして日本代表で別格の存在となり、世界最高峰のサッカーリーグであるイタリア・セリエAの一員に、多くのオファーの中から自ら選び取って加わった選手です。それほどの成功を勝ち取ることが、なぜ中田英寿選手は可能だったのでしょうか。
この「伝説の年シリーズ」を書き綴っていて、その理由を考える時、中田英寿選手がアスリートとしての「心・技・体」が少なくとも日本最高レベル、そして世界に十分通用するレベルにあったからだというところに行き着きます。「心・技・体」のうち、残る1つ「技」の部分も、今回の移籍活動にあたって多くのチームからオファーを受けたことが、それを物語っています。
中田選手はまだ高校2年生の時に、U-17世界選手権に出場して以来、各カテゴリーの世界大会に出場した経験を持つ数少ない選手です。最初の頃の中田選手は、身体能力を生かしたスピード、身体のキレといった面を武器にしていましたが、サッカーの技量を高めるため相当意識した練習を繰り返し、次第に世界で通用する「技」をも身に付けたのです。
こうした、自分に足りないものを常に加えていく日々の研究・努力ができるというのも中田選手の大きな特徴です。
あらためて中田英寿選手というアスリートは、日本のサッカー選手として最高のレベル、そして世界に十分通用するレベルの「心・技・体」を備えた選手です。そして、それは天賦に恵まれたものもありますが、少年の頃から、自分に足りないものを常に加えていく日々の研究・努力を積み重ねてきて、今の「心・技・体」を作ってきたのです。
そうした積み重ねが、ついに世界最高峰のサッカーリーグであるイタリア・セリエAの一員に加わるという成果となって現われたと言えます。
この中田英寿選手の「心・技・体」については、このあとも日本サッカー界の巨星となっていくサッカー人生を辿ることになりますので、このサイトの「ヒストリーパビリオン」⇒「伝説のあの選手シリーズ」の中で、詳しくご紹介いたしますので、楽しみにしてください。
中田英寿選手のサクセスストーリーは、いわば第一幕を終えたところではないでしょうか? このあと、まずイタリア・セリエAの戦いの場で、私たち日本のサッカーファンにどのような夢を見させてくれるのか、その第二幕の幕が開こうとしています。
チームは8月12日からホームスタジアムで練習を再開、13日からはスペイン・テネリフェ島遠征に入り、いよいよセリエA開幕に向けて実戦でチームを仕上げていく段階に入りました。
Jリーグ前期、W杯期間中の2ケ月半の中断後再開、磐田が優勝、前年後期・年間王者に続き鹿島を凌ぐかのような強さ、清水も大健闘、同じ勝ち点ながら得失点差で優勝逃す
Jリーグ前期は、日本代表が「FIFAフランスワールドカップ98」への準備を含めて5月9日の12節で一旦中断した後、ワールドカップ終了後、7月25日の13節から再開しました。
1stステージは第13節終了時点で磐田・清水・川崎・鹿島・横浜Mの5チームが勝ち点で並ぶという混戦状態になり、そこから4連勝で締めくくった磐田と清水が抜け出し、8月8日最終17節、最終的に得失点の差で磐田がステージ優勝を果たしました。
中断前、5月9日に行われた12節までの順位は、首位ヴ川崎・勝ち点27、2位磐田・勝ち点24、3位横浜M・勝ち点24、4位鹿島・勝ち点24、5位清水・勝ち点24、6位名古屋・勝ち点21。
2位から5位清水まで4チームが同じ勝ち点で、首位首位ヴ川崎を勝ち点3の差で追うダンゴ状の展開となっていました。
【前期13節から最終17節までの動き】
・7月25日13節 首位ヴ川崎が柏に敗れ勝ち点27のまま、2~5位グループの4チームはすべて勝ち27に伸ばし、同じ勝ち点に5チームがひしめく大混戦に。
・7月29日14節 柏にアメリカW杯得点王・ブルガリアのストイチコフが加入、さっそくデビュー戦神戸戦で後半33分ピッチに立つと、さっそく名刺代わりのゴール、4-0の大勝に貢献。
・8月1日15節 川崎・鹿島・横浜Mの3チームが星を一つ落とし、ここまで連勝の磐田・清水と勝ち点3差。
・8月5日16節 清水が広島に勝利、磐田も難敵名古屋を下し、ともに勝ち点36で最終節へ
Jリーグ最年少出場記録 阿部勇樹選手(市原・16歳と333日)
1998年8月5日 前期16節(vsガンバ大阪戦・万博記念競技場)
・8月8日17節 清水は磐田が負けない限り、得失点差で大きく差をつけられているため望みがない状況の中、福岡を3-0で下し6連勝したものの、磐田も平塚に3-1で勝利して同じく6連勝でフィニッシュ。
磐田は前年の後期優勝、年間王者経験によりすっかり勝ち方を身に付け、7月のナビスコカップも初制覇しており、貫禄の優勝だったと言えます。
ただ、あの中山雅史選手の4試合連続ハットトリックというド派手な記録を残したチームが優勝を逃してしまっては洒落にならないところでしたから、清水と同じ勝ち点で得失点差で上回った僅差とはいえ、ホッとする優勝でもありました。
一方の清水、前年は前期7位、後期6位とやや振るいませんでしたが、その前年暮れの経営危機によるクラブ経営会社の変更や、そこまでのサポーターを中心とした市民の後押し、そしてアルディレス監督の契約延長などによりクラブの結束が増しての大健闘でした。惜しむらくは序盤2節からの3連敗でした。
8月16日 慌ただしい日程でJリーグオールスター戦
8月8日に前期を終えたばかりのJリーグ、ワールドカップフランス大会を挟んだため、その後の日程が窮屈になり、8月22日からは後期に突入します。通常年であれば夏の期間ですから、多少長めのオフがあるところですが、そのわずかな期間、8月16日に、横浜国際競技場に約6万人の観客を集めて、第6回目となるコダックオールスター98が行われました。
Jリーグ各クラブを東西に分ける方式に昨年から戻して、ファン投票結果をベースに、他の大会参加のためや、ケガによる欠場などを理由に監督推薦により選手入れ替えで選ばれた合わせて30人の選手が選ばれました。
J-EASTの井原正巳選手が唯一6回連続出場、昨年は京都所属でJ-WASTのメンバーとして出場したラモス瑠偉選手、今年はヴ川崎に復帰して再びJ-EASTのメンバーとして5回目の出場となりました。初選出はワールドカップメンバーに選ばれたJ-EASTの小野伸二選手、J-EASTの山口素弘選手、J-EASTの呂比須ワグナー選手、そして今年Jリーグに昇格した札幌の吉原宏太選手ら12人となりました。
「J-EAST」と「J-WEST」のチーム分けを主な選手とともに紹介しておきます。
J-EASTの札幌、鹿島、柏、浦和、市原、ヴ川崎、横浜M、横浜F、平塚
吉原宏太選手(札幌)、酒井直樹選手(柏)、小野伸二選手(浦和)、武田修宏選手(市原)、中西永輔選手(市原)、カズ・三浦知良選手(ヴ川崎)、北澤豪選手(ヴ川崎)、ラモス瑠偉選手(ヴ川崎)、山口素弘選手(横浜F)、楢崎正剛選手(横浜F)、呂比須ワグナー選手(平塚)
J-WEST 清水、磐田、名古屋、京都、G大阪、C大阪、神戸、広島、福岡
伊東輝悦選手(清水)、斉藤俊秀選手(清水)、名波浩選手(磐田)、ドゥンガ選手(磐田)、ストイコビッチ選手(名古屋)、黒崎比差支選手(京都)、岡中勇人選手(G大阪)、森島寛晃選手(C大阪)、永島昭浩選手(神戸)、柳本啓成選手(広島)、山下芳輝選手(福岡)
試合は前半、J-EASTのペースで進むと35分、カズ・三浦知良選手から小野伸二選手に渡ったボールを受けた武田修宏選手が押し込んで先制します。
しかし後半、J-WESTは、3バックに変更、中盤を厚くすると攻勢に出て、まず後半9分ストイコビッチ選手が同点ゴール、後半15分には右サイドのストイコビッチ選手からのクロスが相手DFにカットされたこぼれ球を森島寛晃選手が叩き込んで逆転に成功、そして、最後の仕上げもストイコビッチ選手でした。
後半31分、右サイドからストイコビッチ選手が大きなサイドチェンジ、これを左サイドで受けた名古屋の同僚、平野孝選手が中に絶好のクロス、それを、またしても森島寛晃選手がゴール、J-EASTを突き放す3点目となりました。
ワールドカップ決勝T1回戦でオランダに阻まれたユーゴスラビア代表キャプテンのストイコビッチ選手、決勝でフランスに完敗したブラジル代表キャプテン・ドゥンガ選手、ともにエキシビジョンマッチでも全力でプレーする2人のスーパーな選手のマインドが際立った試合でした。MVPは川淵チェアマンが森島選手とどちらにするか迷った末、ストイコビッチ選手に、敢闘賞にはスタメン出場でJ-EASTの1点をアシストした小野伸二選手が選ばれました。
9月13日 セリエA開幕、ユベントスとの開幕戦にスタメン出場を果たした中田英寿選手、いきなりの2ゴール、衝撃のデビュー
セリエA開幕を前にもたつく契約交渉のため選手登録も延び延びに
8月15日からのスペイン・テネリフェ島遠征のあと、中田選手の最初の公式戦は8月23日のコパ・イタリア1回戦になるはずでした。
ところが、7月26日の5年契約のみの契約書のあと詳細を固めるはずの契約交渉がまとまらず、少なくとも8月20日までに支払われるはずだった初回の移籍金がベルマーレ平塚に支払われていなかったため、平塚は「移籍承諾書」の発行を保留、そのため中田選手がイタリアリーグの公式戦に出場するためのイタリアサッカー協会への選手登録が終わっておらず、コパ・イタリア1回戦でのデビューはお預けとなったのです。
中田選手不在のまま行われたコパ・イタリア1回戦1Lgのアウェー戦を落としてしまいます。危機感を抱いたペルージャ・カスタニエル監督は、あらためて中田選手を早く使えるようにして欲しいとアレッサンドロ・ガウチ氏に訴えました。
そこでガウチ氏は、ベルマーレ平塚との交渉にあたっていたペルージャ側の代理人・堀田正人氏との契約を破棄しましたが、堀田代理人のほうが降りたというのが真相でしょう。
というのは、堀田代理人は、ペルージャから平塚に支払う移籍金を、自分がペルージャから受け取る報酬で立て替えておくように指示されていたのですが、ペルージャから受け取る報酬が換金できるのは9月以降来年までの間で、8月20日期限の平塚への1回目の移籍金支払いができるものではなかったのです。
ほかにも堀田代理人がペルージャと交わした契約書には、中田選手本人が承諾していない肖像権の使用権や、ペルージャの試合の放映権など、個人が持てるはずのない権利が謳われていて、こうした契約ではあり得ない無知もしくは常識のない内容だったことから堀田代理人の甘さも指摘されることになりました。
堀田代理人がイタリア語で書かれた内容を理解していないまま交渉に臨んでいたのか、それとも、これを機会に少し儲けてやろうという下心があったのか定かではありませんが、こうした内容だったことが発覚すると、ガウチ氏はマスコミに対して「あれは堀田が勝手にやったこと」と吹聴してまわりました。
怒った堀田氏は、代理人を降りた後、自分も会見を開き契約書の内容をすべて公開「ガウチ氏を名誉棄損で訴える」と語る事態に発展しました。
ペルージャというクラブは、現場のカスタニエル監督が中田のサッカーに対する考え方を高く評価して「セリエAで勝ち残るためには中田中心のチームを作る」と言ってくれているのですが、金を払うガウチ家のほうが、次第に中田選手を「金になる商品」と見て、自分が出す金は少しでも少なく、取れる金はいくらでも取ろうという商売人根性丸出しという、いびつなクラブと交渉していることが明らかになってきたのです。
一方、ペルージャと中田本人との交渉も暗礁に乗り上げていました。中田側のゴードン氏と次原社長もガウチ氏との交渉で一歩も引かない構えでいたからです。そのため、いらだったガウチ氏が「代理人がそんなに言い張るなら、ナカタ、今すぐ日本に帰ってもらってもいいんだぞ」と凄むありさまで、中田選手もストレスをためている時期でした。
8月26日午前の練習後、10数人の子供たちに囲まれてサインに応じている時、駆け寄ってきた日本のカメラマンたちに向かって中田選手は「邪魔なんだよ、どけよ、虫けら! 」と言い放ちました。この暴言に、当然の如く日本のスポーツ紙は飛びつきます。27日、中田選手は自ら設定した週1回の記者会見の場で記者から「虫けら発言は本心ですか」と問われると間髪を入れず「本心です。そのままの意味です。」と答えました。
日本時間28日朝のスポーツ紙は「虫けら発言 まったく反省なし(スポーツ報知)」などと批判的に報じました。
9月に入りアレッサンドロ・ガウチ氏が平塚と直接交渉のため来日しました。そこで9月8日までに手付金60万ドル、その後移籍金の残額270万ドル、合計330万ドル(4億4500万円)を一括で支払う契約がまとまったのです。
9月8日の手付金入金を受けて平塚は即刻「移籍承諾書」を発行、それを受けて日本サッカー協会もイタリアサッカー協会に対して「国際移籍証明書」を送付、ついに中田選手の選手登録が実現しました。
それにしても、サッカーの世界における海外クラブとの交渉では、契約書の怖さを改めて知ることになったわけで、現地で活動している日本人代理人でさえ翻弄される非常に難しい世界だという教訓を教えてくれた出来事でした。
イタリア全土はもとより日本中のサッカーファンも驚かせ歓喜させて開幕デビュー
晴れて選手登録を終えた中田英寿選手、公式戦はいきなりセリエA開幕戦、1998年9月13日午後4時、98-99イタリアリーグ第1節、ペルージャvsユベントス戦。
奇しくも1996年1月、短期留学ということで2週間練習に参加したユベントスが最初の相手となったのです。その時、トップチームの練習には参加させてもらえず悔しさを噛みしめながら遠くから眺めるだけの選手たちと肩を並べてにピッチに入場したのでした。
ペルージャのホームスタジアムは観客2万8000人、気温は17℃、あいにくの雨模様にもかかわらず、スタンドは満員で溢れチームカラーの赤と白に染まっています。観客の中には日本から応援にきた中田選手の家族をはじめ友人たち200人がツァーで観戦に訪れたほか、イタリアサッカーに熱心なファンたち、さらには日本からの報道陣も多く、合わせて500人ほどが含まれていたようです。ところどころに日本語の横断幕も見えました、
契約に至るどろどろした暗闘を身をもって体験した次原社長は、所用のため長いイタリア滞在を終えて日本に戻っておりテレビの生放送画面の前にいました。次原社長にとっては、こうして中田選手が海外移籍を実現させてピッチに立っていることが奇跡のように思いで画面を見つめていました。
次原事務所のフジタ通訳と、中田選手の個人マネージャーとなった後藤氏はレナト・クーリのメインスタンドの最上段からピッチに登場した中田選手を見守っていました。隣にはガウチ家のルチアーノ会長とアレッサンドロ社長が、そして、中田選手の難しい契約を見事まとめたゴードン氏も後藤氏たちと肩を並べていました。
相手のユベントスは、マルチェロ・リッピ監督が率いてセリエAを2シーズン連覇、3連覇に向けての初戦でした。先のフランスワールドカップでスーパースターの座に昇りつめたジネディーヌ・ジダンを司令塔に、ジダンの同僚でもありワールドカップ優勝トロフィーを最初に高々と掲げたデシャン、ベスト4まで駒を進めたオランダの心臓部と言われるエドガー・ダービッツ、そしてイタリアの若きエース、デルピエロなどビッグネームがひしめくセリエAの王者です。
我がペルージャは、セリエBで4位だったところからプレーオフで昇格できた地方の小さなクラブ、その中で中田英寿選手がどれだけのことができるのか、特に日本のサッカーファンは過去に、開幕戦でACミランに挑んだジェノア・三浦知良選手のことが脳裏に残っていましたから、ある意味、祈るような気持ちでキックオフのホイッスルを待ったかも知れません。
ましてや、この試合が日本サッカー史全体の中でも燦然と輝く「伝説の試合」になろうとは、誰一人思いもよらないことだったに違いありません。
日本とイタリアの時差は7時間、日本時間9月13日午後11時からのテレビ中継、衛星放送WOWOWが生中継しました。実況は柄沢晃弘アナ、解説信藤健仁氏という布陣でした。
一方、地上波でフジが深夜2時半から録画放送しました。担当は青島達也アナ、解説風間八宏氏とイタリア人、ジロー・ラモ氏という布陣でした。
選手が蛇腹のトンネルを抜けるようにピッチ中央に現れるとカメラマンたちが一斉に群がりました。テレビ画面に大写しにされた中田英寿選手に大勢のカメラマンがレンズを向けますが、中田選手は大きく表情を変えることはなく、それでも胸を張るような姿勢で撮影を受けていました。
そして、小雨模様の中、いよいよ試合はキックオフされました。さっそく王者ユベントスがゲームを支配します。自陣ベナルティエリア付近でのFKを与える回数も増え、たびたびシュートを浴びます。
その間、中田選手は時折、相手陣内に攻め上がった時にきれいなスルーパスを出しますがオフサイドの網にかかったり、味方FWのファウルのためシュートに結びつきません。
そうこうしている内、前半23分、ユベントスに先制されます。自陣右サイド、ゴールまで25mからのFK、デルピエロがやさしくダービッツの打ちやすいところにボールをずらします。それをダービッツが狙いすまして放った左足シュートを、横っ飛びに飛んだペルージャGKパゴットがパンチングしようとしましたが、手を弾くようにゴールに吸い込まれました。雨でスリップしたこともあるでしょうし、ダービッツの弾丸シュートがブレ気味に来たこともあったのでしょう。ともかく先制点を許しました。
このあと、すでにタックルを受けて右膝を痛めピッチの外に出ていたジダンが、そのまま交代、わずか23分でピッチを去りました。代わりにダニエル・フォンセカが入りました。
その直後、前半24分にはペルージャが相手陣内右タッチライン際で得たフリーキック、ラパイッチが蹴ったボールにニアサイドにいた中田選手がヘッドですらし、ボールの角度を変えてゴール前の味方選手に合わせようとしましたが、ボールの角度が変わらず、そのままゴールラインを割りました。
前半30分には相手陣内右タッチライン際でペトラッキが粘って得たスローインからラパイッチが中に入れ、弾かれたボールをさらに二次攻撃、中田選手がゴール前にクロスを入れると味方がヘディングで落とします。するとFWトバリエリ選手がフリーでGKと1対1の場面となりました。しかしトラップしたボールがわずかに大きく相手GKベルッツィ選手に押さえられてしまいました。
今度は、その直後前半31分、デルピエロ選手が相手陣内左サイドを駆けあがり、ボールはカットされたものの左からのCKを得ます。これをデルピエロ選手が蹴るとゴール正面の身長193㎝DFトゥドールが頭で合わせ、あっさりと追加点を奪われてしまいました。
しかしペルージャもホームですから、へこたれてはいられません。前半39分、自陣左のコーナーフラッグのところからボールを持ち出したペルージャは、そのままパスをつなぎ、じわじわと相手陣内に攻め上がります。ユベントスは、2点をリードして前半も残りすくなくなりプレッシャーが弛んできたのでしょう。
時計の針が40分を回ったあたりで、中田が中央に丁寧にグラウンダーで出したパスを、味方選手がゴール方向に持ち出すとみせかけて右サイドのペトラッキにパス、ペトラッキはペナルティエリア内で相手をかわしながらゴール前にクロスを入れます。その時、ペナルティエリア内に侵入していた中田選手が、相手GKの正面の位置からクロスボールに合わせて助走をつけながら大きくジャンプ、ヘッドで捉えたボールはゴールマウスに飛びますが、惜しくもGKペルッツィの正面、がっちり止められてしまいました。地上からかなり高い位置でのヘディングで、中田のジャンプ力があったから届いたという高さ、身体を十分ひねってのヘディングでしたが、GKの足元を抜けるほど叩きつけることはできませんでした。それでも中田選手の初シュートでした。
ペルージャは前半42分にも右サイドで中田選手が粘ってキープしたボールを味方が拾って前線のペトラッキにパス、これをペトラッキが突破して中央にクロス、今度はFWトバリエリに合いますが相手DFに潰されてしまいました。
前半残り時間もなくなりロスタイムに入ろうかという44分、ユベントスが自陣右コーナー付近からボールを繋ぎ始め中央のダービッツに渡ります。ダービッツは左サイドを駆けあがったサイドパックのペッソットに出します。ペッソットはするすると上がるとゴールマウスまで25m以上はあろうかという地点から、思い切りよくシュートを放ちました。ペルージャDFが寄せきっていないところから狙いすまして打ったシュートは、大きく弧を描いてゴールポスト左隅に吸い込まれました。これで3-0、前半だけで絶望的かというリードを奪われてしまいました。
ロスタイム2分50秒後に前半終了ホイッスルがなりました。もはや日本時間、深夜0時になろうかというところでの3-0、テレビ観戦していた日本のサッカーファンの中には、観戦をあきらめた人も多かったのではと思われる経過でした。
ハーフタイムが終わって後半のホイッスルが鳴る頃、雨があがってきました。ハーフタイムで小松成美氏の著書「中田英寿 鼓動」の中では、ハーフタイムにカスタニエル監督が「今のペルージャには失うものは何もない」と言って選手を送り出したとあり、中田は違っていたとあります。「このまま終わってしまえば、多くのものを失ってしまうのだ」と自分に言い聞かせて後半のピッチに向かったというのです。
後半が始まってからのペルージャの戦い方に変化が表れました。驚くべきことに後半キックオフから9分経過まで1本もファウルを与えることなくプレーし続けたのです。
この間、ユベントスのほうも与えたファウルは1本だけ、ボールがタッチを割ってスローインを与える場面は何本かあったものの両チームの攻防が途切れることなく続いた見ごたえのある9分間でした。レフェリーがアドバンテージをとって笛を吹かなかった場面があったせいもありますが、それにしても見事な攻防でした。
しかも、その9分間の多くはペルージャがボールを支配して特に右サイドから何度もペナルティエリアに迫る場面を作ったのです。
そんな中から中田英寿選手のファインゴールが後半7分生まれたのでした。相手GKペルッツィがハンドスローで送ったボールをベルージャの中盤カンポロがカット、右サイドのペトラッキに送ります。このボールがそれてタッチを割りそうになりますがペトラッキはスライディングしながら出さずにキープ、前を向き直すと突進します。そして中にカットインすると見せかけて右アウトサイドでパスを送った先に中田選手がいました。中田選手は右横から自分の前に流れたボールをきっちりトラップ、小刻みにボールを前に運びながらGKペルッツィが守る位置の左側、ゴールポストの間のニアサイドを狙ってふり幅の小さい蹴り足で振り抜きます。
ボールはGKペルッツィが倒れ込んでとめようとするより一瞬早くゴールに吸い込まれました。角度のないところからこじ開けた見事なゴールでした。中田選手のこのシュートは、ある意味もっとも正確に、そしてもっとも威力あるボールを打てる体勢、角度だったと思います。もともと右サイドのウィングプレーヤーだった中田選手は、何度もあの体勢・角度から正確で速いクロスを供給してきた経験があるからです。
この場面では「このままで終わっては、多くのものを失ってしまう」と自分に言い聞かせてピッチに戻ってきていましたから、迷わずシュートを選択したに違いありません。
ペルージャのチームメイトたちは、カスタニエル監督から「失うものは何もないのだから、身体の力を抜いて思い切りやりなさい」と言われたとおりに、後半キックオフから相手に対してファウルをせずに、自分たちのペースを握り続けてプレーしていました。
中田選手だけは「多くのものを失っては元も子もないので気合を入れて」プレーしていたのです。思惑の違っていた10人と1人でしたが、見事に融合してゴールを生み出したのです。
ゴールを決めた中田選手は、右手で拳を握りしめ、自分に言い聞かせるように控えめなガッツボーズを作りました。おそらく小さく声も発したに違いありません。
中田選手はセリエA開幕戦という大きな舞台で、しかも3連覇を狙う王者ユベントス相手にゴールを決めたのです。これ以上ない出来栄えです。けれどもチームメイトも中田選手も、これで十分などとは、つゆほども思っていません。ホームゲームであり、これからの長いシーズンに弾みをつけるためには、何としてもこのまま終わるわけにはいかない気持ちで共通していました。
試合が後半10分を過ぎた頃、また雨が降り出し、すこし激しくなってきました。それに伴い両チームのプレーもヒートアップしてきました。中田選手の1点はユベントスのプライドに火をつけたようです。
後半13分、中盤からドリブルで右サイドを駆けあがるベルージャ・ラパイッチを追うダービッツでしたが追い切れず、一旦あきらめた後、ラバイッチがペナルティエリア内に侵入しそうになると、たまらず背後からタックル、イエローカード。ペルージャがFKを得ます。
ラパイッチが蹴ったFKは相手に当たってCKに、それをラパイッチがショートコーナーにして中田が受け、またラバイッチに戻します。今度はゴール前にクロスを入れましたがユベントスに跳ね返されます。それを中盤でペルージャが拾い、タテにロビングパス、これをペトラッキが頭で落とすと、ボールは1点目に中田選手がボールを受けたと同じ場所に落ちます。それを中田選手は1点目と同じように前に持ち出しました。まるで1点目と同じシュチエーションでした。そしてシュートを放ちました。
1点目と少しだけ違っていたのは中田選手がシュートを放った位置が少しだけ遠かったことでした。その分、GKペルッツイの反応を許し、横っ飛びのペルッツイの手に阻まれてしまいました。それでも攻勢は続きます。ペルージャのCK、ボールは競り合いで真上にあがり、それをペルッツィがパンチングします。
そのボールが落ちたのはペナルティエリアの中、そこに中田選手が待ち構えていました。ボールから目を離さず上から叩きつけるだけを考えて右足をボールにかぶせます。ヒットしたボールは出て来たペルッツイの脇を抜け、ゴールマウスにカバーに入っていたDFもかわしてゴールに吸い込まれました。
痛快な2点目でした。時計の針は14分を指していました。1点目からわずか7分後の出来事です。ペルージャの攻勢を見事に得点に結びつけました。
ゴールを決めた中田選手は向きを変えながら軽く手を叩きました。彼の最大限のガッツポーズでした。そのあとチームメイトが輪を作ってもみくちゃにされます。
すぐセンターサークルに戻って相手のキックオフを待つ中田選手の表情を、やや斜めからカメラが捉えました。「まずは仕事をしたけど、まだまだ・・・」そんな表情に見えました。
スタジアムは狂喜乱舞といった光景でした。雨が降り続いているにもかかわらず、埋め尽くしたペルージャのサポーターは歓喜に沸いていました。王者ユベントスから「ナカータ」が2点も奪ってくれたのです。このあと、まだまだ、いいことが待っているに違いない、そう信じるに足る出来事が起きたからです。
中田選手は、アスリートとしての「心・技・体」を極めて高いレベルで備えた稀有の選手
中田英寿選手のこの英雄的なプレーはなぜ生まれたのでしょうか? 一番強い相手から、一番最初の試合で、そう簡単に2ゴールもあげられるものでしょうか?
並みの選手なら考えられないパフォーマンスでしょうし、日本が誇るスーパースターだったカズ・三浦知良選手さえも何もできずにピッチを後にしたのに、中田英寿選手は、私たちの想像を遙かに超える結果を見せてしまう、これは一体何なのかと考えてしまいます。
考えた先に辿り着く答えが、やはり、類まれな、並外れた「心・技・体」を持ったアスリートだからだという答えです。
特に指摘したいのが「心」の部分、どんなことにも動じない平常心、感情を高ぶらせたりすることのない、起伏のほとんどない「心」の持ち主だという点です。
今回の2点目を振り返りながら普通の人の気持ちと中田英寿選手の気持ちを比較してみたいと思います。
まずGKペルッツィがパンチングしたボールが目の前に来ることになりました。普通の人は「来た!!」とは思い「よし!!」という気持ちになると、身体が固くなってしまうタイプの人と、気持ちがはやってしまうタイプの人と、慎重にしようと考えてタイミングを失してしまうタイプの人など、いろいろです。
ところが、中田選手には、そういう気持ちの揺らぎが起きないのです。すでに後半に入る時に気持ちの集中度を一段と高めていますし、何かチャンスがあれば必ずモノにするという攻めの気持ちも強めていますから、パンチングのボールが来た時は、ボールから目を離さず、上から被せるように、そしてコースを間違わないようにと、技術的なことだけを考えていますし、その「技」も高い水準にありますから、ふかしてしまったり、当て損なったりする確率が極めて小さい状態で蹴っているのです。
パンチングのボールが来てから蹴るまでの間、わずかに1秒です。その1秒の間に確実にゴールをゲットするには、平常心で流れるように身体が動かなければ、とても出来るものではありません。「来た! よく見て!、上から被せて!、コースを間違わず!、シュート!」これを1秒の中で情報処理して身体を動作させているのです。
大舞台なのにとか、初めての試合なのにといった、普通の人が意識してしまう心境とは全く無縁で試合に臨むタイプの選手ですから、平常心そのものなのです。羨ましいと言えば羨ましい資質ですが、逆にそういう感情の起伏の少ない選手だからこそ、チームメイトから「なんでもっと嬉しそうな顔をしないんだよ」とか「ゴールを決めたときぐらい喜べよ」と不思議がられ、変わったヤツだと思われてしまうこともまた、中田英寿選手ならではなのです。
日本代表での試合で、中田選手がこれほどペナルティエリアの中に積極的に上がるシーンというのは、実はあまり見かけないことです。これにはベルージャ・カスタニエル監督からの要求が影響しています。カスタニエル監督もフランスワールドカップでの中田選手のプレーを見ていて、これほどの選手が積極的にゴール前に上がっていこうとしていないことを感じていました。
弱小ペルージャにあって、中田選手がゴールに絡む仕事をしてくれなければ、勝利の可能性を高めることはできないと考えたカスタニエル監督は中田選手に「もっともっとゴール前で仕事をしてくれ」と要求します。
中田選手も、この監督に全幅の信頼をおいて、これからのペルージャで自分自身も成功を勝ち取る決意でいますから、ゴールに絡むことが成功への必須条件だと要求されれば、納得づくでプレーできる選手です。
ここが日本代表との違いと言えます。日本代表における岡田監督との関係は、少し違います。中田選手は、岡田監督がワールドカップで戦える戦術として、自分を中心に据えてくれていることを理解していますから、岡田監督が選んだやり方に忠実にプレーしています。しかし、その役割は、自分もゴール前に積極的に絡んでいくほどの攻撃的なものではなく、むしろ常に守りのバランスを意識してプレーしていくことでしたから、必然的にゴール前まで侵入する場面は少なくなります。
したがって、日本代表でプレーする時には見られなかった積極的なゴール前への上がりが随所に見られたのです。
ペルージャは0-3という絶望的なスコアで前半を終えたにもかかわらず、後半あと30分以上残して2-3としたのです。これで試合はわからなくなりました。
しかし、これでユベントスはイレブン全員が気持ちのネジを巻き直しました。後半開始から2点目をとられるまで、ユベントスは攻めも守りも気持ちが緩んでいたからです。
ユベントスが攻撃の圧力を強め始めると、すぐペルージャは自陣ゴール前に押し込められてしまいました。後半20分、左CKをデルピエロが入れると、ニアサイドでユベントスの選手が二人潰れたところにペルージャの選手も4人道連れになり、ゴール中央にいたユベントス、ダニエル・フォンセカが「どフリー」の状態で身体を倒しながらショートバウンドのボールを蹴り込みゴール、2-4となり、また2点差に開きました。
その後もペルージャの攻撃に対するユベントスのチェックは厳しく、なかなかチャンスが作れませんでしたが、後半42分、中盤から前線に大きく出されたボールをラパイッチが懸命に追いかけてゴールライン間際で残し、さらにペナルティエリアに侵入するとユベントス・ペッソットがたまらずファウル、イエローカードが出されるとともにペルージャ、PKを獲得します。
すでに2点をとっている中田選手のハットトリックを賭けたPKと誰もが期待した場面ですが、中田選手は早々とペナリティエリアから離れてしまいます。チームの決め事だったのか、自分にボールは渡されないと見切っての行動だったようです。キッカーはベルナルディーニ、これを冷静に決めました。後半43分でした。
ユベントスのDFが不安定だったこともあり、ロスタイム3分の中で同点への期待もあって最後までレナト・クーリは盛り上がりました。雨も上がりスタジアムには傾いた夕日も差し込む中、ペルージャは攻め続けましたが後半48分40秒、終了ホイッスルが鳴り試合は終了しました。スタジアムの満員のペルージャサポーターもそうでしょうけれど、日本でWOWOWの生中継やフジTVの録画放送を観戦したファンたちも「凄い試合を見た」「伝説に残るであろう試合を見れてよかった」という気持ちでした。
翌朝9月14日のスポーツ紙は一斉に大見出しで報じました。
・サンケイスポーツ 歴史的! 中田2発、デビュー戦ゴール、地元熱狂ナカタ! ナカタ!
・日刊スポーツ 中田2発、見たかユベントス! 日本の中田、いや世界のヒデだ!!
ヒデすっげぇ、スタンド熱狂
パスでゴールでペルージャ仕切った。次こそ1勝
・スポーツ報知 中田2発!、世界仰天!、どうだユーベ!
・スポーツニッポン 中田ゴール、興奮セリエAデビュー、深夜の日本に大歓声
・東京スポーツ(夕刊) 中田スーパーデビュー2ゴール、最高点8点の評価
ユベントス監督が、イタリアのスポーツ紙が大絶賛
そして9月14日朝のテレビ番組も、軒並みこのニュースをトップで報じましたが、特に放送権を持つフジテレビは「めざましTV」「おはよう!ナイスディ」と続けて中田選手緊急特集を組んで詳しく報じました。同局では「セリエAダイジェスト」という番組も放送していますから、これで、あらたな目玉コンテンツとなった感がありました。
中田選手の海外移籍、真の動機と、イタリアを選んだ真の理由
こうして、中田英寿選手は海外移籍の第一歩を、申し分ない形で踏み出しました。
スポーツ紙やテレビが華々しく報じたこの快挙のニュースを見ながら、多くの日本のサッカーファンは、中田選手の海外移籍を「日本代表の押しも押されぬ中心選手、ナンバーワンプレーヤーが自然な流れとして海外移籍を果たした」と感じたに違いありません。
しかし、それは半分当たっていますが、半分は違っていました。中田英寿選手が日本代表のナンバーワンプレーヤーであることは事実ですが、海外移籍が自然な流れだったのではなく、むしろ追い詰められた末の移籍だったからです。
今年の初めに掲載された、マスコミによる心ない1本の記事によって、中田選手は思想団体からの容赦ない攻撃に巻き込まれ、もはや「日本でサッカーをやるのはゴメンだ、海外に行くしか道はない」とまで追い詰められて始まった移籍計画だったのです。
もう一つ、半分当たっていて、半分は違っていた選択がありました。それは、選んだ地がイタリアリーグという点です。多くの日本のサッカーファンは、中田選手がイタリアリーグを選んだのは「世界最高峰と言われているリーグであり、挑戦の場としてこれ以上ないリーグだから」と感じたに違いありません。
確かにイタリアリーグが世界最高峰と言われているのは間違いありませんし、最初に対戦したユベントスのメンバーを見ても、ワールドカップ優勝の立役者フランスのジダンをはじめ、デシャン、ダービッツ、デル・ピエロなど、まるでオールスターメンバーのような豪華なメンバーが集結するリーグです。
けれども、中田選手は「世界最高峰のリーグだから」といって行先を選ぶ選手ではありません。むしろ、自分の価値観、ライフスタイルに照らして、どこが一番間違いない選択なのか、慎重に比較検討して選んだ先がイタリアであり、それがたまたま「世界最高峰のリーグ」だったに過ぎないのです。
とりわけ中田選手が重視したのは毎日を過ごす環境、それは食生活をはじめとした生活環境であり、毎日プレーすることになるチームの状況でした。中田選手にとってイタリアは「自分に一番合っている」と感じられる国であり「パスタは毎日でも食べられる」というほど相性のいい国だったのです。
そしてペルージャが、何と言ってもカスタニエル監督が指揮をとるチームだったという点です。中田選手にとって、自分のサッカー観を理解してくれる監督であるかどうかは、選択にあたっての譲れない条件であり、自分もまた監督が考えているサッカー観を共有できなければ選択しない基準を持っていましたが、イタリアリーグで名将として名高いカスタニエル監督と出会えたことで、イタリアリーグ挑戦を決断したのです。
このように中田選手の海外移籍の真の動機と、イタリアを選んだ真の理由を整理してみましたが、彼が飛び込んだイタリアリーグ、それは決して桃源郷などではなく、プレーの一挙手一投足までも厳しく言い募る厳しいサッカーメディアの存在をはじめ、サッカービジネスという巨大マーケットに群がり、権謀術数を駆使して暴利をむさぼろうとするクラブ関係者など、およそ日本とは比較にならないほどの怖い社会だということがわかってきます。
すでに中田選手の所属事務所の次原社長は、ペルージャとの契約交渉を通じて、その難しさ、怖さというものを、いやというほど味わわされていましたから、そのあとのビジネスに対して、相当身構えていく覚悟ができていましたが、ペルージャとの契約交渉の渦中から隔離されていた中田選手の本当の戦いはこれから始まることになるのでした。
日本代表監督にフィリップ・トルシエ氏就任、毀誉褒貶半ばする「トルシエ時代」スタート
8月7日の日本サッカー協会技術委員会で「トルシエ氏との契約交渉」決定を受けて、フィリップ・トルシエ氏は、8月29日から9月1日まで4日間、来日して日本サッカー協会との交渉を行なった結果、監督就任内定となりました。
トルシエ氏は、8月31日に記者会見を開き、正式に監督就任受諾の意向を表明しました。
トルシエ氏は、この来日のことを、2001年12月に出版された自身の著書「情熱 フィリップ・トルシエ」(日本放送出版協会刊)の中で次のように語っています。
「(7月12日の大仁技術委員長他との)パリでの会合との違いは、日本サッカー協会にはほかにも選択肢があったことだ。候補者はぼくひとりではなかった。日本国内だけでもジーコやアルディレスの名前があがっていた。フランスサッカー連盟も、ぼく以外にふたりの候補者をあげていた。20人ほどの監督が、このポストに就くことを望んでいてもおかしくなかった。
しかし、そんな状況の中、日本サッカー協会の気持ちをぼくのほうに向けさせたのは、アーセン・ベンゲルの助言だった。名古屋グランパスを去ったあとも、このプロフェッサー(教授)は、日本サッカー界の代表者たちと良い関係を維持していた。ふだんめったに口を差し挟むことのない男だけに、その発言は重みがあり、協会の幹部が注意深く耳を傾けるのも当然のことだった。」
トルシエ氏はベンゲル氏と1980年代初めにコーチライセンス取得の研修を共に受講してから交友関係があり、自身がアフリカに渡ってからも続いていたと述懐しています。お互いに相手を尊重し、敬意を抱き合う、そんな関係があったからこそ、ベンゲル氏はぼくをサッカー協会に推薦してくれたのだろう、と述べています。
週刊サッカーマガジン誌は、98年9月23日号で「大仁邦彌・技術委員長を直撃」と題して「フィリップ・トルシエ氏の起用を決断した技術委員会の狙いはどこにあるのか」などについて、大仁委員長にインタビューした特集記事を掲載しています。
その中で、大仁委員長は「トルシエ氏招請はベンゲル氏の推せんではない」と明確に否定しています。
「サッカー協会の気持ちをぼくのほうに向けさせたのは、アーセン・ベンゲルの助言だった」と振り返っているトルシエ氏と「トルシエ氏招請はベンゲル氏の推せんではない」と言い切る大仁委員長の話は食い違っていますが、日本サッカー協会にしてみれば、もっとも望んでいたベンゲル氏の招へいが叶わなかった中で、そのベンゲル氏が、大仁委員長ではなく、誰かほかの協会首脳陣にトルシエ氏のことを推せんしていたとしても、何ら不思議ではないことです。
のちに、2000年5月12日付けスポーツニッポン紙には、2000年2月に行なったアーセン・ベンゲル氏への「2001年からの代表監督就任要請」に対する回答を得られていない状況を受けて、日本サッカー協会の岡野俊一郎会長がこう述べたと伝えています。
「トルシエ監督はベンゲル監督の推薦(で日本に来たん)だし、この問題(注・トルシエ監督をどう考えているか)についてもベンゲル監督の意向を(技術委員会が)聞いたのかも知れないが、一向に構わない。」
この記事が意味しているのは、やはり、日本サッカー協会はベンゲル氏からトルシエ氏の推薦を受けていたということです。
同日発売(98年9月23日号)の週刊サッカーダイジェスト誌も、大仁委員長への直撃インタビューを掲載しています。それを読むと「ベンゲル氏の推せんを受けたという報道もありますが。」という質問に対し大仁委員長は「それは違います。ベンゲル氏に会う前にトルシエ氏に会っています。」と答えています。
つまり、大仁委員長が「トルシエ氏招請はベンゲル氏の推せんではない」と否定しているのは「協会で作成したリストにトルシエ氏の名前は最初から入れてあり、ベンゲル氏から推せんがあったから入れたのではない。しかも、ベンゲル氏に断られる前にトルシエ氏に会っている」という意味のようです。
ベンゲル氏招へいを断念せざるを得なくなった段階で、技術委員会が残りの候補者から誰を選ぶかというかという議論を行なった中で、大仁委員長がトルシエ氏がいいのではないかと、議論をリードしたと見て間違いないでしょう。そして、それはベンゲル氏からも推薦があったからということではなく、あくまで大仁技術委員長の主体的な判断だという意味なのでしょう。
現に、トルシエ氏に(7月に)面会した大仁委員長は、前述サッカーマガジン誌のインタビューでトルシエ氏を次のように絶賛している。
「トルシエ氏に会って強く感じたのは、日本に対する強い興味、関心でした。また彼はアフリカという環境の下で苦労して実績を残してきている。そういった中で貫かれてきた信念には感心させられました。」
(トルシエ氏は)「非常に責任意識が強く、そのために自分が考えている組織にするという強い意思がある。自分の考えで組織や環境をきっちりと整え、自分の新しいアイディアやモチベーションを選手に与えていくという、リーダーシップがある。」
さらに「戦略家というよりはオーガナイザーということですかね」という記者の問いに対して「オーガナイザーですね。かなり細かいことも事実ですが、若い世代の代表チームへの意見や指導者育成にも時間があればかかわっていくという全体に対する責任感がある。良い意味でのカリスマ性もある。」
大仁技術委員長が、この7月の面会で、かなり「素晴らしい人だ」という印象をもったことがヒシヒシと伝わってくるインタビューです。「若い世代の代表チームへの意見や指導者育成にもかかわっていきたい」というトルシエ氏の考えについても「そこまで考えるのは越権行為」と受け止めるのではなく「そこまで考えているのか」とポジティブに捉えていて、これからの日本代表強化に必要な指導者と感じたのでしょう。
大仁技術委員長がこのような感触を持ち帰り、協会首脳陣に報告すれば、深い関心を寄せるのは自然の成り行きであり、リストアップされた候補者がいくらいても、トルシエ氏について大きな懸念事項がなければ、ほかの候補者を検討するまでに至らなかったのでしょう。
しかし、実際は、トルシエ氏について大きな懸念事項がなかったのではなく、就任要請を前提に来日した協会首脳陣との面会の席でも”極めて優等生としてふるまっていた”トルシエ氏の本当の顔に気が付かなかった、あるいはネガティブ情報を十分集めきれていなかったというのが真実だったようです。
現に大仁技術委員長は、さきに引用した2000年5月12日付けスポーツニッポン紙のインタビューの後段で「アフリカで協会とトラブルになっていたという話は聞いていなかった。」と回想しています。
こうして、つぶさに、トルシエ氏に決めたこの時の監督選定の流れを辿っていくと、アーセン・ベンゲル氏の招へいが成らなかったための次善の選択とも言えますが、たとえアーセン・ベンゲル氏の推薦であっても、トルシエ氏について毀誉褒貶の激しい人物像や、大きな懸念事項、ネガティプ情報を十分把握できていたら、トルシエ氏という選択があったのだろうかと思わざるを得ません。
「トルシエ氏はベンゲル氏を招くことができるまでのつなぎ」という思いがあったので「とりあえずトルシエ氏」ということになったと見る向きもありますが、いずれベンゲル氏が日本代表監督を受諾するという「覚書」でも交わしているならいざ知らず、単なる期待だけで「2002年はベンゲル氏で」と考えるのは無謀な期待というものでしょう。
1998年10月号「ストライカー」誌は、フランスのギバーシュタイン記者のレポートの中で「フランスのスポーツ紙『レキップ』は「トルシエは2000年まで日本代表監督を務め、その後はベンゲルが監督に就任、トルシエはアシスタントコーチに回るものと思われる。」という記事を掲載しました。
「少なくともフランスのメディアは、ベンゲル、トルシエ、日本協会の三者間で、何らかの隠された契約、あるいは口頭による合意があったではないか、という疑いを持っている。もちろん、そうした裏約束があるかないかは誰も知らない。だが、そういうプランが本当にあるとしたら、トルシエを日本代表監督に据えるのは一層意義のあることだ。」と結んでいます。
いくら大仁技術委員長が「ベンゲル氏の推薦ではない」と否定しても、最終的にはベンゲル氏招請という着地点ありきのシナリオがトルシエ監督を誕生させたように思えてしまいます。
しかし、もしトルシエ氏の「人となり」についてもう少し詳しい情報を得ていれば、いくらベンゲル氏に繋ぎたいという願望があったとしても、日本ではほとんど知る人のいないトルシエ氏を選択しただろうか、むしろ、選択しなかったのではないかと、どうしても考えてしまいます。
結局、トルシエ氏を選択したということは、日本のサッカーや日本の文化・日本人の気質に通じている監督のほうがいいのではという考え方ではなく、フランスW杯を制したフランスの強化策、指導力は凄いという評価から入り、まずフランス人のベンゲル氏、ベンゲル氏でダメなら同じフランス人の「トルシエ氏も素晴らしい」から、トルシエ氏でいいのではないか、という流れで決まったのではないかという思いを拭いきれないのです。
8月31日に記者会見を開き、正式に監督就任受諾の意向を表明したトルシエ氏の会見を報じた「サッカーストライカー誌」1998年10月号は「なぜ、トルシエ氏なのか」という当時、同誌記者だった西部謙司氏のレポートを掲載しています。
それによると、協会が「国際的な経験と実績を主眼に」候補者を絞り、その中から(トルシエ氏を)選出したとしているが、トルシエ氏のアフリカでの実績はそれが決定打となるほどのインパクトはない。最大の成功といわれるコートジボワールのクラブチームでの実績にしても(中略)それが数ある候補者の中で格別に優れたポイントになったとは考えにくい、と論じた上で、「そもそもトルシエ氏とはどんな指導者なのか?」と問いかけています。
そして「フランスのギバーシュタイン記者、南アフリカのグレソン記者の記事にもあるとおり、アフリカという異文化の中で、一歩も引かずに戦い続けたタフな人物であることは確かだ。(中略) 戦術能力や成績ではなく、その激しい気性で連盟側と戦い続けたことこそ、トルシエ監督の他にない個性であろう」と喝破しています。
そして「では、日本代表はそのトルシエ氏の個性を本当に必要としているのだろうか」と続け、「田嶋(技術委員会)副委員長は、トルシエ氏を推薦する理由として”組織”をあげる。やはり、トルシエ氏への期待は戦える”組織”作り一役買ってもらうということなのだろう」と推察しています。
その上で「ただ、組織が重要でそこを強化したいという意図があったとしても、トルシエ氏が最適といえるのかという疑問は残る。なぜなら、ギバーシュタイン記者の記事にもあるとおり、トルシエ氏が奮闘してきたのは、ホテルの予約、グラウンドの確保といったレベルでのオーガナイズであり、あるいは連盟の派閥争いに対抗するといったものがメインだった。(中略)日本協会側が期待する<組織>とトルシエ氏が強調する”組織”にズレはないのか? 日本の組織の問題点は、アフリカとは違いのではないか? という素朴な疑問が残る。」と結んでいます。
この「トルシエ氏を推薦する理由として、戦える”組織”作り一役買ってもらう」という技術委員会の意図は、西部氏が指摘しているとおり疑問の晴れない説明です。どちらかと言うと「何だか煙に巻かれたような」説明のようです。
その真意が「サッカー協会やJリーグなどの組織側に問題があると感じたら、どしどし指摘してもらって、いい方向に改革していくのに一役買って欲しい」といった意味なら、いかにも立派な理由に思えますが、その後トルシエ監督が、さんざん協会ともめ続け、また他の組織ともさんざん喧嘩続きだったことを、果たしてどれだけ予測していたのか、その後の関係者の述懐をひも解けば推して知るべしです。
当時の記録を丹念に見ていくと、まず「日本代表監督に内定」という報道を受けた、海外メディアのトルシエを知るジャーナリストたちからも、懐疑的な見方が幾つか伝えられています。
さきにも紹介した1998年10月号「ストライカー」誌は、「(トルシエ氏の監督就任)大いに疑問」という見出しを打って、南アフリカのグレソン記者のレポートも紹介しています。先に紹介したフランスのギバーシュタイン記者のレポートの見出し「(トルシエ氏の監督就任)成功する」と対をなすようなレポートです。
それによると、
「94年アメリカW杯出場を目指したトルシエ率いるコートジボワール代表”エレファンツ”だったが、ナイジェリアに行く手を阻まれた。トルシエはテレビのインタビューでサッカー協会・ディエン会長を『バカ』と罵ったあと、解雇された。その後、南アフリカ、モロッコ、ナイジェリアと渡り歩き、1998年はブルキナファソに渡った。」
「98年アフリカ選手権の開催国、ブルキナファソが次の雇い主だった。弱小ブルキナは開催国のメンツをトルシエに賭けた。そしてトルシエはまたしても渦中の人物となる。ブルキナのスター、ママドー・ゾンゴをメンバーから外して、得意のオーバーホールを始めたのである。だが、この時は政府要人の後ろ盾を得て、トルシエの改革は順調に進んだ。(中略)ブルキナは誰もが予想しなかったグループリーグ突破という快挙を成し遂げた。レフェリーの判定にかなりの恩恵を得ていたのも事実ではあるが、準決勝まで進んだのは大成功といっていいだろう。」
「アフリカ最後の地は、南アフリカ。トルシエにとっては二度目の挑戦だが、今度は代表監督。フランスW杯という大舞台が用意されていた。緒戦の相手はトルシエの母国フランスに決まっていて、彼にとっては最大のチャレンジであった。ところが、またしても彼は自らが蒔いたトラブルにつまずく。トルシエ新監督が代表選手を招集して行なった合宿は”地獄のキャンプ”と報道され、人種差別問題、選手虐待問題にまで発展した。選手との関係は悪化し、W杯緒戦に0-3でフランスに敗れると、チームは完全に自信を失い、トルシエ監督への不信感も決定的なものになった。マルセイユでのフランス戦後、トルシエと選手の間では激論が始まり、トルシエは怒って退席、以後2日間のトレーニングを放棄した。(中略)W杯を含め6試合の指揮を執ったトルシエは、結局1勝もあげられないまま職を解かれている。」
「アフリカにおけるトルシエは、確かに実績を残している。だが、それ以上に彼はトラブルメーカーであり、性急で強引なやり方は常に批判の対象となっていた。戦術面でもこれといった印象を残していない。大いに疑問だ。」
1998年9月2日号「週刊サッカーダイジェスト誌」は、日本代表監督に内定したフィリップ・トルーシエが「白い呪術師」と呼ばれるが、実際の評価はどうなのか、彼を熟知するフランスフットボール誌のヴァンサン・マシュノー記者のレポートを田村修一氏の翻訳で紹介している。
それによると、寄稿の前段では彼の選手歴に始まって、アフリカでの監督歴をざっと紹介しながら、日本代表監督の話について、こう切り出している。
「(フランス)W杯終了とともに南アフリカを離れ、次の就職先を探しているときに出会ったのが、日本サッカー協会の人々だった。正直言って、日本サッカー協会の決断には驚いた。というのも、トルーシエは”白い呪術師”というニックネームのわりに、本当の奇跡をアフリカで起こしてはいないからだ。彼のキャリアは、ベンゲルやサッキ、ジャッケ、ミルティノビッチ、パレイラといった本物の超一流の監督と比べたときに見劣りする。」
「しかし、彼には精神的な逞しさがある。選手には厳格に接し、多くの要求をする。譲歩したり妥協したりするのは彼のイメージに似合わない。練習中の彼は近づいて話しかけるのがはばかられるほどだ。どちらかというと気難しく、人間的には天性の指導者タイプといえるかもしれない。」
「とはいえあくまでも私見だが、彼は重厚さを欠いている。権威はあるが、それはカリスマ性にまでは至っていない。また戦術的にも、他の監督よりも優れているところを見せたわけではない。(中略)」
そして最後に「選手や周囲の人々の心をすぐに捕まえられるようになれば、日本でいい結果を得られるだろう。そのための信頼をどうやって得ていくか。それが彼の課題になる。」
「果たして彼は、日本人が放つデリケートなメッセージを、正確に読み取ることができるのだろうか。たしかにサッカーは世界共通の言語と言われている。しかしアジアのそれとアフリカのそれとでは、明らかに異なっている。」
「これがベンゲルであるならば、話はまったく別なのだが・・・・。」と結んでいる。
・大仁技術委員長は「(トルシエ氏には)良い意味でのカリスマ性もある。」と感じたと語っていますが、フランスフットボール誌のヴァンサン・マシュノー記者は「(トルシエ氏には)権威はあるが、それはカリスマ性にまでは至っていない。」と評しています。こうした違いを見ると、先にも述べましたが、トルシエ氏が日本協会の首脳陣を前に「極めて優等生としてふるまった」こと以上に、自分を権威付けてカリスマ性があるとまで思わせるほどに売り込むことに長けた人物だったように思えます。
それ故、ある人は「素晴らしい」と手放しで絶賛する一方で、その実、トラブルメーカーであり、性急で強引なやり方は常に批判の対象となっていたのだと思います。
・大仁技術委員長は、トルシエ氏と面会した際に受けた、あまりに素晴らしい印象が故に、委員長自らが認めているとおり、トルシエ氏の実像についての情報収集を怠ってしまったことは否めません。例えば南アフリカでばどうだったのか、ナイジェリアではどうだったのか、現地の日本大使館を通じて、トルシエ氏の評判に関する情報を少しでも収集しようと思えば、彼が現地で何らかのトラブルを起こしたことぐらい入手できたと思います。そういった情報を手にした場合にも、果たして協会首脳は、トルシエ氏を選択したのかどうか、今となっては「たられば」の世界でしかありません。
その後、フラットスリーなど未知の戦術、従来の日本の選手が経験したことのないエキセントリックな指導、何もかもが違和感だらけの監督となったトルシエ氏、日本代表を指導した外国人といえば、古くはドイツ人のクラマー氏、オランダ人のオフト氏、ブラジル人のファルカン氏、皆どの人も紳士的でしたし、フランス人の指導者では名古屋のベンゲル氏、この人も紳士的でした、トルシエ氏のように、協会と平気で喧嘩したり、マスコミに毒づいたり、選手をけなしたり、いわば迷惑行為を振りまくような監督はいませんでした。どうして、こんなことになってしまったのでしょうか?
トルシエ氏に決めることにした、日本サッカー協会の大仁強化委員長という方は、つくづく不思議な人だと思います。前年のW杯アジア予選の時も「加茂監督でダメなら岡田コーチ昇格でいこう」と何を根拠に決めたのか、さっぱりわからない決め方をしていますし、今度もそうです。
しかし、これから先にわかる歴史の結末は「トルシエで大丈夫だった」ということになるのですから、前年の「岡田でよかった」という結末とまったく同じです。
なぜ決めたのかわからないけれど、結末は「大丈夫だった。よかった」
これが日本サッカー協会の意思決定のスタイルなのか、とまで思ってしまいます。
ともあれ、1998年9月10日、日本サッカー協会理事会は「日本代表・五輪代表兼任監督にフィリップ・トルシエ氏」を正式決定、1998年9月21日、日本サッカー協会とフィリップ・トルシエ氏が契約書にサイン。日本代表・五輪代表兼任監督フィリップ・トルシエ氏(43歳)の誕生です。
コーチには山本昌邦氏、山本氏は1996年五輪代表コーチからU-20代表監督に就任、1997年ワールドユース選手権出場権を獲得、本大会でもベスト8に導いています。そして昨年磐田のヘッドコーチに就任、中山雅史選手をマンツーマンで指導、今年の大爆発の影の功労者として知る人ぞ知る存在です。
山本コーチは、まだこの時、トルシエ監督と付き合っていくことの大変さを、露ほども感じていなかったと、のちに述懐しています。
このほか、トルシエ監督はアフリカ時代からの盟友サミア氏もコーチに加えています。
またトルシエ監督と選手のコミュニケーションを橋渡しする通訳は、この時はサッカー協会が手配した日本人の方でした。のちにトルシエ監督に影のように寄り添うとまで評されたフローラン・ダバディ氏が通訳となるのは、まだ先のことです。
兎にも角にも、日本代表フィリップ・トルシエ監督は誕生しました。そして、まさに、後年になって毀誉褒貶に相半ばする評価のトルシエ時代の4年間がスタートしたのです。
その4年間も、面白いことに「素晴らしい」と絶賛される実績と「大丈夫なのか」と懸念される実績が交互に繰り返されていて、トルシエ時代の4年間を余計複雑なものにしています。
JOMO CUP’98ドリームマッチ、柳沢敦選手のハットトリックでJリーグ日本人選手選抜が勝利
10月10日、体育の日の中央記念行事として「JOMO CUP’98ドリームマッチ」Jリーグ日本人選手選抜vsJリーグ外国人選抜戦が行われました。
前年はフランスW杯アジア最終予選の日程の関係で、日本代表強化試合の位置づけで、日本代表vsJリーグ外国人選抜戦として行われましたが、今年は通常のスタイルに戻りました。
ファン投票で選ばれた各15名づつが参加して、国立競技場で開催されました。
Jリーグ日本人選手選抜のほうは、監督を務めた柏の西野朗監督が「フランスワールドカップの4戦目みたいなもの」と形容したように、フランスワールドカップ出場メンバーが中心でしたが、ルーキーの浦和・小野伸二選手、柏GK・南雄太選手が選出されるなどフレッシュ感もあるメンバーでした。
一方の外国人選抜のほうは、欧州選手権予選対応のため名古屋・ストイコビッチ選手と柏・ストイチコフ選手が不在だったものの、それでもドュンガ選手、サンパイオ選手のブラジル代表コンビに、横浜Mに加わった元スペイン代表フリオ・サリナス選手、そしてゲスト参加のパラグアイ代表GK・チラベルト選手が加わりました。
スタンドで、就任したばかりのフィリップ・トルシエ日本代表・五輪代表兼任監督が見守る中、試合は前半0-0で折り返すと、後半から中山雅史選手に代わって出場した五輪世代の柳沢敦選手が大爆発、ハットトリックを達成して日本人選手選抜を3-1の勝利に導きました。
柳沢敦選手は今シーズン前期から好調で、4月4日と5月5日にハットトリックを達成するなど鹿島のエースストライカーとして活躍していましたがフランスワールドカップメンバーからは外れてしまいました。それでも腐ることなくシュート練習を黙々と重ねていたそうで、この日10月10日のゾロ目の日に3度目のハットトリックを達成するという珍しい記録も作りました。
これにはゲスト出場したチラベルト選手もお手上げ「日本人FW選手の進歩は素晴らしい」と賛辞を送りました。
Jリーグ後期は5節から13連勝の鹿島が優勝、終盤、横浜F問題が惹起
Jリーグ後期は8月22日開幕、11月14日最終節の日程で行われました。
2ndステージは第10節終了時点で鹿島・磐田・浦和・横浜M・名古屋の5チームが勝ち点差2の中にひしめく状況となり、そこから連勝で抜け出した鹿島と磐田の一騎討ちとなりました。
第15節で両チームが直接対決し、鹿島がマジーニョのゴールを守り切って勝利。第5節から10連勝で磐田を振り切ってステージ優勝を果たしました。
しかし後期終盤には、突然、横浜F(フリューゲルス)の経営危機が表面化、地元のライバルクラブ・横浜M(マリノス)が吸収合併するという案が浮上、Jリーグ機構もやむなくその案を承認するという事態に発展、リーグ優勝の行方そっちのけで、横浜F問題が社会問題として大きく報じられることとなりました。この問題については後述することとします。
【後期の動き】
・9月5日 3節 浦和3連勝、開幕ダッシュ
・9月19日 6節 浦和6連勝、首位キープ
・9月23日 7節 柏・バジーリオ選手、Jリーグ通算5000ゴール目を札幌戦で記録
・9月26日 8節 浦和連敗で首位陥落、変わって横浜M首位に立つ。
神戸、前期9節から続いていた連敗記録15でストップ、中断期間を含めて5ケ月ぶりに勝利(ヴ川崎戦)、前日のフローロ監督辞任でチームが結束か
磐田・奥大介選手と高原直泰選手が、市原戦で同時にハットトリック達成、1チームから2人は史上初の快挙
・10月17日 11節 鹿島、延長で横浜Mを下し7連勝、首位浮上
・10月29日(木) 突然、横浜フリューゲルスが横浜Mに吸収合併されるという一斉報道
・10月31日 14節 鹿島、平塚に勝ちチーム初の10連勝、磐田も勝ち点差1で追走
・11月14日 17節 鹿島、神戸に勝ちチーム初の13連勝で文句なしの後期優勝を地元で達成
ヴ川崎・ラモス瑠偉選手、柏戦を最後に引退
横浜F、マリノスへの合併は覆らず、報道発覚から負けなしのままシーズン終了、後期最終成績7位
この経過を見ていくと序盤戦は浦和、中盤戦は横浜M、そして終盤戦は鹿島怒涛の13連勝でフィニッシュという流れがくっきりと浮かび上がります。
その結果、後期順位は優勝・鹿島、2位・磐田、3位・浦和、4位・横浜M、5位・清水という結果となりました。浦和は3年ぶりに3位を確保しました。
鹿島の優勝は見事でした。終盤に降って湧いたフリューゲルス問題にも動揺することなく13連勝で駆け抜けた圧倒的なチーム力、そして今回のステージ制覇で特に際立ったのは、地元・鹿島地域との強い絆、すなわち「鹿島の優勝はJリーグの理念の勝利だ」という点でした。
これまでJリーグ年間王者1回、天皇杯、ナビスコ杯各1回、Jリーグステージ制覇2回、計5回の優勝を経験している鹿島でしたが、不思議なことに優勝決定試合は5回ともすべてアウェーゲームでした。
ところが今回は、最終17節の試合を地元・カシマスタジアムに16,944人、もはや入りきれないほどの大観衆に見守られて、初めて鹿島サポーターの前で優勝を決めました。
それ以上に、優勝が決まったあと、サポーターとともにビールかけを楽しみ、さらに夜にはホームタウンの鹿嶋市、神栖市、波崎町にそれぞれ選手たちが移動して優勝報告会を開く、しかも鹿嶋市では1度では会場に入りきれず2回に分けて実施、全会場合わせて6000人もの人々と優勝の喜びを共有するという、まさに「Jリーグの理念ここにあり」といった姿が、鹿島の優勝を際立たせました。
Jリーグ各クラブ経営陣は、鹿島の優勝の夜を知って「自分たちのクラブも、かくあるべし」と鹿島に範を見たのではないでしょうか?
鹿島は実は前期5位でした。前年から引き続き指揮をとっていたジョアン・カルロス監督が、フランスワールドカップによるJリーグ前期の中断中に、ケガの治療のためキャンプに遅れて参加したジョルジーニョ選手と確執が生まれ、ビスマルク選手やマジーニョ選手もジョルジーニョ選手に同調したため辞任しました。
クラプは急遽、関塚隆コーチを監督代行として、Jリーグ前期の中断明けの試合を乗り切ったのでした。
その後、フランスワールドカップのブラジル代表に帯同していたジーコが、終了後すぐにカタール代表監督を務めていたゼ・マリオ氏を口説き、鹿島監督に招聘したのです。
もともと、DFラインをフランスワールドカップのレギュラーメンバーで固める強力な守備陣がいて、ジョルジーニョ選手、ビスマルク選手がゲームを作り、柳沢敦選手、マジーニョ選手のツートップが試合を決めるパターンが機能すれば強いチームでしたが、ジーコテクニカル・ディレクターの全力サポートがあったこともあり、指揮をとったゼ・マリオ監督が全く死角のないチームを築き、見事な優勝を果たしました。
U-19アジアユース選手権では3大会連続ワールドユース出場権獲得、小野伸二選手、高原直泰選手、稲本潤一選手らがU-17大会に続き世界へ、U-16アジア選手権は世界選手権出場権逃す
10月17日から10月31日まで、タイで第30回U-19アジアユース選手権が開催されました。日本は前回、前々回と2大会連続でワールドユース出場権を獲得していて、3大会連続の期待がかかる大会でした。
日本代表は、清雲栄純監督のもと、高原直泰選手、小野伸二選手、稲本潤一選手、遠藤保仁選手、中田浩二選手、本山雅志選手、小笠原満男選手、加地亮選手といった将来の日本代表、Jリーグの中心となる選手が多く、のちに「ゴールデンエイジ」と呼ばれる日本サッカー史に残る世代でした。
5ケ国づつで争うグループリーグ、日本は、韓国、中国、イラク、カタールと同組となり、気の抜けないグループでしたが、初戦中国と2-2で引き分けたあと、イラクに6-2、カタールに4-0と快勝、最終戦韓国には敗れたもののグループリーグを2位で通過しました。
勝てばワールドユース出場が決まる準決勝、相手はサウジアラビアです。この試合、本山雅志選手のゴールで1点を先制した日本ですが、その後2点を奪われ逆転されて前半を終了しました。
ハーフタイム、清雲監督から「闘う気があるのか、ボールをもったらもっと早くフィニッシュしろ!」とFW陣にゲキが飛ぶと、後半、高原直泰選手が爆発します。後半7分に同点ゴール、後半11分には逆転ゴールを叩き出すと、勢いはとまらず後半37分ハットトリックとなるゴールを決め、結局サウジアラビアを4-2と撃破、見事、3大会連続でFIFA U-20ワールドカップの出場権を獲得しました。決勝では、またしても韓国に1-2で敗れ優勝は逃しました。
この大会前、実はフランスワールドカップメンバーとなっていた小野伸二選手を招集するかどうかサッカー協会技術委員会と清雲栄純監督との間で綱引きがあったといいます。それは、技術委員会が「小野は上のレベルでプレーさせる」という方針をもっていたためでした。しかしグループーグの相手が、いずれも侮れないチームということで清雲監督の不安が大きくなり技術委員会に強く小野選手のメンバー入りを求めたのでした。
小野選手がいない場合には稲本潤一選手をゲームメイク役にしていたのですが、その分、ボランチが1枚になり守りの不安が大きくなっていたのです。小野選手をゲームメーカーに置き、稲本選手をダブルボランチの1角に回せば盤石の中盤ができあがり、大会でもイメージどおりの試合運びができたのです。
小野伸二選手もフランスワールドカップを経験して、ちょっとのミスが敗戦につながる厳しさを肌で感じてきたせいか、DF陣に対して「もっと勇気と度胸をもって戦わないと、本大会ならここで終わっている」と注文をつけ、チームリーダーとしても小野選手の存在感が大きいことを示しました。
一方、9月3日から9月17日まで、カタールで第8回アジアU-16選手権(のちにU-17選手権に変更)が開催されました。
この時の日本代表は、市原ユースの佐藤寿人選手、清水商の佐野裕哉選手などが中心メンバーで、5チームで争われたグループリーグ、佐藤寿人選手が4試合連続ゴールをあげる活躍でしたが、最終戦でバングラディシュと2-2の引き分けに終わり、2勝1敗1分けの3位、グループリーグ敗退となりました。
フィリップ・トルシエという難解な人物を船長に抱いてしまった「日本代表」丸、未知なる航海への船出
1998年9月21日、日本代表監督に就任したフィリップ・トルシエ氏、さっそく精力的にJリーグの試合を観戦、全国を飛び回りました。そして、まず新生日本代表のメンバー選びに着手したのです。
今回のトルシエ監督の契約の特徴は、フル代表と、翌年行われるシドニー五輪アジア予選を戦う五輪代表の監督を兼任するということでした。日本サッカー協会としても2002年日韓W杯を見据えた場合、五輪代表の成長は欠かせないことから、兼任による一貫指導体制は望むところで、協会とトルシエ監督の思惑が一致したのでした。
トルシエ監督は、福島県Jヴィレッジで行われた10月4~8日までのフル代表合宿、8~11日までの五輪代表(U-21)合宿をこなし、10月25~27日には、フル代表の初戦が行われる大阪で短期合宿を行ないました。その間、10月20~22日にはタイで行われているアジアユース(U-19)選手権も視察するという精力的な活動でした。
フル代表のメンバー選びは、まだ個々の選手について把握していなかったこともあり、サッカー協会がフランスワールドカップ代表メンバーを中心に作成した候補選手リストから、なんと72人もの選手を合宿に呼んだのでした。これには大仁技術委員長も「前代未聞」と驚きましたが、まず自分の目で見て、それからJリーグなどの様子も加味して選び出す方法がとられ、初戦エジプト戦もメンバーも基本的にフランスワールドカップ代表メンバー中心となりました。
メンバーにはセリエAペルージャで見事な活躍を見せている中田英寿選手も招集されました。所属のペルージャにはルチアーノ・ガウチ氏という、独裁者と呼ばれる会長がいることから、日本サッカー協会との間で招集交渉が難航しましたが、中田選手は日本のサッカーファンに元気な姿を見せてくれました。
10月28日、キリンチャレンジ98エジプト戦が、大阪・長居スタジアムで行われました。観客47,996人、トルシエ監督初戦、中田選手凱旋といった関心が集まったこともあり長居スタジアムでの最多観客数となりました。
試合は前半25分、中山雅史選手が得たPKを自ら決めて、これが決勝点、1-0勝利で発進、無難なスタートになりました。
中田英寿も後半27分まで72分間プレー、そのあとトンボ返りでイタリアに戻りました。
皮肉なことに翌日のスポーツ紙をはじめマスコミの多くが「横浜フリューゲルス、横浜Mに吸収合併」という突然のニュースを大々的に取り上げたことから、トルシエ監督のデビュー戦は霞んでしまった感じもありました。
そのニュースバリューを予測したわけでもないでしょうが、試合後のトルシエ監督、会見をわずか3分で打ち切り席を立ちました。身勝手なトルシエ流だけはさっそくエンジン全開のスタートとなりました。
トルシエ監督と最初に関係がまずくなったのはマスコミだったかも知れません。Jヴィレッジでの最初の合宿から練習を非公開にして、その上、エジプト戦の会見がわずか3分、これではマスコミの心証を害するのは当然ですが、そんなことを気にするトルシエ監督ではないことを、これから徐々に見せつけられていくことになります。
11月に入ると、五輪代表(U-21)の活動が始まりました。11月30日からタイで開催されるアジア大会サッカーに参加するための準備です。
11月17日~21日までJヴィレッジで合宿、11月23日にはアルゼンチン代表との強化試合が組まれています。
Jヴィレッジの合宿では、トルシエ流が全開となりました。「もっと闘志をみせろ」と言っては選手を次々と怒鳴り散らしながらユニフュームを引っ張るは、胸をド突くは。自分勝手なプ
と見るや「お前はスターか?」、弱気なプレーと見るや「お前は女か? オカマか?」と答えに窮する質問を選手に投げ続け、指示通りのプレーができない選手にベテランであろうとお構いなし罰走を命じ、ヤワな選手は恐怖を感じる練習となりました。
また練習も、攻撃でも守備でもほとんど相手を置かず、想定される状況に応じた反復練習の繰り返しでした。トルシエ監督は、それを「オートマティズム」すなわち、自分で意識しなくとも自然と身体が動くようになるまで、ひたすらパターンの反復練習を繰り返し身体に叩き込む、そういう考え方でした。
トルシエ監督は「少しのミスですべてが終わる、それだけ厳しい世界を相手にするということを自覚してもらいたい」と涼しい顔でした。
さらにピッチ外でも、例えば食事ではキャプテンが食べ終わるまでは席をたってはいけないなどの管理主義を徹底しました。
11月23日、国立競技場にアルゼンチンU-21代表を迎えて、日本・アルゼンチン修好100周年記念試合が行われました。
トルシエ体制となってからの五輪代表(U-21)の初戦は、47,374人の観客を集めました。リケルメ、アイマール、カンビアッソといった主力選手が招集外となったアルゼンチンU-21代表とはいえ、前年のワールドユース選手権優勝メンバーが4人加わっていて明らかに格上の相手でした。
これに対して、日本代表は、DF宮本恒靖選手、DF古賀正紘選手、MF中村俊輔選手ら本来のU-21代表に、U-19代表から抜擢された小野伸二選手、稲本潤一選手、柏でレギュラーを奪取しているGK南雄太選手らをスタメンに抜擢した布陣で臨みました。
試合は、相手に攻勢を許しながらも、この試合で初めて採用した、守備ラインのいわゆる「フラットスリー」が、宮本恒靖選手の巧みなライン統率もあって、相手をオフサイドに10回もかける試合運びをみせました。
そして前半42分、稲本潤一選手の突破から得点が生まれました。相手陣内左サイドで中村俊輔選手からボールをもった稲本選手、ゴール方向に突進、一旦FW福田健二選手に預けてワンツーをもらってペナルティエリアに侵入しようとしましたが、ボールコントロールがずれて、少し左後ろにいた中村俊輔選手の前にこぼれました。
ボールを受けた中村俊輔選手、一瞬の判断で「GKが前に出ていることが多く、チャンスがあったら狙おうと思っていた」と振り返ったとおり、相手GKはゴールエリアから前に出ていていました。レフティの繊細な左足から繰り出されたループシュートはゆっくりと孤を描き47,000人余の観客の歓声に送られて、ゆっくりとアルゼンチンゴールに突き刺さりました。
まさにファンタジスタ中村俊輔選手ここにありというゴールでした。
中村俊輔選手は厳しい相手のチャージを受け続け、思い通りのプレーができず、また代表チーム内でライバルとなるであろう小野伸二選手との競演ということもあり、気持ちがやや空回りしたこともあって自身の全体のプレーには満足していなかったことから、値千金の決勝ゴールと相殺「プラマイゼロですね」と振り返っていました。
6月のフランスワールドカップで苦杯をなめたアルゼンチンにリベンジを果たしたかのような試合、中村俊輔選手、小野伸二選手、稲本潤一選手が揃った中盤、これに中田英寿選手が加わったらと思うと、大きな期待が膨らむ試合を見た感じでした。
横浜フリューゲルス合併消滅問題勃発、なぜ消滅しなければならなかったのか、ヴ川崎、平塚にも異変
1998年Jリーグ後期終盤に突然降って湧いた横浜フリューゲルスの吸収合併問題、年の初めからワールドカップ狂騒曲に踊っていた日本中のサッカーファンが、シーズンも押し詰まった頃に突然、冷や水をザーッと浴びせられ「いつまでもワールドカップの余韻に浸ってるんじゃない。Jリーグは大変なことになってるんだ。足元を見つめ直せ!!」と喝を入れられたようなものでした。
この問題が発覚したのは10月29日(木)の新聞報道でした。
Jリーグクラブの経営危機は、ちょうど1年前、1997年暮れにも清水エスパルスで表面化しました。その後、清水は地元企業がクラブを引き継ぐことで危機を脱しましたが、横浜フリューゲルスに関しては、その類いの噂がなかったこともあり、唐突感のある報道でした。
この日の新聞は、前日、大阪の長居スタジアムでは日本代表がエジプト代表を迎えた親善試合、そして、それはフランスワールドカップ(W杯)後の初戦。フィリップ・トルシエ監督の「デビュー戦」が最大のニュースのはずでした。しかし「フリューゲルス消滅」のニュースは、2002年W杯に向けたトルシエジャパンスタートのニュースを、後面に追いやるほど衝撃の大きいものでした。
しかし、横浜フリューゲルスの経営危機は、内部では1998年はじめの段階から共有されていたのです。この問題について、後年、どうしても解明したいと、取材開始から4年以上の歳月を費やして『横浜フリューゲルスはなぜ消滅しなければならなかったのか』という著書にまとめたノンフィクション作家がいます。田崎健太氏です。
2024年に出版されたその労作は、やはりノンフィクション作家で写真家でもある宇都宮徹壱氏が「31年間の闇を暴いたのは、職人のような地道な愚直さ」と評したほど綿密で、横浜フリューゲルスの原型となる街クラブが産声をあげた1964年から34年の流れを辿った一つ歴史書としても価値ある書物です。
著者・田崎健太氏は「最終章」の中で、「なぜ20年以上前に消滅したクラブを題材に取りとげるのだ」と何度か訊ねられ「スポーツクラブと支援企業の関係という永遠の問題を抱えているからだ」と応じていた。と書いています。
田崎氏は、膨大な関係者への取材と、その編纂を通じて「スポーツクラブと支援企業の関係という永遠の問題」について、一つの解を導き出したとまでは断じていませんが、かつてJリーグで清水やヴ川崎の監督を務め、その後ブラジルの名門サントスFCの監督に就任したエメルソン・レオン監督を例にひいて、次のように述べています。
「2003年1月、サンパウロでキャンプを張っていたサントスFCの監督だったエメルソン・レオン監督に話を聞いた時のことを思い出した。」
「レオンは前年にブラジル全国選手権で優勝していた。レオンが引き受けたとき、サントスFCは経営危機に陥り、年俸の高い主力選手を放出していた。レオンは下部組織にいた若手選手をトップチームに引きあげて、結果を残したのだ。」(中略)
「フリューゲルスでも同様のことができたはずだ。」
そして田崎氏は、当時の横浜フリューゲルスの親会社である全日空にも、フリューゲルスの運営会社である全日空スポーツにも、本来、企業なら当然行なうはずの「コストを削減して、収入を増やす」という常識的なことを「横浜フリューゲルスの経営」においては誰も行なおうとせず「経営危機? じゃあ、合併だ、消滅だ」と突き進んだのではないかと考え、当事者たちに会い、そのことをぶつけてみようと考えます。
まず、当時の直接の責任者である、全日空スポーツ社長に対して「1998年夏の移籍市場の際、サンパイオ選手にイタリア・セリエA、ACミランから獲得の打診があり、億単位の移籍金を受け取れるチャンスだったのに、どうして、そうしなかったのか? そして1999年元日の天皇杯優勝をもってフリューゲルスの活動は終わり、サンパイオ選手がブラジル・パルメイラスに復帰した際は、移籍金ゼロで手放している、サンパイオ選手というクラブの価値ある資産を無償で手放したとあれば、背任行為に相当すると思いのだが・・」とぶつけたかったのですが、その社長とは結局会えずじまいだったそうです。
その社長にしてみれば「とても合わせる顔がない」という気持ちだったでしょうけれど、「逃げている」との誹りは免れません。
次に、親会社の全日空の担当部長に対して「サンパイオ選手にACミランから獲得の打診があったことは知っていたか? また山口素弘選手や日本代表経験のある選手を移籍させて、ある程度の移籍金を得る、残った若い選手たちに経験を積ませる、そして結果を残した選手を売却して運営資金に回す、南米大陸の少なくないクラブは、そのように経営していますよ・・」とぶつけると、担当部長は「サンパイオ選手のことは知らなかったし、選手を売却して運営資金を捻りだすなんて考えたこともなかった。全日空スポーツに、そういう智恵のある人間がいればよかったんだよな」と呟いたといいます。
この2人の当事者への取材で「横浜フリューゲルスが、なぜ消滅しなければならなかったのか」、おおよその察しがついたかと思います。
横浜フリューゲルス、誕生から消滅までの軌跡
この項の冒頭、田崎氏の著書は1964年から34年の流れを辿った一つ歴史書としても価値があると書きましたが、それによると、横浜フリューゲルスが、まだ神奈川県リーグのアマチュアクラブで、別のチーム名だった1970年代から全日空が関わるようになっています。
「ヨコハマサッカークラブ」という名前で活動していたチームに、1977年、全日空が社員選手を加えるとともに、試合時の移動経費などの面倒を見る形で関与することになったのです。全日空にとっては、前年に勃発したロッキード疑惑によって地に堕ちた社内士気を、サッカー部活動によって高める狙いでしたし、「ヨコハマサッカークラブ」にとっても、今後、関東リーグ、さらにその上を目指すため資金的な基盤強化に迫られていたのです。
1979年、チームは名称を「全日空横浜トライスターサッカークラブ」に変更、1984年、日本リーグ二部昇格を機に「全日空横浜サッカークラブ」となったチームです。
その後、横浜フリューゲルスは、1992年、全日空(ANA)と佐藤工業(SATO)が出資するクラブとなり、Jリーグ最初の公式戦・ナビスコカップの時は「AS(ANAとSATO)フリューゲルス」という呼称で参戦しています。出資比率は全日空が6割、公共土木に強い建設業・佐藤工業が4割でした。
1992年の段階で佐藤工業が出資企業として加わるようになったのは、佐藤工業がもともと富山県発祥の企業であるところに、全日空の社長・会長を長年務めた若狭得治氏が富山県出身という縁で、両社のトップ同士の話で決まったとされています。
1993年にはJリーグの呼称ルール(地域名と愛称)に従って「横浜フリューゲルス」と呼ばれるようになったのです。
この横浜フリューゲルスは、ホームタウンが横浜市だけではなく、日本全国をカバーする航空会社である全日空が母体となっていることもあり、鹿児島、熊本、長崎という九州の3県も「特別活動地域」として認められるという特殊な形でスタートしています。
これは、Jリーグスタート時、全国の中に北海道、東北、四国、九州といったJリーグクラブのない空白地域が多かったことから、少しでも空白地域を減らしたいというJリーグ側の意向に沿って、九州3県を加えたという経緯でした。
しかし、横浜市には「マリノス」があり、九州での試合も結構多かった「フリューゲルス」は横浜に定着しきれず、横浜でサッカーというと「マリノス」というイメージが定着し始めてしまい、難しい状況になりました。
1996年に福岡県のアビスパ福岡がJリーグに昇格したこともあり、「特別活動地域」の認定は1995年で終了、1996年以降は原則として横浜市だけの活動になったのですが、ホームタウンでの人気はマリノスに及ばず、結果的にはそれがクラブ経営を苦しくさせる要因のひとつとなりました。
そうした経緯と背景を踏まえて、横浜フリューゲルスの経営がどのような経過で危機的状況に陥っていったのか、田崎健太氏の著書から引用する形で、時間を追って記録しておきたいと思います。
・1995年シーズンを迎えるにあたり横浜フリューゲルスは、日本代表監督に転出した加茂監督の後任にコーチを務めていた木村文治監督が就任、一方で、新外国人獲得による戦力強化を目指した。その結果、ブラジル・バルメイラスからジーニョ、サンパイオ、エバイールの3選手を獲得、その見返りとして横浜フリューゲルスからFWのバウベル選手をパルメイラスにレンタル移籍させるという交渉がまとまった。この時投資した額がいくらかは明らかにされていないが、関係者によればレンタル移籍料の相殺分があったので支出は抑制できたという。
・1995年、Jリーグで活躍している外国人選手の所得税の処理方法について国税局の査察が一斉に各クラブに入った。
この頃、外国人選手に対してクラブが提供してした住居や自動車は、本来、選手の所得として処理すべきところを、会社が損失として処理していたのを、外国人の数が増えてきたことから国税局も見逃すまいと査察に入った。
この査察の際に、フリューゲルスの収支を精査してみると「こんな収支でやっていけるんですか?」という内容だった。フリューゲルスの関係者の返事は「不足分は本社から来るから大丈夫」ということだった。
「全日空スポーツ」の経営陣には、赤字を減らすという発想がなかった。本社からの補填分は数億円程度だった。
・1996年、Jリーグが1シーズン制で行なわれたため年間試合数が前年に比べ15試合も減り、加えてフリューゲルスの1試合平均入場者数も1995年から約2000人減っており入場料収入が大幅に減少した。
さらには、この年招聘したオタリシオ監督がブラジルからコーチを何人も連れてきたため、これが結構な額にのぼり、その結果、この年は全日空が10億円、佐藤工業が6億円補填することとなった。
・その一方、「全日空スポーツ」の親会社の一つである出資比率6割の全日本空輸(全日空)は、世界的な格安航空会社の参入による価格競争の流れ(いわゆる航空ビックバン)や、バブル経済が弾けたことによる乗客の出張費削減、レジャーにおける飛行機利用の減少などから国際線での赤字が続き、会社全体として厳しい経費節減に取り組み始めていた。
・「全日空スポーツ」のもう一つの親会社、出資比率4割の佐藤工業の経営も、主力事業である公共土木工事の減少や、バブル期に広げたリゾート開発の行き詰まりなどで、かなり厳しさを増してきていた。
・1997年9月に佐藤工業が発表した再建計画の記者会見の席上「フリューゲルスからの撤退も検討している」と発言した。この発言はすぐに社長名の文書で撤回されたが、覆水盆に返らずの印象だった。
・そして1998年1月、佐藤工業は「全日空スポーツ」への出資比率を4割から3割に下げると発表、同時に1999年には撤退すると発表した。
・佐藤工業が音を上げた時、全日空1社だけで支え切れるかどうか、すでに全日空は本体だけでのコスト削減に留まらず、子会社を含めたグループ全体の高コスト体質見直しを図ろうとしていて、本体経理部から「全日空スポーツ」への補填は今年(1998年)まで、と通告された。
・1998年3月5日、全日空は年度決算会見を行ない、30年ぶりに「無配」すなわち株主配当ゼロを発表した。
1997年に「全日空スポーツ」に補填した額は10億円、全日空本体の経営危機が表面化したことから「全日空スポーツ」への補填は経理部からの通告どおり、今年、1998年をもって打ち切られることになった。
・しかし事態は「補填打ち切り」だけに留まらなかった。本社で「全日空スポーツ」の経営をチェックする部門である関連事業部は、これまでもたびたび「全日空スポーツ」の経営陣に対して「収支を改善せよ」「経営を立て直せ」と警告しているのに、改善の兆しがみられないことを、本社経営陣に報告していたことから、本社経営陣は「フリューゲルス」そのものから撤退するという結論を出した。
・関連事業部は「フリューゲルスからの撤退」の稟議を起案、本社では1998年3月以降、撤退に向けた動きに変わっていくこととなった。そのことは「全日空スポーツ」側には何一つ知らされなかった。
・全日空本社では「フリューゲルスを手放すのに譲渡金などいらない、継続して年間2~3億円は負担するという条件で、とにかく引き受けてくれるところを探すこと」という方針のもと、はじめは金融機関ルートから探したが経済環境が悪く引き受け手が見つからなかった。そんな時、一人の役員から「日産自動車に合併をもちかけたらどうか」という意見が出た。
・関連事業部サイドは「スポーツの世界で2つのチームが合併するというのは難しいのではないか」と答えると「相手に話をする前から諦めるな、まずは可能性を探れ」ということになり日産自動車にあたることになった。これまで八方手を尽くした上、もし日産自動車もダメなら、全日空は「腹をくくってやるしかない」という方針を決めた。
・話を持ちかけられる側となった日産自動車も実は、バブル崩壊以降、不振にあえいでいた。1998年3月期決算での有利子負債は約2兆円を超えていて、この数字は日産グループ全体の連結売上高の75%に相当する経営の重荷になっていた。日産自動車が子会社であるマリノスをどうするか検討していることは明白だった。
・全日空から日産自動車の人事部に連絡をとると「非常に興味がある、すぐに会いたい」という返事があり、すぐ両者の役員同士の話し合いになった。日産自動車は「横浜の2つのチームが一緒になるのは非常にいい話だ。日産としても経営が厳しいので、1つになってやれるのはありがたい。」ということだった。
・全日空は「マリノスを主体として全日空が支えるという形ではなく、一緒に横浜を強くするという対等な関係で合意した。」と受け止めた。そして「フリューゲルス」の「F」を残すため「横浜F・マリノス」というチーム名とすることについてもマリノス側の了承を得て、シーズン終了後に正式発表することとした。
・全日空本社は、これを「全日空スポーツ」の経営陣に通告した。「全日空スポーツ」の経営陣は突然の通告に「佐藤工業が手を引き、これからは全日空だけでやっていくものだとばかり思っていたらマリノスと一緒になるとは何事だ」と怒りを露わにしたが「これはすでに親会社の決定事項」と言われて従うしかなかった。
・1998年10月6日、「全日空スポーツ」社長と、横浜マリノスの運営会社「日産フットボール」社長が、川淵チェアマンを訪問した。2人は「両チームが合併することになった」と切り出し、事の経緯を川淵チェアマンに説明した。
川淵チェアマンは「びっくり仰天だよ、まさか合併するなんて、しばらく声がでなかった」というほど驚いた。
加えて、川淵チェアマンは「日産フットボール」社長が、日産自動車グループの労働組合である「日産労連」の会長経験を持つ、日産経営陣の中でも大変な発言力を持つ人物であることを知っていたことから「この話を覆すことはおそらくムリだ」と観念せざるを得ないと感じた。
・川淵チェアマンは2人に「サポーターは反対するし、選手も動揺する。きちんとしたタイムスケジュールを作り、どういう話し方をするのか、フォローはどうするのか、あらゆる問題を整理して話を詰めて欲しい。他言は無用、発表する最後の最後まで、さまざまな角度から検討して欲しい」と要請した。
この日の話は、発表日が未定のまま終わったが、その後、正式発表は11月1日と決まった。
・関係者だけの極秘事項であったはずの「合併話」は、漏れてしまい、10月29日(木)の新聞報道となった。
・新聞報道が出たことから「Jリーグは承認したのか?」と問われることが必至であり、Jリーグも、29日、即座にJリーグは臨時理事会を開催し、両クラブの合併を承認した。
Jリーグ規約では「リーグを脱退するクラブは1年前に申請しなければならない」と規定されていたが、Jリーグ内部にも『クラブをなくすのは絶対にだめだ。なんとか存続させるべきだ』という考えがあり、最終的には同じ横浜市のマリノスに引き取ってもらうなので、形式上、脱退ではないという決定だった。両親会社による決定事項に理屈づけをすることが最優先だった。
・同10月29日、Jリーグ川淵チェアマン、日産フットボール高坂社長、全日空スポーツ山田社長が揃って記者会見、両クラブの合併を正式に発表した。
以上が、横浜フリューゲルスの経営危機と横浜マリノスとの合併に至る表向きの経過です。
寝耳に水の出来事だった選手、サポーターたち
選手たち、サポーターたちにとって、10月29日の新聞報道による「合併」発覚とJリーグによる正式発表は、まるで寝耳に水の出来事でした。GK楢崎正剛選手などはトルシエジャパンの初戦エジプト戦のメンバーとして大阪市内に滞在しており、そこでニュースで知ったほどです。
しかし選手たち、サポーターたちは「自分たちが行動を起こせば合併を白紙に戻すことができるのではないか」と一縷の望みを捨てずに、即座に署名活動や球団、Jリーグへの要望活動を試みます。
川淵チェアマンが指摘したとおり、選手たちの動揺とサポーターたちの怒りが噴出して、特に「全日空スポーツ」の経営陣は矢面に立たされます。
田崎健太氏の著書『横浜フリューゲルスはなぜ消滅しなければならなかったのか』には、それらの動きについても克明に記録されています。選手たち一人ひとりに丹念に取材して、その当時の胸の内、その後の心の軌跡を描いています。
また「全日空スポーツ」の経営陣たちの苦悩に満ちた日々も描いています。
そこには、自分たちに関わることを、親会社という遠いところで決められてしまったことに対する怒りと無力感に苛まれながら、選手もサポーターたちも「言ってどうなるものでもないことを知りながら言わずにはいられない」心の叫びとも言える心情が綴られています。
選手、サポーターたちのそうした叫びを、ひたすら受け止め続けることしかできない、自分たちに課された過酷な役割を「全日空スポーツ」の経営陣たちもまた、勝手に決めた親会社に対する怒りと無力感に苛まれながら果たしていました。
結局のところ、選手たち、サポーターたちの署名活動や要望活動は徒労に終わります。両チームの親会社は、この動きをどう見ていたのでしょう。「何をやっても無駄だよ、もう決定したことなのだから」と思って見ていたのでしょうか。
大企業の上層部から見れば、選手たち、サポーターたちの動きは末端の些末な出来事だったのでしょうか。時には何千人もの社員の生活に関わるような決断を迫られることがある大企業の経営を考えれば、致し方のないことなのでしょうか。
報道による発覚直後からの選手、サポーターたちの必死の活動の足跡
報道による発覚後の選手、サポーターたちの必死の活動ぶりを当時の関係者の証言や報道などから時系列的に記録しておきます。最初は、無駄なこととは知らず踊らされ、次第に無駄なことと思いつつも、何かをせずにはいられない気持ちの何と空しいことかを、のちのちまで語り継ぐために、克明に記録したいと思います。
・新聞報道の日、10月29日、横浜フリューゲルスは、午前9時半からの練習前、クラブハウスで山田社長が選手たちに新聞報道の内容がおおむね事実であることを認めた上で「クラブの経営が成り立たなくなり合併せざるを得なくなったこと」「他のスポンサーを探したが見つからなかったこと」「親会社・全日空の決定なので仕方がないこと」と説明しました。
実は、この日、社長からの話があることについては、2~3日前に連絡されていましたが、内容を知らされていなかったため新聞報道で知ることになったのでした。
・新聞報道の翌日、10月30日、10数人のフリューゲルスサポーターが行動を起こしました。Jリーグオフィスを訪問、アぽなしで川淵チェアマンをたずねたのです。川淵チェアマンは事務局スタッフが「アポなしですし、会わないほうがいいと思います」と進言したにも関わらず会いました。川淵チェアマンはのちに自著「Jの履歴書・日本サッカーとともに」の中で「会わないと逃げていると思われるのが嫌で部屋に通した」と書いています。
常識的にはアポなしの訪問に会わなくても「逃げている」ことにはならないのですが、そこが川淵チェアマンの、他のリーダーと違うところです。
そして、川淵チェアマンは、彼らの話が単なる感情的なものではなく「自分たちにプランがあるので11月末まで合併話を凍結して欲しい」という内容に驚きました。
つまり彼らの話は「11月末までにフリューゲルスを助けるスポンサーを探すから待って欲しい。J2に落ちても応援するから残して欲しい」という嘆願書を携えての真摯な要望だったのです。彼らが礼儀正しく、それでいて必死な気持ちの話しに川淵チェアマンも思わず落涙してしまったそうです。
サポーターたちも、川淵チェアマンも涙ながらに自分たちの話を真剣に聞いてくれたことと感じたのでしょう。声を荒げることなく「よろしくお願いします」と言って帰ったそうです。
川淵チェアマンは、サポーターたちの気持ちを痛いほど理解できましたが、もはや「フリューゲルスを助けるスポンサー」が見つかるような日本経済の状況でないことは、これまでの全日空の対応からも明らかでしたし、ここは心を鬼にするしかないと考えたといいます。
・新聞報道から2日目の10月31日、合併のことを世間が知ることになって初めての、横浜フリューゲルスの試合(Jリーグ後期14節)対C大阪戦が、横浜国際競技場で行なわれました。スタジアム前では開門前からサポーターたちによる存続を求める署名活動が行なわれました。
この日の観客は14,234人、観客席には「Mと合併? ふざけるな」とか「合併撤回の道は残っている」などと書かれた横断幕が掲げられました。横浜国際競技場でのフリューゲルスの試合は最後になる関係もあってか、場内の大型ビジョンに1993年のJリーグ開幕からの横浜フリューゲルスの歴史を辿る映像が流され、これが選手たちにとっては「クラブ消滅は既成事実」といわんばかりに映ったことから、反骨心に火を付けました。吉田孝行選手のバットトリック、永井秀樹選手の2ゴールなどチーム新記録となる7ゴール、守ってはGK楢崎正剛選手が完封しての圧勝でした。
サポーターたちとクラブの話し合い、10月31日は深夜2時半頃まで、11月2日は翌朝7時半頃まで延々と
試合後、クラブ社長をはじめ幹部が5000人ほど残ったサポーター席の前に立ち経緯を説明しました。
しかし説明が終わっても納得できないサポーターたちが約1200人残り、存続を求めて口々に意見を述べました。
「みんなが少しづつお金を出し合えばチームは続けられる」「2部でも地域リーグでもいい。とにかくフリューゲルスをなくすな」「全日空が勝手に出ていけばいい。フリューゲルスを道連れにするな」(11月1日スポーツ報知)
「(クラブ幹部が)オレたちと同じ気持ちだというなら署名してくれ。社長がまず署名してくれないと他の人たちもできない。してくれ。」(11月1日スポーツニッポン)
サポーターたちの直談判はスタジアムが閉鎖される時間の深夜になっても続き、スタジアム外のメインゲート付近に300人ほどが残りクラブ側に合併撤回を要求しました。クラブ社長は「親会社にサポーターの意見を伝え11月4日までに回答します」と約束しましたが、サポーターたちは納得せず「いますぐ親会社の社長に、この携帯電話を使って電話を入れてくれ」と要求、サポーターたちの携帯電話10数台を並べて「サポーターの熱意がわからないのか!」と怒鳴った。(11月1日日刊スポーツ)
この日の「話し合い」は結局深夜2時半頃まで続いたのでした。
・同じ日、横浜マリノスは、京都西京極競技場で京都サンガとの試合を行ないました。試合後、300人ほどのマリノスサポーターがクラブ幹部からの説明を受けましたが、サポーターたちの怒りは大きく、クラブ幹部はサポーターの一人から投げ付けられたハンドマイクで額から出血してしまい、応急処置をうけながら対応するという受難の日でした。
・11月1日、日曜夕方の横浜駅前で署名活動を行なうため選手24名とスタッフ12名がサポーターたちとともに集まりましたが、署名活動は事前の許可が必要で、それをとっていなかったことから15分後には制止され中断となってしまいました。
・11月2日20時、親会社・全日空とサポーター代表との「話し合い」が持たれました。集まった200人ほどのサポーターの中から60人ほどが親会社・全日空担当者との話し合いに臨みました。
しかし、話し合いはサポーター側の「合併は撤回せよ」、全日空側の「会社として手続きを踏んだ上での決定なので撤回できない」、話し合いは平行線、堂々巡りのまま翌朝7時30分まで、11時間30分も続いたのでした。
・11月3日、スポーツ報知1面に「マリノス、フリューゲルス合併、白紙も」の大見出し、これは、夜を徹して行なわれた前夜の話し合いの中で出た、佐藤工業広報部長の発言をスポーツ報知記者が思い込みで書いたものと思われました。
・11月3日、祝日でのJリーグ開催日のため全国の試合会場で「横浜フリューゲルスの存続を求める」署名活動が繰り広げられました。この日の日刊スポーツは「広島に移動するフリューゲルスイレブンが、全日空便での移動を拒否して新幹線で移動」という記事を掲載しましたが、これは違っていました。初めから新幹線移動を予定していたのに、今回の問題に引っかけて書かれたものでした。フリューゲルスはこの日の広島戦も2-1で勝利、この日の朝まで親会社・全日空との話し合いに参加していたサポーターも含めてアウェーゲームに駆け付けた200人ほどの応援団に勝利をプレゼントしました。
・11月3日、国立競技場で行なわれた横浜マリノスvs浦和戦の試合前、マリノスサポーターがクラブ側と話し合いの場を持ちました。
・11月4日、広島から慌ただしく横浜に戻ったフリューゲルスの選手たちは、横浜マリノスの選手たちとともにJリーグ選手会事務局と顧問弁護士と会合、チーム存続の可能性を探る方法について2時間ほどの打ち合わせを行ないました。会合後、フリューゲルスの選手を代表して前田浩二選手会長が内容を説明しました。それによると、
①川淵チェアマンとの話し合いの場を求める、②全日空からの事情説明の場を求める、③合併の再検討を「全日空スポーツ」「日産フットボールクラブ」両者に求める。
・11月5日夕方、「全日空スポーツ」の経営陣とフリューゲルス選手全員の話し合いが行なわれましたが、両者の意見は平行線。「全日空スポーツ」の一人は「ただ選手の恨みつらみを聞く、頭を下げるだけ、だってこちらの代案は何もないんだから」
田崎健太氏の著書『横浜フリューゲルスはなぜ消滅しなければならなかったのか』では、この時の山口素弘選手の印象を山口選手自身の著書から引用して、こう紹介されています。
「(全日空スポーツ側は)『すみません。私どもの力不足です』 そう謝るばかりで、それはもう質疑応答というものではなかった。」
「『新しいスポンサーを、ちゃんと探したんですか』『探しましたが、見つかりませんでした。私どもの力不足でした。』 話し合いは1時間半にも及んだ。しかし、何の進展もなかった。時間がたつにつれ選手が感情的になるだけだった。」
「『合併が発表されたのが10月29日、昨日までの1週間、僕らには何の連絡もなかったけど、いったいなにをしていたんですか』『いつ合併の話が出たんですか』 そんな質問にもただ言葉を濁すだけだった。(中略)山田社長の返答はなんの実りもなかった。時間の無駄だった」
選手たちからはクラブ側のあまりに情けない対応ぶりに「天皇杯をボイコットしよう」と泣きながら悔しさをぶつける話も出たといいます。しかし、クラブ側には1986年に旧・全日空チームが起こしたボイコット事件を知る人がいて「それをやったら選手生命が終わってしまう」と考えたそうです。とは言っても、それを話しても選手たちが聞く耳を持たない負のスパイラルに陥っていたら元も子もない、逆に天皇杯を戦うモチベーションを示そうということで「天皇杯で1試合勝つたびに勝利給1000万円を出すよう全日空に掛け合う」という提案をして収めたといいます。
選手たちは、自分たちの今後をしっかりと確保する方向に対応方針を切り替え
・11月6日、選手たちは午前、再びクラブハウスに集まり11月4日に打ち合わせた方針を再確認しました。前夜は感情的になってしまい、捨てゼリフを残しながら散会した感じでしたが、この日は冷静になっていて「このあと自分たちはどうすべきか」という考え方で打ち合わせを行なったといいます。
もはや、怒りや追及からは何も得られないと考えた選手たちは、自分たちの今後をしっかりとした形で確保するための戦いに切り替えたのでした。
・11月6日、横浜マリノスの選手たちに対してクラブ側から事情説明が行なわれました。
・11月6日、サポーターたちが横浜市議会に対して陳情書を提出、行政による合併の回避、スポンサー募集の助力を求めました。
・11月7日、今シーズンのホーム最終戦、対福岡戦、スタジアムに選手たちのクラブバスが到着すると全員黒のスーツに揃えた選手が降り立ち、サポーターたちに配るスマイルカードの企業名は黒く塗りつぶされていました。キックオフ前の写真撮影、先発イレブンはユニフォームの胸と腕についている企業名を片手で覆ったまま撮影に臨みました。精一杯の意思表示でした。
この日の三ッ沢公園球技場には13,156人の観客が集結、見納めになってしまうかも知れないフリューゲルスの応援に駆けつけたのです。
試合は、この1週間、合併問題に翻弄されてきたフリューゲルスの選手たちの疲労の色がありありと見られましたが、サポーターたちと気持ちが一つになったエネルギーで福岡の攻撃を凌ぎ2-1で勝利、ホーム最終戦を終えました。
通常ならサポーターとともにシーズン終了の労をねぎらうはずのセレモニーも、この日は17時を回った薄暮の中、口々に「あきらめてはいない」という言葉を発しながらのセレモニーとなりました。マイクを握ったゲルト・エンゲルス監督は「だれでもいい、助けてください」と声を張り上げました。
しかし、クラブの山田社長が挨拶に立ち、横浜マリノスと合併することになったと報告「これは、さらなる経営基盤の確立、地域密着を目指すものなので、予定どおり行なわざるを得ない。フリューゲルスは新チームの中に生きていく」と声明文を読み上げました。
サポーターたちからは大きなブーイングが浴びせられましたが、山田社長はそのブーイングを背にスタジアムを後にしました。
サポーターたちが結束「横浜Fを存続させる会」を発足させる
・11月7日、横浜フリューゲルスサポーターによる「横浜Fを存続させる会(代表・辻野臣保氏)」が発足しました。それまで3派に分かれていた団体が、組織を一本化して戦いを続けて行くことになりました。この日さっそく20時からクラブ側に対して、・合併の白紙撤回、横浜Fの存続、・チーム名、ロゴ等の使用権利の第3者への譲渡、・合併調印の延期、を要求しましたが、すべて却下され、11月下旬には両チームの合併調印が行なわれる予定であることも通告されてしまいました。
しかし「横浜Fを存続させる会」は、これまでに全国から集まった約5万人の署名を全日空本社に届けるなど、チーム存続を目指して活動を続けることにしています。
・11月8日、Jリーグ選手協会(会長・柱谷哲二氏)が都内のホテルで各チームの選手代表者による会合を開催、議題は「リストラで職を失う選手の救済策」今回の合併問題を踏まえて選手協会としてできることを議論しましたが、予定時間をはるかにオーバーして5時間に及んだにも関わらず、立場や利害が異なるチーム、選手たちの議論のため、柱谷会長は「何も決まりませんでした」と発表するしかありませんでした。
このあと、急遽、選手協会の役員だけのミーティングが行なわれ「サッカー人気の回復を図り、お茶の間のファンに対するJリーガーの認知度をあげていくことで、第2のフリューゲルスを出さないようにしていこう」と「Jリーガー全員のタレント活動強化」を打ち出すこととしました。
それまでJリーグ選手は、比較的テレビ等への出演に消極的な選手が多いと見られており、またクラブによっては安易なテレビ出演を規制しているところもあることから、今後は選手が率先してテレビ、ラジオなどの媒体に出演、自助努力を図ろうという趣旨でした。
・11月14日、Jリーグ後期最終節、横浜フリューゲルスはアウェー・札幌戦、4-1で勝利して合併発覚後の4試合を全勝でフィニッシュ、試合後「フリューゲルスを助けて!」などの横断幕を持って場内を1周しました。
・11月16日、フリューゲルスの前田選手会長以下、山口素弘選手、楢崎正剛選手、佐藤浩選手の4名が、川淵チェアマンに都内のホテルで、集めた署名などを持参して直談判、存続の可能性をギリギリまで探る話し合いを行ないました。(別の資料では「選手たちには木之本専務が対応した」という情報がありますから、川淵チェアマンは中座して、あとは木之本専務が対応したということかも知れません)
・11月16日、フリューゲルスサポーターが結成した「横浜Fを存続させる会(代表・辻野臣保氏)」が、集めた5万人の署名を持参してJリーグ事務局、全日空本社、横浜市役所を訪問、存続を訴えました。全日空本社は20日、同会に対して「合併は撤回できない」と最終回答、これを受けて「存続させる会」は活動方針を「フリューゲルスの名前を残すこと」に切り替え、あらためて「横浜F・マリノス」から「F」を削除することを要求、全日空本社は12月4日まで回答することとしました。(結局、これも「削除できない」と回答がありました)
・サッカーダイジェスト誌98年11月25日号が短期集中連載「私のクラブはどこへ・・・・クラブは誰のものか」という特集を組みました。
この中で、同誌は「取材に追われながら、疑問が沸いてくる。どの立場の人にも論理がある。企業はクラブに対して多大の資金援助をしている。地方自治体はクラブに対して税金からインフラを整備してあげている。観客は入場料収入という形でクラブの収入の重要な部分を占めており、とくにサポーターは熱心な固定客だ。そしてプレーをしているのは選手たちである。」と、Jリーグクラブを取り巻く、いろいろな立場の人たちを紹介したあと、「『企業がクラブ化』した日本のクラブは本当のクラブと言えるのか? クラブは誰のものとして存在しているのか? サポーターは『自分のクラブ』という夢をみせられていたのか?」と問題提起しました。
この最後の部分「サポーターは『自分のクラブ』という夢をみせられていたのか?」という問いかけ、これが今回の事件のもっとも核心の部分です。サッカークラブにおいて、もっとも大切にされなければならない「熱心な固定客であるサポーター」が、大切にされるどころか、一番最後まで置き去りにされたのですから「今までのオレたちは一体何だったんだ! 」ということになって当然です。
Jリーグスタート以来、『フリューゲルスは自分のクラブ』という夢を見続けてきたつもりだったのに、我々は、いつの間にか消えてしまう、ただの蜃気楼を見ていただけなのか・・。もはや、この先、どうやっても『フリューゲルスは自分のクラブ』という夢を見続けることはできないのか・・。
この号の特集の中でサポーターの声がまとめられているページがありました。あるマリノスサポーターはこう述べていました。
「今回のことは、生きている2つの魂をつぶして、1つの別のものを作ろうとしていることなのだとわかって欲しい。新しくできるものはどちらの魂も受け継がない(受け継いでなんかいない)。」
フリューゲルスサポーターだけでなく、マリノスサポーターであっても「自分のクラブ」に魂を込めていれば、そう考えて当然だと気持ちがこもったメッセージでした。
粛々と進む合併手続き、選手との契約・移籍に関するスケジュールが固まる
そんな中でも、合併手続きは粛々と進んでいきました。新チームとなる「横浜F・マリノス」を中心に、他のJリーグクラブも含めた、選手との契約・移籍に関するスケジュールが固まり、それに沿って作業は進みました。
11月15日、フリューゲルス、マリノスの合併調印が近くなる中、マリノスが契約を希望するフリューゲルス6人が該当選手に通知されマリノスによる優先交渉がスタートするとともに、それ以外の選手について他クラブからのオファーが解禁に。
11月30日、横浜F・マリノス、他クラブは契約する選手にに対して通知書交付。
12月2日、フリューゲルス・マリノス合併正式調印、事前の発表もなく結局抜き打ち的に実施され、最後までファン・サポーターの願いは届かず。
12月4日、全クラブとも契約更新しない選手の「移籍リスト」への登録申請開始
12月8日、Jリーグ移籍リスト公表
横浜フリューゲルス、伝説となって1999年1月1日消滅
大きな社会問題にもなり連日マスコミはこの問題を報じました。横浜フリューゲルスの選手たちとサポーターの一体感はこれまでになく強まり、Jリーグの残り試合と天皇杯の戦いに大きなパワーを与えました。
そして横浜フリューゲルスというチームは、合併・消滅が決まった残りの試合を、リーグ戦はもちろんのこと、最後の公式戦、第78回天皇杯サッカーも勝ち進み、1999年1月1日の決勝で清水を下し、一つも負けることなく戦い抜いて、無敗のまま消滅するという栄光と悲劇をまとったまま、その歴史に幕を閉じたのです。
これを「横浜フリューゲルスの伝説」と言わずして何と呼びましょう。
Jリーグ川淵チェアマンも一目置く古参のサッカージャーナリスト、フリューゲルス合併・消滅問題に魂の寄稿
1999年1月1日の天皇杯決勝を報じたサッカーダイジェスト誌(1999.1.20号)に、「平成意見箱」という連載コラムを担当している毎日新聞の荒井義行記者が「怒りの」といったらいいのか「魂の」といったらいいのか、フリューゲルス合併・消滅問題について、思いのたけをすべてぶちまけたような文章を寄せました。
少し長くなりますが、このあともJリーグ関係者、各クラブ関係者に真剣に考えて欲しいと訴えている内容ですので引用したいと思います。
企業常識のかけらもない人々が運営していたのか
「5週続けて横浜問題、マリノスとフリューゲルスの合併問題についてこの欄を使うことになる。(中略)今回の合併問題は日本サッカーの根幹にかかわる問題であり、日本サッカー界はいま重大な分岐点に立たされていると思えるからだ。」
「日産自動車、全日空が合併を申し入れ、Jリーグがそれを認めてしまったのも、日本ではサッカーが文化として根づいていない証拠だろう。地域に根づいたクラブ作りを理念に掲げながら、真剣にその理念を実現する方向を探ろうとしていなかったから、合併を認めるような愚挙を機関決定しまったのだ。」
「サポーターは有難いお客様だと言いながら、その存在を軽視、あるいは無視していたから、単なる株式会社や銀行のような合併を承認してしまったのだ。サポーターの根強い抗議活動で、初めてその存在に気がついたと言ってもいいだろう。」
「50万人もの抗議の署名をつきつけられて『拙かった』と気づいた関係者もいたろうが、日産自動車、全日空はサポーターへの回答日の前に、正式調印を発表するという中央突破を図り、ますますサポーターを無視した。」
「50万人の署名の中身は、サポーターばかりでなく一般のファン、サッカー少年たち、その指導者と広くスポーツを愛する人たちの思いも込められているのだろう。」
「社会の公器になろうとしているプロのサッカークラブが、お客さんを無視するような態度をとることが許されると思っているのだろうか。」
「『お前たちは、我々の所有物』だと言わんばかりに、最後まで選手たちに謝罪すらしなかったというのは厚顔無恥も甚だしいと言わざるを得ない。改めて怒りがこみ上げてくる。ワープロのキーボードを叩く指先も震えがとまらない。」
「やむを得ず吸収合併される株式会社の社長やオーナーは『力が及ばなかった。皆さんの努力には感謝する。残念ながら吸収されるが、これより方法がなかったから許して欲しい』と頭ぐらい下げてもいいだろう。選手に謝罪もしないとは、社会常識のかけらもない人々が運営していたJクラブということになる。」
「過ちだったと気がづいたら直ぐに改めればいいものを、Jリーグも『両チームが合併の白紙撤回を申し入れてこなければ、J2からでもというチームは認められない』と機関決定を改めようとはしなかった。Jリーグも改めて言うまでもなく社会的な存在だ。50万人の署名、5千万円近く集まった基金に対しても、機関として態度を表明しなければならないだろう。(中略)」
「5千万円というお金は並大抵の額ではないだろう。大不況だ、リストラだと失業が話題になっている時に、一口1万円という家族で食事ができるような金額を、多くの人が身銭を切って基金に投じた思いは『絶対に、理不尽に企業の論理だけで優先した合併など許せない』で一致しており、Jリーグの現状に対する非難の結集だろう。」
「熱い熱い思いが込められた5千万円であり、Jリーグは重く重く受け止めなければならない金額だろう。もしJリーグがこれを軽視したならば、日本のサッカーに未来はないと言えよう。」
クラブとサポーターの関わり方を真剣に考え、企業頼みのクラブ経営からの脱却を図れ
「Jリーグは、地域に根ざしたクラブを理念としていながら、依然として”企業にオンブにだダッコ”体質の発想から抜け出していない。真の市民クラブをどのように運営できるかについてはノーアイディアであり、何も考えていないのと同じことだ。サポーターとのつながりなど、まったく考えていないのだ。」
「あらたに結成された『横浜フリューゲルス再建協議会』は、①サポーターグループの組織化を図り、ボランティア登録の整備、②ファンクラブの募集、③3年契約のオーナーシップ(年間シート販売)などのアイディアを出して、なるべく企業に頼らない運営を模索しているのに、『Jリーグはチームの経営が難しい』と、いまだに企業に保証してもらう発想から抜け出せないのだ。これでは百年経っても市民クラブなどできるわけがない。」
「今回の合併に、反対の先頭に立って活動したのはサポーターだ。不眠不休に近い活動で署名を集めたから、短期間に34万人もの人々が協力してくれたのだろう。それにつられて横浜の少年サッカーも動き出したのだ。」
「Jリーグはサポーターの存在を軽く見ていたから、フリューゲルスのサポーターもマリノスのサポーターと一緒になって応援すればよいなどと、とんでもない考え方をしている企業の論理に乗ってしまったのだ。」
「日本のサポーターは熱烈な応援団だがフーリガンではない。サポーターグループにもいろいろな考え方があるだろうが、1つのクラブを応援することで一致している。これからクラブとサポーターの関わり方を真剣に考えていかなければ、日本のスポーツの将来は開けてこないだろう。(中略)」
「マリノスとフリューゲルスの合併という大ピンチをビッグチャンスにしなければならない。企業にオンブにダッコの体質から脱却して、理念である市民クラブ作りの方策を探るチャンスでもある。」
「50万人の署名と5千万円の基金が何を求めているかを真剣に考え、サッカー界全体でその対応を誤らないようにしないと、日本のサッカーは滅びの道を転げ落ちることになるだろう。」
以上が、サッカーダイジェスト誌(1999.1.20号)連載コラム「平成意見箱」担当、毎日新聞の荒井義行記者の寄稿です。
ここからは、横浜フリューゲルス合併・消滅問題の原因と、大きな社会問題にまで発展した要因、さらには学び取るべき教訓について検証しておきたいと思います。
検証1 横浜フリューゲルスを合併・消滅に追い込んだ原因は何だったのか
原因1 運営会社「全日空スポーツ」経営陣の、およそスポーツクラブ経営者とは言い難い自覚のなさ、甘さ
横浜フリューゲルスでプレーしたことがある選手が、チームを去った時に一様に口にする印象があったといいます。
それは「クラブの雰囲気というか、気風といったらいいのか、とにかく自由な雰囲気だった。本当に独特な雰囲気で、あんなクラブは珍しい。」というものです。
それは必ずしも「自由を謳歌できた幸福感」を指す印象ではなく、ある意味「ゆるい」「ぬるい」「いい加減」という意味も含んだ印象だったようです。
「プロサッカークラブ」において、この「ゆるい」「ぬるい」「いい加減」という雰囲気、気風は、長丁場のシーズンを乗り切れない致命的な脆さを意味しています。横浜フリューゲルスが、天皇杯こそ今回を含めて2度制したものの、リーグ制覇を、もう一歩まで近づいた経験はあるものの一度も成し得なかったのは、そうしたクラブの雰囲気、気風によるものでしょう。
それは、つまるところクラブ経営者の放任がもたらしたもので、勝負の世界という宿命を背負った組織を率いる覚悟も、自覚も、知見も持たなかった人たちが、クラブを合併・消滅に追い込んだのでしょう。
田崎氏は著書の中で「全日空スポーツ」の経営陣の自覚のなさ、甘さを感じた点を具体的に幾つも例示していますが、ここでは省きます。
原因2 親会社「全日空」と「佐藤工業」の運営会社への関与の弱さ、Jリーグクラブを持つことに対する責任感の低さ
横浜フリューゲルスの運営会社である「全日空スポーツ」に対しては、親会社である全日本空輸が6割、佐藤工業が4割の比率で出資しています。それとともに「全日空スポーツ」に対して人材を送り込み、経営に当たらせていましたが「全日空スポーツ」が出す赤字に対する危機意識は、佐藤工業が経営危機のため撤退を決める1998年1月まで無かったに等しい状態です。
全日本空輸側で子会社である「全日空スポーツ」を所管する関連事業部では、「全日空スポーツ」が出す赤字に対して1996年頃から強く改善を申し入れていますが、それは「プロサッカークラブ」の経営とはどうあるべきかを知悉した上でなされた申し入れではなく、いわば口先だけのことでした。
佐藤工業側は「『全日空スポーツ』への関与はオーナーマター」であるといった他人事のような意識でした。
つまり両会社とも「Jリーグクラブ」を持つことに対する責任感が低く、したがって「全日空スポーツ」に対して「プロサッカークラブ」の経営がわかる専門性を持った人材を出すこともなく、親会社の所管部門も「プロサッカークラブ」の経営について専門性を高めようという意識が最後までなかったことが、安易な合併・消滅という道を選んだ原因のようです。
全日空という航空会社の、サッカーへの関与が、確たる企業理念に裏付けられた芯の通ったものでなかったことは、歴史を辿ると、以前にもあったことでした。
1986年に起きた「全日空、試合ボイコット事件」です。今回の横浜フリューゲルス合併消滅事件と、根っこの部分では同じでした。
1986年の頃の全日空は、横浜の地域クラブを母体にして日本リーグ一部まで強くなったにも関わらず、地域クラブが抱えていた中高生の下部組織育成などには目もくれず、トップチームの選手たちも、全日空側が揃えた選手たちと入れ替えるために容赦なく切り捨てています。
横浜の地域クラブ時代からの関係者にしてみれば、クラブを乗っ取られ追い出された感覚しか残らない対処の仕方だったのです。
Jリーグがスタートしてからといえば、あれだけ地域密着のクラブに、と叫ばれながら、横浜フリューゲルスの地域密着の姿とはどういうものかを真剣に考えることもなく、いわば他人事のようにしか考えていなかったということです。
航空会社における企業理念とJリーグが掲げる地域密着の理念をどう昇華させていけばいいのか、果たして、もともと航空会社とJリーグは親和性のある関係なのかどうかという議論もありますが、サッカーへの関与が、確たる企業理念に裏付けられた芯の通ったものでなかったことだけは確かです。
原因3 Jリーグ川淵チェアマンが下した、全日空、日産自動車という大企業の決定を覆せない、追認するしかないという決断
一連の動きの中でJリーグがとった判断がどうだったのかについても検証しておく必要があります。
Jリーグ側の対応者は川淵チェアマンです。川淵氏は、のちのちまで一貫して「フリューゲルスはなくなったわけではなく、合併して残った。あの件に関しては間違った対応ではなかった。」と語っています。
そう語るのは、心底から出ている気持ちでなく、いわば「全日空、日産自動車という大企業の決定は覆せない、追認しなければ、ことは収まらないから、そう思うことにした」というのが本心ではないでしょうか。
というのも、田崎氏の著書の中で、10月6日、両クラブの運営会社社長と会った川淵チェアマンは「観念した」といいます。
「川淵が観念したのは、マリノス社長、高坂弘巳の存在だった。(中略)高坂は1992年に日産労連の会長に就任、その後、日産フットボールの社長に転じていた。労組の会長であった高坂は日産自動車本社と太い繋がりがある。フリューゲルスとの合併は日産自動車にとっても落し所なのだろうと川淵は思った。フリューゲルスは潰れるのではない。合併するのだと自分を納得させた。」
そこには、これまでならJリーグ規約に照らしてとか、Jリーグ理念に則って、といって論陣を張るいつもの川淵チェアマンの姿はなかったのです。
川淵チェアマンとしては2人に対して「サポーターは反対するし、選手も動揺する。きちんとしたタイムスケジュールを作り、どういう話し方をするのか、フォローはどうするのか、あらゆる問題を整理して最後の最後まで、さまざまな角度から検討して詰めて欲しい。」と要請するのが精一杯だったのです。
しかし、歴史に照らすと、かつてJリーグに「時の運」をもたらした日産自動車が、今回は「時の不運」となって立ちはだかったと言えるのではないでしょうか。
すなわち、かつて1989年6月、日本サッカー協会の理事会で「プロリーグ検討委員会」の設置について審議した際、当時、日本サッカーリーグ(JSL)の最高意思決定機関である「評議委員会」の議長が、リーグ初制覇を果たした日産自動車出身の評議委員に変わっていたという「時の運」が「プロリーグ推進」を後押ししたという歴史があります。
しかし、今回は「横浜フリューゲルス」の合併相手が「横浜マリノス」であり、その代表者が日産自動車本社と深い繋がりを持つ人物であったことで、もはや合併が落し所と判断せざるを得ない、いわば「時の不運」としか言いようのない、皮肉な歴史の巡り合わせになったということです。
川淵氏は、これから先も「フリューゲルスはなくなったわけではなく、合併して残った。あの件に関しては間違った対応ではなかった。」と言い続けるのでしょうけれど、選手たち、サポーターたちにとっては、やはり「悲劇」であり「不運」であり続ける出来事だと言わざるを得ません。
横浜フリューゲルスの問題が表面化した時、チェアマンの脳裏に「チームがなくなって18から17に減れば、翌年度の参入チームを決める「Jリーグ参入決定戦」の結果、降格するチームを一つ減らせる。フリューゲルスの消滅は残念だが、クラブ経営が健全なチームを1つJ2に落とさずに済むと思えばやむを得ない」という思いがよぎっています。
当時、川淵チェアマンも自ら「JリーグスタートからのJリーグバブルの成功に酔い過ぎて、クラブ経営が赤字を垂れ流し続けても、出資企業からの補填に頼るだけで、自らの手でいかに赤字から脱却するかという経営努力がなかった。」と指摘していましたが、いざ破綻してしまった際の処理について事前の想定がなかったのも事実です。
けれども、地元のライバルチームにくっ付けてしまう形での合併・消滅という選択はあまりにも悲劇的でした。
Jリーグが取り組む再発防止対策
1.「経営委員会(仮称)」の新設
Jリーグ側では、ここ1~2年前から、各クラブが親会社から多額の補填を受けながら経営している状況はクラブから提出される決算書で把握していましたが、それをJリーグとしてどう改善していけばいいのか、なかなか踏み込めないでしました。
それは各クラブが曲がりなりにも独立した法人として運営されている組織であり、Jリーグ側に指導監督権限があるわけではないことを考えればやむを得ないことでしたが、前年暮れ、清水エスパルスの経営危機が表面化した頃から、Jリーグ側も各クラブの収支内容を把握するところまで踏み込まないと、この先も経営危機に陥るクラブが続出すると判断し始めました。
そして、この年1998年1月には、Jリーグ事務局が所管する機関が各クラブの収支状況を細かく把握する新たな対策を各クラブに提案しました。しかし、各クラブから見た場合、Jリーグから監査を受けるイメージとなり「既に法人として監査を受けているのに」という反発が出た経緯があります。
Jリーグ川淵チェアマンは、ヨーロッパのサッカー先進国のリーグには、すでにリーグが各クラブの経営状態をチェックする機関を設置しているところがあることから、いずれJリーグでもそういうチェック機関が必要になる時期が来ると考えていことから、各クラブからの反発で簡単に引っ込めようとはしませんでした。
そこでJリーグ側は、監査のイメージではなく「指導・相談」の立場から各クラブ経営に関与する独自の機関の設立準備を進めてきました。
新機関の名称は「経営委員会(仮称)」。1999年シーズンの開幕時期をメドに発足させることとして、会計士、弁護士などからなる外部の経営の専門家4~5人で構成するメンバーが、各クラブの経営データを分析・検討して、それぞれのクラブに即した指導・相談を行なっていく場となります。
各クラブの経営規模は、大きいところで30億円、小さいところで10億円程度とバラツキがあるため、各クラブによって経費のかけるべき分野が自ずと異なります。「経営委員会(仮称)」は主として、そのアンバランス是正により各クラブが健全な経営を図れるよう「指導・相談」を行なっていくイメージのようです。
この組織に各クラブを縛る法的拘束力はありませんが、少なくともJリーグ側が、各クラブの中味が見えていなかった問題は解消されますし、各クラブに対する第三者の専門家からの指導・相談が一定の効果を発揮することは間違いなさそうです。
2.クラブ保有の選手枠上限の設定
Jリーグが、各クラブの経営に関する「指導・相談」の機関を設置する案と並行して進めていた改革が、各クラブが保有するプロ選手枠に縛りを設けることでした。これは、今回のフリューゲルス事件が発覚する前に、すでに1999年シーズンから移行することが発表されていたものです。
Jリーグは1993年のスタート前、1990年の段階で「Jリーグへの参入条件」を示しましたが、その時は「プロ契約選手を18人以上保有すること」が条件の一つとされていました。つまり以前は、下限数が決められていた規約でしたが、契約選手数の上限がなかったため各クラブは、それぞれの事情やチーム戦略に基づいてプロ契約選手を保有していました。
その結果、年俸総額だけで10億円以上も支出しているチームが複数出るなど、クラブ経営の最大の支出項目である人件費・選手年俸総額の高騰が、クラブ経営を相当圧迫していることが明らかになってきたのです。
そこでJリーグは、年俸480万円以上で、一定の試合出場時間数をクリアしている選手との契約を「A契約」(最上位の契約)とし、その上限数を25名以下と規定することで、選手年俸総額の抑制、川淵チェアマンの言葉によれば「身の丈にあった経営」に方向転換させることにしたのです。
契約種別には、年俸480万円未満で契約する「B契約」、さらには新卒で新卒で3年間を限度として契約する「C契約」があり、B,Cの関しては25人枠に縛られない条件とすることにしました。
この新たな契約規定により、各クラブは年俸の高い選手の放出や、選手の選別などの対応を迫られることになります。
しかし、今回、横浜フリューゲルスの合併・消滅問題が発生したことから、Jリーグはフリューゲルス所属の選手を獲得した場合に限り「A契約」枠の1名追加を認める特例措置を講じることにしましたから、選手年俸総額の抑制、身の丈経営への移行に少しブレーキがかかったとも言えます。
それでも、この保有選手枠の上限制度が定着すれば、これまでのような青天井の年俸総額高騰は避けられ、クラブ経営の健全化の方向に向かうと期待されますが、世界全体から見たJリーグの魅力が低下することも避けられないかも知れません。
検証2 横浜フリューゲルス合併・消滅問題が、これほど社会の関心を集めたのはなぜか
要因1 選手、サポーターたちが何も知らされずに突然宣告を受けた形の出来事に、社会も一緒になって、ことの真相、この問題の行く末を見たい、知りたいという劇場型のニュースとして反応したこと
当初は企業の論理としてやむを得ない選択と思われていた合併・消滅問題ですが、何も知らされずに突然宣告を受けた形の選手、サポーターたちが、それぞれ即座に行動を起こし「自分たちは納得できない」と強く意思表示したことにより、次第に社会の共感が集まり、また選手、サポーターたちを置き去りにした企業側の姿勢が強く批判を浴びるなど、テレビ・新聞などのメディアを通して劇場型のニュースになったからでした。
要因2 選手、サポーターたちは、各方面との話し合いと同時並行でリーグ戦、天皇杯を戦うことになり、彼らはどういう結末を迎えるのかという関心も増幅していったこと
事件はJリーグ後期の終盤に発覚したため、選手、サポーターたちは行動を起こしつつも、目の前の試合も同時並行デ戦うことになり、彼らはどういう結末を迎えるのかという関心も増幅していきました。
そして、横浜フリューゲルスが、事件発覚後の試合から1試合も負けることなくリーグ戦を戦いきり、さらには天皇杯も勝ち進むにつれ社会の関心も相乗効果的に高まりました。そして1999年1月1日の天皇杯決勝で勝利、栄冠を手にするに至って「栄光の勝利とともに消滅」というドラマチックなエンディングとなったことから、このチームは「伝説」となって語り継がれるチームになりました。
要因3 社会がまさに、企業におけるリストラや倒産・合併等の厳しい環境におかれている中、我が事のように感じる出来事であったこと
バブル崩壊後の日本経済が低迷のスパイラルに入りつつある中での合併・消滅は、現代日本の企業社会の縮図としても語られる出来事でした。多くの人々が、企業におけるリストラや倒産・合併等の厳しい環境におかれている中、我が事のように感じる出来事として映ったのです。それが社会の関心を一層高める要因ともなりました。
要因4 横浜フリューゲルス問題が顕在化すると同時期に、ヴ川崎や平塚など他のクラブの問題も報じられ、Jリーグは理念倒れになってしまうのかという危惧が増幅したこと
Jリーグのいくつかのクラブ経営が厳しいとささやかれる中、このあと、いつまた、どのクラブの問題が表面化するのだろうかという懸念されていた矢先、ヴ川崎や平塚などの親会社の撤退が報じられ、ドミノ倒し式になりはしないか、このままJリーグは理念倒れになってしまうのかという危惧が増幅したことも、横浜フリューゲルス問題をさらに深刻にしました。
幸い、ヴ川崎や平塚以外のクラブの問題が現実化することはなく1999年には沈静化しましたが、クラブ経営者、その親会社に大きな警鐘となったことは事実でした。
横浜フリューゲルス合併・消滅問題、1998年秋のリアルタイムでは、主として事象・現象面の情報が流布されていて、当事者たちの心の奥底まで知ることができるまで20年以上の長い沈黙の時間を要したという、知られざる真実
この問題の発端は新聞報道からでした。ここまで経緯を時系列的にご紹介したように、すでに全日空、日産自動車という出資企業のところで意思決定されてしまっていた案件が、まるで「どうやら、その方向で進む模様」つまり、まだすべてが決まったわけではない、と受け止めてしまう伝わり方だったため、選手、サポーターをはじめ多くの人たちが、長い時間、撤回の可能性を信じて活動しました。
その結果、それが徒労に終わった時の無力感、虚無感は相当大きいものがあったと思います。世の中の理不尽さを恨んだことでしょう。
それらの動きを報道を通じて受け取っていた側は、選手たちの悲劇、サポーターたちの怒りという面だけから、この問題を見てきたことになります。
それゆえ、その中で奮闘する選手、サポーターたちを美化することが中心になってしまい、問題の真の原因は何であり、そこから学び取るべきことは何なのか、なかなか見えてこなかったことも確かです。
選手の中には、例えば前田浩二選手のように「翌年から母校・鹿児島実業の教員となることが内定していた」のを辞退して、選手会長としてクラブやJリーグとの交渉にあたった選手がいます。彼らのことは、一般的には美談として語られていますが、前田選手自身は、その後長い間、フリューゲルスについて語ることを避けていたといいます。
田崎健太氏の著書の中で前田選手はこう話しています。
「軽はずみに話してしまうと、美化されてしまう。軽い感じで受け止められるのが嫌でした。ぼくたち選手は行き場所があって、それなりに生活のためにサッカーを続けた。ただ、あれだけ応援してくれたファン、サポーターの心情を汲み取れていないじゃないですか。だから、自分の主観だけでフリューゲルスについて喋りたくなかったんです。」
「自分の中でフリューゲルスがなくなったことを消化する時間が必要だっというのもあるかも知れませんと呟くように言った。」
この話を聞いた田崎氏自身も「何が起こったのか当事者たちが噛みしめるためにそれなりの時間を置いて良かったと思った」と書いています。
また、楢崎正剛選手は、1999年から名古屋に移籍しています。その後、一度も移籍せずに名古屋で現役引退を発表しています。特に最後のシーズンは一度も出場機会がなかったにも関わらず名古屋に留まり続けました。
このことについて楢崎選手は、田崎健太氏の著書の中で「別に最初からそう決めていたわけではないけれど、長い間名古屋に在籍して、次第に、毎年の選手名簿の「前所属チーム」の欄が「横浜フリューゲルス」となっているのを意識するようになり、全体の名簿から横浜フリューゲルスになっている選手が少なくなっていくのを知って、自分が最後になるまで残そうと考えるようになった。」と話したそうです。
田崎氏からそれを聞いたサンパイオ選手は「知らなかった。鳥肌がたったよ。素晴らしい。いまの選手はいい契約があればどこへでも移籍してしまう。楢崎のような選手は絶滅した。」と述べたそうです。
事ほど左様に、何か大きな事件などが起きた時の原因や教訓を学び取ろうとする時、当事者たちから本心や真相といったものが語られるまで、多くの時間が必要なことが、いくらでもあるということがわかります。
そうした長い時間軸の中で、やっと見えてくるものがあるということを、心しておかなければならないと痛感します。
横浜フリューゲルスという樹木が倒れたあとから芽吹いた幾つかの種子
田崎健太氏の著書『横浜フリューゲルスはなぜ消滅しなければならなかったのか』には、横浜フリューゲルスを倒れてしまった樹木になぞらえて、倒れた樹木から芽吹いた種子についても紹介されています。
一つは「横浜マリノス」に埋め込まれた「F」という種子。「横浜F・マリノス」というチーム名です。これは、もともと全日空から「フリューゲルス」の「F」を残すため「横浜マリノス」に「F」を加えたチーム名にして欲しいと要請して、マリノスの了承を得てできたチーム名でした。このことで全日空側も資金負担を継続する理由が立つというわけです。
こうして「F」が種子が埋め込まれたことによって「フリューゲルス」という固有名詞は、その後、一人歩きできない名称になってしまいました。ちょうど両チームの社長がJリーグ・川淵チェアマンに合併について報告した直後の時期に、川淵チェアマンのところには「フリューゲルス」という名前を使わせてもらうことを条件に「横浜フリューゲルス」を引き受けてもいいという話が持ち込まれていたのですが、横浜マリノス側が「フリューゲルスを引き受けるという意味で決めた「F」の埋め込みを外すわけにはいかない」と承知せず、お流れになったいきさつがあります。
11月7日のJリーグ後期ホーム最終戦のセレモニーで「フリューゲルス」のクラブ社長は「フリューゲルスは新チームの中に生きていく」と述べましたが、後年、「横浜F・マリノス」の「F」が「フリューゲルスというチームがあった証しだ」ということを知らないファン・サポーターが増えてしまい、結局「横浜フリューゲルス」という名称も次第に消滅しているのは残念なことです。
二つ目は「横浜FC」という新しいクラブの創設です。さる11月7日、横浜フリューゲルスサポーターによる「横浜Fを存続させる会(代表・辻野臣保氏)」が発足して、存続活動を続けていましたが11月下旬、横浜マリノスと横浜フリューゲルスの合併調印が行われ存続の可能性が失われました、
そして1999年元旦の天皇杯サッカー決勝での栄冠をもって、横浜フリューゲルスはすべての活動を終了したわけですが、この「横浜Fを存続させる会」は「横浜フリューゲルス再建協議会」と名を変えて活動を継続していくこととなりました。
そして、さっそく精力的に活動を展開、1月初旬までに50万人の署名と、5千万円の基金を集めています。それらをもとにした活動は、翌年「1999年」以降の中で紹介していくことになりますので、ここでは「横浜フリューゲルス再建協議会」という種子が芽吹いたことだけを紹介しておきます。
三つ目は「横浜YSCC」というクラブのことです。田崎健太氏は著書『横浜フリューゲルスはなぜ消滅しなければならなかったのか』の中で「横浜YSCCというのは、1960年代に横浜フリューゲルスの原型としてスタートした『中区スポーツ少年団』、それを引き継いだ『FCゴール』に途中から挿し木をしたようなクラブ」と表現しています。
つまり「FCゴール」が次第に社会人チームを中心としたクラブに成長して、1970年代に全日空が関与するクラブに変わっていった当時、中高生を指導していた人たちが立ち上げたクラブというわけです。枝分かれしたと言ってもいいかも知れません。
1986年に「横浜スポーツクラブ」という名称で、女子を含む中高生26名で立ち上げられたクラブは翌1987年「横浜YSCC=横浜サッカー&カルチャークラブ」に改称されています。
1986年というのは、全日空の試合ボイコット事件があった年ですが、それが引き金になったというよりは、その前年1985年に、中高生を指導していた人たちが、グラウンド確保などの環境改善にまったく関心を示さない状況に見切りをつけて立ち上げたクラブのようです。
「カルチャー」という文字を入れているのは、指導する子供たちがサッカー選手である前に一人の教養人であるべきである、という思いがあったからだそうです。
そして「サッカークラブが企業におんぶにだっこではいけない。地域に根差して地域の活性化を図るクラブを理念としながら、子供たちの健全育成を図る。」という信念を持った人たちのクラブでした。
1988年に神奈川県社会人3部リーグから始まり、1990年には社会人1部リーグと昇格していきます。後年、J3に昇格そしてJ2に参戦していることはよくご存じのとおりです。
この1998年段階では、横浜フリューゲルスに追いつき追い越すことがクラブ幹部のモチベーションだったようですが、突然、目の前から、その対象が消滅してしまい、呆気にとられつつ、複雑な思いでニュースを見ていたことでしょう。
プロスポーツクラブと支援企業の関係において、永遠に保たれなければならないものとは何か
最後に、田崎健太氏が著書の「最終章」の中で、「なぜ20年以上前に消滅したクラブを題材に取りとげるのだ」と何度か訊ねられ「スポーツクラブと支援企業の関係という永遠の問題を抱えているからだ」と応じていた。と書いていた点について、触れたいと思います。
田崎氏がいう「スポーツクラブ」は、おそらく街の小さなスポーツクラブであっても、支援企業の存在によって「プロスポーツクラブ」にまで膨らんでいくことを考えての「スポーツクラブ」だと思います。
ここでは「プロスポーツクラブと支援企業との関係」という点に絞って触れることにします。
私たちは「プロスポーツクラブと支援企業の関係」が、一つ間違うと社会問題にまで発展する危うい関係だということを、横浜フリューゲルスの事件で思い知らされました。
支援企業が「プロスポーツクラブ」に対して出資して運営に関与していくにあたっては、他の事業に出資することと全く違う認識が必要になるということを示してくれたのです。
それは「プロスポーツクラブ」が、出資企業と運営会社である「プロスポーツクラブ」だけのものではなく、ファンやサポーター、そしてスタジアムなどを所有する自治体、さらにはホームタウンを形成する地元経済界など、すべてのステークホルダーを含めた「地域の公共財」という存在であることを認識しなければならないのです。
したがって、そこに出資・関与していくということは「プロスポーツクラブという地域の公共財」と、この先永遠に関係を保っていく「一蓮托生の覚悟」が求められるのです。
もう一つは「プロスポーツクラブ」が、勝負の世界に生きていくという宿命を背負っているということを認識しなければならないという点です。
勝負の世界に生きていく宿命の中で、長きにわたり「プロスポーツクラブ」を維持・継続させていくには、勝ち負けに踊らされない、クラブとしての普遍的なアイデンティティを持たなければ耐えられないのです。
どのクラブも、永遠に勝ち続けることなどあり得ないことで、必ず低迷にあえぐ時期が来ます。その時にクラブを支える精神的バックボーン、普遍的なアイデンティティがしっかりしているかどうかが、クラブの維持・継続の分かれ道になるからです。
ヨーロッパや南米のプロスポーツクラブ、とりわけプロサッカークラブが100年単位の長さで「地域の公共財」として存在し続け、勝負の世界に生き続けているのは、すでに、そこに「プロスポーツクラブと支援企業の関係」が、永遠に関係を保っていく「一蓮托生の覚悟」ができているからであり、また、クラブを支える精神的バックボーン、普遍的なアイデンティティがしっかりあるからに他ならないのです。
それら、ヨーロッパや南米のプロスポーツクラブでも、長い歴史の中で多かれ少なかれ、なにかしらの出資企業の異動があったことでしょう。しかしプロサッカークラブが連綿と受け継がれているのは「地域の公共財」として、しっかりと根付いているからであり、そこに、クラブを支える精神的バックボーン、普遍的なアイデンティティがしっかりあるからです。
田崎氏も「スポーツクラブと支援企業の関係という永遠の問題」について考えてきた結果、辿り着いたと自分に言い聞かせるように、次のように締めくくっています。
「サッカーに限らず、スポーツクラブは経済学者である宇沢弘文が提唱した社会的共通資本に含まれるとぼくは思う。(中略)(スポーツクラブは)生命存続に必須ではないかもしれないが、人間らしく、そして豊かに生きるために必要な文化財だ。はじまりは企業内の組織であったとしても、時を経るうちに地域、関与した人間の社会的共通資本となる。決して、運営資金を出した企業が生殺与奪の権を握る所有物ではない。」
「横浜フリューゲルスは、オリジナル10、Jリーグにおいて消滅した唯一のクラブである。」
「川淵三郎はフリューゲルスの消滅が大騒ぎになったことで、撤退を検討していた他のクラブの抑止力になったと評した。確かにそのとおりかも知れない。ただ、割り切れないものは残る。」
「Jリーグが始まって31年目となる。今後、フリューゲルスのようなクラブが出ないことを祈って、筆を置く。」
これからも長く続く「クラブ経営」、撤退・消滅の可能性は決してゼロではない。もしそうなった時、出資会社、運営会社が「横浜フリューゲルス合併・消滅事件」から「この失敗だけは二度と繰り返してはならない」と絶対肝に銘じるべき「唯一の失敗」とは
田崎氏が著書の中で「プロサッカークラブ経営」に関与するということは、「時を経るうちに地域、関与した人間の社会的共通資本となる。決して、運営資金を出した企業が生殺与奪の権を握る所有物ではない。」と強調したように、これからのJリーグクラブは、出資会社も運営会社も相当気を引き締めて「クラブ経営」に携わっていくに違いありません。
これからもクラブ経営は10年、20年、50年と長く続いていくことでしょう。しかし、その長い年月の中で何か起こるかわかりません。それが世界経済、日本経済といった要因になるか、個別の出資会社、運営会社の事情によるものかはわかりませんが「クラブ消滅」の可能性は決してゼロになることなどあり得ません。
そのことは「Jリーグクラブ」に関わるすべての関係者が心しておかなければならないことです。
しかし、万が一、そうなってしまった場合、出資会社、運営会社が、今回の「横浜フリューゲルス合併・消滅事件」から「この失敗だけは二度と繰り返してはならない」と絶対肝に銘じるべき「唯一の失敗」があります。
それは「クラブは自分の夢」と考えて支えてくれた「クラブの固定客であるサポーター」に対して、何一つ「やってあげられることがなかった」という失敗を犯してはならないということです。
今回の「横浜フリューゲルス合併・消滅事件」、出資会社も運営会社も、選手も、自治体も地域経済界も皆、傷つきました。けれども、傷ついただけで、決して死んでしまったわけではありませんでした。
ところが唯一「クラブの固定客であるサポーター」だけは、何一つやってもらえず、夢を奪われ、魂を失ってしまったのです。死んだも同然の扱いを受けたのです。合併・消滅が発覚してから、サポーターたちは、最初は「合併・消滅撤回を」と叫び、次に「何らかの方法で存続できるようにして欲しい」と望み、最後は「せめて『フリューゲルス』という名前だけでも使えるようにして欲しい」と要望しました。
ところが、出資会社も運営会社も、そのすべてに対して「ゼロ回答」、すべて拒否だったのです。
なぜ、そんなことをしてしまったのか、なぜなら全日空、日産自動車という出資会社だけで、全てを決定済みの状態にしてしまい、どこをどうあがいても動かしようのない状態にして「合併・消滅」に突き進んだのです。今回の悲劇で最も罪が重い「この失敗だけは二度と繰り返してはならない」と肝に銘じるべき「唯一の失敗」とは、このことです。
横浜フリューゲルスも横浜マリノスも、出資会社そして運営会社が、いかに「クラブの固定客であるサポーター」の存在を軽んじていたか、いや、サッカーダイジェスト誌で荒井義行氏が指摘していたように、まったく眼中になかったための失敗だったのです。横浜フリューゲルスも横浜マリノスも、出資会社そして運営会社は、サポーターが「自分の夢であるクラブ」を奪われた時、よもや「夢を奪われる」とか「魂を失なってしまう」と絶望してしまうとは考えもしなかったのです。
1998年秋、Jリーグクラブの中には、サポーターに対する認識はその程度のクラブがあったのです。クラブの大切な固定客であるはずなのに、その程度だったのです。
出資会社も運営会社も「撤退・消滅」を決めることは、これから先、いつでも起こり得ることですが、その時「クラブの固定客であるサポーター」に対してできることを絶対「ゼロ」にしてしまってはならないのです。
どうしても出資会社が撤退し、クラブが消滅するというなら「クラブの固定客であるサポーター」から「撤退・消滅は受け入れるけれど、これだけは残して行って欲しい」という要望を受けた際、「ここまでならできます。これとこれはやりましょう。」という答えを、できるだけ多く残しておくこと、これが、この先のJリーグクラブの出資会社、運営会社が絶対守らなければならない唯一の「失敗から学ぶべき教訓」です。
横浜フリューゲルス所属選手の進路
横浜フリューゲルスには、レギュラーシーズン終了時点で30人の選手と、監督・コーチ3人が在籍していました。
チームの合併・消滅という激動の中、レギュラーシーズンから1999年1月1日の天皇杯決勝まで勝利にこだわり、遂には天皇杯優勝という栄冠とともに消滅するという伝説となったチームの選手・スタッフを永遠に語り継ぐため、その後の進路を記録しておきます。
【横浜F・マリノスから契約希望されて移った選手 5人】
・MF佐藤一樹選手(24)、MF三浦淳宏選手(24)、FW吉田孝行選手(21)、MF永井秀樹選手(27)、MF波戸康弘選手(22)
【J1他チームへの移籍選手】 順不同
【京都へ移籍した選手 7人】・DF大嶽直人選手(30)・MF遠藤保仁選手(18)、・DF佐藤尽選手(24)、・DF手島和希選手(19)、・FW大島秀夫選手(18)、GK仁田尾博幸選手(25)、・DF辻本茂輝選手(19)
【名古屋へ移籍した選手 2人】・MF山口素弘選手(29)、・GK楢崎正剛選手(22)
【市原へ移籍した選手 1人】・MF井上雄幾選手(21)
【柏へ移籍した選手 1人】・DF薩川了洋選手(26)
【清水へ移籍した選手 1人】・FW久保山由清選手(22)
【磐田へ移籍した選手 1人】・DF前田浩二選手(29)
【C大阪へ移籍した選手 1人】・MF原田武男選手(27)
【広島へ移籍した選手 1人】・GK佐藤浩選手(26)
【J2チームへの移籍選手】 順不同
【札幌へ移籍した選手 2人】・DF埜下荘司選手(28)、・FW桜井孝司選手(21)
【大宮へ移籍した選手 3人】・GK岸川義隆選手(20)、・DF奥野誠一郎選手(24)、・DF氏家英行選手(19)
【新潟へ移籍した選手 1人】・MF瀬戸春樹選手(20)
【JFLへの移籍選手】
【本田技研へ移籍した選手 1人】MF大久保貴広選手(24)
【海外移籍した選手】 順不同
・MFサンパイオ選手(30)ブラジル・パルメイラス、・MFアンデルソン選手(21)ブラジル
・FWレディアコフ選手(30)レンタル元スペイン・スポルディングヒホン
選手 以上30人
【監督・スタッフの移籍】 順不同
【市原監督に就任】ゲルト・エンゲルス監督
【名古屋GKコーチに就任】マザロッピGKコーチ
【京都コーチに就任】佐野達サテライトコーチ
スタッフ 以上3人
横浜フリューゲルスと相前後するように噴出したヴ川崎、平塚のクラブ経営悪化問題
Jリーグにおけるクラブの経営問題の表面化は横浜フリューゲルスにとどまりませんでした。
1998年11月12日、読売新聞社がヴ川崎の出資企業から撤退することが明らかになりました。この日、読売新聞社・渡邊社長名の談話が発表されたのです。
それによると、これまで読売新聞社と日本テレビが各49%、よみうりランドが2%出資で運営してきたヴェルディ川崎を、1999年2月1日から日本テレビの100%出資に変更、読売新聞社とよみうりランドが撤退するという内容でした。
以下、渡邊社長名の談話の骨子を記録に残しておきます。
・Jリーグ18チームすべてが莫大な赤字に苦しんでいる。これは川淵チェアマンの誤ったリーグ運営の結果だ。
・私は、この6年間、ことあるごとに川淵チェアマンの方針を批判し、リーグ改革を訴えてきた。これは各クラブ親会社に共通した願いだったが川淵チェアマンはそうた声に一切耳をかさず、各親会社が抱える苦しい状況を見て見ぬふりをして極めて独断的なリーグ運営を続けてきた。その結果、チーム数だけは増え観客動員数は激減してしまった。
・ヴェルディの場合、昨年度の赤字はついに26億円にも達した。こうした事情は他の17チームも同じ。このままでは第2のフリューゲルスが出ることは必至、Jリーグ自体も存続の危機に瀕する。
・川淵チェアマンに改革への真摯な取り組みが見られない以上、ヴェルディへの支援をこのまま続けるのはもはや限界。日本テレビに株の譲り渡しを持ちかけたところ快諾してくれた。
・最後に川淵チェアマンが今後、各クラブの声に謙虚に耳を傾け、Jリーグ規約の改正にも大胆に取り組むよう、Jリーグ全チームのために要望する。
この方針は11月16日の読売グループ役員会で正式決定され、翌17日のJリーグ理事会で承認されました。
読売新聞・渡邊社長と日本テレビ・氏家社長との話し合いの中では「ヴェルディを潰そうか」という話もあったそうで、日本テレビ側が今後始まる予定の民放BS事業に参入することになればソフトが必要になり、2002年W杯でサッカー人気が盛り返すことも考えて、一応残しておいたほうがいいという経営判断だったそうです。
言い換えれば、もし、そうした見通しがなければ「ヴェルディを潰そう」という話が現実のものとなっていたかも知れません。
この読売新聞社・渡邊社長の談話を受けて日本テレビ・氏家社長も記者団の質問に答え「ヴェルディが担ってきた使命もあったが、もうそれは終わった。赤字を縮小することが最優先で、それがうまくいかなければ手放すこともある。」と発言、総額12億円にのぼる選手年俸の圧縮が最優先ということで、高年俸選手の放出をはじめとした大胆なチーム改革に着手することになりました。
ヴ川崎の運営会社の社長には、森下源基社長に代わって日テレ出身で、現専務チーム統括部長の坂田信久氏が就任することとなりました。
そのためクラブは、カズ・三浦知良選手を筆頭に高年俸の主力選手の放出が避けられない状況となりました。ラモス瑠偉選手と柱谷哲二選手は引退を表明しましたので、カズ・三浦知良選手、兄の三浦泰年選手、エウレル選手らの去就に関心が集まることとなります。
セルジオ越後氏、スポーツ紙のコラムで「ヴ川崎の経営再建策に拍手を送りたい」
横浜フリューゲルスの合併・消滅問題がまだ続いている中での、ヴ川崎からの読売新聞社の撤退発表に「ヴェルディよ、お前もか !!」の声が聞こえそうですが、評論家・セルジオ越後氏が、11月13日日刊スポーツ紙のコラムに「華を捨て地道に再建の時、縮小ヴ川崎を見習え」という見出しの一文を寄せました。(コラム構成・日刊スポーツ後藤新弥編集委員)
セルジオ氏は、紙面で「ヴ川崎の経営再建策に拍手を送りたい。選手もリーグ関係者もファンも、この反撃のやり方を見習うべきだと思う」と述べ、こう続けています。
「何も、大きな華だけがサッカーじゃない。時には縮小し、根を肥やす時も必要だ。川崎はいち早く、潔くそれに切り替えた。それは日本のプロ化へリードしてきたチームが、今度は『華美を排して生き残る』時代の、新しい歴史を先頭に立って作り始めたんだ。」
「第二の横浜Fになる危機を、けんかしながら生き抜いてきたタフさと信念、サッカーへの情熱で切り返し、切り抜けた。それを主導する『人』に恵まれたことも幸運だった。(中略)」
「経営側の関係者は逃げ出すことばかり考えず、『いったん花を切ってでも寒さに耐える根を伸ばす』道を考えて、身を捨てて考えることが人としての誠意。それをしないで自分のことばかりを考える人が多すぎる。」
と持論を展開、縮小再建に踏み切ったヴ川崎の戦いをひとつの起点として、選手もサポーターも力を合わせて「反撃に移ろう」と具体的なポイントを示しました。
1.リーグ選手協会も各チーム選手会も、クラブ経営をチェックする力をつけ、クラブ側に収支のガラス張りを要求、反撃材料を持て
2.リーグ選手協会も各チーム選手会も、Jリーグ側の対応に問題がないのかどうか、選手会に代わって調査・監視、必要に応じて勧告などを行なう「オンブズマン制度」を置くように運動せよ
3.社会に自分たちの立場や活動をアピールする時はマスコミを上手に使え
セルジオ越後氏と日刊スポーツの共同アピールのような記事ですが、今回のヴ川崎の決定を、単に「読売新聞社の撤退」や「ナベツネ氏、ヴェルディを投げ出す」といった視点から報じるのではなく「身の丈にあった経営に移行する」決断として評価しているのは、スポーツマスコミとして、かなり意欲的な姿勢です。
これまで、ともすれば「ナベツネ氏vs川淵チェアマン、不倶戴天の敵」といった視点でとらえてきたヴェルディ絡みの問題が、実は両者共通の「落しどころ」に収まったのは、何とも不思議な感じです。
Jリーグ川淵チェアマンが「読売新聞社 渡辺恒雄社長のコメントについて」と題した短いコメントを発表しました。
「今までJリーグをご支援いただいた読売新聞社には、心から感謝いたします。」
「今、何よりもJリーグに求められているのは、各クラブの経済的自立です。このことが、苦しい経済情勢の中でご支援をいただいている企業に対する最大の恩返しになると考えています。現在、各クラブと共に、身の丈にあった経営を実現するべく努めております。」
「今後も、Jクラブと一丸となってJリーグの理念の具現化に向けて、全力を尽くしていく覚悟です。」
タイトルを「読売新聞社 渡辺恒雄社長のコメントについて」としていながら、ヴェルディや読売新聞社については、最初の1行だけにとどめ、あとは決意表明です。要は「考えていることは一緒です。大丈夫です。やっていきます。」と伝えたコメントでした。
これで「ナベツネ氏vs川淵チェアマン」論争は終止符が打たれるのでしょうか。
平塚も経営難から主力選手全員を放出
ヴ川崎に続いて、ベルマーレ平塚も経営難も表面化しました。平塚の親会社である大手ゼネコン・フジタ工業が次年度1999年からの補填額を大幅に削減することを決定、そのためクラブは1999年度予算を9億円に設定、支出の大半を占める人件費削減のため、主力選手の多くを放出するリストラ策を断行することを発表しました。
すでに移籍が固まっている選手あるいは移籍交渉進行中の主力選手は次のとおりです。
・FW呂比須ワグナー選手(名古屋へ)、・DF洪明甫選手(柏へ)、・MF田坂和昭選手(清水へ)、・GK小島伸幸選手(福岡へ)、・DF名塚善寛選手(札幌へ)
1995年の福岡に始まり、仙台、鳥栖と続き1997年の清水、そして今年の横浜フリューゲルス、ヴ川崎、平塚と、日本経済の低迷に伴う親会社の経営状態悪化、それに伴うクラブ運営会社の経営危機はピークに達し、社会問題にまで発展したのです。
横浜フリューゲルスから最初に撤退を決めた、公共土木が主力の佐藤工業は、2002年会社更生法の適用申請しました。事実上の倒産でした。
長引く日本経済の低迷は、のちにプロ野球チームの消滅問題も引き起こしました。
長引く日本経済の低迷は、のちにプロ野球チームの消滅問題も引き起こす
プロ野球パ・リーグの「近鉄バファローズ」が、後年、2004年11月30日に球団と近鉄グループの経営難からオリックス・ブルーウェーブの運営会社「オリックス野球クラブ」に営業譲渡し、運営会社も2005年3月31日に解散することになったのです。この時、職員の大半はオリックス野球クラブ、一部は新規に創設された楽天野球団に移り、選手は分配ドラフトにより、オリックス・バファローズ(ブルーウェーブから改称)と同時に新規参入した東北楽天ゴールデンイーグルスに配分されました。
この時も、長年バッファローズを「自分の夢」として応援しつづけた熱烈なファンにとっては、まさに「魂を抜かれて座して死を待つ」かのような辛さだったことでしょう。
日本経済の長期低迷、その後「失われた20年」とも「30年」とも言われる経済の低迷の中で、プロスポーツ界が何事もなく乗り切れると考えるのは無理なことだったのでしょうか? プロスポーツ界に、なにがしかの悲劇をもたらずにはいられない宿命だったのでしょうか。
Jリーグ年間王者は鹿島、磐田との宿命のライバル対決を制す
11月14日にJリーグ後期を終え、1998年Jリーグチャンピオンシップは、前期覇者の磐田と後期覇者の鹿島との対決となりました。2年連続の同一クラブ同士の戦いです。
とはいえ、シュチエーションが前年と全く逆になりました。前年1997年Jリーグは前期覇者が鹿島、後期覇者が磐田で、後期覇者の磐田が年間王者につきました。果たして後期覇者がそのままの勢いを持ち込むため有利なのかどうかも試される戦いとなりました。
ちなみに1993年以来、1996年を除き4回行われたチャンピオンシップでは、後期覇者が制した年が3回(93,94,97)、前期覇者が制した年が1回(95)と、後期有利というデータがあります。
この両チーム、前年の1997年Jリーグ前期から、ここまで、いわゆる三大タイトルといわれるタイトルを以下のとおり、すべて両チームだけで占めているという、まさに現在、最高峰の2チームの激突です。
・1997Jリーグ前期 鹿島
・1997ナビスコ杯 鹿島
・1997Jリーグ後期 磐田
・1997年間王者 磐田
・1998元旦天皇杯 鹿島
・1998Jリーグ前期 磐田
・1998ナビスコ杯 磐田
・1998Jリーグ後期 鹿島
第1戦は11月21日、磐田ホーム扱いの国立競技場、観客40,263人
11月21日、国立競技場で14時キックオフ、第1戦が行われました。試合は磐田が前半7分に得たPKを中山雅史選手が決めて先制、その後も押し気味に試合を進めますが追加点を奪えず1-0で前半を折り返しました。
すると後半27分、ジョルジーニョのパスに抜け出した柳沢選手がゴール前にクロスを送ると、長谷川祥之選手がドンピシャのヘッドで同点に追いつきます。
試合は延長に入り、鹿島ペースで進み延長後半5分、ビスマルクからのCKのこぼれ球を秋田選手がペナルティエリア外にいたジョルジーニョ選手に渡すと、そこからジョルジーニョ選手が強烈なシュート、磐田GK大神選手がキャッチできずに弾くと、そこにCKのため上がっていたDF室井市衛選手が詰めてVゴール、第1戦をモノにしました。
今年のリーグ戦、2敗している磐田は、中山雅史選手の後ろに奥大介選手を置く布陣で対抗、相手の攻撃の起点となっているジョルジーニョ選手からのパス出しも封じる役割を担った奥選手の起用が効果を発揮していましたが、後半、ジョルジーニョ選手がサイドに逃げる位置取りをしたことから、磐田ベンチは奥選手を下げ、高原選手を送る選手交代を行ないました。
これが鹿島ベンチを助ける采配になってしまい、名波選手が「采配ミス」と吐き捨てるほど試合の流れを変えてしまいました。
また、この試合、磐田の心臓部を担うドゥンガ選手が「きょうは試合会場に来る前に負けていた」と振り返っています。それが治まらない右足の痛みからくる自分自身のモチベーションが低くかったことを意味していたのか、チームの戦う執念の足りなさを指摘したのか不明ですが、ドゥンガ選手自身のパフォーマンスが良くなかったことは明白でした。
また本来であれば磐田スタジアムで戦う第1戦をホームで戦えなかったことも影響したのか、後期13連勝、リーグ戦2試合とも磐田に勝利しているという鹿島の、目に見えない自信に屈した形の試合でした。
第2戦は11月28日、鹿島ホーム、カシマスタジアム、観客16,991人
先勝してホームスタジアムに戻った鹿島には、前年失った年間王者の称号奪還に賭ける並々ならぬモチベーションがありました。
またカシマスタジアムが2002年W杯仕様に改修工事に入るため、現在のスタジアムでの最終ゲームを有終の美で飾りたいというモチベーションもありました。
迎えた第2戦、もうこれ以上の入場はムリと思われる観客が集まり、19時35分キックオフされました。
磐田は、第1戦を落としたとはいえ勝利に対する自信は揺らいでおらず、持ち前の攻撃力が発揮できれば十分逆転できる可能性がありました。
しかし磐田は、第1戦で後半スタミナ切れを起こしたこともあったためか、先に失点したくないという意識が強くなり、思い切りのいい攻撃が見られない前半となりました。
そこを鹿島に突かれました。前半39分、ビスマルク選手のFKを秋田豊選手が豪快ヘッドで合わせて先制すると、その2分後、今度はビスマルク選手自身が直接FKを叩き込み追加点、鹿島の圧倒的優位で前半を終えました。
後半に入ると磐田は攻勢に出ます。後半1分、守備的MF福西選手を下げてFW川口信男選手を投入、前線の攻撃が活性化しました。後半30分には鹿島ビスマルク選手が2枚目のイエローカードを受け退場、その3分後には磐田が足の痛みを抱えたドゥンガ選手を下げ、FW高原直泰選手を投入、一人少ない鹿島を攻め立てます。
そして後半39分、藤田俊哉選手が追撃のゴール、ロスタイム4分を含めた残り時間、攻勢一方となります。
鹿島は、名良橋選手が接触時に左太ももを痛めて一時は×サインを出すほどでしたが、激痛をこらえてプレーを続け、ジョルジーニョ選手も足をひきづりながらピンチになると痛みをこらえながら相手に激しいプレッシャーをかけ続けました。
チーム全体が満身創痍の中、勝負に対する執念が磐田を上回ったとしかいいようのない守りでした。年間王者を奪還した鹿島の選手は口々に言いました。
「年間王者の座を失った1年前の悔しさを、どうしても晴らしたかった。」
鹿島には完全にチーム全体に「勝者のメンタリティ」が宿りました。
Jの理念を体現した鹿島、3000人ものサポーター主催のお祭り祝勝会
ホームスタジアムで年間王者を奪還した鹿島、祝勝会の舞台はスタジアム外の駐車場に設置された特設ステージとそれを取り巻く3000人ものサポーター、優勝チーム恒例のビールかけに用意されたビールは4000本、ジーコ総監督の発声で一斉にビールファイトが始まると、お祭りは最高潮に。選手、サポーターが一体となって喜びに酔いしれる中、打ち上げ花火の祝砲で、ホームタウン4市町は、Jリーグクラブのある幸せに浸ったのでした。
【画像・鹿島祝勝会のビールファイト】
今シーズンの鹿島は、ジョアン・カルロス監督体制でスタートしたものの、フランスワールドカップによるJリーグ中断期間中に、外国人選手たちと監督の確執が表面化、監督が辞任するという危機がありました。
ジーコ総監督が急遽、ゼ・マリオ監督を招聘、自分も監督を支えながらチームの立て直しに成功、後期には5節から13連勝、チャンピオンシップの連勝を含めて15連勝でシーズンを締めくくったのでした。
横浜フリューゲルスの合併・消滅問題やヴ川崎、平塚の経営危機などで「Jリーグの危機」が叫ばれる中、盤石のクラブ運営、自治体との厚い信頼関係、サポーターと一体となった試合環境づくりなど、どこをとってもJリーグのお手本となった鹿島が、Jリーグそして日本サッカーを牽引していることがはっきりした年間王者制覇でした。
ドゥンガ選手ラストプレー、日本サッカーに残してくれた「勝利へのあくなき姿勢」
磐田は年間を通して圧倒的な攻撃力を発揮してきました。しかし鹿島にだけはすべて敗戦、4敗でシーズンを終えることになりました。悔しさは相当なものでしょう。もしドゥンガ選手が来シーズンも残ってプレーする予定であれば、鹿島に4敗したチームに対する怒りはただならぬものだったかも知れませんが、ドゥンガ選手は第2戦、後半33分に退いた時、日本でのプレーを終えました。
試合後、私服姿に着替えたドゥンガ選手は、磐田サポーターのみならずスタンド全体から沸き起こる「ドゥンガコール」に穏やかな表情で応えスタジアムをあとにしました。
1995年後期から磐田に加入したドゥンガ選手、日本文化を愛しながらも、一方では勝つことにあくなき姿勢を示した「伝道師」でした。
磐田が「ドゥンガロス」状態になるか「ドゥンガイズム」が浸透したチームになるか、問われる来シーズンになりそうです。
12月 Jリーグ参入決定戦、川崎F昇格逃し、札幌が唯一降格決定
Jリーグは、翌年からスタートするJ1,J2体制を決めるため、今年の18チームからJ1リーグを16チームに絞ることになりました。そのためJリーグがスタートして6年目にして遂に降格チームが出るという時代に突入したのです。本来であれば2チームが降格するところですが、横浜フリューゲルス消滅が決まったため一つ降格枠が減り、降格チームはあと一つ、そこにJFLからの昇格をめざす川崎フロンターレも加わってJリーグ4チームとの「Jリーグ参入決定戦」が行われたのです。
最後のジャパンフットボールリーグ(JFL)、本田技研が初優勝、2位に川崎フロンターレ、9チームが翌年からJ2に、残り7チームが翌年から新JFLに
翌年からJ1,J2体制に移行するため、1992年にスタートして、第7回にして最後のジャパンフットボールリーグ(JFL)となったこの年、前年優勝のコンサドーレ札幌が抜け、また福島FCが解散、西濃運輸が廃部となり、全国社会人地域リーグ決勝大会1位のソニー仙台と2位のアルビレックス新潟が昇格、これで15チームの奇数になることから、全日本大学サッカー連盟推薦枠扱いとして国士舘大学が参加する事になりました。大学生チームとして初めて、社会人を対象とした全国リーグへの参加となったわけですが、これは、部員数を多く抱え大学側が出場機会の少ない選手達の実戦の場を求めていた事情があったからでした。
16チームによる2回戦総当たり、全30節のリーグ戦の結果、東京ガスと川崎フロンターレがデッドヒートを演じ最終節までもつれ込みましたが、首位の川崎が1-2でソニー仙台に敗れたのに対し、東京ガスは2-1でアルビレックス新潟を退け、最後のシーズンで初優勝を果たしました。
すでに1997年10月、ジャパンフットボールリーグ(JFL)のチームから新体制のJ2(Jリーグディビジョン2)に参入するチームが次の9チーム決まっていました。
・ベガルタ仙台(現ブランメル仙台)、・モンテディオ山形(NEC山形から変更)、・大宮アルディージャ(NTT関東から変更)、・FC東京(現・東京ガス)、・川崎フロンターレ、・ヴァンフォーレ甲府、・アルビレックス新潟、・サガン鳥栖、・大分トリニティ
このうち川崎フロンターレが「Jリーグ(ディビジョン1)参入決定戦」に参戦する資格を得ましたので、もし川崎フロンターレが昇格を果たせば、現Jリーグから2チームが降格して10チーム、川崎フロンターレが昇格に失敗した場合は、現Jリーグから1チームが降格して10チームが翌年からのJ2(Jリーグディビジョン2)に参戦するチームが出揃います。
現在ジャパンフットボールリーグ(JFL)のチームで、翌年からのJ2(Jリーグディビジョン2)に参加しない次の7チームは、あらたにスタートする社会人全国リーグ「日本フットボールリーグ」(新JFL)を戦うことになりました。
・本田技研、・徳島ヴォルティス、・デンソー、・ソニー仙台、・水戸ホーリーホック、・国士舘大学、・ジャトコ
Jリーグスタート以降、初めてJ2への降格チームが出る熾烈なサバイバル戦の末、札幌が涙
Jリーグで参入戦対象となるチームは、97年シーズンと98年シーズンの年間総合順位をポイント化(98年度は97年度の倍のポイント化)して決めることになっており、その結果、ポイント上位から京都、市原、神戸、福岡の順となりましたが、京都が免除となり他の3チームと札幌が参加することになりました。
札幌はこの年1シーズンのポイントしかなく年間順位では14位と他の3チームより上位で、ポイントも倍加されたものの、如何せん1シーズンのポイントだけだったことから2年間のトータルポイントでは京都、市原の次の順位となり免除ポイントには至らず、参加対象となったのです。
まず11月19日の初日、Jリーグ総合順位最下位の福岡とJFL川崎Fが一発勝負の決定戦に臨みました。負ければ即翌年のJ2が決定するという試合だけに両チームの闘志は鬼気迫るものがあり、まさしくJリーグの新たな修羅場の出現となりました。その結果、福岡が延長Vゴールで勝利し2回戦に進出。敗れた川崎Fの次年度のJ2への参入が決定しました。川崎Fは前年にも勝ち点1の差でJリーグ昇格を逃していて、これで2年連続涙を飲む結果となりました。
次いで11月22日と26日、神戸vs札幌戦、市原vs福岡戦がホーム&アウェー方式で行われ、神戸vs札幌戦は、神戸が連勝して残留決定、市原vs福岡戦は、市原が連勝して残留決定しました。敗れた札幌と福岡が最後の一枠を巡って、12月2日と5日、ホーム&アウェー方式で行われました。福岡は、またしても負ければ即翌年のJ2が決定する試合だけに、川崎Fとの試合経験がモノを言ったのかも知れません。
こうなると年間ポイントが上位のため勝ち上がってくるチームを待ち受ける形となる札幌は、必ずしもアドバンテージがあるとは言えない状況で戦ったことになります。
案の定、札幌は1戦目をアウェー戦を1-0で落として2戦目をホームで迎えました。札幌はホームスタジアムの札幌厚別公園競技場が積雪のため使えなかったのも不運でした。やむなく積雪のない室蘭で試合を行なうこととなりましたが、ここでも0-3で完敗、J2降格が決定してしまいました。
その結果、J2参入(事実上の降格)となったのは、決定戦に参加したJリーグ4チームの中で、この年の年間順位が最も上位14位の札幌という皮肉な結末となりました。翌年以降、下位2チームの自動降格、J2上位2チームの自動昇格という制度が導入されて、その制度が続いた時期は年間勝ち点の下位クラブが残留し、それよりも上位のクラブが降格する事例はなくなったため、この年の札幌の降格は極めて稀なケースとなりました。
札幌サポーターからは1年の成績しか対象にならないのに、2年分のポイント加算規定に巻き込まれたことに対する不満が当然のように出ましたが、果たして不公平感のない方式が他にあったのかどうか。
札幌は1996年シーズン、神戸だけが昇格を決めたJFL(ジャパンフットボールリーグ)で5位に終わっており、しかも準会員資格がまだ認められていない年でしたので、2年間のJリーグ在籍期間を有することが事実上できない状況だったと言うしかありません。したがって、今回の参入決定戦を勝ち抜く以外、残留の道を求めることは難しかったのかも知れません。
Jリーグアウォーズ、MVPには今年の顔・中山雅史選手、得点王とベストイレブンで3冠、新人王に小野伸二選手
鹿島の年間王者で幕を閉じた1998年Jリーグ、12月7日Jリーグアウォーズが、今年も横浜アリーナで開催されました。
選手間投票で決める今シーズンの年間最優秀選手(MVP)には、4試合連続ハットトリックの離れ業を含む36ゴールを叩き出した磐田・中山雅史選手が選ばれ、得点王とベストイレブンと合わせて3冠に輝く、まさに今年のJリーグの顔となりました。
Jリーグでの日本人選手のMVPは、Jリーグ初年度1993年のカズ・三浦知良選手以来やっと2人目の受賞でした。
また新人王には浦和の小野伸二選手が選ばれました。高卒ルーキーがルーキーイヤーで受賞したのは史上初めて、また新人王とベストイレブンとのダブル受賞も史上初めての快挙となりました。小野伸二選手が10年に1人とも20年に1人とも言われた才能を1年目から如何なく発揮、フランスワールドカップのピッチにも立った規格外のルーキーだったことを見事に証明しました。
年間最優秀選手(MVP)の中山雅史選手は、先に表彰があった得点王の受賞コメントで「炎のゴールハンター・得点王の中山雅史です」と「ゴン中山節」を炸裂させると会場はどっと沸きました。また、この授賞式に合わせて「4試合連続ハットトリックのギネスブック登録」の栄誉が伝えられると神妙な顔をしながら「子供や孫の代までギネス記録が残るよう、みなさん、点をとらないでください」とやって、また会場を沸かせました。
ただ、ベストイレブンに磐田から6人もの選手が選ばれた時のコメントでは「得点王がとれたのは磐田にいて、おいしいボールをもらえからです」と、今度こそ神妙にコメントしましたが、逆に名波選手から「あと10点はとれたはずです。来年の課題にして欲しいですね」と突っ込まれてしまいました。なまじ神妙なコメントがどこまでも似合わない中山選手でした。
中山選手は「おいしいボールをもらえた」と謙遜しましたが、ボールをもらう前の動きやトラップの仕方など、地道な練習の繰り返しから技を磨いた努力も身を結んだ結果でした。
この年のベストイレブンは、年間王者を争った磐田と鹿島から合計9人選ばれたのが目立ちました。
最も多かったのは磐田の6人、中山雅史選手(2回目)、ドゥンガ選手(2回目)、名波浩選手(3回目)、藤田俊哉選手(初)、奥大介選手(初)、田中誠選手(初)、年間王者の鹿島からは、柳沢敦選手(初)、秋田豊選手(2回目)、相馬直樹選手(4回目)の3人、ほかには浦和・小野伸二選手(初)、横浜F・GK楢崎正剛選手(初)というメンバーでした。
また、功労選手賞として今シーズン限りで引退を決めたヴ川崎・ラモス瑠偉選手と平塚で現役を終えた都並敏史選手が表彰されました。功労選手の表彰は、1994年の加藤久選手、木村和司選手以来でした。実は、この年限りで引退した選手にヴ川崎・柱谷哲二選手がいましたが、柱谷選手は、このJリーグアウォーズ表彰段階では、まだ現役続行の意思だったため表彰対象とはならず、翌1999年に功労選手表彰を受けています。
ラモス瑠偉選手、柱谷哲二選手、都並敏史選手が現役引退、鹿島・ジョルジーニョ選手、磐田・ドゥンガ選手も退団、12月8日発表の移籍リストには140人もの名前が
今シーズンも後期終了をもってチームを離れる選手がいました。
Jリーグ後期最終節をもって現役を引退した選手の中に、ヴ川崎のラモス瑠偉選手がいました。41歳でした。前項でご紹介したとおり、Jリーグアウォーズで功労者表彰を受けました。
ラモス瑠偉選手は、この「伝説の年」シリーズの中でも、1989年に日本に帰化して、さっそく日本代表に招集されて以来、節目節目でご紹介してきた、日本サッカー界の偉大な選手です。
特に、1993年Jリーグがスタートした年、秋にアメリカワールドカップアジア最終予選の最終戦、いわゆる「ドーハの悲劇」の時には、こう書き込みました。
「結局ワールドカップのピッチに立つことができなかったカズ・三浦知良選手やラモス瑠偉選手など『ワールドカップという舞台がどれだけ凄い舞台か』をブラジルでの選手経験を通じて肌感覚でわかっている選手にとって、どれほどの痛恨事だっかということです。
歴史を知ってしまった者が、あとから彼らにかけられる言葉があるとすれば、それは「あなた方は少し早く生まれ過ぎてしまったのではないでしょうか?」という言葉しかないのではと思います。
なぜかといいますと、アメリカW杯は24ケ国しか出場できずアジアからは、わずか2ケ国の狭き門だったのですが、次の98年フランスW杯は32ケ国が出場できて、アジアには3.5ケ国の出場枠が与えられるからです。」
「それを思えば『あなた方の選手としてのピークが98年フランスW杯のあたりであれば・・・』と思わざるを得ません。ですから「あなた方は少し早く生まれ過ぎてしまった」と思ってしまうのです。
カズ・三浦知良選手もラモス瑠偉選手も、Jリーグ誕生の時期に全国のサッカー少年たちのヒーローとしての名声を得ました。アメリカW杯の出場が叶わなかったのは、サッカーの神様が、2人に『Jリーグ誕生の時期のヒーロー』の称号はあげますが『ワールドカップ出場戦士としての称号』は次の時代の人たちに譲りなさい、という差配だったのかも知れません。」
そう書き込んでは見たものの、それは歴史を知っているものの後付けでしかないわけで、ラモス瑠偉選手への何の「いたわり」にも「ねぎらい」にもならないことは承知の上でした。
もしラモス瑠偉選手が、イラク戦の前の試合、韓国戦の終了直後、チームメイトが勝利に浮足立つ中、一人仏頂面のまま怒気をはらんで語った「まだ何も決まってはいないよ!」という気持ちを、イラク戦のハーフタイムのロッカールームでもぶつけてくれたら・・・と思わずにはいられませんが、ラモス瑠偉選手もまたロッカールームに起きた止めようのない興奮状態の渦に巻き込まれてしまったのですね、と言わざるを得ません。
それにしても、ラモス瑠偉選手は、まさしく「Jリーグ誕生の時期のヒーロー」でした。1993年後期9節の浦和戦で見せたビスマルク選手とのヘディングによるパス交換、やられた浦和の選手にしてみればプロのチームとしてこれ以上の屈辱はないというほどのプレーを見せつけられてしまいましたが、まさに記憶に残るプレーを見せてくれましたし、1994年のJリーグチャンピオンシップ第2戦では、なんとも華麗なループシュートを決めてヴ川崎を連覇に導きました。
その一方、1995年前期4節の広島戦では、1993年の浦和戦の逆パターンをやられてしまう直前に、なんとバスケットボールのバスカットのようにして相手のヘディングパスを止めてしまうという愚かなこともしてしまう選手でした。
1996年にはヴ川崎にエメルソン・レオン監督が就任することが決まると、即座にヴ川崎を退団、京都に移籍、翌1997年、そのレオン監督が解任されると、ちゃっかりヴ川崎に出戻るという徹底ぶりでした。エメルソン・レオン監督が若手を積極的に起用する監督であることを熟知していて、彼の下では絶対自分の出番はなくなると見切っていたのでしょう。
そして、今年フランスワールドカップに日本代表が出場すると、独占放送のNHKの解説者として3試合のスタジオ解説を担当、歯に衣着せぬ解説で、大会終了後の選手バッシングの世論をリードしたと評されました。
1977年に来日したラモス瑠偉選手、翌1978年には1年間の出場停止処分、1981年にはオートバイによる選手生命の危機と言われた大ケガ、1984年にも4ケ月間の出場停止処分など、度重なるブランクがありながら、その都度、不屈の精神力と練習で乗り越え、32歳で日本代表、37歳でJリーガー、そして41歳で引退を迎えました。
このように、プレーでも言動でも伝説となるような、さまざまなインパクトを残したラモス瑠偉選手、ブラジル人の熱い血と日本人の魂を合わせ持った稀有のサッカー選手がピッチをあとにしました。
もう1人、都並敏史選手も現役を引退しました。37歳でした。都並選手も、前項でご紹介したとおり、Jリーグアウォーズで功労者表彰を受けました。
都並選手もヴ川崎の前身・読売クラブ時代から全盛期のクラブの中心選手として活躍、日本代表にはわずか19歳で日本代表に招集され、以来10年以上にわたり日本代表の不動の左サイドバックとして活躍しました。1993年のアメリカW杯アジア最終予選の時は、Jリーグでのプレー中に負傷した左足首にボルトを埋め込む手術により代表選出に間に合わせましたが、結局、痛みがひかず試合出場は叶いませんでした。
この頃の壮絶なケガとの戦いを題材に、ノンフィクション作家の一志治夫氏が著書「狂気の左サイドバック」を上梓、この作品が1994年、第1回小学館ノンフィクション大賞受賞したことと相まって、都並選手のことは全国のサッカーファンの知るところとなりました。
Jリーグでは、1993年の歴史的な開幕戦、横浜マリノス戦で先発出場、前半28分にイエローカードを受け、Jリーグでのイエローカード第1号の選手としても歴史に名を残すことになりました。
その都並選手も、1996年にはヴ川崎から福岡に移籍、前年1997年からは平塚に加入してプレーしていました。そして今年1998年に入り、もはや自分たちの時代は終わったと痛感させられる目に遭います。そのことを11月24日放送のテレビ朝日ニュースステーションにゲスト出演した際、詳しく語ってくれていましたが、その試合は今シーズンの前期12節、ちょうどフランスワールドカップのためJリーグが一旦中断される最後の5月9日のG大阪戦でした。
前半18分、センターサークル脇でボールを受けたG大阪・稲本潤一選手を右後方から追って、都並選手は止めにかかろうと身体を寄せに行きますが、稲本選手、ビクともせずに加速していきます。たまらず都並選手は弾き飛ばされる格好でピッチに置いてけぼりを食らいました。
稲本選手はそのままゴール前まで40mを疾走、ペナルティエリア少し前から狙いすましてシュート、ゴールを決められてしまいました。
置いてけぼりを食らった都並選手、後ろから、その稲本選手のゴールを見送りながら「自分は絶好調なのに、こんな風にされてしまった。もうダメだ。潮時だ」と痛感したそうです。
ちなみにこの試合、ベルマーレ平塚のチームメイト・中田英寿選手が精神的ストレスから来る皮膚炎で顔にまで発疹を出しながらプレー、結果的に彼のJリーグでの最後の試合になったことは、すでにご紹介しました。
都並選手は、その明るい人柄、軽妙な語り口で、すでにこれまでも、テレビ朝日ニュースステーションに時々出演、サッカーコーナーを担当する川平慈英キャスターと息の合ったトークを繰り広げ、お茶の間のサッカーファンを増やしてきました。
その後は、指導者の道を歩みながらも、引き続きテレビ朝日ニュースステーションのサッカーコーナーで長く親しまれることになります。
選手の去就では、鹿島・ジョルジーニョ選手と磐田・ドゥンガ選手、横浜F・サンパイオ選手という、3人のワールドカップ優勝メンバーが日本を離れることになったこともあげなければなりません。ドゥンガ選手のことは1997年シーズンの年間MVPに輝いた時に、詳しくご紹介していますので、ここでは1996年の年間MVPでもあるジョルジーニョ選手について記録にとどめ長く語り継ぎたいと思います。
鹿島・ジョルジーニョ選手、最後に日本サッカーについて思いのたけを語り苦言を呈す
鹿島・ジョルジーニョ選手は1995年シーズンから4シーズン、鹿島でプレーしてくれました。1994年アメリカワールドカップ・ブラジル優勝メンバーの中心的存在であり、世界最高の右サイドバックといわれ、ブンデスリーガの名門バイエルン・ミュンヘンでも不動のレギュラーだったジョルジーニョ選手の鹿島加入は、そのまま鹿島を黄金時代に導く請負人であり、プレーを通して本物のプロサッカー選手の姿を見せてくれた伝道師でもありました。
特に直近の、Jリーグチャンビオンシップ第2戦の終盤のプレーは、彼の偉大さを象徴していました。その試合、すでにジョルジーニョ選手の足は限界を超えていたのですが、本人もベンチも、いまここでピッチを去ったらチームが崩壊して逆転負けを食らってしまうことは火を見るよりも明らかだと知っていましたから、痛みをこらえて最後まで相手の攻撃を矢面にたって防ぎ続け、鹿島を年間王者奪還に導いたのです。
今年、フランスワールドカップのジャマイカ戦で、中山雅史選手が骨折で、中田英寿選手も相手からの激しいチャージで足を痛め、試合後になって、こんな状態でプレーしていたのかと、チームドクターやトレーナーが驚くほどの痛みに襲われていながらプレーを続ける、本物のプロサッカー選手の姿に畏怖したものですが、ジョルジーニョ選手もそういう「本物のプロサッカー選手」だけが集う世界最高峰の舞台を積み上げた百戦錬磨の選手なのです。
日本をあとにしたジョルジーニョ選手に、サッカーダイジェスト誌がブラジル人ジャーナリストを通じてインタビューを行なっています。そこには、これまで、あまり本音を話すことがなかった、日本のサッカー界に対する苦言が吐露されています。
ジョルジーニョ選手の日本のサッカー界に対する置き土産でもありますので、抜粋してご紹介します。
【1999.1.20サッカーダイジェスト誌、インタビュー、リカルド・セティオン氏(サンパウロ在住のスポーツジャーナリストでブラジル代表・プレスオフィサーの肩書も持つ)、翻訳 テツヤ・タカハシ氏】
「ボクは96年度のMVPに選ばれ、鹿島はボクの年俸を最初の2年よりも5割以上上げてくれた。ボクはとても幸せだった。でもその頃から日本のサッカーが危機に陥り始め、深刻になっていった。つまり観客が減ってきていて、このことに対して誰も何もしていないんじゃないかと思った。」
「いまでももちろんそうだけど、カシマスタジアムだけはいっぱいの観客で埋まっていた。しかし他では本当に誰も見にきてくれないんじゃないかと心配したよ。広島のあの立派なスタジアムのゲームのときなんか、本当に少ない観客の中での試合だった。」
(そのとき、ジョルジーニョ選手は、95年、96年にJリーグのクラブが適正ではないと思われる年俸を選手に支払っていたことを憂慮していました)
「たとえばジャウミーニャ(元清水)、決して彼がよい選手じゃないと言ってるんじゃない。ただ彼に、たった6ケ月のプレーに対し、100万ドル(当時の為替レートで約1億円)も支払われたということになる。コンディションも悪く、ジャウミーニャは日本のサッカーにもたらしたものがほとんど何もないまま、ブラジルに帰ってしまった。」
「これは正しいこととは言えないよ。あの頃Jリーグのクラブはお金を払い過ぎていた。そしていま、本当に大切なプレーヤーのために払うお金がない。これはクラブのマネージャーがプロの仕事をしていないという証拠だ。彼らはプロのサッカーマネージャーではなかった。他から駆り出された人たちが片手間にこの仕事に就いていたという問題を露呈したんじゃないかな。」
「さらにJリーグ自体が犯した間違いもある。これは日本人気質なのかもしれないが、クラブのマネージャーたちもJリーグの幹部に対して勇気をもって対峙できなかった。Jリーグ側が間違っていたとき、クラブ経営者たちは彼らと戦うことをしなかった。」
「97年の最後、われわれは優勝を争ったが磐田に敗れた。でも他のカップ戦ではタイトルを取ったし、自分の仕事や鹿島としてのプレーには満足していた。ただJリーグ全体としての状況は悪化してしまったと思う。スタジアムに足を運ぶサポーターの数は減り、スター選手も少なくなった。」
「それから日本のサッカーについてボクはいつも思うんだが、メディアがサッカーをあまり大きく取り上げてくれない。サッカーの記事が競馬や競輪より小さいのは悲しいよ。でも本当にガッカリしたことは、ボクも他の外国人選手も日本ではインタビューや記事の対象となっていないことだ。日本人選手がゴールをあげたり、ちょっとよいプレーをするとマスコミはその日本人選手を追いかけ、われわれには目もくれようとしない。まるで日本のマスコミは新しいヒーローを必死で探しているようだね。こうした状況は、日本のサッカーにとってよいこととは言えないな。」
フランスワールドカップ、日本はオカダを代表監督にすべきではなかった
(98年シーズンに入ってまもなく、ジョルジーニョ選手は中国でのアジアクラブ選手権の試合で左足を骨折してしまいます。懸命にリハビリを行なっているうちに背中まで痛めてしまい治療のためドイツに渡りました。回復してJリーグに復帰しましたが、ふたたび骨折、また6月まで休んでしましました。ちょうど、その頃、日本代表がフランスワールドカップを戦っていました。彼は日本代表を見ていて『耐え難い間違いがある』と強烈な話をしました。)
「日本がワールドカップの大会中にしたこと、それから大会前にしたことで耐え難い間違いがたくさんある! まず最初に監督は決して岡田にするべきではなかった。」
「加茂さんの後を岡田が引き継ぎ、チームが出場権を得たことで誰もが彼を信じた。そして彼は残り、日本人は外国人の助けなしですべてをできると考えてしまったんだ! 大会前にボクはインタビューを受けるたびに言った。フランスワールドカップで日本代表は何もできないだろうと。よい選手はいたが、ゲームシステムや経験を持ち合わせていなかった。」
「ボクは数えきれないくらい言ったよ。ジーコや他の経験者に、サッカーを知っている人物に会うべきだと。日本人はもうすべてを知っていると思ったようだけれど、実際には選手たちをフィールドのなかや外で励ましたり、勇気づけたりして助ける誰かがとても必要だったんだ。だからボクははっきりと言える。岡田は決して監督になるべきではなかったとね。」
「彼はフランスに17歳の選手を連れて行き、経験のある選手を置いていった。信じられないことだ。なぜなら日本にはあそこにいる資格のある選手、あそこに必要だった素晴らしい選手がいたわけだから。なぜ小野を連れて行き、カズやラモスを残していけるんだ。もしそれが岡田や他の人たちが下した選択ならば、彼らはもっとサッカーを勉強する必要がある。」
(ジョルジーニョ選手は、日本人が国民性として深刻な問題を抱えていることを指摘しました)
「日本の人たちは、自分たちが解決すべき問題を、それほど深刻に話し合わないという国民性をもっているのではないか? まるで問題自体が存在しないかのように振る舞う。深刻で重大な問題は伏せておき、誰もそのことには触れない。悲しいことだよ。だって日本のサッカーは、問題を直視する必要があるからさ。そうしない限り、問題はどんどん大きくなってしまう」
(今回、ジョルジーニョ選手は、いまが自分が去る潮時だと悟ったのでした)
「Jリーグの現状は理解できるし、経営面の危機による年俸カットもわかるよ。でもボクはワールドカップ優勝メンバーで国際的なプレーヤーでもあり、4年間で日本の年間タイトルも2回取っている。今年だって、ボクがいなかった前期はダメで、ボクが戻った後期は優勝して、年間タイトルもとった。鹿島でこれだけの成功を収めていて年俸が下がってしまうのは、普通で考えても受け入れ難いことだよ。最低でも今年と同額は維持できるんじゃないかと思っていた。」
「磐田と年間王者を争っている時、ドゥンガに来年のことを聞いてみたんだ。すると、提示された年俸が今年の半分だと教えてくれたよ。その話を聞いてボクは本当に怖かった。ドゥンガに起こるなら、他の誰に起こったって全然不思議なことじゃない! 」
「何回かの交渉の後、彼らが提示した額はボクがブラジルで取れる年俸と同じか、それよりも低いということがわかった。だから同じ額でのプレーを考えたときにボクは生まれ故郷のブラジルを選んだわけだよ。」
「鹿島がなぜそんな結論を出したのか理解できない。年俸が2割下がったとしてもボクは日本にいたと思う。鹿島は結局チーム全員の年俸を少しづつ削るのを嫌がり、一番年俸の高い選手を切ることを選んだわけだ。これは間違いだと思う。結果としてボクもチームも、誰もが失うものしかなかったんだから」
「ボクはジーコがいつも鹿島に言っていることを繰り返したい。もし97年や98年の鹿島のような高いレベルのチームが欲しいのなら、ある程度のお金は必要だ。」
「実は、鹿島との交渉の最中、他の日本のクラブからとてもよいオファーがあった。柏レイソルだ。でもボクは鹿島の最終的な提示にすっかり落胆してしまい、日本にいる気になれなくなったしまった。ボクにとって他のチームでプレーするのは、そんなに簡単なことじゃない」
日本サッカーの将来を考えた時、まだまだ外国人の国際的選手や有能な外国人指導者の力が必要だ。
「ボクがブラジルに帰ることが決まった時、チームメイトが皆ボクのところに来て、とても悲しいと言ってくれた。ボクらはいつだって良い関係を築いてきたからね。ボクはいつでも日本人選手を手助けし、勇気づけ、サッカーテクニックの向上に力を注いだ。でもそのボクがいなくなることを彼らは知った。その役目をする人物がいなくなることを。」
「嬉しかったのは誰もが将来ボクが鹿島の監督として戻ってくることを願ってくれたことだ。ボクも鹿島に戻りたい。監督としてではなく、鹿島の役に立つために」
「日本サッカーの将来をボクはとても憂慮している。来年はサッカーの質が急激に落ちるだろう。いなくなる良い選手が多すぎる。自動的にスポンサーも減る。そして間違いなくサッカーはあまりテレビに登場しなくなるだろう。事態は雪だるま式にどんどん悪化しJリーグを潰してしまうかも知れない。」
「どんなことがあっても2002年のワールドカップまではJリーグを続けるだろうけど、日本サッカーについては心配だな。(中略)日本サッカーを救うにはまず最初に国際的なスター選手をある程度残しておくことだ。お金がかかることだけど、大学を出たばかりの若い選手や、1~2しかプロ経験のない選手に100万ドル払うよりはずっといい。どのチームにも最低ひとりの国際的スター選手が必要だね。」
「2番目に若い日本人選手の年俸を一定の水準まで下げること。それからマスメディア、とくにテレビがもっとサッカーを取り上げるべきだ。そのためには何らかの契約や取引が必要かも知れない。サッカーの番組を増やして盛り上げていかないとダメだ。これはとても大切なことだよ。世界中どこでもテレビはサッカーを育てる肥やしになっている。日本だけが違うという理由はない。」
「そして監督に外国人を雇うこと。これが一番大切かもしれないな。日本人はまだ戦術を作り上げる段階にはなく、独自の固有なサッカーを展開している。例えば鹿島にはたくさんの日本人トッププレーヤーがいるが、これはエドゥー(ジーコの兄)に負うところが大きい。彼は、若手選手の中からよい選手を見出しトップチームで育てた。彼のようにサッカーのことを知り尽くしている人物は日本人の中にはいないんだよ。」
「最後にクラブのマネージャーについてだが、クラブのマネージャーには元選手を採用して、いろいろな面で考え方や環境を向上していく必要がある。日本協会やJリーグにすぐにでもジーコを連れてきて日本サッカーの向上をめざすべきだ。彼こそが適任だからね。なぜジーコがそのポジションにいないかがボクには不思議だ。最高責任者としてではなく、変化をもたらす役員のひとりとして。日本サッカーのためにも、日本を本当に愛しているジーコは最適だ。」
「ボクは40歳になるまで現役でいたい。もっともっと日本サッカーの手助けをしたい。ボクは悲しみながら日本を去るけれど、いままで日本のためにベストを尽くしてきたことだけは確かだ。」
「あなたからも日本のサッカー関係者にはっきりと伝えて欲しい。日本にいたこの数年間、ボクはいろいろな人から受けた親切にとても感謝しているということを。誰からもよくされたし、ブラジルにいた時だって、こんなによくしてもらったことはない。(中略)持ち帰るのはよい思い出だけだよ。ボクが言いたいのは世界中どこに行ってもネガディブな側面はあるわけだし、日本の人たちもボクの批判を受け入れて将来に役立てて欲しいということさ」
サッカーダイジェスト誌のリカルド・セティオン氏によるインタビューからの抜粋は以上です。話す相手が同邦人だったからでしょう。かなり内部的なことまで踏み込んだ話が含まれていましたので長い抜粋になりました。
ジョルジーニョ選手の目には、Jリーグがかなり危機的に見えていたことがよくわかります。そして、口をついて出た言葉は、各クラブがなすべきこと、Jリーグが取り組むべくこと、そして日本サッカー界が取り組むべきことまで多岐にわたる、かなりの苦言、直言でした。日本人の国民性にまで言及して指摘してくれたのは、彼がいかに日本という国を愛してくれていたかを物語っています。
清水・アルディレス監督も「Jリーグ最優秀監督賞」を花道に退任
このほか、清水・アルディレス監督も、Jリーグアウォーズでの「Jリーグ最優秀監督賞」の受賞を花道に、辞任することになりました。1996年に清水の監督に就任以来、1996年のナビスコカップを初制覇に導くなど手腕を発揮、1997年シーズン終了時期のクラブの存続危機の際には「今、クラブを投げ出すわけにはいかない」と契約を延長したのでした。アルディレス監督は、一旦日本を離れますが、後年、また日本の各クラブの指揮をとることになったことはご存じのとおりです。
監督では、前期優勝とナビスコカップ優勝を果たした磐田のバウミール監督も、年間王者タイトルを失ったこともあり退任となりました。
Jリーグ移籍リストには140人もの名前が掲載、合併・消滅の横浜Fをはじめヴ川崎、札幌、福岡から多数
12月8日、Jリーグから移籍リストが発表されました。その数140人、これまでにない多数の掲載となりました。
理由として、まずあげられるのが合併・消滅が決まっている横浜フリューゲルスのメンバーが掲載されたことがあります。横浜フリューゲルスのメンバーについては、すでに全員の進路をご紹介していますので、ここでは省きます。
そのほか、これもすでにご紹介したとおり、1999年シーズンからクラブ保有の選手枠に上限が設けられることになった(A契約選手は25人以下となった)こと、また各クラブの経営立て直し気運が高まり選手人件費の削減を図る動きが活発化したためです。
横浜フリューゲルス以外に掲載人数が多いのは、読売新聞社が撤退して日本テレビ単独の出資に変わったヴ川崎、氏家社長が宣言していたとおり年俸の高い選手はもとより、10数名もの選手を掲載しました。
また、J2降格に決まった札幌と、辛くもJ1残留を果たした福岡、市原も軒並み10人以上の掲載、さらに神戸、京都も大幅な戦力入れ替えを図るため多数の移籍リスト掲載を行ないました。この時点では移籍交渉がこれからですので、来シーズンの各チームの顔ぶれがかなり変わることになります。
日本サッカー協会、各種指導者養成講習会の講師を養成する「JFAインストラクター制度」創設
日本サッカー協会は、4月、各種指導者養成講習会の講師を養成する「JFAインストラクター制度」創設しました。その制度をもとに、11月、初めての、指導者向けの研修会「第1回JFAフットボールカンファレンス」を開催(於・福島Jヴィレッジ)しました。以後、原則として2年毎に開催していくことにしています。
この研修会は、日本全国でサッカー指導にあたっているJFA指導者S・A・B・C・D級コーチなどを対象として、現在の世界のサッカーがどのようになっているかについて体系的な研修を行ない、トップクラスの指導者から草の根レベルの指導者まで、最新のトレンドを共有する場として創設されたものです。
研修会には全国から数百名の指導者たちが福島県Jヴィレッジに参集、テーマを「日本から、アジアへ、そして世界へ 1998FIFAワールドカップ フランス大会 テクニカルレポート」と題して、日本サッカー協会・技術委員会がまとめたフランスワールドカップ大会の技術的な面からの詳細な報告がなされました。
中田英寿選手、ペルージャで不動の司令塔の地位を確立、森山泰行選手はイタリアの隣国スロベニアで、前園真聖選手もブラジル・サントスで奮闘
さる9月13日のイタリアリーグ・セリエA開幕戦、中田英寿選手は、ペルージャに加入して、いきなりの公式戦で、昨シーズンの覇者ユベントスを相手に2ゴール、あわや王者撃破かとペルージャサポーターを狂喜乱舞させる見事なデビューを飾りました。
開幕戦で2ゴールとなれば、当然対戦相手のマークが厳しくなる中、中田選手は、その後も逞しくプレーを続けます。チームも名将カスタニエル監督の采配で昇格組とは思えない戦いぶりを見せました。
6節のパルマ戦、チームメイトの活躍で強豪に勝利した中田選手、10月28日開催の日本代表トルシエジャパンの初戦に参戦のため、日本にとんぼ返りして、試合後、またイタリアに戻りました。
この帰国、中田選手に2つの難題を突き付けました。一つは日本代表戦のためチームを離脱することになると生じる、ベルージャ・ガウチ会長と日本サッカー協会との猛烈な綱引きです。すでにチームに欠かせない選手になった中田選手をガウチ会長は1試合たりとも欠きたくないのです。一方の日本サッカー協会は、FIFAが認めたルールに従って日本代表戦に招集をかけます。本来ならチームは黙って選手を送り出さなければならないのですが、そこが独裁者と言われているガウチ会長です。
日本サッカー協会は、これまで、そうした海外クラブの選手を招集する際の難しい交渉の経験がありませんでしたから戸惑います。ガウチ会長の剣幕に気圧されながらも、なんとか招集に漕ぎつけたのでした。これからも中田選手は、ずっと、この代表招集のたびに板挟みになっていきますが、今回は、その一発目となりました。
もう一つの悩ましいことは、日本代表戦のたびに生ずるイタリアと日本の長距離移動、時差の問題とコンディョン維持の苦労です。今回はイタリアに戻った直後の7節、カスタニエル監督が休養を命じましたから中田選手の体調は戻りましたが、チームは0-2と敗戦、中田選手不在の影響がもろに出てしまいました。これについても、これから先、ついて回る苦労になります。
またもやレナト・クーリの観衆を狂喜乱舞させた完璧なオーバーヘッドゴール
イタリアの寒さが厳しくなってきた頃、中田選手は手袋を着用、その後、おなじみになるスタイルでプレーを始めました。そして迎えた11月29日の11節、ピアチェンツァ戦、ゴールへの意識が高まっている中田選手にスーパーブレーが生まれます。
前半19分、相手ゴール前右側約25m付近でペルージャがFKを得ます。蹴るのはラパイッチ選手、ゴールキーパーの前、ペラルティスポット付近に相手DFが3人、ペルージャは中田選手ともう一人が有利な位置取りをしようとしていました。ラパイッチ選手が左足からフワリとしたボールをいままさに上げようという瞬間、中田選手がその混戦から回り込むように抜け出し、ボールの落下地点を見定めて走りました。
ボールはちょうど、ラパイッチ選手とゴールキーパーを結んだ軌道上に来たのです。中田選手は、その軌道を予測していたかのように、後方からのボールが少しづつ中田選手に近づいてくると、中田選手は意を決してバイシクル体勢に身体を回転させます。そして空中に蹴り上げた右足でボールをジャストミート、ボールはGKが右上にジャンプした手に触れることなくネット中央に突き刺さりました。
中田選手は身体を1回転させながらゴールと見届けると、すぐにいつものようにセンターサークルに向かって走り出しましたが、チームメイトが黙っていません。おそらく口々に「ナカ~~タ、ケ・ベッロ!(何て素晴らしいんだ!)」というようなことを叫びながらでしょう、皆、中田選手を満面の笑顔で讃えました。すると、いつもは控えめな中田選手も「してやったり」という気持ちだったか、珍しく笑顔でチームメイトとセンターサークルに走りました。
ホームスタジアム、レナト・クーリの観衆もゴールが決まった瞬間総立ちになりました。あの開幕戦・ユベントス戦以来の興奮に沸き立ちました。
なんという選手でしょう。点をとらなければ認められない助っ人外国人、しかもアジアから来た人間という懐疑的な評価を覆すにはゴールを上げ続けなければダメだ。そう決意した時の中田英寿選手は、研ぎ澄まされた集中力と類まれな身体能力、技術を駆使して、やり遂げてしますのです。まさに「中田英寿選手の心・技・体」が完璧に機能した時に生まれるスーパープレーでした。
この日は、後半にも自ら追加点を入れて勝利の主役になるとともに、ペルージャの司令塔として不動の地位を築き、セリエAの中でも完全に注目される選手となりました。
それにしても、このバイシクルシュート、落下地点への走り込み方といい、ラパイッチ選手との呼吸といい、おそらく練習を通じてデザインされたプレーに違いありません。バイシクルに行くかどうかは咄嗟の判断だったかも知れませんが、あの地点への走り込みのタイミングに余裕があったからこそ判断できたプレーだと思います。
中田選手は、このあともラバイッチ選手と言う相棒を得て、さまざまなコンビプレーを見せてくれます。
セリエAはクリスマス休暇から新年まで短いオフに入りますが、チームは14節終了時点で9位、一つの目標である10位以内をキープ、自らも7ゴールを上げる申し分ない成績で新年を迎えることになりました。
イタリアの隣国スロベニアの地に名古屋・森山泰行選手、レンタル移籍
世界最高峰のリーグと言われるイタリアリーグで中田英寿選手が見事な活躍をみせている頃、そのイタリアと北東部で国境を接している国スロベニアのリーグに、7月、名古屋からのレンタル移籍でFWの森山泰行選手が加入しました。ヒット・ゴリツァというチームです。
森山選手が海外移籍を熱望するようになったのは前年のJリーグ終了の時点でした。名古屋ではスーパーサブの役割でいながら、スタメンFW以上のゴール実績をあげてきた森山選手、しかし、友人の死をきっかけに自分のサッカー人生を見つめ直し、海外でゼロから挑戦する道を選んだそうです。
名門・帝京高校では天才ゲームメーカーと謳われた磯貝洋光選手とのコンビで高校サッカー界のスターとして活躍、その後、順天堂大学でもエースストライカーとして活躍したきた森山泰行選手にとって、このままスーパーサブの代名詞でもある「8時半の男」では終わりたくない、知らない世界のサッカーを経験したいという気持ちが29歳になった男を突き動かしたのでした。
所属チームからレンタル移籍で海外でプレーするケースは、前年1997年には横浜MのFW安永聡太郎選手がスペイン2部リーグに、鹿島のFW鈴木隆行選手と阿部良之選手がブラジルでジーコが立ち上げたプロクラブにレンタル移籍するという事例が出始めました。
森山泰行選手の場合は、移籍先を自分が直接入団テストを受けるという形でオーストリア、チェコ、スロベニアなど入団テストの許可を得た中から、最初に受けて入団を勝ち取ったのがスロベニア、ヒット・ゴリツァでした。
名古屋にいた時の1/20の給料、劣悪な練習環境、Jリーグでの恵まれた環境をかなぐり捨ててまで、新天地を選んだのは「とにかく原点に戻って精一杯やる中から自分の欠点を見直し、プレーの幅も広げる」という強い信念からでした。そのためには、どの国であるとか、どのリーグであるとか、そして年俸も森山選手にとっては関係ないことだと言います。
見知らぬ土地で人知れず、愛妻に支えられながら挑戦する一人の日本人選手、中田英寿選手の場合は、日本の社会全体が注目するほどの海外移籍でしたが、ここにも紛れもなく海外挑戦の逞しい姿があります。
前園選手、ブラジル・サントスへの3ケ月レンタル移籍、最初の試合でいきなりゴール
昨シーズンからヴ川崎でプレーしていた前園選手、今年に入っても調子はあがらずフランスワールドカップメンバーからも外れてしまいました。
もともと海外志向が強かった前園真聖選手(25)は、弟分だったはずの中田英寿選手がイタリアリーグ・セリエAに飛躍、心中穏やかではない日々を送っていたことでしょう。所属のヴ川崎に海外移籍先を計らってもらったところ、ブラジル・サントスへの3ケ月レンタル移籍が成立しました。
サントスの監督は、前年までヴ川崎の指揮をとっていたエメルソン・レオン監督です。
ようやく念願の海外でのプレーの機会を得た前園選手、ブラジルの名門サントスですから、自分の力を示すには申し分ないチームです。
10月19日デビュー戦ポルトゲーザ戦で後半20分から途中出場した前園選手、わずか1分後に相手ゴール前でファーストシュート、これが相手DFにあたって大きくはね、そのまま先制ゴールとなりました。スタンドに向かって両手を広げるおなじみのポーズをとるとチームメイトが次々と抱き着き押し倒された前園選手、髪の毛までわしづかみにされる手荒い祝福を受けました。
いきなり初ゴールのニュースを聞いたラモス瑠偉は「デビュー戦でゴールするなんて凄い、レンタル期間が3ケ月間なんて短い、自分なら日本に帰らない、もう1~2年やらなきゃ、日本人選手でいい選手がたくさんいることをアピールして欲しい」(98.10.20スポーツ報知)と激励しました。
一方、サッカージャーナリストの富樫洋一氏は「前園選手は体力的に、今後1~2戦はうまくこなせても、その後が厳しいと思う、警戒されてハードタックルでガンガン来られると難しい」(98.10.20スポーツ報知)と指摘しました。
エメルソン・レオン監督は「ブラジルに来て間もないのに、よくやってくれた。彼の才能の一端を示すものだ」と評価しましたが、果たして前園選手の活躍はこのあとも見られるでしょうか?
海外移籍の「本格化元年」とも言える年に
こうして、中田英寿選手、森山泰行選手、前園真聖選手、3人3様の形で海外でプレーする選手が現れたのも今年の大きな出来事でした。
中田選手21歳、森山選手29歳、前園選手25歳、それぞれ年齢が違う3選手、まさに、その年齢から来るサッカーへの向き合い方が現れている3人です。
翌年以降、海外移籍を果たす選手が途切れることなく続いていったことを考えれば、1998年は「海外移籍の本格化元年」といってもいいのかも知れません。
では、なぜ、この年が「本格化元年」になったのでしょうか。それは、紛れもなくJリーグに対する選手の価値観の変化だと思います。
1993年にスタートしたJリーグ、選手たちにとって、最初の頃は凄い外国人選手とともにJリーグでプレーできること、そのこと自体が素晴らしい体験でした。
しかし3年、5年と時を経るごとに選手たちは、これだけ屈強な外国人DFと互角にやれている自分は、もっとやれるのではないかと次第に考えるようになり、しかも、そこに国際大会などの経験も加わると海外挑戦への誘惑が次第に強くなっていきます。
海外挑戦を考える場合、初めの頃は、海外からのオファーがあれば行けるけど、オファーがなければあきらめるしかないと考えていました。しかし、あきらめきれない選手は、クラブに相談して、受け入れ先とレンタル移籍など方法をクラブに計らってもらう方法をとるようになりました。
そして、森山泰行選手のように、自ら入団テストを受けでも移籍先を探すという具合に、次第に主体的、能動的になってきたのです。
そこにJリーグ各クラブの経営状態の悪化といった要因が出始め、外国人選手たちが、一人また一人と母国へ帰ってしまう状況が生まれ、日本人選手といえどもリストラの例外ではなくなってきました。
中田英寿選手には多くのクラブからオファーが届きましたが、一つの要因として清水の監督を務めたアルディレス監督がJリーグでの中田英寿選手を高く評価していて、アルディレス監督の口から評価が広まったことがあげられます。
日本人選手にとって母国へ戻った外国人選手や監督を通じて、いい評価が伝わりやすくなったことも「本格化元年」の一つの要因と言えます。
タイ・アジア大会サッカー参戦の男子五輪代表(U-21)は二次リーグで敗退、女子は銅メダルを獲得
11月23日の親善試合でアルゼンチン五輪代表(U-21)を撃破した日本五輪代表(U-21)、11月30日から始まったタイ・アジア大会サッカーに参加しました。
参加各国がフル代表で参戦する中、日本と韓国は2002年日韓W杯を見据えた強化目的のため五輪代表(U-21)を送り込んだのです。
まず各グループ3チームづつによる一次リーグ、日本はインド、ネパールと当組、まず12月1日のネパール戦を5-0、12月3日のインド戦を1-0で退け二次リーグに進出しました。
二次リーグは韓国、クウェート、UAEと同組、初戦韓国に0-2で敗戦、2戦目クウェートに2-1で勝利、3戦目のUAE戦、勝利が必要だった日本は0-1で敗れてしまい、グループ3位、準々決勝への進出を逃してしまいました。
トルシエ監督体制になって初めての国際大会、五輪代表(U-21)はチーム戦術もメンバーも試行錯誤段階、しかも選手たちのコンディションもバラバラな状態で実は結果を求めるのが無理な大会だったといえます。経験をして、いろいろと足りないところだらけだったことを知ったことだけが成果といえば成果の大会でした。
特に、二次リーグ3戦目のUAE戦、指揮していたのは1996年名古屋を指揮していたケイロス監督でした。日本選手の特徴や弱点を熟知している監督にしてやられました。
このアジア大会サッカー男子、優勝はイランでした。フランスワールドカップにも出場、1勝をあげた実力国で、今大会も優勝候補にあげられていましたが、決勝でクウェートを2-0で退けて金メダルを獲得しました。
一方、女子代表は8ケ国が参加して2組に分かれ12月7日からスタートしました。日本は北朝鮮、ベトナム、タイと同組。
宮内聡監督率いる日本代表は、別グループで勝ち上がってくるであろうアジア最強の中国と準決勝であたらないために、グループリーグ1位突破をめざして、12月8日の初戦タイ戦6-0で発進しました。2戦目北朝鮮には得意のパスワークで2点をあげたものの試合終了間際にフィジカル、パワーで押し込まれ2-3で敗戦、3戦目ベトナムを8-0で退けたもののグループ2位、準決勝で中国と当たることとなりました。
中国戦、やはり歯がたたず0-3の完敗、日本は銅メダルをかけて3位決定戦に回りました。相手は台湾、日本は前半20分、内山環選手のクロスを大竹奈美選手が先制ゴール、後半20分にキャプテン山木里恵選手のロングシュートが決まり追加点、その後1点返されたものの逃げ切り2-1で勝利、意地の銅メダル獲得といった大会でした。
この大会、日本の中心はやはり10番を背負う澤穂希選手、まだ20歳というべきか、もう20歳というべきか、日本女子代表の司令塔兼得点源として存在感抜群のプレーを見せてくれました。
日本代表FIFAランキング 年初2月には9位という歴代最高順位になるも、異常値?とのFIFA判断から12月には20位でこの年を終了
昨年12月に14位で終えた日本代表FIFAランキングですが、今年に入り上昇、2月には9位という歴代最高順位をつけました。この順位には、さすが日本のサッカーファンも「?」となりました。これは、とにかく国際Aマッチの試合数をこなして勝利を重ねれば順位があがる仕組みですから、間違いというわけではなかったのですが、FIFAもさすがに、実力を反映していないのではないかと判断、12月になって、ランキングの指標となるポイント換算方式を見直しました。その結果、今年の代表関連の全日程を終えた日本代表は20位にランクされました。
というこの話、どこから見つけた情報かと言いますと、2010年夏から2011年1月にかけて出版された「サッカー日本代表 世界への挑戦1991-2010」(ベースボールマガジン社分冊百科シリーズ全10巻)という資料に記載されていたものです。
この冊子は、隔週発刊、1991年から2年分づつを10冊にしたもので、最後にハードカバーのバインダーにとじ込んで完成するシリーズになっています。
その中に各年ごとの年表があるページがあって、そこに「FIFAランク考察」というコメント欄があり、1998年のところに上記の説明があったわけです。
U-19日本代表・清雲監督、J2大宮GM転身のため辞任、後任にトルシエ監督、空前絶後、3世代代表監督兼任体制に
11月下旬、次年度からJ2に参戦する大宮アルディージャのGM(ゼネラルマネージャー)に、U-19日本代表監督を務めていた清雲栄純氏が就任することになりました。日本サッカー協会は、さっそく後任を検討する中で、日本代表・五輪代表監督兼任のトルシエ監督が一貫指導体制の重要性を語っていたことから、アジア大会から帰国後、相談するとトルシエ監督は自ら指導することを申し出ました。
そのため日本サッカー協会はこれを承認、前代未聞どころか空前絶後、トルシエ監督が3世代の代表監督を兼任する体制となって新しい年に向かうことになりました。
果たして、3世代すべてのチームを掌握して、それぞれ予定されている国際試合で満足のいく成果を出せるものでしょうか? 新しい年に起きるさまざまな問題、衝突、軋轢、この時はまだ誰も予感している人がいなかったのかも知れません。
FIFA世界最優秀選手、バロンドールともにジダン初選出、トヨタカップは欧州王者レアル・マドリーが制覇
1998年の世界のサッカーは、フランスワールドカップが圧倒的なニュースバリューを誇りますが、それでも、いくつかの新しいニュースが生まれました。
まずFIFAが世界最優秀選手の受賞者を発表、このFIFA世界最優秀選手の選出は、各国代表チーム監督の投票で行われるもので、フランス代表、ユベントス所属のジネティーヌ・ジダン選手が518ポイント、2位のブラジル代表、ロナウド選手以下を大きく引き離して受賞しました。
また年明けに発表された、1998年のフランス・フットボール誌主催・欧州最優秀選手賞、いわゆるバロンドールもジダン選手が244ポイントで2位のスーケル選手以下を大きく引き離し受賞しました。
フランスワールドカップ決勝であげた2ゴールで、一気にスーパースターの座に駆け登ったジダン選手、この年を象徴する選手として新たな勲章を手にしました。
前年から戦われてきた97-98欧州チャンピオンズリーグ、5月20日にオランダ・アムステルダムで行われた決勝は前回覇者ボルシア・ドルトムントを下したスペイン、レアル・マドリーと、前回決勝で涙を吞んだユベントスとの戦いとなりました。
試合はジダン、デシャン、ダービッツなどの強力中盤を形成するマルチェロ・リッピ監督のユベントスと、ラウル、セードルフ、レドンドらで中盤を構成するユップ・ハインケス監督のレアル・マドリーとの争いとなりましたが、両者譲らず拮抗した展開の中、後半21分、一瞬のスキをついてレアル・マドリーFWミヤトビッチがゴール、これを守り切り、レアル・マドリーは実に32年ぶりに欧州制覇を果たしました。レアル・マドリーはここから2000年代前半にかけて黄金期に入っていく最初のタイトル獲得でした。
ユベントスは3シーズン連続で決勝に進出しましたが、最初のシーズンにタイトルをとってからは、タイトルに見放されることとなりました。
メディア王、ルパード・マードック氏によるマンチェスターU買収計画浮上、しかし翌年、英国政府が買収に「NO」、一方、ビッグクラブによる新リーグ立ち上げ構想も浮上
この年夏、イングランドプレミアリーグの名門、マンチェスターUが、イギリスの衛星放送会社BスカイBから買収計画を持ち掛けられていたことが発覚しました。BスカイBは、アメリカの実業家でメディア王と呼ばれたルパード・マードック氏が影響力を持つ会社で、テレビ放映権とプロスポーツクラブを一体的に保有することで経営を長期的に安定化させようという戦略によるもので、すでにアメリカメジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの買収を成功させた経験から、次にプロサッカーチームに目をつけたと言われました。
しかし、放送事業であるBスカイBによる買収の実現にはイギリス政府の承認が必要だったことから、イギリス政府の対応に注目が集まりました。マンチェスターUのサポーターをはじめサッカーファンからは「外資による金もうけのための買収だ」と猛反対が出ました。
マンチェスターUのファンは、当時ロンドン証券取引所に上場していたマンチェスターUの株を買い集め、ファンによる株主団体「シェアホルダーズ・ユナイテッド・アゲインスト・マードック(SUAM)」を組織化、対抗手段を講じました。
また、マンチェスターを中心とする社会各層からも「本来は市民のものであるべきフットボールが、スポーツ精神ではなく金に振り回されている」との声が上がるようになりました。
プレミアリーグは急速に商業化が進んでいたものの、イングランドのサッカー界には地域を大切にするという古き良き伝統が根付いていたのです。「イギリスでは、サッカークラブは地域社会の資産であり、営利事業であってはならないという」というコンセンサスです。
この問題は年を超えた1999年まで持ち込まれました。イギリスのブレア政権が独占合併委員会に調査を付託したためで、1999年4月、独占合併委員会が調査結果を踏まえて出した結論は、「買収は放送局間の競争に悪影響を及ぼす」すなわち「ノー」でした。「委員会が検討したほぼ全ての考えられるシナリオで、BスカイBの市場支配力を強めることになる」と結論付けたためでした。
日本では今年、危機的状況に陥ったJリーグクラブをファン・サポーターが救おうとする行動に出た元年とも言える年でしたが、プロサッカークラブが買収の対象になるほど魅力のある欧州のビッグクラブには、次元の違った危機が迫った事例でした。
ただ、この買収計画がアメリカのプロ野球であるメジャーリーグチームの買収で成功したシナリオをそのままサッカーの世界に持ち込んだという点では、一つ日本のJリーグも自信をもっていい点があります。
それはメジャーリーグが日本のプロ野球と同じ(歴史的には日本がアメリカを真似たのですが)、いわゆるフランチャイズ制、サッカーの「ホームタウン制」とは異なり、チームの財政悪化や経営戦略上の判断などを理由に簡単に本拠地の移転が可能な制度だという点です。
このことが「地域との長いつながり」を経営の基本に据える世界のサッカークラブの考え方との大きな違いで、Jリーグでも、プロ野球の球団経営と同じ思考回路でサッカークラブ経営に臨んでいるチームがあることはご存じのとおり、そういう思考では「クラブは地域の財産」と考えているサッカーファン・サポーターから反発を受けるのは必然ということになります。
したがって、仮に将来「Jリーグクラブが魅力的な企業だから」といって買収を考えるような大資本が現れても「クラブが地域の財産である」という根本的な部分を見落としてはうまくいかないであろうという先例を示してくれたのかも知れません。
それにしてもつくづく思うのは、欧州におけるサッカークラブの「地域における重さ」です。それは、長い歴史の中で市民、ファン、サポーターが築き上げてきたもので、事業経営としても凄く魅力的なレベルまで高まっているのですから、羨ましいレベルに達しているということです。
しかし、魅力的なビッグクラブを愛しているファン、サポーターの心配事は、ほかにも浮上してきました。
欧州全体にその名を轟かせているビッグクラブが何チームかが、密かに新リーグ立ち上げ構想を練っているという話が暴露されたのです。
1998年7月、ドイツの新聞がスクープ記事として明るみに出ました。この欧州スーパーリーグ構想は、主に ACミランが中心となって、欧州の主要クラブによる閉鎖的な大会を設立しようとしたアイデアでした。
これも、欧州サッカーがテレビ放映権料の急騰で「バブル」状態になったことから出てきたアイディアでした。それまでのクラブ経営とは1ケタも2ケタも違う収益を上げ、ビッグクラブといわれる一部のクラブが、その資金で世界のスター選手をかき集め、さらにクラブ経営が潤うというシナリオを実現するために、いわばエリートクラブだけのリーグを作ろうというのです。
折しも欧州連合(EU)では翌年1999年から単一通貨「ユーロ」の導入が決まってします。最初は会計上の通貨として、2002年からは紙幣と硬貨の流通も始まることになってます。プロサッカーの経営においても単一通貨によるメリットは計り知れないものがありますから、こうしたこともスーパーリーグ構想立ち上げの一因となったに違いありません。
この構想は、当時は、欧州サッカー連盟(UEFA)や各国のサッカー協会、さらにはファンや政府から強い批判を受け、実現には至りませんでしたが、その後もくすぶり続け、2000年代に入るとレアル・マドリーのペレス会長が中心となって画策が進みます。その後の成り行きは歴史を知っている方はご存じのことです。
そして、その後の成り行きに導いた最大の功労者は、対象となったビッグクラブを含む世界中のファン、サポーターだったと言われています。誰でも自分のクラブが大きな収入をあげ、世界のスーパースターを獲得することを望んでいる。
けれども、しかしその一方で、他のクラブにも自分と同じ思いのサポーターたちがいて、人生をかけて応援していることを誰よりもよく理解しているのであり、その人たちの思いを犠牲にして自分たちだけがよければいい、という考えに与しなかったからでした。
Jリーグの何年も先をいっている欧州のクラブ経営、将来、プロサッカークラブ経営を目指す若手人材が欧州に経営を学びに旅立つ例が出始める
こうした欧州で起きているプロサッカークラブ経営を取り巻く出来事を見るにつけ、Jリーグが常にお手本にしていかなければならない考え方の基本が横たわっているように思いますし、クラブ経営のあり方も、何年も先を行っていることがわかります。
こうした中で、日本の若手人材の中に、先進的な欧州のサッカークラブ経営を学ぼうとする機運が出始めたのも、この年の特徴といえるかも知れません。
それまで、日本のサッカー界では、プロサッカークラブ経営を含めたスポーツ全般の理論的な知見を涵養していたのは、大学の専門講座が中心で、日本サッカー協会・技術委員会副委員長を務める田嶋幸三氏が筑波大学大学院、日本サッカー協会・前強化委員長の加藤久氏が早稲田大学大学院で、それぞれ学識を積んでいました。ここにきて、将来、Jリーグでクラブ経営に携わってみたいと考える若手人材が、先進的な欧州のサッカークラブ経営を学ぼうとする機運が出始めたのも、この年の特徴といえるかも知れません。
具体的なケースとして、東京・暁星高校時代に冬の全国高校サッカー選手権でFWとして活躍し、その後早稲田大学でも4年時に第40回全日本大学サッカー選手権大会で優勝した経歴を持つ大倉智選手は、柏レイソルに加入、ブラジル代表のカレカ選手とコンビを組み、お互い「師匠」「愛弟子」と呼ぶ間柄で活躍しました。
その後、ジュビロ磐田、ブランメル仙台に移籍、最後はアメリカ・メジャーリーグサッカー(MSL)でもプレーし、1998年9月、29歳の若さで引退しています。
その大倉智氏、1998年から2000年までスペイン・バルセロナにあるの「ヨハン・クライフ大学」でスポーツマネジメントを学ぶことになります。帰国後はC大阪のチーム統括ディレクターを皮切りに、プロサッカーチーム経営の、まさにプロとしてキャリアを重ねていきますが、この大倉氏をはじめ、多くの志ある若手人材が、プロサッカー経営を担うビジネスマンとして欧州に雄飛していったことは、日本にプロサッカーリーグ「Jリーグ」が生まれたからこそ育った新たな人材と言えます。
海外の最先端知識を直接学ぼうとする気運は、クラブ経営の分野にとどまらず、チーム指導、コーチング理論などの面でも高まりを見せました。
この年、横浜フリューゲルスでプロのキャリアをスタートさせ、平塚に移籍、前年1997年限りで現役を引退していた反町康治氏(34)も、この年、FCバルセロナへの留学を始めています。この時はまだグラブ経営のマネジメントを学ぶというより、サッカーのコーチングを学ぶという目的だったようですが、大倉氏も反町氏もバルセロナに学ぶというところが共通していました。
実はバルセロナには、山梨・韮崎高校時代に天才FWとして将来を嘱望されながら、交通事故のため車いす生活を余儀なくされていた羽中田昌氏が、サッカーへの思い断ちがたく指導者の道を目指して1995年から滞在しており、バルセロナはサッカー指導者を志す人々の聖地となりつつあったと言えます。
第18回トヨタカップは、創立100年を飾りたいバスコ・ダ・ガマの切ない願望を、スター軍団レアル・マドリーが打ち砕く
97-98欧州チャンピオンズリーグでレアル・マドリーが優勝、トヨタカップへの出場権を獲得しましたが、一方、南米王者を決定するコパ・リベルタドーレス98は、8月に決勝が行われました。ブラジル、バスコ・ダ・ガマとコロンビアのバルセロナとの対戦、第1戦を2-0と勝利したバスコ・ダ・ガマが第2戦も2-1で勝利、意外にもリベルトダーレス杯初優勝、12月のトヨタカップへの出場権を手にしました。
12月1日に東京の国立競技場で行われた、第18回トヨタカップ(ヨーロッパ/サウスアメリカ カップ)は、欧州王者スペインのレアル・マドリーと南米王者ブラジルのバスコ・ダ・ガマの戦いです。日本にも多くのファンを持つ両チームの試合に51,514人の観客が詰めかけました。
ブラジル、バスコ・ダ・ガマはクラブ創設100周年の年にトヨタカップに出場することになり、そのお祝いも兼ねて2週間前に一行50名で来日しました。
これでトヨタカップ制覇となれば、まさにクラブの歴史は栄光に包まれるはずでしたが、試合はそうはいきませんでした。
欧州チャンピオンズリーグ決勝とほぼ同じメンバーで臨んだワールドスター軍団のレアル・マドリー、この試合でも、その力を発揮しました。前半25分、サイドバックのロベルト・カルロスが攻め上がりから得意の強烈なシュートと放つと、これが相手選手の頭を直撃、ボールはそのまま角度を変えてゴールイン、記録はオウンゴールでしたが鮮やかなロベルト・カルロスの個人技でした。
一度は同点に追いつかれて相手に攻勢を許したレアル・マドリー、今度は後半38分、21歳の若きエース、ラウルが相手DF2人をかわして決勝ゴールを叩き込みました。
レアル・マドリー、欧州制覇は32年ぶりでしたが世界制覇は実に38年ぶりの出来事でした。レアルを指揮したのは、欧州制覇を果たしながらスペインリーグで4位に終わったため解任されたユップ・ハインケス監督の後を引き継いだフース・ヒディング監督。のちに2002年日韓W杯で韓国代表を率いることになる欧州の名将でした。
一方のバスコ・ダ・ガマ、クラブ創設100周年の最後を飾ることができずにシーズンを終えました。バスコ・ダ・ガマに限らず南米の強豪チームは近年、才能豊かな選手たちが次々と欧州各国リーグに流出するという戦力低下に悩まされており、今回も明らかに個々の選手の力の差が出てしまいました。この先のトヨタカップに影を落としそうです。
AFCアジアクラブ選手権、年前半の97-98シーズン参戦の鹿島は、東地区準々決勝リーグで敗退 年後半の98-99シーズン参戦の磐田は、99年2月予定の東地区準々決勝リーグに勝ち上がり、カップ戦には前半ヴ川崎、後半鹿島参戦
1998年、Jリーグ勢がアジアのタイトル争いに参戦した大会として、各国のリーグチャンピオンが参戦するアジアクラブ選手権と、日本では天皇杯覇者が出場権を獲得するアジアカップウィナーズカップ選手権があります。
まず年の前半に97-98シーズンアジアクラブ選手権があり、96年Jリーグ年間王者の鹿島が参戦しました。鹿島は東地区4チームで争う準々決勝リーグに進出しましたが、韓国・浦項、中国・大連と勝ち点6で並びました。得失点差で韓国・浦項が抜け出し1位、鹿島と大連が同じ得失点差3で並んだため総得点の違いとなり、大連が7、鹿島6と、わずか1点の差で2位の座を逃し敗退となりました。
アジアクラブ選手権では、これで4シーズン連続で準々決勝リーグ敗退、この鬼門をいつどのチームが突破できるでしょうか。過去4シーズン連続で準々決勝リーグ敗退となっている日本勢、果たして磐田は突破できるでしょうか。
また同じく年の前半の97-98シーズンアジアカップウィナーズカップ選手権には1997年元旦の第76回天皇杯サッカー選手権で優勝したヴ川崎が参戦しました。ヴ川崎は東地区4チームで争う準々決勝に進出しましたが、中国・北京国安0-3で敗れました。
次に年の後半、98-99シーズンアジアクラブ選手権には97年Jリーグ年間王者の磐田が参戦しました。磐田は東地区の準々決勝リーグ進出を決め1999年2月に予定されている戦いに臨むことになっています。
また同じく年の後半、98-99シーズンアジアカップウィナーズカップ選手権には1998年元旦の第77回天皇杯サッカー選手権で優勝した鹿島が参戦しました。ヴ川崎は東地区4チームで争う準々決勝に進出、1999年に入ってから行われる戦いに臨むことになっています。
1998年、この年の各カテゴリー国内大会
お正月の第76回全国高校サッカーについてはすでにご紹介しましたので、その他の大会をご紹介しておきます。
・第18回全日本女子サッカー選手権大会(1998年1月4日から1月18日)
日本女子サッカーリーグ(L・リーグ)参加10チームと、地域予選を勝ち抜いた10チーム、合計20チームが参加してトーナメント方式で行われました。
準決勝には前回大会と同じ4チームが進出、読売西友ベレーザが鈴与清水FCラブリーレディースを3-0の大差で破ったのに対し、プリマハムFCくノ一は日興證券ドリームレディースをPK戦で破り3大会ぶりに決勝進出しました。決勝戦では読売西友ベレーザが1-0と辛勝し第15回大会以来の3大会ぶりの優勝を果たしました。
・第10回L・リーグ(日本女子サッカーリーグ) (1998年4月から11月まで)
この年も2ステージ制(前期・後期)で実施されましたが、このシーズンはショッキングな出来事が続いた年となりました。
まず、シーズン中にフジタサッカークラブ・マーキュリーがメインスポンサーであるフジタの業績不振により今シーズン限りでの廃部、続いて日興證券女子サッカー部ドリームレディースも、メインスポンサーの日興證券が証券取引法に関する違反などによる業績の悪化により今シーズンかぎりでの廃部を発表しました。
また、シーズン終了後には鈴与清水FCラブリーレディースとシロキFCセレーナが相次いで脱退を表明、6チームに減少したL・リーグは存続の危機と直面することになったのですが。1999年シーズン2チームが参入、継続は保たれることになりました。
このような中、行われたリーグ戦では、前後期通じて無敗、わずか1引き分けだけでシーズンを戦い抜いたシーズンを戦い抜いた日興證券女子サッカー部ドリームレディースが前後期ともに1位となり、3年連続の優勝で「有終の美」を飾りました。
年間総合順位は、1位日興證券女子サッカー部ドリームレディース、2位読売ベレーザ、3位鈴与清水FCラブリーレディースの順となりました。
個人タイトルは次のとおりでした。最優秀選手には日興證券のアグネッテ・カールセン選手が、新人王には鈴与清水の津波古友美子が選ばれました。得点王は21得点をあげた鈴与清水の泉美幸選手。アシスト王は15アシストの読売の澤穂希選手。
【ベストイレブン】
GK:西貝尚子選手(日興證券)
DF:大部由美選手(日興證券)、酒井與恵選手(読売)、仁科賀恵選手(プリマハム)、埴田真紀選手(松下電器)
MF:アグネッテ・カールセン選手(日興證券)、澤穂希選手(読売)、高倉麻子選手(読売)
FW:泉美幸選手(鈴与清水)、大松真由美選手(日興證券)、パレホ選手(宝塚)
Jリーグの横浜フリューゲルス合併・消滅などがあったサッカー界、厳しい経済環境が女子サッカーも直撃して、女子サッカー全体の関心低下、それによる女子選手の裾野がしぼんでいく懸念が増した年でした。
・第3回全日本フットサル選手権(1998/1/23(金)~1998/1/25(日))
第3回目を迎えた「全日本フットサル選手権」、東京・有明コロシアムで開催された今大会の決勝は、関西代表、滋賀県のルネス学園甲賀フットサルクラブと、関東第一代表、山梨県のAzulの争いとなり6-1でがルネス学園甲賀フットサルクラブ圧勝、第1回大会に続く2度目の優勝を果たしました。
・デンソーカップ大学選抜サッカー 日本大学選抜vs韓国大学選抜(0-1)
前年から2002年日韓W杯決定を記念して、韓国大学選抜を招待する形で始まったデンソーカップ大学選抜サッカー、この年は会場を東京・国立競技場に移して4月12日開催されました。
試合は、韓国大学選抜が1-0で日本大学選抜を下し前年の雪辱を果たしました。
・第22回総理大臣杯大学サッカートーナメント決勝 早稲田大vs青山学院大(3-1) 優勝 早稲田大
・第47回全日本大学サッカー選手権 決勝 国士館大vs福岡大(2-1) 優勝 国士館大
11月14日から11月23日の日程で、9地域の代表15校と総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント優勝校・早稲田大が参加して行われました。
準決勝には関東大学リーグの2校、国士館大、明治大と、東北代表・仙台大と九州代表・福岡大が進出、国士館vs明治大の関東勢対決は、国士館が2-1で競り勝ち、仙台大vs福岡大は、福岡大が2-0、決勝進出を果たしました。
国士館大vs福岡大の決勝は、国士館が昨年逸した王座を奪還するか、福岡大が初制覇を果たすか注目されましたが、試合は後半福岡大が先制したものの国士館が逆転、2-1で2年ぶり3回目の優勝を果たしました。
この年の各大学主な選手とその進路
・国士館大 MF熱田眞⇒京都、MF金沢浄(4年)
・福岡大 FW黒部光明(3年)、DF坪井慶介(1年)
・明治大 MF宮澤克行⇒浦和
・平成10年度インターハイ(高校総体)サッカー決勝 市立船橋vs岐阜工(2-1) 優勝 市立船橋
・第9回高円宮杯全日本ユース(U-18)サッカー選手権決勝 藤枝東vsG大阪ユース(3-2) 優勝 藤枝東、この年は大黒将志選手や二川孝広選手ら、のちにG大阪の主力として活躍する選手を擁すガンバ大阪ユースが準優勝ながら高いパフォーマンスを見せ注目され、クラブ勢の台頭を予感させる年となったことが特徴でした。
・第6回Jユースカップサッカー選手権決勝 鹿島ユースvs市原ユース(3-2) 優勝 鹿島ユース。この年の鹿島ユースは2年生の野沢拓也選手とと根本裕一選手が牽引、優勝の原動力となりました。
・第7回全国女子高校サッカー 決勝 宮城・聖和学園vs鹿児島・神村学園(0-0PK4-2) 優勝 聖和学園(2回目)
・ 第10回全日本ジュニアユース選手権 決勝 清水ジュニアユースvs市原ジュニアユース(1-1PK7-6) 優勝 清水ジュニアユース(初)
・第3回全日本女子ジュニアユースサッカー(U-15)選手権 決勝 横須賀シーガルズFCvs静岡県選抜 優勝 横須賀シーガルズFC
・ 第22回全日本少年サッカー大会 決勝 静岡・浜松JFCvs福岡・小倉南ジュニア(0-0) 両チーム優勝 浜松JFC(2回目)、小倉南ジュニア(初)
テレビ、スポーツ紙、雑誌系いずれのメディアも年の前半はカズ・三浦知良選手の落選を含む「フランスワールドカップ」関係、後半は中田英寿選手のセリエA挑戦の報道、年末にかけては横浜Fの消滅問題が中心に、くっきりと分かれた年でした
前年1997年は、特に後半になって日本がフランスワールドカップアジア最終予選を戦ったことで、日本中のサッカーに対する関心が、かつてなく高まりました。
テレビ、スポーツ紙、雑誌系いずれのメディアも、こぞってフランスワールドカップアジア最終予選を報じました。
今年は、年の初めからワールドカップイヤーの盛り上がり、Jリーグも含めてすべてワールドカップに関連付けて報じられるといった具合で、その過程でカズ・三浦知良選手の落選という問題が社会的に大きな関心を集めました。
日本のプロサッカー界が生んだ最初のスーパースター選手ですから無理もありません。テレビもスポーツ紙も雑誌系メディアも、ハチの巣をつついたような喧噪になり、落選を決めた岡田監督に対するバッシングは、ご自宅に警察の警備がつくほどでした。
その騒ぎが収まる間もなく日本代表の3試合、そこには手に入らないチケット問題も絡み、落ち着かない雰囲気のまま史上初めてのワールドカップへの挑戦というクライマックスがやってきました。
それもつかの間、6月中旬に、日本代表が3戦全敗でグループリーグ敗退に終わると、いずれのメディアもサァーッと汐が引くようにワールドカップの話題から遠ざかりました。
そのあとメディアが関心を持って追ったのが、中田英寿選手のイタリアリーグ移籍のニュースです。21歳の若さで世界最高峰のサッカーリーグに挑戦する話題は、それだけでも大きなインパクトでしたが、9月にデビュー戦でいきなり2ゴールをあげる鮮やかなスタートを切った中田英寿選手に対する日本のメディアの見る目がガラリ変わったとも言えます。
日本でプレーしていた中田選手は、いくつかの不幸な出来事が重なり、すっかりマスコミ不信に陥り、メディアのほうも厳しい視線を向ける関係になってしまい、それも海外に移籍する大きな理由の一つになりました。
その中田選手が、文句のつけようのない活躍を見せたのですから、日本のメディアは、中田選手に向ける視線を少し穏やかにせざるを得なくなりました。
そのかわりということになりますが、中田選手は今度は、イタリアメディアの、厳しいというより辛辣な論調と戦わなければならなくなりそうです。
イタリアのメディアの場合、調子があがらない選手に対するバッシングは、日本のメディアとは比べものにならないほど短いインターバル、極端に言えば1試合1試合ごとに激しくきますから、スター選手しかも責任を押し付けられやすい外国人選手の中田選手は、大変なところで戦っているということになります。
日本では秋が深まった頃、横浜フリューゲルスの合併・消滅問題が突然降って湧き、社会問題になるほどメディアの注目が集まりました。
おりから、日本経済のさまざまな問題が表面化して、世の中のどこもかしこもリストラ、経費節減の大合唱の中、まさに世相を象徴するような出来事が勃発したのですから、注目があつまるのも当然です。
その中で、特に選手、ファン・サポーターの知らないうちに物事が決まってしまった現実に対して、必死に抵抗を試みる選手、ファン・サポーターたちの行動が連日メディアを賑わせました。日本サッカー界がこれまで経験したことのない様相であり、歴史に刻まれる姿になりました。最後は、チーム横浜フリューゲルスが、合併・消滅発覚後の公式戦を一度も負けることなく1999年元旦の天皇杯優勝をもって消滅の日を迎えるというドラマでもなかなか描けない筋書きでエンディングでしたから、これを「伝説」と呼ばずして何と呼びましょう。
そして、最後に、チームのリストラ策の対象となって、やむなく日本を去ることになった鹿島のジョルジーニョ選手が、まるで日本サッカー界に置き土産を残すかのように、思いのたけをインタビューを通じて語りました。
そこには日本のサッカーがメディアから大きく扱ってもらえていない現状を次のように憂いている様子がありました。
「マスメディア、とくにテレビがもっとサッカーを取り上げるべきだ。そのためには何らかの契約や取引が必要かも知れない。サッカーの番組を増やして盛り上げていかないとダメだ。これはとても大切なことだよ。世界中どこでもテレビはサッカーを育てる肥やしになっている。日本だけが違うという理由はない。」
「でも本当にガッカリしたことは、ボクも他の外国人選手も日本ではインタビューや記事の対象となっていないことだ。日本人選手がゴールをあげたり、ちょっとよいプレーをするとマスコミはその日本人選手を追いかけ、われわれには目もくれようとしない。まるで日本のマスコミは新しいヒーローを必死で探しているようだね。こうした状況は、日本のサッカーにとってよいこととは言えないな。」
ちょうど1年前のこの欄で「1997年はスポーツの中でサッカーが話題の中心に躍り出た元年とも言えますし、社会全体の中でもニュースバリューが飛躍的に高まった年でもあります。」と書きました。そして、
「翌1998年は、いよいよフランスW杯に日本が出場することを考えれば、もっと扱い量が増えることになるでしょう。とうとう、こんな日が来たのだと感慨を覚えます。」と結びました。
しかし、それは、本場ブラジルや欧州のサッカーに対する関心度から見れば、まだまだ子供のレベルなのかも知れません。
中田英寿選手がイタリアで今後体験するであろうサッカーに対する注目度の違いから来るケタ違いのバッシングは、ジョルジーニョ選手の言う「サッカーを育てる肥やし」の一つなのかも知れません。
その意味で、フランスワールドカップ敗北の戦犯の一人としてバッシングを受け、帰国した成田空港で清涼飲料水の洗礼を浴びた城彰二選手のことも「サッカーを育てる肥やし」の一つだったのかも知れません。
勝利によって手にする歓喜の大きさは、フランスが優勝によって得たシャンゼリゼ通りの150万人もの人出を見れば、いかに壮大なものかわかりますが、敗戦によって叩かれるバッシングの凄さが、どれほど過酷なものになるのか・・・。
メディアが「サッカーを育てる肥やし」になるのも確かですが、それはコインの表にもなり裏にもなるということを感じざるを得ません。
【テレビ】
この年のテレビ放送の大きなトピックは、NHKによるフランスワールドカップ全試合放送体制が敷かれたことです。
実はNHK、1978年アルゼンチン大会から連続6大会の放送権を獲得していて、この年のフランスワールドカップが最後の6大会目でした。前回1994年のアメリカ大会から全試合放送体制を敷きましたが、今大会大きく異なるのは1つが試合数の増加、前回は48試合でしたが今回は64試合です。もう1つは、我が日本代表の初参加です。
これによりNHKはスポーツ部門総動員はもとより他の部門からも応援を受けての放送体制を組みました。
その結果、私たちサッカーファンは、中心となったBS放送はもとより地上波でも試合・関連番組を含めて、6~7月にかけて大量のフランスワールドカップ情報に接することとなりました。
番組系の個別内容はこのあとご紹介しますが、そのあおりを食った形になったのが、NHK-BSで毎週1回定期放送を行なっていた「BSサッカーダイジェスト」が放送されなくなりました。1993年に始まった「BS Jリーグダイジェスト」以来続いてきた定期番組、しかも時間枠が50分、60分といった豪華版でしたから再開が待ち望まれます。
また、この年から、NHK-衛星BS放送での一部試合放映に加えて、衛星CS放送でのJリーグ放映が、ジュピターテレコム運営「J-SPORTS」に完全移行しました。
ジュピターテレコムは、前年から放映権を取得していたものの、その1997年はCSN1ムービーチャンネル(現ムービープラス)の枠内で「CSN1 J-SPORTS」として各節1試合生中継、他の試合の一部をGAORAやスカイ・Aなどで中継しただけでした。
今年1998年は、J-SPORTSで各節1試合生中継。同年9月には、新規開局の「ディレクTV(サッカーTV・イレブン)」にサブライセンスして、シーズン途中からではありましたが、4年ぶりにJリーグ全試合カバーが復活しました。(「ディレクTV」での全試合カバーは1999年で終了)
【ワールドカップイヤー&トルシエ新体制日本代表応援テレビ特番】
1年を通してフランスワールドカップに出場する日本代表を応援し、ワールドカップ大会の熱狂を伝えるテレビ特番が組まれました。そしてトルシエ新体制となった日本代表関連番組も含めて記録しておきます。
特にNHKが、3月以降はBSで「W杯情報がんばれフランス大会」を毎週放映して、大会が始まってからは日本代表を中心に、日本代表がグループリーグ敗退に終わってからは全体の模様を7月下旬まで続けました。
この密度を見れば、前年まで放映していた週1回の定期サッカー番組「BSサッカーダイジェスト」は休まざるを得ないことがよくわかります。
98-1.1 元旦いきいきワイド・W杯ニッポン応援企画(NHK45’27)
98-1.30朝日ニュースター岡田監督独占インタビュー(CS朝日1H56’55)
98-3.1 W杯特集がんばれフランス大会(NHK-BS58’03)
98-3.1 ダイナスティカップ日韓戦直前SP(NHK-BS50’00)
98-3.8 W杯特集がんばれフランス大会(NHK-BS2H57’49)
98-3.15W杯情報がんばれフランス大会・ゲスト中西永輔(NHK-BS58’24)
98-3.22W杯特集がんばれフランス大会・Jリーグ開幕(NHK-BS59’00)
98-3.29W杯特集がんばれフランス大会・ゲスト北澤豪(NHK-BS1H00’00)
98-4.5 W杯特集がんばれフランス大会(NHK-BS59’01)
98-4.12W杯特集がんばれフランス大会(NHK-BS2H59’05)
98-4.19W杯特集がんばれフランス大会・ゲスト加茂周(NHK-BS59’00)
98-4.19W杯特集がんばれ日本・代表初選出3人(NHK-BS10’30)
98-4.26W杯特集がんばれフランス大会(NHK-BS59’00)
98-5.10W杯特集がんばれフランス大会・ゲスト女子代表2人(NHK-BS1H00’00)
98-5.10W杯日本代表がんばれ緊急特番(日テレ52’43)
98-5.24W杯特集がんばれフランス大会・H組対戦相手傾向と対策(NHK-BS1H57’48)
98-5.30W杯特集がんばれフランス大会(NHK-BS2H00’00)
98-6.9 日本サッカーW杯への軌跡、代表ゴールの歴史他(テレ東1H52’00)
98-6.10フランスW杯開幕直前特番(NHK-BS1H07’58)
98-6.13土曜特集「がんばれ日本代表初勝利をめざして」(NHK1H13’43)
98-6.14フランスW杯グループリーグH日本vsアルゼンチン戦終了特番(NHK総合34’40)
98-6.14フランスW杯グループリーグH日本vsアルゼンチン戦直前特番(NHK-BS52’09)
98-6.20フランスW杯グループリーグH日本vsクロアチア戦直前特番(NHK-BS32’00)
98-6.20フランスW杯緊急SP「悲願の1勝のために」(TBS1H51’02)
98-6.20頼むぞ日本サッカー、クロアチア戦直前特番W杯現地の舞台裏(テレ朝59’04)
98-6.26フランスW杯グループリーグH日本vsジャマイカ戦直前・直後特番(NHK総合49’12)
98-6.26フランスW杯日本代表とことん応援するぞ、ジャマイカ戦直前SP(日テレ1H23’10)
98-6.28フランスW杯グループリーグハイライト・日本代表かく戦えり(NHK-BS2H19’50)
98-6.29フランスW杯総集編①激闘の一次リーグ(NHK-BS1H50’00)
98-6.29フランスW杯日本代表、炎のダイジェスト(フジ54’50)
98-7.1 フランスW杯決勝T1回戦ハイライト(テレ朝54’15)
98-7.5 フランスW杯準々決勝ハイライト②(NHK-BS1H58’07)
98-7.14フランスW杯決勝トーナメントハイライト(NHK-BS1H49’30)
98-7.15フランスW杯スペシャル完結編・中田英寿生出演(TBS1H46’59)
98-7.17フランスW杯総集編「夢の軌跡・世界が燃えた33日間」(NHK1H15’00)
98-7.18フランスW杯感動名場面①ゴール、ゴール、ゴール(NHK-BS9’18)
98-7.18フランスW杯感動名場面②スーパースターの輝き(NHK-BS30’00)
98-7.19フランスW杯感動名場面③日本代表の270分(NHK-BS35’00)
98-7.19フランスW杯感動名場面④燃えたJリーガー(NHK-BS30’00)
98-7.19フランスW杯総集編、20世紀最後の闘い(テレ東1H21’35)
98-7.20フランスW杯感動名場面⑤アジア・アフリカの憂うつ(NHK-BS34’57)
98-7.21フランスW杯感動名場面⑥運命の瞬間(NHK-BS30’00)
98-7.22フランスW杯感動名場面⑦守護神列伝(NHK-BS35’00)
98-7.22フランスW杯感動名場面⑧ベテランとニューパワー(NHK-BS29’54)
98-8.15サッカー日本代表「徹底検証」①ドキュメンタリー日本代表の270分(NHK-BS2H00’00)
98-8.16サッカー日本代表「徹底検証」②徹底討論(NHK-BS1H59’42)
98-11.29アジア大会サッカー特集5回分(NHK-BS1H10’10)
98-12.26スポーツ98サッカー編「夢の舞台で戦った」(NHK31’48)
99-1.5 98フランスW杯ドュキュメンタリー「トリコロールたちとの日々」(NHK-BS1H40’00)
【サッカー専門定期放送番組】
・TBS 毎週1回 スーパーサッカー 30分 生島ヒロシ、三井ゆり⇒98 年9月卒業
全国ネットのサッカー専門定期番組が少なくなっていく中、コアな視聴者を掴み、順調に放送を続けているのがTBSスーパーサッカーです。
専門知識に深入りしすぎず、さりとてバラエティ系にも偏り過ぎず、司会の生島ヒロシさんのテンポよい進行に、三井ゆりさん、TBSアナの清水大輔さん、そして解説の水沼貴史さんたちがバランスよく絡み、さらには選手ゲストや各チームを訪問して行なう俺キンコンテストなど、いろいろな楽しみがあるところが秘訣なのかも知れません。
1998年は通算300回台をめざして継続中のところ、上半期終了時点で大きなメンバー変更がありました。1994年10月から丸4年サブキャスターを務めた三井ゆりさんが卒業したのです。そして白石美帆さんにバトンタッチされました。またTBSから出演していた清水大輔アナウンサーも卒業、土井敏之アナウンサーにバトンタッチされました。
若手選手にとっては、この番組に呼ばれれば全国区の選手に近づいた証しとも言える価値があり、この年1月最初の放送に呼ばれた鹿島・柳沢敦選手と中村俊輔選手は、スーツをビシッと決めて、やや緊張気味に番組に登場したのが、それを物語っているようでした。
・テレビ東京 サッカーTV 30分 久保田光彦、川平慈英
テレビ東京といえば伝説の「ダイヤモンドサッカー」という番組ですが、昨年4月から後継番組のような形で「サッカーTV」がスタートしました。東京・銀座ソニービルにあるテレビ東京のステライトスタジオでの公開放送を多用して、ゲストとともに久保田アナ、川平氏がトークを繰り広げるというスタイルでした。
今年はワールドカップイヤーですから、ワールドカップ出場国そして日本体表の話題が中心となりました。
・テレビ東京 ナンバー12・熱血サッカー宣言 30分 清水圭、さとう珠緒
ワールドカップイヤーに合わせて4月から新番組が始まりました。すでに「サッカーTV」をオンエアしているテレビ東京が、もう1本追加するということは、伝統的に繋がりが深い日本サッカー協会との兼ね合いだったのかも知れません。
「サッカーTV」と違って、番組タイトルに「サポーターの、サポーターによる、サポーターのための」というナレーションがかぶっているように、フランスワールドカップに初出場の日本代表を応援する番組という明確なコンセプト、こちらはグッとバラエティ色の強い番組作りで、毎回きっちりとJリーガーゲストを招いていることも特徴です。
サッカー大好き芸人の清水圭さんに、サッカー音痴プラス天然ボケのさとう珠緒さんが絡みますから、吉本の漫才コンビのような掛け合い、それにテレビ東京の佐々木明子アナ、佐々木アナが不在の時は家森幸子アナが絡んで番組が進行していました。
【単発ドキュメンター系・カルチャー系番組】
98-1.8青春探検・植田朝日(NHK22’30)
ご存じ、サッカー日本代表サポーター集団「ウルトラス」を束ねる植田朝日さん、当時24歳、フランスワールドカップの舞台に立つ日本代表をどう応援するのだろうか。東京・千駄ヶ谷にある彼の店であるサポーターグッズ店をたずねた。
500人ぐらいの仲間からスタートしたウルトラス、昨年のワールドカップアジア最終予選の時は10000人もの輪になった。そんな大きな集団を率いる植田さんのあゆみと、フランスワールドカップへの思いを聞いた。
98-2.22ホリデー日本・20歳プロサッカーへの挑戦(NHK福岡34’59)
昨年10月、日本がマレーシアの地でフランスワールドカップを決めて沸く中、Jリーガーを目指して人知れず挑戦を続ける若者たちがいた。Jリーグの下のカテゴリー、ジャパンフットボールリーグ(JFL)に所属するモンテディオ山形の入団テストに約121人もの若者が集まったのだ。そこに遠く九州から参加した2人の若者がいる。岡山洋幸くん(19)、末森研一くん(19)、九州に初めて誕生した全九州サッカー専門学院でプロをめざしている。
NHK福岡局制作のドキュメンタリー。
98-3.10クローズアップ現代・岡田ジャパンの現在地、ゲスト、アルディレス(NHK28’40)
98-3.22ヒーローたちが泣いた日・中山雅史(日テレ18’28)
98-4.10巨大ビジネス「サッカー」①にらみを利かすサッカー連盟(NHK-BS48’43)
1997年オランダ・ゼヘルスTV制作のドキュメンタリー。欧州チャンピオンズリーグを仕切るUEFA(欧州サッカー連盟)の取り組みに密着、各サッカークラブ、テレビ、スポンサーからなる強固な利益創出トライアングルをいかに作り上げ、巨大ビジネスに成長させたか、UEFAの代理人となって、そのビジネスモデルの維持に奔走するスポーツプロモーション会社への取材から追った。
98-4.11巨大ビジネス「サッカー」②企業の戦略(NHK-BS48’59)
1997年オランダ・ゼヘルスTV制作のドキュメンタリー2夜目。ブラジル代表のメインスポンサーとなって「ブラジルワールドツァー」を企画・敢行したアメリカ・ナイキ社、この巨大スポーツ用品メーカーはどんな戦略のもとに、これを企画・敢行したのかを追った。
98-5.3いざフランスへ、柳沢敦の挑戦(富山・北日本放送53’50)
富山が生んだ日本代表の若きストライカー・柳沢敦選手、この才能あふれる若者はどう作られたのか、ヤナギファンにはたまらない秘蔵映像を交えた富山のテレビ局・北日本放送制作のドキュメンタリー。
98-5.4ワールドカップ10憶人の祝祭イングランド、ドイツを行く(NHK-BS1H40’00)
98-5.17Gスポーツ・特集呂比須ワグナー(テレ朝33’20)
4月からスタートしたスポーツドキュメンタリー。スポーツ総合誌として定着している「スポーツグラフィックNumber」誌のテレビ版を意識したかのような番組づくり。当初は関東地区だけのローカル放送からスタート、プロ野球、ゴルフといった他のプロスポーツと並んで、この年の大きなスポーツイベント、フランスワールドカップに出場する日本代表にスポットをあてた企画が増加。
今回は熾烈なFW枠争いの真っ只中にいる呂比須ワグナー選手を特集、中田英寿選手との連携についての本音や、ブラジルから来日してからのキャリアを紹介。
98-5.18クローズアップ現代・W杯企画①アルゼンチン(NHK29’00)
98-5.19クローズアップ現代・W杯企画②クロアチア(NHK29’07)
98-5.20クローズアップ現代・W杯企画③ジャマイカ(NHK29’07)
98-5.28「いま夢のW杯へ、小野、市川10代の挑戦」(静岡第一TV53’15)
フランスワールドカップメンバー25人の中に小野伸二選手、市川大祐選手という2人の10歳台の選手が入ったことは、サッカー王国・静岡ならでは。最終的に市川選手は外れて帯同メンバーという形にはなったものの、地元・静岡が特番を組むのは当然といえば当然のこと。静岡の他局が類似の番組を企画したかどうかは確認できないが手元にあるのは、日本テレビ系列の静岡第一TVのドキュメンタリー。
98-6.7Getスポーツ、カズ、川口能活(テレ朝38’58) スタジオトーク、セルジオ越後氏、金子達仁氏、角澤照治アナウンサー
6月2日スイス・ニヨンで発表されたカズ・三浦知良選手の落選についてセルジオ氏、金子氏がそれぞれ見解を語った。この部分については、すでに「カズ・三浦知良選手の落選」の項目でも引用している。
一方、日本代表不動のレギュラーGKであるはずの川口能活選手が揺れた3月ダイナスティカップでのプレーを振り返りながら、どう立て直してきたかを金子氏が深掘り、スポーツ総合誌Number紙を読むような感覚になる。
98-6.7魂のゴールキンター・中山雅史(SBS43’50) ナレーション渡辺篤史
収録日が 98-6.7となっているが、放送そのものは、ワールドカップメンバーが25人からスイス・ニヨンの地で22人に絞られた98年6月2日以前に放送されている内容。正確な放送日は不明。静岡第一TVが小野伸二、市川大祐選手の特番で、静岡放送(SBS)TVが中山雅史選手なのかも。
中山雅史選手と親交のあるミュージシャン中西圭三さんとのトークはレアもの?。
98-6.7報道特集・ストイコビッチ世界への復活(TBS23’30)
98-6.21キラリ・松永成立のフランスW杯(ABC朝日放送25’57)プレゼンター中村雅俊、ナレーション窪田等
日本が初めてワールドカップの舞台に立った6月14日アルゼンチン戦、その日をドーハ戦士の一人である京都・松永成立選手はどのような思いで迎えたか。彼の辿ったサッカー人生と彼を取り巻く人々の証言を交えながら、彼に聞いた。
98-6.22クローズアップ現代・W杯チケット暗躍するブローカー(NHK総合29’00)
98-8.15サッカー日本代表「徹底検証」①ドキュメンタリー日本代表苦闘の270分「日本代表かく戦えり」(NHK-BS2H00’00) オープニング&エンディングナレーション・古谷徹、アルゼンチン戦ナレーション・真中了、クロアチア戦ナレーション・大野勢太郎、ジャマイカ戦ナレーション・古谷徹
フランスワールドカップ、グループリーグ敗退に終わった日本代表の試合を振り返りながら検証する2夜連続企画の1日目は、番組全体を通して各試合の総括的なコメントを担当したジーコの話から始まり、各試合のポイントとなったシチュエーションでは関わった選手の思いに迫り、また相手チームの監督・選手にも丹念に取材して検証した番組。番組中に試合データから攻撃・守備の状況検証、今大会で大きく成長した中西永輔選手のクローズアップがある。
エンディングのナレーション。「フランスの3つの都市を駆け巡った13日間、日本代表の270分の戦いは終わった。駆け引き、創造力そして執念、周到な戦術と技術でさえ補うことができないさまざまな要素、これから日本代表は、課題を一つづつ克服していく。それは決して難しいことではない。彼らにとって失ったものなど何もないのだから。」
98-8.16サッカー日本代表「徹底検証」②徹底討論(NHK-BS1H59’42) 司会・進行、山本浩アナ、勝恵子アナ
フランスワールドカップ、グループリーグ敗退に終わった日本代表の試合を振り返りながら検証する2夜連続企画の2日目は、サッカー界の専門家がスタジオに集結「進化せよ、日本サッカー」と銘打って討論を行なった。
・冒頭メッセージ 日本サッカー協会新会長 岡野俊一郎氏
・ゲストによる私の主張(約20分)、①NHK解説者・早野宏史氏、②磐田ベッドコーチ・山本昌邦氏、③ヴ川崎テクニカルコーチ・松永英機氏、④元市原・リトバルスキー氏
・上記4氏による討論、テーマ(1)得点力、テーマ(2)1対1、テーマ(3)国際経験(ジーコ氏、ジャマイカ・シモンエス監督、両氏からも意見)
・日韓レジェンドスペシャル対談 木村和司氏×チェ・スンホ氏
・続・討論、テーマ(4)若手育成
・期待の若手紹介コーナーGK、DF、MF、FW(約25分)
98-8.23きらり・小野と市川、18歳のW杯(ABC朝日放送27’00)プレゼンター中村雅俊、ナレーション窪田等
日本が戦った初めてのワールドカップ、そこにいた2人の18歳、希望の光と言ってもいい小野伸二選手と市川大祐選手、彼らが2002年に向けて学んだもの、そして感じたものとは何だったのか。
98-10.17未来潮流「サツカーに学ぶ日本型システムの未来」(NHK教育1H14’00)ナレーション、ジョン・カビラ、・出演 進行役・セルジオ越後氏、コラムニスト・山崎浩一氏、作家・馳星周氏、文化人類学者・今福龍太氏
すでに、フランスワールドカップ日本代表の敗因について考える項目でもご紹介した番組、
・1st討論テーマ 日本はなぜ勝てなかったのか、W杯に見た日本型システムの壁
ここでの議論は、さる98.6.8 TBS新サンデーモーニングで議論された「『カズ落選』は日本型企業社会が「サッカー型企業社会」に変化していく先駆けか」で議論された視点と非常に相通じるところがあります。
新サンデーモーニングの議論が、今後の日本の経営において必要となってくる「経営判断のスピードと、瞬時の的確な判断力」の重要性を示唆していて、今後、ますます「サッカー型企業社会」に変化していくであろうという予測の例として扱われていますが、今回の議論では、日本代表が一つも勝てなかったのは、指揮官の決断の遅さや、選手一人ひとりが自主的に判断するというメンタリティに欠けていたためで、これは、これまでの日本型企業社会あるいは日本という国に共通した組織の欠点に起因していると指摘されています。
・Half time 4人が選ぶ「フランス大会ベストプレー」
【セルジオ越後氏が選んだベストプレー】決勝T1回戦アルゼンチンvsイングランド戦に飛び出したイングランドの18歳マイケル・オーウェンのドリブルシュート。
【馳星周氏が選んだベストプレー】準々決勝アルゼンチンvsオランダ戦、試合終了1分前に見せたオランダ・ベルカンプの超絶トラップからのゴール。
【今福龍太氏が選んだベストプレー】コロンビアの36歳司令塔バルデラマの必殺スルーパス。
【山崎浩一氏が選んだベストプレー】準々決勝イタリアvsフランス戦で見せたフランス、エマニュエル・プティ選手のフェアプレー。
・2nd討論テーマ W杯に見た激動する世界
ここでの議論は、W杯のプレーあるいはW杯という舞台の中に、現代世界を映し出しているところがあるという視点にたった議論。
一つは「サッカーの世界では、いち早く人材の流動化が進んでいて、才能ある選手が一つの国の中だけでプレーする時代ではなく、世界資本主義といってもいいような経済原理の中で、幾つかの裕福なクラブに寡占化されている。これが今後どうなっていくのか注目したい」という指摘が一つ。
もう一つは開催国フランスの優勝に、現在の世界の縮図のような姿が見られたという指摘です。それは、かつて移民問題に悩まされて取り締まりを強めていたはずのフランスが、代表選手を構成する多くのルーツを持つ多民族チームのような選手たちの活躍によって優勝を勝ち取った。フランスはこの出来事を、自国のナショナリズムの強化に利用しようとすらしているという指摘。
つまり日本もいずれそうなっていくに違いない趨勢の中、多くの国が、移民などにより多民族社会化していく中で、かつて単一民族社会をベースにして唱えてきたナショナリズムの高揚を、多民族で構成された代表チームの快挙を利用してナショナリズムの高揚に結び付けようという思惑が働いていることを目の当たりにした。
ワールドカップという舞台は、そういう「現代世界の縮図」をも映し出す舞台だという。
98-11.22セルジオが行く欧州サッカー紀行98・イングランド(テレ朝53’54)
98-11.24クローズアップ現代「転機を迎えたJリーグ」キャスター・国谷裕子、ゲスト・スポーツ評論家玉木正之氏(NHK29’19)
横浜マリノスとの合併により消滅することになった横浜フリューゲルス問題と、地元行政からの支援継続が瀬戸際にきたアビスパ福岡の状況について取り上げた。
このうちアビスパ福岡は、福岡市が5億円を出資しているが今年初め、経営難から追加出資と無担保融資を行なうこととして2月議会に提案したが「民間企業の支援に税金を使うのはどうなのか」「プロスポーツになぜ行政が支援するのか」といった意見が相次いだ。市は「地域のスポーツ文化発展のために必要」と説明して理解を得たが、秋にはアピスパJ2降格という危機が襲ってきた。もし降格となればクラブ経営は再び危機的な状況に陥る中、果たして危機を脱することはできるのか。
98-11.30特報首都圏・横浜F問題(NHKローカル28’00)
98-12.6Gスポーツ・U-21、市原武田修宏、中村俊輔ほか(テレ朝41’26)
98-12.20Gスポーツ・決定力不足ゴンが救う(テレ朝13’30)
【単発バラエティ系・ワイドショー系番組の主な番組】
さすがにワールドカップイヤーだけに、単発番組でも出演者などを変えて1年を通して何度もオンエアされた番組も多くなりました。来年になるとすぐしぼんでしまうとは思えない、その膨らみ具合を記録しておきます。
特にその中でも放送回数の多かった「TBS筋肉番付」「日テレとんねるずの生でダラダラいかせて」は抜き出してご紹介、その他を一括ご紹介します。
【筋肉番付】TBS 進行古舘伊知郎、中山エミリ、峰竜太、ナレーション朝岡聡
98-2.7筋肉番付・キックターゲット、ラモス、木村和司他(TBS19’03)
98-3.7筋肉番付・キックターゲット城、俊輔初登場(TBS7’30).mpg
98-3.14筋肉番付・キックターゲット・ストイコビッチパーフェクト(TBS18’00)
98-4.11筋肉番付・キックターゲット・秋田、柳沢他(TBS11’07)
98-4.25筋肉番付・キックターゲット・松波、永島、服部浩紀(TBS12’20)
98-5.16筋肉番付・キックターゲット、一般参加(TBS13’11)
98-5.16筋肉番付・キックターゲット、高木琢也、岡山哲也パーフェクト(TBS12’21)
98-5.30筋肉番付キックターゲット、城、相馬、ガジャルド(TBS24’35)
98-6.13筋肉番付・キックターゲット、アルゼンチン少年パーフェクト(TBS13’56)
98-6.20筋肉番付・キックターゲット日本代表総力プレーバック特集(TBS25’50)
98-6.27筋肉番付・キックターゲット、海外プレーバック(TBS16’40)
98-7.3筋肉番付・キックターゲット、レオナルド、ドゥンガプレーバック(TBS19’00)
98-7.11筋肉番付・キックターゲット、森島ほか(TBS18’00)
98-7.18筋肉番付・キックターゲット、平野、望月PF(TBS17’59)
98-7.25筋肉番付・キックターゲット、岡野、小野伸二他(TBS17’14)
98-9.26筋肉番付・キックターゲット、西野監督、加藤望Wパーフェクト(TBS9’44)
98-10.17筋肉番付・キックターゲット、バッジョ他(TBS20’24)
98-10.24筋肉番付・キックターゲット、ジダン、デルピエロパーフェクト(TBS14’30)
98-10.31筋肉番付・キックターゲット、ロナウド(TBS9’30)
98-11.29筋肉番付・キックターゲットランキング(TBS11’30)
98-12.5筋肉番付・キックターゲットⅡ奥・中山(TBS11’52)
98-12.12筋肉番付・新企画ゲームメーカー・一般参加(TBS9’50)
98-12.26筋肉番付年末SP Jリーグチーム対抗戦(TBS35’37)
とんねるずの生でダラダラいかせて 日テレ、木梨憲武
98-3.4とんねるずの生ダラ・ウルトラスと日韓戦応援(日テレ16’40)
98-3.25とんねるずの生ダラPK戦・エムボマ(日テレ38’55)
98-4.15とんねるずの生ダラPK戦レオナルド(日テレ47’41)
98-5.6とんねるずの生ダラPK戦・ボバン(日テレ26’33)
98-5.27とんねるずの生ダラPK戦、デル・ピエロ、ペルッツィ(日テレ50’30)
98-6.17とんねるずの生ダラ・W杯速報、ゲスト・ラモス(日テレ46’13)
98-7.1とんねるずの生ダラPK戦・ジダン、ゲスト、ラモス(日テレ28’40)
【その他バラエティ系・ワイドショー系】
98-1.1元旦いきいきワイド・W杯ニッポン応援企画(NHK45’27)
98-1.1平成あっぱれTV・PK合戦(日テレ24’50)
98-1.2スポーツマンNo.1決定戦(TBS31’40)
98-1.2新春ビッグ放談・岡田、王(ABC朝日26’35)
98-1.4おめでとう日本代表W杯元年(テレ朝40’10)
98-1.5スタジオパーク・ゲスト中山雅史(NHK45’45)
98-1.8真夜中の王国・中山雅史(NHK-BS15’55)
98-1.10 97年間視聴率ランキング・中山雅史(日テレ6’00)
98-1.18平成だんとつキング・柏、大野、棚田(日テレ11’16)
98-1.25平成ダントツキング・PK対決2回分(日テレ34’34)
98-2.15ゴン中山夫妻のジャマイカ遠征日記①(関西TV1H04’05)
98-2.15だんトツ平成キング小学生PK対決(日テレ5’07)
98-3.1だんトツ平成キング小学生PK対決(日テレ14’15)
98-3.8サンデージャングル・中田英寿(テレ朝8’34)
98-3.22横浜ウォーカー創刊記念トークショー・城、山口素弘・楢崎(TVK21’12)
98-3.29新サンデーモーニング・小野伸二(TBS10’01)
98-3.30~4.2ポンキッキーズ・横浜M訪問(フジ18’00)
98-4.6東京フレンドパークⅡ・井原、秋田、岡野(TBS53’05)
98-4.13趣味悠々「W杯を100倍楽しむ方法」②ボランチ(NHK教育29’15)
98-4.25趣味悠々「W杯を100倍楽しむ方法」④ゲスト・川口能活(NHK教育29’40)
98-5.11趣味悠々「W杯を100倍楽しむ方法」⑥ゲスト藤田俊哉(NHK教育29’35)
98-5.18趣味悠々「W杯を100倍楽しむ方法」⑦ゲスト・都並敏史(NHK教育29’35)
98-5.24さんま・ナイナイのワールドカップ熱烈応援SP(フジ1H52’20)
98-6.1~5スポCAN5回分・三浦淳宏(TBS10’00)
98-6.3おはようクジラ・カズ代表落ち(TBS4’40)
98-6.3ルックルックこんにちは・カズ代表落ち(日テレ4’54)
98-6.5ザ・ワイド、カズ代表落ち(日テレ41’45)
98-6.5ビッグトゥディ・カズ代表落ち(フジ22’44)
98-6.6土曜一番花やしき・カズ無念の帰国(フジ28’00)
98-6.8新サンデーモーニング・カズ代表落ちとサッカー型経営(TBS53’22)
98-6.14新サンデーモーニング①チケット問題ほか②群馬県大泉町にいた元セレソン(TBS17’20+19’48)
98-6.15おはようクジラ・アルゼンチン戦の翌朝(TBS17’14)
98-6.15スーパーモーニング・W杯は僕たちの夢だった(テレ朝1H15’50)
98-6.15ワイドスクランブル・アルゼンチン戦燃えた夜(テレ朝1H00’00)
98-6.17所さんの20世紀解体新書・天才の作り方清水FC(TBS5’00)
98-6.21もぎたてサラダ・列島興奮クロアチア戦(TBS13’00)
98-6.27土曜一番花やしき・日本代表3連敗なぜ勝てなかったのか、徹底討論(フジ40’42+24’55)
98-6.28サンデージャングル・日本はなぜ予選リーグで勝てなかったのか(テレ朝7’42)
98-6.29おはようクジラ①今週の気になる話題1位「全敗」②日本列島ため息、歓喜、落胆、涙(TBS9’25+9’34)
98-6.29ザ・ワイド、代表帰国、選手の声、今後のゆくえ他(日テレ16’57)
98-7.10ザ・ワイド、中田移籍情報と難しさ(日テレ8’37)
98-7.12おはようクジラ・W杯決勝超速報(TBS12’26)
98-7.12新サンデーモーニング、W杯特需、カズほか(TBS28’10)
98-7.22B・Tビッグトゥディ・中田移籍会見(フジ12’55)
98-8.4B・Tビックトゥディ・中田アッカ(フジ8’25)
98-8.24開運なんでも鑑定団・小倉智昭・W杯日本代表のお宝(テレ東7’02)
98-10.24デリバティブTV・トルシエと中田の言動をオッズに(テレ朝24’20)
98-10.25ジャニーズ軍団夢のスポーツ対決(スカパー1H18’50)
98-10.31デリバティブTV・トルシエ・中田の言動をオッズに(テレ朝10’40)
98-11.28さんまのトヨタカップ猛烈研修(日テレ53’39)
98-12.6中田英寿CM撮影現場(Direc-TV4’40)
【ニュース・情報系番組】
1997年までは、ニュース・情報系番組をひとまとめに1月から順にご紹介していましたが、今年は情報量の多かった「テレ朝・ニュースステーション」「TBS・ブロードキャスター」「TBS・炸裂スポーツパワー」については抜き出しご紹介、その他番組を一括ご紹介します。
ニュースステーション 平日夜9時54分から放送、テレ朝、キャスター久米宏、川平慈英ほか
98-1.5ニュースステーション・ゲスト中山雅史(テレ朝13’41)
98-3.4ニュースステーション・日本代表モード、ダイナスティ杯(テレ朝6’44)
98-3.20ニュースステーション・明日J開幕(テレ朝11’33)
98-5.7ニュースステーション・W杯代表25人発表(テレ朝10’05)
98-5.18ニュースステーション・植田朝日のフランス報告(テレ朝20’20)
98-6.2ニュースステーション・W杯代表22人決定(テレ朝8’40)
98-6.11ニュースステーション・チケット宛てなくフランスへ(テレ朝20’15)
98-6.15ニュースステーション・アルゼンチン戦様々な表情(テレ朝42’14)
98-7.22ニュースステーション・中田移籍会見(テレ朝6’55)
98-9.15ニュースステーション・J後5節(テレ朝17’10)
98-9.22ニュースステーション・J後7節(テレ朝15’25)
98-9.28ニュースステーション・ゲスト岡田武史(テレ朝14’30)
98-9.29ニュースステーション・FIFA新会長インタビュー2日放送(テレ朝8’35)
98-10.21ニュースステーション・J後12節(テレ朝17’00)
98-10.29ニュースステーション・フリューゲルス問題②(テレ朝3’40)
98-10.29ニュースステーション・横浜F問題①(テレ朝12’35)
98-10.30ニュースステーション・横F問題川淵生出演(テレ朝20’38)
98-11.3ニュースステーション・横浜F問題(テレ朝10’24)
98-11.24ニュースステーション・ゲスト都並敏史(テレ朝11’52)
98-11.26ニュースステーション・札幌の参入戦(テレ朝12’00)
98-12.1ニュースステーション・ゲスト引退ラモス(テレ朝13’00)
98-12.7ニュースステーション・J参入最終決戦(テレ朝11’40)
98-12.22ニュースステーション・スポーツ特集「スポーツ文化と横浜F問題」(テレ朝19’45)
プロードキャスター、毎週土曜夜10時から放送、TBS、キャスター福留功、三雲孝江
98-3.7ブロードキャスター・ゲスト加茂周(TBS12’41)
98-3.21ブロードキャスター・中田英寿(TBS8’48)
98-6.7ブロードキャスター・W杯狂想曲、カズ物語(TBS24’57)
98-6.13ブロードキャスター・チケット空売り問題(TBS25’00)
98-6.27ブロードキャスター・日本はなぜ予選リーグで敗退したのか(TBS20’03)
98-10.31ブロードキャスター・横浜F合併問題(TBS8’04)
98-12.5ブロードキャスター・ゲスト川淵チェアマン(TBS16’30)
98-12.26ブロードキャスター・ペルージャを変えた男中田(TBS11’25)
炸裂スポーツパワー、毎週日曜朝10時から放送、TBS、編集長高嶋政宏(1~3月)、吉田照美(4月~)、副編集長雨宮塔子(1~3月)、小倉弘子(4月~)、コメンテーター青島健太(1~3月)、水沼貴史(4月~)
98-1.11炸裂スポーツパワー・ボクらが選ぶW杯代表(TBS14’30)
98-1.18炸裂スポーツパワー・城彰二鹿児島から(TBS25’00)
98-2.1炸裂スポーツパワー・ゲスト川淵チェアマン(TBS28’30)
98-2.8炸裂スポーツパワー・ボクらが選ぶW杯代表(TBS16’27)
98-2.15炸裂スポーツパワー・日本代表合宿レポート(TBS23’32)
98-2.22炸裂スポーツパワー・ボクらが選ぶW杯代表(TBS20’46)
98-3.8炸裂スポーツパワー・平野孝(TBS18’30)
98-3.15炸裂スポーツパワー・小野伸二(TBS13’11)
98-3.22炸裂スポーツパワー・城、川口、楢崎(TBS26’11)
98-4.5炸裂スポーツパワー・中田英寿(TBS11’29)
98-4.19炸裂スポーツパワー・小野と市川を生んだ静岡サッカーの親(TBS11’00)
98-4.26炸裂スポーツパワー・ラモスの会アピール(TBS9’00)
98-5.10炸裂スポーツパワー・W杯代表25人発表(TBS26’35)
98-5.17炸裂スポーツパワー・中田、ドゥンガ(TBS18’40)
98-5.24炸裂スポーツパワー・川淵チェアマン(TBS23’35)
98-6.8炸裂スポーツパワー・日本中が驚いたカズ落選、カズとゴン(TBS35’32)
98-6.14炸裂スポーツパワー・いざW杯初戦へ(TBS46’00)
98-6.28炸裂スポーツパワー・岡田ジャパンに足りなかったモノ(TBS52’50))
98-7.5炸裂スポーツパワー・城彰二隠し続けた歯の真実(TBS52’30)
98-7.12炸裂スポーツパワー・川口能活の270分、森島ほか(TBS44’20)
98-7.26炸裂スポーツパワー・中田英寿移籍特集(TBS18’00)
98-8.9炸裂スポーツパワー・磐田前期優勝(TBS15’35)
98-10.4炸裂スポーツパワー・同乗インタビュー・呂比須(TBS13’00)
98-10.11炸裂スポーツパワー・トルシエ合宿流儀(TBS8’40)
98-11.29炸裂スポーツパワー・ドゥンガ、武田修宏(TBS27’10))
98-12.6炸裂スポーツパワー・中田英寿全ゴール他(TBS34’50)
その他ニュース・情報系番組
98-1.4サッカー都市宣言「咲かそうスポーツ文化の華」画像不良(TVK58’25)
98-1.5ニュース23・ゲスト中田英寿(TBS16’13)
98-1.8ニュースの森・中山雅史(TBS5’00)
98-1.10サタデースポーツ・ゲスト柳沢敦(NHK10’20)
98-1.14スポーツTODAY・W杯スター予想(テレ東16’30)
98-1.20スポーツTODAY3回分、山口素弘、秋田、城(テレ東36’10)
98-1.20ニュース23・前園主張とメディア(TBS12’00)
98-1.23スポーツTODAY・岡野雅行(テレ東8’00)
98-1.24サタデースポーツ・ゲスト名波浩(NHK12’54)
98-1.29FIFA-TV・スーケル、ジダン他(Direc-TV23’00)
98-1.31サタデースポーツ・ゲスト西野朗×松木安太郎(NHK21’07)
98-2.4スポーツTODAY・羽中田昌(テレ東15’30)
98-2.22スポーツうるぐす・前園(日テレ5’24)
98-2.25ニュース11・アルゼンチン分析(NHK11’45)
98-2.26ニュース11・クロアチア分析(NHK13’35)
98-2.28プロ野球ニュース・風間八宏デビュー(フジ7’36)
98-3.1サンデースポーツ・ダイナスティ日韓戦(NHK12’53)
98-3.4プロ野球ニュース・ダイナスティ香港戦(フジ5’21)
98-3.14今年のJリーグ展望(日テレ6’53)
98-3.15独占スポーツ情報・ゲスト岡田監督(日テレ17’55)
98-3.20アジアサッカーダイジェスト(Skyスポーツ19’58)
98-3.21Jリーグ開幕特番・横浜国際競技場(TVK43’11)
98-3.21サタデースポーツJ開幕(NHK15’59)
98-3.25スポーツTODAY・小野初ゴール(テレ東8’38)
98-3.25フットボールムンディアル・ラウル他(GAORA25’57)
98-3.27プロ野球ニュース、小野・市川(フジ4’39)
98-4.5独占スポーツ情報・韓日戦(日テレ9’45)
98-4.8フットボールムンディアル・バレージ(GAORA26’02)
98-4.15ニュース11・中山5得点(NHK4’57)
98-4.18サタデースポーツ・ゲスト呂比須(NHK15’37)
98-4.19スポーツTODAY/ゲスト加茂周(テレ東9’52)
98-4.25サタデースポーツ・デルピエロ4分(NHK13’45)
98-4.26独占スポーツ情報・セルジオが代表選考に予言(日テレ10’07)
98-5.7スーパーJチャンネル代表25人発表(テレ朝13’40)
98-5.7ニュース23・W杯代表25人発表(TBS7’12)
98-5.13フットボールムンディアル・各国リーグ優勝続々(GAORA25’10)
98-5.15フランスW杯プレビュー・オランダ他(Sport-iESPN30’00)
98-5.16スポーツTODAY、小野、市川、中田(テレ東13’49)
98-5.22フットボールムンディアル・イラン、日本(GAORA10’30)
98-5.23スポーツTODAY中西英輔と斉藤俊秀(テレ東12’14)
98-5.24スポーツTODAY・新戦力小野(テレ東11’10)
98-5.26フランスW杯プレビュー⑨イタリア他(Sport-iESPN23’45)
98-5.30フランスW杯プレビュー⑩日本特集ほか(Sport-iESPN29’45)
98-5.31フランスW杯プレビュー⑪ドイツ他(Sport-iESPN29’55)
98-6.2NHKニュース9・W杯代表22人決定(NHK2’44)
98-6.2ニュース23・代表22人決定(TBS9’16)
98-6.2今日の出来事・カズ代表落ち(日テレ4’27)
98-6.3スーパーニュース・カズ二度目の悲劇(フジ13’25)
98-6.3ニュースの森・カズ代表落ち(TBS8’17)
98-6.3フットボールムンディアル(GAORA26’08)
98-6.4フランスW杯直前テストマッチ特番(TBS26’10)
98-6.10フットボールムンディアル(GAORA26’20)
98-6.11ニュース7、城の決意、チケット(NHK13’51)
98-6.11ニュースの森、チケット問題・城の父、W杯開幕(TBS27’54)
98-6.15ニュース+1青い炎に燃えたアルゼンチン戦(日テレ23’10)
98-6.20スポーツTODAY・クロアチア戦終了速報(テレ東13’50)
98-6.21スーパーJチャンネル・クロアチア戦3つの戦略をチェック(テレ朝20’30)
98-6.21スーパーニュース・クロアチア戦一人のサポーターとともに(フジ12’52)
98-6.24ニュース7・小野伸二、南ア監督トルシエ・アパルトヘイトを乗り越えて(NHK9’00)
98-6.24ニュース11・特集ロナウド(NHK7’15)
98-6.24フットボールムンディアル・ナイジェリア代表ミルティノヴィッチ監督ほか(GAORA26’10)
98-6.29スポーツMAX代表帰国、秋田、相馬インタビュー(日テレ11’51)
98-6.29ニュース+1①代表帰国、秋田、相馬生出演、②選手の声、W杯の波及効果(日テレ8’16+20’44)
98-6.29ニュースの森・秋田、相馬生出演(TBS8’37)
98-7.1スーパーJチャンネル・井原生出演(テレ朝20’30)
98-7.1ニュースの森・井原生出演(TBS11’07)
98-7.1フットボールムンディアル、パウロ・ソウザ他(GAORA9’47)
98-7.4スポーツTODAY・W杯準々決勝、日本代表新監督条件(テレ東14’20)
98-7.4スポーツうるぐす・川口能活笑顔の秘密(日テレ7’49)
98-7.5スポーツTODAY・W杯川口能活の思い(テレ東11’58)
98-7.5独占スポーツ情報・相馬、秋田、名良橋(日テレ14’38)
98-7.7スーパーニュース・中田移籍確実か(フジ4’54)
98-7.8ニュース7・準決勝司令塔対決の結果(NHK9’49)
98-7.9トランスWスポーツ・W杯初出場はJリーグを救うか(NHK-BS2’57)
98-7.19サンデースポーツ・ナビスコ決勝ほか(NHK13’30)
98-7.21TeNYスポーツ・快速のニューヒーロー川口信男(TV新潟4’51)
98-7.22ニュース+1中田移籍会見(日テレ4’44)
98-7.22ニュース23中田移籍会見(TBS4’25)
98-7.24ニュース11・J再開、解説反町康治(NHK7’56)
98-7.24プロ野球ニュース・城彰二インタビュー(フジ8’20)
98-7.25サタデースポーツ・J再開ほか(NHK18’00)
98-7.25スポーツTODAY・J再開ほか(テレ東16’00)
98-7.26サンデースポーツ・ゲスト岡野新会長(NHK14’30)
98-7.26スポーツTODAY・海外移籍のカギ(テレ東9’01)
98-7.26独占スポーツ情報・ゲスト中西永輔(日テレ13’10)
98-8.1スポーツうるぐす、奥寺が中田に(日テレ10’15)
98-8.4スーパーJチャンネル、ゲスト・ストイチコフ(テレ朝17’53)
98-8.8サタデースポーツ・磐田前期優勝・祝勝会(NHK7’31+15’37)
98-8.8プロ野球ニュース・磐田前期優勝(フジ15’25)
98-8.9独占スポーツ情報・磐田前期優勝(日テレ10’23)
98-8.10トランスWスポーツ・日韓共催他(NHK-BS15’49)
98-8.11アジアサッカーダイジェスト・川口能活、ヴ川崎(sky-sports15’49)
98-9.16フットボールムンディアル・デルピエロ(GAORA9’53)
98-9.20スポーツTODAY・トルシエは本物か(テレ東8’21)
98-9.26スポーツうるぐす・中田英寿情報(日テレ10’30)
98-9.27スポーツTODAY・中田は本物か(テレ東9’00)
98-10.10サタデースポーツ・JOMO CUP(NHK8’35)
98-10.11スポーツTODAY・トルシエ流合宿(テレ東9’55)
98-10.18スポーツTODAY・U-19特集(テレ東4’21)
98-10.20アジアサッカーダイジェストU-16アジア日本vs韓国ダイジェスト(sky-sports11’40)
98-10.31サタデースポーツJ14節、アジアU-19(NHK13’58)
98-11.1サンデースポーツ・ゲスト岡田武史(NHK20’15)
98-11.1スポーツうるぐす・中田英寿の1ケ月(日テレ7’22)
98-11.5スポーツMAX・掛布スポーツロマン旅、森山泰行訪問(日テレ6’45)
98-11.7サタデースポーツ・J後16節(NHK14’55)
98-11.8スポーツTODAY・U-19特集(テレ東11’10)
98-11.24ニュース11・トルシエインタビュー(NHK8’00)
98-11.28サタデースポーツ・鹿島年間優勝(NHK17’53)
98-11.28スポーツTODAY・鹿島年間優勝、秋田、相馬、名良橋(テレ東19’18)
98-11.28スポーツうるぐす・鹿島年間優勝、秋田(日テレ9’18)
98-11.28プロ野球ニュース・鹿島年間優勝、秋田、相馬①(フジ15’00)
98-11.28プロ野球ニュース・鹿島年間優勝、秋田、相馬②(フジ2’23)
98-11.29サンデースポーツ・ゲスト引退ラモス(NHK26’30)
98-11.29スポーツTODAY・特集アジア大会サッカーU-21代表(テレ東25’52)
98-11.29プロ野球ニュース・引退ラモスインタビュー(フジ28’54)
98-11.31プロ野球ニュース・J後15節、アジアユース決勝(フジ16’00)
98-12.1スポーツMAX・トヨタカップ(日テレ7’41)
98-12.5プロ野球ニュース・ペルージャ(フジ12’39)
98-12.6サンデースポーツ特集ドゥンガ他(NHK27’45)
98-12.6スポーツTODAY・ドゥンガインタビュー他(テレ東26’00)
98-12.8スポーツMAX・ヴ川崎を救え(日テレ10’36)
98-12.8ニュースの森・J生き残り福岡・札幌二都物語(TBS10’45)
98-12.14プロ野球ニュース岡田監督生出演(フジ15’32)
98-12.20スポーツTODAYワイド・ゲスト川口能活(テレ東33’40)
98-12.21FIFA-TV・ジーコ(Direc-TV7’04)
98-12.21スポーツMAX・情熱の肖像カズの挑戦他(日テレ7’26)
98-12.29ニュースプラス1SP・中田英寿特集(日テレ12’30)
【チーム応援番組】(地方からの収集分含む)
・毎週1回 Kick off マリノス TVK 25分 進行役・水沼貴史さん、中願寺香織さん
・毎週1回 GOGO! レッズ 埼玉TV 30分 進行役・水内猛さん、田中敦子さん
・隔週1回 CanDoレイソル チバTV 30分 進行役・瀬川慶さん
・月1回 月刊ジェフくら チバTV 30分 進行役・宮澤ミシェルさん、飯野みのりさん
・毎週1回 フォルツァ・ジュビロ SBS 30分 進行役・上田朋子さん
この年9.10放送で通算200回を達成、チームの好成績も相まって全国の磐田ファン
が静岡ローカル限定のこの放送を何とか見たいと熱望しました。
・毎週1回 フォルサ・アントラーズ CS放送J-sports 進行役・高城光代さん
1年前の10月放送を開始したものの、今年4月~9月まで休止が入り10月から再開
・毎週1回 3丁目サッカー部、オーレ・グランパス 名古屋TV 25分
・毎週1回 グランパスTV CBC(中部日本放送) 15分
・毎週1回 グランパス・エクスプレス 東海TV 25分
・毎週1回 GOGOアビスパ 福岡放送 15分
ナビゲーター 南省吾さん、たさきかおりさん
・毎週1回 Vダッシュ セレッソ テレビ大阪 5分
・毎週1回 GOGOヴィッセル サンテレビ 15分
・毎月1回 めざせJリーグ フロンターレ TVK 15分
・毎週1回 静岡kick off 98 静岡サッカー全般 静岡第一TV
【月刊誌・週刊誌・全国新聞・スポーツ紙】
1998.1.4-12合併号週刊プレイボーイ W杯出場獲得立役者・岡野雅行、山口素弘、中田英寿5p(欠落あり)
1998.1.6週刊ポスト これがW杯メンバー、カズ不要論も2p
1998.1月号文芸春秋 金子達仁・20歳のリーダー「中田英寿」誕生の夜10p
1998.2.5週刊ヤングジャンプ 本宮ひろ志×中田英寿5p
1998.2.7週刊現代 前園を食って中田を食う美人社長の正体3p
1998.3.5週刊女性セブン 中田英寿努力する天才の21年8p(欠落あり)
1998.3.5週刊文春 中田英寿バッシング報道に答える3p
1998.3.15サンデー毎日 加茂前監督激白「岡田君と約束したこと」2p
1998.3.17週刊女性 中田英寿新恋人の父は完全無視1p
1998.3.24週刊女性自身 城彰二「俺のヘッドで日本を変える」5p
1998.3.25週刊宝石 中田英寿父激白「不愛想を装う息子の真実」他4p+ W杯出場主要374選手、10段階格付一覧3p
1998.4.16週刊女性セブン 若きエース・城彰二インタビュー5p(一部欠落)
1998.4.19サンデー毎日 小野・市川を育てた父と母2p
1998.5.3サンデー毎日 エースの城・W杯インタビュー2p
1998.6.8 Sports SAIO 山崎浩一・ハッとさせられる警告1p
1998.6.11週刊文春 直前告白・家族たちのW杯、名波、城、岡野、川口3p+日本代表候補・W杯を夢見た頃、秘蔵カラーフォト公開7p
1998.6.15週刊AERA カズ「神話」の終焉2p+岡田武史・23年前に約束されていた男3p
1998.6.18週刊文春 W杯開戦総力特集、カズの無念を晴らせ8p+W杯日本vsアルゼンチン戦、羨望のチケット実物1p
1998.6.18週刊宝石 中田英寿の語録を父・邦彦氏が読む4p
1998.6.20週刊現代 巻頭カラー日本代表に密着撮、中田だ、ゴンだ、城だァ5p+ 新聞・テレビが報じない日本代表の真実4p
1998.6.26週刊朝日 W杯「消えたチケット」のナゾ+ W杯キッフオフ ①スーパースター候補カラーグラビア②似顔絵塾テーマW杯10p +村上龍の優雅で知的なW杯観戦旅行 2p +林真理子対談 川淵チェアマン 3p
1998.6.27週刊現代 新聞・テレビが報じない日本代表裏ナマ情報、岡田監督錯乱3p
1998.7.3週刊ポスト W杯「世界」と戦った後でby金子達仁モノクログラビア3p、W杯内幕スクープ①移籍情報2p、②W杯チケット大量詐欺2p
1998.7.4週刊現代 フランスW杯特集 残すはジャマイカ戦のみ10p
1998.7.7週刊プレイボーイ ①日本にもこんな選手がいてくれたら(モノクログラビア)、②日本が世界に届かない5つの理由7p
1998.7.8週刊朝日 フランスW杯特集日本敗北8p
1998.7.10週刊朝日 W杯ついに勝てず、日本選手よ傭兵たれ カラーグラビア4p含む9p
1998.7.20週刊AERA ラモス「戦犯は城、カズが出ていれば」発言が呼ぶ論争
1998.7.21週刊女性自身 激撮・川口能活、帰国の日いちばん会いたかった女性の部屋に2p
1998.8.6週刊新潮 初めて自身を語った中田英寿のW杯日記3p
1998.8.13-20合併号週刊文春 阿川佐和子のこの人に会いたい・川口能活3p
1998.8.13週刊宝石 城彰二独占120分「俺に対するバッシングにすべて答える!」4p
1998.8月号文芸春秋 W杯日本代表、戦場の肉声by佐藤俊7p + カズ独占全告白by一志治夫6p
1998.10.2週刊朝日 村上龍現地観戦記・中田英寿セリエA鮮烈デビュー2p
1998.10上旬 週刊プレイボーイ 新生日本代表、混迷の旅立ち、U-19等6p
1998.11.10週刊プレイボーイ 19歳の決意・本山雅志に可能性をみたモノクログラビア1p
1998.11中旬週刊女性自身 横F消滅、次に危ないのはココだ4p
1998.11.24週刊プレイボーイ 横F合併でJリーグ大再編成時代に突入! 6p
1998.11.24週刊女性自身 城彰二は私をボロボロに傷つけた4p
1998.11下旬週刊女性 城彰二の恋人は新恋愛教祖・古内東子3p
1998.12.18週刊ポスト 中田英寿の本命恋人はあの「爽健美茶」CM美女だった2p
【総合スポーツ誌】
1998.1.15Number435 表紙マイケル・ジョーダン
ナンバーMVP・中田英寿、特別インタビュー・秋田豊
1998.3.26Number440 表紙中田英寿×前園真聖
スペシャル対談中田英寿×前園真聖、密着レポート岡田ジャパン新たなる船出
単独インタビュー・ジーコ、特別寄稿村上龍、馳星周
1998.5.21Number444 表紙デル・ピエロ
欧州最終決戦、レアル・マドリー、ユベントス、小倉隆史が語る欧州ストライカー
密着インタビュー井原正巳のすべて
1998.6.18Number446 表紙日本代表
フランス98プレビュー、7大インタビュー、ロナウド、デル・ピエロ、ジダン、ドゥンガ、ストイコビッチ、エムボマ、洪明甫
スペシャル対談馳星周×金子達仁
密着ドキュメント中田英寿栄光への助走、日本代表25人のプライドほか
1998.7.2Number447 表紙中田英寿
フランス98ヒートアップ、緊急速報日本vsアルゼンチンby金子達仁、
開幕戦レポート、クロアチア・ボバン、密着インタビュー山口素弘
1998.7.16Number448 表紙川口能活
日本代表戦いの果て 緊急速報日本vsジャマイカby金子達仁
徹底分析、クロアチア戦、アルゼンチン戦
戦士たちの肖像、川口能活、秋田豊、山口素弘ほか
城彰二「エースは何を思ったのか」、中田英寿「ピッチに残したもの」
ロベルト・バッジョ「再び、アズーリへ」
1998.7.30Number449 表紙ジダンほかフランス代表
W杯一次リーグ+決勝トーナメント詳報、トリコロール軍団、悲願の初V
単独インタビュー、ジネディーヌ・ジダン
1998.8.13Number450 表紙中田英寿
緊急企画「中田英寿、移籍の真実」by小松成美
特別インタビュー・中山雅史「終わらない夏」、クロアチア密着レポート
1998.9.10Number452 表紙中田英寿
欧州サッカー開幕・クラブシーンへようこそ
巻頭インタビュー、マイケル・オーウェン、独占インタビュー、ロベルト・バッショ
ペルージャ発・中田英寿の衝撃、時代をリードするクラブ・ユベントス、レアル・マドリー、アーセナル、アヤックス
スペシャルインタビュー、小野伸二、ストイチコフ
1998.10.8Number454 表紙マーク・マグワイア
現地レポート・中田英寿イタリアを揺るがす
1998.10.22Number455 表紙ロナウド
欧州サッカー98-99 2大インタビュー・ロナウド、ジダン
密着レポート、中田英寿、インテル、スペインダービー、森山泰行
1998.12.3Number458 表紙小野伸二
2002年へ 小野伸二・天才の内側、日本人ストライカーの現在系、柳沢敦、中山雅史、久保竜彦、独占インタビュー、フイリップ・トルシエ
ペルージャ訪問記・中田英寿、横浜フリューゲルス最後のホームゲーム
【サッカー専門誌】
サッカー専門誌は、週刊発行のサッカーマガジン誌、サッカーダイジェスト誌、月刊発行のストライカー誌、そして隔月刊発行のサッカー・アイ、そして海外サッカー専門誌として月刊発行のワールドサッカーダイジェスト誌、ワールドサッカーグラフィック誌の6誌体制で推移していましたが、中田英寿選手のイタリアリーグ・セリエAでの活躍に触発されて12月「イタリア発! グローバルサッカー誌」という触れ込みで月刊「CALCiO 2002」(カルチョ2002)という新サッカー専門誌が誕生しました。
「CALCiO 2002」は、日本におけるイタリアサッカー評論の第一人者を自他ともに認める富樫洋一氏が編集長となって、イタリアのサッカー誌「グェリン・スポルティーボ」と提携してスタートしました。
また、サッカーダイジェスト誌は1月28日号で通巻400号となりましたが、特別な企画はありませんでした。
【フランスW杯特集誌】
1998 4月Number PLUS フランス98を愉しむ。W杯観戦完全ガイド
・特別対談川口能活×城彰二、21歳の肖像・中田英寿「未来への使者」
1998 8月Number PLUS フランス98 ビジュアル完全保存版64試合全記録
・フランスを彩った35人の英雄たち、・川口能活ロングインタビュー
1998.7.5アサヒグラフ緊急増刊「ニッポンかく闘えり」フランスW杯一次リーグ総集編
1998.7.15週刊読売臨時増刊「ワールドカップ 日本無念、フランスに散る」
ストライカー特別編集 98フランスの肖像・オリジナルフォトブック
サッカーマガジン98.7.18増刊号 日本代表のフランス98 270分間の軌跡
【書籍】
「決戦前夜」金子達仁著(新潮社1998年2月刊)
サッカー日本代表が史上初めてワールドカップ出場を決めたフランスワールドカップアジア最終予選、著者がアトランタ五輪当時から密着してきた中田英寿選手と川口能活選手の心の軌跡を辿りながら最終予選を振り返った一冊。タイトルを「決戦前夜」としたのは、著者にとって生涯最大の決戦だったアジア最終予選が、中田英寿選手にとってはまだ「決戦」ではなく「決戦前夜」であることを、1997年12月のFIFAチャリティ世界選抜vs欧州選抜戦に参加した彼から感じ取ったからとのこと。
「日本代表に捧ぐ」都並敏史著(ザ・マサダ1998年3月刊)
帯紹介文「岡田監督、中田ヒデ、三浦カズ、ゴン中山・・・あの都並だから語れる代表メンバーのエピソード満載! 」
「熱狂ロード Rord to France」ウルトラス・ニッポン代表植田朝日著(ザ・マサダ1998年3月刊)
帯紹介文「絶望のドーハから感動のジョホールバル。そして今フランスへ! 『ニッポン』W杯初出場に青春を賭けた男たちの汗と涙の記録。激闘1479日サッカー日本代表サポーター、ウルトラス・ニッポンの軌跡」
「エースのjo 城彰二」城彰二著(リヨン社1998年4月刊)
帯紹介文「イランに起死回生の同点ゴールをたたき込み日本を初のワールドカップへと導いた時代のストライカー城彰二。アトランタ五輪からW杯最終予選、そしてサッカーへの想い。炎のストライカー城彰二の素顔」
「セレソン」ドゥンガ著(日本放送出版協会1998年4月刊)
帯紹介文「ワールドカップへの情熱、自らのサッカー人生、そして日本へのいくつかの提言。『世界』を掴んだ男の言葉は、いま限りなく重い。」
「まるごと中田英寿」全日本サッカー記者連編著(辰巳出版1998年4月刊)
まえがきから抜粋「サッカーに命を賭けてるわけじゃない」と広言し「サッカーは仕事です」と割り切るドライな発言は、一方では生意気だとのそしりを受けながら、しかし多くの人に受け入れられ始めた。これまでのスポーツ選手にすれば、まるで異星人のような存在であることも確かだ。(中略)その彼になぜサッカーファンたちが注目するのか。それはチームの一人としてではなく、中田英寿としての、日本のサッカー界で初めて自己を確立した選手だったからだ。集団に寄りかからず、客観的な判断で自分の道を切り拓く。それが「彼」を天才にし「国際的に通用する唯一の選手」とため息をつかせるゆえんなのだ。
「名波浩 泥まみれのナンバー10」平山譲著(TOKYO FM出版1998年5月刊)
帯紹介文「名波浩が初めて語る苦闘の果てに見つけたもの。誕生からワールドカップまで、天才パサー25年間の軌跡」
「ドーハ以後 世界のサッカー革新の中で」杉山茂樹著(文藝春秋社1998年5月刊)
帯紹介文「年間200日の海外取材に裏打ちされた明快&広角レポート。サッカーの醍醐味が倍になる、CGを使った日本代表の戦術分析、欧州におけるモダンサッカーの現状、世界のサッカー・タウン行脚のコツetc.」
「たったひとりのワールドカップ・三浦知良1700日の闘い」一志治夫著(幻冬舎1998年8月刊)
すでに、本文の中でもご紹介した、カズ・三浦知良選手の「フランスW杯日本代表メンバーからの落選」、サッカーの枠を超えて大きな社会的話題となった結末に至る、本人の心の軌跡を描いた書籍。
帯紹介文「ドーハの悲劇から1700日。念願のフランス・ワールドカップの舞台にカズの姿はなかった。この間、彼は何を考え。そして、今、何を思っているのか。ついにカズがすべてを語ったスポーツノンフィクション。」
「勇者の残像 フランスワールドカップ98」佐藤俊著(リヨン社1998年11月刊)
帯紹介文「最後まで闘い続けた男たちに・・・。城彰二は、なぜゴールできなかったのか、なぜ、エース・カズの魂は封印されたのか、ブラジルの天才ロナウドはなぜ倒れたのか、極限の中で燃え尽きた男たちのW杯32日間の壮絶な闘いの瞬間。その熱き鼓動は2002年へと続く」
1998年とは、日本サッカーがめざしてきた一つの到達点として、日本サッカー史に刻まれる「伝説的な年」ですが、2つの歴史的な偉業という「光」と、2つの悲劇的な出来事という「陰」を浮かび上がらせた年でもありました
1998年、1つ目の偉業、では、これから日本が世界の舞台で勝っていくにはどうすればいいのか、Jリーグでの経験を持つ外国人サッカー関係者の言葉が語る
1998年は、日本代表が史上初めてワールドカップの舞台に立った年であり、それは日本サッカーに関わるすべての人たちが、長年の悲願を実現したという意味で、一つの到達点に立った「伝説的な年」になりました。
この年開催されたフランスワールドカップへの出場、それ自体が歴史的な偉業であり、奮闘空しく3戦3敗の結果ではあったものの、この先の長い世界のサッカーへの挑戦のスタートラインに立ったことは紛れもない事実でした。
フランスW杯で日本代表は、はやる気持ちを抑えながら世界の檜舞台に初めて立ったのですが、一度も勝てなかっただけでなく勝ち点1すら取れませんでした。
では、これから日本が世界の舞台で勝っていくにはどうすればいいのか、日本人論、日本文化論的な視点からの議論も含めて、サッカー関係者の間でさまざまな議論が巻き起こりました。
そのような中、かつて日本で、Jリーグでプレーしたり指導した経験を持つ外国人サッカー関係者の言葉が、珠玉の輝きをもって蘇り、私たちサッカーファンに響いてきたのです。
例えば、1994年、鹿島でのプレーを終えたジーコが、日本サッカー界に残していった「ワールドカップの真実」という著書に書かれている言葉があります。
「今回、日本は予選で敗退したわけだが、その方が良かったのかもしれない。思わぬ成功に、選手たちも(日本中全体も)、少々浮かれ気味だったとおもっている。」
「これからは地に足をつけ、もっと現実を見すえてプレーしなければいけない。サッカー、ワールドカップ、そして人生(すべて)は、真剣勝負なのだ。」
ここで言う「予選で敗退」というのは、実はフランスワールドカップの予選敗退のことではなく、いわゆる「ドーハの悲劇」での敗退を指しています。
けれども、そこを「フランスワールドカップの予選敗退」と置き換えても、そのまま通じる言葉です。
それから、1997年には、名古屋での指揮を終え日本を離れたベンゲル監督が「勝者のエスプリ」という著書で、世界で勝っていくための提言を次のように述べています。
「ナショナルチームが成功を収めるために重要なのは、大会を前にしたスケジュール調整(準備、メンタルを含めた選手のコンディション調整)だ。(中略)トレーニングにおいても、選手のコンディションは最優先されるべだろう。こうしたことの重要性もまた、経験によって知ることができるものだ。」
さらに、1998年に磐田でのプレーを終えたドゥンガ選手が、のちに出版された「セレソン」という著書の中で、次のように述べています。
「何度もいうようにワールドカップのレベルとアジアのレベルは違う。ワールドカップに出場することだけで喜び、満足してしまったら、きっとアルゼンチンやクロアチアに敗れ、帰ってこなければならなくなる。」
「代表チームはどこも同じだ。いつも勝たなければならない。できるだけ勝つように努力しなければならない。ここまででいいという限界はない。常にトレーニングをし、堅実で強い意思を持ち、満足せずにレベルアップしていくことだ。」
「日本には謙虚さが必要だ。サッカーというスポーツに勝利のロジックはない。(中略)強いチームも謙虚さを失っては簡単に負けてしまう。」
「(日本がアジア最終予選を勝ち抜いた時のような)スピリットもワールドカップに参戦するために重要な要素だが、それだけでは十分ではない。フィジカル、技術、戦術などさまざまな面でレベルアップを図り、欠点をなくす努力をしなければならない。ワールドカップまでに、ほぼ完全な状態に持っていかなければならない。」
彼らは、フランスW杯に日本代表が臨む以前に、すでに日本代表というチーム、そして監督、選手たちが備えるべきこと、やるべきことについて的確に指摘していたのです。
それは、ワールドカップという舞台が、完璧なまでの準備と、メンタル・フィジカル両面にわたるコンディションを完璧なまでに整えなければ戦えない世界だということでした。
完璧な準備の中には、豊富なアウェーでの試合経験なども含まれます。コンディションの準備の中には、メンタル・フィジカル両面で完璧に準備されている選手を見極めて起用することも含まれています。
彼らは揃ってこうも述べています。「それらは経験によってわかることであり、経験によって次に活かしていくものである」と。
2002年は、予選免除の形で日本がワールドカップの舞台に立ちます。そこに立つ次の日本代表チーム、監督・選手たちが今回の経験から学び、活かしていかなければならないということになります。
1998年、2つ目の偉業、磐田というチームが生み出した中山雅史選手の4試合連続ハットトリック
こうして、1つ目の偉業である「日本代表のフランスW杯挑戦」はホロ苦いものとなりましたが、
1998年の日本サッカー界は、もう1つの偉業を生み出しました。
磐田・中山雅史選手の4試合連続ハットトリックという離れ業です。多くのJリーガーは自分のキャリアの中で一度でもハットトリックを達成してみたいものと考えてプレーしているわけですが、それを何と2試合連続、3試合連続ならず4試合も連続で達成してしまうのですから、驚きを通り越してしまいます。
4月後半から5月はじめにかけて達成されたこの離れ業については、すでに詳しくご紹介していますが、中山雅史選手自身の集中力、技術力もさることながら、どのポジションからでも中山選手にラストパスが出てくる伝説的なチーム力が生み出した偉業です。
それは、まさに「ギネス記録」として登録されるだけの価値がある希少な記録だったのです。後年おそらくその記録は更新されることになると思いますが、日本サッカーにおける金字塔としての価値は永遠に色褪せることはないと思います。
このほかにも1998年のJリーグは、後世に語り継がれる価値が非常に高い、素晴らしい伝説がいくつか生まれました。
1つは、磐田と鹿島の宿命の頂上決戦です。前年の図式のちょうど裏返し、前期は磐田優勝、後期は鹿島優勝で相まみえたチャンピオンシップ、今年は鹿島が年間王者を奪還しましたが2年連続の同一チームによるチャンピオンシップは両チームのサポーターはもとよりJリーグファン、そして全国のサッカーファンを唸らせる魅力あふれた戦いでした。
この年のJリーグは、翌年からスタートするJ1,J2体制を決めるため、Jリーグがスタートして6年目にして遂に降格チームが出るという戦いでした。JFLから川崎フロンターレも加わってJリーグ4チームとの「Jリーグ参入決定戦」が行われたのです。最終的には、この年初昇格を果たした札幌が降格してしまう結果となりましたが、どのチームも生死を賭けた戦いを経験したのです。
2つの歴史的な偉業を含む、これらの出来事が1998年を輝かせた「光」の側面なのですが、一方では、この年、2つの悲劇的な出来事があった年としても、長く歴史に刻まれることになりました。
1年の中で浮き沈みが激しかった年という点では、前年の1997年もそうでしたが、前年の場合にはハッピーエンドで1年を終えた気持ちが強かったのに比べ、この年1998年は、2つの悲劇が、2つの歴史的な偉業を押しつぶさんばかりの衝撃度を持って発生したという印象が強い年でした。
1998年、1つ目の悲劇、カズ・三浦知良選手のワールドカップメンバー落選
1つ目の悲劇は「カズ・三浦知良選手のワールドカップメンバー落選」です。それは、カズ・三浦知良選手が、日本サッカー界に生まれた最初のスーパースターであり、その選手の落選という社会的衝撃以上のダメージを、フランスワールドカップを目前にした日本代表チームに与えたからです。
すなわち、カズ・三浦知良選手がフランスワールドカップを戦う日本代表チームからいなくなってしまったことによって、代表チームの主力選手のメンタルがガタガタになってしまい、ただでさえ格上のチームとの戦いに寸分のスキも許されないはずのチームが、最初から大きなハンディキャップを負ってしまう結果になったのです。
この悲劇は、日本代表を構成する選手たちが、すでに完全にプロ選手だったにも関わらず、その選手の生殺与奪を握る立場の監督が、昨年までどのカテゴリーでの監督経験もないアマチュア、今回、フランスワールドカップの指揮を執るために初めてプロ契約した人だったことによって発生した悲劇でした。
1992年から日本代表監督は、国際経験豊富なプロ監督を起用することに決めていたはずですが、前年のアジア最終予選のさなかに監督交代を行なうというドタバタの中で、いつの間にか監督経験のない人が日本代表監督になり、フランスワールドカップの指揮も任されることになったわけです。
国際経験豊富なプロ監督ではないことが、どう日本代表に影響を及ぼしたのかと言えば、それは試合の戦術などの問題ではなく「カズ・三浦知良選手を外した場合、このチームは何の影響もなくやれるチームなのかどうか」という選手心理へのアプローチがまったくできなかったことにあるのです。国際経験豊富なプロ監督というのは、ある意味「心理学者の素養がなければならない」と言われるほどのチーム掌握力を持った人たちなのです。
そこをまったく考慮することなく、経験のない人を監督に据えたのは、まさに「日本サッカー界全体のプロ化」が、まだ途上段階でしかなかったということを示しています。
1998年、もう1つの悲劇、横浜フリューゲルスの合併・消滅
この年起きたもう1つの悲劇が「横浜フリューゲルスの合併・消滅」です。10月下旬、一斉に報じられた新聞報道から始まったこの悲劇、その後の選手・サポーターたちの必死の存続活動も空しく決定が覆ることはありませんでした。この出来事が伝説として長く語り継がれるほど悲劇的だったのは、合併・消滅の報道以後、横浜フリューゲルスがJリーグ後期の残り試合、そして続く天皇杯サッカーを1試合も負けることなく戦い抜き、ついには1999年1月1日、元旦恒例の天皇杯サッカー決勝に勝って栄冠を手にしたにも関わらず、その瞬間、チームの歴史が幕を閉じるというエンディングを迎えたからでした。
この悲劇もまた「日本サッカー界全体のプロ化」が、途上段階でしかなかったことを示しています。
Jリーグクラブという「プロサッカーのクラブ」を切り盛りする横浜フリューゲルスの経営陣が、およそ「プロサッカーのクラブ」の経営とは程遠いずさんな有り様だったことが悲劇を生んでしまったのです。
看板だけは「プロサッカークラブ」、しかし、それを切り盛りする人たちは、ズブの素人、これでは破綻するのも時間の問題ということになります。
「横浜フリューゲルス合併・消滅」に続き、ヴ川崎から読売新聞社の撤退、平塚からのフジタ工業の関与縮小が明らかとなり、Jリーグ各クラブは一斉に経費削減方針を打ち出しました。そのため横浜F・サンパイオ選手に続き、磐田・ドゥンガ選手、鹿島・ジョルジーニョ選手といったチームの心臓部を担った選手が退団の憂き目に合ったのも悲しいことでした。
この年起きた2つの伝説的な「悲劇」。それは、日本サッカー界に関わるすべての人たちが「世界を追いかけ、世界に追いつく」ことを目指して作り上げた、Jリーグを中心とした「日本サッカー界全体のプロ化」が、この1998年段階では、まだ発展途上であることを日本中そして世界に対して曝け出した姿でした。
顧みれば1986年以来、「世界を追いかけ、世界に追いつく」ことを目指して取り組んできた日本のサッカー界は、この年1998年、フランスワールドカップへの出場によって、一つの到達点を迎えた光り輝くような年であったのですが、一方で、懸命に走り続けてきた無理がたたったかのように2つの「悲劇」を曝け出してしまい、暗い陰を落してしまった年でもあります。
こうして、1998年は一つの区切りの年となりました。来たる1999年からは、選手もプロなら監督、クラブ経営者もすべて「サッカーに関してはプロ」でなければならないことを強く求められる、そういう時代に入っていくことになります。
このことをしっかりと記録して、記憶に留め長く語り継ぎたいと思います。
1998年をもって、日本サッカーの一つの時代が終わったことを記し「伝説のあの年」シリーズの第1巻を稿了いたします。